2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
2月も末日に至りました。自分の生活は千年一日の如く変わり映えしません。
昨日最高気温は13度C迄上がって、いよいよ花粉が飛び交う季節に入ったようです。そんな対策のクスリの宣伝も多くなりました。体調は悪くないけれど、早朝覚醒して二度寝もできない。朝の洗濯、ストレッチ、そしてYouTube鍛錬もいつも通り済ませて市立体育館に向かう途上、ゴミ拾いの功徳も意気が上がらない、ペットボトルと缶珈琲を数本拾ったのみ。こんな日もあるよなぁ、なんて自分に言い訳しつつ運動公園に差し掛かったら、テーブルのところに前日の宴の後、汚らしく盛大なゴミ散乱目撃。仕方がないのでちょっと時間を掛けてキレイにしました。トレーニングルームにはいつもより10分ほど遅れて入ったけれど、自分含めてたった4人、マシンは誰も使っていない。ゆっくりゆる筋トレ+エアロバイク15分消化できました。帰り、久々にスーパーに寄って食材補充済。ちょうどお気に入りの柔らかいクリーム入りの菓子パンが入荷していて、3個も喰ってしまって大後悔。
女房殿は気分転換に美容院〜昼から婆さんのところへ泊まり。今朝の体重は67.8kgほぼ変わらず、カロリー高そうなクリームパン一気喰いを後悔して「【食後におすすめ】血糖値を下げる室内ウォーキング!1000歩歩いてダイエット」で体重増阻止!
和田 秀樹さんによると「老化の速度を緩やかにするカギとなるのは働くことだ」とのこと。長野県の寿命が長いのは高齢者の就業率が高い(65歳以上の就業率31.6%/2020年国勢調査)のが要因なんだそう。新しいスキルの習得、知的な活動、社会的なつながりを持つことなどが、前頭葉の萎縮を遅らせる助けとなるとのこと。定年制は「差別」との主張でした。長野県には農業が盛んだから働きやすいこともあるそう。
一理も二理もある主張だけど、自分は65歳の時にお仕事を辞めました。ま、婆さんとの関係とか家庭の都合もあったけれど、いちおう70歳迄働くことは可能、職場では多くの若い人たちと馴染んで楽しくやっていたつもり。でも、ヴェテランの押しの強い爺(=ワシ)の存在は職場には迷惑やろ、そう自覚して引退転居を決めました。その時同期の数人に連絡を取ってみたら「70歳迄働くよ」なんて、結局そのあと一年ほどで辞めたようです。
毎日ヒマな生活は退屈だけど、そこそこ愉しんでますよ。どこか別な職場で新たに〜市立体育館は未だ夕方〜夜間の時間給職員を募集しているけれど、もうそんな元気はないなぁ。ヒマな自由な時間も悪くないし、エラソーにするつもりはないけれど人間関係も気詰まり、かえって寿命を縮めるかも。経済的にどうしても働かなくちゃいけない方々には申し訳ない、贅沢な言い分でした。
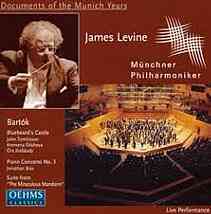 Bartok 歌劇「青ひげ公の城」〜ジェームズ・レヴァイン/ミュンヘン・フィル/ジョン・トムリンソン(bbr)/クレメーナ・ディチェーヴァ(s)/エルス・キスファルディ(語り)(2003年ライヴ)・・・James Levine(1943-2021亜米利加)がミュンヘン・フィル首席に在任したのが1999-2004年、前任セルジウ・チェリビダッケ(在任1979-1996年)の後を受けて、当時元気だったけれど、しっかりミュンヘンに腰を据えた印象はありませんでした。幸いこの時期のライヴ音源はまとめて発売されて即入手したもの。これは独逸語上演?(違ったら教えて下さい)いずれ言語理解不如意だけど、青ひげ公と7人の妻を巡る猟奇的な筋書き、大昔テレビでオペラに非ず、そんな風情の洋画を見た記憶もあります。CD一枚に収まる長さ、色彩豊かに幻想的なサウンドと妖しくも美しい旋律連続、暴力的な爆発、不快な響きの混濁もない静謐をベースとした神秘の作品。さすがオーケストラの扱いの名人、ミュンヘン・フィルもクリア明晰な響きに整ったアンサンブル、John Tomlinson(1946-英国)の雄弁も含めて、ウェットな怪しさみたいなものを感じさせぬサウンドでした。オーディオ通のコメントによると素晴らしい音質なんだそう、こちら安物オーディオには明晰だけど、乾いて臨場感重量感が足らぬと受け止めたもの。
Bartok 歌劇「青ひげ公の城」〜ジェームズ・レヴァイン/ミュンヘン・フィル/ジョン・トムリンソン(bbr)/クレメーナ・ディチェーヴァ(s)/エルス・キスファルディ(語り)(2003年ライヴ)・・・James Levine(1943-2021亜米利加)がミュンヘン・フィル首席に在任したのが1999-2004年、前任セルジウ・チェリビダッケ(在任1979-1996年)の後を受けて、当時元気だったけれど、しっかりミュンヘンに腰を据えた印象はありませんでした。幸いこの時期のライヴ音源はまとめて発売されて即入手したもの。これは独逸語上演?(違ったら教えて下さい)いずれ言語理解不如意だけど、青ひげ公と7人の妻を巡る猟奇的な筋書き、大昔テレビでオペラに非ず、そんな風情の洋画を見た記憶もあります。CD一枚に収まる長さ、色彩豊かに幻想的なサウンドと妖しくも美しい旋律連続、暴力的な爆発、不快な響きの混濁もない静謐をベースとした神秘の作品。さすがオーケストラの扱いの名人、ミュンヘン・フィルもクリア明晰な響きに整ったアンサンブル、John Tomlinson(1946-英国)の雄弁も含めて、ウェットな怪しさみたいなものを感じさせぬサウンドでした。オーディオ通のコメントによると素晴らしい音質なんだそう、こちら安物オーディオには明晰だけど、乾いて臨場感重量感が足らぬと受け止めたもの。
Applaus(0:24)Prolog(6:27)Bluebird's Castle(5:34) Doors I See...(4:41)First Door: Torture Chamber(4:29)Second Door: Armoury(4:39)Third Door: Treasury(2:51)Fourth Door: Garden(5:22)Fifth Door: Bluebird's Realm(6:50)Sixth Door: Lake Of Tears(5:09)The Last Door I Will Not Open(4:31)Presentiment Seventh Door(4:13)Seventh Door: Bluebird's Former Wifes(11:25/拍手有)
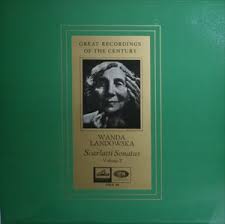 D.Scarlatti ソナタ集 ト長調 K.124/ト短調 K.8/ニ長調 K.430/ヘ短調 K.519/ハ長調 K.159/ヘ長調 K.107/ホ長調 K.380/嬰ハ短調 K.247/嬰ヘ短調 K.447/ホ長調 K.20/ト長調 K.328/ニ長調 K.397/ニ短調 K.32/ニ短調 K.141/ヘ短調 K.481/ニ長調 K.492/ト短調 K.234/ヘ長調 K.6/変ホ長調 K.193/ト短調 K.450〜ワンダ・ランドフスカ(cem)(1934-1939年)・・・20世紀にほとんど虫の息であったチェンバロを復興させたWanda Landowska(1879ー1959波蘭→亜米利加)の演奏。プレイエルに特注したモダーン・チェンバロは鳴りがよろしく、音色やタッチの変化も多彩。音質はこの時期にしてかなり良好でした。D.ScarlattiはBachのゴールドベルク変奏曲同様、表現の幅や現代の演奏会場に相応しい音量という意味で、ピアノ演奏のほうが楽しめると思うけれど、先人に敬意を評して拝聴いたしました。軽快に表情豊かな珠玉の愛らしい小品集、ほとんどシンセサイザーを連想させるメタリックっぽい音色、古楽器に慣れている耳にはちょっぴり異形に響きます。しかし、ヴィヴィッドに躍動するリズム感、そして音色とタッチは刻々と変化して馴染みの旋律をたっぷり堪能可能。資料的価値を凌駕して、21世紀に残すべき記録でしょう。
D.Scarlatti ソナタ集 ト長調 K.124/ト短調 K.8/ニ長調 K.430/ヘ短調 K.519/ハ長調 K.159/ヘ長調 K.107/ホ長調 K.380/嬰ハ短調 K.247/嬰ヘ短調 K.447/ホ長調 K.20/ト長調 K.328/ニ長調 K.397/ニ短調 K.32/ニ短調 K.141/ヘ短調 K.481/ニ長調 K.492/ト短調 K.234/ヘ長調 K.6/変ホ長調 K.193/ト短調 K.450〜ワンダ・ランドフスカ(cem)(1934-1939年)・・・20世紀にほとんど虫の息であったチェンバロを復興させたWanda Landowska(1879ー1959波蘭→亜米利加)の演奏。プレイエルに特注したモダーン・チェンバロは鳴りがよろしく、音色やタッチの変化も多彩。音質はこの時期にしてかなり良好でした。D.ScarlattiはBachのゴールドベルク変奏曲同様、表現の幅や現代の演奏会場に相応しい音量という意味で、ピアノ演奏のほうが楽しめると思うけれど、先人に敬意を評して拝聴いたしました。軽快に表情豊かな珠玉の愛らしい小品集、ほとんどシンセサイザーを連想させるメタリックっぽい音色、古楽器に慣れている耳にはちょっぴり異形に響きます。しかし、ヴィヴィッドに躍動するリズム感、そして音色とタッチは刻々と変化して馴染みの旋律をたっぷり堪能可能。資料的価値を凌駕して、21世紀に残すべき記録でしょう。
(1:57-2:34-1:35-1:26-2:15-4:38-3:49-1:27-1:30-3:30-3:04-1:15-3:53-4:10-4:21-2:59-1:33-2:27-1:52)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日は予報通り気温は上がりました。朝、独りでもいつもどおりのヘルシー朝食、ぼちぼち自家製ヨーグルトが尽きそうなので、2L牛乳パックの底を浚(さら)えました。すると・・・怪しく変色しているじゃないの! わずか1週間、この寒さでも変敗するのか、ガッカリしつつよーくみると、それはブルーベリー。前回種菌にしたのが婆さん宅から持参したブルーベリーヨーグルトだったのですね。すっかり忘れてました。幸い残りおいしく全部いただきました。新たにまた牛乳パック1本分ブルーベリーヨーグルトを種菌にして増殖培養いたしました。
ストレッチ、YouTube鍛錬済ませて眼科へ。予想通り予約時間よりたっぷり1時間以上待たされ、たくさん検査して現状維持を確認、けっこうカネは掛かってサイフの現金ぎりぎり、クスリ代支払いはカードが使えて助かりました。そのあとコンビニで現金をおろしたけれど、新旧札混合、どうも新札は慣れていなくて偽札みたいに感じます。往復コミュニティバスが使えて通院は楽勝、買い物は最低限野菜のみ駅の高級スーパーで済ませました。自宅に戻ってみると女房殿は体育館へ、自分は洗濯。また出掛けて、デイサービスから戻った婆さんに夕飯のお世話して、夕方遅く二度目の帰宅。自分だけだったので夕食は簡素に済ませたものです。今朝の体重は67.85kg+200g、フツウの食事でも体重維持できないのは悩ましいもの。
日本の風土が生み出した世界に誇るべき健康食品・納豆について気をつけるべき点の記事を勝手にネットより引用。こどもの頃より納豆を偏愛する自分には重要知識なんです。以前、訪日中国人が「日本人が長生きなのは納豆の力」妙な知識を振りかざしていたテレビ番組を見た記憶もあります。(ほんまか?太っていた時期もコレステロールは低かったのはそのせいか)
常温に戻さない(発酵が進む)よく混ぜる(マイルドになる。これはタレを入れる前ですね)酢を入れない(粘りがなくなるそう。だいたい味的におかしくないか?)喰い過ぎない(当たり前/一日一パックが適度でしょう)
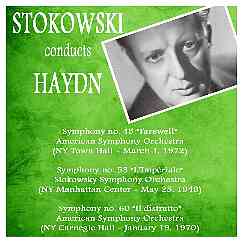 Haydn 交響曲第45番 嬰ヘ短調「告別」(アメリカ交響楽団/1972年ライヴ)/交響曲第53番ニ長調「帝国」(彼の管弦楽団/1949年)/交響曲第60番ハ長調「うかつ者」(アメリカ交響楽団/1970年ライヴ)〜レオポルド・ストコフスキー・・・正直なところこんな怪しい音源ムリして求めなくてもLeopold Stokowski(1882ー1977英国)だったら聴いてみたいけれど、もっと音質条件整った音源あるでしょ、自分でもちょっと呆れております。音質はどれも大味に肌理粗いけど、オン・マイクにまずまず我慢できる音質。でも、一度聴いたらもうエエかな、と云ったところ。
Haydn 交響曲第45番 嬰ヘ短調「告別」(アメリカ交響楽団/1972年ライヴ)/交響曲第53番ニ長調「帝国」(彼の管弦楽団/1949年)/交響曲第60番ハ長調「うかつ者」(アメリカ交響楽団/1970年ライヴ)〜レオポルド・ストコフスキー・・・正直なところこんな怪しい音源ムリして求めなくてもLeopold Stokowski(1882ー1977英国)だったら聴いてみたいけれど、もっと音質条件整った音源あるでしょ、自分でもちょっと呆れております。音質はどれも大味に肌理粗いけど、オン・マイクにまずまず我慢できる音質。でも、一度聴いたらもうエエかな、と云ったところ。
第45番 嬰ヘ短調の編成はオーボエ2/ファゴット1/ホルン2/第1ヴァイオリン2/第2ヴァイオリン2/ヴィオラ1/チェロ1/コントラバス1、ストコフスキーはもちろん弦の人数を増やしております。最終楽章がひとりひとり舞台から去っていく有名な趣向。劇的な始まりから分厚い響き、やがて寂しく終わる作品は思わぬパワフルに骨太な演奏でした。(Allegro assai/Adagio/Menuetto: Allegretto/Finale: Presto - Adagio/21:21)
第53番ニ長調の編成はフルート1/オーボエ2/ファゴット1/ホルン2/ティンパニ/弦五部。これのみ古い録音だけど、セション録音は意外と音質状態は悪くない。快活にヴィヴィッドな作品であり、演奏も熱気に充ちた勢いを感じます。これもかなり大柄な演奏。アンダンテの優雅な旋律最高。(Largo maestoso - Allegro Vivace/Andante/Menuetto/Prest/18:07)
第60番ハ長調はオペラ「うかつ者」から再編した作品とか。編成はフルート抜き、オーボエ2/ファゴット/ホルン2/トランペット2/ティンパニ/弦五部。これが一番音質はまとも。たっぷり優雅な表情に親しみやすい旋律が続いて楽しめました。(Adagio - Allegro di molto/Andante/Menuetto - Trio/Presto/Adagio (di Lamentatione)/Finale: Prestissimo/22:54)
 Scriabin 交響曲第1番ホ長調/夢想 作品24/2つの詩曲 作品32(ogal-Levitsky編)〜イーゴリ・ゴロフスチン/モスクワ交響楽団/モスクワ・カペラ/ミハイル・アガフォノフ(t)/リュドミラ・イヴァノヴァ(ms)(1995年)・・・Igor Golovschin(1956-露西亜)の録音は数年前に聴いて、ほとんど印象が残っていなかったことを反省して再聴したもの。スヴェトラーノフの1963年録音を聴いて、作品にはそれなり目覚めたけれど音質にちょっと不満有。こちら以前にも感じたけれど、収録音量が低いのが難点、ボリュームを上げるとかなり鮮明な音質でした。但し、1989年創立のモスクワ交響楽団は素朴なサウンドにアンサンブルにそれなり優れても、ソヴィエット国立交響楽団よりは弱くて薄い感じ。1895年初演の作品は甘美な風情に穏健素直な旋律が続いて、悪くないんだけどゴロフスチンの表現は起伏とメリハリが足らん感じ。Scriabinにはもっとノーコーにエッチが必要です。
Scriabin 交響曲第1番ホ長調/夢想 作品24/2つの詩曲 作品32(ogal-Levitsky編)〜イーゴリ・ゴロフスチン/モスクワ交響楽団/モスクワ・カペラ/ミハイル・アガフォノフ(t)/リュドミラ・イヴァノヴァ(ms)(1995年)・・・Igor Golovschin(1956-露西亜)の録音は数年前に聴いて、ほとんど印象が残っていなかったことを反省して再聴したもの。スヴェトラーノフの1963年録音を聴いて、作品にはそれなり目覚めたけれど音質にちょっと不満有。こちら以前にも感じたけれど、収録音量が低いのが難点、ボリュームを上げるとかなり鮮明な音質でした。但し、1989年創立のモスクワ交響楽団は素朴なサウンドにアンサンブルにそれなり優れても、ソヴィエット国立交響楽団よりは弱くて薄い感じ。1895年初演の作品は甘美な風情に穏健素直な旋律が続いて、悪くないんだけどゴロフスチンの表現は起伏とメリハリが足らん感じ。Scriabinにはもっとノーコーにエッチが必要です。
第1楽章「Lento」(7:38)第2楽章「Allegro dramatico」(9:23)第3楽章「Lento」(10:07)第4楽章「Vivace」(3:48)第5楽章「Allegro」(8:07)*この辺りはラスト、かなり頑張っております。第6楽章「Andante」声楽入りのクライマックスもいま一歩の力強さ、盛り上がりが欲しいところ。(13:32)
「夢想」は木管が囁き合う始まり、やがて弦と金管が参入して情感が高まる哀愁甘美な小品。(5:36)「2つの詩曲」はピアノ曲からの編曲。いかにも幻想的、絶品の妖しい旋律でした。(5:00/1:55)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
露西亜の烏克蘭侵攻丸三年、トランプさんの本音はどうなんでしょう。露西亜軍撤退国連決議に亜米利加反対。たんなる功名心による前のめりなのか、深慮遠謀なのか、中国分断なのか、ようわかりません。独逸総選挙は右派躍進(左派も伸びたそう/若者に支持が高い)既に人口の20%が移民絡みが占めて、実際に治安とか不況とか生活苦とかリアルな問題が眼前にあるのでしょう。日本はその状況からなにを学ぶのか、引退した自分もよく考えてなくては。維新の兵庫県議はトンデモない人、岸和田市長も含めて人材育成ができていないようですね、政治家一般に劣化しているのか、それとも昔から表に出なかっただけなのか、これもようわからない。
2月もあともう数日。朝一番にゴミ出しは相当寒く、市立体育館に全身ゆる筋トレ帰りは日差しもかなり緩んで温かい感じ。途中の白梅も今を盛りに咲いておりました。トレーニングルームに到着したら、手袋が片方ない〜帰り順路を辿ったらちゃんと落ちてました。ストレッチもYouTube鍛錬も2025年に入って一日も休まず皆勤賞。別途思い立ってスワイショウも継続して、これがけっこう効いているのかも。なんとか流行り病には罹患せず、このまま乗り切りたいものです。本日これより、久々に眼科の定期検診と目薬をいただきに出掛けます。あの女医さんはちゃんと症状を説明しないからイヤなんだけど、そこが一番近いので仕方がない。冷蔵庫はすっからかん、ついでに野菜など仕入れるつもり。女房殿は前夜婆さんのところに泊まり、すると食事はぐっと手抜きして粗食に至ります。睡眠が浅く、途中覚醒も頻繁だけど、昼寝で埋めれば良いんです。今朝の体重は67.65kg▲350g。
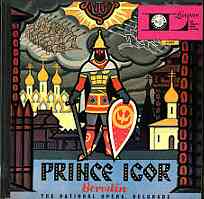 Borodin 歌劇「イーゴリ公」〜オスカー・ダノン/ベオグラード国立歌劇場管弦楽団/同合唱団/イーゴリ公:ドゥシャン・ポポヴィチ(br)/ヤロスラヴナ:ヴァレリヤ・ヘイバル(s)/ウラジーミル:ノニ・ジュネチ(t)/コンチャク汗:ジャルコ・ツヴェイチ(b)(1955年2月/ベオグラード文化の家/モノラル)・・・これは英DECCAによるステレオ録音らしいけど、自分が入手したのはモノラル音源。それでも臨場感溢れて低音もしっかりした音質にほとんど不足を感じさせません。声楽オペラに疎いから歌い手の知識は皆無、Oskar Danon(1913-2009塞爾維)は1945-1963年ベオグラード歌劇場の総監督だったとのこと。最近の録音はあまり見掛けぬ歌劇場のオーケストラも、合唱も充実して、主人公役バリトンも、妻ヤロスラヴナ役声楽ソロも圧巻の押し出しと説得力でした。
Borodin 歌劇「イーゴリ公」〜オスカー・ダノン/ベオグラード国立歌劇場管弦楽団/同合唱団/イーゴリ公:ドゥシャン・ポポヴィチ(br)/ヤロスラヴナ:ヴァレリヤ・ヘイバル(s)/ウラジーミル:ノニ・ジュネチ(t)/コンチャク汗:ジャルコ・ツヴェイチ(b)(1955年2月/ベオグラード文化の家/モノラル)・・・これは英DECCAによるステレオ録音らしいけど、自分が入手したのはモノラル音源。それでも臨場感溢れて低音もしっかりした音質にほとんど不足を感じさせません。声楽オペラに疎いから歌い手の知識は皆無、Oskar Danon(1913-2009塞爾維)は1945-1963年ベオグラード歌劇場の総監督だったとのこと。最近の録音はあまり見掛けぬ歌劇場のオーケストラも、合唱も充実して、主人公役バリトンも、妻ヤロスラヴナ役声楽ソロも圧巻の押し出しと説得力でした。
歌劇「イーゴリ公」は未完、Rimsky-KorsakovとGlazunovが補筆完成させたそう。これは自分が馴染んでいる数少ないオペラのひとつ。魅惑の旋律「だったん人(ポロヴェツ)の踊りと合唱」があまりに有名、露西亜のイーゴリ公とポロヴェッツとの戦い、捕虜となって、やがて帰還といった筋らしい。ちょっと浮き立つように勇壮な序曲から、例のオリエンタルに泥臭い旋律が圧巻の魅力、露西亜歌劇らしい男声の低音+綺羅びやかに多彩な管弦楽もあいまって、オペラ・ド・シロウトな自分にもCD3枚分、言葉の壁も乗り越え、知っている旋律(「だったん人の踊りと合唱」)以外にもたくさん魅惑の旋律登場して、たっぷり楽しめました。
「序曲」(9:59)イーゴリ公は「ポロヴェツ人の侵攻を防ぐ」ために戦場へ向かう。不吉な予兆有。
第1幕「プチーヴリ市内のガーリッキィ公の館の中庭/イーゴリ公の妻の兄であるガーリツキイ公は横暴を極める」(4:10-2:42-5:34-8:31-2:08-4:02-1:12-2:35-0:56-3:26-2:45-9:43-5:12-7:45/9:20)
第2幕「ポロヴェツ人の陣営/イーゴリ公と息子ヴラヂーミルが捕虜になり、息子はコンチャク汗の娘・コンチャコヴナと恋に落ちる」(5:17-2:17(*ここが有名な「娘たちの踊り」)-6:19-4:23-6:08-5:46-7:58*ここ感極まるバリトン・ソロ「苦しむ魂に眠ることも休むこともできない」-4:31-7:00-3:29-3:44(*いちばん有名な安らぎの「だったん人の踊り」もちろん女声合唱入)-7:49(*引き続き有名な「賛美の歌」の躍動は泥臭い魅惑の雰囲気たっぷり。これはコンチャック汗が捕虜であるイーゴリ公をもてなす場面))
第3幕「ポロヴェツ人の陣営/イーゴリ公が息子を残して逃亡する」(5:06(*「だったん人の行進」は怪しくも泥臭いリズム。ここも単独で演奏会に取り上げられます)-3:09-7:36-2:23-3:46-4:44(*逃亡の場面は素晴らしい盛り上がり))
第4幕「プチーヴリ市内/イーゴリとオヴルールの帰還/民衆が「イーゴリ公の栄光」を称える」(10:40(*イーゴリの妻ヤロスラヴナが夫を思って嘆く悲痛なアリア)-3:23-7:47-8:35-3:45)最後の盛り上がり迄、音質状態よろしく楽しく拝聴できました。
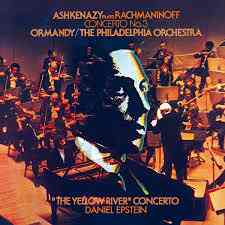 Rachmaninov ピアノ協奏曲第3番ニ短調〜ウラディミール・アシュケナージ(p)/ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団(1975年)・・・アシュケナージ三度目の録音は2年ほど前に拝聴。この時期のRCA録音は落ち目になって1960年代のLiving Stereoとは大違い、こぢんまりとしてそう悪くないけれど、そこそに美しい音質。リアルな臨場感に足らず、ピアノは鳴り切らず、おとなしい印象でした。Vladimir Ashkenazy(1937露西亜→氷島)は当時38歳、彼はOssiaを採用することが多いと記憶するけれど、ここでは小カデンツァを採用。たっぷり甘い、濃厚な旋律とピアノの華麗なテクニック披瀝が魅惑の名曲。
Rachmaninov ピアノ協奏曲第3番ニ短調〜ウラディミール・アシュケナージ(p)/ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団(1975年)・・・アシュケナージ三度目の録音は2年ほど前に拝聴。この時期のRCA録音は落ち目になって1960年代のLiving Stereoとは大違い、こぢんまりとしてそう悪くないけれど、そこそに美しい音質。リアルな臨場感に足らず、ピアノは鳴り切らず、おとなしい印象でした。Vladimir Ashkenazy(1937露西亜→氷島)は当時38歳、彼はOssiaを採用することが多いと記憶するけれど、ここでは小カデンツァを採用。たっぷり甘い、濃厚な旋律とピアノの華麗なテクニック披瀝が魅惑の名曲。
第1楽章「Allegro ma non tanto」音質印象か、余裕のある技巧に端正に粒の揃ったピアノ、泥臭く叩きつけたり前のめりの熱狂とは無縁の上品な表現でした。(18:37)
第2楽章「Intermezzo. Adagio」響きはスッキリとして、ここはピアノもオーケストラもしっとり絶品の仕上がり。(12:04)
第3楽章「Finale. Alla breve」しかしここ迄休まず弾き詰めて、この技巧の冴えはお見事、力みとか熱気に非ず気品を感じさせる優しいタッチが流麗に続いて、名残惜しく抑制を感じさせるピアノ。作品の美しさ際立って、あとはなんとも重量感と厚みの足りない音質が残念。(15:30)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
現役世代は本日お仕事や学業再開、自分は寒いし、食材在庫もまずまずあるので引き隠った昨日祝日。青森では大雪に家の倒壊が出ているそう。こちら、これより急激に気温は上がるそうだから桜は早いでしょうか。いつもの洗濯、ストレッチ、YouTubeのZumba!は継続、自分はぬくぬくとコタツに隠って、女房殿は市立体育館へ向かいました。昼から婆さん宅に介護、夕食準備して戻ってきました。こちら、在庫の野菜全部消化して、婆さん宅から回収したかなり年季の入った冷凍食品もぶち込んで調理しました。埼玉にてまたまた上水道破裂して道路冠水とか、続きますね。今朝の体重は68.0kg+250gまた危険水域に逆戻り。運動が足りないのか?左腰辺り微妙に鈍く痛みます。
日曜夜の「ナニコレ珍百景」は女房殿が好きな番組なので、付き合って拝見しております。先日そのなかの投稿に74歳キックボクシングに日々鍛える女性登場!69歳よりトレーニングを始めて、朝5時より自宅に自主トレ、毎日ジムに通って、とうとう若い選手と2ラウンドのエキジビション・マッチも経験したそう。これは励まされるなぁ、元気いただきました。
女房殿はそろそろ大東市民大学を卒業、健康ウェルネス、とくに筋トレの大切さについて学んで発表したそう。同じチームの少々齢上、シャキッとしてカッコ良い女性はいつもクルマ通学。ところが先日ちょっと一緒に歩く機会があって、歩幅が短い所謂「老人歩き」に驚いたそう。なんのために筋トレの大切さを学んだの?
市立体育途中によくお散歩のご老人夫婦に出会うけれど、もちろん健康のため、気分転換のために大切な日課。だけど、ぼちぼちゆっくり、そろりそろり歩くだけでは運動になりません。やや速歩に心拍数をちょっぴり上げる有酸素運動、そして下半身を鍛える筋トレが別途必要でしょう。自分はなんちゃってユル筋トレ全身、隔日継続中。
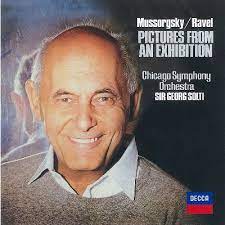 Mussorgsky 組曲「展覧会の絵」(オリジナル)/Ravel編 組曲「展覧会の絵」 /Ravel クープランの墓〜ウラディミール・アシュケナージ(p)(1982年)/ジョージ・ショルティ/シカゴ交響楽団(1980年)・・・2021年に拝聴済。・・・オリジナルの「展覧会の絵」と云えばリヒテルの鬼神の如き強靭なライヴ!(1958年)が刷り込み。アシュケナージの表現は着実なテクニックに力強く明晰、過不足ないバランス演奏。露西亜風の泥臭さは感じさせず、洗練され最終盤の盛り上げ、追い込みも立派な演奏・・・なんだけどなぁ、なんか一歩引いたような風情が感じられました。(1:29-2:38-0:52-4:39-0:27-0:57-2:39-0:46-1:09-2:25-1:27-1:19-4:18-3:30-5:45)
Mussorgsky 組曲「展覧会の絵」(オリジナル)/Ravel編 組曲「展覧会の絵」 /Ravel クープランの墓〜ウラディミール・アシュケナージ(p)(1982年)/ジョージ・ショルティ/シカゴ交響楽団(1980年)・・・2021年に拝聴済。・・・オリジナルの「展覧会の絵」と云えばリヒテルの鬼神の如き強靭なライヴ!(1958年)が刷り込み。アシュケナージの表現は着実なテクニックに力強く明晰、過不足ないバランス演奏。露西亜風の泥臭さは感じさせず、洗練され最終盤の盛り上げ、追い込みも立派な演奏・・・なんだけどなぁ、なんか一歩引いたような風情が感じられました。(1:29-2:38-0:52-4:39-0:27-0:57-2:39-0:46-1:09-2:25-1:27-1:19-4:18-3:30-5:45)
Georg Solti(1912ー1997洪牙利→英国)はシカゴ交響楽団音楽監督在任1969-1991年、世評は高かったけれど自分はあまり好んで聴く演奏家ではありません。作品との相性は選ぶかも。シカゴ交響楽団の十八番であるRavel編は自分にとって弾丸ライナー(1957年)のイメージが刷り込み。若き小澤征爾の真っ直ぐ元気な演奏とか(1967年)ジュリーニのまったりと慌てぬ辛口演奏(1976年)も印象に残っているのに、いかにも作品に似合っていそうな強靭なショルティの演奏はどうも存在感が影が薄い、印象に残らない。冒頭雄弁なトランペットは名手ハーセス(最初から最後迄凄い存在感)先頭に、技術的にはどこにも瑕疵のない大爆発+英DECCAの定評あるクリアな音質=ある意味爽快、文句あるか・・・馬力に押し切ってストレート一本、正確にリアルだけれど割り切ったようなフレージングにはユーモアの欠片もない、絵画の風情や余韻、色彩など感じさせぬドライに非情な表現。弱音部分のデリカシーにも魂がこもらぬように受け止めました。ラスト「バーバ・ヤガー」「キーウの大門」に至る圧巻の暴力的ド迫力力技は強烈、体育会系筋肉質演奏がお好きな方は存在するのでしょう。(1:39-2:28-0:59-4:40-0:33-0:59-2:40-0:48-1:12-2:17-1:21-4:10-3:23-6:23)
「クープランの墓」も緻密というか、機械的なほど正確に快速テンポ、まるでコンピューターのように味気ない。(15:59)
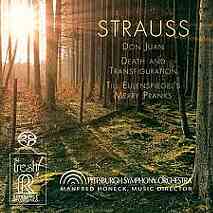 R.Strauss 交響詩「ドン・ファン」/交響詩「死と変容」/交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」〜マンフレッド・ホーネック/ピッツバーグ交響楽団(2012年)・・・Manfred Honeck(1958ー墺太利)は2008年より長期ピッツバーグ交響楽団の音楽監督。オーディオ・フリークには評判の高品質音源らしい・・・自分のオーディオ環境には無縁の話題だけど、かなり優秀録音であることは理解できました。「ドン・ファン」のヴィヴィッドな推進力、優しい部分のデリケートな対比の優雅な美しさ(18:28)「死と変容」の悠々たる優雅な歩み、粛々と洗練された響きからの高揚を聴いていると昔の金属的に重量感たっぷりのサウンド・イメージも覆ります。(26:16)「ティル」に於ける極端なリズムの強調はユーモラス、跳ね跳ぶような躍動と抑制はかつてない表情豊かなこと! 金管の驚くべきキレと爆発にオーケストラの力量をしっかり確認できました。(14:50)
R.Strauss 交響詩「ドン・ファン」/交響詩「死と変容」/交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」〜マンフレッド・ホーネック/ピッツバーグ交響楽団(2012年)・・・Manfred Honeck(1958ー墺太利)は2008年より長期ピッツバーグ交響楽団の音楽監督。オーディオ・フリークには評判の高品質音源らしい・・・自分のオーディオ環境には無縁の話題だけど、かなり優秀録音であることは理解できました。「ドン・ファン」のヴィヴィッドな推進力、優しい部分のデリケートな対比の優雅な美しさ(18:28)「死と変容」の悠々たる優雅な歩み、粛々と洗練された響きからの高揚を聴いていると昔の金属的に重量感たっぷりのサウンド・イメージも覆ります。(26:16)「ティル」に於ける極端なリズムの強調はユーモラス、跳ね跳ぶような躍動と抑制はかつてない表情豊かなこと! 金管の驚くべきキレと爆発にオーケストラの力量をしっかり確認できました。(14:50)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
本日も祝日、いったいなんの祝日なのかもうわからなくなって、じつは天皇さんの誕生日だったのですね。昨日日曜も好天、気温は低くても朝一番の洗濯、ストレッチ、そしてYouTubeは10分間のZumba!実施、2km歩いて市立体育館を目指しました。受付に定期券を出してトレーニングルームに向かったら呼び止められて、うっかり期限切れ発覚。慌てて更新済。いつも通り空いていて、昼近くに通う女房殿情報によるとけっこう混んでいるらしいから時間的な問題でしょう。新顔爺さん登場、この人がマシンを使ったあとにアルコール消毒をしないんですよ、マナー違反は困ったもの。途中の白梅は今や盛りでした。
女房殿は昼過ぎに婆さんのところに出掛けて、夕方には戻りました。前日は居酒屋だったのでしっかり夕食料理を仕立てて、呑んだ翌日でも体調は悪くありません。今朝の体重は67.75kg▲550g、まだまだ。前日呑んだ息子は奥歯にヒビが入って治療とのこと。抜くだけかな?
お仕事引退して丸三年。こどもの頃にゆっくり音楽聴いて過ごしたいな、そんな夢を見た通り、ほぼ思い描いた通りの引退生活となりました。そんなことを想像していたのはもう50年以上前のこと、当時はLP時代、あれは贅沢品、高かったですよ。やがてカセット・テープが登場して一生懸命FM放送エア・チェックしたり、MDは短い生命やったなぁ、ちょっとの間に関係オーディオ機器を処分した記憶もありました。DATも個人用としてはあまり長い時間利用しませんでした。自分にとってCDは20年くらいの付き合い?廉価盤輸入盤激安中古盤ばかりたくさん集めて喜んでました。(データよりCDRに焼き込む自主CDも大量に作成/これは未だ数百枚残存して機会あるたびに捨てております)それもお仕事引退前にキレイに全部処分済、巨大ラックも廃棄済。まさかデータで音楽を聴くようになるなんて、想像を遥かに凌駕するテクノロジーの進歩は驚くべきものですよ。
1999-2007年は岡山在住、ご近所のHARD・OFFにTANNOY のスピーカーが売っておりました。引退したら退職金で買おうかな、なんてぼんやり考えていたけれど、とうとう高級オーディオには手を出さず仕舞い。相変わらず激安オーディオのまま。(退職金の一部は歯の矯正に使って、中古TANNOYより高かった)細やかな思い出話しでした。
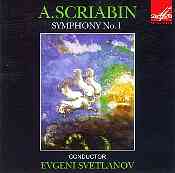 Scriabin 交響曲第1番ホ長調〜エフゲニ・スヴェトラーノフ/ソヴィエット国立交響楽団/ロシア合唱団/Larissa Avdeyeva(ms)/Anton Crigoriev(t)(1963年)・・・この作品は数年前イーゴリ・ゴロフスチン/モスクワ交響楽団(1995年)を聴いて「甘く濃密な旋律に声楽も入って・・・音量レベルが低すぎて、様子がようわかりません」とはあまりに情けない。こちら御大Yevgeny Svetlanov(1928-2002露西亜)の旧録音。音質はちょっとオフ・マイクっぽく、音像が遠い感じなのは残念でした。新録音のほうはいかがでしょうか。三管編成+ティンパニ+グロッケンシュピール、男女声楽ソロ、合唱にハープが加わって、この巨大なる合唱付き交響曲の全曲初演は1901年。当時は「圧倒的に否定的か、さもなくば無関心」(Wikiより)だったのこと。かなり後期浪漫の残滓たっぷりに甘い旋律連続、終楽章はMahlerの「復活」風。初演は1895年、後期浪漫の残滓がたっぷり漂いました。
Scriabin 交響曲第1番ホ長調〜エフゲニ・スヴェトラーノフ/ソヴィエット国立交響楽団/ロシア合唱団/Larissa Avdeyeva(ms)/Anton Crigoriev(t)(1963年)・・・この作品は数年前イーゴリ・ゴロフスチン/モスクワ交響楽団(1995年)を聴いて「甘く濃密な旋律に声楽も入って・・・音量レベルが低すぎて、様子がようわかりません」とはあまりに情けない。こちら御大Yevgeny Svetlanov(1928-2002露西亜)の旧録音。音質はちょっとオフ・マイクっぽく、音像が遠い感じなのは残念でした。新録音のほうはいかがでしょうか。三管編成+ティンパニ+グロッケンシュピール、男女声楽ソロ、合唱にハープが加わって、この巨大なる合唱付き交響曲の全曲初演は1901年。当時は「圧倒的に否定的か、さもなくば無関心」(Wikiより)だったのこと。かなり後期浪漫の残滓たっぷりに甘い旋律連続、終楽章はMahlerの「復活」風。初演は1895年、後期浪漫の残滓がたっぷり漂いました。
第1楽章「Lento」木管と弦による瞑想的幻想的に静謐な始まり。ヴァイオリン・ソロもたっぷり歌って、爽やかに耽美的な旋律がデリケートに絡み合って爆発場面が存在しない。さすがスヴェトラーノフのオーケストラには余裕の厚み有。遠いホルンにほのかに例のヴィヴラートが木霊します。(7:51)
第2楽章「Allegro dramatico」ホ短調による不安げな、小さな躍動とスムースな疾走。ここもホルンのエッチなヴィヴラートが効果的に響きます。やがて雄弁な浪漫風盛り上がりがやってきても音像が遠く、期待の金管や打楽器爆発には足りないような気がする。(8:14)
第3楽章「Lento」オーボエの切ない旋律から始まって弦がサポートする緩徐楽章。リヒャルト・ワーグナーを連想させるトリスタン和声(Wikiより)なんだそう。なるほど、官能に迫り上がっていく情緒の高揚がなかなかセクシーでした。ここもホルンのヴィヴラート出現は期待通り。(9:39)
第4楽章「Vivace」はハ長調のユーモラスに躍動するスケルツォ。一貫して弱音にデリケートに奏されます。(3:15)
第5楽章「Allegro」ホ短調の哀愁にうねうねした旋律は弦に始まって、情緒豊かに高揚を続ける実質上の最終楽章。しみじみとした風情にイマイチの爆発を望みたいのは音質印象でしょうか。Scriabinは魅惑のメロディ・メーカーと思います。(6:55)
第6楽章「Andante」Scriabin自作による「芸術賛歌」声楽入り。木管の静かな導入からメゾ・ソプラノ、テナーも参入して爽やかな表情に、穏健な情感が広がります。やがて転調して金管参入、ここの響きがちょっと薄くて残念。合唱は「地上の全能の支配者よ、そなたは人を揺り動かして栄えある行いをせしむる。万人よ来たれ、芸術の許に。われら芸術賛歌を歌わん」(Wikiより)フーガに歌ってクライマックスを迎えるけれど、Mahlerの「復活」(1895年初演)風とことん大仰に雄弁な爆発には足らん感じ。(12:46)
 Berlioz 幻想交響曲〜ポール・パレー/デトロイト交響楽団(1959年)・・・久々の拝聴。いやもうこれは一切の逡巡や躊躇いのない一気呵成、乾いて飾りも色気も一切ない快速、即物的ストレート表現一本槍。音質はかなり良好、デトロイト交響楽団は鳴り切って、アンサンブルに優れ、繰り返しはありません。名曲故に星の数ほど新旧録音は存在するけれど、これは際立って個性的な淡麗辛口演奏、味も素っ気もないと云われても仕方がない。しかし、この作品を食傷気味に聴き過ぎた人には新鮮に響くかも・・・自分は大好き。(11:30-5:33-14:37-4:28-8:56)
Berlioz 幻想交響曲〜ポール・パレー/デトロイト交響楽団(1959年)・・・久々の拝聴。いやもうこれは一切の逡巡や躊躇いのない一気呵成、乾いて飾りも色気も一切ない快速、即物的ストレート表現一本槍。音質はかなり良好、デトロイト交響楽団は鳴り切って、アンサンブルに優れ、繰り返しはありません。名曲故に星の数ほど新旧録音は存在するけれど、これは際立って個性的な淡麗辛口演奏、味も素っ気もないと云われても仕方がない。しかし、この作品を食傷気味に聴き過ぎた人には新鮮に響くかも・・・自分は大好き。(11:30-5:33-14:37-4:28-8:56)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
週末から連休は厳しい寒さとのこと。こちら天気は良いですね。前夜女房殿は婆さん宅に泊まり、独りさっさと就寝したらなぜか寝付き悪く、挙げ句途中覚醒、二度寝も叶わず起き出してしまいました。ちゃんと前日しっかり運動もしたはずなのに、どうもあきまへん。音量低く音楽など拝聴して、やがて朝食はいつもどおり、ストレッチしてYouTubeのHIIT(High Intensity Interval Training/高強度インターバルトレーニング)10分ほど済ませました。女房殿が婆さんのところで飯を喰うのなら、わざわざの料理はあまり必要ないけど、ちょっと食材は不足気味、業務スーパーに往復3.3kmほどウォーキング兼食材補充に出掛けました。スキムミルクとか切れそうだったので。いちおうこれでスマホ・アプリ上は一日の運動量達成。女房殿は昼前に帰宅して市立体育館へ、弟と介護交代。久々にちゃんとした夕食を仕立てようと準備していたら、息子(40歳)の休日出勤が早めの終わるとの連絡有、せっかくのダイエットも台無しにまたまた居酒屋に出掛けました。連休初日の梅田駅前ビル地下は混んでおりました。しっかり呑んで喰って、女房殿のストレス解消の意味もあります。今朝の体重は68.35kg+500gも自業自得。これから鍛えて減らしましょう。
芸能人の消息にはほとんど興味はないけれど、最近見ないなと思ったロス五輪体操金メダリストの森末慎二さん。宮古島で天丼専門店を経営していたんですね。なんと自分と同い齢、同世代だったのか。スポーツマンとして超一流、芸能界に十数年活躍して、なんか水のトラブルのCMにも出てましたっけ。スポーツ選手の引退後はいろいろ生活設計が難しいと伺ったけれど、ちゃんと次の道を模索して立派やなぁ、自分の無為無策な現状を考えると溜息も出そうになる・・・ま、いまのところ、そこそこ元気だから文句はあまりありません。
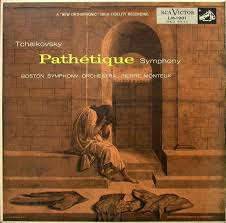 Tchaikovsky 交響曲第6番ロ短調「悲愴」〜ピエール・モントゥー/ボストン交響楽団(1955年)・・・先日、久々に聴いてその音質にガッカリ〜と書いたばかり。昔からの記憶ではかなり優秀なRCA Living Stereo録音だったはず、世評を伺っても高品質CD化の好ましい声もあるから、それは偶然自分が入手した音源の巡り合わせと考えて、他のものを探しました。なんせ1955年初期ステレオ録音、ちょっと左右分離を強調し過ぎな録音(対向配置でもある)だけど、ようやくかなりの手応えにかつての記憶と感激が蘇って、こどもの時から馴染みの「悲愴」は新鮮。Tchaikovskyの憂愁甘美な旋律が慟哭する名曲をたっぷり堪能できました。Pierre Monteux(1875ー1964仏蘭西)既に80歳の記録。ボストン交響楽団はシャルル・ミュンシュ時代。
Tchaikovsky 交響曲第6番ロ短調「悲愴」〜ピエール・モントゥー/ボストン交響楽団(1955年)・・・先日、久々に聴いてその音質にガッカリ〜と書いたばかり。昔からの記憶ではかなり優秀なRCA Living Stereo録音だったはず、世評を伺っても高品質CD化の好ましい声もあるから、それは偶然自分が入手した音源の巡り合わせと考えて、他のものを探しました。なんせ1955年初期ステレオ録音、ちょっと左右分離を強調し過ぎな録音(対向配置でもある)だけど、ようやくかなりの手応えにかつての記憶と感激が蘇って、こどもの時から馴染みの「悲愴」は新鮮。Tchaikovskyの憂愁甘美な旋律が慟哭する名曲をたっぷり堪能できました。Pierre Monteux(1875ー1964仏蘭西)既に80歳の記録。ボストン交響楽団はシャルル・ミュンシュ時代。
第1楽章「Adagio - Allegro non troppo」さらりと速めのテンポ、詠嘆や絶叫を強調しない。かなりさっぱりとした語り口に、モントゥーの統率も推進力もおみごと。ボストン交響楽団は明るい響きに優秀なアンサンブル、管楽器のヴィヴラートも魅力的でした。(17:30)
第2楽章「Allegro con gracia」は4/5拍子の甘いワルツ。弾むように淡く、軽快にリズムを刻みました。ステキなフルートはDoriot Anthony Dwyer(1922-2020亜米利加)ですかね。(7:05)
第3楽章「Allegro molto vivace」そっと始まる行進曲風、爆発も抑制気味にデリケートなスケルツォ。かっちりと力まず、流れを重視した表現でしょう。(9:05)
第4楽章「Finale: Adagio lamentoso- Andante」悲劇的な旋律が左右ヴァイオリンに振り分けれて効果的なフィナーレ。慟哭に非ず、楚々とした哀しみが溢れる風情にここも意外なほど淡白に抑制が効いた表現でした。弦も管も美しく洗練された響き、やがて情感の高まりへの流れ、テンポの揺れも恣意性を感じぬもの。銅鑼が鳴って最後の審判のようなトローンボーンのヴィヴラートの色気、そして弦の泣きが楚々として低弦の動きもリアルに消えていきました。(10:35)
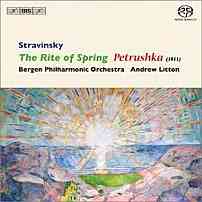 Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1911年版/2009年)/バレエ音楽「春の祭典」(2008年)〜アンドルー・リットン/ベルゲン・フィル・・・Andrew Litton(1959-亜米利加)は2003-2015迄ベルゲン・フィルの首席在任。これは惚れ惚れするほどクリアな優秀録音、オリジナル四管編成に分厚い響きの「ペトルーシュカ」(10:08-4:14-6:32-14:01)そして20世紀の古典「春の祭典」(15:39-18:25)いずれもベルゲン・フィルの迫力や熱気、勢いも正確な技量も充分、華やかに細部迄クリア、弦も管もそして打楽器の低音も見事に響いて文句なし。正直なところ、ちょっと予想外の上出来に驚かされました。
Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1911年版/2009年)/バレエ音楽「春の祭典」(2008年)〜アンドルー・リットン/ベルゲン・フィル・・・Andrew Litton(1959-亜米利加)は2003-2015迄ベルゲン・フィルの首席在任。これは惚れ惚れするほどクリアな優秀録音、オリジナル四管編成に分厚い響きの「ペトルーシュカ」(10:08-4:14-6:32-14:01)そして20世紀の古典「春の祭典」(15:39-18:25)いずれもベルゲン・フィルの迫力や熱気、勢いも正確な技量も充分、華やかに細部迄クリア、弦も管もそして打楽器の低音も見事に響いて文句なし。正直なところ、ちょっと予想外の上出来に驚かされました。
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
ガーラ湯沢スキー場では雪が降り過ぎて駐車場閉鎖とか、週末連休に向けて全国的に厳しい天候になるそう。昨日早朝洗濯途中にゴミ出しをしたけど、寒かったなぁ。冷えるけれどこちらは好天です。幸い咽の痛みも口内炎も悪化せず、体調は大丈夫。本日より一週間お嫁さんと孫二人は天草の実家へ、向こうの爺婆は狂喜乱舞でしょう。息子は独りお留守番だから誘って呑みにいこうかな?でも、出掛けるのも億劫な感じ。自分はいつもどおりのストレッチ、YouTube鍛錬済ませてから市立体育館へゆる筋トレ、女房殿はこども食堂のボランティア経由婆さんのところへ。週2回のデイ・サービスはコロナ患者が出たとかで入浴は休止中なんだそう。自分は年柄年中連休状態、なにもしておりません。今朝の体重は67.85kg▲300g。思うように減りません。
自分には縁があまりないようにも感じるけれど・・・トランプさんの二期目は、間違って当選して準備不足だった第一期とは違って周到な手筈、有言実行にやりたい放題。公約を守る!その点では立派と云えば立派だけど、それが思い描いた通りの佳き結果になるのかは不明です。プーチンは好きだけど(思い通りに動かぬ)ゼレンスキーさんは嫌いみたいで「独裁者」呼ばわりしておりますね。痩せても枯れても亜米利加は大国、その影響は巡り巡ってどんな結果に至るのか。ま、戦争はあまり好きじゃない人みたいだから、その点はマシなのかも。欧州の極右政党を公然と応援してます。
幾度も書いたけれど、日本ではコメと野菜が高騰。その対策はほとんど無為無策に見えます。ガソリンとか電気ガス、なにもかも値上がりしているけれど、これは世界情勢もあるけれど、これから自分の老後生活の見通しに狂いが出かねない・・・なんて、場末の引退爺同士激安酒場で愚痴って駄弁ってもなんの社会的影響もありません。残念。
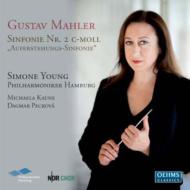 Mahler 交響曲第2番ハ短調「復活」〜シモーネ・ヤング/ハンブルク州立フィル/ミヒャエラ・カウネ(s)/ダグマル・ペチコヴァー(a)/北ドイツ放送合唱団/ラトヴィア国立合唱団(2010年)・・・Simone Young(1961-濠太剌利)はハンブルク・オペラ総監督を2005-2015年在任、その辺りの録音でした。10年以上前に拝聴。シドニー交響楽団と2022年新録音が出て、これは旧録音。Brucknerには新鮮な印象を得たけれど、こちらにはさほどでもない出足オーソドックスにまずまず、あまりオモロない演奏でした。オーケストラの渋い響きは魅力だけれど、さすがオペラの人、声楽の扱いが上手くて本領発揮は第4楽章〜フィナーレでしょう。ラストの壮麗な盛り上がりはほんまに立派に感動的に締め括って下さいました。
Mahler 交響曲第2番ハ短調「復活」〜シモーネ・ヤング/ハンブルク州立フィル/ミヒャエラ・カウネ(s)/ダグマル・ペチコヴァー(a)/北ドイツ放送合唱団/ラトヴィア国立合唱団(2010年)・・・Simone Young(1961-濠太剌利)はハンブルク・オペラ総監督を2005-2015年在任、その辺りの録音でした。10年以上前に拝聴。シドニー交響楽団と2022年新録音が出て、これは旧録音。Brucknerには新鮮な印象を得たけれど、こちらにはさほどでもない出足オーソドックスにまずまず、あまりオモロない演奏でした。オーケストラの渋い響きは魅力だけれど、さすがオペラの人、声楽の扱いが上手くて本領発揮は第4楽章〜フィナーレでしょう。ラストの壮麗な盛り上がりはほんまに立派に感動的に締め括って下さいました。
第1楽章「Allegro maestoso」聴手をぐっと引き寄せる魅惑の緊張感はもっとほしいところ。(20:34)
第2楽章「Andante moderato」ここも淡々とオーソドックスな表現。(9:29)
第3楽章「In ruhig fliessender Bewegung(穏やかに流れる動きで)」冒頭衝撃のティンパニからの3/8拍子、ここはもっとオモロいリズムなんやけどなぁ。(10:45)
第4楽章「Urlicht: sehr feierlich, aber schlicht (原光:きわめて荘厳に、しかし簡潔に )」この辺りから雰囲気はグッと盛り上がって(5:18)
第5楽章「Finale: in Tempo des Scherzos(スケルツォのテンポで )」万感胸に迫る壮麗な管弦楽声楽の構築物がみごとなクライマックスに至りました。(33:18)
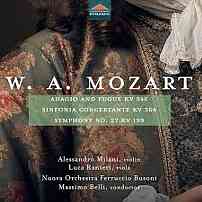 Mozart アダージョとフーガ ハ短調 K. 546/協奏交響曲 変ホ長調 K. 364/交響曲第27番ト長調 K. 199(161b)〜マッシモ・ベッリ/新フェルッチョ・ブゾーニ室内管弦楽団 /アレッサンドロ・ミラーニ(v)/ルカ・ラニエーリ(va)(2022年)・・・Massimo Belliの詳細情報調べ付かず。新フェルッチョ・ブゾーニ管弦楽団とは、1965年にトリエステのヴェルディ歌劇場のメンバーによって創設された団体とのこと。モダーン楽器による引き締まったサウンド、所謂古楽器系の影響を受けたリズムにはキレがあって、やや硬質に窮屈っぽい感じでした。直接音中心に音質は極めてクリア。
Mozart アダージョとフーガ ハ短調 K. 546/協奏交響曲 変ホ長調 K. 364/交響曲第27番ト長調 K. 199(161b)〜マッシモ・ベッリ/新フェルッチョ・ブゾーニ室内管弦楽団 /アレッサンドロ・ミラーニ(v)/ルカ・ラニエーリ(va)(2022年)・・・Massimo Belliの詳細情報調べ付かず。新フェルッチョ・ブゾーニ管弦楽団とは、1965年にトリエステのヴェルディ歌劇場のメンバーによって創設された団体とのこと。モダーン楽器による引き締まったサウンド、所謂古楽器系の影響を受けたリズムにはキレがあって、やや硬質に窮屈っぽい感じでした。直接音中心に音質は極めてクリア。
深刻な風情のアダージョとフーガ ハ短調 K. 546は少人数、切迫して前のめりな弦楽アンサンブル。(6:35)
協奏交響曲 変ホ長調 K. 364はすごぶるヴィヴィッドにメリハリたっぷりに軽快、天才の天翔る晴れやかな名曲ですよ。第1楽章「Allegro maestoso」から、おそらくは団員と類推されるソロも思いっきりノリノリに歌い交わします。ソロは美しくも名残惜しいヴィヴラート、端正なヴァイオリンに、ヴィオラは雄弁でした。(13:21)第2楽章「Andante」しっとり哀しみからの情感の高まりは絶品!(10:37)第3楽章「Presto」快活にキレッキレのソロが掛け合って、スリムなサウンドに歓喜が疾走しました。(6:36)
交響曲第27番ト長調 K. 199はフルート2/ホルン2/弦楽5部の編成、1733-34年ザルツブルク時代の作品。第1楽章「Allegro」快活、溌溂なリズムを刻んで華やかに走り出す始まり(6:42)第2楽章「Andante grazioso」淡々としたピチカートのリズムに乗って、弱音器付きのヴァイオリンが優しく、憂いを含んで歌いました。フルートも思わぬ存在感に登場。(8:16)第3楽章「Presto」はヴィヴィッドに躍動する主題から、力強いフーガに締め括りました。(5:53)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
前日呑んだ翌日、咽が少々痛い。口内炎もあります。ちょっとヤバいかなぁ、熱はなくて倦怠感もありません。前日人混みに出掛けて呑んだから自業自得。洗濯して、いつものストレッチ、10分ほどのスワイショウを実施して、あとはコタツにじっとしておりました。良い天気だったけれど、こちらも氷点下迄下がったみたい。昨年2024年10月、ちょうど火が出た辺りに通り掛かった火事現場に三人亡くなった件、それはお母さんの葬儀に集まった兄弟と父親、次男が放火した疑いが持たれ、書類送検に至ったらしい。父親には介護が必要となって、将来を悲観したのではないか、とのこと。ほんの近所に悲劇はあるものですね。今朝の体重は68.15kg+250g。かなり食事を抑制して菓子も喫していないのに減りませんでした。残念。
またまたマニアックなヲタク趣味話題だけど、せっかく集めたBruno Walter-Columbia Recordings-69CD分の圧縮ファイルは23枚目迄しか閲覧できない〜そんな類の話題は以前言及済。なんとか四苦八苦しつつ全部解凍して分割再圧縮保存出来、ほっとしたけれど・・・そんな作業をしつつ拝聴したのは
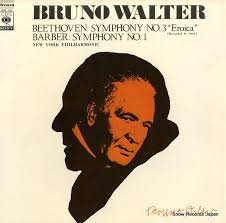 Beethoven 交響曲第3番 変ホ長調「英雄」〜ブルーノ・ワルター/ニューヨーク・フィル(1941年)・・・颯爽として明るい響き、SP復刻も乾き気味だけどかなり良心的な音質。第1楽章提示部繰り返しはなし。Bruno Walter(1876ー1962独逸)未だ元気な65歳、ニューヨーク・フィルは快調に力こぶが入ったアクセント、意外とバランスのよろしい演奏を堪能しつつ、色々感慨有。(15:14-16:30-4:34-15:14)
Beethoven 交響曲第3番 変ホ長調「英雄」〜ブルーノ・ワルター/ニューヨーク・フィル(1941年)・・・颯爽として明るい響き、SP復刻も乾き気味だけどかなり良心的な音質。第1楽章提示部繰り返しはなし。Bruno Walter(1876ー1962独逸)未だ元気な65歳、ニューヨーク・フィルは快調に力こぶが入ったアクセント、意外とバランスのよろしい演奏を堪能しつつ、色々感慨有。(15:14-16:30-4:34-15:14)
古民家再生、ゴミ屋敷片付け、親が溜め込んだ荷物整理、そんな動画を見るのは大好き。ちょうどその日も、未だ御健在な両親宅玄関に溢れる、膨大なる靴の点検整理廃棄作業でした。足は二つしかないのに、驚くほどの物量! 彼(か)の購入欲が日本の経済成長を支えたのか。もう朽ち果てたものはさておき、これは高かった、思い出がある、使うかも知れない・・・いつまでも捨てられない・・・これは自分にも思い当たるフシがありました。
ブルーノ・ワルターは好きだけれど、意外と拝聴機会は少なくて、とくにモノラル時代旧録音にはあまり食指が伸びないもの。「使いもしない(聴かない)ものを溜め込んで、やがてその存在さえ忘れる」って、自分のことじゃん。この作業の前に「Haydn」音源の点検確認整理をしていて、うわぁこんな珍しいの持っていたんだっけ、これはダブっているから削除とか、ま、老後の趣味としては充実しているけれど、ちょっと虚しさも感じたもの。一年ほど前?一生懸命集めたハンス・スワロフスキーのHaydn音源を一箇所に集めて、挙げ句誤って全削除廃棄にガッカリ、でもその後、Haydn音楽拝聴にあまり不自由はしていないのもリアルな事実。集めるだけじゃ意味ないよね。
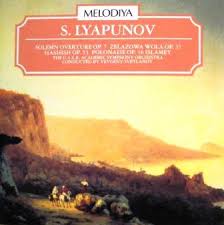 Lyapunov ロシアの主題による荘厳序曲 ハ長調 作品7/交響詩「ジェラゾヴァ・ヴォラ」作品37/ 東洋風交響詩「ハシシ」変ロ短調 作品53/ポロネーズ ニ長調作品16/Barkorev イスラメイ(Lyapunov編)〜エフゲニ・スヴェトラーノフ/ソヴィエット国立交響楽団(1986年)・・・できるだけ未知の作曲家作品に見聞の幅を広げようと、Sergey Lyapunov(1859-1924露西亜)を聴いてみました。最後の国民楽派、Anatoly Lyadov(1855-1914露西亜)と並んで微妙な時期の作曲家らしい。いままでほとんど拝聴機会はなくて「イスラメイ」の管弦楽編曲に名前があったののを記憶するくらい。露西亜革命(1917年)前が主たる活躍の時期、甘美なTchaikovskyやRachmaninovの濃密に非ず、次世代のStravinskyのような原始的破壊的エネルギーでもない、どの作品もほとんど穏健保守的な旋律サウンドは甘さ控えめにきちんと類型的、演奏機会が少ないのも頷けました。Yevgeny Svetlanov(1928- 2002露西亜)はCD3枚分の録音を残しております。
Lyapunov ロシアの主題による荘厳序曲 ハ長調 作品7/交響詩「ジェラゾヴァ・ヴォラ」作品37/ 東洋風交響詩「ハシシ」変ロ短調 作品53/ポロネーズ ニ長調作品16/Barkorev イスラメイ(Lyapunov編)〜エフゲニ・スヴェトラーノフ/ソヴィエット国立交響楽団(1986年)・・・できるだけ未知の作曲家作品に見聞の幅を広げようと、Sergey Lyapunov(1859-1924露西亜)を聴いてみました。最後の国民楽派、Anatoly Lyadov(1855-1914露西亜)と並んで微妙な時期の作曲家らしい。いままでほとんど拝聴機会はなくて「イスラメイ」の管弦楽編曲に名前があったののを記憶するくらい。露西亜革命(1917年)前が主たる活躍の時期、甘美なTchaikovskyやRachmaninovの濃密に非ず、次世代のStravinskyのような原始的破壊的エネルギーでもない、どの作品もほとんど穏健保守的な旋律サウンドは甘さ控えめにきちんと類型的、演奏機会が少ないのも頷けました。Yevgeny Svetlanov(1928- 2002露西亜)はCD3枚分の録音を残しております。
どの作品も優等生的によくできているけれど、例えばBorodinのようなぐっと泥臭いオリエンタルな魅惑とか(「ハシシ」辺りちょっと似ているけれど/これはなかなかの盛り上がりを見せる名曲)Rimsky-Korsakovみたいにきらびやかデーハーに効果的な管弦楽法とか、その辺りをイメージすると「映え」が足りぬオーソドックスがいまいちオモロない印象でした。スヴェトラーノフの演奏は相変わらずパワフルですよ。ラスト「イスラメイ」はピアノの超絶技巧作品からの管弦楽編曲、これはオーケストラの腕の見せ所。強烈な作品であり、安寧静謐部分も際立ってみごとな演奏でした。(15:40-14:53-23:47-7:24-7:56)
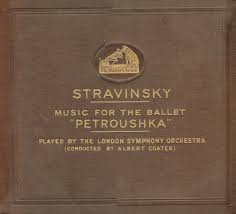 Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」〜アルバート・コーツ/ロンドン交響楽団(1927-1929年)・・・改訂版出現前、もちろん正真正銘の四管編成のオリジナル版(と、思う/詳細カットや編成云々は不明)そしてこの時期にしてかなりの鮮度、驚異の音質。SP盤面ごとに音の雰囲気が替わるのもリアル、打楽器がちょっと遠く、弱いけれど低音の伸び、臨場感、解像度含めて作品を堪能するにほとんど不足を感じさせません。この時期のロンドン交響楽団は既に優秀な技量を誇って、Albert Coates(1882ー1953英国)の統率がここまで立派なものだったとは!ちょっと前のめりにヴィヴィッドな勢い、遊園地?祭りの喧騒はウキウキと感じられて、資料的価値を凌駕する記録と受け取りました。(30:10)ちょっと音質は落ちるけれど、YouTubeで聴けます。
Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」〜アルバート・コーツ/ロンドン交響楽団(1927-1929年)・・・改訂版出現前、もちろん正真正銘の四管編成のオリジナル版(と、思う/詳細カットや編成云々は不明)そしてこの時期にしてかなりの鮮度、驚異の音質。SP盤面ごとに音の雰囲気が替わるのもリアル、打楽器がちょっと遠く、弱いけれど低音の伸び、臨場感、解像度含めて作品を堪能するにほとんど不足を感じさせません。この時期のロンドン交響楽団は既に優秀な技量を誇って、Albert Coates(1882ー1953英国)の統率がここまで立派なものだったとは!ちょっと前のめりにヴィヴィッドな勢い、遊園地?祭りの喧騒はウキウキと感じられて、資料的価値を凌駕する記録と受け取りました。(30:10)ちょっと音質は落ちるけれど、YouTubeで聴けます。
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
寒いなぁ、天気はよろしいけど。週末に向けて大寒波到来の予報となっております。既に東北新幹線は止まったとか、山陽新幹線が遅れているとか。なんか微妙に体調いまいち、前夜半に一生懸命スワイショウをしておきました。朝一番の洗濯物はけっこう大量、ストレッチもサボらず、YouTube鍛錬は最近お気に入り「EMMA Fitness」実施。どこの国かはわからんけど元気一杯な東南亜細亜系の女性たち、真ん中に仕切っているお姉さんがノリノリのリズムに乗って、自在に動きを変化させて、取り巻きがその動き合わせる(あまりきっちりとは合っていないのがラフでエエ感じ)といった趣向でした。要らん説教とか説明とか励ましもない20分、朝から汗が出ました。そのまま勢いをつけて市立体育館へ、なんか年明けはずっと空いてますね。ゆっくりマシンを使って帰り、ちょっぴり食材買い物にスーパーに寄りました。
昼過ぎのんびり、ぼんやりして居眠りしていたら爺友からLINE連絡有。いつもよりやや遅くに出掛けて、いつもの梅田駅前ビル地下居酒屋でいつもの馬鹿話もボケ防止のつもり。一軒目に寄った店がとても不味くて即退出、二軒目へ、今月三度目の散財、ちょっと呑み過ぎました。今朝の体重は67.9kg+100gも自業自得、心入れ替えてダイエット再開、厳しい寒さを乗り切りましょう。
テレビはあまり見ないけど、BS辺りを試しに覗いてみると通販番組が多くて早朝なんてそればかり、けっこう需要はあって成り立っているんでしょうね。やたらと健康食品健康衣料や用具機器のCMが多い。団塊の世代は健康食品が好きなのか、黒酢とかすっぽんとかニンニク、コンドロイチンが有り難いのか(紅麹!?とか)利用者は多いと類推されるのは両親のゴミ屋敷片付け動画を眺めるとわかります。身体鍛える努力抜きに、カネ掛けてなんとかしようとするのはあまりよろしくない考えかと。
ホンダとの経営統合が破談になった日産のCMもけっこう頻繁、クルマは売れていくなくて大赤字出てタイヘンなんでしょ?それでもCMは止められないのか。クルマつながりで【WECARS】のCMも精力的、これってBIGMORTOR後継会社、経営者も変わって、従業員教育も徹底して誠実に生まれ変わったのでしょうか。(被害者への補償などを行う存続会社BALMとは別とのこと)彼(か)のパワハラ元副社長は何処?似たような行状に不正経理していたGOODSPEEDはその後どうなったのか(検索すると債務超過、別会社に買い取られたそう)後追い報道はすっかり消えて、話題は現在中井/フジテレビに移ってしまったのか。それも即過去の話題に消えてしまうのかも知れません。あえなく倒産したFUNAIの建物は毎日ように恨めしく拝見しております。
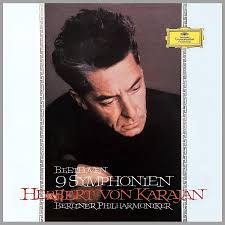 Beethoven 交響曲第7番イ長調/交響曲第8番ヘ長調〜ヘルベルト・カラヤン/ベルリン・フィル(1962年)・・・なにを今更な鉄板中の鉄板演奏。あまりに評判になり過ぎて、かつて「アンチ・カラヤン」という言葉も存在、それさえ死語となって「棺を覆いて事定まる」先人の言葉通り、冷静にHerbert von Karajan(1908ー1989墺太利)の遺産を堪能できる時代となりました。幾度聴いているようで、古楽器やデイヴィッド・ジンマンのBeethovenが気に入って以来、ここ数十年聴いていないかも。
Beethoven 交響曲第7番イ長調/交響曲第8番ヘ長調〜ヘルベルト・カラヤン/ベルリン・フィル(1962年)・・・なにを今更な鉄板中の鉄板演奏。あまりに評判になり過ぎて、かつて「アンチ・カラヤン」という言葉も存在、それさえ死語となって「棺を覆いて事定まる」先人の言葉通り、冷静にHerbert von Karajan(1908ー1989墺太利)の遺産を堪能できる時代となりました。幾度聴いているようで、古楽器やデイヴィッド・ジンマンのBeethovenが気に入って以来、ここ数十年聴いていないかも。
「舞踏の聖化」である交響曲第7番イ長調は古典的二管編成+ティンパニ。第1楽章「Poco sostenuto - Vivace」から速めのテンポに重量級のサウンドにテンション高く、ベルリン・フィルのサウンドは艷やかに弦も管も磨き上げられて颯爽とスタイリッシュ、自分が若い頃はこれがどうにもハナに付いて仕方がなかった、そんな記憶も雲散霧消。(提示部繰り返しなし/11:27)第2楽章「Allegretto」初めて聴いたときからこの変奏曲は好きやったなぁ。ここも急ぎ足に速めのテンポ、颯爽としてカッコよろしく弦も管もさわさわと極上の洗練。(8:02)第3楽章「Presto, assai meno presto」スケール巨大なる重量級スウィングのメヌエットはティンパニが圧巻の存在感。このリズム感は先進的な作品と感じます。(7:48)第4楽章「Allegro con brio」ここも重いのに速めのテンポに、リズムの勢いがモウレツな追い込み。ホルンの潰れた音色最高、大見得を切るようなタメも決まって、テンションは最高潮。ベルリン・フィルの圧倒的パワー威力に最初っから最期迄ぐうの音も出ない。ちょっと感覚が麻痺しそう。(6:35)
革新的な趣向が多く取り入れられている交響曲第8番ヘ長調も同じく古典的二管編成+ティンパニ。第1楽章「Allegro vivace e con brio」からオーケストラのパワー全開!まるで重量級の蒸気機関車が疾走するような濃い存在感と勢いたっぷり。(9:22)第2楽章「Allegretto scherzando」意表を付いたシンプルなリズムの刻み。緩徐楽章に非ず、これはスケルツォ?ヴィヴィッドな色気を感じさせます。(3:58)第3楽章「Tempo di menuetto」優雅にまったり落ち着いた表現のメヌエット、Haydn辺りとは随分遠い雄大なる浪漫の世界に至りました。トリオのホルンの深い響きは絶品。(5:59)第4楽章「Allegro vivace」ここも速いテンポに重量級の蒸気機関車疾走して、余裕の馬力に微笑みを感じさせる余力とユーモア。(7:18)
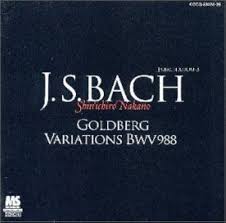 Bach ゴールトベルク変奏曲BWV988〜中野振一郎(cem)(1999年)・・・日本が世界に誇る中野振一郎さん(1964-京都)によるBach屈指の名曲音源を入手したら・・・既に手許にあって、そう云えば薄っすらと聴いた記憶もありました。こちらDENON録音、これは古楽器レプリカFlemish double-manual harpsichord使用(今回聴いたのはこれ)同時にモダーン・チェンバロNeupert modelによる録音をしておりました。Mesiter Music(c)(p)2006(詳細情報不明)録音とは音質も楽器の音色も、タイミングもまったく違うからそれは再録音らしい。
Bach ゴールトベルク変奏曲BWV988〜中野振一郎(cem)(1999年)・・・日本が世界に誇る中野振一郎さん(1964-京都)によるBach屈指の名曲音源を入手したら・・・既に手許にあって、そう云えば薄っすらと聴いた記憶もありました。こちらDENON録音、これは古楽器レプリカFlemish double-manual harpsichord使用(今回聴いたのはこれ)同時にモダーン・チェンバロNeupert modelによる録音をしておりました。Mesiter Music(c)(p)2006(詳細情報不明)録音とは音質も楽器の音色も、タイミングもまったく違うからそれは再録音らしい。
チェンバロは実演に接すると驚くほど音量小さく、デリケートなもの。DENONによる近接したリアルな収録は音量たっぷり、各変奏ごとの微妙なタッチや音色の違いが手に取るように理解できるものでした。かなりノリノリ、リズミカルな演奏は古楽器?と訝(いぶか)るほどに雄弁、表情は豊かに鳴り響きました。なんせお気に入りの作品、変幻自在に延々と続く変奏曲は後半に向かうほど熱気を帯びて、たっぷり感銘受け止めました。
(アリア)3:52-2:37-1:53-2:42-1:11-1:56-1:28-2:07-2:41-1:57-1:44-2:12-2:53-4:02-2:20-4:30-2:58-2:37-1:30-1:25-2:54-2:53-1:22-2:30-2:51-7:15-2:08-2:12-2:33-2:27-1:58-(アリア)4:09
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
前夜Netflixを誤って契約延長したリベンジ、だらだらと某連続ドラマを一気見してしまって夜更かし。睡眠不足になったのも情けない感じ。外はどんより曇って寒そうだし、体調を勘案して引き隠って野菜などを煮ておりました。ストレッチと数日前気に入ったYouTubeのHIITトレーニング再度実施しました。女房殿は昼前に帰宅して、市立体育館へ向かいました。自分は昼にピーナツをけっこう喰ってしまって体重は67.8kg+500g残念。
【水道管の破損相次ぐ】1km交換するのに2億円〜前々から薄々知っていたけれど、これはタイヘンな事態がいよいよ具現化してきました。鉛製給水管なお残200万件・・・20年前に全廃目標、水道管から溶け出し腹痛や神経のまひの恐れ〜そんな報道もあって、わかっていた問題を先送りしたんやろなぁ、地方自治体の関係者も。これは上水道の話題だけれど、昨今問題になっている下水道の老朽化とは別ですよ。いやほんま、これからどうなるんでしょう。上下水に限らず、多くのインフラが老朽化して危うくなっていると類推します。国もそうだけど、地方自治体の中長期経営的な視点が欠けている。民間だったら当然施設の計画的更新はあたりまえでしょう。
 Bruckner 交響曲第5番 変ロ長調〜マルクス・ボッシュ/アーヘン交響楽団(2005年ライヴ)・・・Marcus Bosch(1969-独逸)によるBruckner交響曲全曲録音は先に第9番短調(1894年原典版/2000年グンナー・コールス校訂/フィナーレ付き)を聴いておりました。アーヘンの歌劇場のオーケストラはやや響きがヤワい感じはあるけれど、残響豊かに爽やかに素直な響き。この作品は第8番ハ短調と並んで、屈指の巨大なる威容を誇る名曲、自分はこれが一番好き。
Bruckner 交響曲第5番 変ロ長調〜マルクス・ボッシュ/アーヘン交響楽団(2005年ライヴ)・・・Marcus Bosch(1969-独逸)によるBruckner交響曲全曲録音は先に第9番短調(1894年原典版/2000年グンナー・コールス校訂/フィナーレ付き)を聴いておりました。アーヘンの歌劇場のオーケストラはやや響きがヤワい感じはあるけれど、残響豊かに爽やかに素直な響き。この作品は第8番ハ短調と並んで、屈指の巨大なる威容を誇る名曲、自分はこれが一番好き。
第1楽章「Adagio - Allegro」中庸のテンポに恣意的な動きのない、流れは自然な始まり。重心低い渾身の重量感!と云ったサウンドではないけれど、ハデさはなくて、金管にはちょっぴりパワーが足りない。(19:35)
第2楽章「Adagio」浮き立つような高揚感に、気持ちよろしく情感が高まっていく緩徐楽章。弦も管も響きが素直過ぎて、さらさらと、ちょっと物足りないほど爽やかサウンドはBrucknerとしてはちょっと異形でしょう。(16:00)
第3楽章「Scherzo: Molto vivace」このスケルツォのリズム感はけっして軽くないけれど、どうもサウンドにエッジが足らん感じ。勢いある快活な第1主題と、ノンビリとした第2主題(レントラー)との対比は、いま一歩の緊張感が欲しい散漫な印象から、ラストはアッチェレランドに切迫感を加えました。トリオは早足にさっぱりエエ感じの可愛らしさ。(13:12)
第4楽章「Finale: Adagio - Allegro moderato」前のめりの速めのテンポに勢いあるフィナーレ。荘厳な金管のコラールから圧巻のクライマックスに向けてさらさらと爽やか軽快なサウンドは最後迄継続します。(22:59)
 Chopin Bolero in C op.19/Variations brillantes in B Flat op.12/Scherzo in B Flat minor op.31 n.2/Prelude in C Sharp minor op.45(30:38)
Chopin Bolero in C op.19/Variations brillantes in B Flat op.12/Scherzo in B Flat minor op.31 n.2/Prelude in C Sharp minor op.45(30:38)
Ballade in g minor op23 n.1/Etudes in e op.10 n.3 & n.12/Fantasie Impromptu in C sharp minor op.66/Andante Spianato & grande polonaise brillante in G op.22(35:30)〜マルチェッラ・クルデーリ(p)(2005年ローマ・ライヴ)・・・Marcella Crudeli(1940-伊太利亜)とは初耳、津山市作陽短期大学の名誉教授らしいから日本にも縁が深いのでしょう。これは良質な放送録音。かなり力強い、明晰に曖昧さのない輝かしい骨太タッチでした。バリバリ弾くテクニック!といった風情、ヴィヴィッドな推進力にChopinにはちょっと異形な溌剌さ。作品的にはキレのあるスケルツォ 変ロ短調辺りが似合っているでしょうか。バラードト短調はかなりのテンポの揺れと大仰な表情の変化が雄弁。「別れの曲」(作品10-3)も抑制からの劇的情熱の発露、そんな対比も効果的でした。練習曲 ホ長調は豊かな表情、かなり豪快。幻想即興曲は慌てず煽らず、じっくり腰を据えて充分劇的。幻想即興曲 嬰ハ短調は優雅な表情に流麗な技巧でした。大好きな「アンダンテ・スピアナート」前半の抑制した美しさに対して「華麗なるポロネーズ」はかなり表情明快に、リズムのタメがしっかりした表現でした。
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
日々なんのドラマもない、代わり映えせぬ日々にも春は接近して、朝曇り空に市立体育館に向かう途中の抜け道、美しからぬ疎水沿いの梅の花がほころんでおりました。 2本あって、昨年はまったく実が生らんかったなぁ、異常気象のせいか。これから全国的に再びの厳しい寒さと雪が戻るんだそう。岸和田市長自動失職へ、税金たっぷりムダ遣いして、さらにこれから市長選。また兵庫県知事選挙みたいになるのか、ならなんのか、ようわかりません(ならんと思うけど)。他、例の下水道沈没に絡んで、周辺住民に怪しい電話が掛かっているらしい。困ったものです。
2本あって、昨年はまったく実が生らんかったなぁ、異常気象のせいか。これから全国的に再びの厳しい寒さと雪が戻るんだそう。岸和田市長自動失職へ、税金たっぷりムダ遣いして、さらにこれから市長選。また兵庫県知事選挙みたいになるのか、ならなんのか、ようわかりません(ならんと思うけど)。他、例の下水道沈没に絡んで、周辺住民に怪しい電話が掛かっているらしい。困ったものです。
朝一番の洗濯、ストレッチ、そしてYouTubeは懐かしい「Billy Blanks Tae BoR Ab Burner!」実施してから、ゆる筋トレに出掛けたものです。女房殿は婆さんのところに出掛けて、結局夕方「泊まる」との連絡有。自分の体調はちょっぴり鼻詰まりが気になるけれど大丈夫みたい。今朝の体重は67.3kg▲300g、かなり食事抑制したつもりでもあまり減っておりません。
定期的に見るテレビ番組は少ないけれど、女房殿が好きなので付き合っているのが土曜夜「博士ちゃん」サンドイッチマン、芦田愛菜ちゃんも品行方正に好感が持てる司会。「バブル博士」ちゃんの特集にすっかり考え込んでしました。例えば、清里の高級ログハウス(当時壱億五阡萬圓)は加奈陀産ぶっとい木材使用、それは既に輸出禁止となって貴重品に〜というのは初めて知りました。瀬戸大橋建設は日本の技術の粋を集めてプロジェクトXにも取り上げられたほど。自分は1999-2007年迄岡山に居住して、未だ瀬戸大橋ブームの名残があった(崩壊済?)とは知りませんでした。瀬戸大橋架橋記念博覧会(1988年)はバブル真っ最中、その辺りの開発途上に打ち捨てられた寂しい廃墟も紹介されておりました。
そこから勝手に連想して・・・大阪万博はことし2025年開催、想像だけどこれを推進した人々の脳裏には「景気が良かった=万博」高度成長〜バブル発想が根強くあるんじゃないか。だから「万博開催=景気が良くなる」図式が成り立って、それはほとんどノーミソお花畑状態ですか(失礼)現在はリアルに景気はよろしくないし、明るい未来の希望や奇抜な発想を一箇所に集めてハコモノ造り、みたいなイヴェントは嗜好が多様化分散した現代社会にはあまり意味を成さないんじゃないか、そんなことを勝手に考えました。
昔のビデオには万博会場に押し寄せる団体客、嬉しそうにインタビューに応えるお年寄りの顔々。既にほぼ皆鬼籍に入ったことでしょう。大阪万博にカネ掛ける前に老朽化する上下水道修復が先でしょうが。云っちゃ失礼な極端な例え話しやけど、某隣国のミサイル・パフォーマンスが国民の飢えより優先されることを連想しました。大失敗大赤字が予想される中、更に跡地はカジノ誘致ですって。(最近の新聞調査によると万博「行きたいとは思わない」67%なんだそう)
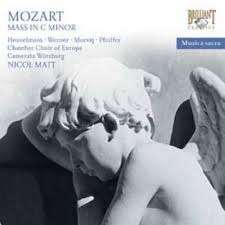 Mozart ミサ曲ハ短調K.427(417a) 〜ニコル・マット/ヴュルツブルク・カメラータ・アカデミカ/ヨーロッパ室内合唱団/ヴァレンティナ・ファルカス(s)/アンネマリー・クレーマー(s)/ダニエル・サンズ(t)/クリフトフ・フィシェサー(b)/イェンス・ヴォレンシュラーガー(or)(2001年)・・・Nicol Matt(1970ー独逸)は合唱指揮者としてBrilliantにMozartの宗教声楽作品をまとめて録音しておりました。声楽陣+二管編成/ティンパニ/オルガン、未完の作品でありCredo以降は以降は研究者による補筆完成されたものらしい。
Mozart ミサ曲ハ短調K.427(417a) 〜ニコル・マット/ヴュルツブルク・カメラータ・アカデミカ/ヨーロッパ室内合唱団/ヴァレンティナ・ファルカス(s)/アンネマリー・クレーマー(s)/ダニエル・サンズ(t)/クリフトフ・フィシェサー(b)/イェンス・ヴォレンシュラーガー(or)(2001年)・・・Nicol Matt(1970ー独逸)は合唱指揮者としてBrilliantにMozartの宗教声楽作品をまとめて録音しておりました。声楽陣+二管編成/ティンパニ/オルガン、未完の作品でありCredo以降は以降は研究者による補筆完成されたものらしい。
この明るく溌溂とした作品との出会いはフェレンツ・フリッチャイ(1959年)もしかしたら十数年ぶりの拝聴、正直なところ記憶にあった(聴きたかった)旋律とは別作品だったのも恥ずかしい。これは音質も良好だし、あまり大柄にせず、声楽の扱いも素直なクセのないもの。Wurzburg Camerata Academicaとはどういったモダーン楽器アンサンブルなのか調べは付かなかったけれど、素朴にスッキリ、濁りのない響きに脇役に徹して耳あたりがよろしい。
Kyrie (Chorus, Soprano 1)出足は嘆きの風情だけど(7:26)Gloria: Gloria (Chorus)ここはとても明るく、前向きの合唱(2:27)Gloria: Laudamus te (Soprano 2)喜ばしい風情、ここは奥様であるコンスタンツェのためのソロ?と類推。ソプラノの腕の見せ所(5:02)Gloria: Gratias (Chorus)荘厳壮麗な合唱(1:09)Gloria: Domine (Soprano 1, Soprano 2)魅惑の陰影豊かな旋律、女声二人絡み合います(2:44)Gloria: Qui tollis (Chorus)足取り重いリズムに清潔かつ劇的な合唱がゆっくり、決然と歩みました。これはキリストの処刑台への歩み?(5:12)Gloria: Quoniam (Soprano 1, Soprano 2, Tenor)ここの声楽ソロも魅惑の旋律が競い合って緊張感有。+楚々として美しい木管が旋律を追いかけます。(3:51)Gloria: Jesu Christe - Cum Santo Spiritu (Chorus)荘厳なコラール、堂々と充実して立派な合唱。(0:45)Gloria: Cum Sancto Spiritu (Chorus)合唱による壮麗、カッコよいフーガ。(4:01)Credo: Credo in unum Deum (Chorus)ここも堂々たるリズムに乗った力強い合唱。そして魅惑の劇的旋律。(3:37)Credo: Et incarnatus est (Soprano 1)木管のステキなオブリガートに、ソプラノがしみじみ敬虔に歌いました。ここが一番長くて、感極まる美しいクライマックスかも。(9:06)Sanctus: Sanctus (Chorus)堂々たる、輝かしい合唱(1:36)Sanctus: Osanna (Chorus)合唱のフーガも劇的に(2:07)Benedictus (Soprano 1, Soprano 2, Tenor, Bass, Chorus)声楽ソロ勢揃い、魅惑の旋律を歌い交わして明るく、軽快かつ力強くフィナーレを迎えました。(5:20)
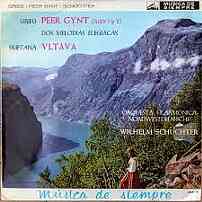 劇音楽「ペール・ギュント」第1組曲/朝/オーセの死/アニトラの踊り/山の魔王の宮殿にて/第2組曲/イングリッドの嘆き/アラビアの踊り/ペール・ギュントの帰郷/ソルヴェイグの歌/2つの悲しき旋律/胸の痛手/過ぎた春/Smetana 交響詩「モルダウ」〜ウィルヘルム・シュヒター/北西ドイツ・フィル(1954年)・・・日本でもお馴染みWilhelm Schu"chter(1911-1974独逸)による名曲録音はもちろんモノラル(LP復刻)驚きの臨場感たっぷり、低音も充分な優秀録音でした。我らの世代には学校の音楽の時間に必須だった「ペール・ギュント」はかっちりと洗練されたアンサンブル、民族的な旋律リズムは弦の蠱惑な音色、ヴィヴィッドな表情に重心の低い演奏。ノルトライン=ヴェストファーレン州ヘルフォルトのオーケストラは1946年創設、この時期既にかなり厚みのある立派なアンサンブルでした。(29:39)「2つの悲しき旋律」はたっぷり泣ける旋律、深み厚みを感じさせる弦楽アンサンブルは7部/9部に分かれているそう。(7:21)
「モルダウ」はどっしりと構えて比較的イン・テンポを維持して、オーソドックスな演奏でした。ラストもあまりテンポを上げない。(11:45)
劇音楽「ペール・ギュント」第1組曲/朝/オーセの死/アニトラの踊り/山の魔王の宮殿にて/第2組曲/イングリッドの嘆き/アラビアの踊り/ペール・ギュントの帰郷/ソルヴェイグの歌/2つの悲しき旋律/胸の痛手/過ぎた春/Smetana 交響詩「モルダウ」〜ウィルヘルム・シュヒター/北西ドイツ・フィル(1954年)・・・日本でもお馴染みWilhelm Schu"chter(1911-1974独逸)による名曲録音はもちろんモノラル(LP復刻)驚きの臨場感たっぷり、低音も充分な優秀録音でした。我らの世代には学校の音楽の時間に必須だった「ペール・ギュント」はかっちりと洗練されたアンサンブル、民族的な旋律リズムは弦の蠱惑な音色、ヴィヴィッドな表情に重心の低い演奏。ノルトライン=ヴェストファーレン州ヘルフォルトのオーケストラは1946年創設、この時期既にかなり厚みのある立派なアンサンブルでした。(29:39)「2つの悲しき旋律」はたっぷり泣ける旋律、深み厚みを感じさせる弦楽アンサンブルは7部/9部に分かれているそう。(7:21)
「モルダウ」はどっしりと構えて比較的イン・テンポを維持して、オーソドックスな演奏でした。ラストもあまりテンポを上げない。(11:45)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日日曜朝、曇って地面は濡れていたのでちょっと降ったのでしょうか。気温はちょっと落ち着いて、明日以降またぐっと冷えるらしい。朝一番に洗濯、ストレッチ+いつものスワイショウ実施して、女房殿は婆さんの許へ、夕方には戻ってきました。自分は業務スーパーに不足している調味料など購入、このウォーキング含めて(スマホアプリ上は)壱日の運動目標達成いたしました。ちゃんと料理を仕立てて夕食後、フロに入った後どうにも肩が凝って・・・なんか体調イマイチ。今朝の体重は67.6kg▲250g。
数日前におコメを買いに行ったけれど、店頭品薄。供給が安定しない、価格も高騰の中、政府は備蓄米を一部市場放出するそう(4月以降らしい)一方でネットの記事には「米の廃棄」問題提起がありました。スーパーではおコメの店頭品質保持期限が切れれば廃棄、食堂や弁当業者、コンビニなどでは賞味期限切れから廃棄、ご家庭でも残してしまって捨てる食料はけっこうあることでしょう。食中毒や衛生上の問題もあるから安易には云々できんけど、一方で貧しくてちゃんとご飯が食べられないこども達も存在して、厳然と信じられぬ量の「廃棄」が発生している現状を憂います。佳き妙案はないものでしょうか。自分は自家製ヨーグルトの種菌残を腐らせてしまうことを反省、できるだけ日常入手した食材をきっちり使い切る努力をしているつもりだけれど、美食を求めてけっこう贅沢な食生活を送っていると自覚しております。ま、山海の珍味みたいなことには縁がはない日常食だけれど。
 Stravinsky 組曲「プルチネルラ」/Weil 交響曲第1番「ベルリン・シンフォニー」〜アリアーヌ・マティアク/ラインラント・プファルツ州立フィル(2016年ライヴ)・・・Ariane Matiakh(1980ー仏蘭西)は現役女流、これからの人でしょう。これはCD2枚分の音源(ファイル収録がそうなっている)けど、ネットに検索してもCD発売された痕跡を探せません。放送音源かも。どうやって音源入手したのか記憶も雲散霧消。「プルチネルラ」はDomenico GalloやPergolesiなどバロック音楽を多く引用した小編成(声楽なし/二管編成)端正にユーモラスな作品。音質印象故かやや元気とメリハリが足りない感じ。
Stravinsky 組曲「プルチネルラ」/Weil 交響曲第1番「ベルリン・シンフォニー」〜アリアーヌ・マティアク/ラインラント・プファルツ州立フィル(2016年ライヴ)・・・Ariane Matiakh(1980ー仏蘭西)は現役女流、これからの人でしょう。これはCD2枚分の音源(ファイル収録がそうなっている)けど、ネットに検索してもCD発売された痕跡を探せません。放送音源かも。どうやって音源入手したのか記憶も雲散霧消。「プルチネルラ」はDomenico GalloやPergolesiなどバロック音楽を多く引用した小編成(声楽なし/二管編成)端正にユーモラスな作品。音質印象故かやや元気とメリハリが足りない感じ。
Sinfonia(2:13)/Serenata/Scherzino - Allegro - Andantino(7:28)/Tarantella/Toccata(3:18)/Gavotta con due variazioni(4:14)/Vivo(1:39)/Minuetto - Finale(5:14/拍手有)
Kurt Weill (1900-1950独逸)の交響曲は当時Busoni門下21歳の作品(1921年)。楽器編成情報不明。単一楽章(Grave/Allegro vivace - Sehr drangend - Nicht schleppend - (Sehr pathetisch)/Andante religioso/Larghetto - Wie ein Choral - Sehr ruhig, mystisch - Langsam und feierlich - Andante espressivo)後期浪漫の甘く濃厚な風情に、怪しい不協和音がそろそろ接近しつつある、デリケートに美しい作品。ラストは勇壮に盛り上がりを見せました。これは初耳作品だったかも、こちらの演奏に特別な感慨を得るほど未だ聴き込んでおりません。(22:45/拍手有)この後にKrenek ヴァイオリン協奏曲第1番/Mussorgsky/Ravel編 組曲「展覧会の絵」が収録されるけれど、お楽しみは後回し。
 Ravel ジャンヌの扇〜ファンファーレ/古風なメヌエット/シェエラザード(フルール・バロン(ms))/ドゥルシネア姫に思いを寄せるドン・キホーテ(アレクサンドル・デュアメル(br))/ステファヌ・マラルメの3つの詩(フルール・バロン(ms))/高雅で感傷的なワルツ〜ルドヴィク・モルロー/バルセロナ交響楽団(2025年release)・・・Ludovic Morlot(1973-仏蘭西)は日本でもお馴染み、ばりばりの現役世代。このオーケストラとRavel全曲録音を目指しているそう。最近の録音は詳細録音情報が探せないことが多くて困ります。Barcelona Symphony and Catalonia National Orchestra歴代の音楽監督には大植英次や大野和士の名前も見えました。西班牙のオーケストラ?そんな先入観打ち砕くようなデリケートに緻密なアンサンブル。
Ravel ジャンヌの扇〜ファンファーレ/古風なメヌエット/シェエラザード(フルール・バロン(ms))/ドゥルシネア姫に思いを寄せるドン・キホーテ(アレクサンドル・デュアメル(br))/ステファヌ・マラルメの3つの詩(フルール・バロン(ms))/高雅で感傷的なワルツ〜ルドヴィク・モルロー/バルセロナ交響楽団(2025年release)・・・Ludovic Morlot(1973-仏蘭西)は日本でもお馴染み、ばりばりの現役世代。このオーケストラとRavel全曲録音を目指しているそう。最近の録音は詳細録音情報が探せないことが多くて困ります。Barcelona Symphony and Catalonia National Orchestra歴代の音楽監督には大植英次や大野和士の名前も見えました。西班牙のオーケストラ?そんな先入観打ち砕くようなデリケートに緻密なアンサンブル。
華やかな「ファンファーレ」(1:53)から、20歳のピアノ作品である「古風なメヌエット」は中世・ルネサンス音楽の音組織である教会旋法を用いて作曲されたとのこと(Wikiより)晩年に二管編成の管弦楽に編曲され、優雅であり大仰シニカルな風情が楽しめる作品。(7:12)歌曲集「シェエラザード」は妖しくも切ない、言葉の壁を超えて大好きな作品。第1曲「アジア」 Asie(8:31)第2曲「魔法の笛」 La Flute enchantee(2:44)第3曲「つれない人」 L'Indifferent(3:04)
「ドゥルシネア姫」は例の「ドン・キホーテ」映画化のための音楽とか(採用されなかった)Ravelのラスト作品らしい。「空想的な歌」(Chanson romanesque/2:04)「英雄的な歌(叙事詩風の歌)」(Chanson epique/3:10)/「酒の歌」(Chanson a boire/2:04)西班牙風リズムに乗って、これも言葉の意味は理解できなくても、カンチガイ生真面目な爺の妄想が連想できます。
「ステファヌ・マラルメ」は「溜息」(soupir/2:52)「叶わぬ望み」(placet futile/3:21)「臀部より出でて,ひと跳びで」(surgi de la croupe et du bond/2:27)Ravel38歳の作品。室内楽伴奏。とっても官能的なソプラノ連続、ちょっと今までの旋律範疇を超えて、前衛風に外れた高揚がありました。「高雅で感傷的なワルツ」なんとも気高い風情の名曲、清潔な響きに端正なアンサンブルだけど、ちょっぴり色気には足りないかも。(1:25-2:24-1:24-1:24-1:12-0:50-2:59-3:31)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日土曜は佳き天気。前夜けっこう冷えたみたいで、市立体育館へ向かう道中、缶やペットボトルを拾って・・・中のお茶が凍っておりました。洗濯済ませてストレッチ、YouTube「7日間のチャレンジ/ 10分でおなかの脂肪を減らすためのトレーニング/おなかの脂肪を早く失うためのエクササイズ」エアロビクス系動画もいろいろあるんやなぁ、皆工夫している、そんな感心してから出掛けたものです。朝一番の週末トレーニングルームはやはり空いていて、ゆっくりマシンを使えました。しっかり鍛えて帰宅したら女房殿清掃中、久々にしっかり昼食調理してご馳走しました。昼から婆さんのところに向かって泊まらずに戻ってきたけれど、かなり弱って認知症っぽく症状進行しているそう。なんせ95歳ですから。今朝の体重は67.85kg▲200gほとんど変わらない。
オンラインカジノ利用で人気お笑い芸人事情聴取、との報道。急遽番組も差し替えとか。そんなのがあることも、どういうものかもわからない。例の大谷選手元通訳の逮捕絡みに噂を訊いたくらいだし、お笑い芸人も顔見知りくらい、その芸はテレビで見たこともありません。違法なんですってね、違法とは知らなくても罪になるそう。芸人にはヘンな人もけっこういるのかな?自分はオフ・ラインのリアル賭博(競馬競輪競艇の類)はもちろん、パチンコや宝くじの経験もありません。世の中には危ういものが身近にゴロゴロしているのですね。それに加えて新たにカジノ誘致とは・・・
カネは自分で稼いだものしか身に付かない、ありきたりだけれどそう考えて日々慎ましく暮らしております。
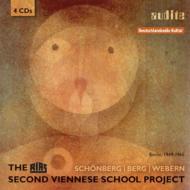 Scho"nberg 月に憑かれたピエロ 作品21 (1912)(ヨーゼフ・ルーファー/イルメン・ブルメスター(シュプレッヒシュティンメ/語る声)/クラウス・ビリング(p)/ハンス・ペーター・シュミッツ(fl)(piccolo)/アルフレッド・ビュルクナー(cl)(bcl)/ハンス・バスティアーン(v)/ヴァルター・ミュラー(va)/ヴェルナー・ハウプト(vc)/1949年)/室内交響曲ホ長調 作品9 (1906)(フェレンツ・フリッチャイ/RIAS交響楽団のメンバー/1953年)/ピアノ協奏曲 作品42 (1942)(ペーター・シュタドレン(p)/ヴィンフリート・ツィリヒ/RIAS交響楽団)・・・RIAS放送局が新ウィーン楽派を意欲的に取り上げたプロジェクトより、Arnold Scho"nberg(1874-1951墺太利)の著名な作品を集めた一枚。フリッチャイは現在でも有名だけど、他音楽学者とか往年のベルリン・フィルのメンバーが参加しているみたい。もちろんモノラルだけど、音質はかなり良心的でした。
Scho"nberg 月に憑かれたピエロ 作品21 (1912)(ヨーゼフ・ルーファー/イルメン・ブルメスター(シュプレッヒシュティンメ/語る声)/クラウス・ビリング(p)/ハンス・ペーター・シュミッツ(fl)(piccolo)/アルフレッド・ビュルクナー(cl)(bcl)/ハンス・バスティアーン(v)/ヴァルター・ミュラー(va)/ヴェルナー・ハウプト(vc)/1949年)/室内交響曲ホ長調 作品9 (1906)(フェレンツ・フリッチャイ/RIAS交響楽団のメンバー/1953年)/ピアノ協奏曲 作品42 (1942)(ペーター・シュタドレン(p)/ヴィンフリート・ツィリヒ/RIAS交響楽団)・・・RIAS放送局が新ウィーン楽派を意欲的に取り上げたプロジェクトより、Arnold Scho"nberg(1874-1951墺太利)の著名な作品を集めた一枚。フリッチャイは現在でも有名だけど、他音楽学者とか往年のベルリン・フィルのメンバーが参加しているみたい。もちろんモノラルだけど、音質はかなり良心的でした。
「月に憑かれたピエロ」はアニア・シリアとか、最近ではヴァイオリニストのコパチンスカヤなどの演奏を聴いておりました。これは「シュプレッヒシュティンメ/語る声」の女声が不思議な効果を上げていて、言語不如意でも題名から類推される、常軌を逸して危うそうな内容をしっかり受け止めること可能。シロウトなりに楽譜を覗いたら、ちゃんと声楽音程音節の記譜があるのですね、イルメン・ブルメスターの情報はネットより探せなかったけれど、ヴェテランのバックは思いっきり怪しい緊張感を湛えて、モノラル録音も妙に雰囲気たっぷり。
月に酔い(1:42)コロンビーヌ(1:58)伊達男(1:22)蒼ざめた洗濯女(1:21)ショパンのワルツ(1:38)聖女(2:03)病める月(2:18) 夜(2:28)ピエロへの祈り(0:53)盗み(1:23)赤いミサ(1:47)絞首台(0:19)打ち首(2:23)/十字架(2:21)/ 郷愁(2:11)/悪趣味(1:23)/パロディ(1:37)/月のしみ(1:00)/セレナーデ(2:39)/帰郷(2:17)/おお、いにしえの香りよ(1:28)
室内交響曲 作品9は15人編成のオリジナル版。乾いて無機的にムダのない響き連続、初演時は野次怒号の嵐だったそう。現在の耳にはたっぷり後期浪漫の残滓に響きます。Ferenc Fricsay(1914ー1963洪牙利)は鋭い集中力に押し切って、かつてない濃厚濃密な風情に仕上げておりました。RIAS交響楽団は素晴らしい技量ですよ。(19:56)
ピアノ協奏曲 作品42はグレン・グールドとかポリーニとかブレンデル、一流の演奏家のレパートリーでもありました。厳格なドデカフォニーによる単一楽章作品、初演はエドゥアルト・シュトイアーマン(p)/ストコフスキー。Andante(穏やかな人生に/4:33)Molto allegro(突然憎しみがわき起こり/2:14)Adagio(暗い状況が作り出されるが/7:37) Giocoso: Moderato(しかし人生は何もなく過ぎてゆく/6:11)に分けられるらしい。若い頃ブレンデル辺りで出会った頃からずっと歯が立たず、やがて静謐に浮遊するように、つかみどころのない妖しさに魅力を感じるように至りました。Peter Stadlen(1910ー1996墺太利→英国)は初耳、同時代音楽の擁護者であり、この作品は十八番だったらしい。Winfried Zillig(1905-1963独逸)も初耳指揮者、Scho"nbergの弟子なんだそう。これもいつになく熱のこもった力強さに、時に激昂して陰影たっぷりに、わかりやすい演奏でした。
 Straivnsky バレエ音楽「火の鳥」(1910年全曲)〜マイケル・ティルソン・トーマス/サンフランシスコ交響楽団(1981年ライヴ)・・・病と戦っているMTT。セッション録音が1998年だからそれとは別の演奏会ライヴ(FM放送エアチェック?らしい)。エド・デ・ワールト時代(1977-1985年音楽監督在任)の客演、これは珍しい記録かも。ちょっと薄いけど音質はかなり良好。たっぷりメルヘンな旋律を表情豊か、メリハリ陰影たっぷり、夢見るように色彩的、ヴィヴィッドに表現してくださって陶酔のひととき、全曲はあっという間に終わります。小澤、エド・デ・ワールトと続いて、オーケストラはこの時既に絶好調だったことが伺えます。(44:00拍手入り)
Straivnsky バレエ音楽「火の鳥」(1910年全曲)〜マイケル・ティルソン・トーマス/サンフランシスコ交響楽団(1981年ライヴ)・・・病と戦っているMTT。セッション録音が1998年だからそれとは別の演奏会ライヴ(FM放送エアチェック?らしい)。エド・デ・ワールト時代(1977-1985年音楽監督在任)の客演、これは珍しい記録かも。ちょっと薄いけど音質はかなり良好。たっぷりメルヘンな旋律を表情豊か、メリハリ陰影たっぷり、夢見るように色彩的、ヴィヴィッドに表現してくださって陶酔のひととき、全曲はあっという間に終わります。小澤、エド・デ・ワールトと続いて、オーケストラはこの時既に絶好調だったことが伺えます。(44:00拍手入り)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日バレンタイン。残念ながら自分の生活には一切無縁、カカオ原料も高騰しているそうな。ここしばらくチョコレートは口にしていないと記憶します。お仕事現役時代はいくらでもサンプルがあって、けっこう喰っていましたよ。毎朝、健康のためにグラノーラに純ココア・パウダー(きな粉青汁粉末とともに)は微量摂取継続中。
月末カード請求明細が届いて、女房殿が点検したらNetflixの請求が続いているとの指摘有・・・前月解約したつもりが手続き処理がちゃんと完了していなかったらしい。なんかおかしいなぁ、1月22日迄は利用できますって、案内に出ていたような?今回再度解約手続きしたけれど、2月22日迄利用できます〜って前回と似たような表示有。お客様のメンバーシップは2025年2月22日に終了しますので、今後料金のご請求はありません・・・とのこと。890円だけど、なんかとってもムダ遣いをしたような、残念な気持ちでいっぱい、悔やまれてならない。金額の大小じゃないっすよ。自らのボケによる自業自得、もっと早く気付けば、それはそれでたっぷりドラマを見たのになぁ。あと一週間ほど再度頑張りましょう。メールに「Netflixメンバーシップのキャンセル」が届きました。こんどは大丈夫か、前回はどうだっけ。
夜しっかり眠って、朝食もいつもどおり、ストレッチしてYouTubeスワイショウ+HIITトレーニング実施して、買い物は必要なし。好天の寒空に引き隠りました。ゴミは前日のうちに出しておきました。昼前に女房度は帰宅して市立体育館へ、再度婆さん宅に戻ってから夕方遅くに帰ってきました。今朝の体重は68.05kg+250gまた危険水機へ逆戻り。自宅にじっとしてましたから。
 Smetana 連作交響詩集「我が祖国」〜ラファエル・クーベリック/ウィーン・フィル(1959年)・・・Rafael Kubelik(1914-1996捷克)45歳の記録、1952年のシカゴ交響楽団録音から、いったい何種録音があるのか知らんけど、これはおそらく2番目の英DECCA録音、ちょっと分離もよろしくなく草臥れ気味だけれど、作品拝聴に問題ない厚みある音質。カスタマー評価を伺うと評判よろしからぬ声が多いみたい。曰く
Smetana 連作交響詩集「我が祖国」〜ラファエル・クーベリック/ウィーン・フィル(1959年)・・・Rafael Kubelik(1914-1996捷克)45歳の記録、1952年のシカゴ交響楽団録音から、いったい何種録音があるのか知らんけど、これはおそらく2番目の英DECCA録音、ちょっと分離もよろしくなく草臥れ気味だけれど、作品拝聴に問題ない厚みある音質。カスタマー評価を伺うと評判よろしからぬ声が多いみたい。曰く
まだこなれていないどこか浅っぽさが残る演奏
(オーケストラに)あまり気が 感じられない・・・すれ違いも散見
一方で
一糸乱れぬオーケストラの精密さ
一音一音を精密に聞き取ることができる実にスマートで紳士的な演奏
美しくも実にドラマチックな・・・ファーストチョイス
音楽は嗜好品なので評価が分かれるのは当たり前(自分の守備範疇外だけど)音質だっていろいろご意見を伺えるのが興味深いものです。自分として誠実な演奏にウィーン・フィルの美しさたっぷり堪能できました。まだ、作品の聴き込みが浅いから、祖国愛に充ちた郷愁の旋律の魅力はたいていの演奏に感銘をいただけます。
「ヴィシェフラト(高い城)」は思わず拝みたくなるような神々しい始まり。ここの劇的旋律があちこち登場して感動的。(14:14)
「モルダウ」は木管と弦の美しさ、金管の深み、旋律への共感をたっぷり感じさせてくださるもの。ラストのテンポ・アップに不自然さはありません。(11:22)
「シャールカ」は劇的に歯切れがよろしい(9:24)
「ボヘミアの野と森から」は木管の掛け合いが美しく、やがて不安な弦がさわさわ、そしてホルンがシミジミ深い音色に牧歌的な旋律を歌って、情感は高まります。このテンポの動きにも説得力充分。(12:23)
「ターボル」不穏な静謐に蠢くような始まり、やがて決然とティンパニが鳴り響いて、フス派の讃美歌「汝ら神の戦士」がコラール風に高らかに歌われます。そして戦いのテンポ・アップへ、なかなかカッコよい緊張感が続きました。ちょっと洞穴みたいに響くけれど、低音もリアル。(13:08)
「ブラニーク」戦いに敗れたフス派の戦士たちが眠るブラニーク山。民族の危機、いざ鎌倉!には蘇って戦うのだそう。アタッカで前曲と同じ旋律から始まって、やがて牧歌的な木管がやすらぎ、それも風雲急を告げる弦の疾走が遮りました。やがて讃美歌の旋律が力強く「ヴィシェフラト(高い城)」主題が高らかに回帰して全曲を締め括ります。(13:53)感動的な名曲でっせ。
 Dvora'k 交響曲第9番ホ短調「新世界より」〜ハミルトン・ハーティ/ハレ管弦楽団(1927年)・・・先日、昔馴染みの音質に耐えられないと書いたばかり。自分で勝手な言い種と自覚しているけれど、これはHamilton Harty(1879-1941英国)史上初の「新世界」録音とか、SP復刻ですよ。入手した音源は針音ノイズを上手く消してあるけれど、高音も低音も伸びない、こども時代が懐かしいゲルマニウム・ラジオみたいに情けない音質だけど、それなりの解像度有。収録の都合から速めのテンポ、もちろん提示部繰り返しはなし。ま、細部迄旋律馴染じんだ名曲ですし。
Dvora'k 交響曲第9番ホ短調「新世界より」〜ハミルトン・ハーティ/ハレ管弦楽団(1927年)・・・先日、昔馴染みの音質に耐えられないと書いたばかり。自分で勝手な言い種と自覚しているけれど、これはHamilton Harty(1879-1941英国)史上初の「新世界」録音とか、SP復刻ですよ。入手した音源は針音ノイズを上手く消してあるけれど、高音も低音も伸びない、こども時代が懐かしいゲルマニウム・ラジオみたいに情けない音質だけど、それなりの解像度有。収録の都合から速めのテンポ、もちろん提示部繰り返しはなし。ま、細部迄旋律馴染じんだ名曲ですし。
それでも第1楽章「Adagio - Allegro molto」から颯爽とした勢いが楽しめるし(8:36)
第2楽章「Largo」は弦のポルタメント奏法もエッチな風情満載、妙にいやらしい雰囲気たっぷり(11:44)
第3楽章「Molto vivace」スケルツォは叩きつけるようなヤケクソ的疾走がオモロいもの(6:11)
第4楽章「Allegro con fuoco」フィナーレの堂々たるタメとスケールは悠然とした構えに立派に高揚する演奏でした。(10:42)
オーケストラもけっこう上手いんじゃないの?なんせ昔馴染みの作品だから脳内から不足情報を補って楽しめるのか。もちろん資料的存在だけど、全曲続けて聴いてけっこう作品を堪能できました。こんな太古録音ばっかり聴く元気と体力、気力は残っていないけど。
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
やはり前夜はちょっぴり降ったみたいですね、市立体育館への道中、あちこち地面は濡れておりました。日々早朝覚醒の時間は早まって、ストレッチ、YouTubeスワイショウ+短時間HIIT実施してからのトレーニングルーム筋トレへ。時間を早めたせいかずっと空いておりました。鍛錬から戻ると女房殿一旦帰宅、また婆さん介護に戻りました。今朝の体重は67.8kg▲200g、運動して食事を控えてもほとんど変わらない。
流暢な日本語を操る在留外国人さんの動画は大好き、日本の現場や文化が切り口を変え、立体的に見えてくるから。ちょっと日本を持ち上げ過ぎだけどね。その話題の中で、亜米利加ではもう15年くらい前からテレビ番組の地位は完全に落ちてしまったとのこと。日本でもじょじょにそうなっている印象はあって、CMを集めて無料放送するビジネス・スタイルは弱まっていると感じます。スマホやコンピューターででも拝見できる有料放送が主流、先日Netflixを一ヶ月のみ契約して、そのオリジナルドラマのひつの高さに驚きましたもの。
テレビはほとんどニュースと天気予報くらい、時間を拘束されるよりTVerを使って翌日以降に確認することが増えました。自由な時間に眺めて、用時ができたら途中で止められますし。
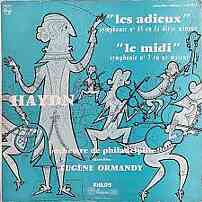 Haydn交響曲第45番 嬰ヘ短調「告別」(1951年)/交響曲第7番ハ長調「昼」(1950年)〜ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団・・・オーマンディのHaydnは珍しいと感じます。音質はかなり良好。例の如し豊かな響きにムリのない優雅な演奏が聴かれました。モノラルでは他第99-100-101番の録音が存在して、ステレオ含めてもっとあるのかも。
Haydn交響曲第45番 嬰ヘ短調「告別」(1951年)/交響曲第7番ハ長調「昼」(1950年)〜ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団・・・オーマンディのHaydnは珍しいと感じます。音質はかなり良好。例の如し豊かな響きにムリのない優雅な演奏が聴かれました。モノラルでは他第99-100-101番の録音が存在して、ステレオ含めてもっとあるのかも。
交響曲第45番 嬰ヘ短調「告別」は1772年「疾風怒濤」期の作品。フルートなし、オーボエ2/ファゴット1/ホルン2/第1ヴァイオリン2/第2ヴァイオリン2/ヴィオラ1/チェロ1/コントラバス1。第3楽章にはFis管のホルンが使われて、それはとても珍しい例なんだそう。例の最終楽章「告別(Adagio)」(ほんまかどうかわからぬ)エピソード部分は団員12人全員分のパートが別々に作られているそう。いろいろ意欲的な工夫をしていたのですね。ここではもちろんもっと大人数な編成でしょう。
第1楽章「Allegro assai」切迫していかにも「疾風怒濤」風な始まり。オーケストラにはたっぷり厚みが感じられて、劇的な旋律に緊張感たっぷりな始まり。
第2楽章「Adagio」ノンビリかつリズミカルな緩徐楽章、かと思ったら情感の揺れに名残惜しい暗さも漂って陰影は豊かでした。弦が瑞々しく美しい、ほとんど陶酔の世界。
第3楽章「Menuetto: Allegretto」軽妙だけどちょっぴり陰もあって味わい深いメヌエット。Fis管のホルン(とやら)が活躍して、それはどんな必須な効果なのか門外漢には理解不能でした。
第4楽章「Finale: Presto - Adagio」ここも快速に緊張感ただよう「疾風怒濤」風、フィラデルフィアの輝かしい厚みのある響きが魅惑の弦がしっかりリズムを刻みます。そして団員が自分の役割を終えて一人ずつ壇上から去っていく「Adagio」へ。ホルンは雄弁、コントラバスのソロも素材感たっぷり、ヴァイオリンも切なく歌って〜これは団員の腕の見せ所なのでしょう。(22:45)
交響曲第7番ハ長調「昼」は1761年の作品。二管編成(トランペット/ティンパニはない)各楽章にソロがあって、協奏交響曲風。幾度も聴いているはずなのに、こんなステキな作品だったのか、思いを新たにしました。
第1楽章「Adagio-Allegro」快活に優雅な始まり、ヴァイオリン2本とチェロのソロが楽しく掛け合います。
第2楽章「Recitativo」憂鬱な風情にヴィオリン・ソロがたっぷり嘆きます。途中爽やかなフルートも歌って、それにヴァイオリン、チェロのソロが相和して、ゆったり切なくも雄弁に絡み合いました。
第3楽章「Menuetto-Trio」優雅に元気な典型的メヌエットはホルンが活躍して独奏チェロと呼応します。弦の厚みはさすがフィラデルフィア、コントラバスもソロに参入(あまり目立たないけど)。
第4楽章「Allegro」快活なフィナーレはフルート大活躍、そしてヴァイオリン2本がソロに加わりました。鈍重ではないけれど、それなり重量級立派な演奏でした。(24:19)
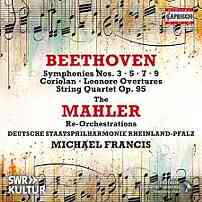 Beethoven 交響曲第3番 変ホ長調「英雄」(Mahler編)〜マイケル・フランシス/ラインラント=プファルツ州立フィル(2022年)・・・Michael Francis(1976-英国)によるMahler編の録音。ホルンは倍管、第2楽章「葬送行進曲」フーガのクライマックス、第4楽章コーダ前にティンパニが加筆されているそう。あちこち時代の推移によって進化した管楽器の効果を活かして、パート旋律が一部変更されているらしい。Mahlerは近現代の演奏会場に相応しい分厚い響きを求めて、現実的な手を加えたのでしょう。しかし、ここでの演奏は昨今の古楽器風キレのあるリズム方向、速めのテンポにスッキリとした響きを目指したもの。オーケストラの響きは素直にスリム、音質はまずまずでしょう。編成の趣旨と表現方向は矛盾しているかも。「英雄」は全曲中一番拝聴機会の多い、浪漫時代への幕開けを告げるBeeやんの傑作。
Beethoven 交響曲第3番 変ホ長調「英雄」(Mahler編)〜マイケル・フランシス/ラインラント=プファルツ州立フィル(2022年)・・・Michael Francis(1976-英国)によるMahler編の録音。ホルンは倍管、第2楽章「葬送行進曲」フーガのクライマックス、第4楽章コーダ前にティンパニが加筆されているそう。あちこち時代の推移によって進化した管楽器の効果を活かして、パート旋律が一部変更されているらしい。Mahlerは近現代の演奏会場に相応しい分厚い響きを求めて、現実的な手を加えたのでしょう。しかし、ここでの演奏は昨今の古楽器風キレのあるリズム方向、速めのテンポにスッキリとした響きを目指したもの。オーケストラの響きは素直にスリム、音質はまずまずでしょう。編成の趣旨と表現方向は矛盾しているかも。「英雄」は全曲中一番拝聴機会の多い、浪漫時代への幕開けを告げるBeeやんの傑作。
第1楽章「Allegro con brio」冒頭の和音から響きは軽く、颯爽とスリムな推進力に溢れました。提示部繰り返しなし。テンション高く、ティンパニが際立ち、各パートが浮き立つのは楽譜のせいなのか、フランシスの意向なのか定かではありません。旧来の重厚長大表現からは遠い、ウキウキと若々しい始まり。(13:50)
第2楽章「Marcia funebre: Adagio assai」葬送行進曲もリズミカルにテンポは中庸に重苦しくない。表情はかなり豊か。強奏に於けるティンパニは相当にデーハーな存在感、クライマックスは激情に叩きつけて効果的でした。(15:09)
第3楽章「Scherzo: Allegro vivace」蒸気機関車の疾走も控えめに軽量級な出足。それは即、パワフルな爆発に(ここも)ティンパニが力強い、カッコ良いアクセントでした。中間部ホルンの三重奏もお見事、そしてアタッカで(5:45)
第4楽章「Finale: Allegro molto」終楽章へ。速めのイン・テンポにアクセントしっかり、各変奏曲は表情豊かにスムースに流れました。ティンパニ先頭に、あちこち明らかに聴き慣れたものとは違う音型があり、颯爽とノリノリの勢いがカッコよく全曲を締め括りました。(11:46)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日はどんより曇り空に冷え込みました。夜半には雨予報、降ったのかどうかは確認しておりません。埼玉の例の下水陥没事故、排水制限は解除されたそう。福島県野地温泉、雪に孤立した客はヘリで救助された報道有、せっかくの温泉旅行もえらい災難でしたね。一連の大雪被害に全国12人死亡、重軽傷158人の被害だったそう。そして、千葉に続いて堺でも水道管老朽化破裂があったとのこと。
朝一番の洗濯は大量、夕方乾きはいまいちな感じ。ストレッチ、YouTube「STANDING CARDIO ABS & tips on how to lose belly fat」は短かったので、スワイショウを足しておきました。正月に買った米もぼちぼち切れそう、珈琲や塩胡椒もなくなり掛けなので業務スーパーに出掛けました。
お隣の皮膚科の前を通り掛かって、ぼちぼちクスリも切れそうと思い立って寄りました。食材はなにもかも値上がって、相変わらずの野菜激高、またキャベツ畑から大量に盗まれたとか、そんな世知辛いニュースも相次いでおります。お米が高騰続いていることは報道から知っていたけれど、入荷も減っていることに驚き。コシヒカリがそこそこの値頃だったので5kg背負って帰りました。今朝の体重は68.0kg+350gまた危険数域へ逆戻り。
婆さんがまた体調不良、女房殿が泊まり込みに出掛けました。
さらに最近不快なニュースが〜広島県・大久野島にて残虐なウサギ殺傷。鬼畜の所業やけど、きっと罪は軽いのでしょう。他、飼っていた鳩が懐かないから殺したとか、なんか日本は最近おかしい。それよりマシだけど、福岡のコンビニで菓子パンを押しつぶした女性逮捕とか、現場を押さえられたけれど幾度行為は続いていたみたい。これも心の闇を感じます。憎むべき幼児虐待に近いような気がします。訪日外人さんの日本礼賛動画はありがちだけど、治安も路上ゴミもトイレも公共交通機関での静謐も、すべて積み上げられてきた成果、自然にそうなったワケじゃない。努力の賜物ですよ。油断すればあっという間に悪化する可能性があります。
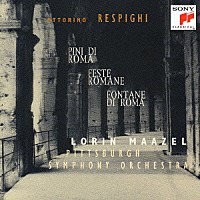 Respighi 交響詩「ローマの松」/「ローマの噴水」/「ローマの祭」〜ロリン・マゼール/ピッツバーグ交響楽団(1994年)・・・2015年に拝聴済。当時
Respighi 交響詩「ローマの松」/「ローマの噴水」/「ローマの祭」〜ロリン・マゼール/ピッツバーグ交響楽団(1994年)・・・2015年に拝聴済。当時
慌てず騒がず、ゆったり目のテンポ(とくに「祭」)微に入り細を穿つ配慮+迫力を以て完璧なコントロール、艶やかなアンサンブルをたっぷり堪能・・・でもね、これだけ種々条件が揃って完全に入り込めぬ感じ有。作品に賭ける灼熱の思いというか情熱?不足
(2:43-7:10-7:25-4:55/5:33-2:20-3:04-5:03/4:50-7:29-7:29-5:36)
これが10年経ってもほとんど印象は変わらない。それは以下クリーヴランドとの旧録音を聴いて、しっかりその違いを体感いたしました。
 Respighi 交響詩「ローマの祭り」/交響詩「ローマの松」(1976年)/Rimsky-Korsakov 組曲「金鶏」(1973年)〜ロリン・マゼール/クリーヴランド管弦楽団・・・こちらクリーヴランド時代(1972-1982音楽監督在任)英DECCA録音。臨場感や分厚い低音に仰け反りました。申し訳ないけど、20年後ピッツバーグ交響楽団との再録音とはオーケストラの技量が桁違い。
Respighi 交響詩「ローマの祭り」/交響詩「ローマの松」(1976年)/Rimsky-Korsakov 組曲「金鶏」(1973年)〜ロリン・マゼール/クリーヴランド管弦楽団・・・こちらクリーヴランド時代(1972-1982音楽監督在任)英DECCA録音。臨場感や分厚い低音に仰け反りました。申し訳ないけど、20年後ピッツバーグ交響楽団との再録音とはオーケストラの技量が桁違い。
「ローマの祭り」は初演1929年(トスカニーニ)三管編成+ティンパニ+11種の打楽器/ハープ/ピアノ/オルガン/マンドリンと大掛かりなもの。「チルチェンセス」ヒステリックな弦から金管のファンファーレがあまりに鮮やか。オルガン先頭に低音や打楽器の威力最高。(4:37)「五十年祭」弦の荘厳な巡礼者たち歩み、木管が神妙に呼応して、「永遠の都・ローマ」への讃歌へ。鐘も鳴ります。色彩の変化が素晴らしいところ。(8:06)「十月祭」は華やかなホルンとトランペットの躍動から始まって(これが狩りの合図ですか?)賑やかなリズムに俗っぽい愛の歌も決まっております。またホルンによる狩りの合図、マンドリン登場はいかにもセレナーデの風情から夕暮れへ(7:39)「主顕祭」狂喜乱舞する金管と打楽器は騒乱状態。手回しオルガンのジンタは祭りや遊園地に必須、物売りの声、酔っぱらいの喧騒は大混乱の熱気のうちに全曲を閉じました。すごい名曲!(5:18)
「ローマの松」の初演は1924年。三管編成+ティンパニ先頭に9種の打楽器/ピアノ/ハープ/チェレスタ/オルガン、更に舞台裏トランペット/ブッキナ/ナイチンゲールの声(テープ)という大編成。輝かしい「ボルゲーゼ荘の松」は切迫感に充たされて充実(2:56)「カタコンバ付近の松」に於けるトランペットの存在感もリアル、情感が迫り上がっていく金管の圧も余裕でした(6:58)「ジャニコロの松」の幻想的な陶酔も文句なし。ここでナイチンゲールが啼きます(6:38)「アッピア街道の松」は古代ローマ軍の進軍。心持ち速めのテンポに、重低音が鳴り響いいて圧巻のクライマックスを迎えます。(4:41)
組曲「金鶏」はオペラからの管弦楽組曲、初演は1908年。二管編成(と、思う/Wikiの書き方が曖昧)10種の打楽器+チェレスタ+ハープというけっこう大掛かりに多彩なもの。Respighiに比べると流石に作品風情はぐっと穏健でした。
幻想的な「序奏とドドン王の眠り」作品の出足から安らぎの旋律が静謐なメルヘン(10:51)
「戦場のドドン王」露西亜民謡風親しみやすい旋律がそっと疾走します(3:37)
「ドドン王とシェマハの女王の踊り」甘くしっとり始まって、ちょっぴりユーモラスに「シェエラザード」を連想させる旋律は徐々にテンポと熱を加えて、オリエンタルな風情に至ります。(6:53)
「婚礼の祝宴とドドン王の哀れな末路と死−終曲」なぜか不穏な始まり、テンポ・アップして華やかに賑やかな風情へ。序奏のテーマもちょっぴり再現され、あっけなく終わりました。(5:50)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
こんどは千葉の方で上水道破裂から道路陥没とか。明日は我が身、我が街かも。その我が街では火災があって、昨年初当選した女性議員宅に火災、お子さんが亡くなったらしい。この時期、空気は乾燥しているし、暖房に火を使うこともあったことでしょう。
昨日祝日も好天、でもけっこう冷える日々が続きます。女房殿不在でも規則正しい生活、ヘルシー朝食もいつもと同じ、ストレッチしてYouTube鍛錬済ませて、洗濯物は溜まっていないので休止。早朝ゴミ出しも済ませて市立体育館を目指しました。トレーニングルームは休日メンバー新顔含めて混み合う前にさっさと筋トレ、エアロバイクを済ませました。体調は未だ大丈夫。中国古来の動きにヒントを得たスワイショウ継続は地味に効いている手応えがあります。女房殿は昼過ぎにいったん帰宅してトレーニングルームへ。再び婆さん宅に出掛けて、夜戻ってきました。今朝の体重は67.65kg▲300g、ちゃんと運動して食事控えてもほとんど減らない。そしてちょっと油断すればすぐ増えるのでしょう。
ヒマな引退生活に勝手な感想だけど、ネット記事や動画の題名表題は不快に感じております。類型的な言い回し、ワン・パターンな言葉遣いは日本語を歪めているんじゃないか、例えば「すごすぎました」→すごく悪いのか、良いのか、大きいのか、小さいのか、甘いのか、辛いのかさっぱりわからない。それを学んで真似する人が増えていると感じます。5W1Hの過半が抜けて所謂「匂わせ」的表題からの釣り記事ばかり。とくに芸能ネタはあとで揚げ足取られないような、卑怯な引用とか言い回しにエエ加減な噂話しも多い。他、売れなくなったタレントの提灯記事、不祥事に活動自粛しているタレントの復活様子見観測気球など、できるだけ見ないように気を付けいるのは、ノーミソ減りそうな気がするから。先のフジ・テレビのマラソン会見にも、ろくでもない似非ジャーナリスト出現してましたもんね・・・これはきっと時代遅れ爺(=ワシ)の戯言なのでしょう。
ま、嘘八百言ったもん勝ち動画や迷惑系ユーチューバーよりマシか。流言飛語に騙されやすい世間はいまも昔も変わらぬのかも知れません。
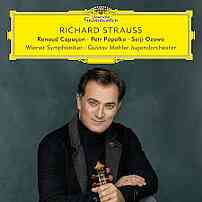 R.Strauss 交響詩「英雄の生涯」〜小澤征爾/マーラー・ユーゲント管弦楽団/ルノー・カプソン(v)(2000年ザルツブルグ・ライヴ)・・・ボストン交響楽団との録音が1981年、こちらは小澤征爾65歳の記録。以前の印象と方向性とあまり変わらない、煽らず走らず余裕、ごりごりパワフルに非ず、肩の力が抜けて落ち着いた演奏でした。ソロ(コンマス)にRenaud Capucon(1976-仏蘭西)を迎えて彼も当時24歳。ヴァイオリン・ソロはあまり目立ちません。若者たちを導いて、ていねいしっとりとした細部描き込み、あいまいさなくクールに緻密な「英雄」を堪能いたしました。こんな個性だからラスト「英雄の隠遁と完成」辺りがシミジミ。音質は残響豊かに音像やや遠く、瑞々しいもの。
R.Strauss 交響詩「英雄の生涯」〜小澤征爾/マーラー・ユーゲント管弦楽団/ルノー・カプソン(v)(2000年ザルツブルグ・ライヴ)・・・ボストン交響楽団との録音が1981年、こちらは小澤征爾65歳の記録。以前の印象と方向性とあまり変わらない、煽らず走らず余裕、ごりごりパワフルに非ず、肩の力が抜けて落ち着いた演奏でした。ソロ(コンマス)にRenaud Capucon(1976-仏蘭西)を迎えて彼も当時24歳。ヴァイオリン・ソロはあまり目立ちません。若者たちを導いて、ていねいしっとりとした細部描き込み、あいまいさなくクールに緻密な「英雄」を堪能いたしました。こんな個性だからラスト「英雄の隠遁と完成」辺りがシミジミ。音質は残響豊かに音像やや遠く、瑞々しいもの。
「Der Held (英雄)」(4:47)/「Des Helden Widersacher (英雄の敵)」(3:39)/「Des Helden Gefahrtin (英雄の伴侶)」(12:52)/「Des Helden Walstatt (英雄の戦場)」(7:28)/「Des Helden Friedenswerke (英雄の業績)」(7:11)/「Des Helden Weltflucht und Vollendung der Wissenschaft (英雄の隠遁と完成)」(11:59/拍手有)
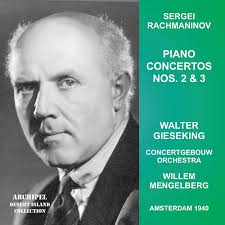 Rachmaninov ピアノ協奏曲第2番ハ短調/ピアノ協奏曲第3番ニ短調〜ワルター・ギーゼキング(p)/ウィレム・メンゲルベルク/コンセルトヘボウ管弦楽団(1940年ライヴ)・・・幾度も聴いていた演奏、ホロヴィッツの歴史的録音(第3番)は別格として、この濃密な浪漫溢れて壮絶なテクニックを必要とする名曲は、できれば状態のよろしい音質で聴きたいもの。Walter Gieseking(1895ー1956逸)とメンゲルベルクとの戦前のライヴは予想以上に状態はよろしいと感じました。
Rachmaninov ピアノ協奏曲第2番ハ短調/ピアノ協奏曲第3番ニ短調〜ワルター・ギーゼキング(p)/ウィレム・メンゲルベルク/コンセルトヘボウ管弦楽団(1940年ライヴ)・・・幾度も聴いていた演奏、ホロヴィッツの歴史的録音(第3番)は別格として、この濃密な浪漫溢れて壮絶なテクニックを必要とする名曲は、できれば状態のよろしい音質で聴きたいもの。Walter Gieseking(1895ー1956逸)とメンゲルベルクとの戦前のライヴは予想以上に状態はよろしいと感じました。
第2番ハ短調協奏曲第1楽章「Moderato」からピアノも管弦楽も濃厚自在に揺れて浪漫の風情たっぷりだけど、センスは(自分のリファレンスである)リヒテル辺りとは違って苦甘い暗い闇と激情は感じさせぬもの(9:52)
第2楽章「Adagio sostenuto」も音楽に耽溺するような極限の入念ていねい仕上げでも、大仰な時代は感じさせぬどこかクール。ホルンの音色や弦の洗練を聴いていると、このオーケストラは名人揃いだったことが理解できました。(11:40)
第3楽章「Allegro scherzando」冒頭からソロの華やかな技巧の冴え、快速テンポに粗いくらいモウレツな勢い、雄弁だけどドライなピアノでした。(10:09/喝采入)
第3番ニ短調は「オッシア(大カデンツァ)」を聴きたかった、いずれ大きい方でなくてもカデンツァは超難物の技巧必須なんだそう。メンゲルベルクの伴奏は相変わらず思いっきり、大仰に濃い味付けでした。こちらも前曲に負けぬ、濃密に甘い旋律満載の名曲。
第1楽章「Allegro ma non troppo」は遅めのテンポに明晰なタッチ、じっくり甘い旋律を歌う始まり。肩の力が抜けて流麗なテクニックは徐々に熱を加え、やがて一気に走り出します。揺れ動くテンポと激情、そしてオッシアの圧巻アクロバティックに強靭なピアノ。ライヴで披露するのはよほどの自信なんでしょう。(16:16)
第2楽章「Intermezzo」は哀愁の主題は弦がポルタメントして、これは時代ですねぇ。ピアノはさらりとしてしみじみ、かつ情熱的にオーケストラと濃厚な絡み合い。(9:22)
第3楽章「Finale」は細かい音型に疾走して、凄い技巧の冴えは素っ気ないほどの流れ。管弦楽と丁々発止と遣り合って、テンポは揺れ動いて微妙にずれる緊張感、ライヴならではの熱気。ラスト前にしっとり情感が漂って、フィナーレ向かってテンポは熱狂的に早まって荒々しい。(12:36/拍手有)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
全国を席巻した寒気は山を超えたそうだけど、全国各地依然として影響が続くようです。こちらも朝、ご近所の草むらや雑草には霜が降りておりました。朝一番の洗濯、ストレッチ、YouTubeスワイショウ済ませて、往復3kmのウォーキング=激安美容院(カットのみ980圓也)に駆けつけて二番札、元・眼鏡マスク越し北川景子似(先月から眼鏡と髪型変わってもはやあまり似ていない)別嬪さんに短くカットしていただきました。女房殿は大東市民大学とやら?最終発表日を迎え、それから婆さんのところに泊まりに出掛けました。腰の圧迫骨折の症状は落ち着いて、嚥下障害発生も軽快したらしいけれど95歳、急激に認知症っぽい感じは進行して、もう日常行動は自分ひとりでできなくなりつつあるとのことでした。朝の運動+ウォーキングの結果、スマホアプリ上は壱日の必要運動量はクリア。体重は67.95kg▲200g、かなり食事節制したつもりでもほとんど減らない。残念。
先月1月に名古屋で呑んだ大学の先輩は昨年2024年交通事故にて左足靭帯断裂、ニ週間ほど前に再建手術を受けて入院してぼちぼち退院、これからリハビリがしばらく続きます。LINEから全国らお見舞いが続いて、なんせもう70歳前後世代、病自慢はありがち。先に心臓を手術をされた方の入院時の経験、じつは糖尿病で、とか、転倒して左足首複雑骨折して修復中、6月に金属を抜くとか、ま、いろいろ。ガン経験者もいるし、自分はなんとか大丈夫でも奥様が軽い脳梗塞とか、くも膜下出血からもう21年奥様を介護されている先輩もおります。
やれオモロないワン・パターンにヒマな毎日〜なんて、そこそこ元気だったら、それが一番贅沢なシアワセ。そう自覚して、毎日休まず鍛錬は継続しましょう。
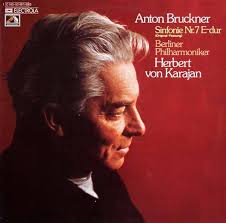 Bruckner 交響曲第7番ホ長調(ハース版)〜ヘルベルト・カラヤン/ベルリン・フィル(1971-72年)・・・これは学生時代にLP2枚組(第4番と)を入手した記憶有。若い頃はBrucknerを聴き込んでいなかったので、演奏云々どころか作品も(録音のことも)あまり理解できておりませんでした。もしかしたら拝聴はほとんど50年ぶり?これが・・・仰け反るほど美しい。後に高品質CDになったほどの優秀録音らしい。未だ気力体力充実した60歳代前半の記録、ベルリン・フィルとの組み合わせはこの辺りが絶頂期でしょう。シルクのように艷やかな弦、色気たっぷりの木管、分厚い深みを感じさせる金管、どの部分にも入魂の表情付け色付け万全、やや遅めのイン・テンポを基調として流れはスムースにムリムリをいささかも感じさせない。この作品は全交響曲中もっと旋律、それは美しさ際立って、ほとんど耽美的にセクシーな艶を感じさせる洗練されたBruckner。朝比奈隆の粗野に不器用な演奏も好きだけれど、こんな精緻かつ余裕のゴージャスなサウンドも大好き。
Bruckner 交響曲第7番ホ長調(ハース版)〜ヘルベルト・カラヤン/ベルリン・フィル(1971-72年)・・・これは学生時代にLP2枚組(第4番と)を入手した記憶有。若い頃はBrucknerを聴き込んでいなかったので、演奏云々どころか作品も(録音のことも)あまり理解できておりませんでした。もしかしたら拝聴はほとんど50年ぶり?これが・・・仰け反るほど美しい。後に高品質CDになったほどの優秀録音らしい。未だ気力体力充実した60歳代前半の記録、ベルリン・フィルとの組み合わせはこの辺りが絶頂期でしょう。シルクのように艷やかな弦、色気たっぷりの木管、分厚い深みを感じさせる金管、どの部分にも入魂の表情付け色付け万全、やや遅めのイン・テンポを基調として流れはスムースにムリムリをいささかも感じさせない。この作品は全交響曲中もっと旋律、それは美しさ際立って、ほとんど耽美的にセクシーな艶を感じさせる洗練されたBruckner。朝比奈隆の粗野に不器用な演奏も好きだけれど、こんな精緻かつ余裕のゴージャスなサウンドも大好き。
第1楽章「Allegro moderato」静謐に爽やかな旋律がゆったりと弦、木管に引き継がれて高揚していく、屈指の美しい始まり。一貫して抑制された弱音でも各パートはしっかり溶け合って、ベルリン・フィルの深いサウンドは極上です。やがて金管の炸裂も余裕でした。慌てぬテンポ設定、イエス・キリスト教会(ダーレム)の残響が素晴らしい。(21:49)
第2楽章「Adagio: Sehr feierlich und sehr langsam」ハース版となっているけれど、クライマックスに強烈な打楽器が出現します。そのあとに金管が弱音に遠ざかっていく寂しげな存在感、ラスト強烈なホルンのダメ押しがベルリン・フィルの実力でしょう。上空に浮遊するフルート、サワサワと鳴る弦のデリカシーも特筆すべき。(22:55)
第3楽章「Scherzo: Sehr schnell」Brucknerのキモはスケルツォ。ここも悠々とリズムを刻んでまったりと八分目の力感でした。トリオの優雅な節回しも極上の甘い響きでした。(10:31)
第4楽章「Finale: Bewegt, doch nicht schnell」抑制した始まりに、ここは明るい風情、リズムも弾むよう。この楽章のみならず弦の表情付けはそっとていねいに入念、ここを決然と明快クリアに表現するかどうか、それは嗜好の問題でしょう。金管の決然とした合奏はそれをぶち破るド迫力、それは露西亜風絶叫に非ず。地鳴りのするような重量級低音に優しい木管が絡みあって、肩の力は抜けた余裕の演奏でした。(12:50)
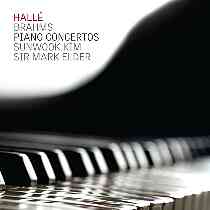 Brahms ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調〜キム・ソヌク(p)/マーク・エルダー/ハレ管弦楽団/Nicholas Trygstad (vc)(2016年)・・・Sunwook Kim(1988-韓国)は期待の若手ピアニスト。テクニックに不足はあるはずもなし。Amazonを検索したらCDR発売、メインはデータ供給となって時代を感じたものです。ピアノ・オブリガート付きの交響曲とも云われる巨魁な作品なのに、じつは古典的二管編成、しかもトランペットとティンパニは第3−4楽章お休みという驚き。
Brahms ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調〜キム・ソヌク(p)/マーク・エルダー/ハレ管弦楽団/Nicholas Trygstad (vc)(2016年)・・・Sunwook Kim(1988-韓国)は期待の若手ピアニスト。テクニックに不足はあるはずもなし。Amazonを検索したらCDR発売、メインはデータ供給となって時代を感じたものです。ピアノ・オブリガート付きの交響曲とも云われる巨魁な作品なのに、じつは古典的二管編成、しかもトランペットとティンパニは第3−4楽章お休みという驚き。
第1楽章「Allegro non troppo」幽玄に美しい冒頭ホルンから細身にデリケート、洗練された管弦楽+力任せに非ず、若者らしい清潔な軽みのあるタッチに始まりました。重厚長大なBrahmsを求めるなら、ちょっと軽量過ぎと受け止められる方もいらっしゃることでしょう。(18:52)
第2楽章「Allegro appassionato」物々しい緊張感に充ちたピアノと管弦楽の対話はスケルツォですか?ここもオーケストラは分厚くなく、ピアノも重量感を強調しない。メリハリとパワー、勢いにちょっと不足を感じます。(9:10)
第3楽章「Andante」冒頭諦念に充ちたチェロが切々と主題を歌って、そが弦に引き継がれて、ピアノの登場はかなりあと。呟くような陶酔の時間がゆったり流れて、ていねいなソロと管弦楽の対話は消え入るように息を潜めて絶品の緩徐楽章。(13:02)
第4楽章「Allegretto grazioso」晴れやか上機嫌な表情に軽妙なソロとオーケストラの始まり。穏やかな対話が続いて、タッチは軽妙、重厚長大スケールを強調しない爽やかなフィナーレでした。(9:33)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
そう云えば本日息子は40歳の誕生日。可愛い妻と小さな息子二人、シアワセに暮らしております。
昨日こちらはちょっぴり気温は上がったけれど、雪国はいかがでしょうか。前夜なぜか眠り浅く、華麗なる加齢にトイレも近く、深夜途中覚醒、二度寝したけれどウトウトしたのみ。それでも連日スワイショウの成果か、体調は悪くありません。洗濯ストレッチ済ませてYouTube鍛錬したら、女房殿が居酒屋飯が喰いたいとのこと。夜は弟が婆さんのところに泊まってくれるそうです。ほぼ壱時間おきにトイレに行くから付き添いはタイヘンなんすよ。先日自分はストレス発散に爺友と呑みに行ったけれど、女房殿はもっといっそう精神的には閉塞していることでしょう。朝一番、いつも通り市立体育館へ出掛けて日曜常連はお仕事現役世代。デニス・ラッセル・デイヴィスにクリソツな禿頭中年と順番に筋トレマシンを利用しました。
午前中婆さんの様子を見に行った女房殿が戻るのを待って、昼寝してからコミュニティバスに乗りました。5日ほど前に呑んだばかりだけど、また馴染の激安居酒屋に贅沢しました。日曜午後の梅田駅前ビル地下は予想外に混んでいて、若い女性が多い。女房殿が注文した「涙巻き」に鼻を摘んで涙しました。JR北新地から最寄りの駅、幸い帰りもコミュニティバスを利用できました。今朝68.15kg+250gも自業自得自己責任、本日は抑制しましょう。
ちょっと残念な話題なんだけど、贅沢になった反省と云うか、堕落したと云うか、昔若い頃心ときめかせて聴いた馴染み深い音源にガッカリすることが増えております。例えば昨年2024年7月に遭遇したHDDお釈迦事件に露西亜音楽関係全部失って、昔馴染みな著名音源かつ比較的再入手しやすいものから順繰りにネットを探ったら・・・
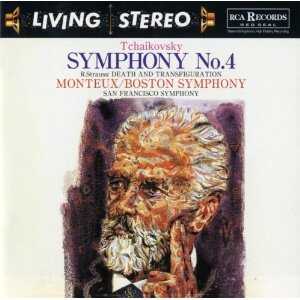 Tchaikovsky 交響曲第4番ヘ短調(1959年)/第5番ホ短調(1958年)/第6番ロ短調(1955年)〜ピエール・モントゥー/ボストン交響楽団出現。往年のRCA録音、このファイルをダウンロードしてちょっぴり確認してガッカリ。こんな音質だったのか・・・もしかしたら、たまたま、偶然入手した音源の問題なのか、自分のオーディオ環境の力不足なのか。
Tchaikovsky 交響曲第4番ヘ短調(1959年)/第5番ホ短調(1958年)/第6番ロ短調(1955年)〜ピエール・モントゥー/ボストン交響楽団出現。往年のRCA録音、このファイルをダウンロードしてちょっぴり確認してガッカリ。こんな音質だったのか・・・もしかしたら、たまたま、偶然入手した音源の問題なのか、自分のオーディオ環境の力不足なのか。
「音楽日誌」になんとか再入手したいと書いたら、心ある読者より連絡があって音源提供いただいた
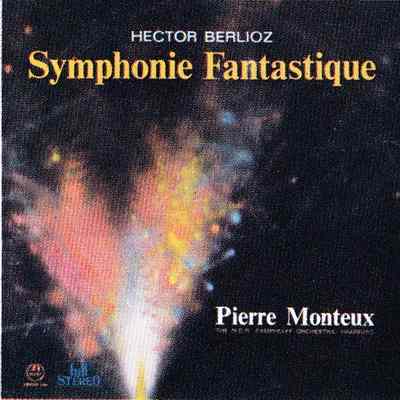 Berlioz 幻想交響曲〜ピエール・モントゥー/ハンブルク北ドイツ放送交響楽団(1964年)も久々の拝聴。これも演奏の質や個性さておき、音質水準に嘆息、せっかくのご厚意に申し訳ないけど、作品そのものに未だ集中できておりません。Pierre Monteux(1875-1964仏蘭西)にはウィーン・フィルとの音質状態よろしい1958年録音が存在して、フツウちょっと曇った、冴えぬ音質のこちらを求める方はいらしゃらないことでしょう。残念繰り返しもコルネットもありません。(13:57-6:01-15:28-4:59-10:09)
Berlioz 幻想交響曲〜ピエール・モントゥー/ハンブルク北ドイツ放送交響楽団(1964年)も久々の拝聴。これも演奏の質や個性さておき、音質水準に嘆息、せっかくのご厚意に申し訳ないけど、作品そのものに未だ集中できておりません。Pierre Monteux(1875-1964仏蘭西)にはウィーン・フィルとの音質状態よろしい1958年録音が存在して、フツウちょっと曇った、冴えぬ音質のこちらを求める方はいらしゃらないことでしょう。残念繰り返しもコルネットもありません。(13:57-6:01-15:28-4:59-10:09)
更に、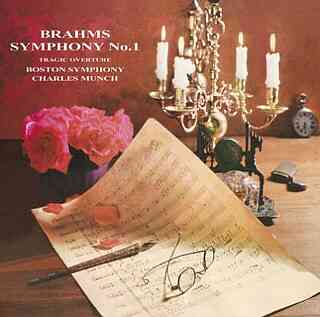 Brahms 交響曲第1番ハ短調(1956年)/悲劇的的序曲(1955年)〜シャルル・ミュンシュ/ボストン交響楽団・・・2004年に拝聴記録有、かつてもその熱血演奏に感激したけれど、やはり音質とアンサンブルの粗さが気になって以前ほど愉しめませんでした。
Brahms 交響曲第1番ハ短調(1956年)/悲劇的的序曲(1955年)〜シャルル・ミュンシュ/ボストン交響楽団・・・2004年に拝聴記録有、かつてもその熱血演奏に感激したけれど、やはり音質とアンサンブルの粗さが気になって以前ほど愉しめませんでした。
たまたまかなぁ、これはきっと堕落ですよ。有名な作品だったら新しい、ぴかぴかの録音が次々と出ていて、それに耳慣れてしまったらもう過去にもう戻れない。よろしからぬ曇った音質から、表現個性の真髄を聴きとる集中力やら耳の減退は華麗なる加齢なのでしょう(涙)人生の残り時間はさほどに潤沢ではないから、思い出ばかり追っても仕方がない・・・と云うのは虚しい言い訳と自覚しております。
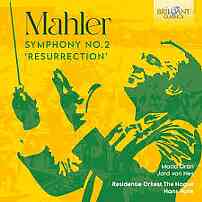 Mahler 交響曲第2番「復活」ハ短調〜ハンス・フォンク/ハーグ・レジデンティ管弦楽団/オランダ劇場合唱団/マリア・オラン(s)/ヤルト・ファン・ネス(con)(1986年)・・・Hans Vonk(1942-2004阿蘭陀)はこのオーケストラの首席指揮者を1980-1991年在任。これは自主制作音源なんだそう。おそらくは20世紀中、昔の恥ずかしい自らのコメントを仕切り直し、修正しようと思っても、その音源を処分済だったら打つ手なし。これはこの度ようやく再拝聴叶いました。これも上記似たような話題の流れ、久々の印象は音質はいまいち(いえ、かなり)曇ってよろしくない、この大掛かりにデーハーな管弦楽声楽効果的巨魁な作品にはちょっと不利、ガッカリいたしました。音質を気にするようになった自分が情けない。
Mahler 交響曲第2番「復活」ハ短調〜ハンス・フォンク/ハーグ・レジデンティ管弦楽団/オランダ劇場合唱団/マリア・オラン(s)/ヤルト・ファン・ネス(con)(1986年)・・・Hans Vonk(1942-2004阿蘭陀)はこのオーケストラの首席指揮者を1980-1991年在任。これは自主制作音源なんだそう。おそらくは20世紀中、昔の恥ずかしい自らのコメントを仕切り直し、修正しようと思っても、その音源を処分済だったら打つ手なし。これはこの度ようやく再拝聴叶いました。これも上記似たような話題の流れ、久々の印象は音質はいまいち(いえ、かなり)曇ってよろしくない、この大掛かりにデーハーな管弦楽声楽効果的巨魁な作品にはちょっと不利、ガッカリいたしました。音質を気にするようになった自分が情けない。
第1楽章「Allegro maestoso」大昔の記憶ではその集中力に感銘深かったんだけどなぁ、テンポは揺れ動いてかなり浪漫的な表現に細部入念な表現、それも音質故かオーケストラの響きがジミに感じました。残念。(20:48)
第2楽章「Andante moderato」弱音主体に優雅に落ち着いた緩徐楽章。ここも落ち着いて抑制した始まりから、途中情感の高まりにしっかりテンポを上げて・・・やはり曇った音質は気になります。(9:45)
第3楽章「In ruhig fliessender Bewegung(穏やかに流れる動きで)」衝撃的なティンパニから始まるユーモラスな「魚に説教するパドヴァの聖アントニウス」旋律のスケルツォ。ここのリズム感、表情の豊かさは立派。(10:26)
第4楽章「Urlicht: sehr feierlich, aber schlicht (原光:きわめて荘厳に、しかし簡潔に )」ヤルト・ファン・ネスの落ち着いて神々しい声は文句なし。オーケストラの緻密なフォローもよろしい感じ。(5:07)
第5楽章「Finale: in Tempo des Scherzos(スケルツォのテンポで )」レジデンティ管弦楽団圧巻の爆発から始まる終楽章へ。この辺りに至って音質の件はかなり耳慣れて、それは歴史的音源を聴くような気分か。但し遠くのホルン、木管がじっくり囁き合う場面の弱音にはクリアな響きは求めたいもの。ティンパニの存在感は立派だから、もったいないなぁこの音質。やがてすべてのパートが力強く「怒りの日」疾走してテンポ・アップ!この辺りの迫力ある熱血集中力は聴きもの。
そして静かに抑制された管弦楽に乗って、合唱がしみじみ声楽と管弦楽のバランスはよろしく、音質云々はあまり気になりません。ホルンの響きも魅力的、アルトとソプラノの二重唱は合唱に引き継がれて、その神々しい響きは、感動的なフィナーレの締め括りに至りました。この楽章にはかなり感銘をいただきました。(32:56)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
毎日覗くブログにも厳しい寒波や積雪(史上最高とか)の話題が多いようです。新幹線在来線もあちこち遅延しているそう。昨日早朝BS-NHKの国際ニュースを拝見したら韓国南部も荒天、交通機関が麻痺して多くの旅行者観光客が空港に立ち往生しているようすを映し出しておりました。もちろん日本のことが心配なのは前提として、日本海側にたくさん雪が降れば、その対岸である朝鮮半島もそうであろうことは想像に難くない、当たり前のことに思い至らぬことは日常ありがち。なんせ自分の身近な生活にはあまり影響ないっすから。
Myコンピューター・オーディオ部屋はホットカーペットのみではあまりに寒さ厳しく、長時間滞在したくありません。エアコンは電気代がもったいなくて入れたくない。女房殿が座っているリビングには朝一番より入れて温めております。外は氷点下に下がったらしいけれど引き隠って外出はご遠慮、床屋にでも行こうと思ったけれど断念、ムリはしません。食材在庫ムダにせず使い切って夕食を仕立てました。朝一番大量の洗濯物をベランダに干すのもちょっと寒過ぎ、連日乾燥した寒風にけっこうよく乾きました。
いつものストレッチ後、YouTube鍛錬はバレエの動きを元にした体感を鍛えるもの、さらに恒例スワイショウもちょっぴり加えました。数日前、梅田の人混みに出掛けたけれど幸いウィルスは拾っていなかったみたい。体調は大丈夫。洟水はちょっとあるけどね。体重は67.9kg▲750g。2月に入って初めての67kg台だけど、高め安定に変わりありません。
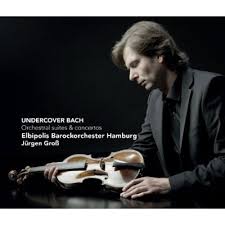 Bach 序曲イ短調 BWV822(他者作品の編曲とのこと/Jo"rg Jacobi フルートと弦楽編)/無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番ニ長調 BWV1006(Jo"rg Jacobi チェンバロと弦楽編)/協奏曲ト長調 BWV Anh. 125(C.P.E Bach作/Jo"rg Jacobi 弦楽編+Lute?)/序曲ヘ長調 BWV820 (Jo"rg Jacobi オーボエと弦楽編)/管弦楽組曲第2番イ短調 BWV1067(Werner Breig 復元版)/ファンタジア ト長調 BWV 571 (Jo"rg Jacobi 弦楽編)〜ユルゲン・グロス/ハンブルク・エルビポリス・バロック管弦楽団 (2013年)・・・Jurgen Gross(1969-独逸)はヴァイオリン奏者とのこと、もちろん古楽器。こんな珍しい疑作?含めた編曲乃至復元版録音は意欲的な取り組みでしょう。どれも練り上げられた技術と軽快なリズム、佳き音質に典雅なバロック音楽をたっぷり堪能いたしました。
Bach 序曲イ短調 BWV822(他者作品の編曲とのこと/Jo"rg Jacobi フルートと弦楽編)/無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番ニ長調 BWV1006(Jo"rg Jacobi チェンバロと弦楽編)/協奏曲ト長調 BWV Anh. 125(C.P.E Bach作/Jo"rg Jacobi 弦楽編+Lute?)/序曲ヘ長調 BWV820 (Jo"rg Jacobi オーボエと弦楽編)/管弦楽組曲第2番イ短調 BWV1067(Werner Breig 復元版)/ファンタジア ト長調 BWV 571 (Jo"rg Jacobi 弦楽編)〜ユルゲン・グロス/ハンブルク・エルビポリス・バロック管弦楽団 (2013年)・・・Jurgen Gross(1969-独逸)はヴァイオリン奏者とのこと、もちろん古楽器。こんな珍しい疑作?含めた編曲乃至復元版録音は意欲的な取り組みでしょう。どれも練り上げられた技術と軽快なリズム、佳き音質に典雅なバロック音楽をたっぷり堪能いたしました。
序曲ト短調 BWV822はBachの真作に非ず、もともと他者の編曲作品らしい。符点のリズムにOverture(フランス風序曲/3:56)から始まるフルートをソロとする管弦楽組曲 Aria(4:21)/ Gavotte en Rondeau(0:57)/ Bourree(0:51)/ Menuet I-III(2:46)/ Gigue(1:35)趣向や雰囲気は管弦楽組曲第2番ロ短調BWV1067に似て、ちょっぴり憂鬱な風情のフルート協奏曲。
馴染の旋律が続くパルティータ第3番ニ長調 BWV1006はまるっきり闊達な合奏協奏曲に変貌して、違和感なし。通奏低音はリュートですか?Preludio(2:49)/Loure(3:30)Gavotte en rondeau(2:49)Menuet I-II*チェンバロのソロと弦楽ピチカートにユーモラス(3:30)Bourree(1:20)Gigue(1:55)
協奏曲ト長調 BWV Anh.125はC.P.E Bachの鍵盤作品なんだそう。たしかに古典的端正な風情がちょっぴり風情が漂って、通常低音はやはりリュートだと思います。Affectuoso(1:50)Allegro(2:04)Adagio(1:35)Vivace(1:39)
序曲ヘ長調BWV 820 のオリジナルは鍵盤作品、これをオーボエが表情豊かに活躍する管弦楽組曲に仕上げております。通奏低音はリュートか。符点のリズムにフランス風序曲「Overture」これはまるっきりオリジナル風に響きました。(2:13)「Entree」ここには太鼓?が典雅なリズムを刻みます。(2:35)「Menuet - Trio」は優雅に落ち着いて(2:25)快活な「Bourree」(0:45)「Gigue」は素っ気なく、あっという間に終わりました。(0:49)
管弦楽組曲第2番イ短調 BWV1067はもともとロ短調、なにがどう復元なの?ここにはフルートは入らぬ弦のみ、おそらくOVPP(One Voice per Part/各声部一人)馴染みの哀愁の旋律は、快速快活リズミカルにノリノリに歌われ、これはこれで完成された趣がありました。Ouverture(6:11) Rondeau(1:35) Sarabande(2:51) Bourree I-II*ここにもコンガ?みたいな打楽器が入って効果的(1:54) Polonaise*ここはもっと低音が効いた太鼓がしっかりアクセント(1:22)Menuet*リュートの通奏低音が美しい(1:10)Battinerie*賑やかに激しいフィナーレ。ここにも太鼓登場(1:26)
ファンタジア ト長調 BWV571はオルガン曲からの編曲。愉悦に充ちた快活な弦楽アンサンブルがカッコ良く躍動しました。Allegro(2:45)Adagio(1:41) Ciaconna - Allegro(2:13)
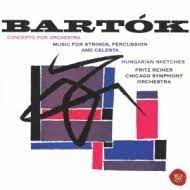 Bartok 管弦楽のための協奏曲〜フリッツ・ライナー/シカゴ交響楽団(1955年)・・・いったい数十年前出会いから幾度聴いているのか、この作品は大好きだから、新しいのもの含めて幾種も”上手い演奏”を聴いていて、それでも聴く度この圧巻のオーケストラの厚みのある響きと技量、音質の鮮度の高さ、自信漲(みなぎ)る迫力に打ちのめされます。テンポはどれも適正を感じさせるのは、これが刷り込みだからでしょう。三管編成+ティンパニ先頭に7種の打楽器+ハープ2台による名曲中の名曲。
Bartok 管弦楽のための協奏曲〜フリッツ・ライナー/シカゴ交響楽団(1955年)・・・いったい数十年前出会いから幾度聴いているのか、この作品は大好きだから、新しいのもの含めて幾種も”上手い演奏”を聴いていて、それでも聴く度この圧巻のオーケストラの厚みのある響きと技量、音質の鮮度の高さ、自信漲(みなぎ)る迫力に打ちのめされます。テンポはどれも適正を感じさせるのは、これが刷り込みだからでしょう。三管編成+ティンパニ先頭に7種の打楽器+ハープ2台による名曲中の名曲。
第1楽章「Introduzione(序章)」から圧巻のテンションの高さ、旋律節回しの絶妙なこと。リズムの厳しさとキレ、トランペットの輝かしさ。(10:02)
第2楽章「Presentando le coppie(対の提示)」は冒頭の乾いた小太鼓から剽軽な木管、弦のピチカートはノリノリのリズム感。前のめりの勢い、中間部の金管によるコラールは正確無比なアンサンブル。(6:04)
第3楽章「Elegia」は幻想的に濃厚な静謐から始まる「夜の歌」。やがて朗々とした絶叫が微細なニュアンスを伴って決然とやってきて、そして冒頭に戻る・・・オーケストラのパワーは圧巻でした。(7:59)
第4楽章「Intermezzo interrotto(中断された間奏曲)」は強烈に雄弁な弦から、剽軽な風情に木管がそれに呼応してそれは自身に充ち、やがて弦が幽玄に歌います。そしてShostakovichの引用とトロンボーンのグリッサンドによる「ブーイング」による「中断」出現。この表情対比が決然! 剽軽な木管に終了しました。(4:15)
第5楽章「Finale(終曲)」細かい弦のパッセージはあまりアクロバティックに速くはないけれど、縦線ぴったりに重量級。金管のフーガは色彩と熱気に溢れて、怪しいパワーマシマシにフィナーレに向かって突き進みました。最高。(8:59)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
よりいっそう寒さ募って、雪の被害は全国各地に出ているよう。豪雪に鳥取名産の白ネギ壊滅との報道、また野菜高が続くのか。米と野菜高騰に政治は無策に感じます。そういえば本日は札幌の兄は72歳の誕生日。2年前に大病を患って、ま、年に1-2回LINEの遣り取りをするくらい。両親を見送って、墓の始末も任せてしましました。
前日夕方は久々にお魚焼いたり、カリフラワーのサラダを作ったり、ちゃんとした夕食を女房殿と二人、自家製ヨーグルトも仕込みました。自分がさっさとフロ入ったところに婆さん降圧剤ニ度服用事件発生して、慌てて女房殿出動、結果独り暮らしが続きました。音楽は聴いているし、定期的なストレッチや鍛錬も継続しているけれど精神的にはヤバいと自覚しております。テレビ番組、ドラマ、YouTubeを眺めてもほとんどつまらない、オモロない。新しいことに興味が持てない。欲しいものもなにもない。数日前ヒマな爺友同士呑んで、会話のやり取りはボケ防止のつもり。朝は一日溜めた洗濯物は大量、ストレッチ、YouTube鍛錬はいつもどおり、そして0度C?雪の予報も出た中、市立体育館目指して、いつもどおりのメニューを消化しました。(マルチ・チェストだけはマッチョ・ダンベル兄さんが30分以上独占して使えない)女房殿は昼過ぎご帰還、昼は喰い過ぎ自覚、夕食は豆腐をダブって買っていたので野菜とともに消化した挙げ句、体重は68.65kg危険水域継続中。これは健康上よろしくない。
テレビがオモロないなんて云った先から、「女弁護士水島由里子の危険な事件ファイルNo.1」なにかと話題のフジテレビ、ずいぶんと久々に二時間ドラマ(再放送/BS)偶然拝見。
1997年と云えばもう30年ほど前、主役の高島礼子当時33歳、若い! 思っきりセクシーに化粧が濃い。服装もステキだけれど時代を感じさせました。周りを固める今井雅之、古尾谷雅人ふたりとも、とうに鬼籍に入って、ヴェテラン刑事役の山田吾一とは懐かしい名前、亡父と同郷同世代、知り合いでした。雰囲気も似ております。ドラマでは必ず大切な役どころに登場する岸部一徳、本田博太郎も若々しい。悪役が多い濱田万葉も未だ若手だった23歳、なんか今と違って可愛らしい。今井雅之がやたらと暴力的なのが時代でしょうね。もちろん職場での煙草スパスパなのはあたりまえ。トドメは「証拠のフロッピー・ディスクはどこだ!」。なんか後ろ向きの感慨を堪能いたしました。
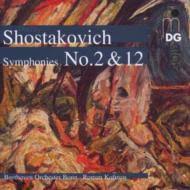 Shostakovich 交響曲第2番 変ロ長調「十月革命に捧げる」/交響曲第12番ニ短調「1917年」〜ローマン・コフマン/ボン・ベートーヴェン管弦楽団(2002-2007年)・・・Roman Kofman(1936ー烏克蘭)による全集録音。昨年2024年に第5番第9番を聴いておりました。優秀録音と思うけれど、ダイナミックレンジが広すぎて、我が安物オーディオ環境では第2番冒頭はほとんど聴き取れないほど。ボン歌劇場のピットにも入るオーケストラにはパワーはあまりないけれど、意外と誠実なアンサンブル、2003-2008年音楽監督を務めたコフマンの統率の成果でしょう。この作品の組み合わせは同じ1917年10月革命を題材としたものだったのですね。
Shostakovich 交響曲第2番 変ロ長調「十月革命に捧げる」/交響曲第12番ニ短調「1917年」〜ローマン・コフマン/ボン・ベートーヴェン管弦楽団(2002-2007年)・・・Roman Kofman(1936ー烏克蘭)による全集録音。昨年2024年に第5番第9番を聴いておりました。優秀録音と思うけれど、ダイナミックレンジが広すぎて、我が安物オーディオ環境では第2番冒頭はほとんど聴き取れないほど。ボン歌劇場のピットにも入るオーケストラにはパワーはあまりないけれど、意外と誠実なアンサンブル、2003-2008年音楽監督を務めたコフマンの統率の成果でしょう。この作品の組み合わせは同じ1917年10月革命を題材としたものだったのですね。
交響曲第2番 変ロ長調は1927年初演「楽章構成を破棄した単一楽章の形式、無調・27声部におよぶウルトラ対位法などの技法」とのこと(Wikiより)三管編成に+混声合唱+6種の打楽器+サイレンを駆使した政治的宣伝音楽(どこが交響曲なんだよ!)・・・時代が変われば純音楽として愉しめる時代に至っております。
静謐に息を潜めるように重苦しい「Largo(序奏)」やがて苦しくも軽妙なテンポ・アップに金管打楽器が参入して、オーケストラは予想外に集中力の高い洗練されたもの。この辺りの音の鮮度最高。「Allegro - Poco meno mosso - Allegro molto(フガート)」脈絡なく木管弦も疾走して緊張感が高まります。(12:16)やがて風雲急を告げるサイレンに乗って合唱参入する「Meno mosso(合唱 - コーダ)」(言葉の意味はわからんけど革命礼賛でしょう)ラストはシュプレヒコール(≒死語)「これこそ旗、これこそ生き生きとした世代の名称、10月、コミューン、そしてレーニン」で締めくくられる・・・(Wikiより引用)パワーや荒々しさに足りぬけれど、知的に整った見事な演奏でした。(6:38)
交響曲第12番ニ短調はこの間種々いろいろな演奏で聴いて、もしかしてこれは第5番や第7番以上にわかりやすい旋律、大衆的な作品、そんな考えに至りました。ここも収録音量が低く、リアルな優秀録音であることを認識するにはボリュームを上げる必要があります。オーケストラは細身のサウンドに洗練され、キレ味もありました。
第1楽章「革命のペトログラード」序奏「Moderato」から始まる物々しい嵐の前の静けさは、チェロとコントラバスによる旋律がとてもわかりやすい。やがて「Allegro」は全曲を貫く旋律が楷書鋭角な表現に爆発して、泥臭さや停滞を感じさせぬ、線は細くさっぱりとスリムな響き。カッコよい推進力を感じさせます。打楽器もノリノリに、アンサンブルは意外と優秀。(13:54)
第2楽章「ラズリーフ(Adagio)」暗鬱な静謐が続いてちょっとわかりにくい緩徐楽章。ここもさらりと爽やかに軽い響き、洗練された表現から、例の第1楽章のわかりやすい主題も静かに出現します。(12:36)
第3楽章「アヴローラ(Allegro)」弦のピチカートによる静かな「アヴローラ」(巡洋艦)の主題からやがて第1楽章の主題が高らかに登場して打楽器が連打爆発!=大砲が十月革命の火蓋が切られる。(4:10)
第4楽章「人類の夜明け(L'istesso tempo - Allegretto - Moderato)」前楽章ラストの爆発のまま、ホルンの高らかな勝利の歌は金管全体にちょっぴり軽量だけど、カッコよいもの。やがて第1楽章の主題が回帰して、輝かしいくらいマックスを築きました。打楽器の迫力キレ味もなかなかですよ。(1:27-8:38)
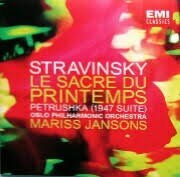 Stravinsky バレエ音楽「春の祭典」/バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)〜マリス・ヤンソンス/オスロ・フィル/ゴンザロ・モレノ(p)(1992年)・・・Mariss Jansons(1943-2019拉脱維亜)は1979-2000年までオスロ・フィルの首席指揮者を務めて、オーケストラも彼自信も一躍評価を高めた時期の録音。オーケストラの技量が問われるデーハーな近現代管弦楽法の精華作品、音質はまずまずだけど、この時期としてはやや不満を感じました。ネットに評価を探ると真反対の評価が出るからオモロいもの
Stravinsky バレエ音楽「春の祭典」/バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)〜マリス・ヤンソンス/オスロ・フィル/ゴンザロ・モレノ(p)(1992年)・・・Mariss Jansons(1943-2019拉脱維亜)は1979-2000年までオスロ・フィルの首席指揮者を務めて、オーケストラも彼自信も一躍評価を高めた時期の録音。オーケストラの技量が問われるデーハーな近現代管弦楽法の精華作品、音質はまずまずだけど、この時期としてはやや不満を感じました。ネットに評価を探ると真反対の評価が出るからオモロいもの
●管楽器の名手が揃うオスロ・フィルならではの見事な演奏
■手堅く拍子を含めて管理し、アンサンブルが浮足立たないように努めているのだが、金管セクションが慣れない音楽を目を白黒させながら演奏しているのが目に見えるようだ
自分なりの印象は後者支持かな?「春の祭典」はヤンソンスがかっちりと統率して、フクザツなリズムを曖昧さなく進めて爽やかな響きだけれど、オーケストラ各パートの技量がいまいちスムースではない、音色がオモロない感じ。第1部「大地の礼賛」後半、指揮者の叱咤激励が感じられました。第2部「生贄の儀式」の追い込みは見事だけれど、オーケストラには余裕が足りない印象がありました。(3:23-3:28-1:17-3:44-1:50-0:43-0:21-1:18/3:48-2:57-1:36-0:44-3:24-4:39)
「ペトルーシュカ」は三管編成の改訂版使用。これもまったく同様の印象。元気よろしい悪くない演奏だけど、オーケストラのサウンドがどうにもヤワい。作品を知り、堪能するには充分な存在でしょう。ファンの方々、申し訳ない。(7:04-2:48-4:19-3:29-3:11-1:03-2:24-1:31-1:09-2:08-1:33-0:47-0:52-1:08-0:50)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
こちらは良き天気だけれど、寒い日々が続きます。女房殿不在時には電気代節約してエアコンは使用せず、ホットカーペットやコタツで過ごして、なかなか身動きがとれません。呑んだ翌日なのにぐっすり眠れ、朝目覚めて体調も悪くない。洗濯は女房殿が戻るまで待機、ストレッチ+YouTubeスワイショウ実施して引き隠っておりました。前日、業務スーパーに大豆を入手して一晩水に漬けて、朝圧力鍋に軽く加熱して二度アク抜き、それから砂糖+ちょっぴり醤油+昆布を細かく刻んで加えてしっかりと煮ました。女房殿は昼前に帰宅、当面婆さんは大丈夫みたい。大豆煮豆は甘さ控えめに柔らかく絶賛いただきました。(夕方、薬をのみ間違えたらしくて、あわてて出掛けていきました)自家製ヨーグルトは概ね週一製造、種菌にするヨーグルト残分またダメにしました。さっさと喰うべきであった。今朝は68.7kg+700g、身動きせず引き隠って今月最悪の体重(涙)
先日眺めた90歳元気に微笑ましい爺さんの動画の続き。
サブスクはシルバー世代に重大な問題を引き起こしているのか?インスタント味噌汁の入金、督促、W支払いやら(おすすめされたら断れない?)
ホームセンターに出掛けたらムリムリ、カードを作らされて、なにを勧められたのか最後迄わからんかったとか。そもそもカード4枚分(娘さんが説得して)解約したばかりだったそう。通話しか使わないのに、最新型の高価高級アイフォンを使って(おそらくはショップの方にお勧めされるままに購入)挙げ句「動かなくなった」→再起動させることも知らない。ショップに出掛けようとして、その前に娘さんがフォローしておりました。
これは人ごとじゃない、自分がお仕事現役時代には存在しないものが次々と実社会に出現して、そらくは身体で理解できない。それは自分だって同じこと。この先心身ともに衰えて、トンデモ想像を絶する「新たなもの」が登場して、その無知に付け込む悪人がある日玄関を叩くかも。
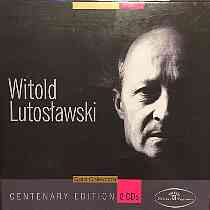 Lutoslawski ラクリモーサ(ヴィトルド・ルトスワフスキ/ステファニア・ヴォイトヴィチ(s)/シレジア・フィルハーモニー合唱団/ポーランド放送交響楽団)/交響曲第1番(ヴィトルド・ルトスワフスキ/ワルシャワ・フィル/1976-7年)/管弦楽のための協奏曲/弦楽のための葬送音楽(ヴィトルド・ロヴィツキ/ワルシャワ・フィル/1964年)・・・Witold Lutoslawski Centenary Edition(8CD)は2012年発売。おそらく生誕100年を記念してWitold Lutoslawski(1913ー1994波蘭)の主要作品を自演や波蘭の代表的な演奏家によってまとめたものの一枚目。音質極めて良好。録音年を探すのに四苦八苦しつつ、先日ストコフスキーの交響曲第1番が思わぬカッコ良さだったので、こちらも聴いてみました。
Lutoslawski ラクリモーサ(ヴィトルド・ルトスワフスキ/ステファニア・ヴォイトヴィチ(s)/シレジア・フィルハーモニー合唱団/ポーランド放送交響楽団)/交響曲第1番(ヴィトルド・ルトスワフスキ/ワルシャワ・フィル/1976-7年)/管弦楽のための協奏曲/弦楽のための葬送音楽(ヴィトルド・ロヴィツキ/ワルシャワ・フィル/1964年)・・・Witold Lutoslawski Centenary Edition(8CD)は2012年発売。おそらく生誕100年を記念してWitold Lutoslawski(1913ー1994波蘭)の主要作品を自演や波蘭の代表的な演奏家によってまとめたものの一枚目。音質極めて良好。録音年を探すのに四苦八苦しつつ、先日ストコフスキーの交響曲第1番が思わぬカッコ良さだったので、こちらも聴いてみました。
「Lacrimosa(涙を流す)」はソプラノと合唱がデリケートに嘆く神聖な静謐。(3:29)
交響曲第1番は1948年初演。ピッコロ2/フルート1本というのは三管編成。弦、金管の他、ティンパニ/ドラム/シンバル/シロフォン+ピアノ/ハープが入ります。この作品はすっかりお気に入りになりました。
第1楽章「Allegro giusto」いきなりの管楽器の絶叫から、ヒステリックな切れ味鋭い細かい音型が疾走してド迫力リズム。金管主導の旋律は意外と平易、圧巻のカッコ良さ。オーケストラのアンサンブルは優秀。(5:00)
第2楽章「Poco adagio」ホルンが暗鬱に絶望的な弦がうねうね蠢(うごめ)く緩徐楽章。これはその風情のまま狂気を帯びてパワフルに育ちます。金管の細かい音型が圧巻にカッコよい。(9:21)
第3楽章「Allegretto misterioso」怪しい暗いピチカートのリズムから始まって、これはスケルツォですか?ドデカフォニーらしいけど、聴手(=ワシ)は不安げな雰囲気と突然の絶叫を堪能しただけ。(4:52)
第4楽章「Allegro vivace」これもモウレツにヒステリックな疾走と爆発、金管先頭にキレ味最高。不協和音なんだけど、なんかとってもクリアにカッコよく響きは濁らない。(5:44/拍手有)
後半のWitold Rowicki(1914-1989波蘭)による演奏はPHILPSから出ていたもの。
「管弦楽のための協奏曲」は1954年初演、過去記録を探ると数回いろいろ拝聴して、その硬質にキレのある響きをけっこう堪能しておりました。三管編成に+ティンパニ先頭に9種の打楽器、チェレスタ、ピアノ、ハープ2台。どこがどう協奏曲なのかいまいち理解できていないけれど、新バロック様式なんだそう。音質やオーケストラの響きは前曲よりちょっぴりマイルド。
第1楽章「Intrada: Allegro maestoso」ティンパニの連打に乗って弦が憂鬱に歌って、やがて激しいリズムを刻み続けます。素材は民謡らしく、あちこち懐かしい木管の歌なども出現します。(7:51)
第2楽章「Capriccio notturno e arioso: Vivace」細かくデリケートな弦と木管の静かな疾走するスケルツォ。この辺り、かなりオーケストラの技量が問われそうなところ(後半のピチカートも含めて)ワルシャワ・フィルはみごとなアンサンブルですよ。途中金管がファンファーレみたいな風情に叫んで(ariosoなんだそう)暴力的に響きが濁らぬのがLutosawskiでしょう。(5:51)
第3楽章「Passacaglia, toccata e corale: Andante con moto - Allegro giusto」表題からしていかにもバロック風情、Passacagliaは暗く静かなコントラバスが主題を提示して、やがて静かに目覚めるように変奏され、高揚絶叫して怪しさマシマシ。でも、カッコよいですよ。一転、元気なTaccataが疾走して無調だから明るいんだか、暗いんだか?でも不安な風情にリズムを激しく刻んで徐々に盛り上がります。それは暴力的に響かぬ快走。そしてクライマックスから平和なコラールへ、不協和音だけど妙な高揚感がカッコよいもの。(16:41)
「Musique funebre」は1958年、Bartokの死を悼んで作曲された作品だそう。R.Straussの「メタモルフォーゼン」を思いっきり不協和音に仕上げたような悲痛な音楽でした。(14:02)
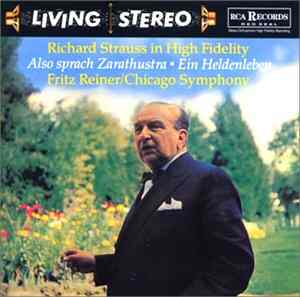 交響詩「英雄の生涯」〜フリッツ・ライナー/シカゴ交響楽団(1954年)・・・幾度聴いている鉄板の演奏。1954年のRCAステレオ録音は驚異的、肌理の細かさ、奥行き高さ云々すればキリはないけれど、70年前でこの鮮度だったら文句はないでしょう。そしてシカゴ交響楽団の金管の威力が有無を云わせぬ輝かしいド迫力、テンションの高さ。恐ろしいほどの集中力は基本イン・テンポに一気呵成。いろいろ新しいのも含めて聴いて、これと「ツァラトゥストラ」はやっぱFritz Reiner(1888-1963洪牙利→亜米利加?)に限る!
交響詩「英雄の生涯」〜フリッツ・ライナー/シカゴ交響楽団(1954年)・・・幾度聴いている鉄板の演奏。1954年のRCAステレオ録音は驚異的、肌理の細かさ、奥行き高さ云々すればキリはないけれど、70年前でこの鮮度だったら文句はないでしょう。そしてシカゴ交響楽団の金管の威力が有無を云わせぬ輝かしいド迫力、テンションの高さ。恐ろしいほどの集中力は基本イン・テンポに一気呵成。いろいろ新しいのも含めて聴いて、これと「ツァラトゥストラ」はやっぱFritz Reiner(1888-1963洪牙利→亜米利加?)に限る!
Der Held(4:16)/Des Helden Widersacher(3:04)/Des Helden Gefahrtin(11:58)
/Des Helden Walstatt(8:44)/Des Helden Friedenswerke(4:40)/Des Helden Weltflucht und Vollendung(10:54)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
寒いですね。日本海側はいつにない大雪、北海道も記録的な積雪量は災害級、交通にも影響が出ているそう。こちらは寒くても知れております。朝、ゴミ出しに出掛けたら集積所はすっからかん、昨日だったことに気付きました。日時を間違えるようじゃノーミソちょっと危ういかも。婆さんの症状は心配だけど、申し訳ないけど気分転換にちょっと呑みにいこうか、ヒマ同士な爺友を誘いました。独り暮らしだとどうも食生活が不規則、粗末になりがちです。朝、ストレッチしっかり、YouTubeエアロビクス済ませて市立体育館へ。トレーニングルームはますます閑散として、いつもどおりの筋トレ+エアロバイクさっさと済ませて、帰宅後洗濯しました。
コミュニティバスに乗って最寄りの駅迄けっこうな雪が舞って、ホームに出たら尼崎の先の方で線路火事とか、ダイヤ滅茶苦茶。(あとで報道を確認すると四萬壱阡人に影響とか/自分がそのひとり)京橋で止まってしまって環状線に乗り換えて梅田へ、待ち合わせには間に合いました。いつもの梅田駅前ビル地下の激安居酒屋でバカ話して夕方明るいうちに帰宅しました。帰り業務スーパーにて野菜など入手。LINEに婆さんの検査結果が出て、とくに大きな問題はないそう。散々喰って呑んで結果68.0kg、危険水域から抜け出せない。
芸能ネタには疎いけれど、小島瑠璃子さんの旦那が自裁したとの残念な報道、周りの類推だけど会社経営は上手くいっていなかったらしい。詳細はわからぬけれど、他にも要因があったのでしょうか。彼女はコロナ前?大人気だったことは知っていて、中国留学目指して引退、コロナでそれを断念してやがて結婚、たしか赤ちゃんが生まれたばかりのはず。この先、生活していくためには芸能界復帰するのかも。その立ち位置は難しそう。
あまり興味も知識もない芸能界やけど、昨今話題の「一寸先は闇」転落事件連続を見ていると、これは「夢を売る」虚業やなぁ、しみじみそう思います。彼女の場合は不適切な行為自業自得に非ず、たまたま偶然の巡り合わせがよろしからぬ方向に続いたのでしょう。なんか気分の滅入るニュースばかり。宝塚市に240億円?寄付した剛毅な夫婦のニュースはなんかとっても凄いけど。
 Berlioz 交響曲「イタリアのハロルド」(ユーディ・メニューイン(va)/1962年)/Tippett ピアノ協奏曲(ジョン・オグドン(p)/1963年)〜コリン・デイヴィス/フィルハーモニア管弦楽団・・・既に幻想交響曲の成功に名を挙げていたBerlioz1834年の作品。珍しい独奏ヴィオラ+二管編成+打楽器は4種+ハープという意外と古典的なもの。20世紀作品の普及にはトスカニーニとウィリアム・プリムローズの功績があったそう。Colin Davis(1927-2013英国)が未だ40歳前の記録、幾度か聴いているはずだけど、かつての印象より意外に音質は悪くない、まずまずか。フィルハーモニア管弦楽団のアンサンブルも優秀でした。
Berlioz 交響曲「イタリアのハロルド」(ユーディ・メニューイン(va)/1962年)/Tippett ピアノ協奏曲(ジョン・オグドン(p)/1963年)〜コリン・デイヴィス/フィルハーモニア管弦楽団・・・既に幻想交響曲の成功に名を挙げていたBerlioz1834年の作品。珍しい独奏ヴィオラ+二管編成+打楽器は4種+ハープという意外と古典的なもの。20世紀作品の普及にはトスカニーニとウィリアム・プリムローズの功績があったそう。Colin Davis(1927-2013英国)が未だ40歳前の記録、幾度か聴いているはずだけど、かつての印象より意外に音質は悪くない、まずまずか。フィルハーモニア管弦楽団のアンサンブルも優秀でした。
第1楽章「山におけるハロルド、憂愁、幸福と歓喜の場面」は物憂い序奏の始まり、穏やかな表情のヴィオラがしっとり歌って活躍するけれど、これはPaganiniが求める華やかな技巧を披瀝するものに非ず、叙情的に美しいけどジミもの。メニューインは立派だと思います。符点にリズムにヴィヴィッド、後半の華やかな金管炸裂はいかにもBerlioz、二管編成とは思えぬ華やかな効果でした。(16:26)
第2楽章「夕べの祈祷を歌う巡礼の行列」優しい落ち着きに充たされ、平和な旋律の緩徐楽章。ヴィオラのソロはアンサンブルに溶け込んで一貫してジミでした。(9:00)
第3楽章「アブルッチの山人が、その愛人によせるセレナード」弾むようなリズムに始まる穏健なスケルツォ楽章。牧歌的なオーボエやホルンが優しく歌って、しっとりヴィオラ・ソロがそれに応えます。それは目まぐるしい技巧的な動きに非ず、シンプルな穏健に切ないワルツでした。そして愉快に弾むリズムに乗って、ヴィオラが切々とセレナードを歌います。(6:32)
第4楽章「山賊の饗宴、前後の追想」風雲急を告げるフィナーレは激しい始まり。ヴィオラ・ソロがそれを諌めても金管の咆哮は交互に続いて緊張感は高まります。途中からヴィオラ・ソロの出番は消え、金管の元気よろしい、華やかな進撃が続きました。フィルハーモニア管弦楽団の実力は充分。幻想交響曲に於けるわかりやすい甘い旋律や、グロテスクな迫力に足らぬけれど、こちらも名曲ですよ。(12:15)
Michael Tippett(1905ー1998英国)のピアノ協奏曲初演は1956年(ルイス・ケントナー(p))三管編成+打楽器(ティンパニ+トライアングル+シンバル)+チェレスタ。Beethovenのピアノ協奏曲第4番ト長調の影響を受けているんだそう(ド・シロウト耳にはどこが?状態)。John Ogdon(1937-1989英国)に残された録音に外れはありません。こちらも音質はまずまず。耳をつんざく濁った不協和音ではない、むしろ静寂と調和が支配する美しい作品。
第1楽章「Allegro non troppo」怪しく不安にきらきらとした静かな始まり。ピアノはなかなか登場せず、突出せず、オーケストラ各パートとほとんど対等に(時に伴奏風に)扱われる合奏協奏曲。旋律に晦渋さはなく、夢見るように感情の起伏を感じさせるもの。後半にソロの腕の見せ所(カデンツァですか?)チェレスタと絡み合って、やがて各パートが静かに参入して終了。(15:56)
第2楽章「Molto lento e tranquillo」ホルンの不安な合奏から始まって、ピアノはそのアルペジオ伴奏風。木管は不協和音だけれど、それは不快に非ず一貫した不安でした。合奏協奏曲らしく、各パートは対等にその存在を主張してピアノと絡み合います。(8:14)
第3楽章「Vivace」軽妙快活なオーケストラの合奏に始まるフィナーレ。ここもなかなかピアノは登場せず、満を持して情熱的なブルース風に疾走、それをオーケストラが受け止めて各パート雄弁に華やかに登場場面有。20世紀の音楽だからモダーンな風情に、調性もよくわからないけれどそこは英国音楽、暴力的な爆発に非ず、晴れやかにリリカルな躍動が続いてわかりやすい。ピアノは華やかな出番は少ない(おそらく)難物な技巧、オグドンは難なくクリアして、若きコリン・デイヴィスのバランスもお見事でした。(8:11)
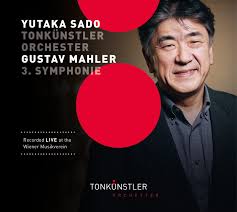 Mahler 交響曲第3番ニ短調〜佐渡裕/トーンキュンストラー管弦楽団/ケイト・リンジー(ms)/ウィーン少年合唱団/ウィーン楽友協会合唱団(2021年ムジークフェライン・ザール・ライヴ)・・・ギネス級の巨大な美しい作品、編集はしてあると思うけれど、ライヴ収録。優秀なアンサンブル、ムダに急いだり、雑になったりせず、細部ていねいに落ち着いた立派な仕上げはスケールも大きい完成度でした。最初から最後迄感動的に聴き通したけれど、技術的な問題は一切ない透明なサウンドに、各パートの色気とか個性とか味わいとか、どうも素直に過ぎてオモロない。ドキドキするスリリングなうねり、みたいなものが足りない感じ。誠実な演奏だから実演ではさぞ感銘深いであろうと類推されました。第1楽章「Kraftig - Entschieden」(33:25)第2楽章「Tempo di menuetto. Sehr massig」(9:55)第3楽章「Comodo. Scherzando. Ohne Hast」(17:18)第4楽章「Sehr langsam. Misterioso」(9:12)第5楽章「Lustig im Tempo und keck im Ausdruck」ウィーン少年合唱団は天使の声ですよ。(4:08)第6楽章「Langsam. Ruhevoll. Empfunden」(25:45拍手込)
Mahler 交響曲第3番ニ短調〜佐渡裕/トーンキュンストラー管弦楽団/ケイト・リンジー(ms)/ウィーン少年合唱団/ウィーン楽友協会合唱団(2021年ムジークフェライン・ザール・ライヴ)・・・ギネス級の巨大な美しい作品、編集はしてあると思うけれど、ライヴ収録。優秀なアンサンブル、ムダに急いだり、雑になったりせず、細部ていねいに落ち着いた立派な仕上げはスケールも大きい完成度でした。最初から最後迄感動的に聴き通したけれど、技術的な問題は一切ない透明なサウンドに、各パートの色気とか個性とか味わいとか、どうも素直に過ぎてオモロない。ドキドキするスリリングなうねり、みたいなものが足りない感じ。誠実な演奏だから実演ではさぞ感銘深いであろうと類推されました。第1楽章「Kraftig - Entschieden」(33:25)第2楽章「Tempo di menuetto. Sehr massig」(9:55)第3楽章「Comodo. Scherzando. Ohne Hast」(17:18)第4楽章「Sehr langsam. Misterioso」(9:12)第5楽章「Lustig im Tempo und keck im Ausdruck」ウィーン少年合唱団は天使の声ですよ。(4:08)第6楽章「Langsam. Ruhevoll. Empfunden」(25:45拍手込)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
曇りとの予報も日差しは出て、気温が低いのはそのとおり。食材は切れ掛けだけど寒いから外出する元気はありません。体調はグズグズ連続、熱はないからウィルスには侵食されていないはず。温いコタツに引き隠りました。鼻詰まり悪化はぼちぼち花粉症なのか。それとも流行りの某ウィルスに敗北しつつあるのか。女房殿不在でも朝のヘルシーフードは変わらず、ストレッチ済ませて、YouTube鍛錬は懐かしいラジオ体操出現! 数十年の所作もちゃんと覚えているのはこどもの頃からの刷り込み、しかしラジオ体操第3は動きがわからない。女房殿は昼頃に戻って市立体育館へ、婆さんは入院するかも知れない。体調整えてから、また婆さんのところに戻っていきました。今朝の体重は68.05kgこの大台から抜け出せない。
埼玉・八潮市の陥没事故から1週間。事態は泥沼にトラック運転手の安否も不明、周辺住民にも大きな不便が出ているそう。そういえば昨年、広島の地盤云々の件ももうなったのでしょう。下水上水道橋梁、日本全国あちこち寿命が尽きているものは多いと思います。我が街だって例外に非ず。
「ドラッグストア 外国人の万引深刻」〜複数人で来店の手口も…来日外国人による万引き1件あたりの被害額が平均8万8,531円 医薬品・化粧品の被害が半数以上(警察庁)
なんか気分が滅入る話題が続きます。自分がお仕事現役時代、取引先の店舗現場に内情を伺ったのはもう数十年前時点、既に化粧品の万引きが多かったそう。小さいし、単価が張るし、転売しやすいものですから。おそらくは亜細亜系の素性よろしくない方々が組織的に手っ取り早く稼げるものを狙ってのことでしょう。福祉の進んだ北欧でしたっけ、難民を多く受け入れたEC諸国含めて、治安の悪化は目を覆うばかり。旧植民地の歴史的の流れもあるから一概に云えないけれど、日本は難民認定に厳しい、もっと受け入れを!みたいな声もあってそれも一理有。
一方で外国人の流入を抑制してきたから、未だ治安が維持できてきたということもあるのでしょう。労働力不足とインバウンド目当てにそれを緩める動きもあるけれど、話題になった「富士山の見えるコンビニ」とか、鉄道マニア(日本人の一部もマナー悪いけど)が事故に遭ったり、なかなか訪日観光客の迷惑行為問題、オーバーツーリズムは悩ましいですね。狙った施策が思わぬ結果や副作用を呼ぶこともあるようです。ま、我が街は観光とはあまり縁がないので、ピンときておりません。
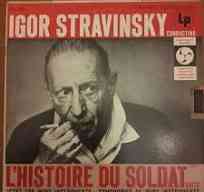 Stravinsky 組曲「兵士の物語」/管楽八重奏曲(室内アンサンブル/1954年)/管楽器のためのサンフォニー(北西ドイツ放送交響楽団/1951年)〜イーゴル・ストラヴィンスキー・・・自作のモノラル録音は録音情報が混乱して1954年→1951年とのネット情報もあったし「サンフォニー」はSONYのサイトには1958年ケルン放送交響楽団(分離前なのに?)となっていて、貼付(ちなみに「ちょうふ」と読むのが正解)ジャケ裏の写真を正解としました。音質はほんのちょっぴり落ちます。この辺りの作品は自分のツボでした。
Stravinsky 組曲「兵士の物語」/管楽八重奏曲(室内アンサンブル/1954年)/管楽器のためのサンフォニー(北西ドイツ放送交響楽団/1951年)〜イーゴル・ストラヴィンスキー・・・自作のモノラル録音は録音情報が混乱して1954年→1951年とのネット情報もあったし「サンフォニー」はSONYのサイトには1958年ケルン放送交響楽団(分離前なのに?)となっていて、貼付(ちなみに「ちょうふ」と読むのが正解)ジャケ裏の写真を正解としました。音質はほんのちょっぴり落ちます。この辺りの作品は自分のツボでした。
語りの入らぬ短縮版である「兵士の物語」組曲は1920年エルネスト・アンセルメ初演。すこぶる良好な音質でして、最初は後年のステレオ録音?そう信じて聴いておりました。メンバーは腕利き揃えて(アレクサンダー・シュナイダー(v)/ジュリアス・レヴァイン(cb)/エルヴィン・プライス(tb)/ロバート・ナーゲル(tp)/アルフレッド・ハワード(pec)/ローレン・グリックマン(fg)/デイヴィド・オッペンハイマー(cl))脈絡のない乾いた旋律、ムダのないサウンドが喜怒哀楽起承転結なくエピソードが連続して、兵士が悪魔に騙される怪しいおとぎ話は筋と題名を確認しながら聴くとすこぶる楽しく、大好きな作品でした。
兵士の行進曲(1:41)兵士のヴァイオリン(2:44)パストラール(2:59)王の行進曲(2:39)小コンサート(2:43)3つの舞曲(タンゴ・ワルツ・ラグタイム)(2:01-1:55-2:04)悪魔の踊り(1:19)コラール(2:57)悪魔の勝利の行進曲(2:09)
先日エド・デ・ワールトを聴いたばかりの管楽八重奏曲は1923年初演(クーセヴィツキー)。素っ頓狂に元気のよろしい旋律がモウレツに楽しい、これもユーモラスな作品。フィナーレは人懐こく終わります。(メンバーはジュリウス・ベーカー(fl)/デイヴィド・オッペンハイマー(cl)/ローレン・グリックマン(fg)/シルヴィア・ドイチャー(fg)/ロバート・ナーゲル(tp)/テッド・ワイス(tp)/アーウィン・プライス(tb)/リチャード・ヒクソン(tb)/Sinfonia(3:54)Tema con varizioni(0:53-0:30-0:58-0:26-0:48-1:01-0:31-2:30)Finele(3:49))
管楽器のためのサンフォニーがDebussy追悼のための作品とは知りませんでした。クーセヴィツキー初演(1921年/大失敗したそう)ここではおそらく1947年改訂版使用と類推。編成はフルート3/オーボエ2/コーラングレ1/クラリネット3/ファゴット3/コントラファゴット1/ホルン4/トランペット3/トロンボーン3/テューバ1。これは所謂交響曲に非ず「共に鳴り響くもの」という昔の意味なんだそう。華やかだが気まぐれなファンファーレと、遅くしめやかなコラールの交替で曲は進行する(Wiki引用)時にヒステリックに、つかみどころのない作品、現在ではけっこう演奏機会は多いと思います。(9:11)
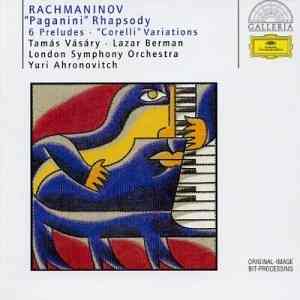 Rachmaninov パガニーニの主題による変奏曲〜タマーシュ・ヴァーシャリ(p)/ユリ・アーロノヴィッチ/ロンドン交響楽団(1976年)・・・2014年に拝聴記録有。Vasary Tamas(1933-洪牙利→瑞西)は晩年指揮にも手を染めていた名ピアニスト。駅売海賊盤時代よりお気に入りでした。Chopinもステキな出来でしたよ。この作品は屈指の甘い旋律を誇る名曲、清潔なタッチにしっとり歌って、テクニックに曖昧さがない。Yuri Ahronovitch(1932-2002露西亜)も雰囲気たっぷり、ロンドン交響楽団のキレあるバックも文句なし。音質もリアルに優秀でした。第1-6変奏(3:34)第7-10変奏(3:16)第11-15変奏(5:23)第16変奏-17変奏(4:09)第18変奏(3:19)第19変奏-24変奏(5:28)
Rachmaninov パガニーニの主題による変奏曲〜タマーシュ・ヴァーシャリ(p)/ユリ・アーロノヴィッチ/ロンドン交響楽団(1976年)・・・2014年に拝聴記録有。Vasary Tamas(1933-洪牙利→瑞西)は晩年指揮にも手を染めていた名ピアニスト。駅売海賊盤時代よりお気に入りでした。Chopinもステキな出来でしたよ。この作品は屈指の甘い旋律を誇る名曲、清潔なタッチにしっとり歌って、テクニックに曖昧さがない。Yuri Ahronovitch(1932-2002露西亜)も雰囲気たっぷり、ロンドン交響楽団のキレあるバックも文句なし。音質もリアルに優秀でした。第1-6変奏(3:34)第7-10変奏(3:16)第11-15変奏(5:23)第16変奏-17変奏(4:09)第18変奏(3:19)第19変奏-24変奏(5:28)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
数日前の節分をすっかり失念しておりました。だから業務スーパーに巻き寿司がいっぱいあったのか・・・これからこの冬一番の寒気が押し寄せて、日本海側は大雪予想、こちら太平洋側も寒くなることでしょう。先日Dr.Stretchの効果もぼちぼち切れて、幸い左肩の違和感は消えたまま、朝一番いつもの洗濯、ストレッチ、YouTubeエアロビクス済ませて市立体育館へ。ここ最近トレーニングルームは空いていて、いつもの常連メンバーは少なめ。お忙しいのか、それともインフルエンザにでも罹患したのか、幸い自分はなんとか流行り病ウィルス関係には侵襲されていないと思うけれど、体調は微妙によろしくない。手抜きなし、いつも通りの筋トレ+エアロバイクをしっかりこなしました。鍛錬中記憶を辿って食材の在庫から夕食メニューを考えておりました。買い物には寄っておりません。今朝の体重は68.0kg。危険水域から逃れられない。婆さんの調子よろしくないようで、女房殿はまた泊まりへ。
「大阪万博」チケット転売続出。チケット屋さんでは買取価格3,000円とか、前売り定価の半額以下、これは逆ダフ屋状態じゃないか。前売りは目標の半分らしいけれど、おそらくそれは協賛企業が買い取ったもの、それが流出しているんでしょう。どう考えたって、高いカネ払って人混みに長蛇の列作っても夢や新しい情報は得られませんよ、今時。50年前の発想は時代錯誤。現在は情報も娯楽も溢れていて、万博行くならUSJのほうが楽しいかも、若い世代はきっとそう考えることでしょう。きっと大赤字に至って工事を請け負った業者が儲かっただけ、そんな結末になるでしょう。効率の悪い景気対策でっせ。
64歳孤高を守っている爺友は「楽しみにしている」とのこと。そんな方もいらっしゃることでしょう。半世紀前の夢と希望を経験された方は概ね身体が動かぬ年齢に至ったり、鬼籍に入ったはず。
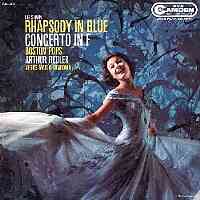 Gershwin ラプソディ・イン・ブルー(1935年)/ピアノ協奏曲へ調(1940年)/ストライク・アップ・ザ・バンド〜ヘスス・マリア・サンロマ(p)/アーサー・フィードラー/ボストン・ポップス管弦楽団・・・Jesus Maria Sanroma(1902-1984波多黎各)は若い頃亜米利加に活躍して、この時期ボストン交響楽団の公式ピアニストだったそう。1950年母国に帰国して後進の指導にあたったとのこと、ステレオ時代の録音もいくつか見かけました。SP復刻ですか?これは驚異の音質!とくにラプソディがいっそうよろしい感じ。かなり奔放に自在な装飾音も加わって疾走するカット有版、収録時間の都合でしょうか。細部かなり粗い演奏もテクニック不足という風情じゃなくて、緻密さよりノリノリの勢い重視したのでしょう。(13:44)大人気のBoston Pops Orchestraは1885年創設なんですね。Arthur Fiedle(1894ー1979亜米利加)は1930年から亡くなる迄常任指揮者、21世紀の現在に至って現役音源がたくさん残ります。
Gershwin ラプソディ・イン・ブルー(1935年)/ピアノ協奏曲へ調(1940年)/ストライク・アップ・ザ・バンド〜ヘスス・マリア・サンロマ(p)/アーサー・フィードラー/ボストン・ポップス管弦楽団・・・Jesus Maria Sanroma(1902-1984波多黎各)は若い頃亜米利加に活躍して、この時期ボストン交響楽団の公式ピアニストだったそう。1950年母国に帰国して後進の指導にあたったとのこと、ステレオ時代の録音もいくつか見かけました。SP復刻ですか?これは驚異の音質!とくにラプソディがいっそうよろしい感じ。かなり奔放に自在な装飾音も加わって疾走するカット有版、収録時間の都合でしょうか。細部かなり粗い演奏もテクニック不足という風情じゃなくて、緻密さよりノリノリの勢い重視したのでしょう。(13:44)大人気のBoston Pops Orchestraは1885年創設なんですね。Arthur Fiedle(1894ー1979亜米利加)は1930年から亡くなる迄常任指揮者、21世紀の現在に至って現役音源がたくさん残ります。
ピアノ協奏曲へ調もかなり良好な音質。二管編成+打楽器8種従えて、よりクラシックな体裁を整えた傑作!ソロも前曲よりていねいな仕上げに細部描き込んで、遊びや装飾音は少なめにしっかりとした技巧、アツい勢いは文句なし。
第1楽章「Allegro moderato - Cantabile - Poco meno scherzando」始まりはいかにもアメリカンな物憂い旋律から、やがてチャールストンが踊ってノリノリ。(11:56)
第2楽章「Andante con moto」出足のトランペットからブルースの色濃い、気怠い風情も妖しく盛り上がる緩徐楽章。ソロも管弦楽も雰囲気たっぷり。(10:44)
第3楽章「Allegro con brio」疾走するアツく、上機嫌なフィナーレ。ソロの細かい音型連続も管弦楽と息がぴったり、速めてのテンポに疾走します。上手いオーケストラですよ。(5:46)
Strike Up the Bandは詳細情報がわからない。フィードラーは幾度も録音している元気のよろしい管弦楽、最初の録音と類推します。(2:25)
ついでにGershwin ラプソディ・イン・ブルー〜ミッシャ・スポリアンスキー(p)/ジュリアン・フース/彼のバンド(1927年)拝聴・・・Mischa Spoliansky(1898-1985独逸→英国)は映画音楽の作曲家として活躍したらしい。Julian Fuhsは(189-1975独逸→亜米利加)。Wiki情報を眺めるとこれは欧州初の「ラプソディ」録音らしい。SP復刻はこれも驚異的音質、あちこちばっさりカットはある短縮版だけれど、ノリノリの技巧に支えられてこれも楽しい演奏でした。伴奏はGrofe編の大管弦楽団に非ず、ジャズバンド風でした。(8:21)
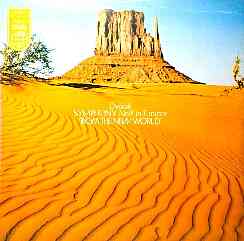 Dvora'k 交響曲第9番ホ短調「新世界より」〜ニコライ・アノーソフ/ソヴィエット国立交響楽団(1960年頃)・・・Nikolai Anosov(1900-1962露西亜)はロジェストヴェンスキーの親父さん、写真を見るとクリソツなのは当たり前。スリーヴ裏の1947年録音は誤表記、立派なステレオでした。やや曇っているけれど、旧ソヴィエットの録音としては出色の臨場感と解像度、期待通りのパワフルな金管炸裂!ちょっと時代を感じさせる大仰なテンポの揺れは頻繁、アンサンブルはびくともしない、凄いオーケストラの技量を堪能できます。物凄いローカルに泥臭い、表情豊かな演奏なんだけど「これでいいのだ!文句あるか」的、あまりに自信に溢れた濃厚パワフルな推進力や爆発には妙な説得力たっぷり。第1楽章「Adagio - Allegro molto」提示部繰り返しもこの時期としては珍しいかも。第2楽章「Largo」はやや速めのテンポに楚々とした深い哀しみが漂う。第3楽章「Scherzo」も怒涛の進撃と迫力。第4楽章「Allegro con fuoco」は次々と表情を変えて、笑ってしまうほど頻繁なテンポの揺れはかつて経験したことはない。ソヴィエット国立交響楽団は優秀でしたよ。(11:14-11:09-7:25-10:38)
Dvora'k 交響曲第9番ホ短調「新世界より」〜ニコライ・アノーソフ/ソヴィエット国立交響楽団(1960年頃)・・・Nikolai Anosov(1900-1962露西亜)はロジェストヴェンスキーの親父さん、写真を見るとクリソツなのは当たり前。スリーヴ裏の1947年録音は誤表記、立派なステレオでした。やや曇っているけれど、旧ソヴィエットの録音としては出色の臨場感と解像度、期待通りのパワフルな金管炸裂!ちょっと時代を感じさせる大仰なテンポの揺れは頻繁、アンサンブルはびくともしない、凄いオーケストラの技量を堪能できます。物凄いローカルに泥臭い、表情豊かな演奏なんだけど「これでいいのだ!文句あるか」的、あまりに自信に溢れた濃厚パワフルな推進力や爆発には妙な説得力たっぷり。第1楽章「Adagio - Allegro molto」提示部繰り返しもこの時期としては珍しいかも。第2楽章「Largo」はやや速めのテンポに楚々とした深い哀しみが漂う。第3楽章「Scherzo」も怒涛の進撃と迫力。第4楽章「Allegro con fuoco」は次々と表情を変えて、笑ってしまうほど頻繁なテンポの揺れはかつて経験したことはない。ソヴィエット国立交響楽団は優秀でしたよ。(11:14-11:09-7:25-10:38)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
インフルエンザに寝込んでいる下の孫(3歳)の動画がLINEに届いて「誰に会いたいの?」「じいじとばあば」〜息子が云わせたんやろけど、爺婆をとろけさすには充分な衝撃。自分は孫には昨年2024に年4-5回しか会っていないけれど、年末両親の忘年会に泊まり込んで終わりなきバトルに疲れ果てた翌朝、下の孫が寝ているうちに御暇(おいとま)して、目覚めたあとで怒っていたそう。その記憶が鮮明なのでしょうか。息子宅は二時間の距離、あまり日常接していないけれど、これが当たり前の孫との関係かと思ったら大間違い! いつも呑んでいる爺友は孤高を保って独り身(珍しい苗字の墓をどうするのか?嫁に出た姉に責められているそう)もう一人はせっかく孫ができたけれど息子は離婚、小学校入学にランドセルは送ったけれどふだん交流はないそう。
経緯はわからぬけれど「嫁に縁を切られた」そんな悩みを抱える記事も拝見しました。それは長い過去の積み重ねなのでしょう。一方の言い分だけではなんとも云々できません。
昨日朝も冷えて、地面は濡れておりました。洗濯、ストレッチ、YouTubeスワイショウ(用手→実際は用に似た変わった漢字)とは中国の気功の一種とのこと、それを15分済ませて、野菜とチーズを入手に業務スーパーに出掛けました。我が街の業務スーパーは定番切れが多くて、前回も珈琲フレッシュが切れている!今回は愛用のピーナツ(100圓也)がない。相変わらずクソ高い野菜など少々入手して、店を出てしばらく、ベビーチーズ購入失念を思い出しました。仕方がなく途中の(やや高級)スーパーに寄ったらQBB4Pが155圓!数年前の記憶では100圓が相場、物価上昇はここ数年でどんだけ?庶民は嘆息するばかりですよ。これでいちおう1日分の運動量は確保できました。今朝の体重は68.05kgほぼ変わらず高め安定中。
 Bartok 管弦楽のための協奏曲〜ヘルベルト・カラヤン/フィルハーモニア管弦楽団(1952年)・・・三管編成+ティンパニ+6種の打楽器+ハープ2台、1944年初演(クーセヴィツキー)わかりやすい作風は作曲者最晩年の傑作。カラヤン40歳代壮年の気力も体力も充分な演奏、音質かなり良好、フィルハーモニア管弦楽団の明晰なアンサンブルにも驚かされました。カラヤンの表現は耳辺りよろしくスムースだけど、後年の粘着質レガート表現に未だ至らない。
Bartok 管弦楽のための協奏曲〜ヘルベルト・カラヤン/フィルハーモニア管弦楽団(1952年)・・・三管編成+ティンパニ+6種の打楽器+ハープ2台、1944年初演(クーセヴィツキー)わかりやすい作風は作曲者最晩年の傑作。カラヤン40歳代壮年の気力も体力も充分な演奏、音質かなり良好、フィルハーモニア管弦楽団の明晰なアンサンブルにも驚かされました。カラヤンの表現は耳辺りよろしくスムースだけど、後年の粘着質レガート表現に未だ至らない。
第1楽章「Introduzione(序章)」旋律の歌わせ方、構成が上手いのはもちろんだけど、颯爽と筋肉質ストレートな勢いが魅力。オーケストラは明るい響きに各パート存在感を主張します。(9:44)
第2楽章「Presentando le coppie(対の提示)」印象的な小太鼓のリズムから、ファゴットのとぼけた音色から各木管が次々に旋律を歌う(これが素晴らしく上手い)スケルツォ風のところ。リズミカルに軽妙な統率はけっこうノリノリでした。金管による中間部のコラールは荘厳でした。対旋律のパートもよく浮き立って効果的なところ。(5:44)
第3楽章「Elegia(悲歌)」ここは夜の歌、妖しい木管の遣り取りは「青ひげ公の城」を連想させるとのこと。(なるほど/Wikiより)途中悲痛な叫びは第1楽章の主題を踏襲したものに聞こえて、アクセントも明晰です。(7:58)
第4楽章「Intermezzo interrotto(中断された間奏曲)」木管によるとぼけた始まりと、雄弁勇壮な弦の歌の対比が印象的。途中Shostakovich「レニングラード」が引用され、トロンボーンのブーイングと木管楽器の嘲笑が入る(Wikiより)ラストあたりのフルート先頭に木管が素晴らしい技量を発揮します。(4:24)
第5楽章「Finale(終曲)」ホルンのぶちかましから、弦がモウレツなスピードで疾走して、ここはオーケストラの腕の見せ所。カラヤンは速めのテンポに息も付かせぬ勢いに疾走、弦の縦線がピタリと合うのはもちろん、木管も金管も自分の出番をみごとにクリアして楽勝、華やかに全曲を締め括りました。(9:11)
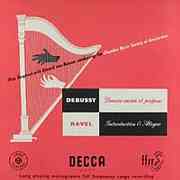 Debussy 神聖な舞曲と世俗的な舞曲/Ravel 序奏とアレグロ〜ソフィア・ローザ・ベルグハウト(hp)/エドゥアルド・ファン・ベイヌム/アムステルダム室内音楽協会(1950年頃)・・・Sophia Rosa Berghout (1909-1993阿蘭陀)は著名なハーピストだったらしい。20世紀に代表的な妖しい魅惑のハープ名曲揃えて、音質は時代相応。こんなデリケートな作品はもっと状態のよろしい音質で聴いたほうが細部わかりやすいから、これは忘れられた音源でしょう。アルカイックな微笑みを湛えたDebussyも、知的に哀しいRavelもセピア色に黄昏れて、オーケストラも雰囲気たっぷりに華麗に夢見るようなハープの舞を堪能できました。(9:37-10:27)これは10インチのLP復刻らしくて贅沢収録、
Debussy 神聖な舞曲と世俗的な舞曲/Ravel 序奏とアレグロ〜ソフィア・ローザ・ベルグハウト(hp)/エドゥアルド・ファン・ベイヌム/アムステルダム室内音楽協会(1950年頃)・・・Sophia Rosa Berghout (1909-1993阿蘭陀)は著名なハーピストだったらしい。20世紀に代表的な妖しい魅惑のハープ名曲揃えて、音質は時代相応。こんなデリケートな作品はもっと状態のよろしい音質で聴いたほうが細部わかりやすいから、これは忘れられた音源でしょう。アルカイックな微笑みを湛えたDebussyも、知的に哀しいRavelもセピア色に黄昏れて、オーケストラも雰囲気たっぷりに華麗に夢見るようなハープの舞を堪能できました。(9:37-10:27)これは10インチのLP復刻らしくて贅沢収録、
この音源をネットから保存した時に同時入手したのは
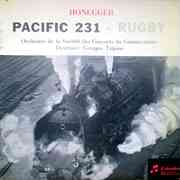 Honegger 交響的運動「ラグビー」/交響的運動「パシフィック2-3-1」〜ジョルジュ・ツィピーヌ/パリ音楽院管弦楽団(1953-57年)・・・前者はラグビーのフォーメーションを、後者は蒸気機関車の疾走を描写した名曲!ちょっとヒステリックなだけど低音も効いて音質かなり良好。パワフルなスポーツマンの動きや、当時の文明の利器であった蒸気機関車の馬力が目に浮かぶほど、破壊的に躍動するパワフルな表現に名曲を実感いたました。(7:44-6:20)
Honegger 交響的運動「ラグビー」/交響的運動「パシフィック2-3-1」〜ジョルジュ・ツィピーヌ/パリ音楽院管弦楽団(1953-57年)・・・前者はラグビーのフォーメーションを、後者は蒸気機関車の疾走を描写した名曲!ちょっとヒステリックなだけど低音も効いて音質かなり良好。パワフルなスポーツマンの動きや、当時の文明の利器であった蒸気機関車の馬力が目に浮かぶほど、破壊的に躍動するパワフルな表現に名曲を実感いたました。(7:44-6:20)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
週末も好天だけど冷えて、夜半にはちょっぴり降ったのか。昨日は久々の女房殿と朝食後、洗濯物は大量、ストレッチしてYouTube「おすすめダイエット運動 お腹・太もも・腕を細く引き締める簡単エクササイズ」一緒に実施、土曜の朝一番に知り体育館を目指しました。トレーニングルームはやはり人数少なめ、ひとりデッド・リフトのスキンヘッド兄さんがバーベルを下ろす音がうるさい! 道具の扱いが乱暴なのは言語道断です。自分は悠々といつも通りのMy 筋トレメニュー+エアロバイク15分消化して体調を整えました。食材買い物には寄っておりません。今朝の体重は68.1kg▲400gまだまだ危険水域中。
「ペコりん【実家片付け】Ch/クセ強めの90歳一人暮らし父=じっちゃんが住む実家がゴミ屋敷に戻らないように娘の私が定期的に片づけに通っています」偶然に拝見した動画はツッコミどころ満載。90歳の爺さんは奥様を20年ほど前に亡くされて独り暮らし、二人の娘さんが定期的に掃除をしてくださるのも愛されている証拠でしょう。とても元気であり、活発に外出し、人々との交流もあり、経済的にも余裕がありそう。別にとくべつな主張とか、ためになる教訓じゃない、ご老人の暮らしぶりと清掃のようすを、けっこう共感をもって眺めている方はいらっしゃると思われます。世代故か、それとも年齢を重ねるとそうなるのか、とにかく捨てられない。巨大な太い針金オブジェを拾ってきたり、ポケットティッシュとかお手拭きとか溜め込んで、健康サプリメントは袋を開けて品質保持期限ニ年超過したものごろごろ出現(シルバー世代はそんなのが好きなのか、たくさんCMが流れます)冷蔵庫も伏魔殿状態〜大学に進学する孫と同居するためにゴミ部屋清掃に着手するとのこと。きっと孫にも愛されているやろなぁ、タイヘンだけどどこかほのぼのとして応援したい・・・これがYouTubeドキュメンタリーの醍醐味、絶対にテレビ番組にはならんでしょう。
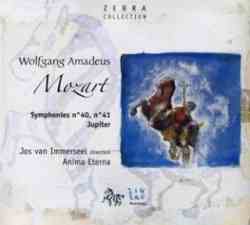 Mozart 交響曲第41番ハ長調K.551「ジュピター」/ファゴット協奏曲 変ロ長調K.191(K. 186e)〜ジョス・ファン・インマゼール/アニマ・エテルナ/ジェーン・ガワー(fg)(2001年)・・・写真は作品組み合わせの違うもの。Jos van Immerseel(1945-白耳義)は古楽器演奏に大きな成果を残して、昨年2024年アニマ・エテルナより馘首されたとのこと。37年という時間と高齢に至ってノーミソが硬くなったのか。先日の某大御所ヴェテラン・フリーアナウンサーみたいなものか。これは未だ意欲的な演奏が話題になっていた頃の代表的な録音でした。
Mozart 交響曲第41番ハ長調K.551「ジュピター」/ファゴット協奏曲 変ロ長調K.191(K. 186e)〜ジョス・ファン・インマゼール/アニマ・エテルナ/ジェーン・ガワー(fg)(2001年)・・・写真は作品組み合わせの違うもの。Jos van Immerseel(1945-白耳義)は古楽器演奏に大きな成果を残して、昨年2024年アニマ・エテルナより馘首されたとのこと。37年という時間と高齢に至ってノーミソが硬くなったのか。先日の某大御所ヴェテラン・フリーアナウンサーみたいなものか。これは未だ意欲的な演奏が話題になっていた頃の代表的な録音でした。
仰ぎ見るような威容を誇る「ジュピター」は親密、第1楽章「Allegro vivace」からノンヴィヴラートの弦、素朴な木管、マイルドな金管にいかつい風情はありません。提示部繰り返し有。粗野なティンパニの存在際立って、艶消しの風情に好感を抱きました。(10:39)
第2楽章「Andante cantabile」速めのテンポ、浮き立つようなリズムを感じさせる緩徐楽章。 (8:29)
第3楽章「Menuetto (allegro-trio)」ここも快速テンポ、素っ気ないほどヴィヴィッドなリズム感。(4:01)
第4楽章「Molto allegro」デリケートな「ジュピター音型」は力みのないフィナーレが始まりました。粗野なティンパニのアクセントに、各パートの存在感が浮き立って馴染の旋律は新鮮、繰り返し有。ラストのフーガのホルンもずいぶんとジミな音色、自分の嗜好は古楽器ですよ。(11:29)
ユーモラスに闊達なファゴット協奏曲。Jane Gowerは著名な古楽器演奏家とのこと。第1楽章「Allegro」からソロは思いっきりジミな音色、きっと取り扱いの難しい楽器、ちょっぴり自信なさげに素朴な風情もなかなか味わいあるもの。伴奏は軽快軽妙そのもの。(6:50)第2楽章「Andante ma adagio」緩徐楽章の牧歌的なリズム感最高。(6:27)第3楽章「Rondo (tempo di menuetto)」ノンビリとした控えめな風情が趣味わい深い演奏でした。(4:18)
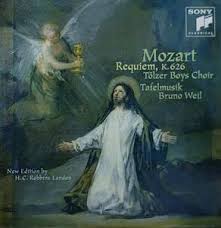 Mozart レクイエムニ短調K.629(ランドン版)〜ブルーノ・ヴァイル/ターフェルムジーク・バロック管弦楽団/テルツ少年合唱団/マリーナ・ウレヴィツ(s)/バルバラ・ヘルツル(ms)/イェルク・ヘリング(t)/ハリー・ヴァン・デル・カンプ(b)(1999年)・・・深い哀しみに充ちた不朽の名作。「Dies iraeからConfutatisまでの楽曲はアイブラーの補筆を全面的に採用し、そこにランドンがさらに補筆した。その他の楽曲はすべてジュスマイヤー版通り」がRobbins Landon(1926ー2009亜米利加)版とのこと(勝手にネットより引用/正直ナニ言ってるんだか?状態)これは極上の古楽器アンサンブル+声楽も充実。Bruno Weil(1949-独逸)はオペラ畑と古楽器演奏が主たる活躍どころとのこと。このレクイエムは特異な楽器編成でして、声楽+バセットホルン2/ファゴット2/トランペット2/トロンボーン3/ティンパニ/弦五部/オルガン、つまりフルート、オーボエなどあるべき基本が編成から抜けていて、それは依頼主の演奏都合だったそう。ここでは声楽と器楽アンサンブルのバランス、各パートの存在感、声楽へのオブリガートなど分離があまりにみごとに際立つ優秀録音。速めのテンポ、小編成の古楽器は控えめにジミな音色だけどデリケートに安定した技巧、素直な表情の声楽、スッキリとした清潔な響きに楚々とした哀しみが表現されました。リズムはヴィヴィッド( Rex tremendae「恐るべき御稜威の王」や「Domine Jesu」辺り)深い感銘をいただきました。旧来の思い入れに重い、濃厚な演奏はしばらくご遠慮しておきましょう。
Mozart レクイエムニ短調K.629(ランドン版)〜ブルーノ・ヴァイル/ターフェルムジーク・バロック管弦楽団/テルツ少年合唱団/マリーナ・ウレヴィツ(s)/バルバラ・ヘルツル(ms)/イェルク・ヘリング(t)/ハリー・ヴァン・デル・カンプ(b)(1999年)・・・深い哀しみに充ちた不朽の名作。「Dies iraeからConfutatisまでの楽曲はアイブラーの補筆を全面的に採用し、そこにランドンがさらに補筆した。その他の楽曲はすべてジュスマイヤー版通り」がRobbins Landon(1926ー2009亜米利加)版とのこと(勝手にネットより引用/正直ナニ言ってるんだか?状態)これは極上の古楽器アンサンブル+声楽も充実。Bruno Weil(1949-独逸)はオペラ畑と古楽器演奏が主たる活躍どころとのこと。このレクイエムは特異な楽器編成でして、声楽+バセットホルン2/ファゴット2/トランペット2/トロンボーン3/ティンパニ/弦五部/オルガン、つまりフルート、オーボエなどあるべき基本が編成から抜けていて、それは依頼主の演奏都合だったそう。ここでは声楽と器楽アンサンブルのバランス、各パートの存在感、声楽へのオブリガートなど分離があまりにみごとに際立つ優秀録音。速めのテンポ、小編成の古楽器は控えめにジミな音色だけどデリケートに安定した技巧、素直な表情の声楽、スッキリとした清潔な響きに楚々とした哀しみが表現されました。リズムはヴィヴィッド( Rex tremendae「恐るべき御稜威の王」や「Domine Jesu」辺り)深い感銘をいただきました。旧来の思い入れに重い、濃厚な演奏はしばらくご遠慮しておきましょう。
Introit: Requiem aeternam(Chorus/4:15)Kyrie eleison(Chorus/2:19)Tuba mirum (Soprano, Alto, Tenor, Bass/1:53)Rex tremendae majestatis(Chorus/3:08)Jesu pie(Soprano, Alto, Tenor, Bass/1:37)Confutatis maledictis (Chorus/4:00)Confutatis maledictis(Chorus/2:16)Lacrimosa dies illa(Chorus/4:29)Domine Jesu Christe (Chorus/3:29)Hostias et preces(Chorus/3:33)Sanctus(Chorus/1:32)Benedictus(Soprano, Alto, Tenor, Bass/4:41)Agnus Dei(Chorus/3:22)Lux aeterna(Soprano, Chorus/5:00)
2025年2月某日/●隠居生活もやや馴染みつつある日々
2月の声を聞いてちょっぴり気温は上がる時期があっても、まだまだ寒い日々は続くそう。日々あまりにヒマ、外は寒いし出掛ける意欲も用事もなし、気分は落ち込むばかり。テレビやYouTubeを眺めてもまったく興味が持てないものばかり。ま、我流ストレッチとYouTube鍛錬はなんとかこなして、あとは無為無策ぼんやり過ごしました。なんとかせんとあかんなぁ、こんな生活。
夕方、女房殿ご帰還。婆さんの腰っ骨圧縮骨折はそれなりに固まったとのこと。夜の付き添いはお役御免になりました。久々、暖かいちゃんとした夕食を摂りました。独りだと粗食をダラダラ喰ってしまって、栄養のバランスや量の加減はよろしくない。体重は68.5kg+450g最悪の2月幕開け。
ヲタク話だから誰も興味ないと思うけれど、毎日聴く音楽音源ファイルは圧縮ファイル(フリーソフトExplzh使用)それを閲覧モードにして再生しております。これが最近おかしい。例えばMahlerの交響曲全集をまとめて圧縮保存してあるけれど、第1番〜第6番迄しか表示されない。残り第7番〜第10番+情報画像ファイルなどが消えております。ファイルサイズは変わらないから、閲覧できないだけか、圧縮解凍ソフトを変えれば解決するのか、当面全部解凍して(すると隠れていたファイルは出現することもある)二分割三分割して各々圧縮し直す作業を続けております。・・・しかしなぁ、なんで突然見えなくなる症状に至ったのか。コンピューター本体の動きが微妙に最近重いのは気になります。3年ほど前中古入手した11年選手、毎日酷使してますから。
その対策についてネットに検索したら、4gbを超えるファイルサイズは表示されないことがあるそう。解決策としてエクスプローラーで開いたら・・・無事、隠れていたファイルは出現しました。これからは大きな圧縮ファイルはそれで開いたら解決するのですね。
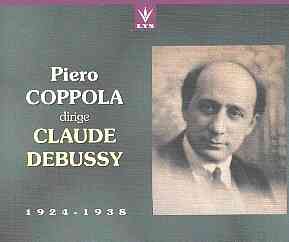 Debussy/Busser編 小組曲(1930年)/二つのアラベスク(リュシアン・シュワァルツ(v)/ピエロ・コッポラ(p)/1927年)/Ravel編 スティリー風タランテラ(1932年)/Durand編「喜びの島」(1929年)/Durand編「グラダナの夕べ」「妖精は良い踊り子」/Caplet編「こどもの領分」(1934年)/フランソワ・ヴィヨンによる3つのバラードより2曲(シャルル・パンゼラ(br)/1931年)〜ピエロ・コッポラ/パリ音楽院管弦楽団・・・驚異の音質。この時期にして作品演奏個性を堪能するのにほとんど不足を感じさせません。Piero Coppola(1888-1971伊太利亜)は1924-1934年辺り仏蘭西に活躍し、その後は瑞西にて作曲に励んだそう。「二つのアラベスク」はヴァイオリン編曲だけど、他すべてコッポラの管弦楽演奏。著名な人気作品はどれも夢見るように美しい旋律ばかり、パリ音楽院管弦楽団は色彩豊かに気怠い、まるで昔の映画のようにセピア色の風情が続きました。どれも編曲?とは感じさせぬ、魅力たっぷり。「バラード」は仏蘭西語の響きの美しさ妖しさ堪能いたしました。(意味はワカランけど)
(3:21-3:06-2:49-3:20/3:19-3:23/4:35/4:52/4:48/4:30/2:17-2:48-4:30-2:17-2:48-2:35/2:20-2:37)
Debussy/Busser編 小組曲(1930年)/二つのアラベスク(リュシアン・シュワァルツ(v)/ピエロ・コッポラ(p)/1927年)/Ravel編 スティリー風タランテラ(1932年)/Durand編「喜びの島」(1929年)/Durand編「グラダナの夕べ」「妖精は良い踊り子」/Caplet編「こどもの領分」(1934年)/フランソワ・ヴィヨンによる3つのバラードより2曲(シャルル・パンゼラ(br)/1931年)〜ピエロ・コッポラ/パリ音楽院管弦楽団・・・驚異の音質。この時期にして作品演奏個性を堪能するのにほとんど不足を感じさせません。Piero Coppola(1888-1971伊太利亜)は1924-1934年辺り仏蘭西に活躍し、その後は瑞西にて作曲に励んだそう。「二つのアラベスク」はヴァイオリン編曲だけど、他すべてコッポラの管弦楽演奏。著名な人気作品はどれも夢見るように美しい旋律ばかり、パリ音楽院管弦楽団は色彩豊かに気怠い、まるで昔の映画のようにセピア色の風情が続きました。どれも編曲?とは感じさせぬ、魅力たっぷり。「バラード」は仏蘭西語の響きの美しさ妖しさ堪能いたしました。(意味はワカランけど)
(3:21-3:06-2:49-3:20/3:19-3:23/4:35/4:52/4:48/4:30/2:17-2:48-4:30-2:17-2:48-2:35/2:20-2:37)
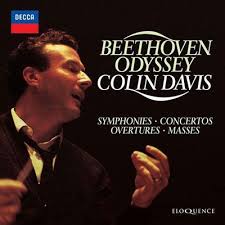 Beethoven 交響曲第3番変ホ長調「英雄」/序曲「コリオラン」(1970年)/序曲「レオノーレ」第1番(1971年)〜コリン・デイヴィス/BBC交響楽団・・・貧しい苦学生から巨匠に上り詰めたColin Davis(1927-2013英国)も亡くなってもう10年以上経ったのですね。後のドレスデンとの全集録音前、1960-70年代にPHILIPSに録音したBBC交響楽団/ロンドン交響楽団と第1-8番迄録音+第9番はバイエルン放送交響楽団(1985年)を加えて全曲録音が揃います。ちなみに序曲、ピアノ協奏曲/ヴァイオリン協奏曲の録音も有。数年前交響曲第1番/第2番(1975年)を聴いて、その質実に落ち着いた響きと、オーソドックスな表現に感銘を受けておりました。PHILIPSの中低音が充実した録音も魅力的。
Beethoven 交響曲第3番変ホ長調「英雄」/序曲「コリオラン」(1970年)/序曲「レオノーレ」第1番(1971年)〜コリン・デイヴィス/BBC交響楽団・・・貧しい苦学生から巨匠に上り詰めたColin Davis(1927-2013英国)も亡くなってもう10年以上経ったのですね。後のドレスデンとの全集録音前、1960-70年代にPHILIPSに録音したBBC交響楽団/ロンドン交響楽団と第1-8番迄録音+第9番はバイエルン放送交響楽団(1985年)を加えて全曲録音が揃います。ちなみに序曲、ピアノ協奏曲/ヴァイオリン協奏曲の録音も有。数年前交響曲第1番/第2番(1975年)を聴いて、その質実に落ち着いた響きと、オーソドックスな表現に感銘を受けておりました。PHILIPSの中低音が充実した録音も魅力的。
古典的二管編成+ティンパニによる巨大なる浪漫の幕開けを飾る傑作!「英雄」はコリン・デイヴィス43歳壮年の記録。
第1楽章「Allegro con brio」から地に足付いた落ち着いた歩み、中庸のテンポにBBC交響楽団はエエ感じに艶消しにジミな響きと適度な力感。走ったり焦ったりとは無縁に、噛み締めるように落ち着いた始まり。提示部繰り返しはありません。ホルンの素直にマイルドな音色は独墺系との違いを感じさせます。(15:44)
第2楽章「Marcia funebre: Adagio assai」神妙な葬送行進曲は暗鬱に重く大仰な表情を強調しない。力まず質実マイルドな抑制が続きました。(16:44)
第3楽章「Scherzo: Allegro vivace」蒸気機関車のようなスケルツォも急がない。あまり重くなくむしろ軽快な流れの良さ、ホルン重奏の明るい響きも個性でしょう。(6:15)
第4楽章「Finale: Allegro molto」怒涛の迫力になだれ込むフィナーレの始まりも抑制が効いております。堂々たる変奏曲はちょっとおとなし過ぎ、力感と勢いに足りないと感じつつ、素直に朗々たるホルンを契機に最終盤には満足できるクライマックスが待っておりました。(12:39)
「コリオラン」パワフルに悲劇的な作品(9:00)「レオノーレ」第1番は物語を予感させる流れ、いずれもバランスのよろしい演奏でした。(10:56)