2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
こんどはりそな銀行にサイバー攻撃があったとか。秋田新幹線でも停電があったそう。こちら2024年ラスト大晦日を迎え、昨日もいつもと変わらぬ生活。曇りがちの寒空に朝一番の洗濯は引き続き大量、ストレッチを入念に心掛けたのは右股関節あたりに鈍い痛みを感じたため、原因は不明です。YouTubeエアロビクスは(朝だけど)「夕食後のやさしい有酸素運動/血糖値を下げて疲労回復」15分。呑みに行く云々は空気の冷たさに外出断念、なぜか胃の調子もいまいち。1年分の「音楽日誌」読み返しての振り返り反省にもたっぷり時間が掛かります。女房殿は絶品の味に仕上がった小豆と丹波黒豆を持参して婆さんのもとへ向かいました。冷蔵庫在庫にダイエット食生活も良いけれど、ご近所やや高級スーパーに好きなもの贅沢惣菜入手に出掛けようか・・・そんな考えも寒さに負けてコタツにじっとして終日引き隠り。身体をほとんど動かさないで菓子など喫した結果は体重は67.3kg+300g。本日、一人用おせち到着予定。
前夜「オールスター合唱バトル 冬の名曲&今年のヒット曲を140人が熱唱3時間SP」拝見。これは半年に一回?主にYouTubeに活躍する「ミリオン再生合唱団」が優勝、前回同点優勝した「ミュージカル合唱団」は今回及びませんでした。優勝経験もある「演歌合唱団」、歌唱力では圧倒的な「最強ボーカリスト合唱団」が及ばなかったのは選曲や編曲の仕上げもあったと思います。連続(でしたっけ?)「令和アイドル合唱団」が最下位なのは、ま、アイドルだから仕方がない。いずれ声と心を全力で合わせることの圧倒的な快感、歌うことの喜び、メンバーが愉しんで、熱気が伝わってステキな合唱番組でした。メンバーの仲の良さがよくわかる。年末に佳き番組を拝見しました。
Netflixが凄い。偶然だけどドラマ「僕のヤバい妻」一気拝見(2016年)。初めて見たけれど、これが大傑作! 主演は木村佳乃(恐ろしい/怪しい/頭が良い/美しい)伊藤英明(振り回されるダメ男ぶりが秀逸)相武紗季の愛人役も似合っておりました。筋書きが凝って二転三転して予測不能、脇役も個性豊かに思わぬ役割を果たします。ラストの大どんでん返しにも痺れました。なんせ途切れることなく一気見できるのが精神的によろしく、一週間待たされた挙げ句クソおもろない最近のドラマなど足元にも及ばない。もう一度確認することもできますし。
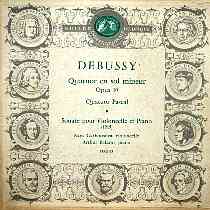 Debussy 弦楽四重奏ト短調(1943年)/チェロ・ソナタ(1947年)~パスカル弦楽四重奏団/ラヤ・ガルボウソヴァ(vc)/アルトゥール・バルサム(p)・・・Quatuor Pascalは1940年代~モノラル時代に活躍活躍した仏蘭西の団体。弦楽四重奏は1893年の作、爛熟した甘い魅惑の旋律を誇る名曲はお気に入りです。録音年代が信じられぬほどの明快な音質。
Debussy 弦楽四重奏ト短調(1943年)/チェロ・ソナタ(1947年)~パスカル弦楽四重奏団/ラヤ・ガルボウソヴァ(vc)/アルトゥール・バルサム(p)・・・Quatuor Pascalは1940年代~モノラル時代に活躍活躍した仏蘭西の団体。弦楽四重奏は1893年の作、爛熟した甘い魅惑の旋律を誇る名曲はお気に入りです。録音年代が信じられぬほどの明快な音質。
第1楽章「Anime et tres decide(活き活きと、きわめて決然として)」悲劇が始まるような劇的な導入。アンサンブルは緊密に、揺れる官能(6:22)
第2楽章「Assez vif et bien rythme(かなり急速に、とてもリズミカルに)」ピチカートが多用されるリズミカルなスケルツォ?とても妖しい風情に変わりはありません。(3:54)
第3楽章「Andantino, doucement expressif(甘く表情豊かに)」切なく官能的なピークを迎える緩徐楽章(8:07)
第4楽章「Tres modere - Tres mouvemente - En animant peu a peu - Tres mouvemente et avec passion(きわめて穏やかに - きわめて躍動して - 少しずつ動きを付けて - きわめて躍動して、かつ情熱的に)」思いっきり気紛れな躍動が続いて、劇的な緊張感が高まりました。(7:28)
チェロ・ソナタは1915年作曲者最晩年の作品。Raya Garbousova(1909-1997卓爾治亜→亜米利加)は初耳チェリスト。Artur Balsam(1906ー1994波蘭→亜米利加)は伴奏の録音が数多い名人。こちらも音質は悪くないけれど、チェロはちょっぴりジミに響きました。
第1楽章「Prologue : Lent(ゆっくりと)」これも遣る瀬ない官能的な旋律。雄弁過ぎぬチェロ。(5:16)
第2楽章「Serenade : Moderement anime(程よく活き活きと)」妖しいピチカートから始まる、自在に蠢くようなセレナーデ?これが。(3:32)
第3楽章「Final : Anime, leger et nerveux - Lento(活き活きと、軽やかに敏感に~緩やかに)」切なさが躍動するような、快活なフィナーレ。(4:09)
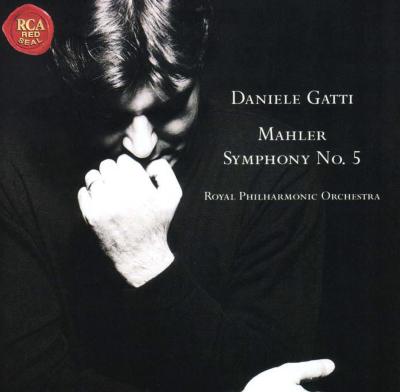 Mahler 交響曲第5番 嬰ハ短調~ダニエレ・ガッティ/ロイヤル・フィル(1997年)・・・2018年来の再聴。Daniele Gatti(1961ー伊太利亜)はコンセルトヘボウを首になって、現在はシュターツカペレ・ドレスデンの首席に復活しているらしい。第4楽章「Adagietto」静謐な官能が大人気な作品、自分は第3楽章「Scherzo」ホルンの躍動が大好きです。発売当時の世評は高く、6年前の自分もロイヤル・フィルの金管を絶賛しておりました。音質はクリアそのもの。これは四管編成+8種の打楽器+ハープという大編成作品、これぞ近現代管弦楽デーハーな精華でしょう。
Mahler 交響曲第5番 嬰ハ短調~ダニエレ・ガッティ/ロイヤル・フィル(1997年)・・・2018年来の再聴。Daniele Gatti(1961ー伊太利亜)はコンセルトヘボウを首になって、現在はシュターツカペレ・ドレスデンの首席に復活しているらしい。第4楽章「Adagietto」静謐な官能が大人気な作品、自分は第3楽章「Scherzo」ホルンの躍動が大好きです。発売当時の世評は高く、6年前の自分もロイヤル・フィルの金管を絶賛しておりました。音質はクリアそのもの。これは四管編成+8種の打楽器+ハープという大編成作品、これぞ近現代管弦楽デーハーな精華でしょう。
第1楽章「Trauemarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt.(正確な速さで。厳粛に。葬列のように)」前作交響曲第4番に出現したトランペット旋律が主役になって冒頭骨太な存在感、カスタマーレビューには「シカゴのハーセスを上回る」などの声もあるけれど、それは音色や個性の違い、嗜好の問題でしょう。たしかにロイヤル・フィルの金管の威力は壮絶。そして36歳当時若手の表現はじっくりたっぷり歌って粘着質に非ず、テンポは動いても清冽雄弁に疾走してパワフル、それは恣意的なものを感じさせぬ有機的な流れと感じます。(13:09)
第2楽章「Sturmisch bewegt. Mit grosster Vehemenz. (嵐のような荒々しい動きをもって。最大の激烈さをもって)」心持ち速めのテンポ、オーケストラは鳴りきって迫力たっぷりに揺れ動くけれど、暴力的な重さに非ず。金管も弦も若々しいエネルギーに充ちて、デリケートな抑制部分も効果的な対比表現でした。(14:18)
第3楽章「Scherzo. Kraftig, nicht zu schnell.(力強く、速すぎずに)」ここが一番好きなところ。明るいホルン・ソロが爽快なスケルツォ楽章。しみじみ上手いもんですよ。優雅なワルツを曖昧さなく歯切れよろしく、しっかりリズムを刻みます。後半の焦ったようなテンポ・アップ、ホルツクラッパーの効果はリアル、それが際立つクリアな音質。(17:23)
第4楽章「Adagietto. Sehr langsam. (非常に遅く)」ここは弦とハープによる躊躇いと官能の吐息。寄せては返す情感の揺れ、肌理細かくもデリケートな仕上げでした。ロイヤル・フィルの弦は洗練されて美しい。(10:13)
第5楽章「Rondo-Finale. Allegro giocoso(アレグロ・楽しげに)」冒頭のホルンは第3楽章とは雰囲気変わって牧歌的。優しい旋律が滑るように進んで、上機嫌なフィナーレが始まりました。ここは前楽章との雰囲気が違い(明る)過ぎて時に違和感のある演奏に出会うこともあるけれど、抑制した表現に移行はスムースでした。快活に清潔なキレを感じさせて、強引さとか力みなき爽やかさが続きました。(15:00)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
アゼルバイジャンにて誤射による航空機墜落。そして韓国にて胴体着陸失敗してほとんどの乗客が死亡とのこと、他人ごとではありません、明日の日本だってあり得ぬ話じゃない。この年末の時期に航空会社へのシステム攻撃があったそうだし。相変わらず幼児乳児虐待のニュースは続いて、胸を痛めております。通販大手ベルーナ年末に到着予定だった、おせち料理約1万5,000件配達不能との報道。悪意はないやろけど、これは消費者も業者側もなんとも切ない事件ですね。物流上の手配ミスらしい。担当はクビでしょう、可哀想に。
いよいよ押し迫る2024年、本日より女房殿は婆さんのところに泊まり込んで年越し準備、自分は不摂生に酒でも呑み行くか?逡巡中。昨日もいつも通り、朝一番に洗濯は大量、フロの残り湯を使い切って足りず二回転、好天に空気は乾燥して風もあったからよく乾きます。ストレッチ+YouTubeエアロビクス「寒さ吹き飛ぶ!!全身ポカポカ有酸素ダンス/エアロビクスで脂肪を燃やそう!」サボりたくなるところを辛くも堪えて実施、そしてウォーキングを兼ねて業務スーパーへ。途中にあるchocoZAPは自転車2台、クルマ2台、つまり正月休みの土曜朝一番に4人以上鍛えて立派!いざ、売り場に到着したら小豆と砂糖のみ購入予定が要らぬもの?いっぱい買ってしまって、肝心の切れていた胡麻油は失念いたしました。
振り返ってちょうど一年前、毎年正月休みに身体が鈍(なま)るのを恐れて、ジョギングや野崎詣りの参道坂道は膝の調子がよろしくないので敬遠、YouTubeのエアロビクスを思いついたもの。いつもはお付き合いしてくださる女房殿の希望もあって短いのを実施、本日より数日間独りなので20-30分しっかり鍛える決意です。おそらく一年で300回以上は実施いたしました。前のめり早足ウォーキングも効果的でしょう。筋トレは一週間ほど休んでも戻せるらしい。もともと肩こり対策程度のユル筋トレですし。今朝の体重は67.0kgほぼ変わらず。
「2024年度上半期(4~9月)の生活保護申請が前年同期比で2.8%増の13万3,274件に上った」(厚生労働省の公表データを共同通信が分析)コロナ支援の縮小+物価高が直撃したとのこと。いつも利用する商品はここ2年ほど10%程度にとどまらぬ値上げ感ありますよ。年の瀬になんとも苦いニュースばかり、物騒な闇バイト?強盗やら無差別刺殺事件、乾燥時期の火災が続いて、せめて2024年正月みたいに大きな天変地異や事故がないことを祈りましょう。
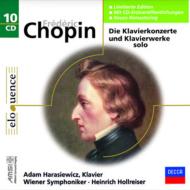 Chopin 即興曲 No.1 A Flat, Op.29/No.2 F Sharp, Op.3/No.3 G Flat, Op.51/No.4 C Sharp Minor, Op.66 Fantaisie/マズルカNo.1 F Sharp Minor/No.2 C Sharp Minor/No.37 A Flat Op.59 No.2/No.51 F Minor Op.68 No.4/No.14 G Minor, Op.2/No.15 C, Op.24 No.2/No.24 C Op.33 No.3/No.34 C, Op.56 No.2/No.35 C Minor, Op.5/No.36 A Minor, Op.59/No.5 B Flat Op.7 No.1/No.6 A Minor Op.7 No.2/No.17 B Flat Minor Op.24 No.4/No.7 F Minor Op.7 No.3/No.22 G Sharp Minor Op.33 No.1/No.29 A Flat Op.41 No.4/No.31 A Flat Op.50 No.2//No.32 C Sharp Minor Op.50 No.3/No.41 C Sharp Minor Op.63 No.3/No.47 A Minor Op.67 No.4~アダム・ハラシェヴィッチ(p)(1959-1972年)・・・Adam Harasiewicz(1932ー波蘭)はご存命中のようです。1955年第5回ショパン・コンクールに優勝してPHILIPSにChopin作品全曲を録音したけれど、その後の活動は意外とローカルな範囲にちょっと忘れられた存在となりました。この一枚は即興曲とマズルカ、十数年の間に各々録音したものを集めて違和感なく、しっとり重心の低い音質に不満はありません。幻想即興曲 変ハ短調 作品66がとくに有名な即興曲集は、きらきら輝いてキレるようなテクニックを期待すると、それはちょっと違う、前のめりにならぬ落ち着きと味わいを感じさせるもの。(4:04-5:00-4:40-5;03)
Chopin 即興曲 No.1 A Flat, Op.29/No.2 F Sharp, Op.3/No.3 G Flat, Op.51/No.4 C Sharp Minor, Op.66 Fantaisie/マズルカNo.1 F Sharp Minor/No.2 C Sharp Minor/No.37 A Flat Op.59 No.2/No.51 F Minor Op.68 No.4/No.14 G Minor, Op.2/No.15 C, Op.24 No.2/No.24 C Op.33 No.3/No.34 C, Op.56 No.2/No.35 C Minor, Op.5/No.36 A Minor, Op.59/No.5 B Flat Op.7 No.1/No.6 A Minor Op.7 No.2/No.17 B Flat Minor Op.24 No.4/No.7 F Minor Op.7 No.3/No.22 G Sharp Minor Op.33 No.1/No.29 A Flat Op.41 No.4/No.31 A Flat Op.50 No.2//No.32 C Sharp Minor Op.50 No.3/No.41 C Sharp Minor Op.63 No.3/No.47 A Minor Op.67 No.4~アダム・ハラシェヴィッチ(p)(1959-1972年)・・・Adam Harasiewicz(1932ー波蘭)はご存命中のようです。1955年第5回ショパン・コンクールに優勝してPHILIPSにChopin作品全曲を録音したけれど、その後の活動は意外とローカルな範囲にちょっと忘れられた存在となりました。この一枚は即興曲とマズルカ、十数年の間に各々録音したものを集めて違和感なく、しっとり重心の低い音質に不満はありません。幻想即興曲 変ハ短調 作品66がとくに有名な即興曲集は、きらきら輝いてキレるようなテクニックを期待すると、それはちょっと違う、前のめりにならぬ落ち着きと味わいを感じさせるもの。(4:04-5:00-4:40-5;03)
マズルカは波蘭特有のリズム(三拍目にアクセントのあるワルツ)をしっかり感じさせて、ピアノはおそらくスタンウェイ?(自信はないけど/作品によって異なるかも)だけど華やかさよりジミな躊躇い風情に揺れてジミジミ。(2:52-2:21-2:18-1:58-2:19-1:58-2:05-1:32-5:27-4:30-2:16-2:47-4:23-2:29-1:36-1:49-2:44-4:42-2:03-2:35)こんなローカルな風情は最近流行らないのでしょう。久々の拝聴に心は落ち着きました。
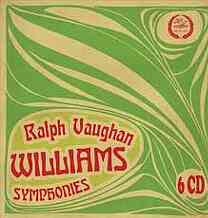 Vaughan Williams 交響曲第8番ニ短調/交響曲第9番ホ短調~ゲンナジ・ロジェストヴェンスキー/ソヴィエット国立文科省交響楽団(1988-89年ライヴ)・・・露西亜風脂っこい、色彩どぎついRVWが聴けるのかと思ったらそんなことはない、意外と端正にまとも、ちゃんとした英国風情の演奏でした。音質はかなり良好と思うけれどソヴィエット露西亜のライヴだから、どうしても評価は甘くなりがち。アンサンブルは優秀。
Vaughan Williams 交響曲第8番ニ短調/交響曲第9番ホ短調~ゲンナジ・ロジェストヴェンスキー/ソヴィエット国立文科省交響楽団(1988-89年ライヴ)・・・露西亜風脂っこい、色彩どぎついRVWが聴けるのかと思ったらそんなことはない、意外と端正にまとも、ちゃんとした英国風情の演奏でした。音質はかなり良好と思うけれどソヴィエット露西亜のライヴだから、どうしても評価は甘くなりがち。アンサンブルは優秀。
交響曲第8番ニ短調は1956年にバルビローリが初演、二管編成だけど5人の奏者による8種の打楽器+チェレスタ+ハープが入ります。
第1楽章「Fantasia (Variazioni senza tema)」主題のない変奏曲とか。ちょっぴり寂しげに木管が歌い交わして時に激昂する(シンバルも入ってなかなかの迫力)牧歌的穏健な幻想曲?なんだそう。自分はこんな鬱蒼として苦い風情も大好きだけど、日本じゃ人気ないやろなぁ。(9:39)
第2楽章「Scherzo alla marcia (per stromenti a fiato)」管楽器のみのスケルツォは妙に辛口な軽妙。なかなか珍しいテイスト、これもユーモアですよ。(3:31)
第3楽章「Cavatina (per stromenti ad arco)」弦のみのこれは絶望的に寂しく、美しい静謐な緩徐楽章。哀愁のヴァイオリン・ソロも切なく、チェロは暗鬱。(8:49)
第4楽章「Toccata」冒頭種々打楽器が怪しい効果を上げて、堂々と落ち着いて勇壮なフィナーレが始まります。金管と打楽器群が絡み合って高揚しつつ終了、この作品大好きですよ。(5:56/拍手有)
ラストの交響曲である交響曲第9番ホ短調の初演は1958年(マルコム・サージェント)三管編成+12種の打楽器+2台のハープ+チェレスタ、かなりの大規模に至っております。この作品はサキソフォーンが聴きもの。ファンである自分でもちょっと難曲と感じます。
第1楽章「Moderato maestoso」劇的に切なく金管が重い足取り、サキソフォーンの音色がとっても怪しい、うねうねとした眉間にシワな始まりは快く盛り上がらない。(10:40)
第2楽章「Andante sostenuto」虚ろに寂しげなフリューゲルホルンのモノローグに始まって、合いの手を入れるオーケストラのリズムも個性的、打楽器も重苦しい。ここも辛口な緩徐楽章でした。(7:40)
第3楽章「Schrzo:Allegro pesante」はグロテスクにスウィングして、巧まざるユーモラスも感じさせる重いスケルツォ。途中3本のサキソフォーンの絡みが幾度もエッチに怪しい。打楽器も盛大に活躍。ロジェストヴェンスキーの表現はなかなか大仰大柄に盛り上がりました。13年前には「魔法使いの弟子」を連想させるとのコメント有。この楽章は傑作!(5:53)
第4楽章「Andante tranquillo」呟くような弦からそっと始まるフィナーレ。それが幻想的に浮遊しつつ、フルート・ハープも加わってゆっくり広がって美しいけれど掴み所がない。やがて荘厳な金管が参入してクライマックス?に迫るけれど、それは力を失いました。ラストに向けて壮絶な締め括りに至るけれど、どうも辛気臭い作品・・・ロジェストヴェンスキーはかなりパワフルですよ。(13:29/拍手有)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
昨日土曜は市立体育館営業最終日。迫る年末も週末もなにも変わらぬ生活、ただ寒い冬というだけ。朝一番に洗濯、そしてYouTubeエアロビクス「10 MIN CARDIO HIIT WORKOUT - ALL STANDING - Full Body, No Equipment, No Repeats」短いのを済ませて寒風の好天の途中、ゴミ拾いの功徳を積みつつ市立体育館へ。マッチョなバーベルメンバーはお休み(一人新顔来訪/いつもはお仕事終わりに来ていると類推)そして週末常連メンバー(例のジャージの上に短パン個性的スタイル爺など)少数、自分よりお姉さん常連女性群は年末年明け準備に忙しいのでしょう、妙齢アスリート女性以外の顔は見えません。マシンは空いていてゆっくり、いつものゆる筋トレ済ませて、エアロバイクはいつもよりちょっぴり強度を上げて15分消化。これにて2024年のトレーニング締め括り完了。一週間お休み。隔日ほぼ皆勤賞、自分で自分を褒めてあげたい(←いったいいつの流行り言葉?)誰も褒めてくれんし。
帰宅してジャンパー、マフラー(いずれも安物)ついでに運動靴も全部洗濯しました。今朝の体重は67.05kg▲100g。思うように減りません。
我が団地には駐車場があって、それは当たり前の風景・・・なんだけど、一台朽ち果てた高級スポーツカー(スープラ?)タイヤも全部パンクしてぺしゃんこ、自分が知る限り転居来3年ほど?ずっとそのまま放置状態。想像だけど、愛車を使っていた方は病気に寝たきりなのかも。駐車料金の負担もタイヘンだろうし、手放したくないクルマならもっとキレイにしたらよいのに。乗らないのなら処分したら~不思議です。ま、人それぞれワケや事情も有、話は違うけれどいつも呑んでいる爺友は亡くなった親父のNHK料金を払い続けているし、空き家になった実家の固定電話もそのまま。ま、既に改装工事完了して転り住むそうだから、それはそれで良いけど。改装後半年、そのまま現在居住アパート継続家賃負担というのが理解できない。
先日のピエール・モントゥーの「幻想」の件に関連して、ごていねいにメールをいただきました。ブログや動画みたいにアクセス状況がほとんどわからない(気にしない)ので読者がいらっしゃる(反応がある)ことがけっこう驚き。そしてありがたい。
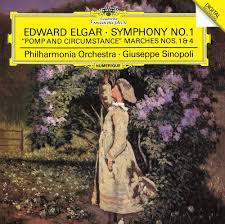 Elgar 交響曲第1番 変イ長調(1990年)/序曲「南国にて(アラッシオ)」(1989年)~ジュゼッペ・シノーポリ/フィルハーモニア管弦楽団・・・いかにも英国!と云った落ち着いた味わいに堂々たる風情の”大きな”交響曲。三管編成+ハープ2台+打楽器はティンパニ他小太鼓大太鼓シンバルも入ります。結論的に茫洋たるスケールにじっくり腰を据えた”大きな”演奏に感銘を受けました。清涼に軽快なサウンドを誇るザ・フィルハーモニアがこのような陰影サウンドも意外、エイドリアン・ボウルト先頭に幾種聴き馴染んだ英国系演奏とはかなりイメージは変わって、うねうねとした色気と雄弁な歌、路線は彼のMahlerと同じでしょう。オーケストラは好調、音質も良好です。
Elgar 交響曲第1番 変イ長調(1990年)/序曲「南国にて(アラッシオ)」(1989年)~ジュゼッペ・シノーポリ/フィルハーモニア管弦楽団・・・いかにも英国!と云った落ち着いた味わいに堂々たる風情の”大きな”交響曲。三管編成+ハープ2台+打楽器はティンパニ他小太鼓大太鼓シンバルも入ります。結論的に茫洋たるスケールにじっくり腰を据えた”大きな”演奏に感銘を受けました。清涼に軽快なサウンドを誇るザ・フィルハーモニアがこのような陰影サウンドも意外、エイドリアン・ボウルト先頭に幾種聴き馴染んだ英国系演奏とはかなりイメージは変わって、うねうねとした色気と雄弁な歌、路線は彼のMahlerと同じでしょう。オーケストラは好調、音質も良好です。
第1楽章「Andante nobilmente e semplice - Allegro」落ち着いた歩みから金管の煽り、劇的な盛り上がりへの持って行き方、デリケートな抑制、詠嘆とタメの対比はみごとでした。冒頭の繰り返しは万感胸に迫ります。(20:41)
第2楽章「Allegro molto」カッコよい進撃の行進はいつになく重量級(7:10)
第3楽章「Adagio」瞑想の緩徐楽章もたっぷり歌って雄弁そのものにセクシー(14:10)
第4楽章「Lento - Allegro」鬱蒼とした序奏から、決然とした主部が疾走してシノーポリの表現は重く、颯爽とした馴染みの英国風に非ず、金管も朗々とたっぷりと寄せては返す”大きな”、決然と情感高まるフィナーレ。自分はワリと好みの演奏でした。(13:17)
伊太利亜への憧れを表現した「南国にて」も、ひたすら高揚し続けて揺れ動き、これほど大仰劇的パワフルな迫力はなかなか経験できないもの。金管が炸裂して爽快!作品イメージを覆す、劇的風情に変貌しておりました。途中夢見るような弦の歌にハープや木管が優しくよりそう対比も感動的。(23:19)
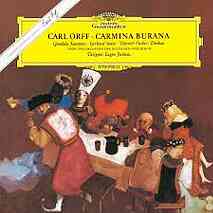 Orff カルミナ・ブラーナ~オイゲン・ヨッフム/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/合唱団/グンドゥラ・ヤノヴィッツ(s)/ゲルハルト・シュトルツェ(t)/ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(br)(1967年)・・・これぞ鉄板!世間ではそうなっているし、自分も幾度聴いているのにサイト内検索に出現しません。
Orff カルミナ・ブラーナ~オイゲン・ヨッフム/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/合唱団/グンドゥラ・ヤノヴィッツ(s)/ゲルハルト・シュトルツェ(t)/ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(br)(1967年)・・・これぞ鉄板!世間ではそうなっているし、自分も幾度聴いているのにサイト内検索に出現しません。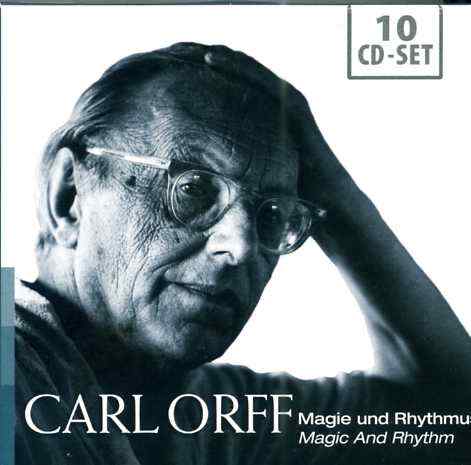 バイエルン放送交響楽団との旧録音(1952年)は聴いていて、その立派な演奏は現在手許にありません。作品との出会いはレオポルド・ストコフスキー(1958年)とってもオモロい、デーハーに輝かしい演奏だけど、あれは各々3回繰り返すところを2回にカットしているんですよね。
バイエルン放送交響楽団との旧録音(1952年)は聴いていて、その立派な演奏は現在手許にありません。作品との出会いはレオポルド・ストコフスキー(1958年)とってもオモロい、デーハーに輝かしい演奏だけど、あれは各々3回繰り返すところを2回にカットしているんですよね。
1936年初演、声楽ソロ3人+合唱+児童合唱+吹奏楽+多種多様盛大なる打楽器+ピアノによる衝撃的なリズムと祝祭的に土俗的な声の節回しがわかりやすく大衆的。とっても賑やかに時にユーモラスな原始の生命エネルギーに充ち溢れた輝かしい声楽作品。これは状態のよろしい音質で聴いたほうが良いに決まっております。声楽各パートの分離と打楽器のキレは臨場感クリアに最高。作品的に煽りまくってテンション高いスケールを誇る作品はEugen Jochum(1902ー1987独逸)の個性にぴったり、明晰にパワフルな演奏。声楽ソロも合唱も端正に表情豊か。音質含めて惚れ惚れするほど、この作品は体調よろしい状態に聴くのが必須でしょう。冒頭とラストに登場する「おお、運命の女神よ」はドラマ・映画・格闘技・スポーツ・ゲームなどに多用されて誰でも知っております。ラストの回帰には泣けますよ。
「運の女神、全世界の支配者なる」1.おお、運命の女神よ (合唱)(2:37)/2.運命の女神の傷手を (合唱)(2:37)
第1部 初春に 3.春の愉しい面ざしが (小合唱)(3:30)/4.万物を太陽は整えおさめる (br独唱)(2:04)/ 5.見よ、今は楽しい (合唱)(2:39)
「芝生の上で」 6.踊り (orchestra)(1:43)/7.森は花さき繁る (合唱と小合唱)(3:02)/8.小間物屋さん、色紅を下さい (大合唱と合唱)(2:59)/9.円舞曲 ここで輪を描いて回るもの (合唱) - おいで、おいで、私の友だち (小合唱)(3:59)/10.たとえこの世界がみな (合唱)(0:53)
第2部 酒場で 11.胸のうちは、抑えようもない (br)(2:16)/12.むかしは湖に住まっていた (tと男声合唱)(3:25)/13.わしは院長さまだぞ (brと男声合唱)(1:31)/14.酒場に私が居るときにゃ (男声合唱)(3:06)
第3部 愛の誘い 15.愛神はどこもかしこも飛び回る (sと児童合唱)(3:04)/16.昼間も夜も、何もかもが (br独唱)(1:59)/17.少女が立っていた (s)(1:50)/18.私の胸をめぐっては (br独唱と合唱)(2:10)/19.もし若者が乙女と一緒に (t3/br1/b2)(0:58)/20.おいで、おいで、さあ来ておくれ (小合唱2)(1:00)/21.天秤棒に心をかけて (s独唱)(1:53)/第3部 愛の誘い 22.今こそ愉悦の季節 (s/br/合唱と小合唱)(2:10)/ 23.とても、いとしいお方 (s)(0:34)
「ブランツィフロールとヘレナ」 24.アヴェ (合唱)(1:39)/「運の女神、全世界の支配者なる」 25.おお、運の女神よ (合唱)(2:32)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
日々刻々と迫る2024年の終わり。昨日は冷たい風に好天。なにも変わらぬヒマな毎日なのに妙な切迫感があります。お仕事現役の後輩たちは昨日最終出勤、本日は早朝最終納品やトラブル対応に何人か出ていることでしょう。自分もかつてそんな担当、なにもかもが懐かしい。大掃除はしないけれど、いつもの小掃除くらい、そして除湿機を掛けている辺りのカーテンにカビ?が気になるとか、女房殿の指示にすべての部屋のカーテンを洗いました。食材は当日分足りているけれど、黒豆を再度炊こうと、ちょっと散歩がてら売り場を覗いたら北海道晩生光黒大豆に非ず、丹波黒豆がけっこう安く売っていて(先日高級スーパーのは価格4倍!)無事自分が思い描いていた価格水準に入手できました。粒がやや小さいのか、ヒネなのかな、ヒネ(古)やヒネヒネ(古々)のほうが品質的には安定しているんです。幸い圧力鍋にて甘さ控えめ、柔らかく、マイルドな味に仕上がりました。これで94歳の婆さんに食べていただけます。
朝は洗濯物み時間が押してストレッチ手抜き、YouTubeは短い「立ったまま腹筋全体を鍛えるトレーニング!6分30秒の4種目」実施したのみ。これより2024年ラストの市立体育館へ出掛けましょう。今朝の体重は67.15kg▲300g。
インフルエンザ6年ぶりの大流行、ご近所医院はもうお休みだし、帰省先でこどもが熱出したりするとタイヘンでしょう。クスリも不足しているらしいですね。息子一家は年末年始お嫁さんの実家である天草には帰らないとのこと。相変わらず乾燥するこの時期、毎年火災が発生しております。芸能人の不祥事が相次いで話題に、自分の縄張り外だから痛くも痒くもないけれど、業界の人は年末年始を挟んでこれから対応はタイヘンなことでしょう。芸能事務所が相次いで倒産の話題、昨日もNetflixの話題に触れたけれど、テレビ番組の質の低下は目を覆うほど、お笑い芸人ばかり便利に使い捨てて、最近のM-1にもまったく興味がない。興奮と共感を以て眺めたラストはサンドイッチマン衝撃の登場! いまやすっかり大御所ですもんね。ああ、ミルクボーイも良かったな。自分が時代に置いていかれただけですか?
動画「老いの限界・・・両手の痛み」著名なユーチューバーであるぺこりーのさんは同い齢。我らはコンピューターの導入と普及が一気に進んだ世代。キーボード操作に小指を使い過ぎ要因に両腕肘肩に痛みがあるそう。気持ちはわかりますよ。華麗なる加齢を重ねればあちこち不調はあるもの、自分も数十年単位に肘腕にマウス腱鞘炎と信じて、それは左手にも発症したから、違ったのでしょう。マウスやキーボードをいろいろ替えて対応、現在未だコンピューター操作に支障はありません。「小指」を使うということは、おそらく正しい指運を駆使されてのこと、自分は我流だから小指はあまり使いません。それに手首肘に優しいキーボード・マウスをずっと愛用してきたこともあるのでしょう。動画処理には縁がなくて、テキストのみのホームページ更新のみだから使用時間は比較的少ないかも。
外野からの勝手な憶測だけど・・・
もし、大きな病気が隠れていなければ、運動不足なんじゃないの?自分は20年以上前にスキーで転倒して左膝前十字靭帯一本切れたまま、そこを意識してよく動かすこと(例えばユルいエアロバイク)膝周りの筋肉を鍛えることで、なんとか日常機能を保持中。肩肘腕の鈍い痛み、こわばりも同様、ストレッチと隔日ゆる全身筋トレで辛くもクリアしている・・・そう自覚しております。いずれ、この鍛錬がいつまで継続できるか、そこが問題です。なんらかのトラブルで骨折でもすれば、仮に骨がつながってもそこから衰えた筋肉、関節の可動域確保や柔軟性、体力を戻すのは至難の業と類推しております。
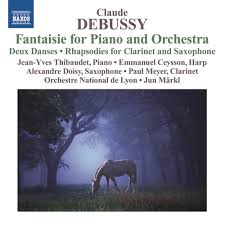 Debussy ピアノと管弦楽打のための幻想曲(Jean-Yves Thibaudet(p)/2011年)/クラリネットと管弦楽版のための第1狂詩曲(Paul Meyer(cl))/Ducasse編 アルト・サキソフォンのための狂詩曲(Alexandre Doisy(sax))/神聖な舞曲と世俗の舞曲(Emmanuel Ceysson(hp))(以上2010年)~純・メルクル/リヨン管弦楽団・・・Jun Ma"rkl(1959ー独逸)もいつの間にかヴェテランの年齢になったのですね。リヨン管弦楽団と9枚組のDebussy録音を残して一部「海」など著名なところ聴いた印象は、さらさらとさっぱりし過ぎ?これは仏蘭西の名手揃えて協奏的作品を集めたもの。音質はちょっとオン・マイクに奥行き不足、肌理は粗いけど雰囲気はあります。独特の芯のない響きが個性的と感じます。なんという天才の天翔る旋律揃い!
Debussy ピアノと管弦楽打のための幻想曲(Jean-Yves Thibaudet(p)/2011年)/クラリネットと管弦楽版のための第1狂詩曲(Paul Meyer(cl))/Ducasse編 アルト・サキソフォンのための狂詩曲(Alexandre Doisy(sax))/神聖な舞曲と世俗の舞曲(Emmanuel Ceysson(hp))(以上2010年)~純・メルクル/リヨン管弦楽団・・・Jun Ma"rkl(1959ー独逸)もいつの間にかヴェテランの年齢になったのですね。リヨン管弦楽団と9枚組のDebussy録音を残して一部「海」など著名なところ聴いた印象は、さらさらとさっぱりし過ぎ?これは仏蘭西の名手揃えて協奏的作品を集めたもの。音質はちょっとオン・マイクに奥行き不足、肌理は粗いけど雰囲気はあります。独特の芯のない響きが個性的と感じます。なんという天才の天翔る旋律揃い!
「幻想曲」は気紛れな自在な旋律が揺れるピアノ協奏曲。初演は1919年、アルフレッド・コルトーだそう。懐かしく、しっとりと悩ましい第1楽章「Andante ma non troppo-Allegro giusto」(7:44)第2楽章「Lento molto espressivo - Allegro molto」(16:33)緩緩急実質上三楽章のきらきらした名曲、ピアノはデリケートに雄弁でした。
「第1狂詩曲」は甘く香るようにセクシーなクラリネットが妖しく揺れます。ヴィヴラートの少ない軽くスムース音色。(7:36)「狂詩曲」はもともとサキソフォンとピアノのための作品だったそう。なんとも気怠い吐息のような音色に魅了されて、Jean Roger-Ducasse(1873-1954仏蘭西)の管弦楽編はホルンが効果的、ソロは浮き立ちました。(10:00)ハープのレパートリーには欠かせぬ名曲「神聖な舞曲と世俗の舞曲」は、なんともアルカイック。弦のみ伴奏にハープが幻想的に浮き立ちました。Danse sacree(4:32)Danse profane(4:41)
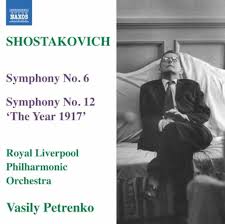 Shostakovich 交響曲第6番ロ短調(2010年)/第12番ニ短調「1917年」(2009年)~ヴァシリー・ペトレンコ/ロイヤル・リヴァプール・フィル・・・Vasily Petrenko (1976-露西亜)によるShostakovich交響曲全集から以前第5番/第9番を聴いていて、あまりよろしからぬ印象を得ていた記憶がありました。曰く”整った姿にどーも面白み(アク、臭み)が足りない”と。世評は高いようです。ところがここ3年更に作品の聴き込みが進んだせいか?印象一変。なにより解像度の高い音質が素晴らしい。露西亜風泥臭さとは無縁にモダーンなスタイルでしょう。オーケストラもけっこう優秀。
Shostakovich 交響曲第6番ロ短調(2010年)/第12番ニ短調「1917年」(2009年)~ヴァシリー・ペトレンコ/ロイヤル・リヴァプール・フィル・・・Vasily Petrenko (1976-露西亜)によるShostakovich交響曲全集から以前第5番/第9番を聴いていて、あまりよろしからぬ印象を得ていた記憶がありました。曰く”整った姿にどーも面白み(アク、臭み)が足りない”と。世評は高いようです。ところがここ3年更に作品の聴き込みが進んだせいか?印象一変。なにより解像度の高い音質が素晴らしい。露西亜風泥臭さとは無縁にモダーンなスタイルでしょう。オーケストラもけっこう優秀。
交響曲第6番ロ短調は三管編成、クラリネット3本に+バス・クラリネットが加わり、打楽器8種にチェレスタ、ハープ迄加わります。第1楽章「Largo」重苦しい延々と蠢くような始まりが、妙に清潔に決然と響いて明晰。暗鬱なまま金管の盛り上がりがあって、あとはほとんど静かに呟くような、掴みどころのない長大なる楽章。オーケストラの響きは比較的軽い、涼し気なサウンド、やがて安寧のホルンも幻想的に響いてここはなかなかの難物でしょう。正直ここはまだすっと耳に馴染まないところ。(19:44)第2楽章「Allegro」一転して軽妙なクラリネットが踊るように始まる、明るいスケルツォ楽章。細かい音型にやがて金管打楽器も炸裂して熱気は高まって・・・やがてそのまま徐々に音量が落ちて収束していくといった趣向でした。(5:53)第3楽章「Presto」ここも軽快な疾走から始まって、これはRossiniの「ウィリアム・テル」を連想させるとの指摘。やがてリズムは3/8拍子に変わって強烈な金管登場、冒頭の軽快な疾走が戻って金管打楽器も賑やかに一気呵成に終了しました。(7:17)
交響曲第12番ニ短調「1917年」はとってもわかりやすい、俗っぽくもカッコ良い旋律連続な作品。三管編成+打楽器6種の編成。
第1楽章「革命のペトログラード(Revolutionary Petrograd)」わかりやすい颯爽とした旋律がモウレツに快速、カッコ良い推進力に始まります。軽快な響きにアンサンブルは縦線が揃って優秀、打楽器もみごとに決まりました。途中優しい、平易な旋律は悠々と歌ってここも速めにリズミカルに落ち着かない切迫感、そして明るく爽やかな勢いを感じさせます。(12:32)
第2楽章「ラズリーフ(Razliv)」暗鬱なトロンボーンから始まる緩徐楽章、ラスト方面にもけっこう存在感たっぷりに登場します。ここも楚々として洗練された風情に速めのテンポに淡々と歩みを進めました。不安な弦の旋律や管楽器の弱音はとてもわかりやすく歌う。途中第1楽章の旋律も印象的に回帰しました。(10:44)
第3楽章「巡洋艦アヴローラ(Aurora)」不安げなピチカートとティンパニより開始していよいよ10月革命の開始。低く第1楽章の主題も登場してやがて絶叫、強烈な打楽器群と弦が呼応して、これはいかにも鉄砲大砲炸裂!決まってますよ、ここは。アタッカで(3:31)
第4楽章「人類の夜明け(The Dawn of Humanity)」ホルンと弦が勇壮な勝利宣言、一貫して速めのテンポにさらさらとした流れと軽さ、晴れやかな表情に俗っぽくもクサくならずカッコ良い!と評したいところ。ラスト、いかにも雄弁な大団円!打楽器は明快、爽やかなな締めくくりでした。(9:55)
云々と比べて~というのはちょっと失礼やけど、先日のマキシム・ショスタコーヴィチよりかなり洗練され、カッコよく感じました。
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
いつもと変わらぬ寒い日々なのに、2024年末は押し迫った感はちゃんとありますよ。昨日もいつもの洗濯、ストレッチ、YouTubeボクササイズを済ませて(これがけっこうキツい)市立体育館を目指しました。せっかく外干ししたのに、曇り空にちょっぴり小雨もパラ付きました。トレーニングルームは年末迫って常連メンバー・マイナス人数に空いていて、マッチョなバーベル連もお休み。ゆっくりゆる筋トレ+エアロバイク15分の有酸素運動も済ませて帰宅いたしました。今年は明日の営業最終日にてラストとなります。2024年は途中風邪などで寝込んだりもなく、ほぼ隔日皆勤賞でした。今朝の体重は67.45kg▲150gなかなか戻りません。
Netflixの効果は思った以上、幾度再放送される安易な、安っぽい作りの二時間ドラマなんてもう見られませんよ。厳選されたオリジナルドラマや売れ筋映画など、試しに再生してみたらもう止められない。地上波放送じゃないので暴力や官能シーンは一歩踏み込んでいるし、筋書きが凝っていて、細部作り込みが凄い。薬物の関係で地上波スポンサーに申し訳が立たぬピエール瀧も復活しておりました。それに何度でも、ちょっと流れが理解できなかったところも繰り返し再確認できます。岡田准一主演映画「ファブル」(2019年)「ザ・ファブル/殺さない殺し屋」(2021年)偶然に出現して、見始めたらもう途中で止められない。激しい暴力流血アクションシーン連続、宮川大輔の超絶しょうもないお笑いも隠し味、木村文乃もなかなかセクシーかつ強いキャラクターでした。
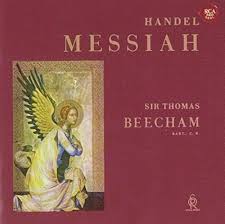 クリスマスも過ぎたけれど・・・
Handel オラトリオ「メサイア」(Eugene Goossens版)~トーマス・ビーチャム/ロイヤル・フィル/合唱団/ジェニファーヴィヴィアン(s)/モニカ・シンクレール(ms)/ジョン・ヴィッカーズ(t)/ジョルジョ・トッツィ(b)(1959年)・・・20年ほど前にこの作品はじっくり腰を据えて聴いておりました。Bachと異なり、初演以来ずっと人気作品として演奏され聴き継がれた名曲、Thomas Beecham(1879-1961英国)による著名な超デーハー、キンキラキンに輝かしいゴージャスな演奏。声楽陣はJennifer Vyvyan(1925-74英国)Monica Sinclair(1925-2002英国)Jon Vickers(1926-2015加奈陀)Giorgio Tozzi(1923-2011亜米利加)
フツウはオーボエ2/ファゴット2/トランペット2/ティンパニ一対/弦5部/通奏低音(オルガン)(定まった版というのがないらしい)Goosens版はそれにホルン、トロンボーン、クラリネット、更にはハープ、大太鼓、トライアングル、クライマックスにはシンバルも加わっているそう。弦はもちろん、各々管楽器パート人数も増やしているのかも。楽器編成さておき、幾種版が存在する「メサイア」、この演奏順がどの版に準拠したものかはわかりません。(第二部、第三部で数曲カットされている部分がある、とのこと)某著名な権威ある音楽サイトには
クリスマスも過ぎたけれど・・・
Handel オラトリオ「メサイア」(Eugene Goossens版)~トーマス・ビーチャム/ロイヤル・フィル/合唱団/ジェニファーヴィヴィアン(s)/モニカ・シンクレール(ms)/ジョン・ヴィッカーズ(t)/ジョルジョ・トッツィ(b)(1959年)・・・20年ほど前にこの作品はじっくり腰を据えて聴いておりました。Bachと異なり、初演以来ずっと人気作品として演奏され聴き継がれた名曲、Thomas Beecham(1879-1961英国)による著名な超デーハー、キンキラキンに輝かしいゴージャスな演奏。声楽陣はJennifer Vyvyan(1925-74英国)Monica Sinclair(1925-2002英国)Jon Vickers(1926-2015加奈陀)Giorgio Tozzi(1923-2011亜米利加)
フツウはオーボエ2/ファゴット2/トランペット2/ティンパニ一対/弦5部/通奏低音(オルガン)(定まった版というのがないらしい)Goosens版はそれにホルン、トロンボーン、クラリネット、更にはハープ、大太鼓、トライアングル、クライマックスにはシンバルも加わっているそう。弦はもちろん、各々管楽器パート人数も増やしているのかも。楽器編成さておき、幾種版が存在する「メサイア」、この演奏順がどの版に準拠したものかはわかりません。(第二部、第三部で数曲カットされている部分がある、とのこと)某著名な権威ある音楽サイトには
音が悪いし、演奏も荒い/洗練された音楽学の裏付けのある演奏に慣れた耳で聴くと「抱腹絶倒もしくは怒り爆発」まちがいなし
他のサイトにも
この猥雑さを耐えられない人には「願い下げ」の音楽
おそらく私の人生においてもう一度聴き直すことはおそらくないだろう
偉大なる時代錯誤
~とあって散々な評価。自分は「メサイア」との出会いはこれ「洗練された音楽学の裏付けのある演奏」に出会う前、これが(おそらく誤った)刷り込みだからまったく違和感なし。成金趣味みたいな下品さは感じない、というか、通常の演奏にはもう物足りなさを覚えるくらい。新星堂のCD以来の再聴、今回拝聴した音源は臨場感たっぷり、音質的な不足をほとんど感じさせないと思います。「荒い」とも思えない。ロイヤル・フィルは弦も管も美しく、静謐な場面の陶酔感、分厚い響きの高揚にも文句なし。ハープがチェンバロのように扱われ(とても効果的)華やかな伴奏に相応しい強烈なソロは雄弁詠嘆、まるでVerdiみたいな伊太利亜オペラ風、合唱団は充実して上質、昔風発声の違和感はありません。とてもわかりやすく、現代社会に長大な作品を飽きずに愉しめる版であり演奏と受け止めました。よく聴き知った旋律連続、どれもとてもわかりやすい。
第1部: メシア到来の預言と誕生、メシアの宣教
1 Overture 荘厳重厚な序曲はしっとりとした表情付け。フルートとハープが美しい(454)/2 Comfort ye, my people 朗々たるテナーの美声が快い(3:40)/3 Every valley shall be exalted 引き続きテナーがたっぷり高揚して喜ばしい躍動(3:37)/4 And the glory of the Lord 盛大に輝かしい混声合唱+トランペットが思いっきり活躍(3:39)/5 Thus saith the Lord of Hosts まさにオペラに於ける主級役バス登場!圧巻の存在感(1:54)/6 But who may abide バスの重量級の嘆きが続きます。管弦楽の疾走はバロック音楽とは思えぬもの(5:08)/7 And he shall purify ここは寂しげな合唱がやがてフル・オーケストラのリズムに乗って盛り上げます(315)/8 Behold, a virgin shall conceive 女声ソロのレシタティーボ(0:46)/9 O thou that tellest good tidings(おお、汝、シオンに良き知らせを語る者よ)敬虔なこのアルト・ソロが一番有名、単独で演奏会に取り上げられる機会も多い。色彩豊かなオーケストラがそっと支えて効果的、やがて喜ばしく合唱も参入して管弦楽も華やかでした。(7:06)/10 For, behold, darkness shall cover バスによる暗鬱なモノローグ。ここも風情はまるっきりオペラ(302)/11 The people that walked in darkness 引き続き静かに物思いに耽るバスの嘆き(4:58)/12 For unto us a child is born 歓喜に溢れる合唱。噛みしめるようなリズムがちょっと重い、というかすごい迫力!(4:53)/13 Pastoral Symphony ゆったりとしたテンポに弦の陶酔感は目眩を感じるほど(4:40)/14 There were shepherds abiding そっと清楚なソプラノにハープがきらきら寄り添う(1:01)/15 And the angel said unto them(0:55)/16 And suddenly there was 引き続きソプラノ(023)/17 Glory to the God in the highest 輝かしく喜ばしい合唱に感極まります。トランペットとティンパニが印象的。(2:20)/18 Rejoice greatly, O daughter これは有名な喜ばしいソプラノ・アリア。演奏家にも単独に取り上げられます(4:39)/19 Then shall the eyes(033)/20 He shall feed his flock; Come unto him 静かな弦に乗せて清楚なソプラノとアルトが感動的(617)/21 His yoke is easy 敬虔さたっぷりだけど、ここの混声合唱はちょっと大仰な、ラスト盛大なるルバート(3:03)
第2部: メシアの受難と復活、メシアの教えの伝播
1 Behold the Lamb of God 神妙に静謐な合唱と管弦楽は浪漫の風情横溢(4:13)/2 He was despised 「彼は侮られて」 アルトによる陶酔のアリア。弦の弱音はデリケート(6:09)/3 Surely he hath borne our griefs Bachを連想させる劇的に詠嘆する合唱。弦とトランペットが印象的な伴奏(3:02)/4 And with His stripes we are healed 引き続き合唱の嘆き。Mozartのレクイエムを思い出しました(2:24)/5 All we like sheep have gone astray 歓喜溢れて躍動する合唱(406)/6 All they that see Him テナーのレチタティーヴォ(0:55)/7 He trusted in God ここもMozartのレクイエムを連想させる合唱(2:28)/8 Thy rebuke hath broken His Heart (2:41)/9 Behold, and see if there be まるっきり伊太利亜オペラ風テナーの詠唱(2:06)/10 He was cut off out of the land 引き続きテナーのレチタティーヴォ(0:29)/11 But Thou didst not leave 安らぎのテナーの朗々と明るい表情。優しい器楽アンサンブルの伴奏(3:29)/12 Lift up your heads 「もろびとこぞりて」風リズミカルに喜ばしい合唱。ホルンとティンパニが効いて賑やか(3:17)/13 How beautiful are the feet しっとりとして歓喜極まるアルトのアリア。美しい旋律絶品(3:08)/14 Their sound is gone out into all lands 静かに喜びを噛みしめる合唱(1:46)/15 Why do the nations so furious rage 勇壮な管弦楽に導かれてバスが朗々と躍動します(2:55)/16 Let us break their bonds asunder ここはソプラノのレチタティーヴォ?収録は喜びに充ちた合唱となって、これは編集ミスなのかか。(023)/17 He that dwelleth in heaven テナーの思いっきり力んで朗々たるレチタティーヴォ(0:24)/18 Thou shalt break them そして決然たるアリア(214)/19 Hallelujah! 誰でも知っている「メサイア」のクライマックス。シンバル一閃!パワフルな合唱は分厚い金管と打楽器群に支えられてスケール最高、これは作品内容と編曲が似合っていると感じます。感銘一入(ひとしお)。(3:39)
第3部: メシアのもたらした救い 永遠のいのち
20 I know that my Redeemer liveth ソプラノの慈愛に充ちた静かなアリアは絶品(6:17)/21 Since by man came death 誠実な合唱が充実しております(3:03)/22 Behold, I tell you a mystery (0:44)/23 The trumpet shall sound 嚠喨たるトランペットに乗せてバスが思いっきり雄弁!(424)/(Then shall be brought/O death, where is thy sting?/God be for usはカットされ、後半に別途収録)/24 Worthy is the lamb 壮麗な合唱とオーケケストラは眩しいほどの迫力。ここのデーハーさはHallelujah! に匹敵します。そして有名な「アーメン・コーラス」ラストのルバートに感極まるところ。(7:53)
(以下はカット分まとめて残り収録)
Unto Which of a Angelテナーのレチタイティーヴォ(0:29)Let all the Angel of God Worship him輝かしい合唱の高揚が続きます(1:40)/Surely He hath borne our griefs(第2部?3:02)/The Lord gave the Word(第2部?1:15)/(24)Then shall be brought to Pass(0:23)/(25)O Deth,Where is Thy Sting?アルトとテナーのの敬虔なアリア(1:26)/But Thanks Be to God(2:26)/(26)If Dod be for Us アルトの切々たるアリア(5:23)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
2024年もあと残すところ5日、大掃除もやる気なし、出掛ける予定もありません。千年一日の如く同じ日々、朝一番の洗濯、ストレッチ、短いYouTube「10 Minute FAT BURN CARDIO HIIT Workout | Low Impact High Intensity!」体操などこなして、好天。一番近いスーパーに、切れていたお気に入り濃厚野菜ジュースを入手に出掛けました。売り場には未だクリスマス惣菜があって、連続フライドチキンが喰いたい!なんとかその欲望を抑え込んで、最低限の食材のみ入手して往復3.8kmほどのウォーキングとしました。このスーパーが自分が通う中では一番高級、商品と質と価格を睨んで、例えば業務スーパーは安いけれど安物に当たる可能性も高くて厳選必須、熟考が必要です。高くてあかんのはアウト!それは当たり前。今朝の体重は67.6kg+200gじわじわ増加中。これから鍛えてきましょう。
ヒマな毎日に音楽ヲタク話しなど。
時間的に精神の集中力維持的にも全部は聴けないのに、日々音源ファイルを求めてネットを探っているのは、新しい刺激を求めていることはあるけれど、若い頃心躍らせて聴いた懐かしい音源を求めているから。自分がこどもの頃LPはほんまに贅沢品、廉価盤や中古盤を大切にていねいに聴いたものです。当時は集中力もありました。
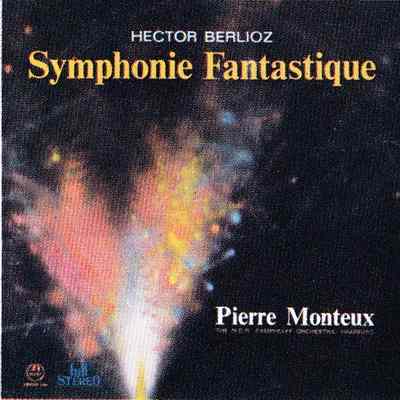 世間より遅れてLPを諦めて、最初に買ったCDがBerlioz 幻想交響曲~ピエール・モントゥー/ハンブルク北ドイツ放送交響楽団(1964年/DENON/2,800円!)音質よろしからぬこの録音は記録から類推して2019年迄手許にあったはずなのに、どのような経緯で手放したのか既に記憶もありません。もしかして.mp3だったので廃棄したのでしょうか。これがあちこち探しても、ありそうで再入手できない。
世間より遅れてLPを諦めて、最初に買ったCDがBerlioz 幻想交響曲~ピエール・モントゥー/ハンブルク北ドイツ放送交響楽団(1964年/DENON/2,800円!)音質よろしからぬこの録音は記録から類推して2019年迄手許にあったはずなのに、どのような経緯で手放したのか既に記憶もありません。もしかして.mp3だったので廃棄したのでしょうか。これがあちこち探しても、ありそうで再入手できない。
Bach 管弦楽組曲/ブランデンブルク協奏曲~ロリン・マゼール/ベルリン放送交響楽団(1965年)・・・これは17cmLP時代に熱心に聴いてて、その後CD時代には管弦楽組曲の一部を愛聴しておりました。これは鶴首してネットへの出現を待っているけれど、再びの出会いがありません。
スコトフスキーの音源もできるだけ集めるように心掛けているけれど、Vanguardのバロック・アルバムはなかなか出てこない。再会を熱望しております。
熱望した挙げ句ようやくの再会に心震わせて聴いてみたら~自分の感性がすっかり変わってしまったのか、さほどの感銘を覚えなかった経験も再三再四。華麗なる加齢を重ね、安物オーディオとは云え、それはそれで良好な音質や新鮮な表現に耳が慣れたということもあるのでしょう。巨匠時代の太古音源も両極端、一周回って現代には失われた輝きと個性を発見することもあれば、とてもだけれど聴いていられない、ガッカリすることもありました。
それでも、昔馴染みの音源にはいつか再会して、確認したいと熱望しております。
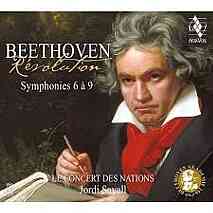 Beethoven 交響曲第9番ニ短調「合唱付き」~ジョルディ・サヴァール/ル・コンセール・デ・ナシオン/ラ・カペラ・ナシオナル・デ・カタルーニャ/サラ・グジ(s)/ライラ・サロメ・フィッシャー(a)/ミン・ジ・レイ(t)/マヌエル・ヴァルサー(b)(2021年)・・・年末は「第九」。最終楽章に声楽を据えて巨大な、屈指の名曲に間違いない。
Beethoven 交響曲第9番ニ短調「合唱付き」~ジョルディ・サヴァール/ル・コンセール・デ・ナシオン/ラ・カペラ・ナシオナル・デ・カタルーニャ/サラ・グジ(s)/ライラ・サロメ・フィッシャー(a)/ミン・ジ・レイ(t)/マヌエル・ヴァルサー(b)(2021年)・・・年末は「第九」。最終楽章に声楽を据えて巨大な、屈指の名曲に間違いない。
演奏表現に賛否あるのは当たり前、一部カスタマーレヴューには
「録音が良すぎるのか、狙いなのか、弦のガシガシ、ゴリゴリ感、ホルンの強奏が痛々しい。推進力はあるが、やがて・・・焦燥感へ」
~なるほどなぁ。艶やかな洗練された響き流麗に重厚長大なモダーン楽器アンサンブルに耳馴染めば、その薄い響きに違和感は一理も二理もあることでしょう。返す刀で逆も真也。速めのテンポに粗野なパワーたっぷりに推進する第1楽章「Allegro ma non troppo, un poco maestoso」には静謐な神秘が足りないかも知れないけれど、これが個性ですから(14:05)第2楽章「Molto vivace - Presto ニ長調 - Molto vivace - Presto」も快速テンポ継続、いっそう激しくその存在を激しく主張するティンパニの強烈躍動に胸熱くして聴き惚れてノリノリ。繰り返し有。(12:56)第3楽章「Adagio molto e cantabile~」ここは素晴らしく深遠なる変奏曲。ここも素朴な弦中心にサラサラと流れるような速いテンポ、素っ気ない、落ち着かぬフレージングに”深遠”が足らぬと感じられる方もいらっしゃると類推できます。ティンパニのリズムは充分衝撃的、この楽章はホルンの妙技に注目、”強奏が痛々しい”かどうかは嗜好の問題、古楽器好きの自分が求めていた音はこの潰れた野蛮な音色でした。(11:23)第4楽章「Presto - Allegro ma non troppo~」ここもフレージングはまことに素っ気なくさっぱり、アクセントしっかりに進みます。古楽器の音色は素朴に陰影深く歌って味わい深い。合唱は少人数ですか?各声部が浮き立ってアクセントも明快。上質な声楽陣揃えましたね。「Alla Marcia」以降も高速進撃継続。ここの古楽器アンサンブルには重量感が足りぬとのご指摘もあることでしょう。引き続き合唱はノリノリ、そして表情は入念を極めてこの楽章の主役は声楽といった扱いなのでしょう。フィナーレは喧しいくらい打楽器の存在感が際立ちました。クライマックスは終楽章に有。(5:47-3:18-9:20-4:16)ご指摘の通りの優秀録音、残響豊かに会場空間がしっかり認識できます。
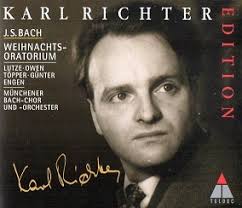 Bach クリスマス・オラトリオ第6部BWV.248~カール・リヒター/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/合唱団/ゲルト・ルッツェ(t/エヴァンゲリスト)/クロエ・オーウェン(s)/ヘルタ・テッパー(a)/ホルスト・ギュンター(b)/キート・エンゲン(b)(1955年)・・・旧モノラル録音。ようやくラスト6日目を迎えました。Karl Richter(1926ー1981独逸)も短命やったなぁ、残念。バロック音楽モダーン楽器演奏の輝やきに充ちた人気の指揮者鍵盤楽器演奏者でした。自分が若い頃は圧倒的な権威と人気の人。音質はかなり良好、トランペット先頭に輝かしい演奏。テナーもバスも、そして合唱も思いっきり大仰雄弁な表現に朗々、昔は皆こんな感じでしたよ。最近の古楽器系の親密に素朴な器楽サウンド、軽快なリズム、清楚に素直な声楽に耳慣れると、これはずいぶんと巨大、立派、かなり肩怒らせて四角四面に響きます。これはこれで先人の成果に敬意を込めて”大きな”Bachを堪能できました。
Bach クリスマス・オラトリオ第6部BWV.248~カール・リヒター/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/合唱団/ゲルト・ルッツェ(t/エヴァンゲリスト)/クロエ・オーウェン(s)/ヘルタ・テッパー(a)/ホルスト・ギュンター(b)/キート・エンゲン(b)(1955年)・・・旧モノラル録音。ようやくラスト6日目を迎えました。Karl Richter(1926ー1981独逸)も短命やったなぁ、残念。バロック音楽モダーン楽器演奏の輝やきに充ちた人気の指揮者鍵盤楽器演奏者でした。自分が若い頃は圧倒的な権威と人気の人。音質はかなり良好、トランペット先頭に輝かしい演奏。テナーもバスも、そして合唱も思いっきり大仰雄弁な表現に朗々、昔は皆こんな感じでしたよ。最近の古楽器系の親密に素朴な器楽サウンド、軽快なリズム、清楚に素直な声楽に耳慣れると、これはずいぶんと巨大、立派、かなり肩怒らせて四角四面に響きます。これはこれで先人の成果に敬意を込めて”大きな”Bachを堪能できました。
第6部 顕現節 (1月6日)「公現祭/カトリック教会、聖公会」
第54曲 合唱「主よ、勝ち誇れる敵どもの息まくとき」ここは思っきりデーハー壮麗に元気いっぱい!トランペットの大きな存在感+合唱の高揚!(5:26)/第55曲 レチタティーヴォ「ここにヘロデひそかに博士らを招きて」ヘロデ王は思いっきり偉そう(1:03)/第56曲 レチタティーヴォ「汝偽り者よ、思うがままに主を倒さんとうかがい」(1:04)/
第57曲 アリア「その御手のひとふりは」ソプラノの決然とした歌と弦楽アンサンブルの力のこもった掛け合い。(4:13)/第58曲 レチタティーヴォ「彼ら王の言葉を聞きて」(1:30)エヴァンゲリストも表情豊かに雄弁そのもの。/第59曲 コラール「われらはここ馬槽のかたえ汝がみ側に立つ」安らぎの合唱はいかにも最終盤を予感させます。(1:29)/第60曲 レチタティーヴォ「ここに神、夢にて」(0:30)/第61曲 レチタティーヴォ「さらば行けよ!足れり、わが宝ここより去らずば」(2:22)/第62曲 アリア「さらば汝ら、勝ち誇れる敵ども、脅せかし」オーボエのオブリガートにテナーが朗々と大仰、怒れるように歌います。(5:35)/第63曲 レチタティーヴォ「陰府の恐れ、今は何するものぞ?」これは合唱によるもの。(0:44)/第64曲 コラール「今や汝らの神の報復はいみじくも遂げられたり」ラストは再び立派なトランペットとティンパニ登場。リズムは違うけれど「おお頭は血潮にまみれ」と同じ旋律に喜ばしく全曲を締め括りました。(3:49)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
やはり老後引退後の夫婦家庭にはサンタさんは来ませんでした。孫のところには訪問したことでしょう。(LINEに希望通りのものが届いたと大喜び!との報告)世間のこども達は終業式、これから帰省などがあって、インフルエンザなどますます広がることがないよう祈りましょう。自分は年末迫って昨日もいつもと寸分違わぬ同じ生活、朝は洗濯時間がちょっと押してストレッチ抜き、短いYouTube鍛錬のみ実施して、冷たい風曇り空のもと市立体育館を目指しました。年末迄しっかり通いますよ。トレーニングルームは常連メンバー少人数+最悪のマルチプレス独占野郎の顔が・・・まずマルチプレスをさっさと終わらせていつもどおりの筋トレ、そしてエアロバイク15分消化。しっかり耐えて帰りはスーパーに寄ってクリスマス商戦の品揃え拝見、相変わらず野菜が高い! そして少々要らぬもの無駄遣いしちゃいました。酒の翌日だったけれど、体調は悪くありません。今朝の体重は67.4kg+350g。クリスマス売り場に見掛けたフライドチキンが美味そうで、3個昼に全部喰ってしまった結果です。
「妻殺害、元長野県議に懲役19年の判決」この先、まだどうなるかわからぬけれど、紀州のドンファンの流れに無罪判決が出るかと思ったら、そんな単純なものではないのですね。ま、はっきりとした殺人事件ですから。岸和田市長は議会解散の報道、兵庫県知事ブームの再来を狙っているのでしょうか。
いつも訪問するブログを拝見すると、出汁を「でじる」と読む店員~そんな話題がありました。このネタは以前TVCMにもありましたよ。麻婆を「あさばあ」というのはCM上の演出。64歳孤高の爺友は「云々」を「いい」と使っておりました。自分もきっとあるやろなぁ、知らんで使っていたら、嗚呼恥ずかしい!
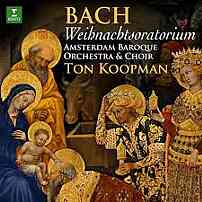 Bach クリスマス・オラトリオ BWV.248(第4部/第5部)~
トン・コープマン/アムステルダム・バロック管弦楽団&合唱団/リサ・ラーション(s)/エリーザベト・フォン・マグヌス(a)/クリストフ・プレガルディエン(t)/クラウス・メルテンス(b)(1996年)・・・これはいかにも古楽器の素朴な響き、穏健なバランスが際立つ演奏でしょう。熟達した楽アンサンブルと声楽陣も息が合って親密そのもの、ここではカウンター・テナーに非ず、アルトが採用されております。
Bach クリスマス・オラトリオ BWV.248(第4部/第5部)~
トン・コープマン/アムステルダム・バロック管弦楽団&合唱団/リサ・ラーション(s)/エリーザベト・フォン・マグヌス(a)/クリストフ・プレガルディエン(t)/クラウス・メルテンス(b)(1996年)・・・これはいかにも古楽器の素朴な響き、穏健なバランスが際立つ演奏でしょう。熟達した楽アンサンブルと声楽陣も息が合って親密そのもの、ここではカウンター・テナーに非ず、アルトが採用されております。
第4部 新年用 (1月1日)
第36曲 合唱「ひれ伏せ、感謝もて、讃美もて」心温まる合唱とホルンの牧歌的な掛け合い(6:02)/第37曲 レチタティーヴォ「八日みちて」(0:32)/第38曲 レチタティーヴォとアリオーソ「インマヌエル、おお、甘き言葉よ!/イエス、こよなく尊きわが生命よ」テナーと女声(少年?)合唱の絡みが神々しい(2:22)/第39曲 アリア「答えたまえ、わが救い主よ、汝の御名はそも」清楚なソプラノのアリア。素朴な音色のオーボエ・オブリガート、女声のエコーも効果的(5:29)/第40曲 レチタティーヴォとアリオーソ「ならばいざ!汝の御名のみ/イエス、わが歓びの極み」ここもテナーと女声(少年?)合唱の絡み(1:24)/第41曲 アリア「われはただ汝の栄光のために生きん」テナーの真っ直ぐななソロ+ヴァイオリンの切迫したオブリガート+チェロとオルガンの自在な通奏低音が際立ちます。第4分最高の聴きもの(4:37)/第42曲 コラール「イエスわが始まりを正し」ホルンもオーボエも総動員して、合唱は喜ばしく呼応して締めくくります。(1:51)
第5部 新年後の第1日曜日
第43曲 合唱「栄光あれと、神よ、汝に歌わん」軽快なリズムを刻む器楽アンサンブルから、その流れを合唱が軽快に、浮き立つように引き継いで始まります。(6:43)/第44曲 レチタティーヴォ「イエス、ユダヤのベツレヘムにて」(0:22)/第45曲 合唱とレチタティーヴォ「この度生まれ給えるユダヤ人の王はいずこにいますか?/その君をわが胸の内に求めよ」(1:47)切迫する合唱とアルト/第46曲 コラール「汝の光輝は全ての闇を呑み」(0:49)/第47曲 アリア「わが暗き五感をも照らし」粗野な音色のオーボエから始まって通奏低音が印象的、バスがしっとり歌います。(4:22)/第48曲 レチタティーヴォ「ヘロデ王これを聞きて」(0:10)/第49曲 レチタティーヴォ「いかなれば汝らはうろたえ慄くか?」(0:27)/第50曲 レチタティーヴォ「王、民の祭司長ら」(1:15)/第51曲 アリア(三重唱)「ああ、その時はいつ現るるや?」ヴァイオリン・ソロから始まって、ソプラノ、テナー、アルトがそのオブリガートに乗って切々と気高く歌う(4:36)/第52曲 レチタティーヴォ「いと尊きわが君はすでに統べ治めたもう」(0:31)/第53曲 コラール「かかる心の部屋は」澄み切った心象風景のような合唱に締め括りました。(1:03)
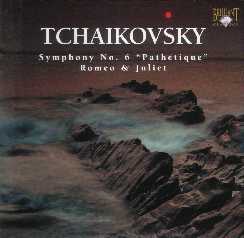 Tchaikovsky 交響曲第6番ロ短調「悲愴」(1979年)/幻想序曲「ロメオとジュリエット」(1977年)~リッカルド・ムーティ/フィルハーモニア管弦楽団・・・2007年来の再聴。Riccardo Muti(1941-伊太利亜)は未だ30歳代の録音。当時の印象は
Tchaikovsky 交響曲第6番ロ短調「悲愴」(1979年)/幻想序曲「ロメオとジュリエット」(1977年)~リッカルド・ムーティ/フィルハーモニア管弦楽団・・・2007年来の再聴。Riccardo Muti(1941-伊太利亜)は未だ30歳代の録音。当時の印象は
颯爽と明快、軽快、ティンパニが強烈アクセント(全編に渡って聴きもの!)であって、良く歌う旋律の”タメ”がなんとも若々しい
そして音質について文句を付けておりました。久々の感触はさほどに悪い音質でもない、弱音の音量が低いくらい。結論的にあまりに馴染み過ぎた名曲「悲愴」をたっぷり堪能いたしました。
第1楽章「Adagio - Allegro non troppo - Andante ~」静謐に抑制した始まりからやがて、途中からの劇的に鋭角な疾走、圧巻のティンパニのカッコ良い打撃に圧倒され、優しい部分詠嘆の対比が雄弁に素晴らしい。これが若さでしょう。もちろん露西亜風泥臭さとは無縁の洗練されたサウンド、オーケストラの上手さが光ります。(18:53)
第2楽章「Allegro con grazia」は甘いワルツ。中間部の暗い対比も意外とフツウのおとなしい演奏。(8:07)
第3楽章「Allegro molto vivace」は闊達に躍動するスケルツォ。軽快に溌剌として元気いっぱい熱烈、浮き立つように流線型の表現でした。ここのアンサンブルも細身に軽いサウンドに文句なしのノリノリ。金管の響きは爽やかでした。ここもティンパニの低音、そしてシンバルの一撃は衝撃。(8:44)
第4楽章「Finale. Adagio lamentoso - Andante - Andante non tanto」は悲劇を強調しない楚々とした始まり。テンポはやや速め、粛々とした歩みはデリケートに歌って大仰に非ず。やがてたっぷり甘い旋律は大きく育ってティンパニ炸裂!やや前のめりに情感は高まって、この辺りいかにも若者の勢いを感じさせました。やがて・・・最後の審判=銅鑼が鳴り響いて、ラストに向けてエネルギーは減衰、諦観のうちに生命尽きました。(10:31)
幻想序曲「ロメオとジュリエット」はTchikovsky初期の傑作。神妙静謐な始まりから、やがて悲劇が出来(しゅったい)するであろう劇的な叫びがやってきて、ここのティンパニも印象的だけど「悲愴」ほどの切れ味はない、少々ぼわんとした響き。緊張感と疾走のテンションと後半に向けて雄弁な歌は充分でしょう。オーケストラは颯爽と整って(露西亜風とは異なる金管の軽さ)これもたっぷり若々しく清涼な演奏でした。(19:31)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
年末に向けてますます冷えて、こちらには雨は降らないよう。日本海側は大雪の可能性も。お仕事現役時代はこの時期、高速道路の雪に荷物が届かぬことに気をもんでいたものですよ。それも懐かしい思い出になりました。昨日朝一番の洗濯ストレッチの前に決意してNetflix契約(CM付き890円/月也)「地面師たち」や「極悪同盟」を見たかったので。制作のカネと手間暇の掛け方が違うみたいですね、ドラマづくりへの本気度を感じさせます。一ヶ月で満足したら解約するかも。
馴染みのYouTube鍛錬済ませてから、いつもの激安美容院を目指して二番札、残念前回に続き北川景子似(眼鏡/マスク越し)別嬪美容師さんは不在でした。さっさとステキな妙齢店長さんに短く刈ってもらいました。終了後、少々食材(+いつもより少々高い珈琲豆など)を購入してさっさと帰宅、昼から爺友との第2回忘年会へ。この一年、幾度馬鹿になって酒呑んで罵詈雑言合戦、元気に過ごせたことに感謝。できちゃった結婚(いまどき「授かり婚」と呼ぶのか)した挙げ句さっさと離婚した一人息子が再婚したいとの話題、来月(年)19日に彼女と会う約束なんだそう。「おそらくまたアカンでしょう」と嘆いてずいぶんと荒れておりました。人生悲喜こもごも。夕方早々に帰宅して「地面師たち」一気見。地上波では放映できない暴力やセクシーな場面も登場して、そのスケールの大きさ、細部キャラクターの描き込みに驚かされました。今朝の体重は67.15kg+100g散々呑んで喰ったワリには増えておりません。
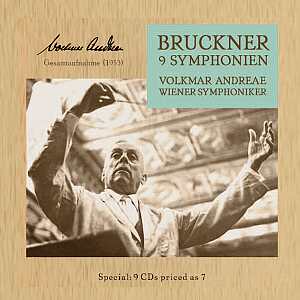 Bruckner 交響曲第8番ハ短調(1892年 Schalk改訂版)~フォルクマール・アンドレーエ/ウィーン交響楽団(1953年)・・・2010年に第5番を聴いておりました。Volkmar Andreae(1879-1962瑞西)は1953年にウィーン交響楽団とBruckner全曲録音して、意外と良質な臨場感あるモノラル音質に驚かされました。これは放送用録音ですか?例のように版のことはほとんど理解しておりません。これはBruckner中屈指の仰ぎ見るように巨大な作品、ウィーン交響楽団も(音質印象か)やや線は細いけれど、かなり好調なアンサンブルでした。演奏スタイルは太古巨匠時代風大仰なものに非ず、現代に通用する立派なものと受け止めました。
Bruckner 交響曲第8番ハ短調(1892年 Schalk改訂版)~フォルクマール・アンドレーエ/ウィーン交響楽団(1953年)・・・2010年に第5番を聴いておりました。Volkmar Andreae(1879-1962瑞西)は1953年にウィーン交響楽団とBruckner全曲録音して、意外と良質な臨場感あるモノラル音質に驚かされました。これは放送用録音ですか?例のように版のことはほとんど理解しておりません。これはBruckner中屈指の仰ぎ見るように巨大な作品、ウィーン交響楽団も(音質印象か)やや線は細いけれど、かなり好調なアンサンブルでした。演奏スタイルは太古巨匠時代風大仰なものに非ず、現代に通用する立派なものと受け止めました。
第1楽章「Allegro moderato」やや速めのテンポにマッチョな熱気を帯びて前のめり、深刻に始まりました。表情やテンポは入念に描き込み変化して勢いある切迫感が続きます。これは改訂版?馴染みの、ちゃんと静かに力尽きるように終わる版でした。一気に全曲録音したのに、ウィーン交響楽団に粗さを感じさせません。(14:05)
第2楽章「Scherzo: Allegro moderato」テンポは通常馴染んだ感じだけど、やはり前のめりな印象。熱のこもった荒々しい金管炸裂!トリオはLangsam (ゆっくりと)ここも表情豊かに、意外とさっくりとした軽妙なニュアンスでした。ホルンの響きはたっぷり魅惑でした。(14:05)
第3楽章「Adagio: Feierlich langsam, doch nicht schleppend」緩徐楽章。悠々とスケールは大きく、テンポは中庸からやがて速度を上げてクライマックスにシンバルの衝撃に至る熱気は素晴らしい。(24:06)
第4楽章「Finale: Feierlich, nicht schnell」は弦によるコサック怒涛の進軍、やがて優しい第2主題が歌って一息、それは深刻な第3主題へとつながります。テンポはうねうね緩急動いて入念に歌って効果的、表現に恣意性をあまり感じさせない。やがて金管炸裂!なかなかの集中力と緊張感あるテンポ・アップして渾身のクライマックスへ。終楽章に至ってオーケストラはちょっとパワーが切れてきたような印象もありました。ティンパニも少々ズレて、金管にも疲れが見られる・・・だけど、感動的な熱のたっぷりこもった立派な演奏でした。(19:56)
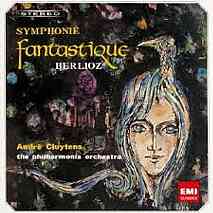 Berlioz 幻想交響曲~アンドレ・クリュタンス/フィルハーモニア管弦楽団(1958年)・・・これはびっくり!LP廉価盤時代からの馴染の存在は数十年ぶりの再聴、音質はかなり良好、フィルハーモニア管弦楽団も絶好調。こどもの頃から聴き続けて不遜にも少々食傷気味に至った著名作品は、これほどニュアンスたっぷりに新鮮に響いたのも久々。1830年初演革新的な名曲はこの演奏、繰り返しもコルネットもないけれど、これは驚きのヴェリ・ベスト。
Berlioz 幻想交響曲~アンドレ・クリュタンス/フィルハーモニア管弦楽団(1958年)・・・これはびっくり!LP廉価盤時代からの馴染の存在は数十年ぶりの再聴、音質はかなり良好、フィルハーモニア管弦楽団も絶好調。こどもの頃から聴き続けて不遜にも少々食傷気味に至った著名作品は、これほどニュアンスたっぷりに新鮮に響いたのも久々。1830年初演革新的な名曲はこの演奏、繰り返しもコルネットもないけれど、これは驚きのヴェリ・ベスト。
第1楽章「夢、情熱」神妙な始まりから、晴れやかに浮き立つような情感の高まりは自然にテンポ・アップしてアツいもの。強弱メリハリ、寄せては返す微細な表情付けも入念に、フィルハーモニア管弦楽団のアンサンブルは優秀です。ホルンの素直な色に感心いたしました。イデー・フィクス(固定観念)は決然として力強く、想いは高まります。残念ながら提示部繰り返しはなし。(13:59)
第2楽章「舞踏会」ゴージャスに不安げな序奏から、優雅に軽妙なワルツが華やかに歌います。ほんのちょっぴりの躊躇いも効果的、木管が浮き立ってハープが夢見るように美しい。コルネットなしは残念。ラストあたり「イデー・フィクス」ハリエット・スミスソンの姿が垣間見えます。(6:26)
第3楽章「野の風景」静謐な大自然に羊飼いの牛追い歌(イングリッシュ・ホルン)が牧歌的に流れて、微妙な心情風景は揺れ動きます。その描写は入念、ふっくらとした情感の高まり表現も、わずかなテンポの動きと追い込みに説得力充分。清潔な木管が上手いなぁ。(16:26)
第4楽章「断頭台への更新」に於けるティンパニの存在感、怪しい金管のキレや広がり方、空間認識も素晴らしい。ファゴットの間の手の存在感充分。木管云々、なんて書いたけれど金管も文句なく上手いオーケストラですよ。ラスト「イデー・フィクス」は首切り断頭台の露と消えました。(4:46)
第5楽章「魔女の夜宴の夢」はグロテスクなサバト(魔女の饗宴)。時代を考えるとほんまに新しい、強烈な作品ですよ。オーケストラのパワーは充分、圧巻の金管の鳴りっぷり、ラッシュに文句ない追い込み。鐘が少々遠いのが残念。「怒りの日」はファゴットとオフィクレイド(?見たことはない楽器)弦のフーガに金管は強烈な呼応して、コル・レーニョ(特殊奏法なんだとか)も出現、やりたい放題のフィナーレは熱狂的に幕を閉じました。(9:29)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
年末迫って、若い人たちみたいに我ら華麗なる加齢世代には残念、クリスマスはやって来ないかも。昨日日曜は終日曇って最高気温は10度Cに届きません。今朝はいっそう寒い。昨日夜、左足の痙攣発生して難儀しました。寒さのせいかなぁ。今朝の体重は67.05kg+200g、昼に菓子を喰い過ぎました。
息子宅より戻ってまたいつもどおりの変わり映えせぬ生活、朝一番たっぷり洗濯物を外干ししても夕方迄には乾きません。ストレッチは入念に+5分ほどのYouTubeエアロビクス済ませて、市立体育館を目指しました。今週土曜で本年は営業終了して一週間お休み、あと鍛錬は残すところ3-4回。日曜朝は常連メンバーほぼ休み、日曜常連顔見知り二人ほどに空いてましたよ。しっかりゆる筋トレ+エアロバイク15分済ませて、早足ウォーキング帰宅しました。冷蔵庫在庫にメニューを考えて、買い物には寄っておりません。前日高級スーパーにて入手した豆腐はいつもの倍の値段、これが滅茶美味、半分残したものを使い切りました。ま、必殺圧力鍋に材料ぶち込んで味付けちょっぴり加熱、タオルなどでくるんで座布団被せて数時間保存するのみ、圧倒的手抜きパターンはいつもどおり。煮豆も同じです。
本日はこれより爺友より2024年ラスト忘年会。これもいつもと変わらぬ激安酒場+罵詈雑言合戦でしょう。
興味深いブログ記事拝見「録音ビジネスの変遷」。
自分が不安に感じていたこと(時代の流れ)が具体的に言及されておりました。自分は親しいご近所の音楽好きお兄さんとか、音楽専攻だった中学の担任とか、兄の音楽通友人とか出会いが偶然が重なって音楽の世界に接近しました。世代的にはLP(当時贅沢品!)社会人になって最初の冬のボーナスで買ったのはグレン・グールドのBachボックス、それに感激した記憶もあります。その後CDが普及した関係で中古LPは急激に値下がり、一時それを一生懸命集めておりましたよ。
記憶では1994年にLPを最終的に諦めて(ぜんぶ売り払って)廉価盤CDへ切り替え、それが【♪ KechiKechi Classics ♪】のネタ元になっておりました。FMからカセット・エアチェックもたくさんしましたよ、貧しかったので。21世紀に入ると激安CDが出回って廉価盤の存在価値や意味は減って、急速にネットの時代へ、CDの媒体としての寿命は短かったなと思います。LPもオーディオ機器も一部のマニアのものとなったような?
例えばニューヨーク・フィルに於けるヤープ・ファン・ズヴェーデン、ベルリン・フィルのキリル・ペトレンコ辺り、売れ筋演目のCDがベストセラーになる、みたいなことは最近なくなって、FMからの拝聴機会も減りました。ネット配信や実演は盛況なのかも、でも、例えば札幌の痩せた暗い中学生(=大昔の自分)がClassic Musicに出会う機会は減っていることでしょう。リビングに家具調のステレオ・オーディオ機器が揃って、ステキな音楽が流れている~そんな家庭の風景はほぼ消えたと思います。
ネットから流れてくる音楽はどんどん短く、刺激的なリズムばかり。スマホからイヤホンで聴く~パーソナルな時代となりました。拝聴するのにちょっと慣れと根性と時間が必要なClassic Musicは風前の灯なのでしょう。幸い自分はお仕事現役中にCDの処分は完了、完全に音源データ移行が完了して、たっぷり貯まったステキな音楽は老後の愉しみに至っております。我が亡き後にはそのまま打ち捨てられても、問題ないくらいのコンパクトに至っております。
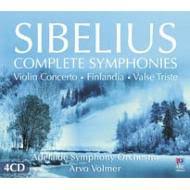 Sibelius 交響曲第5番 変ホ長調/第6番ニ短調/悲しきワルツ~アルヴォ・ヴォルメル/アデレード交響楽団(2007ー8年)・・・
13年前に第2番/第7番を聴いておりました。Arvo Volmer(1962-愛沙尼亞)はもうヴェテランの年齢でしょう。南濠太剌利のアデレードにこんな立派なオーケストラが存在したことも驚き。これは驚くべき充実した演奏、予想外にパワーの不足や響きの薄さ、アンサンブルの弱さをまったく感じさせません。Adelaide Town Hallに於ける優秀録音も特筆すべき水準でしょう。久々のSibeliusをたっぷり堪能いたしました。
Sibelius 交響曲第5番 変ホ長調/第6番ニ短調/悲しきワルツ~アルヴォ・ヴォルメル/アデレード交響楽団(2007ー8年)・・・
13年前に第2番/第7番を聴いておりました。Arvo Volmer(1962-愛沙尼亞)はもうヴェテランの年齢でしょう。南濠太剌利のアデレードにこんな立派なオーケストラが存在したことも驚き。これは驚くべき充実した演奏、予想外にパワーの不足や響きの薄さ、アンサンブルの弱さをまったく感じさせません。Adelaide Town Hallに於ける優秀録音も特筆すべき水準でしょう。久々のSibeliusをたっぷり堪能いたしました。
穏健平和な風情漂う交響曲第5番 変ホ長調は1915年/1919年改定の作品、古典的な二管編成、既にStravinskyが話題になっていた時期(「春の祭典」初演は1913年)だから、保守的と云えばそのとおり、しかし、北欧の冷涼な旅情漂う唯一無二の個性を誇る名曲と思います。実演の方に伺うと独墺系とは異なる特異な話法に戸惑うらしい。
第1楽章「Tempo molto moderato~」茫洋とした遠いホルンから始まる北欧の自然風景。それは不安を孕みながら木管と弦に引き継がれ、パワフルな金管と弦による雄大な輝かしい情景へ爆発します。このテンション、アンサンブルの高揚は文句なし。(13:37)
第2楽章「Andante mosso~」はヴィオラとチェロのピチカートによるシンプルな旋律から始まる変奏曲。途方に暮れた重い足取り、諦め、寂寥が堪らぬ緩徐楽章?なのかな。(9:10)
第3楽章「Allegro molto~」弦の忙しないトレモロから緊張感を高めてデリケート、印象的な低弦のシンプルな繰り返し、それがホルンに引き継がれ、もりもりと成長してスケール大きく、悠々たる清涼な風景が広がりました。ラスト徐々にテンポを落として、終了直前の「間」連続が印象的な作品でした。金管の威力は驚くべき水準。(9:15)
交響曲第6番ニ短調の初演は1923年自らの指揮とのこと。二管編成だけど、バス・クラリネット、ティンパニにハープが加わり弦楽は五部からさらに分割されているそう。これは満天の星、天の川を目指す幻想的な「銀河鉄道交響曲」。破壊的な不協和音や無調時代に、まったく別の繊細な個性が花開いた傑作。
第1楽章「Allegro molto moderato」弱音の細かい音型がきらきらと疾走する幻想的な始まり。これはまるで満天の星空を表現しているよう。転調して印象深い憧憬の旋律が忘れられぬ情景、アデレード交響楽団の弦には深みを感じさせてデリケートですよ。(9:07)
第2楽章「Allegretto moderato - Poco con moto」天空に寂しく浮遊するような木管から始まる寂寥の楽章。儚い風情に低弦はしばらく登場せず、素っ気なくもさらりと終了します。(7:20)
第3楽章「Poco vivace」スケルツォのリズムが弾むけれど、ここも囁くような静かなユーモラスを感じさせるところ。やがて執拗にしっかりとした足取りに緊張感を高めて終了。(3:47)
第4楽章「Allegro molto - Doppio piu lento」悲しくも高貴な旋律から始まって、弦と木管が神妙に呼応します。やがて切迫する旋律に緊張感を高めて決然、弾むリズムに明るい歩みが続くけれど、どこか寂しい。(11:05)
「悲しきワルツ」とっても悲しく、優しい、寂しいワルツも絶品。途中テンポを上げて効果的。(4:49)
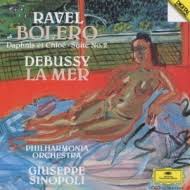 Ravel ボレロ/バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲/交響的素描「海」~ジュゼッペ・シノーポリ/フィルハーモニア管弦楽団(1988年)・・・Giuseppe Sinopoli(1946ー2001伊太利亜)は医者の不養生に早く亡くなって残念、これは忘れられたと云うか、話題にならなかった演奏。ネットを探るとこの「ボレロ」演奏への言及を発見、曰く
Ravel ボレロ/バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲/交響的素描「海」~ジュゼッペ・シノーポリ/フィルハーモニア管弦楽団(1988年)・・・Giuseppe Sinopoli(1946ー2001伊太利亜)は医者の不養生に早く亡くなって残念、これは忘れられたと云うか、話題にならなかった演奏。ネットを探るとこの「ボレロ」演奏への言及を発見、曰く
なんとも破裂的なフレージングで、野蛮というか、お世辞にも綺麗な演奏とは言えない
なんて野蛮なんだ!音が汚いっ
なるほどなぁ、音質もクリアに迫力があって、細部曖昧さのないかっちりとして元気の良い、ラスト盛り上がる演奏と思うけどなぁ。但し、各パート出番を思いっきり歌わせるような自発性や色気、陰影には足りない感じはありますよ。テンションの高い「ダフニス」、雄弁な「海」もそうだけど、鋭角なリズムに正確なクリアなサウンドは仏蘭西のセンスとはなにかまったく違うものなのかも。でも、緻密だし、自在なオーケストラコントロールが効いてアンサンブルはかっちりしているし、けっこう好きですよ、こんな明るい明晰な演奏。ステキな絵画はRaoul Dufy「Nu dans l'atelier rouge de Vence」(1945)(14:11/6:37-6:35-4:57/9:56-7:27-9:00)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
ほとんど曇り空、寒いですねぇ年末は。毎年この時期こんなんでしたっけ。夜半には雨が降り出して雷もありました。温泉に行きたいなぁ、予定はないけれど。
 前日は孫との終わりなきバトルに疲れ果て珍しく熟睡、そして昨日はいつも通り早朝覚醒、持参した台湾名物胡椒餅を温めて、高級珈琲メーカー・デロンギから美味しくいただき、早めにJR神戸線の魚住駅を目指しました。駅前のビルはちょっと時代を感じさせて、けっこうな坂を上ったら、やや草臥れた住宅街に空き家もぼちぼち全国各地同じ情景。新しいマンションも建って、古い家も建て替わって息子が長期ローンに一戸建てを入手、男の子二人大騒ぎだからそれががよろしいでしょう。至近にラーメン屋焼き鳥屋居酒屋キムチ屋など、そのラーメン屋は有名らしく、昼には行列ができるとの息子情報でした。自分はその道路を挟んだ向かい、末枯(すが)れたラーメン台北(餃子も名物とか)に妙にソソられたけれど、開店時間には覗けませんでした。歴史のあるところらしくて、明治時代以来の溜池有、駅への下り坂の途中にかなり広大に荒れ果てた原野風墓場有、我が街のご近所にも(駅前にも)小さな墓場があって、それは町内会が管理して美しく整備されております。しかし今回通りがかった墓場は草ぼうぼう~不思議な光景でした。
前日は孫との終わりなきバトルに疲れ果て珍しく熟睡、そして昨日はいつも通り早朝覚醒、持参した台湾名物胡椒餅を温めて、高級珈琲メーカー・デロンギから美味しくいただき、早めにJR神戸線の魚住駅を目指しました。駅前のビルはちょっと時代を感じさせて、けっこうな坂を上ったら、やや草臥れた住宅街に空き家もぼちぼち全国各地同じ情景。新しいマンションも建って、古い家も建て替わって息子が長期ローンに一戸建てを入手、男の子二人大騒ぎだからそれががよろしいでしょう。至近にラーメン屋焼き鳥屋居酒屋キムチ屋など、そのラーメン屋は有名らしく、昼には行列ができるとの息子情報でした。自分はその道路を挟んだ向かい、末枯(すが)れたラーメン台北(餃子も名物とか)に妙にソソられたけれど、開店時間には覗けませんでした。歴史のあるところらしくて、明治時代以来の溜池有、駅への下り坂の途中にかなり広大に荒れ果てた原野風墓場有、我が街のご近所にも(駅前にも)小さな墓場があって、それは町内会が管理して美しく整備されております。しかし今回通りがかった墓場は草ぼうぼう~不思議な光景でした。
息子夫婦宅は今時なんかなぁ、新築ぴかぴかのお家に食卓も電気製品もけっこうオシャレな最新型揃えて、こどもが小さいから乾燥機も有。お風呂のシャワーヘッドもなんか売っているじゃないですか、特別な機能付きが、あれですよ。贅沢なおもちゃも膨大だし、お菓子もたくさん、まだまだ食材管理や整理整頓に課題は残るのはあたりまえですよ。Netflixも契約していて「地面師たち」噂通り凄いドラマ二話ほど堪能して、ピエール瀧も復活しておりました。なにを考えたかというと、我が家は(流行りの/世間で云うところの)断捨離ほぼ完了、家具も女房殿の立派な嫁入り道具はすべて処分済に超安物壊れ掛け最低限のみ配置、電気製品も「壊れるまで!大切に使う」主義、電子レンジは既に40年が経ちました。シャンプーなどほんま安物(女房殿はお嫁さんのを使って感動/さっそく帰りに同じものを入手)我らはとことん節約が過ぎる!そう自覚いたしました。もっと生活に不要不急な潤いを!ま、現役時代の商売柄美味いもんへの(要らぬ)知識はあって、いろいろ喰っているけどね。家具辺りから順繰り買い替えようかな?
駅にある高級スーパーにて黒豆購入、いまや超贅沢品に至った丹波は買う勇気が出ず、この間アクが抜けず二度失敗した北海道産晩生光黒大豆(それでも業務スーパーのほぼ倍の価格)の品質を信じて圧力鍋に煮ました。味は上々。帰宅して洗濯ものは大量でした。これから市立体育館に鍛えて、明日爺友との第2回忘年会。今朝の体重は66.85kg+150g。昨日はけっこう喰ったからね。
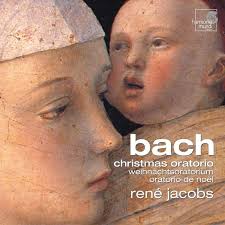 12月はBach。
Bach クリスマス・オラトリオ BWV.248(第2部/第3部)~ルネ・ヤーコプス/ベルリン古楽アカデミー/RIAS室内合唱団/ドロテア・レッシュマン(s)/アンドレアス・ショル(ct)/ヴェルナー・ギューラ(t)/クラウス・ヘーガー(b)(1997年)・・・Rene Jacobs(1946-白耳義)はもともとカウンター・テナーの人。過激なリズムを刻む?ベルリン古楽アカデミーと精緻な声楽アンサンブルに定評あるRIAS室内合唱団との演奏を聴いてみました。これが尖ったリズムに非ず、サウンドは粗野や素朴より、思わぬしっとりジミな穏健バランスに落ち着いております。テンポも特別に速いとは感じない。エヴァンゲリストであるWerner Gu"ra(1964ー独逸)はイメージ刷り込みなシュライヤー辺りに比べればずいぶんと淡々、カウンター・テナーであるAndreas Scholl(1967-独逸)の決然とした説得力はアルトでは出せぬ力感、そしてRIAS室内合唱団の透明な洗練は期待通り。声楽陣はソロが際立たず、器楽アンサンブルも含め全体サウンドに溶け合って敬虔な気分を堪能できました。無粋に無宗教な粗忽もの(=ワシ)の心は鎮静いたしました。
12月はBach。
Bach クリスマス・オラトリオ BWV.248(第2部/第3部)~ルネ・ヤーコプス/ベルリン古楽アカデミー/RIAS室内合唱団/ドロテア・レッシュマン(s)/アンドレアス・ショル(ct)/ヴェルナー・ギューラ(t)/クラウス・ヘーガー(b)(1997年)・・・Rene Jacobs(1946-白耳義)はもともとカウンター・テナーの人。過激なリズムを刻む?ベルリン古楽アカデミーと精緻な声楽アンサンブルに定評あるRIAS室内合唱団との演奏を聴いてみました。これが尖ったリズムに非ず、サウンドは粗野や素朴より、思わぬしっとりジミな穏健バランスに落ち着いております。テンポも特別に速いとは感じない。エヴァンゲリストであるWerner Gu"ra(1964ー独逸)はイメージ刷り込みなシュライヤー辺りに比べればずいぶんと淡々、カウンター・テナーであるAndreas Scholl(1967-独逸)の決然とした説得力はアルトでは出せぬ力感、そしてRIAS室内合唱団の透明な洗練は期待通り。声楽陣はソロが際立たず、器楽アンサンブルも含め全体サウンドに溶け合って敬虔な気分を堪能できました。無粋に無宗教な粗忽もの(=ワシ)の心は鎮静いたしました。
第2部「降誕節第2祝日用 (12月26日)」
第10曲「シンフォニア」は牧歌的に平穏な風情、独立して有名なところ(7:59)/第11曲 レチタティーヴォ「このあたりに羊飼いがおりて」(0:40)/第12曲 コラール「差し出でよ、汝美わしき朝の光よ」心洗われる清潔なコラール(1:30)/第13曲 レチタティーヴォ「御使彼らに言う」(0:42)/第14曲 レチタティーヴォ「神いにしえの日アブラハムに約し給いしことの」(0:38)/第15曲 アリア「喜べる羊飼いらよ、急げ、とく急ぎて行けや」テナーの清潔なソロに+フラウト・トラヴェルソ・オブリガートのジミな音色が堪らぬ魅力(3:25)/第16曲 レチタティーヴォ「かつその徴として」(0:20)/第17曲 コラール「かの暗き畜舎に伏す者」(0:56)/第18曲 レチタティーヴォ「さらば行けかし」(0:51)/第19曲 アリア「眠りたまえ、わが尊びまつる者、安けき憩いを楽しみ」絶品のカウンターテナー・ソロに控えめなオーボエが寄り添います(10:14)/第20曲 レチタティーヴォ「するとたちまち御使のもとに」(0:15)/第21曲 合唱「いと高き所には神に栄光あれ」躍動する歓喜。素晴らしいアンサンブル。(2:19)/第22曲 レチタティーヴォ「その調べもて、汝ら御使よ、歓呼して歌えかし」(0:24)/第23曲 コラール「われらは汝の軍勢にま交りて歌いまつらん」(1:52)
第3部「降誕節第3祝日用 (12月27日)」
第24曲 合唱「天を統べたもう者よ、舌足らずの祈りを聞き入れ」ティンパニがトントントンと刻んでトランペットが高らかに、素朴な喜びに充ちて心温まる始まり。これは自分が未だ20歳代、入院中のクリスマスの早朝FM放送から流れて心奪われた「クリスマス・オラトリオ」との出会いでした。(ハンス=マルティン・シュナイト)(1:59) /第25曲 レチタティーヴォ「御使たち去りて天に行きしとき」(0:09)/第26曲 合唱「いざ、ベツレヘムに行きて」(0:40)/第27曲 レチタティーヴォ「主はその民を慰めたまえり」(0:37)/第28曲 コラール「主この全てをわれらになし給いしは」絶品の声楽アンサンブル(0:57)/第29曲 アリア(二重唱)「主よ、汝の思いやり、汝の憐れみは」軽妙なオーボエに支えられてソプラノとテナーの明朗なデュオ(7:05)/第30曲 レチタティーヴォ「かくて彼ら急いで」(1:24)/第31曲 アリア「わが心よ、この幸なる奇蹟をば」ヴァイオリンと通奏低音が哀愁絶品の掛け合い、朗々としたカウンターテナーの説得力(4:54)/第32曲 レチタティーヴォ「然り、わが心には必ずや内に保たん」(0:24)/第33曲 コラール「われは御身をひたすらに保ち」(1:12)/第34曲 レチタティーヴォ「しかして羊飼いらは再び踝を回して帰り」(0:26)/第35曲 コラール「喜び楽しめ」(1:03)/第24曲(繰り返し) 合唱「天を統べたもう者よ、舌足らずの祈りを聞き入れ」冒頭の浮き立つような気分が回帰されました。(1:48)
CD収録ではラスト3曲が2枚目に押し出されて興醒め、データ拝聴では関係ありませんが。
 Shostakovish 交響曲第1番ヘ短調(1992年)/第12番ニ短調「1917年」(2006年)~マキシム・ショスタコーヴィチ/プラハ交響楽団・・・いずれもライヴとのこと。Maxim Shostakovich(1938-露西亜→亜米利加)は偉大なる親父直系の息子だから正統派の解釈、そんな声もあったけれどそうかなぁ、別に関係ないと思うけれど。もう引退年齢でしょう。プラハ交響楽団とライヴ全集録音というのもちょっと意表を突かれる感じ、音質は上々です。微妙に素朴なサウンド、あまり切れるようなアンサンブルじゃない味わい系。
Shostakovish 交響曲第1番ヘ短調(1992年)/第12番ニ短調「1917年」(2006年)~マキシム・ショスタコーヴィチ/プラハ交響楽団・・・いずれもライヴとのこと。Maxim Shostakovich(1938-露西亜→亜米利加)は偉大なる親父直系の息子だから正統派の解釈、そんな声もあったけれどそうかなぁ、別に関係ないと思うけれど。もう引退年齢でしょう。プラハ交響楽団とライヴ全集録音というのもちょっと意表を突かれる感じ、音質は上々です。微妙に素朴なサウンド、あまり切れるようなアンサンブルじゃない味わい系。
若き日、栴檀は双葉より芳しい交響曲第1番ヘ短調はステキな才気知った走った作品だけれど、そんな風から遠いぱっとしない感じの演奏。第1楽章「Allegretto」(8:22)第2楽章「Allegro」(4:40)第3楽章「 Lento」(9:37)第4番「Allegro molto」(10:04)
第12番ニ短調はカッコよい疾走から始まる第1楽章「革命のペトログラード(Moderato - Allegro)」は大衆的な旋律がわかりやすい。アンサンブルは甘く、プラハ交響楽団は上手いオーケストラじゃないけれど、勢いと雰囲気はありますよ。(13:40)
第2楽章「ラズリーフ(Adagio)」は思索的な緩徐楽章。第1楽章と同じ旋律も登場。若い頃難解な作風に四苦八苦していたのがウソのように、美しい静謐、弦と木管による平易な旋律サウンドがが快いもの。粗野に不器用なトロンボーンも泥臭い音色が個性的でした。(11:48)
第3楽章「巡洋艦アヴローラ(Allegro)」いよいよ十月革命の火蓋が切られる描写。前楽章の蠢く静謐の流れから始まって、徐々に熱を帯びて切迫感は高まって、クライマックスの打楽器の迫力や切れ味、テンションがまったく足りない。縦線も揃っていません。ここが決まるとカッコ良いところなんやけどなぁ。(4:39)
第4楽章「人類の夜明け(L'istesso tempo - Allegretto - Moderato)」勝利のファンファーレも遠慮気味、その後の締め括りもいまいち煮えきらぬ感じ。第1楽章の晴れやかな旋律が戻っても、オーケストラの非力が目立って、なんか後半戦に向けて竜頭蛇尾っぽい残念なラストでした。(10:59/盛大なる拍手有)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
昨日も全国的に気温は低く、そして好天。朝一番の洗濯は少なめ、ストレッチもしっかり、前日不本意な中断となったYouTubeエアロビクスも済ませて、市立体育館を目指しました。今度は水筒の蓋をしっかり確認していつもの筋トレ+エアロバイク(有酸素運動15分)消化して帰宅。年末迫ってトレーニングルームはガラガラ、自分含めて常連老中男女5人しかおりません。皆、忙しいのですね。それから婆さんを施設一時預かりに送り出した女房殿と合流、梅田を目指しました。二人の孫は高級ビスケットが好きとのこと、阪神百貨店にてステキな菓子ならぬ台湾胡椒餅を入手し、いつもの梅田駅前ビル地下で寿司唐揚げなど美味いもん+生ビール2杯ほど。自分はけっこうな頻度で出掛けているけれど、女房殿は滅多に出掛けませんから。でも、前日女子会に高級昼食を堪能してきたらしい。
インフルエンザ、マイコプラズマ、コロナのトリプルデミック大流行に薬不足が追い打ちを掛けているとのこと。この騒動に政府厚労省は無策のように見えます。好まぬマスクをしっかり付けて出掛けました。息子の立派な新居は初訪問、女房殿は転居の手伝いに出掛けたけれど爺は役に立たずお呼びが掛かりませんでした。孫とじっさいに逢ったのは夏以来?写真や動画では眺めていたけれど、5歳と2歳(年明け正月には3歳)育ち盛り、ずいぶんと大きくなってその激しい攻撃に疲れ果てました。夜、慣れぬ寝床でも熟睡。息子の住まう街はもちろん初訪問、その暮らしぶりには感慨があって、その件はまた別途。朝食を軽く摂って早々に帰宅しました。最寄りの駅の高級スーパーにてお米ほか、ちょっと贅沢な買い物済ませてコミュニティバスにて帰宅いたしました。参考記録だけれど、昼前の計量は66.7kg▲100g。
 Scho"nberg オーケストラのための5つの小品 作品16(1909年/1922年改定)/Webern オーケストラのための5つの小品 作品10(1923年初演)/Berg オーケストラのための3つの小品 作品6(1923年初演/1962年録音)/歌劇「ルル」組曲*(1934年初演/1961年録音)~アンタル・ドラティ/ロンドン交響楽団/ヘルガ・ピラルツィク(s)*・・・一時あれほど入れ込んで聴いていたのに、最近疎遠になっていた新ウィーン楽派の音楽。Mercuryによる60年以上前の録音はリアルに現役、素晴らしい定位と臨場感ですよ、ピエール・モントゥー時代のロンドン交響楽団は驚くほどパワフル、緻密に洗練された怜悧な響きはあまりの衝撃に三度繰り返して聴きましたよ。デリケートに暴力的、妖しい静謐と破壊的大音量の不協和音、嗤われるかも知れんけどMahlerが熟しすぎて辿り着く先、みたいな爛熟した手応え充分。好きな音楽ですねぇ、なんか病みつきになりそう。
Scho"nberg オーケストラのための5つの小品 作品16(1909年/1922年改定)/Webern オーケストラのための5つの小品 作品10(1923年初演)/Berg オーケストラのための3つの小品 作品6(1923年初演/1962年録音)/歌劇「ルル」組曲*(1934年初演/1961年録音)~アンタル・ドラティ/ロンドン交響楽団/ヘルガ・ピラルツィク(s)*・・・一時あれほど入れ込んで聴いていたのに、最近疎遠になっていた新ウィーン楽派の音楽。Mercuryによる60年以上前の録音はリアルに現役、素晴らしい定位と臨場感ですよ、ピエール・モントゥー時代のロンドン交響楽団は驚くほどパワフル、緻密に洗練された怜悧な響きはあまりの衝撃に三度繰り返して聴きましたよ。デリケートに暴力的、妖しい静謐と破壊的大音量の不協和音、嗤われるかも知れんけどMahlerが熟しすぎて辿り着く先、みたいな爛熟した手応え充分。好きな音楽ですねぇ、なんか病みつきになりそう。
Scho"nbergは四管編成+打楽器6種+ハープ+チェレスタの大編成。異様な緊張感と色彩が散りばめられた無調音楽。息を潜めたような透明な美しさを感じます。初演は1912年、ヘンリー・ウッドとは意外でした。
「予感」非常に速く。(Vorgefuhle, Sehr rasch)追い込まれ切羽詰まった厳しいリズムと不協和音(2:02)
「過去」穏やかに(Vergangenes, Massig)途方に暮れた不安が漂う静謐が美しいところ・チェレスタが印象的(5:43)
「色彩」穏やかに(Farben, Massig)落ち込むような鎮静継続。(3:39)
「急転」非常に速く(Peripetie, Sehr rasch)金管のキレは衝撃的な絡み合い。さきほどの鎮静と交互に叫んでも、それは知的に感じます。(2:34)
「オブリガート・レチタティーヴォ」激しく動いて(Das obligate Rezitativ, Bewegen)いや増すうねうねとした不安がせり上がって、危機が迫ります。不協和音がクリアにとても美しい。(3:47)
Webernの編成はフルートは一本、弦楽に+打楽器は8種+ハルモニウム、チェレスタ、マンドリン、ギター、そしてハープ、編成はセレナーデ?「非常に静かに、そして繊細に」/「生き生きと、そして繊細な動きをもって」/「非常にゆっくり、そして極めて静かに」/「流麗に、極めて繊細に」/「非常に流麗に」連続4:16の短いもの。激しい狂気と冷たくもデリケートに透明な静謐が同居しております。
Bergはいちばん有名かな?拡大された四管編成とか?打楽器11種+ハープ2台、とてつもなく大きな、そして破壊的に美しい作品。
第1楽章 前奏曲(Praludium)(423)/第2楽章 輪舞(Reigen)ここはパワフルに雄弁から静謐に収束(5:03)/第3楽章 行進曲(Marsch)これは異形なリズムを刻んで絶叫する重苦しい行進曲。ラストあたり「運命の動機」を刻むホルン先頭にロンドン交響楽団の威力が凄い。(8:53)
「ルル」はオペラから抜き出した、濃厚に甘過ぎる浪漫がはみ出して腐り掛け、狂気に至る音楽。三管編成に+11種の打楽器+ハープ、ピアノ。「Rondo」(16:22)「Ostinato」(3:43)「ルルの歌」(2:14)「Variations」(4:36)「Adagio」(8:59)
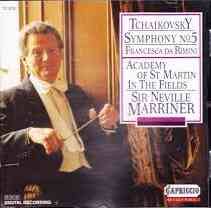 Tchaikovsky 交響曲第5番ホ短調~ネヴィル・マリナー/ジ・アカデミー・イブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ(1992年)・・・Neville Marriner(1924-2016英国)がTchaikovskyの交響曲全集を録音していたとは意外でした。どうも世間の評判はよろしくないらしくて「チャイコフスキーの交響曲をASMIFで聴こうということがそもそも間違いでは?」とのレビューは、かつて云いたい放題某著名な評論家U氏のマネでしょう。音楽は嗜好品だから好き好きなんすよ、各々個性を愉しめばよろしい。この作品は大好きでして、某サイトに執拗に「イマイチ人気がない」と論拠不明な主張を繰り返していたのを見掛けたもの。三管編成+ティンパニ、「運命の主題」先頭にたっぷり例の甘い旋律横溢した傑作ですよ。但し、この演奏を嫌う理由はわからんでもない、ほぼ予想通りの素直過ぎオーソドックスな面白みやアクの足りない?スッキリ表現でした。
第1楽章「Allegro con anima」(14:19)/第2楽章「Andante cantabile」(12:19)/第3楽章「Allegro moderato」(13:09)/第4楽章「Allegro vivace」(24:03)
Tchaikovsky 交響曲第5番ホ短調~ネヴィル・マリナー/ジ・アカデミー・イブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ(1992年)・・・Neville Marriner(1924-2016英国)がTchaikovskyの交響曲全集を録音していたとは意外でした。どうも世間の評判はよろしくないらしくて「チャイコフスキーの交響曲をASMIFで聴こうということがそもそも間違いでは?」とのレビューは、かつて云いたい放題某著名な評論家U氏のマネでしょう。音楽は嗜好品だから好き好きなんすよ、各々個性を愉しめばよろしい。この作品は大好きでして、某サイトに執拗に「イマイチ人気がない」と論拠不明な主張を繰り返していたのを見掛けたもの。三管編成+ティンパニ、「運命の主題」先頭にたっぷり例の甘い旋律横溢した傑作ですよ。但し、この演奏を嫌う理由はわからんでもない、ほぼ予想通りの素直過ぎオーソドックスな面白みやアクの足りない?スッキリ表現でした。
第1楽章「Allegro con anima」(14:19)/第2楽章「Andante cantabile」(12:19)/第3楽章「Allegro moderato」(13:09)/第4楽章「Allegro vivace」(24:03)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
2014年もあと10日ほど、ぐっと冷える日々が続きますね。昨日も終日曇って寒風が吹きました。本日はこれから午前中いつもの鍛錬、昼から昼呑み経由孫のお守りに出掛けて息子一家の新宅に泊まるので、梅田でなにか美味しいものでも買っていきましょう。
昨日朝大量の洗濯済ませてストレッチ、さてYouTubeエアロビクスでも、テレビからFireStickを立ち上げてスタート・・・させたら途中フリーズ、諦めました。しばらく休ませてから必殺!「困ったときの再起動(自分が作った迷言)」電源引き抜いて再起動させたら無事稼働しました。結果、昨日は引き隠りまったく身体を動かしておりません。今朝の体重は66.8kgほぼ変わらず、かっぱえびせん袋喰うたけど、セーフ。
いつものSimplenoteにアクセスすると「これはウィルスの可能性」警告有、そのままムリムリ継続させると自分の保存頁が無事出現いたしました。ノンビリ動画など眺めて、来日した若い印度人女性によると印度のこども達は「忍者ハットリくん」が大好きとのこと。日本のアニメの威力恐るべし!1991年伊太利亜に出張した時に、ホテルのテレビではタイガーマスクが伊太利亜語を話しておりました。「はいからさんが通る」も放映してましたっけ。
北九州中学生刺殺事件の容疑者逮捕とのこと、詳細続報を待ちましょう。千葉県では高騰する野菜価格を受けて、相次いでキャベツの大量窃盗事件。犯人探しは難しいのか、なんせキャベツには製造番号も付いておりませんし。独自の流通経路があるのでしょうか。生産者の嘆きと脱力は想像に余りあります。保険みたいなものはないのでしょうか。
「男女が血だらけで倒れている」複数の刺し傷・切り傷/付近では住宅8棟全焼する火事も(千葉・柏市)年末迫ってまたまた幾度繰り返される物騒な事件、大丈夫か日本。
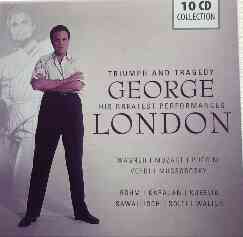 Wagner 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より ハンス・ザックスのモノローグ2曲(Knappertsbusch/1958/Wien/Studio)/ 舞台神聖祭典劇「パルジファル」より "Ja, wehe!.." (Knappertsbusch/Bayreuth/1951live)/ 楽劇「ラインの黄金」よりヴォータンとして3曲(Flagstad/Svanholm/Neidlinger/Solti 1958/Wien/Studio)/楽劇「ヴァルキューレ」より Wotans Abschied(Knappertsbusch/1958/Wien/Studio)~ジョージ・ロンドン(b)・・・寄せ集めGeorge London(1920-1985亜米利加)Triumph and Tragedy10枚組より。基本的に部分切り取り寄せ集め音源はご遠慮なんやけど、オペラは別。長時間集中して聴き通すのは自分にとって難物ですから。これはわずか47歳に咽の不調からキャリアを断念した往年の名バス、定評あるWagner録音を集めた一枚、音質はどれも良好でした(とくに「ラインの黄金」)。オペラ拝聴機会の少ない自分としては生真面目に重厚なバスと云えばこの人、重心の低い艶のある声、圧巻の存在感連続技。どれを聴いても納得、収録作品はほとんど馴染のものばかり、ウィーン・フィルやバイロイト、立派なオーケストラの響きも堪能いたしました。(6:31-7:34/8:07/10:53-16:48-3:38/17:35)
Wagner 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より ハンス・ザックスのモノローグ2曲(Knappertsbusch/1958/Wien/Studio)/ 舞台神聖祭典劇「パルジファル」より "Ja, wehe!.." (Knappertsbusch/Bayreuth/1951live)/ 楽劇「ラインの黄金」よりヴォータンとして3曲(Flagstad/Svanholm/Neidlinger/Solti 1958/Wien/Studio)/楽劇「ヴァルキューレ」より Wotans Abschied(Knappertsbusch/1958/Wien/Studio)~ジョージ・ロンドン(b)・・・寄せ集めGeorge London(1920-1985亜米利加)Triumph and Tragedy10枚組より。基本的に部分切り取り寄せ集め音源はご遠慮なんやけど、オペラは別。長時間集中して聴き通すのは自分にとって難物ですから。これはわずか47歳に咽の不調からキャリアを断念した往年の名バス、定評あるWagner録音を集めた一枚、音質はどれも良好でした(とくに「ラインの黄金」)。オペラ拝聴機会の少ない自分としては生真面目に重厚なバスと云えばこの人、重心の低い艶のある声、圧巻の存在感連続技。どれを聴いても納得、収録作品はほとんど馴染のものばかり、ウィーン・フィルやバイロイト、立派なオーケストラの響きも堪能いたしました。(6:31-7:34/8:07/10:53-16:48-3:38/17:35)
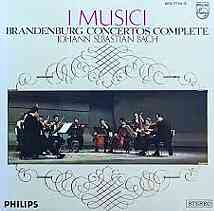 Bach ブランデンブルク協奏曲第1番ヘ長調/第2番ヘ長調/第3番ト長調(1965年)/ヴァイオリン協奏曲ホ長調BWV1042(1958年)~イ・ムジチ/フェリックス・アーヨ(v)・・・往年の名手揃えた旧録音。駅売海賊盤だっけ?自分にとっては懐かしい演奏だけど、ようやく.flac音源をネットより入手できました。喜んで聴き出したけれどちょっぴり”う~む”状態。ややデッドに残響奥行き不足、60年を経ての音質劣化は覚悟の上、第2番ヘ長調はリコーダーに非ずフルート使用(セヴェリーノ・ガッゼローニ)やモダーン楽器使用云々するつもりなし、トランペットは名手Maurice Andre(1933-2012仏蘭西)は嚠喨(りゅうりょう)として洗練、最近耳慣れたたどたどしい古楽器トランペットとは風情がまったく異なります。悪くないけど全体に狩りの雰囲気ある闊達な第1番ヘ長調含め、微妙にノンビリとして明るく中庸、フツウというか中途半端に昔、といった失礼な印象でした。素晴らしい活気ある合奏協奏曲である第3番ト長調は、愉悦に充ちた表情、自然な熱気が横溢。第2楽章はシンプルな二つの和音のみ。ヴァイオリン協奏曲は残響たっぷり豊かに響いて、カリッとしたFelix Ayo(1933-2023西班牙)のステキなヴィヴラート、これは明るく豊かな蠱惑の音色が滔々と歌って絶品。夢見るような、ちょっと明るい軽い、そしてオーソドックスなBach。
Bach ブランデンブルク協奏曲第1番ヘ長調/第2番ヘ長調/第3番ト長調(1965年)/ヴァイオリン協奏曲ホ長調BWV1042(1958年)~イ・ムジチ/フェリックス・アーヨ(v)・・・往年の名手揃えた旧録音。駅売海賊盤だっけ?自分にとっては懐かしい演奏だけど、ようやく.flac音源をネットより入手できました。喜んで聴き出したけれどちょっぴり”う~む”状態。ややデッドに残響奥行き不足、60年を経ての音質劣化は覚悟の上、第2番ヘ長調はリコーダーに非ずフルート使用(セヴェリーノ・ガッゼローニ)やモダーン楽器使用云々するつもりなし、トランペットは名手Maurice Andre(1933-2012仏蘭西)は嚠喨(りゅうりょう)として洗練、最近耳慣れたたどたどしい古楽器トランペットとは風情がまったく異なります。悪くないけど全体に狩りの雰囲気ある闊達な第1番ヘ長調含め、微妙にノンビリとして明るく中庸、フツウというか中途半端に昔、といった失礼な印象でした。素晴らしい活気ある合奏協奏曲である第3番ト長調は、愉悦に充ちた表情、自然な熱気が横溢。第2楽章はシンプルな二つの和音のみ。ヴァイオリン協奏曲は残響たっぷり豊かに響いて、カリッとしたFelix Ayo(1933-2023西班牙)のステキなヴィヴラート、これは明るく豊かな蠱惑の音色が滔々と歌って絶品。夢見るような、ちょっと明るい軽い、そしてオーソドックスなBach。
第1番ヘ長調BWV1046/エーリヒ・ペンゼル/ゲルト・ハウケ(hr)/ハインツ・ホリガー/モーリス・ブルグ/ハンス・クル(ob)/カール・ヴァイス(fg)/フェリックス・アーヨ(v)(4:22-4:59-4:51-8:08)/第2番ヘ長調BWV1047/モーリス・アンドレ(tp)/セヴェリーノ・ガッゼローニ(fl)/ハインツ・ホリガー(ob)/フェリックス・アーヨ(v)(5:22-4:30-3:07)/第3番ト長調BWV1048(6:11-0:17-5:21)/ヴァイオリン協奏曲ホ長調BWV1042(9:22-7:13-3:12)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
北九州に続いて、神戸三宮でも刺される事件発生、幸い被害者の生命は大丈夫らしいけれど、やはり「見知らぬ人」らしい。先の事件に影響を受けたのでしょうか。日本の治安は危ういと感じます。
好天が続いております。今週末金曜は息子夫婦が各々職場の忘年会、夕方より孫のお守りに夫婦で泊まってお留守番を頼まれました。昼呑みして美味いもんでも喰ってから出掛けましょう。昨日朝もいつもどおりの洗濯ストレッチ、YouTube「全身脂肪燃焼ワークアウト15分/ジャンプ禁止、会話禁止」済ませてから市立体育館を目指しました。途中、熱心にゴミ拾いの功徳を続けていたら・・・妙にお尻の辺りが冷たい・・・到着して運動靴を取り出したら・・・リュックの底もお尻もびしょ濡れ。なんと不覚にも水筒の蓋がちょろ締め状態に水が流れて、仕方がないので(周りにバレぬよう)筋トレはいつも通り、使ったあとはていねいに拭き取って完了。エアロバイク(有酸素運動)は水分補給がないので断念、さっさと帰宅しました。帰り道もお尻が冷たい。急ぎ着替えました。今朝の体重は66.85kg▲150gあまり変わらない。
自分は初耳、よう知らんけど人気のスリー・ピースロックバンド「打首獄門同好会」(2004年結成/バンド名は「遠山の金さん」より)のベーシスト・JUNKOさん(65)の記事がネットに出現。自分とほぼ変わらん年齢、現役ばりばりのライヴ活動と若々しい容姿に驚きました。まさに「人類の奇跡」!日々熱心にジムに鍛えているそう。心身ともに充実しているんやろなぁ。「日本の米は世界一」「きのこたけのこ戦争」「私を二郎に連れてって」などの曲があるらしい。インディーズのマニアックなバンドはメンバーチェンジを繰り返してもう20年、立派です。その勇姿に憧れます。ま、音楽の嗜好は違うけど。
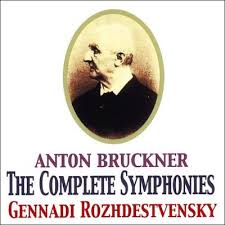 Bruckner 交響曲第4番 変ホ長調(1874年第1稿)~ゲンナジ・ロジェストヴェンスキー/ソヴィエット国立文科省交響楽団(1987年)・・・Gennady Rozhdestvensky(1931-2018露西亜)みたいにアクの強い個性的な指揮者がどんどん消えていきます。かなりの版を揃えたBruckner交響曲全集を録音しておりました。(第4番は3種+1878年稿終楽章異稿「民衆の祭り」)荘厳壮麗な構築物みたいなBrucknerとはまったく別物、とても賑やかにデーハーに泥臭い、パワフルな叫び連続。期待通りの強烈剥き出しな金管が堪能できます。「ロマンティック」との愛称もある、わかりやすい旋律の作品は・・・
Bruckner 交響曲第4番 変ホ長調(1874年第1稿)~ゲンナジ・ロジェストヴェンスキー/ソヴィエット国立文科省交響楽団(1987年)・・・Gennady Rozhdestvensky(1931-2018露西亜)みたいにアクの強い個性的な指揮者がどんどん消えていきます。かなりの版を揃えたBruckner交響曲全集を録音しておりました。(第4番は3種+1878年稿終楽章異稿「民衆の祭り」)荘厳壮麗な構築物みたいなBrucknerとはまったく別物、とても賑やかにデーハーに泥臭い、パワフルな叫び連続。期待通りの強烈剥き出しな金管が堪能できます。「ロマンティック」との愛称もある、わかりやすい旋律の作品は・・・
オンマイクに露西亜の強烈な色彩ホルンに驚きつつ第1楽章「Allegro」が始まったら、例の遠いホルンの動機(あちこち素材)はいっしょだけど、ぜんぜん違う作品じゃん!例の隈取はっきりアクの強い演奏を愉しんでおりました。サイト内検索したら幾度この版は聴いていて、記憶はほとんど残っていない情けなさ。これがネコにコンバンハ状態。ちょっと気紛れにまとまりのない粗削りな作品に感じるのは、ロジェストヴェンスキーの個性なのか?他の演奏も聴いてみないと判断が付きません。(20:11)
第2楽章「Andante quasi Allegretto」も馴染んだ旋律とはかなり違うもの。途中劇的なクライマックスはそうとうに刺激的でした。(18:59)
第3楽章「Scherzo (Bewegt) and Trio (nicht zu schnell)」は馴染みの草原の狩りのスケルツォとはまったく別物。鬱陶しくも途方に暮れたホルン・ソロが幾度しつこく繰り返されて(これはマイルドな響きに相当の実力者)暗い風情が連続して劇的。トリオは優雅にたっぷり歌ってその対比は美しいもの。(15:21)
第4楽章「Finale (Bewegt, doch nicht zu schnell)」第1楽章の素材や馴染みのフィナーレの片鱗がが登場しても、かなり、ほとんど違うもの。なにやらウキウキするような美しい場面もあり、切迫した場面も有、まとまりがない?混乱しているように感じるのは先入観でしょう。ロジェストヴェンスキーは表情濃厚に多彩に変化して朗々、オーケストラの鳴りっぷりはストレス解消に最高。(21:49)
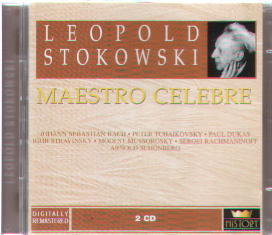 Stravinsky バレエ音楽「春の祭典」~レオポルド・ストコフスキー/フィラデルフィア管弦楽団(1929/30年)・・・17年ぶりの拝聴。Leopold Stokowski(1882-1977英国)の「春の祭典」はこれしか録音しなかったはず(自信はない)。初演が1913年だったからまだほやほやの新しい音楽だったはず、これはSP復刻だからダイナミックレンジが狭いけれど、音の解像度はかなり明晰なことは驚くばかり。打楽器の低音とか大爆発は期待できないけれど、低弦はけっこうごりごり鳴っております。ほとんど作品を堪能するのに不都合を感じさせない。そして当時既にフィラデルフィア管弦楽団の技量は優れ、各パートの色気あるサウンドがしっかり聴き取れます。金管のキレ、鮮やかな節回しや爆発など滅茶苦茶上手い! ストコフスキーの統率もおみごと、未だ40歳代の壮年ですもんね。楽譜のことはようわかっていないけれど、第2部「生贄の儀式」の打楽器など馴染んだものとはかなり違う感じ。(15:08-17:25)
Stravinsky バレエ音楽「春の祭典」~レオポルド・ストコフスキー/フィラデルフィア管弦楽団(1929/30年)・・・17年ぶりの拝聴。Leopold Stokowski(1882-1977英国)の「春の祭典」はこれしか録音しなかったはず(自信はない)。初演が1913年だったからまだほやほやの新しい音楽だったはず、これはSP復刻だからダイナミックレンジが狭いけれど、音の解像度はかなり明晰なことは驚くばかり。打楽器の低音とか大爆発は期待できないけれど、低弦はけっこうごりごり鳴っております。ほとんど作品を堪能するのに不都合を感じさせない。そして当時既にフィラデルフィア管弦楽団の技量は優れ、各パートの色気あるサウンドがしっかり聴き取れます。金管のキレ、鮮やかな節回しや爆発など滅茶苦茶上手い! ストコフスキーの統率もおみごと、未だ40歳代の壮年ですもんね。楽譜のことはようわかっていないけれど、第2部「生贄の儀式」の打楽器など馴染んだものとはかなり違う感じ。(15:08-17:25)
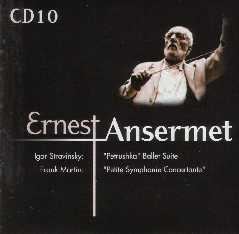 Stravinsky バレエ組曲「火の鳥」(1919年版)エルネスト・アンセルメ/ロンドン・フィル(1950年)・・・これも17年ぶりの拝聴。Ernest Ansermet(1883ー1969瑞西)が幾度録音したかわからぬけれど、短い1919年版組曲はこれとスイス・ロマンド管弦楽団の1950年録音でしたっけ?まったりとしてクールな味わいの演奏は最近の技術的にキレのあるものとは違うけれど、なんともメルヘンな雰囲気が漂って、なにより音質がかなり良好。各パートの分離、金管の鮮度には驚きました。ロンドン・フィルはスイス・ロマンド管弦楽団より上手いと思います。序奏と火の鳥の踊り(4:20)王女たちのロンド(ホロヴォード)(3:56)魔王カスチェイの凶悪な踊り(4:10)子守唄(3:26)フィナーレ(3:15)
Stravinsky バレエ組曲「火の鳥」(1919年版)エルネスト・アンセルメ/ロンドン・フィル(1950年)・・・これも17年ぶりの拝聴。Ernest Ansermet(1883ー1969瑞西)が幾度録音したかわからぬけれど、短い1919年版組曲はこれとスイス・ロマンド管弦楽団の1950年録音でしたっけ?まったりとしてクールな味わいの演奏は最近の技術的にキレのあるものとは違うけれど、なんともメルヘンな雰囲気が漂って、なにより音質がかなり良好。各パートの分離、金管の鮮度には驚きました。ロンドン・フィルはスイス・ロマンド管弦楽団より上手いと思います。序奏と火の鳥の踊り(4:20)王女たちのロンド(ホロヴォード)(3:56)魔王カスチェイの凶悪な踊り(4:10)子守唄(3:26)フィナーレ(3:15)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
粛々と2024年も暮れていきます。世間の現役世代はなにかと忙しいけれど、ヒマな引退身分は変わらぬ生活、冷たい季節を乗り切るのみ。毎日の朝一番の洗濯、ストレッチ、YouTube「15 MIN STANDING ABS WORKOUT (with weights)」済ませてから皮膚科を目指しました。ちょっと手荒れが気になってクスリも切れ掛け、冬休みに入って年末迫ればいっそう混むことを予想したので。30分ほどの待ち時間に夕食メニューを考えて、帰り業務スーパーに寄って食材買い出し。相変わらず野菜は高くて、きのこ類も今回値上がりを確認しました。往復3.26kmの意識して速歩ウォーキングも佳き運動です。体調は整いました。今朝の体重は67.0kg▲100g。昼飯喰い過ぎ懸念したけれど、なんとか増加は食い止めました。
 10年選手のMy Computer VAIO-Tapは中古入手、SSDに交換済のもの。毎日ハードに酷使して3年目、稼働は順調だけど最近動きが時々鈍い感じ。例えばネットより音源CD/LPデザイン画像入手して、それを圧縮保存する時にちょっと時間が掛るような気が・・・SSD容量にはまだまだ余裕ありますよ。Windows11設定を「デザイン重視」→「パフォーマンス重視」に変更したら、要らぬ効果はなくなったけれどフォントがかすれて見にくい。そこは「滑らかにする」に戻しても・・・戻りません。これはなんだろう・・・しばらく悩んで「困ったときの再起動(自分が作った迷言)」ブラウザ(Chrome)再起動させたら戻りました。さてこれから先、速度改善の効果はいかがでしょうか。
10年選手のMy Computer VAIO-Tapは中古入手、SSDに交換済のもの。毎日ハードに酷使して3年目、稼働は順調だけど最近動きが時々鈍い感じ。例えばネットより音源CD/LPデザイン画像入手して、それを圧縮保存する時にちょっと時間が掛るような気が・・・SSD容量にはまだまだ余裕ありますよ。Windows11設定を「デザイン重視」→「パフォーマンス重視」に変更したら、要らぬ効果はなくなったけれどフォントがかすれて見にくい。そこは「滑らかにする」に戻しても・・・戻りません。これはなんだろう・・・しばらく悩んで「困ったときの再起動(自分が作った迷言)」ブラウザ(Chrome)再起動させたら戻りました。さてこれから先、速度改善の効果はいかがでしょうか。
Chromeもメモリを喰うとの評判に、別なのに変えようと検討したけれど、他のマシンとの設定同期という点で乗り換えられません。結局、気分転換にキーボードを久々MS Comfort Curveに交換、これはお仕事現役ラスト数年間職場に持ち込んで愛用した懐かしいもの。Amazonのレビューにはけっこう初期不良やら早期での故障が報告されているけれど、自分のは10年ほど使い込んで不具合はありません。ノーミソ鍛錬には激安中古ノートでも入手して、新しいLINUXなど入れて試すと良いんだろうけどなぁ。ご近所に中古屋さんがたまたまない・・・あってももう買わないかも。
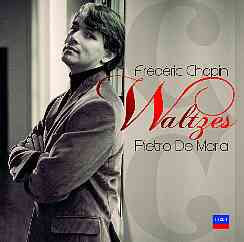 Chopin ワルツ集(19曲)~ピエトロ・デ・マリア(p)(2009?2010年)・・・Pietro De Maria(1967-伊太利亜)はなかなかのイケメン、伊太利亜DECCAにChopinの全曲録音しております。かつて別な作品(既になんの作品だったか?記憶なし)をちょっぴり聴いてちょっとガッカリ、久々に著名な甘い旋律続くワルツを聴いてみたらさほどに悪い印象を感じない。しっかり安定した技巧、清潔にオーソドックスなタッチ、お気に入りワルツ第7番 嬰ハ短調作品64-2/ワルツ第9番「告別」変イ長調 差品69-1/ワルツ第10番ロ短調作品69-2辺り、懐かしくも名残惜しいデリケートに誠実な表現はしっかり心に残りました。色気とか色彩の変化、妖しい節回しや時に力強さとメリハリに足りず表現はやや平板っぽいけれど、淡々と美しい旋律が続いて作品を堪能可能。(19曲収録作品明細タイミングのメモは手抜き)
Chopin ワルツ集(19曲)~ピエトロ・デ・マリア(p)(2009?2010年)・・・Pietro De Maria(1967-伊太利亜)はなかなかのイケメン、伊太利亜DECCAにChopinの全曲録音しております。かつて別な作品(既になんの作品だったか?記憶なし)をちょっぴり聴いてちょっとガッカリ、久々に著名な甘い旋律続くワルツを聴いてみたらさほどに悪い印象を感じない。しっかり安定した技巧、清潔にオーソドックスなタッチ、お気に入りワルツ第7番 嬰ハ短調作品64-2/ワルツ第9番「告別」変イ長調 差品69-1/ワルツ第10番ロ短調作品69-2辺り、懐かしくも名残惜しいデリケートに誠実な表現はしっかり心に残りました。色気とか色彩の変化、妖しい節回しや時に力強さとメリハリに足りず表現はやや平板っぽいけれど、淡々と美しい旋律が続いて作品を堪能可能。(19曲収録作品明細タイミングのメモは手抜き)
 12月はBach。Bach クリスマス・オラトリオ BWV.248/第1部「降誕節第1祝日用 (12月25日)」~リッカルド・シャイー/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団/ドレスデン室内合唱団/マルティン・ラットケ((t)/エヴァンゲリスト)/キャロリン・サンプソン(s)/ヴィープケ・レームクール(a)/ヴォルフラム・ラットケ(t)/コンスタンティン・ヴォルフ(b)(2010年)・・・自分はカソリックの幼稚園にニ年、日曜学校(礼拝)はしばらく通ったけれど残念、長じて宗教的素養は身に付きませんでした。どんな神であれ、宗教的異敬の念はありますよ。これはクリストの生誕を祝う長大なる音楽。この作品は生体験があって、延々長大なる作品を堪能したものです。器楽編成は二管編成+ティンパニ。第1部から順繰り聴いてシミジミいたしましょう。毎年(初体験演奏である)フリッツ・ヴェルナーばかり聴いていたのでRiccardo Chailly(1953-伊太利亜)のを取り出しました。彼は古楽器奏法+一部古楽器を導入して、そのスタイルはコンセルトヘボウ時代にアーノンクールから学んだそう。引き締まった小編成に、声楽も清潔に響いて、なんせ音質がよろしい。残りもちゃんと順繰り聴いて楽しみます。
12月はBach。Bach クリスマス・オラトリオ BWV.248/第1部「降誕節第1祝日用 (12月25日)」~リッカルド・シャイー/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団/ドレスデン室内合唱団/マルティン・ラットケ((t)/エヴァンゲリスト)/キャロリン・サンプソン(s)/ヴィープケ・レームクール(a)/ヴォルフラム・ラットケ(t)/コンスタンティン・ヴォルフ(b)(2010年)・・・自分はカソリックの幼稚園にニ年、日曜学校(礼拝)はしばらく通ったけれど残念、長じて宗教的素養は身に付きませんでした。どんな神であれ、宗教的異敬の念はありますよ。これはクリストの生誕を祝う長大なる音楽。この作品は生体験があって、延々長大なる作品を堪能したものです。器楽編成は二管編成+ティンパニ。第1部から順繰り聴いてシミジミいたしましょう。毎年(初体験演奏である)フリッツ・ヴェルナーばかり聴いていたのでRiccardo Chailly(1953-伊太利亜)のを取り出しました。彼は古楽器奏法+一部古楽器を導入して、そのスタイルはコンセルトヘボウ時代にアーノンクールから学んだそう。引き締まった小編成に、声楽も清潔に響いて、なんせ音質がよろしい。残りもちゃんと順繰り聴いて楽しみます。
第1曲 合唱「歓呼の声を放て、喜び踊れ」(6:40)*ここはかつて聴いた中で最速。ティンパニの軽快なリズムに乗せて喜ばしい始まり。/第2曲 レチタティーヴォ「その頃皇帝アウグストより勅令出で」(1:31)/第3曲 レチタティーヴォ「今ぞ、こよなく尊きわが花嫁」(0:49)/第4曲 アリア「備えせよ、シオンよ、心からなる愛もて」(5:09)*ここのアルトがシミジミ情感を込めて歌う。/第5曲 コラール「如何にしてわれは汝を迎えまつり」(1:10)*「マタイ」の「おお頭は血潮にまみれ」と同じ旋律/第6曲 レチタティーヴォ「しかしてマリアは男の初子を生み」(0:22)/第7曲 コラールとレチタティーヴォ「彼は貧しきさまにて地に来りましぬ/たれかよくこの愛を正しく讃えん」(2:30)/第8曲 アリア「大いなる主、おお、強き王」(4:20)*トランペットも勇壮な、力強いバスのアリア/第9曲 コラール「ああ、わが心より尊びまつる嬰児イエスよ」(1:18)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
昨日も好天、12月はほとんど雨が降っておりません。毎年乾燥するこの頃、全国あちこちで火災が発生しております。北九州の中学生無差別?刺殺事件には暗澹(あんかん)とした気分、犯人は早く逮捕されてほしいけれど、その動機はなんでしょうか。昨日もマンネリの始まり、洗濯してストレッチしっかり、YouTubeエキササイズは舶来別嬪さんのご指導に従って15分、そして市立体育館へ。道中ぼちぼちゴミ拾いもいつも通り。平日朝は完全常連メンバー顔ぶれ揃って、筋トレ・マシンは空いておりました。お隣ではジャージの上から短パンという特異なファッションの爺さん(毎度のこと)が鍛えておりました。今朝の体重は67.1kgほぼ変わらず。夕食は在庫で仕立てて買い物には寄っておりません。本日は基本調味料や食材が足りないので、買い物必須。
挨拶をしない人たち~そんなブログの記事を拝見。
自分の近所ではそんなことはないなぁ、市立体育館に出掛ける途中、見知らぬ爺婆に「おはようございます」と挨拶されるし、ゴミ拾い途上すれ違いざまに「ごくろうさまです」とのありがたい言葉もありました。入口では警備の人にも受付にも挨拶はあるし、トレーニングルームの常連だって黙礼くらいしますよ。但し、階下の婆さんは無愛想やなぁ、某宗教活動に熱心らしいけどそれは思想信条信教の自由、あとは人それぞれの性格でしょう。自分は意地になって明るく「おはようございます!」毎度元気に挨拶は欠かしませんよ、返事はないけれど。
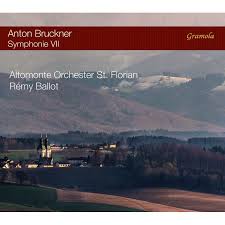 Brukcner 交響曲第7番ホ長調~レミ・バロー/ザンクト・フローリアン・アルトモンテ管弦楽団(2018年聖フローリアン修道院教会ライヴ)・・・少なくとも日本ではあまり話題になっていないRemy Ballot(1977-仏蘭西)による全集録音は 師匠チェリビダッケ譲りの微速前進。風貌も似ております。先に第6番を聴いておりました。残響10秒のライヴ、このオーケストラはここで開催される音楽祭用のオーケストラとか、ホルン先頭に深みのある色を聴かせて下さいました。旋律和音の残響減衰を確認すれば自然とこのテンポになるのでしょうか。アンサンブルの縦線を揃えるのは至難のはず。決して慌てず、煽りや疾走とは無縁、イン・テンポに微妙なニュアンスに緊張感を維持する凄い演奏。チェリビダッケ同様聴手の集中力と体力が問われる74分ほど、Bruckner中屈指の美しい旋律を誇るこの作品の白眉は第2楽章「Adagio」。いつ終わる知れぬ寄せては返す静かなうねりが粛々と続いて、クライマックスには打楽器の楔は必須だったことでしょう。但し、しばらく聴いていないけれどチェリビダッケほどの凄みとか異様な集中力に一歩及ばぬ・・・かも。こちらの根性の劣化の可能性もあるから確認いたしましょう。
Brukcner 交響曲第7番ホ長調~レミ・バロー/ザンクト・フローリアン・アルトモンテ管弦楽団(2018年聖フローリアン修道院教会ライヴ)・・・少なくとも日本ではあまり話題になっていないRemy Ballot(1977-仏蘭西)による全集録音は 師匠チェリビダッケ譲りの微速前進。風貌も似ております。先に第6番を聴いておりました。残響10秒のライヴ、このオーケストラはここで開催される音楽祭用のオーケストラとか、ホルン先頭に深みのある色を聴かせて下さいました。旋律和音の残響減衰を確認すれば自然とこのテンポになるのでしょうか。アンサンブルの縦線を揃えるのは至難のはず。決して慌てず、煽りや疾走とは無縁、イン・テンポに微妙なニュアンスに緊張感を維持する凄い演奏。チェリビダッケ同様聴手の集中力と体力が問われる74分ほど、Bruckner中屈指の美しい旋律を誇るこの作品の白眉は第2楽章「Adagio」。いつ終わる知れぬ寄せては返す静かなうねりが粛々と続いて、クライマックスには打楽器の楔は必須だったことでしょう。但し、しばらく聴いていないけれどチェリビダッケほどの凄みとか異様な集中力に一歩及ばぬ・・・かも。こちらの根性の劣化の可能性もあるから確認いたしましょう。
第1楽章「Allegro moderato(22:17)/第2楽章「Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam(26:07)/第3楽章「Scherzo: Sehr schnell(10:19)/第4楽章「Finale: Bewegt, doch nicht schnell(14:31/かなりの間を置いて拍手有)
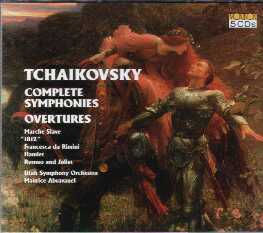 Tchaikovsky 交響曲第1番ト短調「冬の日の幻想」~モーリス・アブラヴァネル/ユタ交響楽団(1972-73年)・・・冷涼として懐かしい旋律が続く名曲。音質はこの時期を勘案すると少々濁り気味。二管編成+ティンパニ、終楽章にはシンバルと大太鼓が入ります。
Tchaikovsky 交響曲第1番ト短調「冬の日の幻想」~モーリス・アブラヴァネル/ユタ交響楽団(1972-73年)・・・冷涼として懐かしい旋律が続く名曲。音質はこの時期を勘案すると少々濁り気味。二管編成+ティンパニ、終楽章にはシンバルと大太鼓が入ります。
第1楽章「冬の旅の幻想」(Allegro tranquillo - Poco piu animato)・・・軽快な民謡風旋律が全編に弾んで力強くリズミカル。雰囲気はあるけれど、オーケストラはなんともぱっとしないジミな響き、でも味わいはあって悪くない。(12:05)
第2楽章「陰気な土地、霧の土地」(Adagio cantabile ma non tanto - Pochissimo piu mosso)緩徐楽章も懐かしく、ちょっぴり寂しく歌って甘い旋律。この音質水準にオーケストラの薄さ、弱さを危惧するけれど、なんかとってもローカルな味わいが続いて雰囲気はたっぷり堪能できました。ホルン・ソロはなかなか立派でした。(10:26)
第3楽章「Scherzo. Allegro scherzando giocoso」リズミカルに平易親密な旋律が歌うスケルツォ。Tchaikovskyはほんまにメロディ・メーカー、中間部のワルツもステキです。但し、この演奏はパワー不足っぽい。(7:04)
第4楽章「Finale. Andante lugubre - Allegro moderato - Allegro maestoso - Allegro vivo - Piu animato」遣る瀬ない暗鬱な民謡風旋律から始まるフィナーレ。一転明るく快活リズミカルな(やはりモロ露西亜民謡風)旋律に走り出して、ここの歩みはなんとももどかしい、カッコよろしくないのが残念。そのまま熱を加えて華やかなクライマックスへ、なんとなく様になって締め括るのもMaurice Abravanel(1903-1993瑞西?→亜米利加)のワザでしょう。(11:48)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
12月もあっという間にもう半分過ぎて新しい一週間が始まりました。毎日けっこう冷えますね。昨日日曜は好天、洗濯は外干し、ストレッチはしっかり、YouTubeエアロビクスは一日サボりました。前夜自家製ヨーグルトを仕込むのが夕方になって、8時間後に終了するときには深夜、それが気になってあまり良く眠れませんでした。ちゃんと終了後に途中起き出して冷蔵庫へ、結果睡眠不足。体調は悪くないけれど、この冷えのせいか左半身膝腰辺りに鈍い違和感有。これは鍛えて治しましょう。結局終日引き隠り状態。今朝の体重は67.2kg+450gガッカリ。
コロナに関連して、爺殺しウィルスとは凄い命名。2020-2022年で日本の寿命は2年減ったとのこと、コロナの威力は凄かったんですね。大騒ぎが収束してから昨年あたりの死者数も減っていない(むしろ増えている?)らしいから、まだまだ要注意でしょう。自分もなんとなく咽に違和感有。
冬休み直前、季節性インフルエンザが猛威を振るっているらしい。全国の1,402の学校などで休校や学級閉鎖となっているとの報道。我が二人の孫も保育所に通って、お友だちからもらって来る可能性も高いから心配です。あと3ヶ月位はシーズンだから、なんとか乗り切ってほしい。自分も女房殿もワクチン接種済、但し流行りの型式に合っていたのかそれは微妙、それに罹らないということじゃなくて、罹患しても重症に至らないということですから。しっかり鍛えて日光を浴びて、帰宅したら手洗いうがいしっかり、それが基本中の基本。外出時には苦手なマスク必須と決意しました。
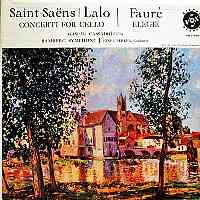 Saint-Sae"ns チェロ協奏曲第1番イ短調/Faure エレジー/Lalo チェロ協奏曲ニ短調~ガスパール・カサド(vc)/ヨネル・ペルレア/バンベルク交響楽団(1960年)・・・Gaspar Cassado(1897ー1966西班牙)による晩年の録音。カサドはよく歌ってノーブルなチェロですよ。1960年の録音にしてはオーケストラが濁りがち。Ionel Perlea(1900-1970羅馬尼亜→?)はオペラの人、懐かしい名前でした。Saint-Sae"nsは「Allegro non troppo -Allegretto con moto -Allegro non troppo」途切れず一気呵成。切迫する細かい音型連続に軽快な疾走、相当なソロの技量を要求されそう。変幻自在な表情の変化、寄せては返す優雅な情感の揺れ、デリケートな抑制、素晴らしいチェロですよ。これが一番音質が良好。(19:30)
Saint-Sae"ns チェロ協奏曲第1番イ短調/Faure エレジー/Lalo チェロ協奏曲ニ短調~ガスパール・カサド(vc)/ヨネル・ペルレア/バンベルク交響楽団(1960年)・・・Gaspar Cassado(1897ー1966西班牙)による晩年の録音。カサドはよく歌ってノーブルなチェロですよ。1960年の録音にしてはオーケストラが濁りがち。Ionel Perlea(1900-1970羅馬尼亜→?)はオペラの人、懐かしい名前でした。Saint-Sae"nsは「Allegro non troppo -Allegretto con moto -Allegro non troppo」途切れず一気呵成。切迫する細かい音型連続に軽快な疾走、相当なソロの技量を要求されそう。変幻自在な表情の変化、寄せては返す優雅な情感の揺れ、デリケートな抑制、素晴らしいチェロですよ。これが一番音質が良好。(19:30)
Faureは管弦楽伴奏版。切ない詠嘆が纏綿と歌って激昂します。これも凄い技巧必須。(7:50)
Laloは第1楽章「Prelude: Lento - Allegro maestoso」たっぷり大仰に浪漫的なソロに、管弦楽は叩きつけるように力強く呼応します。カサドのチェロは詠嘆の表情濃厚に、粘着質にくどい旋律の楽章。(13:38)
第2楽章「Intermezzo: Andantino con moto - Allegro - Presto」切なく寂しい弦の導入に、ソロも嘆きの囁き。やがて軽妙な西班牙風情の舞曲に至りました。(5:31)
第3楽章「Introduction: Andante - Allegro Vivace」雄弁なソロの主題から始まって、颯爽としたオーケストラの響きは濁ってぱっとしない。符点のリズムに弾むソロがリズミカル、これも西班牙風かな?(7:39)
 Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1911年版)/サーカス・ポルカ/花火/ロシア風スケルツォ(1944年Jazz-ver)~エリアフ・インバル/フィルハーモニア管弦楽団(1990年)・・・前回拝聴2005年の印象は
Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1911年版)/サーカス・ポルカ/花火/ロシア風スケルツォ(1944年Jazz-ver)~エリアフ・インバル/フィルハーモニア管弦楽団(1990年)・・・前回拝聴2005年の印象は
ややデッドで自然で鮮明な音質。オーケストラの技術は正確であって、良く歌っているし、サウンドの質感によそよそしさはなくて、基本クールな表情ながらなんとなく親しげです。サイボーグ的ではなく、ちゃんと血が通っている・・・細部入念な味付けとリズム感に不足はない・・・でも、どこか不機嫌というか、ワクワクするような遊園地の喧噪ではないような気もしないでもない
オリジナル四管編成版のたっぷりとした厚み、インバルの統率は緻密に曖昧さは微塵も感じさせない、フィルハーモニア管弦楽団は好調に立派な演奏。もちろん小太鼓つなぎ入り、低音にキレと奥行きのある解像度の高い音質でした。この作品は”ワクワクするような遊園地の喧噪”(祭りが正しいでしょう)を漂ってステキな作品、「どこか不機嫌」というのは細部生真面目にクールな描き込みからの印象だったのか。ここまでリアルな音質に迫力たっぷり、ていねいな仕上げに不満はありません。あまりのお気に入り作品だから聴き過ぎ作品だけど、久々に作品のおもしろさ、色彩の変化、真髄細部迄堪能した気分。
第1部 謝肉祭の市 Fete populaire de semaine grasse-導入 - 群集 Debut - Les foules(5:42)/人形使いの見世物小屋 La baraque du charlatan(1:53)/ロシアの踊り Danse russe(251)
第2部 ペトルーシュカの部屋 Chez Petrouchka(4:30)
第3部ムーア人の部屋 Chez le Maure(3:08)/バレリーナの踊り Danse de la Ballerine(0:50)/ワルツ(バレリーナとムーア人の踊り) Valse: La Ballerine et le Maure(3:20)
第4部 謝肉祭の市(夕景) Fete populaire de semaine grasse (vers le soir)(6:11)(乳母の踊り Danse de nournous/熊を連れた農夫の踊り Danse du paysan et de l'ours/行商人と二人のジプシー娘 Un marchand fetard avec deux tziganes)/馭者と馬丁たちの踊り Danse des cochers et des palefreniers(2:29)/仮装した人々 Les deguises/格闘(ペトルーシュカとムーア人の喧嘩) La rixe: Le Maure et Petrouchka/終景:ペトルーシュカの死 Fin : La mort de Petrouchka/警官と人形使い La police et le chartatan/ペトルーシュカの亡霊 Apparition du double de Petrouchka(5:26)
サーカス・ポルカはガチャガチャと破茶滅茶元気一杯にユーモラス最高。軍隊行進曲がシニカルに登場します。これは1944年管弦楽版。(3:51)花火は1909年の初期作品、色彩豊かに幻想的な描写が秀逸(3:51)「ロシア風スケルツォ」は1944年ポール・ホワイトマン楽団のためのジャズ・バンド用、作曲者はそのレコードを聴いてガッカリしたとWikiにありました(管弦楽版に焼き直したそう)。これも思っきりスウィングして小粋に安っぽくも俗っぽい旋律がステキな作品。ピアノが効いております。(3:54)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
全国的に寒さ募ります。一昨日夜は冷たい雨が降ったようで昨日朝地面は濡れて、洗濯物は室内干しでした。早朝覚醒して二度寝したら寝坊してストレッチの時間なし、マッチョな外国人男性のYouTube動画に身体を動かしてから市立体育館へ出掛けました。道中草むらに悪質なデカいゴミ袋放置発見、それは帰りに我が団地ゴミ捨て場に運搬いたしました。薄曇りに寒くトレーニングルームは常連メンバーもかなりお休み、きっと自転車組は路上が濡れているのをいやがったのでしょう。ゆっくり、いつも通り鍛えました。幼稚園から高校まで過ごした札幌の様子が毎日YouTube動画に上がって、数日前にドカ雪が降ったみたい。ホワイト・アウトしてあちこち車道横に突っ込んで立ち往生している車両がありました。それに比べればこちらの寒さは屁みたいなもんですよ。今朝の体重は66.75kg▲400g。この調子で減らしたいもの。
朝、女房殿が朝食に使い切って自家製ヨーグルトが切れたとの報告。さっそく種菌として使うヨーグルトを取り出したら・・・やや変色有、苦みもあってアウト、泣きながら捨てました。ぼちぼち一ヶ月前だからいくら寒い時期に冷蔵庫保存しても賞味期限はとっくに過ぎている・・・じつは前回一週間ほど前のもいつもより酸味が強かった(≒変敗寸前)。これじゃなんのための節約かわかったもんじゃない。人生いろいろ失敗は付き物です。今朝新しいヨーグルトを使っておいしいのをいただきました。
洋菓子店から「クリスマスケーキやめたい」との声、そんなニュース拝見。原料費が高騰してもケーキの値段はそのまま反映させられない、相場というものがある。困ったものですね。せっかくの風物詩なのに。そしてお隣では大統領弾劾可決、集まった国民は熱狂して、さて、このあと安定した佳き生活が実現できるでしょうか。幾度も云うけど、反日機運で乗り切ろうとすることでしょう。心配です。北九州にて中学生が刺殺された事件発生、静岡県では連続猫の首放置事件、年末迫って物騒な世情が続きます。
 Prokofiev ピアノ協奏曲第2番ト短調~アレクセイ・ヴォロディン(p)/ヴァレリー・ゲルギエフ/マリンスキー管弦楽団(2014年/Stockhrm Berwaldhallen Concert Hallライヴ)・・・2014年にゲルギエフがストックホルムにてピアノ協奏曲を全曲演奏したらしくて、その時の放送音源?オン・マイクにリアルな音質でした。オリ・ムストネンとAlexei Volodin(1977-露西亜)が分担しておりました。このト短調協奏曲は1913年初演、そのオリジナルの楽譜は失われ1924年に復元改定したとのこと。伴奏は二管編成にティンパニ+大太鼓、小太鼓、シンバル、タンバリン。第3番ハ長調ばかり有名だけど、なんとなく他第1番 変ニ長調くらいしかちゃんと聴いていなくて、ようやくこの作品の破壊的、怪しくも激しい魅力に目覚めました。超・難曲とのこと。ヴォロディンはたっぷり鳴るピアノが濃密そのもの。流麗に流すタイプではないようです。(29:44楽章間盛大なる拍手含む)
Prokofiev ピアノ協奏曲第2番ト短調~アレクセイ・ヴォロディン(p)/ヴァレリー・ゲルギエフ/マリンスキー管弦楽団(2014年/Stockhrm Berwaldhallen Concert Hallライヴ)・・・2014年にゲルギエフがストックホルムにてピアノ協奏曲を全曲演奏したらしくて、その時の放送音源?オン・マイクにリアルな音質でした。オリ・ムストネンとAlexei Volodin(1977-露西亜)が分担しておりました。このト短調協奏曲は1913年初演、そのオリジナルの楽譜は失われ1924年に復元改定したとのこと。伴奏は二管編成にティンパニ+大太鼓、小太鼓、シンバル、タンバリン。第3番ハ長調ばかり有名だけど、なんとなく他第1番 変ニ長調くらいしかちゃんと聴いていなくて、ようやくこの作品の破壊的、怪しくも激しい魅力に目覚めました。超・難曲とのこと。ヴォロディンはたっぷり鳴るピアノが濃密そのもの。流麗に流すタイプではないようです。(29:44楽章間盛大なる拍手含む)
第1楽章「Andantino - Allegretto」妖しくも甘く静かなピアノがデリケートに呟いて、弦が優しくサポートして始まります。Wikiには夜想曲風とありました。歩みは粛々として切ない、乾いた情感が漂う始まり。カデンツァは延々と続いて秘めた情熱が高まって荒々しい・・・やがて静謐に戻って終了。
第2楽章「Scherzo: Vivace」 息もつかせぬ快速無窮動。いかにも正確な超絶技巧を要求されそうな疾走する短いスケルツォ。安易に走らず、曖昧さのないタッチの印象も濃密でした。
第3楽章「Intermezzo: Allegro moderato」怪獣でもも出現しそうな重い足取りはゲルギエフの個性充分。それが多彩に変化しつつ延々と繰り返されます。ピアノは破壊的にスウィングして骨太、いかにも重苦しい、泥臭いユーモア漂うProkofievの個性満喫。
第4楽章「Finale: Allegro tempestoso」破壊的に素っ頓狂な旋律とリズム。Wikiにはグロテスクとあるけれど、この暗い、重い足取りの怪しさには妙な魅力を感じます。ラストは追い詰められたような切迫感に爆発、ここの熱気追い込みがすごい、そしてストンと終わりました。
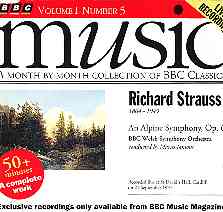 R.Strauss アルプス交響曲~マリス・ヤンソンス/BBC ウェールズ交響楽団(1991年ライヴ)・・・残念な急逝だったMariss Jansons(1943-2019拉脱維亜)の珍しいライヴ、一躍名を高めたオスロ・フィル在任時代の記録。尾高忠明時代のオーケストラは驚くべき進境を見せて、集中したアンサンブルや輝かしい金管のパワーや厚み、艶にもまったく不足を感じさせぬもの。カーディフにあるデイヴィス・ホールの音響も臨場感たっぷり。ヤンソンスのグラマラスな表現はこの時期より充分発揮されていて、クライマックスへのアツい盛り上げに聴手は思わず身を乗り出すほど! 仰ぎ見るような高まりやパワフルな煽りを見せました。先日小澤征爾を聴いたばかりだけれど、あちらのほうがオーソドックスに抑制した表現にウィーン・フィルの気質を活かしたものと気付きました。(3:11-1:29-2:23-4:49-0:45-0:16-0:51-0:55-2:18-1:33-1:16-1:30-5:09-3:33-0:22-1:00-2:05-2:48-3:51-2:44-6:25-2:48)
R.Strauss アルプス交響曲~マリス・ヤンソンス/BBC ウェールズ交響楽団(1991年ライヴ)・・・残念な急逝だったMariss Jansons(1943-2019拉脱維亜)の珍しいライヴ、一躍名を高めたオスロ・フィル在任時代の記録。尾高忠明時代のオーケストラは驚くべき進境を見せて、集中したアンサンブルや輝かしい金管のパワーや厚み、艶にもまったく不足を感じさせぬもの。カーディフにあるデイヴィス・ホールの音響も臨場感たっぷり。ヤンソンスのグラマラスな表現はこの時期より充分発揮されていて、クライマックスへのアツい盛り上げに聴手は思わず身を乗り出すほど! 仰ぎ見るような高まりやパワフルな煽りを見せました。先日小澤征爾を聴いたばかりだけれど、あちらのほうがオーソドックスに抑制した表現にウィーン・フィルの気質を活かしたものと気付きました。(3:11-1:29-2:23-4:49-0:45-0:16-0:51-0:55-2:18-1:33-1:16-1:30-5:09-3:33-0:22-1:00-2:05-2:48-3:51-2:44-6:25-2:48)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
いつものマンネリな日々を過ごして2024年は暮れつつ終末を迎えました。鼻詰まりと痰の絡みは服薬の効果に途中覚醒もなくなったけれど、夢見はよろしくない。いつもどおりのストレッチは手抜き短縮版+YouTubeエアロビクスは久々、竹脇まりなさんの「【15分室内散歩】寒い冬はおうちで脂肪を効率的に燃やそう/【おうちで健康体操】」実施して業務スーパーを目指したのもウォーキングのため。道中はいっそう冷えます。常備したい大蒜とか黒胡椒粒が切れ掛け、そこは定番管理がよろしくなくて、黒胡椒は棚空き残念。店内音楽はいらいらするほどヘタクソなアイドルの歌が不快。途中のスーパー駐車場敷地内に「デザイン・カット1,650円来年1月オープン」とのこと。自分には行きつけの激安美容室カット980円があるので利用する予定はありません。今朝の体重は67.15kg、4日連続同じは珍しい。
節約生活に蓄えを取り崩しつつ無為無策に遊んで暮らす日々。世間では生活のため、自分の充実した人生のために働き続けている同世代は多数派とか。週に三回は通う市立体育館に求人有「午後3-9時勤務。受付や会場整備、かんたんなパソコンを扱える方。週ニ回より応談」既にニ週ほど貼り続けているので未だ決まっていないらしい。なにやら財団に委託している公的施設も人手不足なんでしょうか。
自分は週三回休まず通っているんだし、67歳の爺を採用してくれるのか微妙だけど、想像するにそう難しいお仕事でもなさそう。仮に1,000円/hとして(実際はもっと多い)6時間/日*3日/週*4週=月72,000円か、悪くないなぁ、爺友と時々呑むには充分な小遣いにはなる・・・問題は隔日夕方~夜の時間を拘束されること、その生活リズムに馴染めるか。それと人間関係やろなぁ。
ま、今のところ節約生活に困っていないし、ムリして申し込もうとは思っていないけれど、お仕事引退してすぐ!そんな時期なら、未だ毎日お仕事生活リズムに慣れていたし、可能だったかも知れません。毎日ヒマだけど、自由な時間をそれなり堪能しております。なにも特別やりたいこともないけれど、思い立ったら速攻!な自由時間は確保しておきたい。
 Chabrier 楽しい行進曲/スラブ舞曲(オペレッタ「いやいやながらの王様」より)/田園組曲/歌劇「グヴァンドリーヌ」序曲/気まぐれなブーレ/狂詩曲「スペイン」~アルミン・ジョルダン/フランス国立管弦楽団(1982年)・・・Armin Jordan(1932-2006瑞西)の息子フィリップが現在活躍しております。瑞西の名門スイス・ロマンド管弦楽団の首席1985-1997年在任。Chabrie「スペイン」との出会いはアーサー・フィードラー/ボストン・ポップス管弦楽団(1958年)17cmLPの片面はRVWの「グリーンスリーヴズ」でした。こどもの頃の刷り込みは一生の嗜好を左右するもの。誰が云ったかChabrierは”シャンパンの泡”=これは文句なく楽しくも素っ頓狂に賑やかな作品揃えて、小粋な風情満載の演奏でした。田園組曲(Idylle/Danse villageoise/Sous-bois/Scherzo-valse)と「気紛れなブーレ」のオリジナルはピアノ作品、自分はシンプルなオリジナルのほうが好き。とくに淡々とした「牧歌」がお気に入りでした。歌劇「グヴァンドリーヌ」は聴いたことがないけれど、なんとなく筋書きが類推できそうな雄弁な音楽。そして締め括りは狂詩曲「スペイン」躍動と熱狂溢れる生命の躍動を感じさせる作品、そしてヴィヴィッドな演奏。(4:04/5:08/4:58-4:52-5:49-5:04/10:44/7:01/6:33)
Chabrier 楽しい行進曲/スラブ舞曲(オペレッタ「いやいやながらの王様」より)/田園組曲/歌劇「グヴァンドリーヌ」序曲/気まぐれなブーレ/狂詩曲「スペイン」~アルミン・ジョルダン/フランス国立管弦楽団(1982年)・・・Armin Jordan(1932-2006瑞西)の息子フィリップが現在活躍しております。瑞西の名門スイス・ロマンド管弦楽団の首席1985-1997年在任。Chabrie「スペイン」との出会いはアーサー・フィードラー/ボストン・ポップス管弦楽団(1958年)17cmLPの片面はRVWの「グリーンスリーヴズ」でした。こどもの頃の刷り込みは一生の嗜好を左右するもの。誰が云ったかChabrierは”シャンパンの泡”=これは文句なく楽しくも素っ頓狂に賑やかな作品揃えて、小粋な風情満載の演奏でした。田園組曲(Idylle/Danse villageoise/Sous-bois/Scherzo-valse)と「気紛れなブーレ」のオリジナルはピアノ作品、自分はシンプルなオリジナルのほうが好き。とくに淡々とした「牧歌」がお気に入りでした。歌劇「グヴァンドリーヌ」は聴いたことがないけれど、なんとなく筋書きが類推できそうな雄弁な音楽。そして締め括りは狂詩曲「スペイン」躍動と熱狂溢れる生命の躍動を感じさせる作品、そしてヴィヴィッドな演奏。(4:04/5:08/4:58-4:52-5:49-5:04/10:44/7:01/6:33)
フィル・アップはFaure 組曲「マスクとベルガマスク」(ローザンヌ室内管弦楽団/1981年)Overture(3:36)Menuet(2:47)Gavote(2:55)Pastorale(4:15)。詳細は知らぬけれど、舞台音楽を委嘱され旧作からの転用+アルファに仕上げたものからの組曲とのこと。シンプルに闊達、多彩な変化があってこれも生粋な名曲でした。
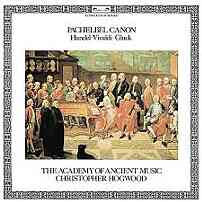 Pachelbel カノンとジーグ ニ長調/Vivaldi 4つのヴァイオリンのための協奏曲 ロ短調 作品3-10/Gluck 歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」第2幕 「復讐の女神の踊り」/「妖精の踊り」/Handel オラトリオ「ソロモン」第3幕 シンフォニア「シバの女王の入城」/Vivaldi 2つのトランペットのための協奏曲ハ長調 RV 537/Handel 歌劇「エジプト王妃ベレニーチェ」 序曲/「水上の音楽」組曲第1番 ヘ長調 HWV 348第6曲 「エアー /ホーンパイプ」~クリストファー・ホグウッド/アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージック(1980年)・・・Christopher Hogwood (1941-2014英国)トレヴァー・ピノックやジョン・エリオット・ガーディナー等と並んで英国古楽器界を牽引した人、晩年にはモダーン楽器アンサンブルや近現代にレパートリーを広げておりました。Haydnの交響曲全集が途中で打ち切りになったのは残念(売れなかったらしい)。これは所謂厳選バロック名曲集みたいな感じ。音質良好なLP復刻音源を入手できました。ここ50年ほど、古楽器復興、普及を経て演奏スタイルが変わったのがバロック音楽、速めのテンポに闊達軽快なリズムにもちろん小編成、こんな清潔な演奏が自分にとって(おそらくは世間一般でも)標準に至っていると思います。Albinoniの「アダージョ」と組み合わされることが多かったPachelbelは「カノン」(山下達郎「クリスマス・イヴ」途中の声楽に引用される)は昔のイメージからはずいぶん快速(オルガンの通奏低音が優しい)そしてちゃんと「ジーグ」が組み合わされることが多くなりました。Vivaldiは「調和の霊感」より、Bachも4台のチェンバロのために編曲した名曲、これは清潔快活な演奏。ちなみにトランペット協奏曲のソロはマイルド、想像よりテンポは余裕にゆったりめでした。Gluckは劇的、そして有名な「妖精の踊り」のフルートには痺れます。(ここまでA面26:21)
Pachelbel カノンとジーグ ニ長調/Vivaldi 4つのヴァイオリンのための協奏曲 ロ短調 作品3-10/Gluck 歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」第2幕 「復讐の女神の踊り」/「妖精の踊り」/Handel オラトリオ「ソロモン」第3幕 シンフォニア「シバの女王の入城」/Vivaldi 2つのトランペットのための協奏曲ハ長調 RV 537/Handel 歌劇「エジプト王妃ベレニーチェ」 序曲/「水上の音楽」組曲第1番 ヘ長調 HWV 348第6曲 「エアー /ホーンパイプ」~クリストファー・ホグウッド/アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージック(1980年)・・・Christopher Hogwood (1941-2014英国)トレヴァー・ピノックやジョン・エリオット・ガーディナー等と並んで英国古楽器界を牽引した人、晩年にはモダーン楽器アンサンブルや近現代にレパートリーを広げておりました。Haydnの交響曲全集が途中で打ち切りになったのは残念(売れなかったらしい)。これは所謂厳選バロック名曲集みたいな感じ。音質良好なLP復刻音源を入手できました。ここ50年ほど、古楽器復興、普及を経て演奏スタイルが変わったのがバロック音楽、速めのテンポに闊達軽快なリズムにもちろん小編成、こんな清潔な演奏が自分にとって(おそらくは世間一般でも)標準に至っていると思います。Albinoniの「アダージョ」と組み合わされることが多かったPachelbelは「カノン」(山下達郎「クリスマス・イヴ」途中の声楽に引用される)は昔のイメージからはずいぶん快速(オルガンの通奏低音が優しい)そしてちゃんと「ジーグ」が組み合わされることが多くなりました。Vivaldiは「調和の霊感」より、Bachも4台のチェンバロのために編曲した名曲、これは清潔快活な演奏。ちなみにトランペット協奏曲のソロはマイルド、想像よりテンポは余裕にゆったりめでした。Gluckは劇的、そして有名な「妖精の踊り」のフルートには痺れます。(ここまでA面26:21)
B面はHandel中心。ワクワクするような「シバの女王の入城」。Vivaldiを挟んで優雅に落ち着いた「エジプト王妃ベレニーチェ」 序曲、そして元気よろしい「水上の音楽」の有名なところに締めくくりました。これはさっぱりとした控えめな語り口。この辺りが自分の音楽嗜好の原点みたいな感じ。(26:40)懐かしい長岡鉄男推薦高音質録音らしい。
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
代わり映えのしない平穏な寒さ募る日々が過ぎて年末は押し迫ります。お仕事現役時代はなにかと忙しい時期に限って風邪などひいたものです。今年幸い、徐々に冷えてきてから体調は維持できております。それでも微妙に体調の上下はあって、昨日朝はやや不調、幸い服薬の効果はあって夜ちゃんと眠れているのに、どういうことか。朝、大量の洗濯物干してストレッチ、YouTubeに偶然出現した舶来別嬪さんの素っ気ない(けどちょっとキツい)エアロビクスを消化してから市立体育館へ「鍛えて治す!」昭和の誤った発想に出掛けました。休んだらそのまま精神がくじけて、ぐだぐだに崩れそうなのが怖い。トレーニングルームはマッチョなバーベル野郎が不在、筋トレ・マシンは思い通り使って、エアロバイクも含めていつもどおり、しっかり鍛えました。帰り、ここ数日似たような圧力鍋料理が続いたので、スーパーに寄って食材を仕入れました。
昼飯喰い過ぎたら胸焼け症状出現、体調は依然微妙です。なんの加減か、愛用するSimplenoteがいちいちメールにコード送信再認証要求復活して面倒くさくて仕方がない。定期的にそんなふうになるのでしょうか。紀州ドンファン(とやら)の元妻に無罪判決、いずれ自分は生命を狙われるような富裕資産とはまったく、寸分も縁がなくてよかった。今朝の体重は67.15kg変わらず三日目。
年末迫ってぼちぼち喪中はがきが届いております。日本郵便が赤字になるのは理解できる~我が家も既に仕舞ってしまった年賀状はもちろんだけど、社会一般に手紙はがきが減っているし、業者のダイレクトメールもEメールに置き換わっていることでしょう。総量は減っても全国隅々迄届ける仕組みは維持しなくっちゃいけない。海外からのお手紙でも現代はスマホで無料テレビ電話できる時代ですもんね。宅配便やゆうちょ、そして保険事業、通販はどんな感じでしょうか。社会構造や時代が変われば商売のあり方も変わるのがあたりまえ、民営化されてその経営手腕が問われます。
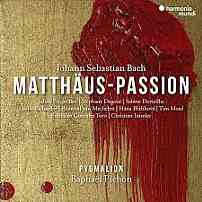 12月はBach。Bach マタイ受難曲~ラファエル・ピション/ピグマリオン/ユリアン・プレガルディエン((t)福音史家)/ステファヌ・ドゥグー((b)イエス)/ザビーヌ・ドゥヴィエル((s)ピラトの妻)/マイス・ド・ヴィルトレイ((s)召使1)/ペリーヌ・ドヴィエール((s)召使2)/ティム・ミード((a)証人1)/エミリアーノ・ゴンザレス=トロ((t)証人2)/クリスティアン・イムラー((b)カイアファ、ピラト)/エティエンヌ・バゾラ((b)ペトロ、大祭司1)/ゲオルク・フィンガー((b)ユダ、大祭司2)/ラジオ・フランス女声合唱(2021年)・・・荘厳かつ劇的、魅惑の多彩な旋律とリズムに溢れた大好きな作品。CD3枚分あまりの巨大さ、押し寄せる感動の大きさにそうそう拝聴機会はありません。Raphael Pichon(1984-仏蘭西)は現役旬のカウンター・テナーであり合唱指揮者。ピグマリオンとは2006年創立の合唱と古楽器アンサンブルとのこと。マタイと云えばメンゲルベルク、他歴代大指揮者が手掛けて、それも間違いなく濃厚な感動をいただけるけれど、新しいクリアな音質でこの名曲を堪能したいもの。
12月はBach。Bach マタイ受難曲~ラファエル・ピション/ピグマリオン/ユリアン・プレガルディエン((t)福音史家)/ステファヌ・ドゥグー((b)イエス)/ザビーヌ・ドゥヴィエル((s)ピラトの妻)/マイス・ド・ヴィルトレイ((s)召使1)/ペリーヌ・ドヴィエール((s)召使2)/ティム・ミード((a)証人1)/エミリアーノ・ゴンザレス=トロ((t)証人2)/クリスティアン・イムラー((b)カイアファ、ピラト)/エティエンヌ・バゾラ((b)ペトロ、大祭司1)/ゲオルク・フィンガー((b)ユダ、大祭司2)/ラジオ・フランス女声合唱(2021年)・・・荘厳かつ劇的、魅惑の多彩な旋律とリズムに溢れた大好きな作品。CD3枚分あまりの巨大さ、押し寄せる感動の大きさにそうそう拝聴機会はありません。Raphael Pichon(1984-仏蘭西)は現役旬のカウンター・テナーであり合唱指揮者。ピグマリオンとは2006年創立の合唱と古楽器アンサンブルとのこと。マタイと云えばメンゲルベルク、他歴代大指揮者が手掛けて、それも間違いなく濃厚な感動をいただけるけれど、新しいクリアな音質でこの名曲を堪能したいもの。
自信に充ちた速めのテンポに軽妙さ、弾むようなリズム感、歌い手たちの清涼な熱気、合唱のクリアに明朗な響き。かつての時に素っ気ない先鋭さばかり際立つような未熟な古楽器に非ず、ヴィヴィッド表情豊かにたっぷり劇的に力強い。技術的には充分成熟しているでしょう。声楽の扱いはノン・ヴィヴラートを基本にモダーンなセンスにのびのびと軽めに正確、こういうスタイルに慣れてしまうと往年のクサい詠嘆はなかなか聴けなくなりそう。器楽アンサンブルも通奏低音のオルガンが雄弁、コラールの強弱つけて表情豊かな表現は説得力を感じさせる陰影でした。エヴァンゲリストの清潔なテンションは往年のペーター・シュライヤーを思い出せば、時代の違い(良し悪しに非ず)をはっきりと感じさせました。「おお、頭は血潮にまみれ」「我らは涙を流してうずくまった」ここの合唱は誰の演奏であれ、涙なしには聴けませんよ。(長大なのでタイミングのメモは諦めました)
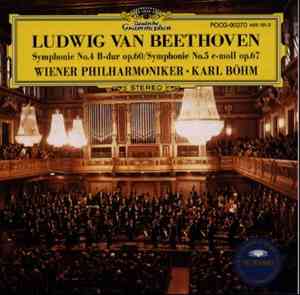 Beethoven 交響曲第4番 変ロ長調(1975年)/交響曲第5番ハ短調(1970年)~カール・ベーム/ウィーン・フィル・・・LP時代 Karl Bo"hm(1894-1981墺太利)の全集を入手、自分も当時若かったせいか「なんや、もっさりとした演奏やなぁ、失敗だったか」そう嘆いた記憶もありました。こうして8年ぶり聴いてみると、仰ぎ見るような堂々たる演奏は余裕、力みは感じさせない。
Beethoven 交響曲第4番 変ロ長調(1975年)/交響曲第5番ハ短調(1970年)~カール・ベーム/ウィーン・フィル・・・LP時代 Karl Bo"hm(1894-1981墺太利)の全集を入手、自分も当時若かったせいか「なんや、もっさりとした演奏やなぁ、失敗だったか」そう嘆いた記憶もありました。こうして8年ぶり聴いてみると、仰ぎ見るような堂々たる演奏は余裕、力みは感じさせない。
フルート1本という小さい編成なのが信じられぬヴィヴィッドな変ロ長調交響曲は慌てぬテンポ設定、弛緩を感じさぬバランスと勢いある第1楽章「Adagio - Allegro vivace」(12:15)第2楽章「Adagio」は符点のリズムも優雅に響いて、やがて静かな熱を感じさせます。クラリネットやホルンが美しい。(9:48)第3楽章「Allegro vivace」も噛み締めるように慌てず、やがてもりもりとした躍動を感じさせるところ。(5:55)第4楽章「Allegro ma non troppo」かなり遅い始まり、しっかり足許を確かめるような着実な歩みから、力のこもったアクセントが停滞を感じさせないパワーに充たされて、厚みのある響きは魅力。例のファゴットの難所はこのテンポではちょっと慎重過ぎ。クラリネットの低音の動きなどとても興味深く、各パートは明晰に浮き立ちます。(7:32)
全9曲中もっとも厳しい集中力と激しさを感じさせるハ短調交響曲。第1楽章「Allegro con brio」じっくり腰を据えて、抑制した緊張感に始まりました。スケールは大きく、提示部繰り返し有。ホルンが分厚くエエ音で鳴ってますね。音質の加減か、前曲より響きはやや薄く感じます。(8:35)第2楽章「Andante con moto」ここもじっくり構えてアクセントしっかり、寄せては返す波のように優雅に、落ち着いた味わい。(10:59)第3楽章「Allegro. atacca」ここは相当に遅い歩み。若い頃はもっさりと感じたのかも。トリオ「象のダンス」もテンポは上がらず、いかにも象の感じ。いやもうこれはこれで徹底していて、よろしいんじゃないでしょうか。(6:17)第4楽章「Allegro - Presto」前楽章が遅いだけに、ここの発射の勢いは相当に力強く感じます。輝かしいクライマックスも落ち着いた風情を湛えてパワフル、ラストようやく、ちょっぴりテンポと熱が上がります。繰り返しなし。(9:19)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
冬空に好天が続いて、週末にはちょっぴり雨の予報もあるようです。前日中途半端な時間に洗濯したからほとんど洗うべきものがなくてお休み。ストレッチと短時間のYouTubeエアロビクスは実施して、業務スーパーに切れていたキウイやオートミール他野菜など入手にウォーキング。合計で1日分必要な運動量は確保できたとのスマホ・アプリ情報でした。
一昨日の市立体育館帰り、例の美しくない疎水沿いの裏道、またカリンが落ちていて一個拾ってきました。糖分がないので腐らんのですよ。鳥も虫も喰わない。先日のジャムはアクが強かったけれど、これをカリン酒にしてみよう・・・女房殿に頼んで婆さん宅より小さい梅酒瓶、帰りに果実酒用焼酎を買ってきもらって、超絶硬い果実をむいて四苦八苦、適度な大きさに切って氷砂糖ならぬ砂糖は適当(あるもので済ませる/量は少ないような気がする)種も一緒に漬け込みました。アクというか渋はアルコールで抜けることでしょう。爽やかな香り最高です。一ヶ月以降から呑めるらしくて、最盛期は半年後、来年5-6月ですね。今朝の体重は67.15kg変わらず。
「自己満足こそ生きる力になる」~これは某ブログより、佳き言葉ですね。若い頃、お仕事現役時代、それはよろしからぬ意味合いに「自己満足」は使われていたと思うけれど、俗世から疎遠になると大切なのはそこなんでしょう。自費出版330万+宣伝費用にあれこれ100万近く掛けている爺友なんか、これなんやろなぁ。(経済感覚が足りないような気もするけれど)無為無策節約生活ばかりな自分と違って前向き、生きる力が漲(みなぎ)っているのでしょう。せいぜい【♪ KechiKechi Classics ♪】毎日更新+身体を鍛えるくらいが自己満足の類(たぐい)でしょうか。最近頻繁に使われるタイパ、コスパ・・・嫌いな言葉です。そんなブログ言及にも遭遇。まったく同感でした。
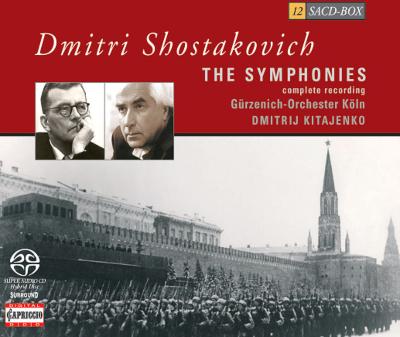 Shostakovich 交響曲第4番ハ短調~ドミトリー・キタエンコ/ギュルツェニヒ管弦楽団(2004年ライヴ)・・・2021年に拝聴記録有(記憶まったくなし)Dmitri Kitaenko(1940-露西亜)はもう年齢的に引退でしょうか。このShostakovich、Prokofievなど交響曲全曲録音で話題になったものです。若い頃から幾度挑戦して敗北、歯が立たなかったShostakovichもここ10年ほど、ようやく暗鬱な旋律サウンドを堪能できるようになりました。1936年に作曲され、権力の圧力により初演は1961年迄遅れたという曰く付き作品、例えば現在の日本で某楽曲が文化庁長官の意向に沿わないから放送禁止、なんてあり得ますか。そんな社会ぞっとしますよ。閑話休題(それはさておき)ずず暗く、重苦しいばかりの風情に絶望したのも昔の思い出。
Shostakovich 交響曲第4番ハ短調~ドミトリー・キタエンコ/ギュルツェニヒ管弦楽団(2004年ライヴ)・・・2021年に拝聴記録有(記憶まったくなし)Dmitri Kitaenko(1940-露西亜)はもう年齢的に引退でしょうか。このShostakovich、Prokofievなど交響曲全曲録音で話題になったものです。若い頃から幾度挑戦して敗北、歯が立たなかったShostakovichもここ10年ほど、ようやく暗鬱な旋律サウンドを堪能できるようになりました。1936年に作曲され、権力の圧力により初演は1961年迄遅れたという曰く付き作品、例えば現在の日本で某楽曲が文化庁長官の意向に沿わないから放送禁止、なんてあり得ますか。そんな社会ぞっとしますよ。閑話休題(それはさておき)ずず暗く、重苦しいばかりの風情に絶望したのも昔の思い出。
第1楽章「Allegretto poco Moderato - Presto」呻くような叫びに重い足取りの始まりから、明晰クリアな響きと切れ味、所謂露西亜風泥臭い風情とは無縁のわかりやすさに驚かされます。どこかのカスタマー・レビューにオーケストラの音色がオモロないとのコメントもあるけれど、デーハーな色彩を感じさせないのも個性、アンサンブルは精緻にかっちりとしてギュンター・ヴァント時代(1945-1974在任)のイメージとはかなり違って洗練されていると受け止めました。後半、狂気のPrestoには切迫した非常事態を感じさせないクリアな響き。(30:38)
第2楽章「Moderato con moto」は途方に暮れた歩み。ここは初めて聴いた時より意外とお気に入りのところ。ここも明晰な響きにあまり絶望的に響かない。(9:50)
第3楽章「Largo - Allegro」は葬送行進曲~序奏付の自由な変奏曲なんだそう。かなり難解にあちこち彷徨う音楽は、20分くらいの地響きする打楽器+金管楽器のクライマックスがやってきて、やがて力尽きるように不気味に悲しく収束・・・金管は力任せではないし、打楽器はクリアに浮き立って、静謐な部分に明晰を失わぬ立派な演奏でした。(28:38)
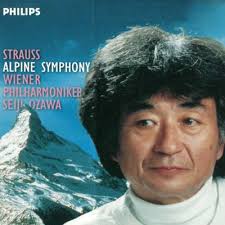 R.Strauss ウィーン・フィルハーモニーのためのファンファーレ/アルプス交響曲/ヨハネ騎士修道会の荘重な入場~小澤征爾/ウィーン・フィル(1996年)・・・CDデザインのセンス最悪だけど、演奏も音質も仕上げは極上でした。ウィーン・フィルのサウンドが生かされて入念、かつ素直なバランス表現に作品をたっぷり堪能いたしました。
R.Strauss ウィーン・フィルハーモニーのためのファンファーレ/アルプス交響曲/ヨハネ騎士修道会の荘重な入場~小澤征爾/ウィーン・フィル(1996年)・・・CDデザインのセンス最悪だけど、演奏も音質も仕上げは極上でした。ウィーン・フィルのサウンドが生かされて入念、かつ素直なバランス表現に作品をたっぷり堪能いたしました。
晴れやかな「ファンファーレ」からスタート、金管とティンパニのみかな?これは珍しい作品でしょう。(2:23)
「アルプス交響曲」は低音管楽器の存在感もアリルに、暗く静謐な夜 Nachtからスタート(3:19)~日の出 Sonnenaufgangの金管には厚みがあって(とくにホルン)輝かしくも爽快(1:37) ~登り道 Der Anstieg(舞台裏でホルンを中心とした金管楽器のファンファーレには痺れるほどの深みを感じる)(2:18)~森への立ち入り Eintritt in den Wald(トロンボーンとホルンによる/弦が優しい響き/4:49)~小川に沿っての歩み Wanderung neben dem Bache(0:43)~滝 Am Wasserfall (ハープ・チェレスタによる滝の流れがきらきら/0:15)~幻影 Erscheinung(水の中にオーボエの旋律による幻影/0:46)~花咲く草原 Auf blumigen Wiesen (0:56)山の牧場 Auf der Alm(カウベルによる牛の存在、牛の鳴き声とアルプホルンを模したホルンの魅力満開/2:04)~林で道に迷う Durch Dickicht und Gestrupp auf Irrwegen(1:26)氷河 Auf dem Gletscher(1:02)~危険な瞬間 Gefahrvolle Augenblicke(遠くから雷鳴=ティンパニのロール/1:24)頂上にて Auf dem Gipfel(トロンボーンが頂上の動機。ここから次はウィーン・フィルの圧巻のパワー爆発!クリアな各パート分離、最高の聴きどころ/4:49)~情景 Vision(ここはあまりに金管が輝かしいクライマックス/3:29)~霧が立ちのぼる Nebel steigen auf(ファゴットとヘッケルフォーン(低音オーボエ?)が不安げな旋律を奏でる/0:20)~しだいに日がかげる Die Sonne verdustert sich allmahlich(0:54)~哀歌 Elegie (2:20)~嵐の前の静けさ Stille vor dem Sturm(不安な気持ち、遠くから雷(バスドラムとサスペンデッドシンバル)風が吹き出してくる(ウィンドマシーン)/2:51)~雷雨と嵐、下山 Gewitter und Sturm, Abstieg(オルガンとウィンドマシーンによる風、サンダーマシーンによる落雷はリアルな迫力/3:50)日没 Sonnenuntergang(2:18)~終末 Ausklang(オルガンによる太陽の動機/5:58) ~夜 Nacht (2:19)
「ヨハネ騎士修道会の荘重な入場」も初耳の吹奏楽。ウィーン・フィルの金管の魅力爆発。(6:08)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
からっとした好天に年末は深まります。この時期乾燥するから全国各地火災が多いのと、物騒な強盗事件の報道は毎度のこと。女房殿不在でもいつも通りの朝目覚めてヘルシーな朝食、ストレッチ、YouTubeエアロビクスも済ませて市立体育館へ。レッグ・エクステンションから始めてその時点、最悪のマルチ・チェスト独占野郎登場、あわてて順番を変更してそれを先に済ませました。いつも通りゆる筋トレ+エアロバイク15分済ませてトレーニングルーム滞在は45分ほど、ここ最近寒いのでシャワーは使っておりません。帰宅したら女房殿がごっそり洗濯物持参して、ようやく洗濯機を回したものです。前夜はシャワーで済ませたのでフロの残り湯はなし、自動運転だからラクラク。冬空に干すのみ。今朝の体重は67.15kg+350g、先日衝動買いしたインスタントラーメンは5食、それを消化したのがあかんかったのか。せっかくの鍛錬も台無し。
藤沢周平 短編集「夜の橋 」。
書籍は拝読都度処分して、お仕事引退転居をを期に、常備していた池波正太郎、藤沢周平すべて処分、古代史関係のみは再読したかったので残しました。結果としてそれは大失敗、古代史関係は4冊くらいとぎれとぎれに読んで放置状態、ここ3年ほど読書の習慣そのものが激減してしまいました。この短編集は藤沢周平の作品中読み漏れていたもの。
いやぁ泣けますね、これ。時代ものにはスマホもテレビも、もちろんネットも登場しない、現代に通じる日本人の真髄が描かれていると感じます。町人や武士、農民の一筋縄とはいかぬ微妙な心の襞みたいなものが、とくに女性の心情の描き方が秀逸だと感じます。短編を一話ずつしみじみ後味を噛み締めるように、至福の時間を過ごしました。
山本一力「研ぎ師太吉」。久々すっかり時代ものにド・ハマリして一気読みしました。太吉を巡る、頑固な職人のワザと一本気な性格に魅力を感じつつ、犯人を拷問で口を割らせるというのはちょっと安易な手法でした。かつて思いを寄せた香織の行く末もちょっと心配です。他、諸田玲子「あくじゃれ瓢六捕物帖」など一気読み。これもなかなか楽しい、突拍子もない設定、女流らしいイケメン男性の描き方、女性の心の動きなど楽しめました。
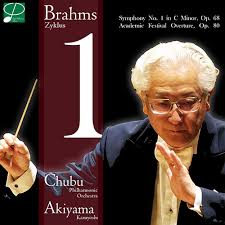 Brahms 交響曲第1番ハ短調/大学祝典序曲~秋山和慶/中部フィル(2017年しらかわホール・ライヴ)・・・既に広島交響楽団とのBrahms交響曲全曲録音している秋山和慶さん(1941ー日本)は中部フィルと再録音、長久手に在住している時にお仕事の関係で幾度も訪問した小牧市に、こんなプロ・オーケストラがあったとは知りませんでした。このホールには数回通ったことがあって、臨場感たっぷりな(おそらくは)優秀録音。CDに非ず、音源配信のみの提供みたい。時代ですね。表現の方向性はこの悠々堂々たる威容を誇る作品イメージに似合って重厚長大な浪漫、たっぷり歌って表現はオーソドックスに飾りが少ない。秋山さんの統率の下、オーケストラは頑張って誠実そのもの、但し素朴に過ぎてサウンドに色気とか華、リズムのキレが足りない。終盤クライマックスに向けてパワー不足が気になる・・・大学祝典序曲もちょっとノリに不足する感じ。実演に立ち会えば、きっとその熱気に感銘は深いのでしょう。(13:41-9:49-5:23-18:58/拍手有/12:09/拍手有)
Brahms 交響曲第1番ハ短調/大学祝典序曲~秋山和慶/中部フィル(2017年しらかわホール・ライヴ)・・・既に広島交響楽団とのBrahms交響曲全曲録音している秋山和慶さん(1941ー日本)は中部フィルと再録音、長久手に在住している時にお仕事の関係で幾度も訪問した小牧市に、こんなプロ・オーケストラがあったとは知りませんでした。このホールには数回通ったことがあって、臨場感たっぷりな(おそらくは)優秀録音。CDに非ず、音源配信のみの提供みたい。時代ですね。表現の方向性はこの悠々堂々たる威容を誇る作品イメージに似合って重厚長大な浪漫、たっぷり歌って表現はオーソドックスに飾りが少ない。秋山さんの統率の下、オーケストラは頑張って誠実そのもの、但し素朴に過ぎてサウンドに色気とか華、リズムのキレが足りない。終盤クライマックスに向けてパワー不足が気になる・・・大学祝典序曲もちょっとノリに不足する感じ。実演に立ち会えば、きっとその熱気に感銘は深いのでしょう。(13:41-9:49-5:23-18:58/拍手有/12:09/拍手有)
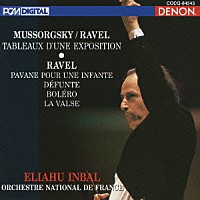 Mussorgsky/Ravel 編 組曲「展覧会の絵」/Debussy/Ravel 編 「ステイリー風のタランテラ」~舞曲/「ピアノのために」~サラバンド/Ravel 高雅にして感傷的なワルツ~エリアフ・インバル/フランス国立管弦楽団(1987-89年)・・・幾度聴いてもその乾いた音質、そして色気の足りない表現、非力なオーケストラの響きに好きになれなかった記憶もありました。これは残響が足りぬ乾いた音質、インバルの個性とオーケストラの個性が似合っていないのかも。それを前提に10年ぶり久々の拝聴印象は・・・露西亜風泥臭い旋律リズムとRavelの極色彩編曲が大好きな作品である「展覧会の絵」に色彩の陰影とか瑞々しさには足りぬけれど打楽器の低音迫力もリアル、デッドっぽいけれど解像度は高く、定位もしっかりとしたDENON録音、それはそれでクールな(というか神妙に寒々しい)サウンドと細部曖昧さのない緻密な表現を堪能いたしました。我が貧者の再生機器の能力にはあまり自信なし、もしかしたら高級オーディオに再生すると凄いのかも。Ravel編にはもっと賑やかに厚みのあるセクシー・サウンドや金管大爆発!が求めたいけれど、これはこれで知的な、ひとつの個性なんでしょう。以前ほどの違和感はありません。ラスト「 バーバ・ヤガー」から「キーウの大門」は各パート浮き立ってオモロいけれど、スカッ!と大爆発みたいなカタルシスに足りません。(1:43-2:54-0:57-4:15-0:32-1:13-2:25-0:43-1:19-2:24-1:24-1:56-1:51-3:34-5:16)
Mussorgsky/Ravel 編 組曲「展覧会の絵」/Debussy/Ravel 編 「ステイリー風のタランテラ」~舞曲/「ピアノのために」~サラバンド/Ravel 高雅にして感傷的なワルツ~エリアフ・インバル/フランス国立管弦楽団(1987-89年)・・・幾度聴いてもその乾いた音質、そして色気の足りない表現、非力なオーケストラの響きに好きになれなかった記憶もありました。これは残響が足りぬ乾いた音質、インバルの個性とオーケストラの個性が似合っていないのかも。それを前提に10年ぶり久々の拝聴印象は・・・露西亜風泥臭い旋律リズムとRavelの極色彩編曲が大好きな作品である「展覧会の絵」に色彩の陰影とか瑞々しさには足りぬけれど打楽器の低音迫力もリアル、デッドっぽいけれど解像度は高く、定位もしっかりとしたDENON録音、それはそれでクールな(というか神妙に寒々しい)サウンドと細部曖昧さのない緻密な表現を堪能いたしました。我が貧者の再生機器の能力にはあまり自信なし、もしかしたら高級オーディオに再生すると凄いのかも。Ravel編にはもっと賑やかに厚みのあるセクシー・サウンドや金管大爆発!が求めたいけれど、これはこれで知的な、ひとつの個性なんでしょう。以前ほどの違和感はありません。ラスト「 バーバ・ヤガー」から「キーウの大門」は各パート浮き立ってオモロいけれど、スカッ!と大爆発みたいなカタルシスに足りません。(1:43-2:54-0:57-4:15-0:32-1:13-2:25-0:43-1:19-2:24-1:24-1:56-1:51-3:34-5:16)
珍しいDebussy作品からの編曲も貴重な録音、これは夢見るようにデリケートな旋律に、淡い色彩が加わりました。(5:37/4:37)「ワルツ」も緻密にクール、そしてデリケートなのは同じ。「展覧会の絵」ほどにパワーと熱気を求めないから、なかなかエエ感じに神妙と感じました。管楽器はなかなかセクシーな音色。(1:20-3:16-1:46-1:17-1:30-0:59-3:11-4:12-1:20-3:16-1:46-1:17-1:30-0:59-3:11-4:12)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
年末らしい気温は落ちてきて、好天が続きます。千年一日の如く同じ生活、前夜の深酒を後悔させる不快感を抱えつついつもの洗濯はけっこうな物量、せめてものストレッチ、YouTubeエアロビクスは短いものを消化して、鼻詰まり痰の絡み限界症状に耳鼻科を目指してウォーキング。人気の耳鼻科はいつもどおり激混み、予約時間より30分ほど押してしまうのは折込済でした。その頃に前夜過ぎた酒の悪しき名残りはすっかり抜け(しばらく服薬をサボっていた)どっさりクスリをいただいて、帰り業務スーパーに寄って夕食の食材を仕入れました。往復4.26kmのウォーキング。昼から女房殿から連絡有、婆さんといっしょに急遽コロナのワクチン接種となって、副反応が心配なので泊まってくるとのこと。今朝の体重は66.8kg▲100g。独りだし、ずいぶんと食事を抑制したつもりでもほとんど減らない。
シリアのアサド政権崩壊。だからといって反政府軍の安定した政権ができるわけでもないらしい。トルコに300万人の難民がいるそうですね。お隣・韓国も迷走状態だし(どちらに転んでも来春くらいにはゴリゴリの反日政策に戻っていると予測)独逸も不安定な状態が続いて、羅馬尼亜は大統領選やり直しとか。トランプさんが動き出して、さて烏克蘭はどうなるのでしょう。日本もいろいろ物騒だけど、比較的ちょっぴりまだマシなのかも。
Yahoo記事に載っていた「年金一人暮らしのぺこりーの」
にはすっかり感心いたしました。これはブログの記事を淡々と動画にしていたのですね。
ぺこりーのさんは自分と同年齢の爺、奥様を先に亡くして東京世田谷区に独り住まい。ベストセラー(「妻より長生きしてしまいまして。金はないが暇はある、老人ひとり愉快に暮らす」)も上梓したYouTuber。若い女性に(妙齢の方も)比べると絵面云々さておき(とっても失礼ごめんなさい)抑えたフツウの動画と淡々とした字幕が押し付けがましくなく、静かな感動を呼びます。幼い頃両親との関係に苦労されて優しい祖父母に育てられ、立派な社会人として働き、やがて引退して年金暮らしの老後を過ごされる現在の潔い姿が眩しいくらい。料理も美しく上手だし、服装も食器も調理器具も皆オシャレ、厳選されたていねいな生活を送っていらっしゃる。自分は犬をあまり好まないけれど、老ペットとの関係も微笑ましい。ビールもラーメンも美味しそう。世代には世代に似合った動画というものがありますよ。年金で足りなかったら、自分で工夫して稼ぐ工夫をせよ、との訴えには説得力がありました。
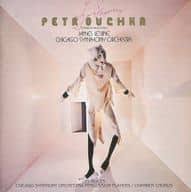 Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)~ジェームズ・レヴァイン/シカゴ交響楽団/メアリー・サウアー(p)(1977年)・・・晩節を汚して病のうちに亡くなったJames Levine(1943-2021亜米利加)34歳若手時代の記録。小澤征爾やこのレヴァインなどラヴィニア音楽祭には次世代の若手が育ちました。これは三管編成の1947年版、浮き立つような遊園地の喧騒を連想させる賑やかな名曲、やや速めのテンポに前のめりに華やかな、活気ある若々しい演奏でした。もしかしてシカゴ交響楽団にとって初めての録音?ジョージ・ショルティ時代のオーケストラは上手いですよ。腰が落ち着かない雰囲気も若手に相応しい、勢いたっぷり元気なきらきら輝くようなサウンド。(33:47)
Stravinsky バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)~ジェームズ・レヴァイン/シカゴ交響楽団/メアリー・サウアー(p)(1977年)・・・晩節を汚して病のうちに亡くなったJames Levine(1943-2021亜米利加)34歳若手時代の記録。小澤征爾やこのレヴァインなどラヴィニア音楽祭には次世代の若手が育ちました。これは三管編成の1947年版、浮き立つような遊園地の喧騒を連想させる賑やかな名曲、やや速めのテンポに前のめりに華やかな、活気ある若々しい演奏でした。もしかしてシカゴ交響楽団にとって初めての録音?ジョージ・ショルティ時代のオーケストラは上手いですよ。腰が落ち着かない雰囲気も若手に相応しい、勢いたっぷり元気なきらきら輝くようなサウンド。(33:47)
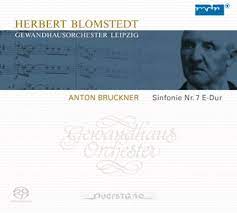 Bruckner 交響曲第7番ホ長調(ハース版)~ヘルベルト・ブロムシュテット/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(2006年ライヴ)・・・細身に痩せた音質との評価もあるそうだけれど、オーディオには疎い自分にはさほどに悪い音質とは思えない。各パートの分離もクリアに浮き立ちます。最長老指揮者による、これはBrucknerの交響曲中、屈指の美しい旋律を誇る穏健な作品。第1楽章「Allegro moderato」から飾りのない真っ直ぐな表現に清潔なサウンド。テンポの動きにあざとさの欠片もない、爽やかな始まり。アンサンブルの集中力になんの不満もありません。(21:33)第2楽章「Adagio,Sehr feierlich und sehr langsam」この緩徐楽章は万感胸に迫る白眉。デリケートな弦が粛々と歌って誠実な歌が広がって呼吸が深い。クライマックスには打楽器が入らぬ版?のはずが、ティンパニが盛大に参入しました。弦と管の各パートがクリアに浮き上がり快く響きあって、ホルンやワーグナー・チューバの音色が惚れ惚れするほど美しい。(24:21)第3楽章「Scherzo:Sehr schnell-Trio:Etwas langsamer」はBrucknerのキモであるスケルツォ。金管の爆発がメタリックならない滋味深さ。適切なリズム感と適度な力感に余裕を感じさせます。(10:09)第4楽章「Finale,Bewegt, doch nicht schnell 」フィナーレもぐっと肩の力が抜けて、さらりとした始まり。詠嘆とか粘着質とは無縁の淡々とした歩み、こんな演奏が聴き疲れしないで安心して聴けました。(12:44)
Bruckner 交響曲第7番ホ長調(ハース版)~ヘルベルト・ブロムシュテット/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(2006年ライヴ)・・・細身に痩せた音質との評価もあるそうだけれど、オーディオには疎い自分にはさほどに悪い音質とは思えない。各パートの分離もクリアに浮き立ちます。最長老指揮者による、これはBrucknerの交響曲中、屈指の美しい旋律を誇る穏健な作品。第1楽章「Allegro moderato」から飾りのない真っ直ぐな表現に清潔なサウンド。テンポの動きにあざとさの欠片もない、爽やかな始まり。アンサンブルの集中力になんの不満もありません。(21:33)第2楽章「Adagio,Sehr feierlich und sehr langsam」この緩徐楽章は万感胸に迫る白眉。デリケートな弦が粛々と歌って誠実な歌が広がって呼吸が深い。クライマックスには打楽器が入らぬ版?のはずが、ティンパニが盛大に参入しました。弦と管の各パートがクリアに浮き上がり快く響きあって、ホルンやワーグナー・チューバの音色が惚れ惚れするほど美しい。(24:21)第3楽章「Scherzo:Sehr schnell-Trio:Etwas langsamer」はBrucknerのキモであるスケルツォ。金管の爆発がメタリックならない滋味深さ。適切なリズム感と適度な力感に余裕を感じさせます。(10:09)第4楽章「Finale,Bewegt, doch nicht schnell 」フィナーレもぐっと肩の力が抜けて、さらりとした始まり。詠嘆とか粘着質とは無縁の淡々とした歩み、こんな演奏が聴き疲れしないで安心して聴けました。(12:44)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
新しい一週間の始まりも好天続き。昨日は地元「第九」演奏会に当日駆けつけるつもりが、爺友との忘年会が入ってしまいました。ここ一年ほど生演奏体験から疎遠になって、反省しております。いつも通り朝の洗濯、ストレッチ+YouTube「【食後の早歩き】ビートにのって楽しく踊る有酸素運動で全身スッキリダイエット!朝のラジオ体操にも使える」10分ほど済ませて市立体育館へ。道中けっこう寒く、途中ビニール袋2個分のゴミ拾い功徳を積みました。トレーニングルームは日曜常連メンバー(おそらくお仕事現役世代)+学生数名に空いていて、自分が思った通りの順番に筋トレ・マシン全身ユルく鍛えました。エアロバイク途中、スマートウォッチに電話着信案内有(安物だからそのまま通話は不可)あわてて中断してリュックのポケットにスマホを探ったものです。名古屋の先輩より新年会の相談、自分は肌見放さずスマホを常に携帯という習慣はないので、時に不義理を重ねる(不在着信状態)こともあって、今回初めてその機能を使えました。
爺友+一回り下の現役幹部のミニ忘年会はいつもの梅田駅前ビル地下。その前に早めに出掛けて京橋BOOK・OFFにて時代小説を三冊ほど仕入れておきました。いつもの勝手気ままな罵詈雑言合戦、散々呑んで帰宅は夕方6時半頃、健全ですよ。ま、身体にはあまりよろしくないけど。今朝の体重は66.9kg+300gは仕方がない。本日はようやくの耳鼻科行き。
「勿体無い」~YouTubeの題名を眺めて、これはひどい!と感じました。コンピューターの変換が安易に出現するから、普段使わぬ漢字表現が多く使われて「有難う御座居ました」みたいなのもありましたっけ。漢字は適度に使うと文書が引き締まるし、意味がわかりやすくなるもの。日本語は融通無礙に変化していくものだけど、正しい日本語も大切だと思います、誤字脱字連続な自分が云々するのもナニだけど。寺社仏閣歴史的城郭ブームが定着したように「美しい日本語ブーム」が巻き起こらぬものでしょうか。
それとはちょっと違う話題、LINEにやたらと絵文字を使うのは高年齢世代だそう。ブログなんかでも見掛けるけれど、たしかに絵文字多用!はうざったらしい(←これも新しい日本語か?)ですよね。自分は滅多に使用してないつもり。稀に(涙)(遠い目)は使用します。
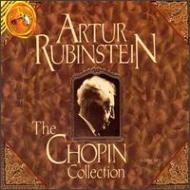 Chopin 即興曲 第1番 変イ長調 作品29/第2番 嬰ヘ長調 作品36/第3番 変ト長調 作品51/第4番 幻想即興曲 嬰ハ短調 作品66/舟歌 嬰ヘ長調 作品60/3つの新練習曲(モシェレスのメトードのための)/ボレロ 作品19/子守歌 変ニ長調 作品57/タランテラ 変イ長調 作品43/アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調 作品22~アルトゥール・ルービンシュタイン(p)(1962-65年)・・・数カ月ぶりにお釈迦HDDが偶然蘇って、Arthur Rubinstein(1887ー1982波蘭)のChopinが我が手に帰ってまいりました。技術的にキレるピアニストはいくらでもいるけれど、この暖かいふっくらとした余裕のタッチが聴きたかった。音質も充分。気紛れに躊躇いがちに揺れる即興曲(4:14-6:01-4:50)劇的な緊張感を呼ぶ哀愁の旋律「幻想即興曲」の表情の変化と流れのよさと(5:17)懐かしさ漂ってゆっくり川面に流れるように、やがて情感が高まっていく「舟唄」(9:28)小粋な陰影を感じさせる「新練習曲」(5:46)情熱的に闊達なリズムを刻む「ボレロ」(8:22)細かい音型が自在に踊ってシンプルなリズムを繰り返す「子守唄」(4:35)闊達に弾むような「タランテラ」(3:16)
Chopin 即興曲 第1番 変イ長調 作品29/第2番 嬰ヘ長調 作品36/第3番 変ト長調 作品51/第4番 幻想即興曲 嬰ハ短調 作品66/舟歌 嬰ヘ長調 作品60/3つの新練習曲(モシェレスのメトードのための)/ボレロ 作品19/子守歌 変ニ長調 作品57/タランテラ 変イ長調 作品43/アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調 作品22~アルトゥール・ルービンシュタイン(p)(1962-65年)・・・数カ月ぶりにお釈迦HDDが偶然蘇って、Arthur Rubinstein(1887ー1982波蘭)のChopinが我が手に帰ってまいりました。技術的にキレるピアニストはいくらでもいるけれど、この暖かいふっくらとした余裕のタッチが聴きたかった。音質も充分。気紛れに躊躇いがちに揺れる即興曲(4:14-6:01-4:50)劇的な緊張感を呼ぶ哀愁の旋律「幻想即興曲」の表情の変化と流れのよさと(5:17)懐かしさ漂ってゆっくり川面に流れるように、やがて情感が高まっていく「舟唄」(9:28)小粋な陰影を感じさせる「新練習曲」(5:46)情熱的に闊達なリズムを刻む「ボレロ」(8:22)細かい音型が自在に踊ってシンプルなリズムを繰り返す「子守唄」(4:35)闊達に弾むような「タランテラ」(3:16)
そしてChopin、ルービンシュタインの魅力に目覚めた大好きな「アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ」。甘い夢が静かに水面を滑るような「アンダンテ・スピアナート」そして歓喜が湧き上がるようにリズミカルな舞曲「ポロネーズ」に移行する経過の名残惜しさ絶品!至福の時間を過ごしました。(15:01)
 Bach ブランデンブルク協奏曲第4番ト長調BWV1049/第5番ニ長調BWV1050/第6番 変ロ長調BWV1051~ニコラウス・アーノンクール/ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス/レオポルト・シュタストニー(fl)/アリス・アーノンクール(v)/ゲオルグ・フィッシャー(cem)(1964年)・・・旧録音。LP時代の超豪華な装幀は新しいほうでしたっけ?貧しい若者には手が出ぬ高級品でした。この作品史上初の古楽器録音?そんな宣伝文句があるけれど、例えばアウグスト・ヴェンツィンガーとか、ホーレンシュタインは違うのか。この作品は大好きでして、いったいいくつ音源を集めたのか~散々聴いてきて、この古楽器演奏も特別特異な個性とは受け止めなくなりました。ヴィヴィッドに表情豊かに余裕の響き、先鋭的なリズムとは感じません。二本のリコーダーが晴れやかに笑顔が溢れるようなト長調協奏曲BWV1049、アリスのヴァイオリン・ソロもクールな超絶技巧(7:32-4:09-5:01)史上初の鍵盤協奏曲?であるニ長調協奏曲BWV1050の見事なソロはGeorg Fischer、名手Leopold Stastnyの名前も懐かしい豊かな響き、皆鬼籍に入りました。(11:08-6:04-5:47)ヴァイオリンを欠く特異な編成である 変ロ長調協奏曲BWV1051はたしかアーノンクール自らガンバでしたっけ?参加しているはず。(5:52-4:47-6:05)
Bach ブランデンブルク協奏曲第4番ト長調BWV1049/第5番ニ長調BWV1050/第6番 変ロ長調BWV1051~ニコラウス・アーノンクール/ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス/レオポルト・シュタストニー(fl)/アリス・アーノンクール(v)/ゲオルグ・フィッシャー(cem)(1964年)・・・旧録音。LP時代の超豪華な装幀は新しいほうでしたっけ?貧しい若者には手が出ぬ高級品でした。この作品史上初の古楽器録音?そんな宣伝文句があるけれど、例えばアウグスト・ヴェンツィンガーとか、ホーレンシュタインは違うのか。この作品は大好きでして、いったいいくつ音源を集めたのか~散々聴いてきて、この古楽器演奏も特別特異な個性とは受け止めなくなりました。ヴィヴィッドに表情豊かに余裕の響き、先鋭的なリズムとは感じません。二本のリコーダーが晴れやかに笑顔が溢れるようなト長調協奏曲BWV1049、アリスのヴァイオリン・ソロもクールな超絶技巧(7:32-4:09-5:01)史上初の鍵盤協奏曲?であるニ長調協奏曲BWV1050の見事なソロはGeorg Fischer、名手Leopold Stastnyの名前も懐かしい豊かな響き、皆鬼籍に入りました。(11:08-6:04-5:47)ヴァイオリンを欠く特異な編成である 変ロ長調協奏曲BWV1051はたしかアーノンクール自らガンバでしたっけ?参加しているはず。(5:52-4:47-6:05)
参加メンバー作品ごとの詳細こちらリンク先へ)
Otto Fleischmann(fg)/Leopold Stastny(fl)(rec)/Georg Fischer(cem)/Hans Fischer, Hermann Rohrer(hr)/Jurg Schaeftlein(ob)(rec)/Walter Holy(tp)/Kurt Theiner(va)/Ernst Knava, Nikolaus Harnoncourt(gamba)/Alice Harnoncourt, Josef de Sordi, Siegfried Fuhrlinger, Stefan Plott(v)/Alice Harnoncourt(Violino Piccolo)/Hermann Hobarth, Nikolaus Harnoncourt(vc)/Eduard Hruza(Violone)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
昨日土曜も好天。今朝はぐっと冷えますね。独り暮らしに戻った婆さん(94歳)のところから洗濯物を持ち帰る女房殿、シーツはたっぷり分厚く暖かそうなもの。洗濯機稼働は一回では終わりません。
しっかりストレッチ、いつものYouTubeエアロビクス15分済ませて、久々気分転換にコンピューターのキーボードでも変えようかな、段ボール取り出したら恨めしいお釈迦HDD2TB出現、ものは試しとダメ元コンピューターに繋いだら・・・奇跡!!! あれほど幾度トライしても認識しなかったのになぜか復活しました。しばらく寝かしたのがよろしかったのか、偶然か。次回接続時に認識するのかは微妙なので、目ぼしいものをコンピューター本体SSD容量許す限り移動途中。
ここしばらくの悲嘆と悪戦苦闘+出費はなんだったのか・・・いえいえ、集めるだけ集めてすっかり忘れて放置していた音源の貴重なこと、有り難さを再認識、失った音源はできる限り再入手して厳選!音楽としっかり向き合う時間となりました。日常生活に大きな支障をきたすわけでもなし、生命にも別状なし、人生に発生するあらゆる事象には理由(わけ)がある・・・妙に哲学的なことを考えてしまいました。
結果、向き合うべき膨大な(ステキな)音源がどっと増え(復活し)ました。さて、なにから手を付けましょうか。これはこれでシアワセな出来事でした。終日音源整理などして引き隠り状態。料理は在庫で仕立てました。本日爺友より第1回忘年会のお誘い有。年末の寒空に風邪などひかぬよう気を付けましょう。ちなみに大学時代の某OB会の流れ、名古屋にて新年会の開催が決まりました。贅沢なもんですよ。今朝の体重は66.6kg▲400g。
 Ravel ラ・ヴァルス/マ・メール・ロワ/ツィガーヌ/ボレロ/逝ける女王のためのパヴァーヌ~カルロ・リッツィ/ゴルダン・ニコリッチ(v)/オランダ・フィル(2012年)・・・Carlo Rizzi(1960ー伊太利)によるRavelは以前2曲のみ収録されるLP復刻を聴いていたけれど、CDではこの5曲が収録されていたみたい。リッツィはオペラの人だから、歌劇場のピットに入ることもあるオランダ・フィルとはその流れの録音でしょう。TACETは優秀録音を誇るレーベル、前回拝聴時には、整ったアンサンブルに技術的には優秀、飾りの少ない表現にメリハリ迫力も充分、沸き立つように妖しくもエッチな色気や色彩個性は期待できない・・・とは失礼なコメント。「沸き立つように妖しくもエッチな色気や色彩個性」は誰の演奏を基準にしていたのか、今回初耳だったマ・メール・ロワ/ツィガーヌ/逝ける女王のためのパヴァーヌはデリケートに清潔、ていねいな仕上げ、とくに「マ・メール・ロワ」は大好きな作品、メルヘンに充ちて文句なしの演奏でしょう。Gordan Nikolitch(1968-塞爾維)はロンドン交響楽団のコンマスを務めた人、泥臭い旋律を上品に表現してくださいました。(12:16/1:49-3:47-4:00-4:57-3:40/9:25/16:38/6:36)
Ravel ラ・ヴァルス/マ・メール・ロワ/ツィガーヌ/ボレロ/逝ける女王のためのパヴァーヌ~カルロ・リッツィ/ゴルダン・ニコリッチ(v)/オランダ・フィル(2012年)・・・Carlo Rizzi(1960ー伊太利)によるRavelは以前2曲のみ収録されるLP復刻を聴いていたけれど、CDではこの5曲が収録されていたみたい。リッツィはオペラの人だから、歌劇場のピットに入ることもあるオランダ・フィルとはその流れの録音でしょう。TACETは優秀録音を誇るレーベル、前回拝聴時には、整ったアンサンブルに技術的には優秀、飾りの少ない表現にメリハリ迫力も充分、沸き立つように妖しくもエッチな色気や色彩個性は期待できない・・・とは失礼なコメント。「沸き立つように妖しくもエッチな色気や色彩個性」は誰の演奏を基準にしていたのか、今回初耳だったマ・メール・ロワ/ツィガーヌ/逝ける女王のためのパヴァーヌはデリケートに清潔、ていねいな仕上げ、とくに「マ・メール・ロワ」は大好きな作品、メルヘンに充ちて文句なしの演奏でしょう。Gordan Nikolitch(1968-塞爾維)はロンドン交響楽団のコンマスを務めた人、泥臭い旋律を上品に表現してくださいました。(12:16/1:49-3:47-4:00-4:57-3:40/9:25/16:38/6:36)
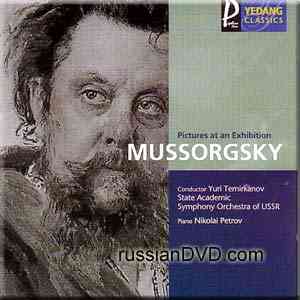 Mussorgsky/Ravel編 組曲「展覧会の絵」~ユーリ・テミルカーノフ/ソヴィエット国立交響楽団(State Academic Symphony Orchestra of USSR/1980年ライヴ)・・・YedangClassics YCC-00003のCDは処分してしまって、このライヴはもう聴けない・・・と思ったら、露西亜の怪しいサイトより(おそらくは同一)音源入手出来。9年ぶりに再聴いてみました。オン・マイクにかなり鮮明な音質、ライヴならではの管楽器ミスや音の外しもリアル、まず他では聴けぬ荒々しいド迫力な泥臭いアクをたっぷり堪能できました。オリジナルの野蛮な旋律リズムをしっかり堪能させてくださいました。サウンドのバランスとかアンサンブルの緻密な完成度はロイヤル・フィル(1989年)とのセッション録音のほうが上だけど、こちらエッチな金管のヴィヴラートも忘れがたい熱気たっぷり。(1:41-3:06-0:59-4:32-0:33-1:09-2:37-0:45-1:16-1:48-4:30-2:08-8:06)(この後、ニコライ・ペトロフのオリジナル・ピアノ版音源も入手)
Mussorgsky/Ravel編 組曲「展覧会の絵」~ユーリ・テミルカーノフ/ソヴィエット国立交響楽団(State Academic Symphony Orchestra of USSR/1980年ライヴ)・・・YedangClassics YCC-00003のCDは処分してしまって、このライヴはもう聴けない・・・と思ったら、露西亜の怪しいサイトより(おそらくは同一)音源入手出来。9年ぶりに再聴いてみました。オン・マイクにかなり鮮明な音質、ライヴならではの管楽器ミスや音の外しもリアル、まず他では聴けぬ荒々しいド迫力な泥臭いアクをたっぷり堪能できました。オリジナルの野蛮な旋律リズムをしっかり堪能させてくださいました。サウンドのバランスとかアンサンブルの緻密な完成度はロイヤル・フィル(1989年)とのセッション録音のほうが上だけど、こちらエッチな金管のヴィヴラートも忘れがたい熱気たっぷり。(1:41-3:06-0:59-4:32-0:33-1:09-2:37-0:45-1:16-1:48-4:30-2:08-8:06)(この後、ニコライ・ペトロフのオリジナル・ピアノ版音源も入手)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
終末を迎え途中覚醒三日連続。これが華麗なる加齢の実体か。そして朝寝坊したけれど洗濯、ストレッチ、そしてYouTube「【15分間の滝汗有酸素運動】早いペースのウォーキングで脂肪燃焼しましょう」実施、いつもの時間に市立体育館を目指しました。トレーニングルームは常連メンバーに空いていて「奥様最近見ませんね」と声を掛けられました。自分と違っていろいろ多忙、時間を変えてちゃんと継続中です。いつもの全身ユル筋トレ+エアロバイク15分の有酸素運動こなして気分爽快に帰宅いたしました。ここ数日、久々に時代小説に入れ込んで読書は進んでおります。自分は近眼乱視、読書やコンピューター作業時には度数の弱い眼鏡(2個)を愛用して老眼鏡は必要ありません。ちゃんとそれなり度数の合った眼鏡は2個、ちょっとレンズに傷があるのとフレームデザインが気に喰わないし、運転もしていないのであまり使っていないけれど、既に10年選手?新しいのを作るかどうかちょっと逡巡中。今朝の体重は67.0kg+350g。
中山美穂さん(54)突然の死亡の知らせ、経緯はわかりません。ヒートショック?お隣韓国の大統領さんはなかなか厳しい状況ですね、これでもう「反日バネ」確実なんやろなぁ、いろいろとこれからが悩ましい。
穫れない葡萄は酸っぱい~そう理解して欲しいけれど、自分はオーディオに一切カネを掛けておりません。基本生来のビンボー症、Kechiな性癖なのとやりだすとキリがないから。機器はもちろん、音響を考えるとそれを鳴らす居住空間も必要でしょ?それとオーディオ通の方に伺った話題だけれど、某金満愛好家の自慢のセットを聴いてみたら数百万の成果も愕然とするほど・・・いぇいぇ本人がそれでシアワセならそれでOK。周りは云々すべきでもない・・・
CDを諦めてデータ移行を進めて十数年、お仕事引退迄に膨大なるCDはぜんぶ段ボールに詰めて中古屋さんに送りました。そして2023年にDVD保存→HDDに変更した時点で(ほぼ基本).mp3音源を諦めました。キリがないので。悩ましいのがやたらとファイルサイズが大きな高品質音源・・・いくつか保存してあるけれど残念、それを我が貧者のオーディオ環境に再生してもびっくりするほどの成果は上げられない・・・「身分相応」「身の丈に似合った」ものではないと自覚できました。所詮場末の引退爺の老後の愉しみ、通常5-600kbps程度の.flacや.ape圧縮音源で充分と考えております。
 Shostakovich 交響曲第11番ト短調「1905年」/ジャズ組曲第1番/第2番よりワルツ第2番/タヒチ・トロット~マリス・ヤンソンス/フィラデルフィア管弦楽団(1996年)・・・三管編成+8種の打楽器+ハープ2‐4台+チェレスタという編成。Mariss Jansons(1943-2019拉脱維亜)の全集録音より、これは珍しいフィラデルフィアとの顔合わせ。厚みのある明快な響きにオーケストラの技量最高、この作品はわかりやすく、平易に響きました。
Shostakovich 交響曲第11番ト短調「1905年」/ジャズ組曲第1番/第2番よりワルツ第2番/タヒチ・トロット~マリス・ヤンソンス/フィラデルフィア管弦楽団(1996年)・・・三管編成+8種の打楽器+ハープ2‐4台+チェレスタという編成。Mariss Jansons(1943-2019拉脱維亜)の全集録音より、これは珍しいフィラデルフィアとの顔合わせ。厚みのある明快な響きにオーケストラの技量最高、この作品はわかりやすく、平易に響きました。
第1楽章「王宮広場(Adagio)」背中がゾクゾクするような怪しい静謐。弱音にテンションの落ちぬオーケストラの技量と音楽が行方不明にならぬ明晰な響きと表現は秀逸。(16:08)
第2楽章「1月9日(Allegro)」は圧巻の機関銃の爆発が快感、フィラデルフィア管弦楽団の実力発揮!な場面は初めてこの演奏をFMより聴いた時より衝撃でした。。(19:39)
第3楽章「永遠の記憶(Adagio)」は死者へのレクイエム(緩徐楽章)だけど、この旋律は露西亜民謡風に俗っぽく、その甘い旋律を上品静謐に仕上げてなかなか上出来でした。(11:39)
第4楽章「警鐘(Allegro non troppo)」ここはいっそう俗っぽいプロパガンダ風勇壮なフィナーレ。誰も知っている(例えば)ワルシャワ労働歌などが引用され、これも圧巻の輝かしくも分厚い響きに激しい盛り上がりをみせます。やがて第1楽章の静謐が回帰してから、圧巻のラッシュから暴力的に締め括りました。(16:12)
「ジャズ組曲」は旧き佳き時代を感じさせて、なんとも懐かしいセピア色の音楽。これは安っぽいジンタがエエ味出してますよ、シンタは死語かな?(2:34-1:41-3:54/3:50)「タヒチ・トロット」はVincent Youmans「二人でお茶を」をShostakovichがなんとも小粋にアレンジしたもの。個人的にShostakovichの作品中、もっともお気に入り。(3:31)
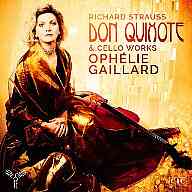 R.Strauss チェロ・ソナタ ヘ長調 作品6*/ロマンス ヘ長調/交響詩「ドン・キホーテ」(騎士的な性格の一つの主題による幻想的変奏曲) 作品35/「あした」~4つの歌 作品27より(作曲者によるチェロ、ピアノとソプラノのための編曲版)*~オフェリー・ガイヤール(vc)/アレクサンドラ・コヌノヴァ(v)/ドヴ・シェインドリン(va)/ヴァシリス・ヴァルヴァレソス(p)*/ベアトリス・ウリア・モンゾン(ms)/ジュリアン・マスモンデ/チェコ・ナショナル交響楽団(2017-18年)・・・Ophelie Gaillard(1974-仏蘭西)は現役旬のチェリスト。2018年に拝聴済。これはリアルな音質と演奏でした。チェロ・ソナタ ヘ長調は学生時代の作、ほとんどBrahmsをイメージさせる王道の浪漫風作品でした。湧き上がるような若さ一杯の活気を感じさせる雄弁な旋律が続く「Allegro con brio」(9:30)たっぷり甘い愛が囁く「Andante ma non troppo」(8:25)闊達に晴れやかにリズミカルな「Allegro vivo」(9:09)。ロマンス ヘ長調はチェロと管弦楽による同時期の作品。囁くようにデリケートに優しい旋律から、雄弁に楽しげな歌が続きました。(8:36)
R.Strauss チェロ・ソナタ ヘ長調 作品6*/ロマンス ヘ長調/交響詩「ドン・キホーテ」(騎士的な性格の一つの主題による幻想的変奏曲) 作品35/「あした」~4つの歌 作品27より(作曲者によるチェロ、ピアノとソプラノのための編曲版)*~オフェリー・ガイヤール(vc)/アレクサンドラ・コヌノヴァ(v)/ドヴ・シェインドリン(va)/ヴァシリス・ヴァルヴァレソス(p)*/ベアトリス・ウリア・モンゾン(ms)/ジュリアン・マスモンデ/チェコ・ナショナル交響楽団(2017-18年)・・・Ophelie Gaillard(1974-仏蘭西)は現役旬のチェリスト。2018年に拝聴済。これはリアルな音質と演奏でした。チェロ・ソナタ ヘ長調は学生時代の作、ほとんどBrahmsをイメージさせる王道の浪漫風作品でした。湧き上がるような若さ一杯の活気を感じさせる雄弁な旋律が続く「Allegro con brio」(9:30)たっぷり甘い愛が囁く「Andante ma non troppo」(8:25)闊達に晴れやかにリズミカルな「Allegro vivo」(9:09)。ロマンス ヘ長調はチェロと管弦楽による同時期の作品。囁くようにデリケートに優しい旋律から、雄弁に楽しげな歌が続きました。(8:36)
「ドン・キホーテ」を担当するJulien Masmondetは詳細情報は探せないけれど、仏蘭西若手のイケメンみたい。この長大なる変奏曲は変幻自在、雄弁に美しい音色を誇ってたっぷり歌うチェロはもちろん、久々のチェコ・ナショナル交響楽団も予想外の好演に親密な絡み合い。表情豊かに牧歌的な素朴なサウンドたっぷりな風情を堪能できました。なんせ音質がよろしい。(5:38-2:04-2:27-1:41-7:30-1:46-4:11-1:15-1:08-1:50-1:06-4:04-4:56)
「あした」はしっとりと気高い女声に、悩ましいチェロと控えめなピアノがオブリガートしました。(4:06)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
好天が続きます。最近耳鼻科をサボって鼻詰まり痰の絡みも悪化して途中覚醒連続、二度寝して寝坊しました。来週ネットに予約を入れました。朝洗濯して時間が押してストレッチはなし、YouTube「脇腹の脂肪と愛のハンドルを落とす/10分間の立ちっぱなしワークアウト - スクワットなし、ランジなし、ジャンプなし」実施してから、切れた野菜仕入れにご近所スーパー迄ウォーキング。野菜が高いですね。これも異常気象の関係でしょうか。農家の収入が上がるのならそれでよろしいけれど、そうでもないみたいですね。こんな時期に団地周辺のいっせい草刈り実施。今朝の体重は66.65kg▲200g。
お隣韓国では戒厳令?を巡って大混乱、おそらくは現職大統領は退陣するかどうかの瀬戸際。また対日強硬派が復活するのか、せっかく落ち着いてきた日韓関係も、また反日政策をバネに乗り切ろうとするのでしょうか。亜米利加ではトランプさん地滑り的勝利、独逸も仏蘭西も政情不安、欧州は右派とか親露西亜派が勢いを増して、コロナ後の生活不安から現政権に厳しいのは日本も同じ。但し、ネットを巡る思わぬ選挙の動きや物騒な闇バイトさておき、暴動に至らぬのがいかにも日本らしい。親露西亜方針に舵を切った卓爾治亜も大都市中心に激しい反対デモが続いているそう。烏克蘭はどうなるかなぁ。
最近読んだ(同世代の)ブログ記事「親って、死ぬんですね」これは至高の言葉と捉えました。とても共感できました。
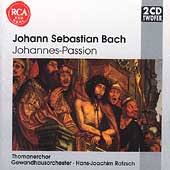 12月はBachでっせ。Bach ヨハネ受難曲 BWV.245~ハンス=ヨアヒム・ロッチュ/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団/ライプツィヒ聖トーマス教会合唱団/ペーター・シュライアー((t)福音史家)/テオ・アダム((bbr)イエス)/アーリーン・オジェー(s)/アルミン・ウーデ(t)/ジークフリート・ローレンツ(br)/ハイディ・リース(contralto)(1975ー1976年ドレスデン聖ルカ教会)・・・所謂キリストの受難の物語だから、巨大なる構築物を感じさせたロ短調ミサ曲に比べ、劇的なストーリーと感情の起伏をたっぷり感じさせる多彩な旋律が続きます。楽器編成はフルート2/オーボエ2(オーボエ・ダモーレとオーボエ・ダ・カッチャ持ち替え)/弦5部/ヴィオラ・ダモーレ/ヴィオラ・ダ・ガンバ/通奏低音/オルガン/リュートまたはチェンバロ+混声合唱+声楽ソロ。マタイ受難曲と旋律個性が違ってより劇的な風情を堪能したけれど、どこがどうの詳しいことは基督教への理解や音楽的素養が薄いのであまりわからない。
12月はBachでっせ。Bach ヨハネ受難曲 BWV.245~ハンス=ヨアヒム・ロッチュ/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団/ライプツィヒ聖トーマス教会合唱団/ペーター・シュライアー((t)福音史家)/テオ・アダム((bbr)イエス)/アーリーン・オジェー(s)/アルミン・ウーデ(t)/ジークフリート・ローレンツ(br)/ハイディ・リース(contralto)(1975ー1976年ドレスデン聖ルカ教会)・・・所謂キリストの受難の物語だから、巨大なる構築物を感じさせたロ短調ミサ曲に比べ、劇的なストーリーと感情の起伏をたっぷり感じさせる多彩な旋律が続きます。楽器編成はフルート2/オーボエ2(オーボエ・ダモーレとオーボエ・ダ・カッチャ持ち替え)/弦5部/ヴィオラ・ダモーレ/ヴィオラ・ダ・ガンバ/通奏低音/オルガン/リュートまたはチェンバロ+混声合唱+声楽ソロ。マタイ受難曲と旋律個性が違ってより劇的な風情を堪能したけれど、どこがどうの詳しいことは基督教への理解や音楽的素養が薄いのであまりわからない。
クルト・マズアがカペル・マイスター時代ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏。わざわざドレスデンのルカ教会を使って定評ある録音会場、音質は極上です。Hans-Joachim Rotzsch(1929ー2013独逸)もかつてエヴァンゲリストだったんですよね。この時期は聖トーマス教会合唱団のトーマスカントル。先日のジョシュア・リフキンとは大違い!に巨大なる演奏。これはもちろんモダーン楽器使用、誠実にしっとり悠々と分厚い響き、合唱だって重厚、自分の世代にとってはエヴァンゲリストといえばこの人!Peter Schreier(1935ー2019独逸)の高揚する雄弁な節回しはほとんど刷り込み、Theo Adam(1926ー2019独逸)による重厚なキリストもあまりに貫禄たっぷりな存在感。声楽ソロを支えるオブリガートの演奏も涙が出るほど美しい。古楽器云々に拘泥するつもりもなし、これはこれでBachの神聖にして偉大なる音楽をたっぷり堪能できました。他の著名な演奏との違いもほとんどわからない。CD2枚分、ラスト迄たどり着いたら感動の嵐ダメ押し状態。この作品事実上の締めは劇的に心揺さぶる第39曲目 「やすらかに眠れ、聖なる骸」なんですね。ところが第40曲「主よ、あなたの愛する天使に命じて」前向きの力強い合唱のうちに終了しました。
Disc 1/●PART 1/01.No.1 Chor `herr. Unser Herrscher.`(10:16)/02.No.2 Rezitativ `jesus Ging Mit Seinen Juengern Ueber Den Bach Kidron.(2:55)/03. No.7 Choral `o Grosse Lieb. O Lieb` Ohn` Alle Masse.(0:58)/04.No.8 Rezitativ `auf Dass Das Wort Erfuellet Wurde. Welches Er Sagte`(1:16)
05.No.9 Choral `dein Will` Gescheh`. Herr Gott.`(0:55)/06.No.10 Rezitativ `die Schar Aber Und Der Oberhauptmann`(0:48)
07.No.11 Arie `von Den Stricken Meiner Suenden`(5:04)/08.No.12 Rezitativ `simon Petrus Aber Folgete Jesu Nach Und Ein Ander Juenger.`(0:14)/09.No.13 Arie `ich Folge Dir Gleichfalls Mit Freudigen Schritten`(4:10)/10.No.14 Rezitativ `derselbige Juenger War Dem Hohenpriester Bekannt` (3:34)/11.No.15 Choral `wer Hat Dich So Geschlagen.`(1:52)/12.No.16 Rezitativ `und Hannas Sandte Ihn Gebunden` No.17 Chor `bist Du Nicht(2:33)/13.No.19 Arie `ach. Mein Sinn.`(2:49)/14.No.20 Choral `petrus. Der Nicht Denkt Zurueck`(1:21)
●PART 2/15.No.21 Choral `christus. Der Uns Selig Macht`(1:07)/16.No.22 Rezitativ `da Fuehreten Sie Jesum Von Kaipha Vor Das Richthaus.` No.23(4:55)/17.No.27 Choral `ach Grosser Koenig. Gross Zu Allen Zeiten`(1:49)/18.No.28 Rezitativ `da Sprach Pilatus Zu Ihm` No.29 Chor `nicht Diesen. Sonder(2:21)/19.No.31 Arioso `betrachte. Meine Seel. Mit Aengstlichem Vergnuegen.`(2:18)/20.No.32 Arie `erwaege. Wie Sein Blutgefaerbter Ruecken`(8:45)
Disc 2/01.No.33 Rezitativ `und Die Kriegsknechte Flochten Eine Krone Von Dornen` No.34(6:16)/02.No.40 Choral `durch Dein Gefaengnis. Gottes Sohn`(0:54)/03.No.41 Rezitativ `die Jueden Aber Schrieen Und Sprachen` No.42 Chor `laesses(4:35)/04.No.48 Arie Mit Chor `eilt. Ihr Angefochtnen Seelen.`(4:36)/05.No.49 Rezitativ `allda Kreuzigten Sie Ihn.` No.50 Chor `schreibe Nicht: Der(2:17)
06.No.52 Choral `in Meines Herzens Grunde`(1:08)/07.No.53 Rezitativ `die Kriegsknechte Aber.` No.54 Chor `lasset Uns Den Nicht(4:13)/08.No.56 Choral `er Nahm Alles Wohl In Acht`(1:30)/09.No.57 Rezitativ `und Von Stund` An Nahm Sie Der Juenger Zu Sich.`(1:27)/10.No.58 Arie `es Ist Vollbracht. O Trost Vor Die Gekraenkten Seelen`(5:20)/11.No.59 Rezitativ `und Neiget Das Haupt Und Verschied.`(0:26)/12.No.60 Arie Mit Chor `mein Teurer Heiland. Lass Dich Fragen.`(5:01)/13.No.61 Rezitativ `und Siehe Da. Der Vorhang Im Tempel Zerriss`(0:34)/14.No.62 Arioso `mein Herz. In Dem Die Ganze Welt`(0:56)/15.No.63 Arie `zerfliesse. Mein Herze. In Fluten Der Zaehren`(6:41)/16.No.64 Rezitativ `die Jueden Aber. Dieweil Es Der Ruesttag War.`(2:24)/17.No.65 Choral `o Hilf. Christe. Gottes Sohn.`(1:06)/18.No.66 Rezitativ `darnach Bat Pilatum Joseph Von Arimathia.`(2:08)/19.No.67 Chor `ruht Wohl. Ihr Heiligen Gebeine.`(7:35)/20.No.68 Choral `ach Herr. Lass Dein` Lieb` Engelein`(2:22)
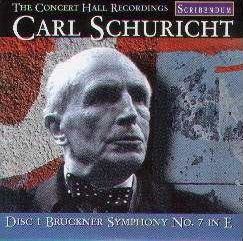 Schubert 交響曲第9番ハ長調~カール・シューリヒト/シュトゥットガルト南ドイツ放送交響楽団(1960年)・・・懐かしいConcertHall音源、LP時代よりの愛聴盤は20年ぶりの拝聴でした。劣悪音質を覚悟していたせいか、イアン・ジョーンズのマスタリングの成果か、響きに濁りはあるけれど意外と臨場感があって聴きやすい音でした。Carl Schuricht(1880-1967独逸)は往年の重厚長大世代だけれど、その個性は特異にその真反対。ステキな歌謡的旋律はどの楽章も軽やかにデリケート、爽やかな熱気にに溢れて疾走します。各楽章ラストのルバートもほとんどなくて素っ気ない。
Schubert 交響曲第9番ハ長調~カール・シューリヒト/シュトゥットガルト南ドイツ放送交響楽団(1960年)・・・懐かしいConcertHall音源、LP時代よりの愛聴盤は20年ぶりの拝聴でした。劣悪音質を覚悟していたせいか、イアン・ジョーンズのマスタリングの成果か、響きに濁りはあるけれど意外と臨場感があって聴きやすい音でした。Carl Schuricht(1880-1967独逸)は往年の重厚長大世代だけれど、その個性は特異にその真反対。ステキな歌謡的旋律はどの楽章も軽やかにデリケート、爽やかな熱気にに溢れて疾走します。各楽章ラストのルバートもほとんどなくて素っ気ない。
第1楽章「Andante - Allegro ma non troppo」冒頭のシンプルなホルン・ソロから夢見るような味わい深さ。提示部繰り返しなし。(13:10)
第2楽章「Andante con moto」途方に暮れた緩徐楽章もシミジミとさっぱり軽やかに穏健。(15:10)
第3楽章「Scherzo. Allegro vivace」ゴリゴリとしたスケルツォもリズミカルに軽快さを失わない。(10:19)
第4楽章「Finale. Allegro vivace」晴れ晴れとした表情に、快い熱気が続きました。(12:43)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
昨日もいつもと同じ朝、深夜途中覚醒して二度寝、やや寝不足気味でも体調は大丈夫。婆さんが独り暮らしに戻った関係で洗濯物増大。ストレッチ、そしていつものYouTube「【全身有酸素運動】ユーロビートにのって/気分が上がる有酸素ダンス!エアロビクスでダイエット」こなしてから恒例市立体育館へ。大学は既に冬休みに入ったのか?初心者風若者が数人筋トレに来訪していたけれど、筋トレ・マシンは順番通り消化できて、エアロバイク(有酸素運動)も15分消化、往復4kmの道中も充分なウォーキングとなります。帰りちょっと悩んで食材買い物は本日に押し出しました。今朝の体重は66.85kg▲150g。
先日朝のワインドショウを眺めていたら、スケジュール管理スマホ・アプリが70%、手帳が30%との調査結果。自分もサラリーマン時代晩年はコンピューター連動スマホ・アプリを使っておりました。ところが手帳売上げは前年比140%なんだそう、使用実態は「日記」「感情を記録する」「気候や服装」「健康状態」記録なんだそう。精神的な安定に効果がある情感の吐露にもなっていて、これって「音楽日誌」と同じじゃないのか。手書きじゃないけれど。自分はもうお仕事引退してあまりにヒマな毎日、油断すれば聴き流して挙げ句忘却してしまうステキな音楽、そして健康管理、あとは日々の些細な感慨記録を継続するのが自分の精神の安定につながっていると自覚いたします。
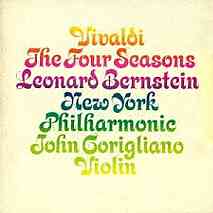 Vivaldi 協奏曲集「四季」(ジョン・コリリアーノ(v)/1963-64年)/協奏曲ハ長調 RV.558(ジョヴァンニ・ヴィカリ/カルロ・デ・フィリップス(mand)/ジョン・ウンマー/ロバート・モリス(fl)/ウィリアム・ヴァッキアーノ/ネイサン・プレージャー(tp)/エンゲルベルト・ブレンナー(ob)/クリスティアーネ・スタヴラーチェ/アストリッド・フォン・ヴルツラー(hp)/ジョン・コリリアーノ(v)/ ラースロー・ヴァルガ(vc))/オーボエ協奏曲ニ短調RV.454(ハロルド・ゴンバーグ(ob))/フルート協奏曲ハ短調RV.441(ジョン・ウンマー(Fl))(1958年)~レナード・バーンスタイン(cem)・・・誰でも知っている朗らかな名曲中の名曲、不遜にも食傷気味に至った「四季」拝聴はずいぶんと久々、ここしばらく大好きなバロック音楽からもちょっと遠退いておりました。バーンスタインの演奏は聴いていたか記憶曖昧です。John Corigliano(1901-1975亜米利加)はニューヨーク・フィルのコンマス1943-1966年在任、著名な同名の作曲家は息子。カリッとして明るい、華やかな響きに細かいヴィヴラートが切れ味よろしいソロでした。バーンスタインはヴィヴィッドに闊達なテンポを頻繁に動かして意欲的、時に爆発的な勢い表現、自らによる自在な通奏低音(チェンバロ)もおみごと。緩徐楽章に於ける陶酔しきった表情(「冬」のLargoはとくにゴージャス)パワフルな演奏でした。オーソドックスなバロック音楽表現からはかなり外れて、以前だったら許容できぬ異形に大仰にゴージャス過ぎと感じたことでしょう。春夏秋冬細部知らぬところはない馴染みの旋律が続いて、各楽章必ずルバートする懐かしいスタイルも個性として楽しめるようになりました。音質もまずまず。(3:10-2:20-4:09/6:34-2:08-2:53/4:39-3:31-3:44/3:24-2:20-2:52)
Vivaldi 協奏曲集「四季」(ジョン・コリリアーノ(v)/1963-64年)/協奏曲ハ長調 RV.558(ジョヴァンニ・ヴィカリ/カルロ・デ・フィリップス(mand)/ジョン・ウンマー/ロバート・モリス(fl)/ウィリアム・ヴァッキアーノ/ネイサン・プレージャー(tp)/エンゲルベルト・ブレンナー(ob)/クリスティアーネ・スタヴラーチェ/アストリッド・フォン・ヴルツラー(hp)/ジョン・コリリアーノ(v)/ ラースロー・ヴァルガ(vc))/オーボエ協奏曲ニ短調RV.454(ハロルド・ゴンバーグ(ob))/フルート協奏曲ハ短調RV.441(ジョン・ウンマー(Fl))(1958年)~レナード・バーンスタイン(cem)・・・誰でも知っている朗らかな名曲中の名曲、不遜にも食傷気味に至った「四季」拝聴はずいぶんと久々、ここしばらく大好きなバロック音楽からもちょっと遠退いておりました。バーンスタインの演奏は聴いていたか記憶曖昧です。John Corigliano(1901-1975亜米利加)はニューヨーク・フィルのコンマス1943-1966年在任、著名な同名の作曲家は息子。カリッとして明るい、華やかな響きに細かいヴィヴラートが切れ味よろしいソロでした。バーンスタインはヴィヴィッドに闊達なテンポを頻繁に動かして意欲的、時に爆発的な勢い表現、自らによる自在な通奏低音(チェンバロ)もおみごと。緩徐楽章に於ける陶酔しきった表情(「冬」のLargoはとくにゴージャス)パワフルな演奏でした。オーソドックスなバロック音楽表現からはかなり外れて、以前だったら許容できぬ異形に大仰にゴージャス過ぎと感じたことでしょう。春夏秋冬細部知らぬところはない馴染みの旋律が続いて、各楽章必ずルバートする懐かしいスタイルも個性として楽しめるようになりました。音質もまずまず。(3:10-2:20-4:09/6:34-2:08-2:53/4:39-3:31-3:44/3:24-2:20-2:52)
残りは1958年録音、これも音質は悪くない。ニューヨーク・フィルの名人達を揃えた趣旨でしょうか。ハ長調協奏曲RV.558は賑やかな盛り沢山多彩なソロを揃えてこの作品は初耳、なんともノンビリ牧歌的に優雅かつヴィヴィッドな風情を感じさせます。(5:49-2:12-3:02)Harold Gomberg(1916-1985亜米利加)John Wummer(1899-1977亜米利加)は当時のニューヨーク・フィルを代表する名手、オーボエ協奏曲ニ短調RV.454は作品8/9つまり「四季」含む「和声と創意への試み」第9曲、これが異様にテンポがゆっくり、引きずるような暗さにしっとり歌って、自分が知っている作品とはしばらく気付かなかったほど。こでも第2楽章「Largo」の切々とした歌が聴きもの。(4:50-2:17-3:16)ハ短調協奏曲RV.441はリコーダー協奏曲として幾度も聴いていたもの、どちらがオリジナルなんでしょうか。これも太い音色にしっとり浪漫風優雅な表現でした。チェロの通奏低音が妙にセクシー。(5:24-3:07-4:32)
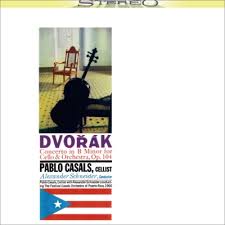 Dvora'k チェロ協奏曲ロ短調~パブロ・カザルス(vc)/アレクサンダー・シュナイダー/カザルス・フェスティヴァル管弦楽団(1960年プエルトリコ・ライヴ)・・・この音源の存在は初めて知りました。これはLP復刻音源、ややオフ・マイクに音像が遠いけれどかなり良心的なステレオでした。Pablo Casals(1876-1973西班牙)気合の唸り声もしっかり聞こえます。Schubert 弦楽五重奏ハ長調とほぼ同時期録音、84歳という年齢から考えてさすがにちょっと技巧的に苦しいのかな、そう予測してその見込は外れました。厳密に云えば細部云々あるけれど、それは気にならぬ骨太剛直な(そして重い)チェロ、馴染みの郷愁の旋律はたっぷり歌って、その説得力は充分な手応えに作品を堪能できました。第1楽章「Allegro」(15:00)/第2楽章「Adagio ma non troppo」(11:27)/第3楽章「Allegro moderato」(12:38)Alexander Schneider(1908ー1993立陶宛→亜米利加/伊太利亜系の人?)はブダペスト弦楽四重奏団のメンバーとして著名、おそらくは臨時編成のオーケストラも想像を超えて誠実に豊かなアンサンブルを聴かせてくださいました。
Dvora'k チェロ協奏曲ロ短調~パブロ・カザルス(vc)/アレクサンダー・シュナイダー/カザルス・フェスティヴァル管弦楽団(1960年プエルトリコ・ライヴ)・・・この音源の存在は初めて知りました。これはLP復刻音源、ややオフ・マイクに音像が遠いけれどかなり良心的なステレオでした。Pablo Casals(1876-1973西班牙)気合の唸り声もしっかり聞こえます。Schubert 弦楽五重奏ハ長調とほぼ同時期録音、84歳という年齢から考えてさすがにちょっと技巧的に苦しいのかな、そう予測してその見込は外れました。厳密に云えば細部云々あるけれど、それは気にならぬ骨太剛直な(そして重い)チェロ、馴染みの郷愁の旋律はたっぷり歌って、その説得力は充分な手応えに作品を堪能できました。第1楽章「Allegro」(15:00)/第2楽章「Adagio ma non troppo」(11:27)/第3楽章「Allegro moderato」(12:38)Alexander Schneider(1908ー1993立陶宛→亜米利加/伊太利亜系の人?)はブダペスト弦楽四重奏団のメンバーとして著名、おそらくは臨時編成のオーケストラも想像を超えて誠実に豊かなアンサンブルを聴かせてくださいました。
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
2024年も粛々と終わりが近づきつつあります。しばらく好天は続くよう。昨日もいつもどおりの朝、ストレッチの後、YouTube「全身の減量のための立ち仕事/ジャンプなし、繰り返しなし、器具なし」MIZIによる20数分の鍛錬しっかり。そして業務スーパーに買い物兼ウォーキング往復3.5kmほど、野菜が高くて思ったものが買う勇気が出ません。急激にインスタントラーメンが喰いたくなって、これは一年ぶり?昼はなんだかんだ喰いすぎた自覚ありました。今朝の体重は67.0kg▲650g。
我が大東市にて「DV等支援措置」申し出た人の住所非公開を担当者が失念~逃げていた場所がわかってしまったミスとの報道。これって最低最悪のミスですね。警察に保護を求めたとのことだけど、その後の処置についての責任は負うのでしょうか、転居費用とか手続きとか、お子さんがいらっしゃれば更に転校なども必要、その物理的精神的苦痛のフォローはあるのでしょうか。これをお役所仕事の典型と呼びたい。
秋田のスーパー居座りクマの射殺に苦情電話とのこと。これにはなんとも呆れるばかり。気持ちはわからんでもないけれど、そこに居住している人の安全が優先と思います。その方は自分が襲われる恐怖を想定していないんじゃないか。
マイナ保険証一本化の運用が始まって、タカハシさんの「はしごだか」は表示されず「●橋」と表示されるんだそう。お仕事雑やなぁ、そんなに大切な制度ならもうちょっとていねいなお仕事してくれよ。女房殿は頑迷なマイナンバーカード反対論者、いまだに申請しておりません。この先どうなるんでしょうか、しばらくいままでの保険証でいけるのでしょうか。
12月はBachですよ。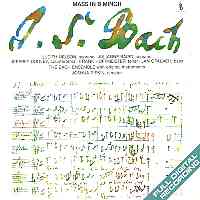 Bach ミサ曲ロ短調 BWV232~ジョシュア・リフキン/バッハ・アンサンブル/ジュディス・ネルソン(s)/ジュリアンヌ・ベアード(s)/ジェフリー・ドゥーリー(ct)/ドリュー・ミンター(ct)/フランク・ホフマイスター(t)/エドムンド・ブラウンレス(t)/ヤン・オパラッハ (b)/アンドルー・ウォーカー・シュルツェ(b) (1981/82年)・・・2016年に拝聴記録有。Bachの受難曲とかミサ曲は仰ぎ見るように巨大なる構築物を感じさせるけれど、OVPP(One Voice per Part/各声部一人)がスッキリ軽いクリアな響きによる演奏の先駆け。鎮魂ならざる力強いヴィヴィッドに前向きな風情の大きな作品、これは親密と静謐に溢れて作品イメージ一新! 40年以上前の古楽器は技術的にはちょっとおとなしくマイルドに過ぎて、最近の研ぎ澄まされた技巧のキレに及びません。声楽は爽やかな躍動に充ちて、各声部クリアに浮かび上がる衝撃は初めてFMから聴いたときから忘れられない。編成は声楽陣+フルート2/オーボエ3/オーボエ・ダモーレ2/ファゴット2/コルノ・ダ・カッチャ/トランペット3/ティンパニ/ヴァイオリン2部/ヴィオラ/通奏低音(ここではおそらくチェロとオルガン)この録音にはほんまにトランペット3本あるの?そう感じるくらい素朴に柔らかい親しみやすい響き。言葉の壁は宗教的儀礼の決まり文句みたいなのであまり気にせず(もちろん理解できない)躍動するカッコ良いBachの旋律リズムを堪能しております。音質も悪くない。あちこちカンタータに流用されて、聴き慣れた旋律もたくさん出現しました。
Bach ミサ曲ロ短調 BWV232~ジョシュア・リフキン/バッハ・アンサンブル/ジュディス・ネルソン(s)/ジュリアンヌ・ベアード(s)/ジェフリー・ドゥーリー(ct)/ドリュー・ミンター(ct)/フランク・ホフマイスター(t)/エドムンド・ブラウンレス(t)/ヤン・オパラッハ (b)/アンドルー・ウォーカー・シュルツェ(b) (1981/82年)・・・2016年に拝聴記録有。Bachの受難曲とかミサ曲は仰ぎ見るように巨大なる構築物を感じさせるけれど、OVPP(One Voice per Part/各声部一人)がスッキリ軽いクリアな響きによる演奏の先駆け。鎮魂ならざる力強いヴィヴィッドに前向きな風情の大きな作品、これは親密と静謐に溢れて作品イメージ一新! 40年以上前の古楽器は技術的にはちょっとおとなしくマイルドに過ぎて、最近の研ぎ澄まされた技巧のキレに及びません。声楽は爽やかな躍動に充ちて、各声部クリアに浮かび上がる衝撃は初めてFMから聴いたときから忘れられない。編成は声楽陣+フルート2/オーボエ3/オーボエ・ダモーレ2/ファゴット2/コルノ・ダ・カッチャ/トランペット3/ティンパニ/ヴァイオリン2部/ヴィオラ/通奏低音(ここではおそらくチェロとオルガン)この録音にはほんまにトランペット3本あるの?そう感じるくらい素朴に柔らかい親しみやすい響き。言葉の壁は宗教的儀礼の決まり文句みたいなのであまり気にせず(もちろん理解できない)躍動するカッコ良いBachの旋律リズムを堪能しております。音質も悪くない。あちこちカンタータに流用されて、聴き慣れた旋律もたくさん出現しました。
Kyrie/Kyrie eleison(五部合唱/9:40)/Christe eleison(ソプラノ二重唱+ヴァイオリン・オブリガート/4:41)/Kyrie eleison(四部合唱/3:30)
Gloria/Gloria in excelsis(五部合唱/6:07)/Et in terra pax(五部合唱)Laudamus te(ソプラノ二人のアリア+ヴァイオリン・オブリガート/4:14)/Gratias agimus tibi(四部合唱/2:59)/Domine Deus(ソプラノとテナーの二重唱/8:06)/Qui tollis peccata mundi(四部合唱/4:24)/Qui sedes ad dexteram Patris(アルトのアリア+オーボエ・ダ・モーレのオブリガート/9:18)/Quoniam tu solus sanctus(バスのアリア+コルノ・ダ・カッチャのオブリガート/4:10)/Cum Sancto Spiritu(五部合唱/4:25)
Symbolum Nicenum/Credo in unum Deum「われは信ず」(五部合唱)Patrem omnipotentem「全能の父」(四部合唱/4:10)/Et in unum Dominum「唯一の主」(ソプラノとアルトの二重唱/2:31)/Et incarnatus est「肉体をとりたまいし者」 (五部合唱+ヴァイオリン/3:21)/Crucifixus「十字架につけられたまいし者」 (四部合唱/3:21)/Et resurrexit「よみがえり」 (五部合唱/3:21)/Et in Spiritum Sanctum「聖霊を」 (バス・アリア+オーボエダモーレ・オブリガート/3:56)/Confiteor「唯一の洗礼を信認す」 (五部合唱/5:46)/Et expecto「来世の命を待ち望む」 (五部合唱/6:47)
Sanctus/Hosanna, Benedictus, and Agnus Dei/Sanctus「聖なるかな」(六部合唱/4:32)/Hosanna「オザンナ」(八部合唱/2:47)/Benedictus「ほむべきかな」(テナー・アリア+フルート・オブリガート/4:13)/Hosanna「オザンナ」(八部合唱ダカーポ/2:47) /Agnus Dei「神の子羊よ」 (アルト・アリア+ヴァイオリン・オブリガート/4:58)/Dona nobis pacem「われらに平安を与えたまえ」 (四部合唱/3:03)
Prokofiev ピアノ協奏曲第3番ハ長調/Ravel 組曲「マ・メール・ロワ」より「パゴダの女王レドロネット」/バレエ音楽「ダフニスとクロエ」~マルタ・アルゲリッチ(p)/ヤニック・ネゼ=セガン/聖チェチーリア音楽院交響楽団/合唱団のクレジットなし(2011年ライヴ)・・・平板に肌理の粗い音質は濁り気味だけど、演奏は鮮烈そのもの。交響曲第5番と並んで大衆的にわかりやすい風情が人気高いピアノ協奏曲第3番ハ長調はAndante - Allegro/Tema con variazioni : Andantino/Allegro, ma non troppoの三楽章。この作品はおそらくMartha Argerich(1941-亜爾然丁)の十八番。速めのテンポに叩きつけるような強烈なタッチとノリ、当時72歳?このパワーには驚くばかり。「大衆的にわかりやすい風情」と書いたけれど、終楽章は破壊的なオーケストラとの遣り取りに興奮! 作品のイメージをガラリと変えました。(29:56)アンコールはネゼ=セガンとの連弾、これもテンポ速く浮き立つよう(3:08)「ダフニス」もオーケストラを自在に扱って、盛り上げもアツい演奏・・・だけれど、この作品はもっと音質状態のよろしい演奏で聴きたいもの。ちょっと音質的に苦しい感じ。(58:40)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
昨日も好天、いつもより1時間半ほど寝坊したから洗濯したらストレッチの時間はなくて、YouTube「【痩せやすい体を作る】血糖値を下げて脂肪燃焼/食後にできる簡単有酸素」済ませて市立体育館へ。しばらく30分~一時間ほど遅れて通ったけれど、筋トレ・マシンが混んでいることに気付いて、やはり朝一番がよろしいかと。途中ゴミ拾いせめてもの功徳はコンビニ袋を拾って満杯、”梨詰め放題壱阡圓也”に似たてんこ盛り状態に限界、すると折よくまたまたビニール袋地面に出現して、残り道中もゴミ拾い継続出来。いつもどおりの常連さんと軽く挨拶して、全身ユル筋トレ+エアロバイク15分しっかりこなしました。気分は爽快。今朝の体重は67.65kg▲100g.
じつは数日前の京都OB会は孫の七五三と日程がダブって、残念欠席。嬉しそうな紋付き羽織姿の孫兄弟の写真が届きました。2-3ヶ月弟のところに過ごした婆さん(年明けには95歳)は昨日より自宅に戻って、一日女房殿が付き添います。この時期必須のコタツが壊れて注文を頼まれました。コタツが壊れるなんて初めて聞きましたよ、いったい何年使ったのか、我が家のも相当に年季が入っているはず。先日の(来年)50年を迎える学生時代の友人たちとの集まりは感慨深く、人生の価値とか一番大切なことなど、深く考えることができて気分転換となりました。自分の姿や個性は自覚できず、長く親しい友人からの視線に相対化して見えてくるものと気付きました。そして佳き友人に恵まれたとシミジミ、人生の区切りを感じました。
「音楽日誌」先月2024年11月分が読めないことをメールに指摘され、慌ててファイル・アップロードいたしました。なんせ二十数年来の読者ですから、ありがたいもの。
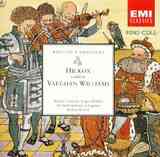 Vaunhan Williams 音楽へのセレナード(管弦楽版)/歌劇「毒とキス」序曲/バレエ音楽「老いたコール王」/5つの神秘的な歌*/古いキャロルによる前奏曲/ランニング・セット/映画「49度線」前奏曲/行進曲「海の歌」(管弦楽版)(1983-1984年)~リチャード・ヒコックス/ノーザン・シンフォニア/シンフォニア・コーラス/スティーヴン・ロバーツ(br)*・・・こりゃなかなか良い感じの音源を仕入れたワイ~そう喜んでいたらEMI/Collectors Editin/30CDの11枚目がこれ、以前にも聴いていたことが判明しました。(まったく記憶なし)Richard Hickox(1948-2008英国)はお気に入り指揮者、最近太り過ぎじゃないか、そんな心配をしていたら残念わずか60歳にて逝ってしまいました。Northern Sinfoniaは英国北部ゲイツヘッド市を拠点とする室内オーケストラとのこと。名室内オーケストラを排出してきた伝統に恥じぬ立派なアンサンブルを聴かせて下さいました。日本では人気さっぱりな英国音楽の素朴な味わいを堪能させてくださる選曲。
Vaunhan Williams 音楽へのセレナード(管弦楽版)/歌劇「毒とキス」序曲/バレエ音楽「老いたコール王」/5つの神秘的な歌*/古いキャロルによる前奏曲/ランニング・セット/映画「49度線」前奏曲/行進曲「海の歌」(管弦楽版)(1983-1984年)~リチャード・ヒコックス/ノーザン・シンフォニア/シンフォニア・コーラス/スティーヴン・ロバーツ(br)*・・・こりゃなかなか良い感じの音源を仕入れたワイ~そう喜んでいたらEMI/Collectors Editin/30CDの11枚目がこれ、以前にも聴いていたことが判明しました。(まったく記憶なし)Richard Hickox(1948-2008英国)はお気に入り指揮者、最近太り過ぎじゃないか、そんな心配をしていたら残念わずか60歳にて逝ってしまいました。Northern Sinfoniaは英国北部ゲイツヘッド市を拠点とする室内オーケストラとのこと。名室内オーケストラを排出してきた伝統に恥じぬ立派なアンサンブルを聴かせて下さいました。日本では人気さっぱりな英国音楽の素朴な味わいを堪能させてくださる選曲。
珍しい声楽なし管弦楽版の「音楽へのセレナーデ」から懐かしい、穏健な風情いっぱい漂って感慨無量(11:41)「毒とキス」序曲には生真面目なユーモアが炸裂!(6:59)「老コール王」は伝説の王様(童謡)なんだとか、ヴォカリーズが参入してなかなか楽しい作品でした。Allegro moderato(4:05)Pipe Dance(3:03)Bowl Dance(1:41)Morris Jig(1:33)Folk Song(3:00)Folk Tune(4:08)Solo Jig(4:39)5つの神秘的な歌は復活祭(5:06)私は花を用意した(2:54)愛はようこそと言った(5:53)使命(2:13)アンティフォン(3:08)古いキャロルによる前奏曲(4:59)生真面目に丹精雄弁な歌。ランニング・セットはシンプルに素朴なリズムが躍動して興奮を高めます(6:18)映画「49度線」前奏曲は落ち着いた黄昏風景を連想させて感無量。(2:39)行進曲「海の歌」はElgarの「威風堂々」にも似て勇壮な歩みでした。(3:53)
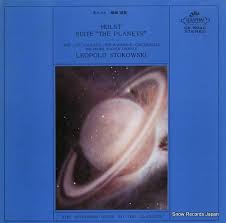 Holst 組曲「惑星」 ~レオポルド・ストコフスキー/ロサンゼルス・フィル(1956年)・・・14年ぶりの拝聴。音質は70年近く経っても驚異のほぼ現役のステレオ。ロサンゼルス・フィルはエドゥアルド・ファン・ベイヌム時代ですね。豊かな残響に分厚いゴージャスな響き、この時点オーケストラの力量も充分。カッコ良いスペクタクルな作品表現はデフォルメも少なく冒頭「火星」怒涛の推進より意外とオーソドックス。有名な「木星」の荒々しい迫力、「天王星」のスケルツォは前のめりにパワフル・ユーモラスに思い切った表情付けでした。あちこちストコフスキーの手も入っているとか?(6:34-8:04-4:04-7:38-7:48-5:45-6:44)
Holst 組曲「惑星」 ~レオポルド・ストコフスキー/ロサンゼルス・フィル(1956年)・・・14年ぶりの拝聴。音質は70年近く経っても驚異のほぼ現役のステレオ。ロサンゼルス・フィルはエドゥアルド・ファン・ベイヌム時代ですね。豊かな残響に分厚いゴージャスな響き、この時点オーケストラの力量も充分。カッコ良いスペクタクルな作品表現はデフォルメも少なく冒頭「火星」怒涛の推進より意外とオーソドックス。有名な「木星」の荒々しい迫力、「天王星」のスケルツォは前のめりにパワフル・ユーモラスに思い切った表情付けでした。あちこちストコフスキーの手も入っているとか?(6:34-8:04-4:04-7:38-7:48-5:45-6:44)
フィル・アップはScho"nberg 「浄められた夜」(彼の管弦楽団/1957年)こちらニューヨーク録音(東海岸の録音用オーケストラ)これも久々の拝聴。たっぷりエッチな表情は陰影濃く、これも分厚い響きに力の入った演奏でした。こちらも音質良好。(2:22-10:19-1:57-9:39-4:10)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
昨日日曜は早く目覚めて「音楽日誌」更新をしたもの。あとは前日の疲れがどっと出て、終日断続的に居眠りばかり。せっかくの佳き天候にも、買い物に出かける意欲も沸かず、歩き過ぎによる足腰の鈍い痛みを癒やしておりました。今朝もいつもより一時間以上寝坊状態。夕食も食材在庫を使ってカンタン手抜きに仕立て済。恒例のストレッチもYouTubeエアロビクスもサボりました。LINEには引き続きOB会の投稿が続いて、楽しい集まりの名残を惜しんでおりました。本日よりトレーニング再開鍛え直しです。体重は67.75g+800g。
「103万円の壁突破」石破首相表明とのこと。さて実際はいくらに落ち着くのでしょうか、105万とか、そんなことにならんでしょうね。財源云々論議があるようだけど、それは国家予算トータルで考えれば良いとのこと、この件だけ取り上げて「何兆円足りない」という論調にはちょっと恣意的なものを感じます。これで現役世代は一息付けるのでしょうか。人手不足解消にも良い影響はあるでしょうか。
政府与党は「在職老齢年金」の見直しで概ね一致/厚生年金減額対象者を「月50万円超」から引き上げへ~狙いは“高齢者の働き控え”解消・・・これって当該年齢の実感としてちょっぴり違和感が・・・年金と継続雇用の安い賃金併せて50万円というのはかなり恵まれた階層と感じます。この物価高に青息吐息なのはもっと収入が少ない人々のはず。それが政治の優先事項なんでしょうか。既に高齢者の医療負担を増やして、高額医療負担限度を上げる動きもあって、なんかもやもや・・・場末の引退爺(=ワシ)が呟いても屁の突っ張りになりませんが。
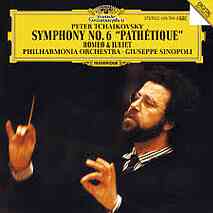 Tchaikovsky 交響曲第6番ロ短調「悲愴」/幻想序曲「ロメオとジュリエット」~ジュゼッペ・シノーポリ/フィルハーモニア管弦楽団(1989年)・・・誰でも知っている甘美な旋律が爆発する名曲中の名曲。けっこう好きな作品ですよ。自分はエフゲニ・ムラヴィンスキー1960年録音の底知れぬ陰影と堀深さに感銘を受けて、ほか数多い録音はどれを聴いてもそれなり・・・といった感慨が多いもの。これは久々に納得できる爽やかな演奏でした。適度な残響も快く、低音もしっかり効いてほぼ理想的な音質。露西亜風泥臭さ、粘着質に濃厚な風情とは無縁にスッキリと解像度の高い響きに始まる第1楽章「Adagio - Allegro non troppo」(19:19)甘さ控えめなワルツも薄味によく歌う第2楽章「Allegro molto vivace」(8:21)第3楽章「Allegro molto vivace」の胸を熱くさせる軽快なるノリとテンポ・アップ。(9:46)深刻に重くなり過ぎず、淡々と流れよろしくクールに情感が高揚して、劇的迫力充分だけど大仰なる”泣き”は存在しない第4楽章「Finale: Adagio lamentoso」にはキレ味たっぷり。(9:58)こんなのTcahikovskyじゃない!そう思われる方も存在しそうな、ある意味薄味な演奏でしょうか。馴染み過ぎた名曲は久々に新鮮そのものに受け止めました。「ロメオ」も中庸のテンポにデリケートな美しい仕上げでした。(22:26)
Tchaikovsky 交響曲第6番ロ短調「悲愴」/幻想序曲「ロメオとジュリエット」~ジュゼッペ・シノーポリ/フィルハーモニア管弦楽団(1989年)・・・誰でも知っている甘美な旋律が爆発する名曲中の名曲。けっこう好きな作品ですよ。自分はエフゲニ・ムラヴィンスキー1960年録音の底知れぬ陰影と堀深さに感銘を受けて、ほか数多い録音はどれを聴いてもそれなり・・・といった感慨が多いもの。これは久々に納得できる爽やかな演奏でした。適度な残響も快く、低音もしっかり効いてほぼ理想的な音質。露西亜風泥臭さ、粘着質に濃厚な風情とは無縁にスッキリと解像度の高い響きに始まる第1楽章「Adagio - Allegro non troppo」(19:19)甘さ控えめなワルツも薄味によく歌う第2楽章「Allegro molto vivace」(8:21)第3楽章「Allegro molto vivace」の胸を熱くさせる軽快なるノリとテンポ・アップ。(9:46)深刻に重くなり過ぎず、淡々と流れよろしくクールに情感が高揚して、劇的迫力充分だけど大仰なる”泣き”は存在しない第4楽章「Finale: Adagio lamentoso」にはキレ味たっぷり。(9:58)こんなのTcahikovskyじゃない!そう思われる方も存在しそうな、ある意味薄味な演奏でしょうか。馴染み過ぎた名曲は久々に新鮮そのものに受け止めました。「ロメオ」も中庸のテンポにデリケートな美しい仕上げでした。(22:26)
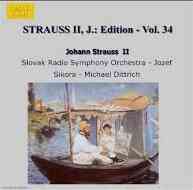 J.StraussⅡロシア行進曲 作品/426スラヴ・ポプリ 作品392/ワルツ「ワルツの法典からの5箇条」 作品105/ポルカ・フランセーズ「お気に入り」 作品217/ニコライ・カドリーユ 作品65/ワルツ「聖ペテルブルグからの別れ」 作品210/ポルカ・マズルカ「いたずらな妖精」 作品226/幻想曲「ロシアの村にて」 作品355/チェロと管弦楽のためのロマンツェ「甘い涙」(ジョゼフ・シコラ(vc))/ニコ殿下のポルカ 作品228~ミハエル・ディトリッヒ/スロヴァキア放送交響楽団 (1991年)・・・Michael Dittrich(?-独逸)は詳細情報探せず。もともとウィーンに学んだヴァイオリニスト、ウィーン交響楽団にも加わっていたとのこと。これは露西亜関連の作品を集めたもの、ワルツは2曲しかない。(第34集)J.StraussⅡ作品を網羅して録音として残す、これはもう商売の範疇に非ず、Marco Poloの貴重な偉業でしょう。音質も悪くないし、素朴に飾りのない素直な演奏も作品を知るには充分な水準でしょう。聴いたことがあるのは「チェロと管弦楽のためのロマンツェ」それと「ロシア行進曲」くらいかな?どれも類型的だけど、平易に馴染みやすい、懐かしい美しい旋律ばかり。ほっと聴き惚れました。(4:06-16:38-8:52-4:02-6:03-9:15-4:25-7:25-4:17-3:54)
J.StraussⅡロシア行進曲 作品/426スラヴ・ポプリ 作品392/ワルツ「ワルツの法典からの5箇条」 作品105/ポルカ・フランセーズ「お気に入り」 作品217/ニコライ・カドリーユ 作品65/ワルツ「聖ペテルブルグからの別れ」 作品210/ポルカ・マズルカ「いたずらな妖精」 作品226/幻想曲「ロシアの村にて」 作品355/チェロと管弦楽のためのロマンツェ「甘い涙」(ジョゼフ・シコラ(vc))/ニコ殿下のポルカ 作品228~ミハエル・ディトリッヒ/スロヴァキア放送交響楽団 (1991年)・・・Michael Dittrich(?-独逸)は詳細情報探せず。もともとウィーンに学んだヴァイオリニスト、ウィーン交響楽団にも加わっていたとのこと。これは露西亜関連の作品を集めたもの、ワルツは2曲しかない。(第34集)J.StraussⅡ作品を網羅して録音として残す、これはもう商売の範疇に非ず、Marco Poloの貴重な偉業でしょう。音質も悪くないし、素朴に飾りのない素直な演奏も作品を知るには充分な水準でしょう。聴いたことがあるのは「チェロと管弦楽のためのロマンツェ」それと「ロシア行進曲」くらいかな?どれも類型的だけど、平易に馴染みやすい、懐かしい美しい旋律ばかり。ほっと聴き惚れました。(4:06-16:38-8:52-4:02-6:03-9:15-4:25-7:25-4:17-3:54)
2024年12月某日/●隠居生活未だ初心者入門の日々
12月に入りました。寒さをしっかり感じる朝になりました。今朝の体重は66.95kg▲200g、安物体重計はどうも信頼ならん。
昨日もいつもどおりの洗濯、ストレッチ、YouTube「【減量】7日後にお腹を鏡でみてください【短時間脂肪燃焼】【本気の1週間】」実施して市立体育館へ。時間の関係で筋トレのみこなして帰宅、着替えて京都を目指しました。京橋より京阪特急樟葉乗り換え、石清水八幡宮下車ロープウェイにて上迄。残念かなり工事中だったけれど、参道は充分美しく静謐、未だインバウンドには知られていないらしく、七五三の可愛らしいこどもがたくさん。 下山時に迷ってしまい、痛む膝に悩みつつ歩いて下迄、そこは見知らぬ住宅街だからまったく駅へのルートがわからない。スマホの案内も目印らしきものが理解できず逆方向?散々歩いてバス停発見、ようやく駅へのルートを見つけました。
下山時に迷ってしまい、痛む膝に悩みつつ歩いて下迄、そこは見知らぬ住宅街だからまったく駅へのルートがわからない。スマホの案内も目印らしきものが理解できず逆方向?散々歩いてバス停発見、ようやく駅へのルートを見つけました。
京阪の三条にて下車、まっすぐ三条高倉目指して「大シルクロード展」(京都文化博物館)へ。テレビや本でしか見たことがない莫高窟、そこからの出土品や、紀元前なのに保存状態のよろしい発掘品、日本の高松塚古墳の壁画によく似た絵とか、北魏様式と云われる仏像(飛鳥寺釈迦如来像など)の本場との類似性、そして正倉院に同じようなものがある、という歴史の悠久をたっぷり堪能、これは眼とノーミソへの贅沢でした。けっこうな人でしたね。
大学某OB会は17名(女性4人)ほぼ時間通り集合。30数年ぶりに再会した先輩後輩は痩せたり太ったり禿たり老けたり、にわかには若い面影を思い出せない。教師になって校長を60歳にて退任、故郷にて農業に従事している人とか、自ら病に様子を見ながら参加二人、交通事故に膝の手術を待っている一人。久々に再会した先輩は奥様が今年2回も脳梗塞を発症して調子はよろしくないとか。自分含めてまったく変わらないのが数人(という評価/お追従か?)但し髪は減少しております。世代的に初対面同士も数人存在。 (写真は通りががりの学生さんにお願い/我が母校の後輩でした)
(写真は通りががりの学生さんにお願い/我が母校の後輩でした)
頼んだコースは京野菜、豆腐、湯葉を中心としたコース+呑み放題(安かった)喰い物に文句出るかと危惧したけれど、さすが爺婆揃い、若者みたいにたくさんは喰えんのです。懐かしく、楽しく、がやがやした会場に大きな声で思い出話、たくさん喋ったので声が潰れました。無事、幹事としての役割は果たして支払いも済ませて帰ろうかな・・・そう思ったら、ムリムリカラオケボックスに連れて行かれ、超ヘタな古い歌を散々聞かされましたよ。自分はご遠慮。最寄りの駅到着は10時半頃、タクシーの姿はなくて仕方がなく更に2km自宅迄歩きました。
来年は九州福岡開催を目指します。でも、もうこんなにたくさんは集まれないでしょう。酒は控えめにしたつもり、今朝は膝も脚も痛い。
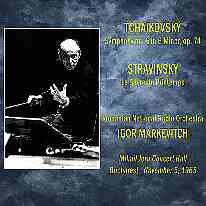 Stravinsky バレエ音楽「春の祭典」~イーゴリ・マルケヴィッチ/ルーマニア国立放送交響楽団(1965年ライヴ)・・・Igor Markevitch(1912ー1983烏克蘭→瑞西?)にはこの作品録音がいったいいくつあるのか。正規録音としてはフィルハーモニア管弦楽団とのモノラル/ステレオ録音2種のみ?あれは凄い激烈なアツい演奏でした。これは初めて聴いたオーケストラとの放送録音(乃至エア・チェック?)音質はかなり良好なステレオ(かな?)。あまり期待していなかったけれど、さすがこの人は強烈な統率力を誇って、驚くべきアンサンブルの集中力、リズムの鋭さ、激烈なテンションはフィルハーモニアにほとんど負けぬアツい演奏でした。原始のエネルギーに充ちた暴力的リズムが魅惑の作品、オーケストラの弱さもほとんど感じさせない仕上げ。(15:29-16:14)
Stravinsky バレエ音楽「春の祭典」~イーゴリ・マルケヴィッチ/ルーマニア国立放送交響楽団(1965年ライヴ)・・・Igor Markevitch(1912ー1983烏克蘭→瑞西?)にはこの作品録音がいったいいくつあるのか。正規録音としてはフィルハーモニア管弦楽団とのモノラル/ステレオ録音2種のみ?あれは凄い激烈なアツい演奏でした。これは初めて聴いたオーケストラとの放送録音(乃至エア・チェック?)音質はかなり良好なステレオ(かな?)。あまり期待していなかったけれど、さすがこの人は強烈な統率力を誇って、驚くべきアンサンブルの集中力、リズムの鋭さ、激烈なテンションはフィルハーモニアにほとんど負けぬアツい演奏でした。原始のエネルギーに充ちた暴力的リズムが魅惑の作品、オーケストラの弱さもほとんど感じさせない仕上げ。(15:29-16:14)