2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�V������T�Ԃ��n�܂��Ă����ז��������ȓ��X�������܂��B�̏d���̒��s�ǂ������̂��A�̒����͂����肵�Ȃ�����̏d���ɂȂ�̂��s���B�����r���o�����Ė��肪�B����͏I���܂�ɍō��C����30�xC�ɓ͂��ʉ߂����₷���C��A�{����9�����I����Ă悤�₭�H������Ă��Ă���܂��B��������ς܂��ăX�g���b�`�AYouTube�G�A���r�N�X�̓T�{���Ă��ߏ��X�[�p�[���E�H�[�L���O��4,500���قǁA����ł͂�����Ɖ^���s���ł��傤�B�G�߂̕ς��ڂ͂ǂ����̒��Ǘ�������A���ɖ�p���Ē����炶���Ƃ��ĉ��ɂȂ��Ă���܂����B���Ɍ��m�����Ɉ�����i�����s���j�o�n�Ƃ̕A���������s�����������������s������ł����B�{�����E����p���n���E�G���[�g�m���ďo�n�̌��͂ǂ����̋L���Ɂu����N�X�����Ȃ��v�Ƃ���܂����B����Ƃ͂��Ȃ艓��������ۂ̐l�ł��ˁB�����̑̏d��68.4kg��100g���߈��蒆�B
�ݗ��O���l�̕����ꍑ�̐e�ʂ�F�l����{�ɏ����āA���̈Ⴂ����������铮��͑�D���B���肪���ȃR���r�j�H�A�g�C���̔������A��]���i�]�X�^�̘b��ɂ͖O��������ǁA���{�ɐ�������Ă���IKITERU����̓����ɂ͋���ł���܂����B�g�̂̕s���R�ȏ������؍������{�ɏ����āA����̓^�N�V�[�𗘗p���铮��B���ɂ��Ԉ֎q�ł��R���r�j���X�[�p�[�K���A�O�H�Ȃ��̗l�q��`���Ă��������܂��B�i�d�Ԃɏ�铮�����j���{���܂��܂����Ǝv������Ǘ����͐i��ł���悤�ł��ˁB���낢��ƋC�t��������܂����B�������쎢�����̃e����������ȑO�̓���ɁA���{�̐g�̂ɕs���R�ȕ��ւ̔z���ɂ��Č��y����Ă����L��������܂��B
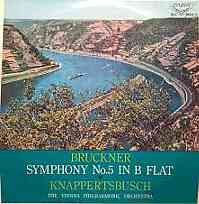 Bruckner �����ȑ�5�� �σ������iFranz Schalk��/1863-1931�j�`�n���X�E�N�i�b�p�[�c�u�b�V��/�E�B�[���E�t�B���i1956�N�j�E�E�E�����LP����ꖇ�ŗB�ꂱ�̍�i�����ł�������A���̍�i�Ƃ̏o��ł������ƋL�����܂��B�������������łƂ��A��3�y�́uScherzo. Molt vivace, Schnell - Trio. Im gleichen Tempo�v�̃J�b�g�A��4�y�́uFinale. Adagio - Allegro moderato�v�ɂ̓f�[�n�[�ȋ��ǑŊy��lj����Ă���Ƃ̂��ƁB������h�E�V���E�g�ɂ͂Ȃɂ������̂��͂����ς藝��s�\�B�X�e���I�����������̓����̉��ɖ��Ă��銴���͂��邯��ǁALP�����ł����Ȃ�̉𑜓x�A��i�≉�t�̕�������\����̂ɂ��قǂ̕s��������܂���B��D������5�������������D���ɂȂ�܂����B
Bruckner �����ȑ�5�� �σ������iFranz Schalk��/1863-1931�j�`�n���X�E�N�i�b�p�[�c�u�b�V��/�E�B�[���E�t�B���i1956�N�j�E�E�E�����LP����ꖇ�ŗB�ꂱ�̍�i�����ł�������A���̍�i�Ƃ̏o��ł������ƋL�����܂��B�������������łƂ��A��3�y�́uScherzo. Molt vivace, Schnell - Trio. Im gleichen Tempo�v�̃J�b�g�A��4�y�́uFinale. Adagio - Allegro moderato�v�ɂ̓f�[�n�[�ȋ��ǑŊy��lj����Ă���Ƃ̂��ƁB������h�E�V���E�g�ɂ͂Ȃɂ������̂��͂����ς藝��s�\�B�X�e���I�����������̓����̉��ɖ��Ă��銴���͂��邯��ǁALP�����ł����Ȃ�̉𑜓x�A��i�≉�t�̕�������\����̂ɂ��قǂ̕s��������܂���B��D������5�������������D���ɂȂ�܂����B
��1�y���uIntroduktion: Adagio - Allegro�v�\�z�O�Ƀe���|�͒x���Ȃ��A�`�������ւ̒n���ւ̊K�i���~��āA�����ɂ͌��グ��悤�ȏ�ǂ������ǂ���I�n�܂�B���Ғʂ�̃X�P�[���ƃp���[�A�d�ʊ��B�Z���\��Ɠ��O�Ȑ߉A���N���N����悤�ȋ���Ȃ鍂�g���B���M�ɏ[���Ă���������畏��̂̂Ȃ����i�́A�����]�X�͖Y���قǖ��f�̋��ǂ͉��[�����́B�i18:50�j��2�y���uAdagio. Sehr langsam�v�ɏ��y�͂��f�p�ȕ���ɏ[���āA�������e���|�͒W�X�ƈӊO�Ƒ����ɐi�݂܂��B����ł��Z�����ǂ̐⋩�͋���ł��Đ����͂͏[���B�i13:23�j��3�y���uScherzo. Molt vivace, Schnell - Trio. Im gleichen Tempo�v�J�b�g�����邩��A���B���B�b�h�ȃX�P���c�H�������Ԃ�ƒZ���B�����������͋����ْ����ؔ��������Ղ�Ƀe���|�͈ӊO�ƒx���Ȃ��A�g���I�̑f�p�ȕ���Ƃ̑Δ�݂͂��ƁA���_���킬���Ƃ��Ă킩��₷���B�i9:36�j�Ⴆ���Ȃ�e���|�̑����I�C�Q���E���b�t���i1958�N�j��12:35�B
��4�y���uFinale. Adagio - Allegro moderato�v��1�y�͂���A���āA��͂�e���|�͒x���Ȃ��A�����̏d�ʊ��ƔM�C��ттĐ��������ăe���|�E�A�b�v�B䩗m�Ƃ����z�����ɂ�Ⴢ�܂���B�ŏI�Ղ̃f�[�n�[�ȋ��ǂƂ������قǂ̃V���o���lj����Ȃ��Ȃ����܂��Ă���܂����B�i18:50�j���Ȃ݂ɃI�C�Q���E���b�t���i1958�N�j�̍ŏI�y�͂�24:05�BBruckner��i����ԍD���ȍ�i�����ǁA�ł̂��Ƃ͂��Ă����A��݂͂ɋ��@�ȉ��t�̓��F���E�x�X�g�̎艞���B���̂��炢�̒����̂ق����h�E�V���E�g�ɂ͏W���͈ێ��ɂ��傤�ǂ�낵�������B�܁A�ʏ�̔łőS�����������C����������܂��B
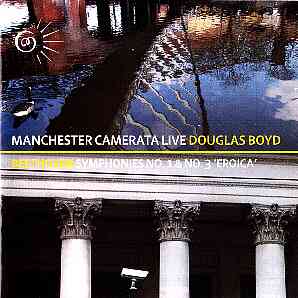 Beethoven �����ȑ�1�ԃn����/�����ȑ�3�� �σz�����u�p�Y�v�`�_�O���X�E�{�C�h/�}���`�F�X�^�[�E�J�����[�^�i2008�N���C���j�E�E�E����͂��Ȃ�ȑO��YouTube�S�W�߂����Ƃ������āA�ւ�Douglas Boyd�i1959-�p���j������Ȋ��Ă���A�Ɗ��S�����L��������܂����B���[���b�p�����nj��y�c�ŃI�[�{�G��S�����āA�₪�Ďw���҂ցB���̒c�̂̌|�p�ēݔC��2011�N���������B�A���T���u���̐��x�͂Ȃ��Ȃ��D�G�B�t�̔����Ƃ��Ċ�]�ɏ[�������������\�ł����n�����������́A���Ґ��ɃX�b�L���i�Ȃ̂Ƀe�B���p�j���ア�j�������A���T���u���ɁA���炳��Ƃ����W�������͒ቹ���ア�A�f���i�߂��j�Ȓ��f�\���̓f���P�[�g�Ɍy���ȃ��Y���A���_�[���y��Ǝv������ǁA���ɂ͂��܂胔�B�����[�g���|�����Ă���܂���B�W�X�Ƃ��Ă��������A�e�N���Ɍ�����V���v���ȕ\�������́ABeethoven�̏�����i���������a���͂��قǂɂ���܂���B�i9:16-7:47-4:04-5:25�j
Beethoven �����ȑ�1�ԃn����/�����ȑ�3�� �σz�����u�p�Y�v�`�_�O���X�E�{�C�h/�}���`�F�X�^�[�E�J�����[�^�i2008�N���C���j�E�E�E����͂��Ȃ�ȑO��YouTube�S�W�߂����Ƃ������āA�ւ�Douglas Boyd�i1959-�p���j������Ȋ��Ă���A�Ɗ��S�����L��������܂����B���[���b�p�����nj��y�c�ŃI�[�{�G��S�����āA�₪�Ďw���҂ցB���̒c�̂̌|�p�ēݔC��2011�N���������B�A���T���u���̐��x�͂Ȃ��Ȃ��D�G�B�t�̔����Ƃ��Ċ�]�ɏ[�������������\�ł����n�����������́A���Ґ��ɃX�b�L���i�Ȃ̂Ƀe�B���p�j���ア�j�������A���T���u���ɁA���炳��Ƃ����W�������͒ቹ���ア�A�f���i�߂��j�Ȓ��f�\���̓f���P�[�g�Ɍy���ȃ��Y���A���_�[���y��Ǝv������ǁA���ɂ͂��܂胔�B�����[�g���|�����Ă���܂���B�W�X�Ƃ��Ă��������A�e�N���Ɍ�����V���v���ȕ\�������́ABeethoven�̏�����i���������a���͂��قǂɂ���܂���B�i9:16-7:47-4:04-5:25�j
�Q���h�ւ̗͋������J���錾�ł����u�p�Y�v�ɂ��̌y���\���͏��X�ア�����B��1�y���uAllegro con brio�v��������e���|�Ɍy���ȃC���E�e���|�B���J��Ԃ��L�B�����͂��邵�A�O�Ȃ�胁���n���͋������ꂽ�n�c���c�\�����A���܂������������ƃp���[�Ɩʔ��݂��͂�����҂葫��Ȃ��B���X�g�̒ǂ����݂ɂ��y����ۂ������܂����B�i16:01�j��2�y���uMarcia funebre: Adagio assai�v�͑����s�i�ȁB�����͏d�������a�[���ɉ���͎̂���x��Ƃ��Ă��A���f�̃e���|�ɐ���t�̏�M�𒍂��ł������͔����A�ቹ�̉A�e���キ�����͂�����Ȃ��B�i15:14�j��3�y���uScherzo: Allegro vivace�v�X�P���c�H�̓p���t���Ȑ��i�͂ƃz�����̉��F�ɒ��ځB������舒B�y���Ƀz�����͑f���ɋ����ăo�����X�\���̓e���V�����������́B�i5:31�j��4�y���uFinale: Allegro molto�v�͗��������ʑ����e���|�ɐi�ޕϑt�ȁB�������e���V�����������āA���̊y�͂���ԏ�o�������B�ł��z�����̂Ȃ�Ƃ������ۂ������͎c�O�B�i11:05�j���������f���ɃX�b�L���Ƃ�������̂Ȃ��\�����D�ޕ������������邱�Ƃł��傤�B
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�̏d���V���b�N����T�ԑ����܂����B�����͋Ɩ��X�[�p�[�̃G���h��5�H198�~�i�Ŕ��j�̔������[�����i�����X�[�v�t/����������j�����Ďv�킸�w���A����𒋂ɋi�����̂��̏d���̈���ł��傤�B�[�H���j���[�ɍs���l�܂��Ĉ��ՂɃJ���[���A�����100�~���i�Ŕ��j�̋Ɩ��X�[�p�[�̃J���[���[�B�Ȃ�ł��l�グ�̎���Ɍ����I�������l�i�����̖��ɃK�b�J���B�d�����Ȃ����ǁA����͂��������܂���B����f�Ă��������������e�m�炸�̈�a���͊��ݍ��݂����߂��āA��̎������ɂȂ��Ă���Ƃ̂��ƁB�����������O�x�����Ă������ł������͎��u���V���͂��ɂ�������A���ԃu���V���K�{�B�����_�~�����g�p���Č����E�ۋ����A���̌�͉��P����Ă���܂��B
����͒���Ԃ̐���A�X�g���b�`�ς܂���YouTube�G�A���r�N�X�͂��x�݁B�v�X��9���ɂ͎s���̈�قɓ˓��B�g���[�j�����[���͋Ă��ċg���}�V���͓Ɛ��ԁA�_���̏��Ԓʂ肱�Ȃ��āA�G�A���o�C�N15����������������ł��܂����B�A��ăo�b�O�Ƃ��^���C�Ƃ��lj����܂����B�܂肪���̓V�C�ɋC���͂��܂�オ�炸�A�߂����₷�����Q���X�A�̒�����������܂���B�A���A�����̒��͍��r�������Ėڊo�߂܂����B�ꃖ���Ɉ�x�͂قڂ���ȏǏo�Ă���܂��B�����̑̏d��68.5kg��400g�Ȃ�Ƃ��Ȃ�B
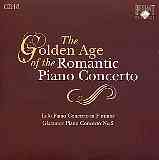 Lalo �s�A�m���t�ȃw�Z���i�}�����[�k�E�h�[�X(p)/�}�e�B�A�X�E�N���V��/�V���g�D�b�g�K���g�E�t�B��/1976�N�j/Glazunov �s�A�m���t�ȑ�2�ԃ������i�}�C�P���E�|���e�B(p)/�W�[�N�t���[�g�E�����h�[/���F�X�g�t�@���������y�c/1975�N�j�E�E�E�����The Golden Age of the Romantic Piano Concerto/��Ȃ��W�߂����̂̒����q���������́BLalo�͂Ȃ��2000�N�ɔq�����Ă���܂��B
Lalo �s�A�m���t�ȃw�Z���i�}�����[�k�E�h�[�X(p)/�}�e�B�A�X�E�N���V��/�V���g�D�b�g�K���g�E�t�B��/1976�N�j/Glazunov �s�A�m���t�ȑ�2�ԃ������i�}�C�P���E�|���e�B(p)/�W�[�N�t���[�g�E�����h�[/���F�X�g�t�@���������y�c/1975�N�j�E�E�E�����The Golden Age of the Romantic Piano Concerto/��Ȃ��W�߂����̂̒����q���������́BLalo�͂Ȃ��2000�N�ɔq�����Ă���܂��B
�����Ƃ����u�X�y�C�������ȁv�B�ł��A�s�A�m���t�Ȃ��Ȃ��Ȃ��������������Ղ�B24���قǁB�X�P�[�����傫���A���}���e�B�b�N�Ȃ������Ƃ��������������������̖��ȁB�܂�Ń`���C�R�t�X�L�[���i�����ƃV���v��������ǁj�̏L�������B���̐[���P���Ȏ��̌J��Ԃ����A���傶��ɃN���b�V�F���h���Ă�������オ��͂Ȃ��Ȃ��̂��́B�i������A�����o������j��2�y�͂��p�^�[���Ƃ��Ă͓����B�i����������E�p�^�[���Ƃ����B�ł��A��͂����������j�I�y�͈͂�]�u���[���X��̏d���Ȃ͂��܂肩��A��1�y�͂̎�肪��A���܂��B
���̋Ȥ�R���T�[�g�f������Ǝv����ł����ǂ˂��A�N�����Ȃ�����ł��傤���B�h�[�X�͗͋��������n���̂����Ō����ō��B�o�b�N���悭���킹�Ă��邪�A�����̔����͉B���悤���Ȃ��B�^�����i���̃��[�x���ɂ��Ắj�܂��܂��ł��傤�B
2018�N�ɂ��Ē�����
��1�y�́uLento;Allegro�v�`���̂������V���v���A�Ă͕Ԃ��g�̂悤�ɉ���������肪�S�҂��x�z���āA���I�ɂ͋����ׂ����ȁI
����1976�N�̘^���Ə��߂Ēm���āA��≹���͍d���BMarylene Dosse�i1939��������j��Ɉ��ė����Ŋ����炵���B���Ȃ肵������Ƃ����^�b�`�ɏ[�����������A��1�y���uLento;Allegro�v�V���v���Ȑ������������J��Ԃ���ď�����܂��Ċ����I�B�i11:55�j��2�y���uLento�v���قƂ�Ǖ��͋C�͕ς��ʁA������������������܂��B�i6:55�j��3�y���uAllegro�v�͈����݂��������āA�₪�Ă���͖��邢�\��ɕω����đ�1�y�͂̃V���v���Ȏ�肪��A���Ă킩��₷���B�i6:17�j���������Ȗ��Ȃł���B
Glazunov�͏����i�ƁA�v���j�P��y�͂ɑ��x�\�L������܂���B��Ȑ��H�̖���A�|���e�B�o��B���̐l�͂����Ȃ�ł�����̂ł��ˁB�������\����������̂ق����N���A�Ɗ����܂��B�܂�ʼn�������Brahms���̗D�����������J�n�B���I�ɂ����Ղ�Ȃ��A�s�A�m�͗Y�قɘN�X�Ǝ��Ƀ����w���̂悤�ɊÂ��̂��đ�c�~�ցB�^���≉�t�@����Ȃ��̂̓E�\�̂悤�Ȗ��ȁB�i19:31�j����i�Ƃ����܂�ɏa�߂���o�b�N�]���ċM�d�Ș^���Ǝv���܂��B
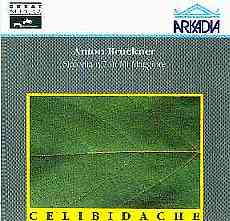 Bruckner �����ȑ�7�ԃz�����i�m���@�[�N�Łj�`�Z���W�E�E�`�F���r�_�b�P/�V���g�D�b�g�K���g���������y�c�i1971�N���C���j�{Wolf �C�^���A�̃Z���i�[�f�i�C�^���A�������[�}�����y�c1968�N���C���j�E�E�E�O���2021�N�ɔq���B�����͂��z�R���ۂ������B����͂����炭DG����o�Ă�����̂Ɠ��������ADG�̂ق������^���ʑ傫���A�C�R���C�W���O�ɂ�苭�チ���n���͂����肵�Ă��镪���������̑��肪�C�ɂȂ�܂��B�ӔN�̔����O�i�ɔA�e���|�͒ʏ�ɋ߂�����ǁA�ו����O�ȕ`�����݂ƃX�P�[���͑傫���A�ċz�[���A�������肽���Ղ�̂��C���E�e���|�̈�ۂ͓����B�S�����Ȓ��A�����Ƃ��������������������ȁA�����ł����2�y�́uAdagio�v�̊����[���ɏ��y�͂́A��������^���Ƀ^���ċ}�����A���ɑŊy����ăN���C�}�b�N�X�Ɏ���J�^���V�X�Ɋ������܂����B�i21:10-23:45-9:46�12:23���荞�j
Bruckner �����ȑ�7�ԃz�����i�m���@�[�N�Łj�`�Z���W�E�E�`�F���r�_�b�P/�V���g�D�b�g�K���g���������y�c�i1971�N���C���j�{Wolf �C�^���A�̃Z���i�[�f�i�C�^���A�������[�}�����y�c1968�N���C���j�E�E�E�O���2021�N�ɔq���B�����͂��z�R���ۂ������B����͂����炭DG����o�Ă�����̂Ɠ��������ADG�̂ق������^���ʑ傫���A�C�R���C�W���O�ɂ�苭�チ���n���͂����肵�Ă��镪���������̑��肪�C�ɂȂ�܂��B�ӔN�̔����O�i�ɔA�e���|�͒ʏ�ɋ߂�����ǁA�ו����O�ȕ`�����݂ƃX�P�[���͑傫���A�ċz�[���A�������肽���Ղ�̂��C���E�e���|�̈�ۂ͓����B�S�����Ȓ��A�����Ƃ��������������������ȁA�����ł����2�y�́uAdagio�v�̊����[���ɏ��y�͂́A��������^���Ƀ^���ċ}�����A���ɑŊy����ăN���C�}�b�N�X�Ɏ���J�^���V�X�Ɋ������܂����B�i21:10-23:45-9:46�12:23���荞�j
�C�^���A�̃Z���i�[�f�͏����ɏ����ɂȂ�Ƃ��X�e�L�ȏ��i�B1960�N��`�F���r�_�b�P�͈ɑ������̃��C�������������c����āA�ǂ�������[������ǁA�قڗ�O�Ȃ������͂�낵���Ȃ��B����̓}�V�ȕ��ł����B�i7:51�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�T�����}���܂����B��������͉J�������炵������ǁA���������͓܂��ɋC���͍ō�30�xC������Ƃ��炢�B������Ə�����������ǁA�ʉ@�̉����ł����قǂ̋�ɂ͂���܂���B����A�X�g���b�`�{YouTube8���قǂ̗������ؑ̑��ς܂��āA�A�_�̖�����炢�ɃN���j�b�N�֏o�|���܂����B�K��������N�ʕ��Ǐ�͂܂������o�Ă���܂���B������9��10���O���炢�ɓ��������̂Ɍ����݁A1���Ԕ��قǑ҂�����܂����B�̏d���X���������㏸�ō�146���v�X�A����̓A�E�g�B���̊Ԃ̘A���������������̂��B���̂��ƋƖ��X�[�p�[�Ɋ���ĐH�ނ��d����܂����B���̃O���m�[���{�I�[�g�~�[���ɂ͒ᎉ�b�������p�B����͋Ɩ��X�[�p�[�̂��_���g�c�ň����B����͌����������玉�b�������̂݁B����ŗǂ���ł��B�ق��̓X�ł́{30�~�قǍ����āA����́u�J���V�E���A�r�^�~��D�����v�Ƃ��t�����ĉ��l�����߂Ă���̂ł��傤�B
�����}���ّI���J�[�B��1�[�ō��s���c���g�b�v�A��̒����ł̔ߎS�ȎE�l�����̉e�����������̂��B�j�㏉�̏����g�b�v�͂�낵������ǁA������ƉE���߂����ȁH����ƌ��I���[�ŐΔj����t�]�A�ӊO�Ȍ��ʂł����B�܁A��Ȃ̂͂��ꂩ��ł���B�����荡���̑̏d��68.9kg�{500g�A7,000���قǂ̃E�H�[�L���O�ł͂��̊�@������Ȃ��B
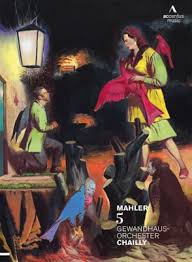 Mahler �����ȑ�5�� �d�n�Z���`���b�J���h�E�V���C�[/���C�v�c�B�q�E�Q���@���g�n�E�X�nj��y�c�i2013�N���C���j�E�E�E�S�W�Ę^�������҂���A����7�ȂŏI�������������ARiccardo Chailly�i1953��ɑ������j�͌��݃X�J�����̉��y�ēB�Q���@���g�n�E�X�̃J�y���}�C�X�^�[�ɂ�2005-2015�N�ݔC�A���̎����̉f���L�^�ł����B�������特���������o�������������A�����͎��R�Ɖ]���Ύ��R�A��������Ă���ƍ�����Ɗ����܂��B
Mahler �����ȑ�5�� �d�n�Z���`���b�J���h�E�V���C�[/���C�v�c�B�q�E�Q���@���g�n�E�X�nj��y�c�i2013�N���C���j�E�E�E�S�W�Ę^�������҂���A����7�ȂŏI�������������ARiccardo Chailly�i1953��ɑ������j�͌��݃X�J�����̉��y�ēB�Q���@���g�n�E�X�̃J�y���}�C�X�^�[�ɂ�2005-2015�N�ݔC�A���̎����̉f���L�^�ł����B�������特���������o�������������A�����͎��R�Ɖ]���Ύ��R�A��������Ă���ƍ�����Ɗ����܂��B
��1�y���uIn gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt.�i���m�ȑ����ŁB���l�ɁB����̂悤�Ɂj�v�`���̃g�����y�b�g�E�\������ۓI�Ȏn�܂�B�s���Ƃ��݂͂Ƃ͖����̉��t�A���@�[�c���t�E�m�C�}����1966�N�^�����v���o���A�����Ԃ�ƃ��_�[���Ȉ������܂����T�E���h�ɕς��������ǁA��͂舟�ė����ӂ�̃p���t���Ƀf�[�n�[�Ȃ��̂Ƃ͈Ⴄ�B���W�~�ȗ}����������������́B�i12:08�j��2�y���uSturmisch bewegt. Mit grosster Vehemenz. �i���̂悤�ȍr�X���������������āB�ő�̌��������āj�v�������u�ő�̌���v�ɔB�V���C�[�̓����͗��h�ɐ������A���T���u���ɏd�ʊ��͂����āA�㔼�ɐi�ނɂ�A�c����M�͍��܂�܂��B�ŏI�Ղ̋��ǂ̔����͓ƈ�̃C���[�W�ł��˂��A�M���M�������h���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�i13:49�j��3�y���uKraftig, nicht zu schnell.�i�͋����A���������Ɂj�v�����̓z�����E�\�����劈��A�y���Ƀ��[�����X�Ȃ�4����3���q�B�z�����̉��F�͊��Ғʂ�̒n���a�����F�A�������n�������M���ɔA���X�g���Ȃ�̃e���|�E�A�b�v���p���[�͏[���A����ł�������������킢�[�����������������܂��܂��B�i16:26�j��4�y���uAdagietto. Sehr langsam. �i���ɒx���j�v�G�b�`�ɂ܂��Ԑl�C�Ȋɏ��y�́B�����̌����T�����Ɨ����낵�������ĉ��ʂ��������������A���˂��˂ƔZ���Ȋ��\�����������Ȃ��B���O�ȃf���J�V�[�͏[���ł��傤�B�i8:13�j��5�y���uRondo-Finale. Allegro giocoso�i�y�����Ɂj�v����₩�ȃz�����A�t�@�S�b�g�A�I�[�{�G�A�N�����l�b�g�̌Ăь��킵����X�^�[�g�A���̉��F���Q���@���g�n�E�X�炵���h�肳�̂Ȃ����́B�₪�Č��̎Q�����a���ăG�G���ɖ��Ă܂���B���̃t�B�i�[���̓w�^����ƑO�y�͂̐�捂��䖳���ɂȂ��Ă��܂��Ƃ���A�������Q�Ă��͂܂����炸�A�͋��������y����}�����������āA�S�Ȃ��o�����X��낵�����߂�����܂����B�i15:27���荞�j
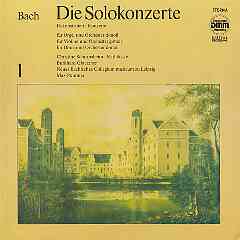 Bach �I���K�����t�ȃj�Z��BWV188�i�N���X�e�B�A�[�l�E�V�������X�n�C��(or)�j/���@�C�I�������t�ȃg�Z��BWV1056�i�J�[���E�Y�X�P(v)�j/�I�[�{�G���t��BWV35/156/1059�i�u���N�n���g�E�O���b�c�i�[(ob)�j�`�}�b�N�X�E�|�}�[/���C�v�c�B�q�V�o�b�n�E�R���M�E���E���W�N���i1985�N�j�E�E�E�����ƈ퐨�ɂ�郂�_�[���y��ɂ��Bach�A�����LP������������������ǁACD������Ă��܂��������H�����I�ɌÊy�퉉�t�������Ɏ����āA����Ȑ��^�ʖڂȃ��Y�������ރ��_�[���y��͂�����Əo�Ԃ����Ȃ��Ȃ����悤�ȋC�����܂��B�ǂ������݂̐����͂����Ⴄ�y��ɂ���ĉ��t����A���̈�a���͂���܂���B�Q���@���g�n�E�X�̃����o�[�ł����H���т��тƂ��ĂĂ��˂��ɃI�[�\�h�b�N�X�ȉ��t�ABach�͂ǂ�ȃX�^�C���ł����̉��y�̍��i�����͕͂ς��Ȃ��B�����Ƃ�Ƃ��ė����������������ǍD�B�i8:32-5:45-8:12/4:04-1:46-3:43/5:38-3:03-3:35�j
Bach �I���K�����t�ȃj�Z��BWV188�i�N���X�e�B�A�[�l�E�V�������X�n�C��(or)�j/���@�C�I�������t�ȃg�Z��BWV1056�i�J�[���E�Y�X�P(v)�j/�I�[�{�G���t��BWV35/156/1059�i�u���N�n���g�E�O���b�c�i�[(ob)�j�`�}�b�N�X�E�|�}�[/���C�v�c�B�q�V�o�b�n�E�R���M�E���E���W�N���i1985�N�j�E�E�E�����ƈ퐨�ɂ�郂�_�[���y��ɂ��Bach�A�����LP������������������ǁACD������Ă��܂��������H�����I�ɌÊy�퉉�t�������Ɏ����āA����Ȑ��^�ʖڂȃ��Y�������ރ��_�[���y��͂�����Əo�Ԃ����Ȃ��Ȃ����悤�ȋC�����܂��B�ǂ������݂̐����͂����Ⴄ�y��ɂ���ĉ��t����A���̈�a���͂���܂���B�Q���@���g�n�E�X�̃����o�[�ł����H���т��тƂ��ĂĂ��˂��ɃI�[�\�h�b�N�X�ȉ��t�ABach�͂ǂ�ȃX�^�C���ł����̉��y�̍��i�����͕͂ς��Ȃ��B�����Ƃ�Ƃ��ė����������������ǍD�B�i8:32-5:45-8:12/4:04-1:46-3:43/5:38-3:03-3:35�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�ѓc����ĐR���ߔ����B58�N�͏d���Ȃ��B�^�Ɛl�͂ǂ��T���̂��B�L���̒��S���ł����Ȃ蓹�H�זv���āA�}���V�������X���Ĕ����Ƃ��B��������i�\����Ȃ����ǁj���������ȓ��X���߂����Ă���܂��B
������ō��C��32�xC���オ���čD�V�A����ł����A�ɓ���Ɨ����������܂��B�O���ǂ������肪�A�C���͗D��Ȃ�����ǐ���A�X�g���b�`�AYouTube�G�A���r�N�X��10���قǂ̃E�F�X�g���i��^���A�������������܂����B�����Ĉ���x��ăg���[�j���O���[���ցA�u���g���ĊJ�ցB�@��͍X�V����Ă��炸�A�o�[�x���̏d�肪�V�����lj����ꂽ���炢�B�����e�i���X�͂����̂�������܂���B��A�����o�[�������{��҂��Q�����ă}�V���͈�܂���ł����B�G�A���o�C�N15���L�_�f�^��������������{���đ̒��͐����܂����B�Ȃ̂ɍ����̑̏d��68.4kg�{500g�ň��B���߂����̂��B
���������BS�������T�X�y���X���ꁄ���̔ƍߑ{�������ޒÎq3�u�̃e�[�v�E�l�����v�i1999�N�j�ڂ��蒭�߂Ă�����A�܁A���Ђ�݂�F�����m���₽��ƎႢ�I�Ƃ��A�P�[�^�C���Â��̂͂��Ă����A�E��ʼn������ς��ϋi�����i�i��������C�j�Ɉ�a���ƕs�����A�l�����I�̎���̗����������������B���ꂪ����������ƑO�ɂȂ�ƃP�[�^�C���o�Ă��Ȃ��Ȃ�܂��B
������C�ɓ���̓���߂Ċ��S�B���s���i�͂�肤���j���y�͂ǂ�ǂ�Z���Ȃ�A�O�t�͒Z���Ȃ�����A���������Ȃ��Ȃ�����A�T�r�ւ̓��B���Z���Ȃ��āA�T�r�݂̂̉��y���o�����Ă���Ƃ��̂��ƁB�����炪Classic Music�͂ǂ��Ȃ�H���������Ă�����ƕ~���������ēr�������Ă��܂��I�y���Ƃ��ABach�̎��ȂƂ���s��������ƐS�z�ɂȂ�܂��B��������ڂ���TikTok��V���[�g�ցA�f���{���Ŋς�Ƃ����\�ɂ͐��B���������h���}�������E�T�C�N���Z���Ȃ��Ă��܂���ˁA�؍��Ƃ������ł͂��Ȃ蒷���p���炵�����ǁB
����͋C�̒Z���C���X�^���g�n�D�Ȃ̂��ȁA������ƈ��ՂɐS�z�Ȑ����������܂��B���ǂ��^�O�ł������ȁy�� KechiKechi Classics ��z�Ȃ�Ċ��S�Ȏ���x��ł��傤�B���Ɍ��m���͎������E�I���ցB�{�������}�̑��ّI�A�쎟�n�I�ȋ����͂���܂��B
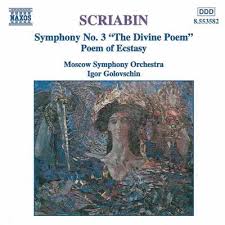 Scriabin �����ȑ�3�ԃn�����u�_���Ȏ��v/�����ȑ�4�ԃn�����u�@�x�̎��v�`�C�[�S���E�S���t�X�`��/���X�N�������y�c/�h�~�[�g���[�E���J�����R�t (tp)�i1995�N�j�E�E�EIgor Golovschin�i1956-1998�I�����j�̉\����ȂƎv������A���ɖS���Ȃ��Ă����̂ł��ˁBNAXOS�ɂ���Scriabin�Ƃ�Glazunov�̂܂Ƃ܂����^�����c���Ă���܂����B���X�N�������y�c��1989�N�n���̐V�����I�[�P�X�g���A������҂�אg�Ɉ����ۂ��H�T�E���h�ɋ�������ǃN���A�ȉ����A�����ĈӊO�Ɨ��h�ȃA���T���u���ł����B
Scriabin �����ȑ�3�ԃn�����u�_���Ȏ��v/�����ȑ�4�ԃn�����u�@�x�̎��v�`�C�[�S���E�S���t�X�`��/���X�N�������y�c/�h�~�[�g���[�E���J�����R�t (tp)�i1995�N�j�E�E�EIgor Golovschin�i1956-1998�I�����j�̉\����ȂƎv������A���ɖS���Ȃ��Ă����̂ł��ˁBNAXOS�ɂ���Scriabin�Ƃ�Glazunov�̂܂Ƃ܂����^�����c���Ă���܂����B���X�N�������y�c��1989�N�n���̐V�����I�[�P�X�g���A������҂�אg�Ɉ����ۂ��H�T�E���h�ɋ�������ǃN���A�ȉ����A�����ĈӊO�Ɨ��h�ȃA���T���u���ł����B
�u�_���Ȏ��v�͎l�ǕҐ��A���t�uIntroduction : Lento�v�̓g�����{�[���ɂ��u�{��̓��v����������n�܂����i1:36�j��1�y���uLuttes : Allegro�i�����j�v�͂��̎������ƂɗE�s�ɃJ�b�R�ǂ��W�J�B�g�����y�b�g���u���ȍL����������������2��肪�N�X�Ɖ̂��Ă킩��₷���B�₪�Č��̎�肪�߂��Ď����A���̂܂ܓr�ꂸ�i25:37�j��2�y���uVoluptes : Lento�i�x�y�j�v�ցB�؊ǃz�������猷�֊Ô��Ȏ�肪�����p����Đ�捂����\�I�B�₪�ď�͊Ă͕Ԃ��g�̂悤�ɍ��܂��āE�E�EWiki�̐����ɂ���u�g�����y�b�g�̐M�����v�Ƃ����Ӗ��������ł��܂���B��ۓI�ɒe�ނ悤�ȃg�����y�b�g�͊��x���o��B�i13:45�j��3�y���uJeu divin : Allegro�i�_���Ȃ�V�Y�j�v���X�g�͋��ǃt�@���t�@�[�����ɍ��g���ăN���C�}�b�N�X���}���܂����B�i11:10�j
�u�@�x�̎��v��Scriabin�̂�����l�C�A�Ƃ��Ă��G�b�`�ȍ�i�B�l�ǕҐ��ɃI���K���A�n�[�v��`�F�X�^��������Ґ��B�ꉞ�n�����ƂȂ��Ă��邯��ǎ��ۂ͉������A�������u�����ȁv�̑̂͐����Ă��Ȃ������������B�_��a���i�h�E�V���E�g�ɂ͈Ӗ��s���j�d�����a���͂��˂�悤�ɘA�����āA���̉��t�ł͑������F�̃g�����y�b�g�̑��݂����ɂ������ēˏo�A���̌J��Ԃ����ƂĂ��킩��₷���B�t���[�g�ƃz�����̓N�[���ɁA���ǂƑŊy��͑����ȃe���V�����Ƌْ����ł����B�i24:10�j
 Mendelssohn ���@�C�I�������t�ȃz�Z���i�L�����E�R���h���V��/�\���B�G�b�g���������y�c/1949�N�j/Bruch ���@�C�I�������t�ȑ�1�ԃg�Z���i�C�[�S���E�I�C�X�g���t(v)/�_���B�h�E�I�C�X�g���t/���C�����E�t�B��/1961�N�j/Glazunov ���@�C�I�������t�ȃC�Z���i�L�����E�R���h���V��/�\���B�G�b�g���������y�c/1948�N�j�`�_���B�h�E�I�C�X�g���t(v)�E�E�E�ʐ^�͑��q�̃\���ɂ��Bruch�A������ƒ���������������ŁA���\���B�G�b�g����̃��m�����^���͗\�z�O�ɏ�Ԃ���낵���ADavid Oistrakh�i1908-1974�G�����j�̖L���Ƀ}�C���h�Ȕ����������Ղ芬�\�ł��܂����B
Mendelssohn ���@�C�I�������t�ȃz�Z���i�L�����E�R���h���V��/�\���B�G�b�g���������y�c/1949�N�j/Bruch ���@�C�I�������t�ȑ�1�ԃg�Z���i�C�[�S���E�I�C�X�g���t(v)/�_���B�h�E�I�C�X�g���t/���C�����E�t�B��/1961�N�j/Glazunov ���@�C�I�������t�ȃC�Z���i�L�����E�R���h���V��/�\���B�G�b�g���������y�c/1948�N�j�`�_���B�h�E�I�C�X�g���t(v)�E�E�E�ʐ^�͑��q�̃\���ɂ��Bruch�A������ƒ���������������ŁA���\���B�G�b�g����̃��m�����^���͗\�z�O�ɏ�Ԃ���낵���ADavid Oistrakh�i1908-1974�G�����j�̖L���Ƀ}�C���h�Ȕ����������Ղ芬�\�ł��܂����B
�N�ł��m���Ă���Mendelssohn��2010�N���̍Ē��B�Ô��Ȑ�����C�萬�A�����Ղ���t���̂�낵�����F�ɗ�������R�ɑS�ȁA�Q���̐��E�����\�ł��܂����B��1�y�́uAllegro molto appassionato�v�i13:24�j��2�y�́uAndante�v�i7:39�j��3�y�́uAllegretto non troppo - Allegro molto vivace�v�i6:32�j�@
Bruch�� Igor Oistrakh�i1931�2021�G�����j��DG�X�e���I�^���A30�̋L�^�B������Q���Ȑ��������Ղ�̏�M�I���ȁA�Ƃ��ɍŏI�y�̖͂�������\���̏d���������ǂ���ł��傤�B��������낵��������Ȃ��̗���ȋZ�I������ǁA�e���̉A�e�����Ղ�ɋ}���݂̋Z���Ă��܂��ƁA���^�ʖڂ��������邩���B��1�y�́uAllegro moderato�v�i8:27�j��2�y�́uAdagio�v�i8:34�j��3�y�́uFinale: Allegro energico�v�i7:04�j
Glazunov�̓n�C�t�F�b�c�̊������������t�ŏo�������i�B�����璆�f�̃o�����X�Ɨ����������̂Ɉ��āA�����H��悤�ȃ��@�C�I�����B�I�y�͂̐���₩�Ȓ��߂�����Ɍ����āA������r��Ȃ����t����܂��B�����������Ԃ̓����ƗǍD�ł����B��1�y�́uModerato�v�i4:39�j��2�y�́uCadenza : Andante sostenuto�v�i10:51�j��3�y�́uAllegro�v�i5:37�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�D�V�����Ē��̍ō��C����31-33�xC���炢�ɏオ���Ă����ӗ������āA�ҏ��̃s�[�N�͉߂��܂����B�H�����瓖����O�B�����̂悤�ɒ��A���������Ă���X�g���b�`�AYouTube�G�A���r�N�X��10���قǂ̃E�H�[�L���O���S�A�r���S�~�E�����s���̈�قɓ���������A�g���[�j���O���[���̓}�V������ւ��{�����e�i���X�ɂďI�����x�݂ɜ��R�B���O�ē��������Ƃ��܂����B���������Β��Ԃ��Ă���N���}�����ɂ������I�V�����������̂́A����������ƎႢ�o���[�{�[���̃����o�[����������ł��傤�B���̂܂܃X�[�p�[�Ɋ���ĐH�ނ�����҂�lj����āA�ʎq���������Ă���͖̂ҏ��Ɍ{���o�e�Ă���̂ƁA�H�́u�����Ȃ�Ƃ��v���j���[���킪�哖����Ŏ��v�����������炾�����B���̓��̉^���̓E�H�[�L���O7,500���قǂŏI���B�{���d�蒼���ċg�����܂��傤�B�����̑̏d��67.9kg��800g�A�܂��܂��B
�����F�͊��ى����̎�p�A���ڈ�C�ɏ��u�A���A�肾�����ł��B�܁A�ؗ�Ȃ������d�˂���������s��͏o�܂���B���Ƃ�LINE�����Ă݂܂��傤�B���������X�}�z�Ɋ��x�����M������E�E�E�J�o���̒��Ɏd�����Ĕw�����Ĉړ����������̂ŁA�C�t���܂���ł����E�E�E�Ƃ����̂̓E�\�B�X�}�[�g�E�H�b�`�ɒ��M���\������A���o���̂��ʓ|�������߁B�����̃X�}�z�ɂ�090�ԍ���050�ԍ�������āA�Ȃɂ��o�^���Ȃ������Ⴂ���Ȃ��Ƃ��ɂ�050�ԍ����L�����Ă���̂́ASMS���͂��̂��T����������B������090�ԍ��Ɋ|�����Ă���̂̓X�p���̉\���������B�A��Ă��璅�M���m�F����Ɓu���f�d�b�v�ƕ\������Ă���܂����B�G������My�X�}�z�B�M�S�Ȃ���ł���B��x�o�Ă݂����Ƃ�����������ǁA�����d�b�ł����B�X�}�z�̗��p��LINE�i�d�b��LINE�j�ƃX�}�[�g�E�H�b�`�̒b�B���јA�g�̂݁A���Ƃ͂قƂ�ǎg���Ă���܂���B�Ȃ�1,100�|200�~/���ł�����B����ł�Wifi�Ȃ̂ő��x�]�X�͖��ɂȂ�܂���B��قǂ�050���M�͖��f�d�b�ł͂Ȃ����������B
 Bruckner �����ȑ�2�ԃn�Z���i�n�[�X�Łj�`���j�b�N�E�l�[=�Z�K��/�O�����E�����g���I�[���E���g���|���^���nj��y�c�i2015�N�j�E�E�E���݂����Ƃ��Z�����w���҂ł���Yannick Nezet-Seguin�i1975����ޑɁj�ɂ��Bruckner�̌����ȑS�W������HDD���߉ގ����ɂ������B��2�Ԃ̂݃l�b�g�ɏo�������̂ōĒ����Ă���܂��B00��0��1��2�ԕӂ�͔q���@����Ȃ��āA��3�Ԃ������A����͋v�X�̍�i�q���ƂȂ�܂����B���Ȃ�ȑO�ɔq�������S�Ȉ�ۂł̓T���T���Ƃ��Ĉ�ۂ̎c��ʉ��t�ɁA������ƃK�b�J�������L���L�B����͑u�₩�ɃN���A�ȋ����ɍ�i�̍\���͂킩��₷���ƒ����܂����B
Bruckner �����ȑ�2�ԃn�Z���i�n�[�X�Łj�`���j�b�N�E�l�[=�Z�K��/�O�����E�����g���I�[���E���g���|���^���nj��y�c�i2015�N�j�E�E�E���݂����Ƃ��Z�����w���҂ł���Yannick Nezet-Seguin�i1975����ޑɁj�ɂ��Bruckner�̌����ȑS�W������HDD���߉ގ����ɂ������B��2�Ԃ̂݃l�b�g�ɏo�������̂ōĒ����Ă���܂��B00��0��1��2�ԕӂ�͔q���@����Ȃ��āA��3�Ԃ������A����͋v�X�̍�i�q���ƂȂ�܂����B���Ȃ�ȑO�ɔq�������S�Ȉ�ۂł̓T���T���Ƃ��Ĉ�ۂ̎c��ʉ��t�ɁA������ƃK�b�J�������L���L�B����͑u�₩�ɃN���A�ȋ����ɍ�i�̍\���͂킩��₷���ƒ����܂����B
��1�y���uZiemlich schnell�v���Bruckner�J�n�i�Â��Ȍ��̃g�������j����`�F���̓��@�A��������ďd�ꂵ�������������ʁA�}�C���h�ȋ����������܂��B�Ј������Ȃ������Ďア�قǁH�f�����߂��ėD�����������ꂽ�����B����������ǁA��i�����̐V���Ȗ��͂����o���قǂɔB�i19:08�j��2�y���uAdagio. Feierlich, etwas bewegt�v���炳��ƃf���P�[�g�ɒW����Y���ɏ��y�́B�݂͂Ȃ�����ȃo�����X���D��ۂł����B�����������ƉA�e�␦�݂��~�����Ƃ���B�i16:23�j��3�y���uScherzo. Schnell - Trio. Gleiches Tempo�v�X�P���c�H��Bruckner�̃L���A�����͑ӂ����t���ƃ��Y�����ۗ����ʂƂ���B�D�u�Ƃ������Y�����ƃm���͂������B�g���I�͗D���������ς��B�i8:13�j��4�y���uFinale. Mehr schnell�v�O�y�͂̃��Y���̂܂n�܂��āA�O���͌����S�ɗD�������������āA�����ɖ��邢����ɐ���オ��܂��B�s��Ȓǂ����݂������������N�̍�i�ɔ�ׁA��i�͂����Ԃ�Ɖ�������Ȋ����B�₪�ăt�B�i�[���Ɍ����Ċ��Ғʂ�̋��ǂ������A�I�[�P�X�g���͂��Ȃ�̋Z�ʂ�����ǁA�n�����̂悤�ȃh���͂ɔA�d�グ�͂����܂Ń}�C���h�B�i17:58�j
 Stravinsky �o���G���y�u�y�g���[�V���J�v�i1947�N�Łj/Ravel �o���G���y�u�_�t�j�X�ƃN���G�v��2�g��/Andrei Petrov(1930-2006�I����)�u�n���L�v*�`���[���E�e�~���J�[�m�t/���j���O���[�h�����y�c/���j���O���[�h�E�t�B�����N�����c*�i1971-1977�N�j�E�E�EYuri Temirkanov�i1938-2023�I�����j30�Α�̎Ⴋ���A�t�B���n�[���j�[�Ȃ�ʌ����y�c�Ƃ̒������L�^�A���\���B�G�b�g����̃Z�b�V�����^���͋ɂ߂đN���ȉ����ł����B����Stravinsky������S�����߉ނɂ��āA����͘I�����̉������T�C�g��T������A10�N�ȏ�O�ɃA�b�v���[�h����Ă������̂��K�������Ă������́B
2021�N�ɔq���L�^��������
Stravinsky �o���G���y�u�y�g���[�V���J�v�i1947�N�Łj/Ravel �o���G���y�u�_�t�j�X�ƃN���G�v��2�g��/Andrei Petrov(1930-2006�I����)�u�n���L�v*�`���[���E�e�~���J�[�m�t/���j���O���[�h�����y�c/���j���O���[�h�E�t�B�����N�����c*�i1971-1977�N�j�E�E�EYuri Temirkanov�i1938-2023�I�����j30�Α�̎Ⴋ���A�t�B���n�[���j�[�Ȃ�ʌ����y�c�Ƃ̒������L�^�A���\���B�G�b�g����̃Z�b�V�����^���͋ɂ߂đN���ȉ����ł����B����Stravinsky������S�����߉ނɂ��āA����͘I�����̉������T�C�g��T������A10�N�ȏ�O�ɃA�b�v���[�h����Ă������̂��K�������Ă������́B
2021�N�ɔq���L�^��������
��������Ƃ��Ă��Ȃ�d���A���l�p�l�ʂȁu�y�g���[�V���J�v�A�F�C�̂Ȃ��u�_�t�j�X�v�A�����͂����ăI�[�P�X�g���͗D�G�ł����B�u�n���L�v��SF�f�批�y���킩��₷�����y�i�ق�܂ɉf�批�y�����j�B
����Ȉ�ۂ͍�����ς��܂���ł����B�����������Ƃ���������y�c�͂��������Ȏ��͔h�B�e���V�����������C�ȉ��t�͂������������߂܂��B�i9:39-4:16-6:34-14:01/16:16/3:42-5:04-4:05-4:05-5:23�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�\�o������J����72���Ԉȏ�o�߂��čs���s���҂̑{���͑����Ă���܂��B�����̐푈�͓D���B
����͍ō��C����30�xC�A���ӂ͂�������������ďH�̋C�z�����܂��Ă���܂��B������͍D�V�A���炭�J�͂Ȃ��悤�ł��B���͂悤�����āA�X�g���b�`�͒Z�߁AYouTube�G�A���r�N�X��15���قǂ��������ȓ����ł��A�������قǂɊ����o�܂���B�̒��͈����Ȃ�����ǁA���Ƃ͂����Ǝ����ɉ߂����܂����B���������G�߂����������Ă��Ă����_�I�ɂȂɂ����C���o�Ȃ��B��T�ʉ@�������̕s�����i�����������a���Ȃ������j���̉����ɕ��ׂ��|�����Ă���̂������Ɨސ��A���ԃu���V�ƌ��������������āA���ݏ�Ԃ͗ǂ������B��������}�̓}��I�]�X�ɂ͂��܂苻���͂Ȃ�����ǁA��������ꐶ�����x�����O�}��ł���|�C�̂Ă����̂��Ȃ��ȁA�Ƃ��������B��c�������N�ł��邱�Ƃ��m��܂����B�ʂɎv��������Ȃɂ�����܂��B�����̑̏d��68.7kg��100g�ň��̍��߈��蒆�B
�e���r�ʼnf��u�d�|�l�~���v�i1981�N�j�q���B���̎����ł��f���͂ƂĂ��������B�剉�̔~��������݉��єV��A���_�̕F���Y�͒����×��Y�Z��B�����{�����q�Ȃ��ǁA��߂��Ă��炭�N���킩��܂���ł����B�����̓��ځE�ߍ]�������͂Ȃ�ƈɒO�\�O�A���̐l�͂ق�܂ɐ����Ȉ������������āA�ԕ�Q�m�ł��g�Ǐ���͂܂���ł����B�Ⴋ���̐^�s���N�}������������ǁA�Ȃ�Ƃ����Ă�����^�R���̘a�����}�����ĐF���ۂ��B���N�̍��ؔz���ƂĂ��˂��Ȏd�グ���y������ǁA���X�g�ӂ�e�ɏ������͂��̔~�����J���^���ɕ������āA���}���d���߂闬��ɓ��S���s���܂���B����ɂ��Ă��A�قƂ�ǂ̔o�D�͋S�Ђɓ�������A���ޏ�ԂȂ͎̂���̗���������܂����B
�g���G�c�̐V����2023�N���͍ו��`�����ݓ��O���ɂ߂āA�V�C�S��̐F�C�͏���^�R���ɕ����Ȃ��B�f���B�e�Z�p�͐i��Ŕ~������̎d�|���I�������������I���Õ��݂ɍׂ��Ȃ�����A�S�҂ɕY���d�����Â��͂�����̕��ɕ�������Ɗ����܂����B
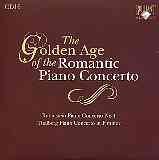 Anton Rubinstein�i1829-1894�I�����j �s�A�m���t�ȑ�4�ԃj�Z���i�I�g�}�[���E�}�[�K/�t�B���n�[���j�A�E�t���K���J/1968�N�jSigismond Thalberg�i1812-1871�����j �s�A�m���t�ȃw�Z���i���`���[�h�E�J�b�v/���F�X�g�t�@���������y�c/1973�N�j�`�}�C�P���E�|���e�B(p)�E�E�E��Ȃ��W�߂�The Golden Age of the Romantic Piano Concerto���BAnton Rubinstein�̍�i�͉ߋ����x�������āA���t�≹����ہH�F�����v�����i��Ō����i�߂悤�Ǝv��Ȃ�������ȉƁB�Ƃ��낪�����j�Z�����t���͖���Michael Ponti�i1937�2022���ė����j�̑f���炵���e�N�j�b�N�̐��ʂ��A�f���炵�����I�ɉ₩�ȍ앗�Ɋ����������܂����B���������Ȗ��ȁB�}�j�A�b�N�ȃo�b�N���}�C�i�[�D���i=���V�j�̐S����������܂��B��1�y���uModerato assai�v���D�Z���Ô����f�̐����̓\���Ɗnj��y�̉�b�ARachmaninov��������҂�A�z�����܂����B�f�b�h�ɃI���E�}�C�N�ȉ����̂����������āA�|���e�B�̃L���̂���s�A�m�i�Y�قȃJ�f���c�@�j���nj��y���t�����f���J�V�[������ʂł��傤���B�i11:15�j��2�y���uAndante�v�͉���������肩����悤�Ȋɏ��y�́B�W�X�Ƃ����\���ɖ؊ǂ̍����̎�����ł����B�i8:40�j��3�y�́uAllegro�v�y���Ƀ��Y�~�J�������Ǐo���ȑz�͈Â��A�ٔ������Y���܂��B�s�A�m�̋Z�I�͉ؗ�ł���Y�فA�͋������́B�₪�đu���Ƀp���t���Ƀt�B�i�[�����}���܂����B�i9:00�j
Anton Rubinstein�i1829-1894�I�����j �s�A�m���t�ȑ�4�ԃj�Z���i�I�g�}�[���E�}�[�K/�t�B���n�[���j�A�E�t���K���J/1968�N�jSigismond Thalberg�i1812-1871�����j �s�A�m���t�ȃw�Z���i���`���[�h�E�J�b�v/���F�X�g�t�@���������y�c/1973�N�j�`�}�C�P���E�|���e�B(p)�E�E�E��Ȃ��W�߂�The Golden Age of the Romantic Piano Concerto���BAnton Rubinstein�̍�i�͉ߋ����x�������āA���t�≹����ہH�F�����v�����i��Ō����i�߂悤�Ǝv��Ȃ�������ȉƁB�Ƃ��낪�����j�Z�����t���͖���Michael Ponti�i1937�2022���ė����j�̑f���炵���e�N�j�b�N�̐��ʂ��A�f���炵�����I�ɉ₩�ȍ앗�Ɋ����������܂����B���������Ȗ��ȁB�}�j�A�b�N�ȃo�b�N���}�C�i�[�D���i=���V�j�̐S����������܂��B��1�y���uModerato assai�v���D�Z���Ô����f�̐����̓\���Ɗnj��y�̉�b�ARachmaninov��������҂�A�z�����܂����B�f�b�h�ɃI���E�}�C�N�ȉ����̂����������āA�|���e�B�̃L���̂���s�A�m�i�Y�قȃJ�f���c�@�j���nj��y���t�����f���J�V�[������ʂł��傤���B�i11:15�j��2�y���uAndante�v�͉���������肩����悤�Ȋɏ��y�́B�W�X�Ƃ����\���ɖ؊ǂ̍����̎�����ł����B�i8:40�j��3�y�́uAllegro�v�y���Ƀ��Y�~�J�������Ǐo���ȑz�͈Â��A�ٔ������Y���܂��B�s�A�m�̋Z�I�͉ؗ�ł���Y�فA�͋������́B�₪�đu���Ƀp���t���Ƀt�B�i�[�����}���܂����B�i9:00�j
Thalberg�͂��Ă�����҂蒮������ۂł́ALiszt��肳��ɋZ�I�D��A�����̃I�����Ȃ��͂��������E�E�E����ȏ���Ȑ���ςł����B�w�Z�����t����翂т��I�[�P�X�g���̋������G�G�����B��1�y���uAllegro maestoso�v�͈ӊO�ɂ��V���v�������Ȑ������Y���������Weber��A�z������o���B�������ăo���o���e���i�߂�悤�ȃ\���̈����ɔB�T���߂ɏ�����܂�悤�ȃs�A�m��������҂舣�����ɊÂ������B���̕ӂ�Chopin�畉���̋C����ɖ����Ȏ���������܂����B�㔼�ɐi�ނقǂɍ����Z�I�͗v�����ꂻ���Ȋ����B�i11:22�j��2�y���uAdagio�v�D�������ۂɏ[�����s�A�m�E�\���B�Z������ǁA�������f���炵�������ł���B�i3:25�j��3�y���uRondo: (Allegro)�v�e�ނ悤�ȕ��ȕ��̃t�B�i�[���͉��ł���A���x�ɖ����������ł����B�i9:21�j
 Bach ���ϗ��N�����B�A�ȏW��1����1�ԃn����BWV846�`��8�� �σz�Z��BWV853/��2����17�� �σC����BWV886�`��22�ԃ�����BWV892�`�O���S���[�E�\�R���t(p)�E�E�EBach�����ɂ�_�����Ă�����o�����������t�@�C���͏��s���A�f�����킩��܂���B�����͗ǍD�ł��BCD���͂���Ă��Ȃ��悤�ŁA1995�N�̃��C�����悪�l�b�g�����ł��邩��A����ł��傤���B�i�~�����w���A�w���N���X�E�U�[���ł̃��T�C�^���j Grigory Sokolov�i1950��I�����j�͌���ō��̃s�A�j�X�g�̈�l�A�����ŋ߂͘I�����̐푈���݂Őg�����͎��Ȃ��Ɨސ����Ă���܂��B���ϗ��S�Ȃ̘^���͂��肻���ŁA���͂Ȃ��E�E�E���ꂪ���������Ȃ������邭�炢�A���������Ă����Ƃ�W�X�Ƃ����\��l�X�Ƒ����āA���������͂ɒ�������܂����B�i1:40-2:09/1:39-1:42/1:05-2:22/3:36-5:17/1:00-1:57/1:25-2:25/3:58-1:45/4:33-5:10/3:44-2:20/3:40-5:39/1:48-1:08/4:49-1:50/8:07-2:13/3:13-5:45�j
Bach ���ϗ��N�����B�A�ȏW��1����1�ԃn����BWV846�`��8�� �σz�Z��BWV853/��2����17�� �σC����BWV886�`��22�ԃ�����BWV892�`�O���S���[�E�\�R���t(p)�E�E�EBach�����ɂ�_�����Ă�����o�����������t�@�C���͏��s���A�f�����킩��܂���B�����͗ǍD�ł��BCD���͂���Ă��Ȃ��悤�ŁA1995�N�̃��C�����悪�l�b�g�����ł��邩��A����ł��傤���B�i�~�����w���A�w���N���X�E�U�[���ł̃��T�C�^���j Grigory Sokolov�i1950��I�����j�͌���ō��̃s�A�j�X�g�̈�l�A�����ŋ߂͘I�����̐푈���݂Őg�����͎��Ȃ��Ɨސ����Ă���܂��B���ϗ��S�Ȃ̘^���͂��肻���ŁA���͂Ȃ��E�E�E���ꂪ���������Ȃ������邭�炢�A���������Ă����Ƃ�W�X�Ƃ����\��l�X�Ƒ����āA���������͂ɒ�������܂����B�i1:40-2:09/1:39-1:42/1:05-2:22/3:36-5:17/1:00-1:57/1:25-2:25/3:58-1:45/4:33-5:10/3:44-2:20/3:40-5:39/1:48-1:08/4:49-1:50/8:07-2:13/3:13-5:45�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
������j�͐��Ԃł͘A�x�ŏI���B��l�̌��t�ʂ�A�����������ފݖ��B�k���̔�Q���Ă����A������͍��������u�₩�Ȗڊo�߁A���̐���A�X�g���b�`�ς܂���YouTube�G�A���r�N�X�̓I�[�\�h�b�N�X�Ȃ���15���ς܂��Ă����͂Ђǂ�����܂���B�s���̈�قւ̓������������̓}�V�A�H�̕���������҂芴���܂��B�j���̃g���[�j���O���[���͏�A�V���o�[�{�Ⴂ�w�����l�ɍ���ł���܂����B�g�����G�A���o�C�N15�����C���u���A�S���������قǂɏオ��܂���B�I���������������đ̒����悤�₭���������܂����B�A�肢���̃X�[�p�[�Ɋ�����炨�Ă͕i�����L�x�A��⍂������lj��i��������Ɨ��������Ă���܂����B�ߘa�̕đ�������i�����B�����̑̏d��68.8kg�{500g�������N�̍ō��l�X�V���A��������̂������̂ɁA����͂ǂ��������Ƃ��B��N�̍Œ�̏d���{5kg�ł����B
�O���̏��[�a���H�����͖����������āA���q�ƎU�X����ēۂ������̎x�����͏��߂āu�y�VPay�v���g���Ă݂܂����B�܁A�J�[�h�ł��ǂ�����ǂˁB�Ȃɂ��Ƃ��o���A���������W���ɕ\�����ꂽQR�R�[�h��������̃X�}�z�œǂݎ��̂ł��ˁB�X�[�p�[�ł̓o�[�R�[�h��ǂݍ���Ō��ς����ǁA���o����Ɏg�����������Ă��������܂����B����ł܂��Љ�̏펯���ЂƂw�т܂�����B�������̒����͗��s���QR�ǂݎ��A�����̂͒ᑬ�Ȃ̂ő��q�̃X�}�z�ł��肢���܂����B���ꂪ�Ȃ��Ȃ��̏d�ʊ��Ǝg���S�n�AiPhone����Google Pixel�ɏ�芷���������B�����Ɏ�����TONE e20�����������o�������܂����B�g�̏�Ɏ������������̋Z�ʂɂ͂҂�����̋@��ł����B
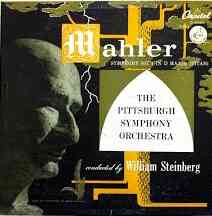 Mahler �����ȑ�1�ԃj�����i1953�N�j/Wagner �W�[�N�t���[�g�q���i1956�N�j/Mozart �A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N K.525�i1958�N�j/J.Strauss�U�s�`�J�[�g�E�|���J/�퓮��/�g���b�`�E�g���b�`�E�|���J�i1967�N�j�`�E�B���A�� �E�X�^�C���o�[�O/�s�b�c�o�[�O�����y�c�E�E�EWilliam Steinberg�i1899�1978�ƈ큨���ė����H�j�ɂ�閼�ȂĂ���̈ꖇ�BMahler�̉ؗ�Ȃ�ߑ�nj��y�̐��͂ł��邾��������Ԃ̉����Œ����������́B�����j�����������͂��Ȃ�ȑO���l�b�g��艹�����肵�₷��������x�������Ă��āA���܂�ɑf���C�Ȃ��\���������L���L�B�v�X�̔q����ۂ͂��Ȃ胂�m�����ł����Ȃ�𑜓x�̂�낵�������A���߂̃C���E�e���|�ɑf���C�Ȃ��\���Ɖ]�����̒ʂ�A�D�u�Ə���̂Ȃ��X�g���[�g�n�\���͐����������Ĉ����Ȃ����ƌ������܂����B��������1�y�͂͒��J��Ԃ��Ȃ��A�A���T���u���͐����ăp���t���ȃT�E���h�A�s�b�c�o�[�O�����y�c�͏�肢�ł��ˁB�i12:52-7:51-10:31-17:29�j�u�q�́v�����l�A���炳��Ƒ����e���|�ɕ������悤�Ȗ��x�A������������������܂����B�i15:11�jMozart�ȍ~�̓X�e���I�A����₩�Ƀe���V�����̍������邢���t�������āA�y���������ς��B�����c�ɔ��C��낵���|���J���X�^�C���o�[�O�ɑ��������I�Ȃł����B�i4:25-2:48-5:46-2:10/2:25-2:31-2:31�j
Mahler �����ȑ�1�ԃj�����i1953�N�j/Wagner �W�[�N�t���[�g�q���i1956�N�j/Mozart �A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N K.525�i1958�N�j/J.Strauss�U�s�`�J�[�g�E�|���J/�퓮��/�g���b�`�E�g���b�`�E�|���J�i1967�N�j�`�E�B���A�� �E�X�^�C���o�[�O/�s�b�c�o�[�O�����y�c�E�E�EWilliam Steinberg�i1899�1978�ƈ큨���ė����H�j�ɂ�閼�ȂĂ���̈ꖇ�BMahler�̉ؗ�Ȃ�ߑ�nj��y�̐��͂ł��邾��������Ԃ̉����Œ����������́B�����j�����������͂��Ȃ�ȑO���l�b�g��艹�����肵�₷��������x�������Ă��āA���܂�ɑf���C�Ȃ��\���������L���L�B�v�X�̔q����ۂ͂��Ȃ胂�m�����ł����Ȃ�𑜓x�̂�낵�������A���߂̃C���E�e���|�ɑf���C�Ȃ��\���Ɖ]�����̒ʂ�A�D�u�Ə���̂Ȃ��X�g���[�g�n�\���͐����������Ĉ����Ȃ����ƌ������܂����B��������1�y�͂͒��J��Ԃ��Ȃ��A�A���T���u���͐����ăp���t���ȃT�E���h�A�s�b�c�o�[�O�����y�c�͏�肢�ł��ˁB�i12:52-7:51-10:31-17:29�j�u�q�́v�����l�A���炳��Ƒ����e���|�ɕ������悤�Ȗ��x�A������������������܂����B�i15:11�jMozart�ȍ~�̓X�e���I�A����₩�Ƀe���V�����̍������邢���t�������āA�y���������ς��B�����c�ɔ��C��낵���|���J���X�^�C���o�[�O�ɑ��������I�Ȃł����B�i4:25-2:48-5:46-2:10/2:25-2:31-2:31�j
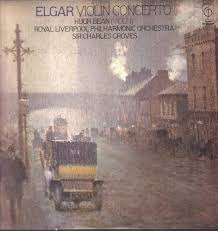 Elgar ���@�C�I�������t�ȃ��Z���i1972�N�j/�s�i�ȁu�Е����X�v��1�ԃj����/��4�ԃg�����i1976�N�j�`�q���[�E�r�[��(v)/�`���[���Y�E�O���[���X/���C�����E�����@�v�[���E�t�B���E�E�E���̃��@�C�I�������t�Ȃ��p�����y�̗�O�ɔA�T���Ɠ��ȓI�A�ǂ��肵���܂��̂悤�ȕ���A���{����l�C�o�Ȃ����Ȃ��BHugh Bean (1929-2003�p���j�̓t�B���n�[���j�A�nj��y�c�̃R���}�X�������l�B��������Ƃ����e�N�j�b�N�ƒ[���ȃX�^�C���ɔ��������W�~�ȕ���A��i����i������f�[�n�[�ȃp�t�H�[�}���X����ȉr�Q�ȂǕs�v�ACharles Groves(1915-1992�p���j�̔��t�������Ƃ�z��������́B��1�y�́uAllegro�v�i18:06�j-��2�y�́uAndante�v�i11:38�j-��3�y�́uAllegro molt-Leto-Allegro molt�v�i19:19�j�B�E�s�ȁu�Е����X�v������Ȃ��̃��B���B�b�h�ȉ��t�B�i6:28-5:21�j
Elgar ���@�C�I�������t�ȃ��Z���i1972�N�j/�s�i�ȁu�Е����X�v��1�ԃj����/��4�ԃg�����i1976�N�j�`�q���[�E�r�[��(v)/�`���[���Y�E�O���[���X/���C�����E�����@�v�[���E�t�B���E�E�E���̃��@�C�I�������t�Ȃ��p�����y�̗�O�ɔA�T���Ɠ��ȓI�A�ǂ��肵���܂��̂悤�ȕ���A���{����l�C�o�Ȃ����Ȃ��BHugh Bean (1929-2003�p���j�̓t�B���n�[���j�A�nj��y�c�̃R���}�X�������l�B��������Ƃ����e�N�j�b�N�ƒ[���ȃX�^�C���ɔ��������W�~�ȕ���A��i����i������f�[�n�[�ȃp�t�H�[�}���X����ȉr�Q�ȂǕs�v�ACharles Groves(1915-1992�p���j�̔��t�������Ƃ�z��������́B��1�y�́uAllegro�v�i18:06�j-��2�y�́uAndante�v�i11:38�j-��3�y�́uAllegro molt-Leto-Allegro molt�v�i19:19�j�B�E�s�ȁu�Е����X�v������Ȃ��̃��B���B�b�h�ȉ��t�B�i6:28-5:21�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�v�X�ɗ�������A�����Ē����}���܂����B���������̘A�x���S���I�ɉJ�͗l�B�x�d�Ȃ�k���ł̔�Q���S�z�ł��B�����ɂ��^�����ӕ�H���o�������B�����������ߑO���ɂ��Ȃ�~��o���āA�����}�������Ɉڂ��܂����B�������ɓ��������o�Ȃ����玼���ۂ�����ǁA�C����30�xC�قǁB��������ŎO���A���̐����s�@�ӁA�r���o���{���������o�͂����Ă�������̒��ň��A�������ɉ��ɂȂ��ĐÂ��ɒ����炢���Q������B����ł����������̑��q����̗U���A���[�a�͂Ȃ���u�H�̍ՓT�v�݂����Ȃ��̂ɏo�|���āA���̌�ɂ����̔~�c�w�O�r���n���ɂč����������܂����B
�܁A�̒��ǂ��̂����̉]���Ă��U�X����ēۂ݂܂����B���q�͉Ƃ��������ŗ����]���A���[���͂Ȃ�ƁI74�Ζ��B���܂Ō��C�œ�����̂��A������S�z���Ă����̎��ɂ͂��̐���������Ă���̂Ŏd�����Ȃ��B�~�c�w�O�r���n���������X�̓_���W�����A���[�a���g�C���ɍs��������A��Ȃ��E�E�E20���قǑ҂������_�ŒT���J�n�B40���߂����i�K�ő��q�͌x�����Ɂu�g�C���ɓ|�ꂽ�l�͂��Ȃ����v�܂��e���r�J�����Ȃǂ������茩������ǁA������Ȃ��B�X�}�z�����z���u�����ςȂ��Ȃ̂ŘA���͕t���ʂ��A����ɋA�邱�Ƃ��ł��Ȃ��͂��B�ꎞ�Ԍo���Ē��߂āA������JR�k�V�n�w�����Ɍ���������A�����ő҂��Ă���܂����E�E�E�����Ă��܂��āA�X�̖��O���m�炸�A�����Ƒ҂��Ă��������B�j�āA�̗�₵���B�����̑̏d��68.3kg+800g�����ŋߐ��N�̍ō��l�X�V�A�{���͂�������b���Č��炵�܂��傤�B
�����H�ޕs���������o���ɃX�[�p�[�Ɋ������A������ꌧ�Y�R�V�q�J���V��5kg5,280�~��4,980�~�̃G���h�������B3,000�~���u�����h�Ă����ׂ��Ă���܂����B�悤�₭�ʓI�ɂ͈��肵�����āA���i�����͏����̐��������܂��B�ĕs���ɐ��{�͂ق�܂ɖ��ז���ł�����B�H�א���̂��ǂ���������ƒ�͔ߎS�A�����͂����Ɠ{��������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�C���t���ɂȂ�Όi�C�͗ǂ��Ȃ�H����ȃV���v���ȏ���Ȃ��悤�ɁA�V���E�g�ڂɂ͉f��܂��B�Ȃ��������͂����Ɖ������Ă܂�����B��������ސ���͂����ƃ^�C�w���B�~���͂�����҂���܂��Ă���݂����B�A�����̂̒l������͊��҂ł���̂ł��傤���B
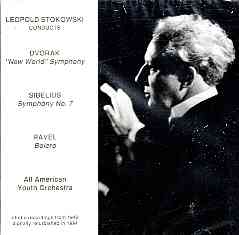 Dvora'k �����ȑ�9�ԃz�Z���u�V���E���v/Sibelius �����ȑ�7�ԃn����/Ravel �{�����`���I�|���h�E�X�g�R�t�X�L�[/�S�Đ��N�nj��y�c�i1940�N�j�E�E�E�I�[�f�B�V�����ɂėD�G�Ȏ�҂��W�A�S�Ă��R���T�[�g�c�@�[�ɉ��\�z�͐푈�̂��ߐ��N�Ő��N�œڍ������Ƃ̂��ƁB���̎��͂��f����^�����c���Ă���܂��B�����͂��Ȃ�ǍD�B�����������^�����c���Ă���A6��H�ł����u�V���E�v���ނ̉��ς��������������Ă��������B
�����Ղ���K���đ��߂̃e���|�ɃA���T���u���͐����āA���݂ɗh��Ă�肽������̕\��t����1�y���uAdagio-Allegro molto�v�̓A�c�����������Ղ�̐��i�́A����I���i���^�̓s���ł��傤���H�j���J��Ԃ��͂Ȃ��B�i8:41�j��2�y���uLargo�v�͂����Ղ�A��̉��������������V�~�W�~�̂��ĔZ���\��t���B�i1417�j��3�y���uMolto vivace�v�X�P���c�H�͏�M�I�Ɍ��C�����ς��B�i7:11�j��4�y���uAllegro con Fuoco�v�͉r�Q�ɗh��āA���X�g�̃A�b�`�F�������h���A�c���A�Ⴓ�����ς��f�[�n�[�ɖ��f�̉��t�ł����B�i11:26�j
Dvora'k �����ȑ�9�ԃz�Z���u�V���E���v/Sibelius �����ȑ�7�ԃn����/Ravel �{�����`���I�|���h�E�X�g�R�t�X�L�[/�S�Đ��N�nj��y�c�i1940�N�j�E�E�E�I�[�f�B�V�����ɂėD�G�Ȏ�҂��W�A�S�Ă��R���T�[�g�c�@�[�ɉ��\�z�͐푈�̂��ߐ��N�Ő��N�œڍ������Ƃ̂��ƁB���̎��͂��f����^�����c���Ă���܂��B�����͂��Ȃ�ǍD�B�����������^�����c���Ă���A6��H�ł����u�V���E�v���ނ̉��ς��������������Ă��������B
�����Ղ���K���đ��߂̃e���|�ɃA���T���u���͐����āA���݂ɗh��Ă�肽������̕\��t����1�y���uAdagio-Allegro molto�v�̓A�c�����������Ղ�̐��i�́A����I���i���^�̓s���ł��傤���H�j���J��Ԃ��͂Ȃ��B�i8:41�j��2�y���uLargo�v�͂����Ղ�A��̉��������������V�~�W�~�̂��ĔZ���\��t���B�i1417�j��3�y���uMolto vivace�v�X�P���c�H�͏�M�I�Ɍ��C�����ς��B�i7:11�j��4�y���uAllegro con Fuoco�v�͉r�Q�ɗh��āA���X�g�̃A�b�`�F�������h���A�c���A�Ⴓ�����ς��f�[�n�[�ɖ��f�̉��t�ł����B�i11:26�j
�����Ȑ�i�F����������Sibelius�͒P��y�͎��݂Ȍ��z�ȁB����n����I�Ƃ���ɔR����悤�ȍ����̐��i�́BSibelius�ɂ��Ă͏��X�����p���t���ɉ߂��邩���B�i21:42�j�{�����͑f���C�Ȃ����m�ȃ��Y��������ŁA���Ȃ葬�߂̃C���E�e���|�B�`���̃t���[�g�擪�ɃI�[�P�X�g���͗D�G�����ǁA�܂�ŌR���s�i�ȕ��ł����B�i12�F05�j
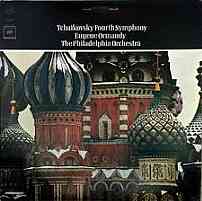 Tchaikovsky �X�����s�i���i1964�N�j/�����ȑ�4�ԃw�Z���i1963�N�j�`���[�W���E�I�[�}���f�B/�t�B���f���t�B�A�nj��y�c�E�E�E2024�N7��HDD���߉ގ������_�@��Tchaikovsky����������Ē����Ă���܂��BEugene Ormandy�i1899�1985�^�嗘�����ė����j�͓��{�ł͂����ƌy������Ă�������ǁA21���I�ɐ����c��ׂ����h�ȋL�^���c�����Ǝv���܂��B�X�����s�i����3�̃Z���r�A���w�{�鐭���V�A���́u�_��A�c�����肽�܂��v�i�变�ȁu1812�N�v�ɂ��o���j�����p�����E�s�Ɉ����I�ȍ�i�B�`���̌��ɂ�鑒���s�i�Ȃ́A�₪�ċ��ǂ��P�������y��I���̑N�x�A�p���[�Ɉ�ꂽ���݂ցB�I�[�P�X�g���̋Z�ʂ�����Ȃ���������āA�ǂ̃p�[�g������Ȃ���肢�B60�N�o���Ă��V�N�ȋ��������\�ł��܂����B�i10:48�j
Tchaikovsky �X�����s�i���i1964�N�j/�����ȑ�4�ԃw�Z���i1963�N�j�`���[�W���E�I�[�}���f�B/�t�B���f���t�B�A�nj��y�c�E�E�E2024�N7��HDD���߉ގ������_�@��Tchaikovsky����������Ē����Ă���܂��BEugene Ormandy�i1899�1985�^�嗘�����ė����j�͓��{�ł͂����ƌy������Ă�������ǁA21���I�ɐ����c��ׂ����h�ȋL�^���c�����Ǝv���܂��B�X�����s�i����3�̃Z���r�A���w�{�鐭���V�A���́u�_��A�c�����肽�܂��v�i�变�ȁu1812�N�v�ɂ��o���j�����p�����E�s�Ɉ����I�ȍ�i�B�`���̌��ɂ�鑒���s�i�Ȃ́A�₪�ċ��ǂ��P�������y��I���̑N�x�A�p���[�Ɉ�ꂽ���݂ցB�I�[�P�X�g���̋Z�ʂ�����Ȃ���������āA�ǂ̃p�[�g������Ȃ���肢�B60�N�o���Ă��V�N�ȋ��������\�ł��܂����B�i10:48�j
�����ȑ�4�ԃw�Z���������͌��𐅏��B��1�y���uAndante sostenuto - Moderato con anima - Moderato assai, quasi Andante - Allegro vivo�v�`���̃z�����ƃt�@�S�b�g�ɂ��u�^���̓��@�v���P���������ǂ��Ăэ���Ō��I�A���ς�炸���̕ӂ�u���ȋ����͐�D���B�₪�Č��ɂ��T���Ƃ�����1��肪�I�X�Ɖ̂��āA���̕ӂ�߉̑f�����A�]�T�̐���グ�ɍ��ꂢ�����܂��B�������I�������J�D�Ƃ͐F���F���Ⴄ�p���t���ȋ��ǂ̓o���o���S�J�A�؊ǂ��V�~�W�~��肢�B�i19:30�j��2�y���uAndantino in modo di canzona - Piu mosso�v�I�[�{�G�ɂ��V���v���ɐȂ����ɓ�����A����͖��f�̌��Ɉ����p����Ĉ������܂�܂��B�₪�Ė��邢���܂�ւƐ������āA�₪�ė͂������Đ�捂Ɏ���������\���̏�肳�A�����Ղ�Ƃ��������̈����͏�X�ł��傤�B�i10:06�j��3�y���uScherzo: Pizzicato ostinato. Allegro - Meno mosso�v���͏I�n�s�`�J�[�g�ɏI�~����V�˂̋Z�B�s�^���Əc���̍������A���T���u���A����A�\��̕ω����ꗬ�̃I�[�P�X�g���̏B�g���I�̖؊ǂ��͂����肭������A���ǂ̍s�i�Ȃ��y���ɐ���オ���āA�₪�ĐÂ��Ɏ������āE�E�E�i5:58�j��4�y���uFinale: Allegro con fuoco�v���ǁ{�Ŋy��唚������Ȏn�܂�͑O�y�͂Ƃ̑Δ�����ʓI�B�t�B���f���t�B�A�̉ؗ�ȃT�E���h�S�J�͂��}���߂ȃe���|�ɐi�݂܂��B�킩��₷���������Ă͕Ԃ��J��Ԃ��A�₪�āu�^���̓��@�v����A���A�I�[�P�X�g���͖���ăf�[�n�[�ȃT�E���h�ɃE�L�E�L�Ɠ˂��i�݂܂����B�i9:57�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�ΐ쌧�ɂđ�J�̓��ʌx��A6,500�˂���d�Ƃ��B�]���҂�s���s�����o�Ă���悤�ł��B�R�`���ʂ̐V�������~�܂��������B������锼��菬�J�͗l�A�{����肿����҂�C���͗��������Ƃ̗\���M���܂��傤�B����͒�����ҏ��p���A�A�����Ė���̒��͈���������낵���Ȃ��B��⓪�ɂ������ĕۗ�܂��I�f�R�Ɋ����Đ��܂����B���̂܂ܓ���A���Q����ł��d�����Ȃ��̂ʼn䗬�X�g���b�`���s�AYouTube�G�A���r�N�X�̓I�[�\�h�b�N�X��15�����{�B�ӂ������Ďs���̈�قɏo�|��������ǁA������Y��ċg���̂݁A�G�A���o�C�N�͒f�O���܂����B�i120�~�̎��̋@�����E�C���o�Ȃ��j�c�O�Ȃ���u�b���Ď����I�v���݂͐��������̒��ǂ���p�����B�̏d��67.5kg�ς�炸�B�{���A��Ɛg���̑��q���A�~�c�ŗ��������܂��B
�[�Z���s�ɂē��{�l10�̂��ǂ����h�E���ꂽ�ߎS�Ȏ����A�����F�D�̊�]�Əے��ƂȂ�ׂ��n�[�t�ł��������ƁA�E�C�͐��S�ȍs�ׂł��������Ƃ�m��܂����B�C���͈ÞȂƂ��Ă���܂��B�����ł͕�SNS�����A�����ɂ́u��ʓI�Ȏ����v�Ƃ����̂́A�ގ��̎����̊g�U��h�������̂ƁA�����̎����̈�����F�߂Ȃ����߂ł��傤�B��������⊴����ɗ��p�A�l�������݂ɃR���g���[���ł���Ƃ̍l�������{�I�Ɍ���Ă���B�E�͌n�����lYouTuber�ł���Poo����ً}���e�u�[�Z���̎����ɂ��āA�ݓ������l�̖{�����Ă��������v
�ނ͖�x���ɃX�[�p�[�ɔ����ɏo�|���ĕ|���v���������Ƃ̂��ƁB�c�O�ȓ��{�l�͂���̂ł��ˁB�����l�ɑ��錵�����ӌ��͂����ɂ��Ă���I�Ƃ̌Ăт����ɍK���A�ǐS�I�ȃR�����g���葱���Ă���܂��B2���قǁuCM�͓�����ł��ˁv�Ƃ̗��₩�Ȑ��͂���܂����B���ؐl�����a���͂������Ƃɂ������Ȃ����낤���ǁA����͏d��Č��B�ƂĂ��Ȃ��傫�ȃ}�C�i�X�ł���B
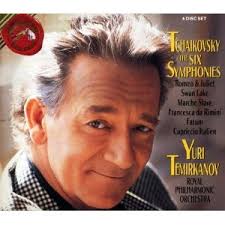 Tchaikovsky �����ȑ�1�ԃg�Z���u�~�̓��̌��z�v/�o���G�g�ȁu�����̌��v�`���[���E�e�~���J�[�m�t/���C�����E�t�B���i1993�N�j�E�E�E2015�N�ӂ�ɂ������璮�����L�^���c���Ă���܂����BYuri Temirkanov�i1938-2023�I�����j��1988�N���炨���炭�������A�����T���N�g�E�y�e���u���O�E�t�B���̉��y�ē߂��͂��B���C�����E�t�B����1992-1998���y�ēݔC�A���������D���Ȏw���҂ł����B�����ȑ�1�Ԃ͒m���x�ɔ䂵�āA�Ƃ��Ă��e���݂₷�����[�J���Ȑ��������Ղ�Ȗ��ȁB�ʓr�T���N�g�E�y�e���u���O�E�t�B���Ƃ̑�S/�T/�U�Ԙ^�������邯��ǁA�����烍�C�����E�t�B���Ƃ̘^�����Ȃ��Ȃ��̋��ǃp���[���ւ��āA������O�����ǘI�������h���I�D�L���T�E���h�ɔB�ł�������Ȃ��Ȃ��̔��͂ł����B��1�y���u�~�̗��̌��z�iAllegro tranquillo - Poco piu animato�j�v�₽����i�F������A�����������w���������y���Ȏn�܂�B�i12:14�j��2�y���u�A�C�ȓy�n�A���̓y�n�iAdagio cantabile ma non tanto - Pochissimo piu mosso�j�v�σz���������ǁA�㉹���t�������@�C�I��������捂Ɏ₵���n�܂�B�₪�ăI�[�{�G�A�`�F���A�z��������̗̉w�I�ɗD�����Ȃ��������V�~�W�~�̂��āA���̕ӂ�Tchaikovsky�̃����f�B�E���[�J�[�̍˔\���@�B�I�[�P�X�g���͐����ȋ����������܂����B�N���C�}�b�N�X�̃z�����̍����ȋ��тɂ�Ⴢ�܂���B�i12:25�j��3�y���uScherzo. Allegro scherzando giocoso�v���̃X�P���c�H�ɂ͕���͂Ȃ��悤�ł��ˁB�ł��ׂ����f���P�[�g�ȉ��^�͂�����҂�Ȃ��A�r������~�̎₵���i�F��A�z�����܂��B���ԕ��̃����c�͒g�����A�D��Ȃ��́B�����Ղ薣�f�̊Â������ł���B�i8:05�j��4�y���uFinale. Andante lugubre - Allegro moderato - Allegro maestoso - Allegro vivo - Piu animato�v�ßT�Ȏn�܂肩��₪�Ă����Ղ胍�[�J���ȘI�������킩��₷�����w�̐������l�X�Ɖ̂��E�E�E����͖��邭���C�悭�������āA�܂�Őᒆ��n��������������悤�Ȏ������������āA���ǂ��Ŋy����m���m���ɔ��͂͏[���B�₪�ď��t���Č�����āA����͋P�������������Ė��邢�t�B�i�[���ɂȂ��ꍞ�݂܂����B�i11:38�j
Tchaikovsky �����ȑ�1�ԃg�Z���u�~�̓��̌��z�v/�o���G�g�ȁu�����̌��v�`���[���E�e�~���J�[�m�t/���C�����E�t�B���i1993�N�j�E�E�E2015�N�ӂ�ɂ������璮�����L�^���c���Ă���܂����BYuri Temirkanov�i1938-2023�I�����j��1988�N���炨���炭�������A�����T���N�g�E�y�e���u���O�E�t�B���̉��y�ē߂��͂��B���C�����E�t�B����1992-1998���y�ēݔC�A���������D���Ȏw���҂ł����B�����ȑ�1�Ԃ͒m���x�ɔ䂵�āA�Ƃ��Ă��e���݂₷�����[�J���Ȑ��������Ղ�Ȗ��ȁB�ʓr�T���N�g�E�y�e���u���O�E�t�B���Ƃ̑�S/�T/�U�Ԙ^�������邯��ǁA�����烍�C�����E�t�B���Ƃ̘^�����Ȃ��Ȃ��̋��ǃp���[���ւ��āA������O�����ǘI�������h���I�D�L���T�E���h�ɔB�ł�������Ȃ��Ȃ��̔��͂ł����B��1�y���u�~�̗��̌��z�iAllegro tranquillo - Poco piu animato�j�v�₽����i�F������A�����������w���������y���Ȏn�܂�B�i12:14�j��2�y���u�A�C�ȓy�n�A���̓y�n�iAdagio cantabile ma non tanto - Pochissimo piu mosso�j�v�σz���������ǁA�㉹���t�������@�C�I��������捂Ɏ₵���n�܂�B�₪�ăI�[�{�G�A�`�F���A�z��������̗̉w�I�ɗD�����Ȃ��������V�~�W�~�̂��āA���̕ӂ�Tchaikovsky�̃����f�B�E���[�J�[�̍˔\���@�B�I�[�P�X�g���͐����ȋ����������܂����B�N���C�}�b�N�X�̃z�����̍����ȋ��тɂ�Ⴢ�܂���B�i12:25�j��3�y���uScherzo. Allegro scherzando giocoso�v���̃X�P���c�H�ɂ͕���͂Ȃ��悤�ł��ˁB�ł��ׂ����f���P�[�g�ȉ��^�͂�����҂�Ȃ��A�r������~�̎₵���i�F��A�z�����܂��B���ԕ��̃����c�͒g�����A�D��Ȃ��́B�����Ղ薣�f�̊Â������ł���B�i8:05�j��4�y���uFinale. Andante lugubre - Allegro moderato - Allegro maestoso - Allegro vivo - Piu animato�v�ßT�Ȏn�܂肩��₪�Ă����Ղ胍�[�J���ȘI�������킩��₷�����w�̐������l�X�Ɖ̂��E�E�E����͖��邭���C�悭�������āA�܂�Őᒆ��n��������������悤�Ȏ������������āA���ǂ��Ŋy����m���m���ɔ��͂͏[���B�₪�ď��t���Č�����āA����͋P�������������Ė��邢�t�B�i�[���ɂȂ��ꍞ�݂܂����B�i11:38�j
�N���m���Ă����u�����̌v�BTchaikovsky�̃o���G���y�͑S�Ȓ����ʂ��̂͂Ȃ��Ȃ���A���̂��炢�̑g�Ȃ��K�Ȓ����ł��傤�B���I�ȊÂ��Ȃ�����������������Ղ芬�\�������܂����B�i3:03-7:04-1:35-7:15-3:06�j
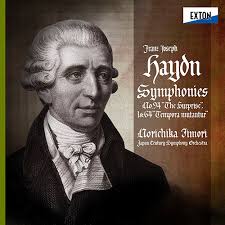 Haydn �����ȑ�94�ԃg�����i2019�N�j/�����ȑ�1�ԃj����/�����ȑ�64�ԃC�����u���̈ڂ낢�v�i2020�N�j�`�ѐX�͐e/���{�Z���`�����[�����y�c�E�E�E�V���t�H�j�[�E�z�[���͑f���炵���c���ł��ˁB���_�[���y�킾���ǁA���̓m���E���B�u���[�g�A�����������݂̂��鋿���A�y���ȃ��Y���Ɠ����ȃT�E���h���f���炵��Haydn�����\�����Ă��������܂��B�R�`�����y�c��Mozart�ɂ�����������ǁA��������̃Z���`�����[�����y�c�͗��h�ȉ��t�ł���B�������{�̃I�[�P�X�g���]�X�Ȃ�ĖډB�����Ă���킩��Ȃ��B
Haydn �����ȑ�94�ԃg�����i2019�N�j/�����ȑ�1�ԃj����/�����ȑ�64�ԃC�����u���̈ڂ낢�v�i2020�N�j�`�ѐX�͐e/���{�Z���`�����[�����y�c�E�E�E�V���t�H�j�[�E�z�[���͑f���炵���c���ł��ˁB���_�[���y�킾���ǁA���̓m���E���B�u���[�g�A�����������݂̂��鋿���A�y���ȃ��Y���Ɠ����ȃT�E���h���f���炵��Haydn�����\�����Ă��������܂��B�R�`�����y�c��Mozart�ɂ�����������ǁA��������̃Z���`�����[�����y�c�͗��h�ȉ��t�ł���B�������{�̃I�[�P�X�g���]�X�Ȃ�ĖډB�����Ă���킩��Ȃ��B
�������u�����v�͌ÓT�I��ǕҐ��A�N�����l�b�g���e�B���p�j�������ē��X������1�y���uAdagio - Vivace assai�v����͋�����������Ƃ����c�̂��鋿���Ƀ��B���B�b�h�B�؊ǂ̕\������c��ɂ����L���ł����B�i8:75�j��2�y���uAndante�v�͒N�ł��m���Ă���V���v���ȕϑt�ȁB�̂т̂тƃp���[�����������郁���n���A�L���̂���ꌂ���u�����v�̗R���A�r�����@�C�I�����E�\���ɂ�鎩�݂ȃJ�f���c�@���o�ꂵ�܂����B�i6:29�j��3�y���uMenuetto. Allegro molto�v�͍����ȃ��Y��������ŔM�C�Ɉ��܂��B�i4:28�j��4�y���uFinale. Allegro di molto�v���͋������߂�����B�i4:13�j
�����ȑ�1�ԃj�����̓t���[�g���e�B���p�j�������3�y�͐��B��1�y���uPresto�v���猳�C�����ς��ɐ��ꐰ��Ƃ����\��A�ӊO�Ƒ傫�ȍ앗�ł���A���t�ł����B�i5:08�j��2�y���uAndante�v�m���r���W�X�Ƃ������̂݁A�V���v�������ljA�e�̂���ɏ��y�́B�i5:57�j��3�y���uPresto�v�D��ȕ���ɋ}���ʃt�B�i�[�������킢�[�����́B�i2:19�j
�����ȑ�64�ԃC�����̕Ґ�����1�ԂƓ����B����̓p�[�g���ɂ��̌��t����������B��1�y���uAllegro con spirito�v�͗D��ɗ]�T��Y�킹��������n�܂�B�r�������~�܂镗������킢�[�����́B�i9:05�j��2�y���uLargo�v���݂��݂Ƃ�������A�����Ղ�[���̂���ۓI�Ȋɏ��y�́B�i5:55�j��3�y���uMenuetto-Allegro-Trio�v�͂��Ⴍ�肠����悤�Ȓe�ޕ����i2:27�j��������4�y���uPresto�v�͌��C�����ς��A�e�L�ɋ삯�����܂����B�i3:04�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�T���ɂ͋C���͗��������E�E�E�Ƃ̗\��͂�����҂�摗�肳��Ă���悤�ŁA���������Ȗҏ��B�{���͂��C���͉������Ė锼�ɂ͉J������悤�ł��B���k�n���ł͑�J�\�S�z�ł��B�O������蔕��ȏ�����߂����������A���ɖ閰�肪�����C�����D��Ȃ��B������̂������āA�X�g���b�`��YouTube�G�A���r�N�X���f�O�A�G�A�R�������ČߑO������Q����ł��܂��܂����B���ł���Ƒ���l�͖{�����c�ɂɋA�ȁA���k����̎O����������ł��B�V���������������̏Ί炪�͂��܂����B������̓_�E�����Ă���J�͐�D���A��C��51-51�B���A�Â��b�����̓��{�Ɉ�̌���������v���B�����͂��̃^�C�~���O�œ��{�̐��Y���A���ĊJ�̏��A���R�ł��傤�B
JR�Z���w�͂�����Ƃ����V���b�s���O�Z���^�[�ɂȂ��Ă��āA�����X�[�p�[��t�@�[�X�g�t�[�h�X�A���i����P�[�L������A100�~�V���b�v��V�}�����A��㉤��������܂��B�X�e�L�ȃP�[�L������A�l�C�̃`���R���[�g������A�n���V�܂��L�q�X�ׂ̗ɘa�َq�����E�E�E���N�قǑO�ɕX�B�l�ʂ������������Ă���ꏊ�Ȃ̂Ɂu���̂��Ɓv�����炸�A�X�����܂܁B�w�Ɍ��炸�A�ǂ��ł����������ǂ��X�̓���ւ��A���s��p��͂����ē�����O�A�ł����̂܂��X�ɕX���Ă����Ď��Ă��܂��͖̂��A�Ƃ��������ꂪ����̐����Ȃ̂��B������l�X���܂��āA�S���ꗥ�ȃ`�F�[���X����ɂȂ�̂����C�Ȃ��B
�N�ɐ��x�K�₷�鋞�s�̒��S�X�͊w�����ォ��̓���݁A�������ǂ�ǂ�S���`�F�[���X�������āA�܁A�Ռp�����Ƃ�����̕ϑJ�Ƃ����낢�뗝�R�͂��邯��ǁA���Љ���ǂ������Ɖ]�����A�n�惍�[�J���Ȍ�����ɂ��������̂ł��B�����̑̏d��67.5kg+300g�I���Q�����肾�����̂Ŏd�����Ȃ��B
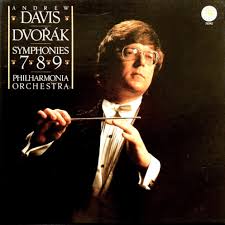 Dvora'k �����ȑ�9�ԃz�Z���u�V���E���v�i�A���h���[�E�f�C���B�X/�t�B���n�[���j�A�nj��y�c/1979�N�j/���y�Z���i�[�f �z�����i���h���t�E�P���y/�~�����w���E�t�B��/1968�N�j�E�E�EAndrew Davis�i1944�2024�p���j�{�N�����A���N80�A���N�O��蔒���a�������炵���B�c�O��Ȃ��A��������ł���N��ł���A�w���҂�������B����͂��傤�ǃf�B�W�^���^���Ɉڍs����Ⴂ���^�������S�W�^�����B�X�������Ȃ��S�Ș^�����Ă���܂��B�قƂ�ǘb��ɂȂ�Ȃ���������ǁA���I�t�B�}�C�N�A�����Ƃ�Ƃ��Ďc���L���ȉ����ɃI�[�\�h�b�N�X�ȉ������t�ł����B��1�y���uAdagio-Allegro molt�v�͑u�₩�ȃt�B���n�[���j�A�nj��y�c�̃T�E���h���������āA��̖閾���O�̂悤�ȃ��N���N������n�܂��āA�����ς�Ƃ����\���ɂ����Ƃ萐�X�����T�E���h�ł����B���ӓI�Ȑ���\���Ƃ͖����ȕ\���B���J��Ԃ��Ȃ��B�i9:42�j��2�y���uLargo�v�N�ł��m���Ă�������͗}���������āA���������C���O���b�V���E�z�����A�₵���ȕ�����Ղ�Y���ɏ��y�́B�z�����̉��F���W�~�߂ɋ����āA�N���C�}�b�N�X�̑�1�y�͎��Ƃ̑Δ�����݂��ƁB�i12:26�j��3�y���uScherzo,Molt vivace�v���₩�ȃX�P���c�H���h���I�Ȍ����������������ʁA�K�x�ȗ͊������������ăf�[�n�[�ȕ����͉������́B����ł����ǂ̑s��ȋ��������̓I�[�P�X�g���̎��͂��܂��B�i7:58�j��4�y���uAllegro con fuoco�v�t�B�i�[���͌��ɂ��H���L�肰�Ƀp���t���ȏ��t����z�����ƃg�����y�b�g�ɂ��V���v���ȑ�1��肪�J�b�R�ǂ��Ƃ���B�������Ƌؓ����Ȑ�������������ǁA�I�[�P�X�g���̋����͂����܂Ń}�C���h�A����͎ア�Ƃ͊��������Ȃ��B�������ǂ��c���L���ɐ[�݂̂��鋿�������܂��B���X�g�����̑唚����]�ޕ��ɂ͏��X�y�ʂȊ��������m��܂���B�����ɂ͏[���s��ȋP���Ǝ~�߂܂����B�i11:21�j
Dvora'k �����ȑ�9�ԃz�Z���u�V���E���v�i�A���h���[�E�f�C���B�X/�t�B���n�[���j�A�nj��y�c/1979�N�j/���y�Z���i�[�f �z�����i���h���t�E�P���y/�~�����w���E�t�B��/1968�N�j�E�E�EAndrew Davis�i1944�2024�p���j�{�N�����A���N80�A���N�O��蔒���a�������炵���B�c�O��Ȃ��A��������ł���N��ł���A�w���҂�������B����͂��傤�ǃf�B�W�^���^���Ɉڍs����Ⴂ���^�������S�W�^�����B�X�������Ȃ��S�Ș^�����Ă���܂��B�قƂ�ǘb��ɂȂ�Ȃ���������ǁA���I�t�B�}�C�N�A�����Ƃ�Ƃ��Ďc���L���ȉ����ɃI�[�\�h�b�N�X�ȉ������t�ł����B��1�y���uAdagio-Allegro molt�v�͑u�₩�ȃt�B���n�[���j�A�nj��y�c�̃T�E���h���������āA��̖閾���O�̂悤�ȃ��N���N������n�܂��āA�����ς�Ƃ����\���ɂ����Ƃ萐�X�����T�E���h�ł����B���ӓI�Ȑ���\���Ƃ͖����ȕ\���B���J��Ԃ��Ȃ��B�i9:42�j��2�y���uLargo�v�N�ł��m���Ă�������͗}���������āA���������C���O���b�V���E�z�����A�₵���ȕ�����Ղ�Y���ɏ��y�́B�z�����̉��F���W�~�߂ɋ����āA�N���C�}�b�N�X�̑�1�y�͎��Ƃ̑Δ�����݂��ƁB�i12:26�j��3�y���uScherzo,Molt vivace�v���₩�ȃX�P���c�H���h���I�Ȍ����������������ʁA�K�x�ȗ͊������������ăf�[�n�[�ȕ����͉������́B����ł����ǂ̑s��ȋ��������̓I�[�P�X�g���̎��͂��܂��B�i7:58�j��4�y���uAllegro con fuoco�v�t�B�i�[���͌��ɂ��H���L�肰�Ƀp���t���ȏ��t����z�����ƃg�����y�b�g�ɂ��V���v���ȑ�1��肪�J�b�R�ǂ��Ƃ���B�������Ƌؓ����Ȑ�������������ǁA�I�[�P�X�g���̋����͂����܂Ń}�C���h�A����͎ア�Ƃ͊��������Ȃ��B�������ǂ��c���L���ɐ[�݂̂��鋿�������܂��B���X�g�����̑唚����]�ޕ��ɂ͏��X�y�ʂȊ��������m��܂���B�����ɂ͏[���s��ȋP���Ǝ~�߂܂����B�i11:21�j
���y�Z���i�[�f�͂��������t�B���E�A�b�v�Ɏg���郋�h���t�E�P���y�̘^���B������u�₩�Ƀj���A���X�ɕx��������i�A���t�ł����B�A���h���[�E�f�B���B�X�Ƒ����Ĉ�a���͂���܂���B������̂ق����I�[�P�X�g�̉A�e��d�S���Ⴂ�B�i4:31-6:54-5:55-5:59-6:04�j
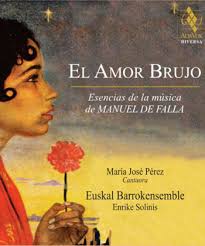 �`�����y�i�I�����_�̉́j�V�G�K�̃^�����^/de Falla �̌��u���͖��p�t�v����i�Y�܂������̉�/�Ղ�̗x��/���@�̗�/�p���g�}�C��/���ˉ̉�/���̋Y��̗x��/���ɉ��t������j/de Falla �閾���̏�/Rodrigo �A�����t�F�X���t�Ȃ���iAllegro/Andante�j/D.Scarlatti �\�i�^ �j�Z��K.32/�\�i�^ �j�Z��K.141/Dimitrie Cantemir (1673-1723)�x�X�e�j�K���̏�i/Tarrega �A���u��z�ȁ`�}���A�E�z�Z�E�y���X�i�́j/�G�����P�E�\���j�X(g)/�G�E�X�J���E�o���b�N�A���T���u���E�E�E�����܂����BჂ�܂����B�ŏ��̓`�����y���Ă����A���Ƃ͒m���Ă����������A���ꂪ�h�E�V���E�g���z������Ƃ���̐��lj�y���ȃ��Y���A�h�X�Ɛ߉̌����������A�����Ղ�D�L���t�������R�E�M�^�[����Z�I�ɖ��t������Ă��̐����Z���I���Y������������ς���āA�����Ȉ��D�́u�A�����t�F�X�v���܂�ŃI���W�i����i�AScarlatti�ӂ肤�����蒮���Ă���ƌ��̐������v���o���܂���B�o���b�N�A���T���u���Ȃ�Ă������O�����҂���ƁA�܂������قȂ郍�[�J���Ȑ��E���L�����Ă���܂��B
�`�����y�i�I�����_�̉́j�V�G�K�̃^�����^/de Falla �̌��u���͖��p�t�v����i�Y�܂������̉�/�Ղ�̗x��/���@�̗�/�p���g�}�C��/���ˉ̉�/���̋Y��̗x��/���ɉ��t������j/de Falla �閾���̏�/Rodrigo �A�����t�F�X���t�Ȃ���iAllegro/Andante�j/D.Scarlatti �\�i�^ �j�Z��K.32/�\�i�^ �j�Z��K.141/Dimitrie Cantemir (1673-1723)�x�X�e�j�K���̏�i/Tarrega �A���u��z�ȁ`�}���A�E�z�Z�E�y���X�i�́j/�G�����P�E�\���j�X(g)/�G�E�X�J���E�o���b�N�A���T���u���E�E�E�����܂����BჂ�܂����B�ŏ��̓`�����y���Ă����A���Ƃ͒m���Ă����������A���ꂪ�h�E�V���E�g���z������Ƃ���̐��lj�y���ȃ��Y���A�h�X�Ɛ߉̌����������A�����Ղ�D�L���t�������R�E�M�^�[����Z�I�ɖ��t������Ă��̐����Z���I���Y������������ς���āA�����Ȉ��D�́u�A�����t�F�X�v���܂�ŃI���W�i����i�AScarlatti�ӂ肤�����蒮���Ă���ƌ��̐������v���o���܂���B�o���b�N�A���T���u���Ȃ�Ă������O�����҂���ƁA�܂������قȂ郍�[�J���Ȑ��E���L�����Ă���܂��B
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
���ɂ��܂��Č������c���A������҂�C�������������̂͏T���Ƃ̂��ƁB����͔�r�I�悭����āA����Ԃ̐���A�X�g���b�`�A������YouTube�G�A���r�N�X��15���ق���������AMIZI�̎w���ɂ͂����艞���������肠���āA�������B������V�����[�ŗ����Ă���������A�����d���s���̈�قցB��A�����o�[�ɍ��g���[�j���O���[���ł͋g���}�V�����͂Ƃ��Ƃ��܂���ł����B�A�肿����҂�H�ޔ��������ɃX�[�p�[�Ɋ�����玠�ꌧ�Y�R�V�q�J��5kg�V��5,280�~��A�������ǂ�������G���h�ɐς�ł���܂����B�Ɩ��X�[�p�[�Ɋ�������[�a�ɂ��ƁA�����ɂ��Ă͓��ׂ����Ƃ̂��ƁB���X�ɏo����Ă���悤�ł��B���A�G�A�R������������|�����Q�{���y�q�����Ă���3����莕��҂ցB���㉜���e�m�炸�̈�a���͑����āA�����ł͍��͑��v�A�����Ȃ��đO��Ɠ����y���������Ƃ̂��ƁB���ݍ��킹�I�ɕ��ׂ��|�����Ă���̂Ǝ��u���V���͂��ɂ��������B�O�����̉��ǎ~�߂�������ėl�q���A�A��ɑ��c�ݎU�ƈꏏ�Ƀ����_�~�����Ă݂܂����B���ԃu���V�̎g�p�p�x�𑝂₵�āA�X�ɂ�������u���b�V���O���ӎ����܂��傤�B�����̑̏d��67.1kg��700g�B
�\��ʂ蕺�Ɍ��c��Œm���s�M�C�ĉ��i������O�Ȃ̂ŋ����Ȃ�/���̌オ���j�B������Ȃɂ��A�[�Z���s�ɂē��{�l10�̂��ǂ����h�E����鎖�����ߎS�B���e�̈����݂͑z���ł��ʂقǁB�����͗��ɑ��Đ��X��X�ɔ��f�A�Ή����悤�ƐS�|���Ă��邯��ǁA����͌��ꓹ�f�Ƀ��o���B�����炭���{�̐e���h�̕��X���G�ɉ܂�����B����������݂̘A����烂̂��ǂ��Ɍ�������s�A��������̓��{��Ƃ̓P�ނ͉�������A�ό��q�������������邱�Ƃł��傤�B�����炭�͍ݗ������l�̑命���͂܂Ƃ��ȕ��A���W�Ȕ�排������Ȃ��悤�ɓ��{�l�̗ǎ����M�������B
���o�m���Ń|�P�x������8�l���S�A2,800�l�ȏ����̕A�����ɂ���ɕʂ̒ʐM�@���i�g�����V�[�o�[�j�����������Ƃ̂��ƁB���ꂪ�����ς�킩��Ȃ��B�ڍח����ł��܂���B�q�Y�{���ƈȐF��̊m���炵�����ǁA�ǂ�����ă|�P�x���i�I�j�Ȃ��̂����j�ł���̂��A���̕ӂ�̏���T���ƁE�E�E�}���E�G�A��p���ăo�b�e���[��������Z�p������炵���B���ӓI�ɑ��荞�܂ꂽ�̂ł��傤���B��p���H���{�̕��i������������i�j�Z���m�̉\�����j���߂ėv��ʊm����������ɔ��ŗ��ʂ悤�F��܂��傤�B������A�z���̂͂邩����s���U���̃e�N�j�b�N���L�����āA�ی��Ȃ������݂̘A���������Ă���܂��B
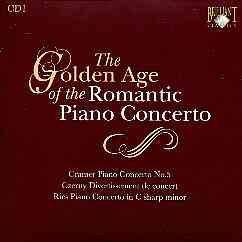 Cramaer�i1771-1858�ƈ큨�p���j �s�A�m���t�ȑ�5�ԃn�Z���i���ǖ��q(p)/�s�G�[���E�J�I/���N�Z���u���N�����nj��y�c/1974�N�j/Czerny�i1791-1857�ґ����j ���t��p�f�B���F���e�B�����g ��i204�i�}�C�P���E�|���e�B (p)/�p�E���E�A���Q���[/�v�t�H���c�n�C���쐼�h�C�c�����nj��y�c/1978�N�j/Ries�i1784-1838�ƈ�j �s�A�m���t�� �d�n�Z���i�}���A�E���b�^�E�A�[(p)/�A���C�X�E�X�v�����K�[/�x�����������y�c1972�N�j�E�E�E�m��ꂴ���Ȃ���W�߂�The Golden Age of the Romantic Piano Concerto���A����͉�������VOX����o�Ă����^���B�����̉��y�q�������f����ΐ̓���݂���A�����͈͂Ɏ����悤�ȍ�i���蒮���Ă��܂��āA�������L���邱�Ƃ͑�ȃm�[�~�\�ւ̎h���ł��BCramaer�̃n�Z�����t���͒O���Ȑ��������ĉ�����Beethoven���A����͎v��ʌy���Ȗ��Ȃł����B��1�y�́uAllegro maestoso�v�i14:25�j��2�y���uLarghetto�v�i6:46�j��3�y�́uRondo a L'hongaroise�v�i8:41�j���ǖ��q����̏ڍ��͒T���ʂ���ǁA�����ȃe�N�j�b�N�̞B�����̂Ȃ����́B�����{�ŗL����Czerny�̃f�B���F���e�B�����g�͎���Ɉ��Ă킩��₷���A�₩�ȕϑt�ȁH������҂�Chopin�����D�̃f���J�V�[��Y�킹�A�s�A�m�̈����͂��Ȃ藬��ɋZ�I�I�B�I�[�P�X�g���̔��t�A���@�C�I�����E�\���̗��ݍ������������B����Michael Ponti�i1937�2022���ė����j�̑N�₩�ȋZ�I�����\�ł��܂��B�i14:45�jRies��Beethoven�̒�q�A����������ĖY�ꋎ����悤�ȑʍ�ɔA�[���ɗ͋����������W�J����邯��ǁA���������H�x�����������y�c�i�����j�������Ԃ�Ƌ����������A�s�A�m���f���J�V�[�Ɍ����܂��B��1�y�́uAllegro maestoso�v�i14:50�j��2�y�́uLarghetto�v�i5:03�j��3�y�́uRondo,Allegretto�v�i10:36�j
Cramaer�i1771-1858�ƈ큨�p���j �s�A�m���t�ȑ�5�ԃn�Z���i���ǖ��q(p)/�s�G�[���E�J�I/���N�Z���u���N�����nj��y�c/1974�N�j/Czerny�i1791-1857�ґ����j ���t��p�f�B���F���e�B�����g ��i204�i�}�C�P���E�|���e�B (p)/�p�E���E�A���Q���[/�v�t�H���c�n�C���쐼�h�C�c�����nj��y�c/1978�N�j/Ries�i1784-1838�ƈ�j �s�A�m���t�� �d�n�Z���i�}���A�E���b�^�E�A�[(p)/�A���C�X�E�X�v�����K�[/�x�����������y�c1972�N�j�E�E�E�m��ꂴ���Ȃ���W�߂�The Golden Age of the Romantic Piano Concerto���A����͉�������VOX����o�Ă����^���B�����̉��y�q�������f����ΐ̓���݂���A�����͈͂Ɏ����悤�ȍ�i���蒮���Ă��܂��āA�������L���邱�Ƃ͑�ȃm�[�~�\�ւ̎h���ł��BCramaer�̃n�Z�����t���͒O���Ȑ��������ĉ�����Beethoven���A����͎v��ʌy���Ȗ��Ȃł����B��1�y�́uAllegro maestoso�v�i14:25�j��2�y���uLarghetto�v�i6:46�j��3�y�́uRondo a L'hongaroise�v�i8:41�j���ǖ��q����̏ڍ��͒T���ʂ���ǁA�����ȃe�N�j�b�N�̞B�����̂Ȃ����́B�����{�ŗL����Czerny�̃f�B���F���e�B�����g�͎���Ɉ��Ă킩��₷���A�₩�ȕϑt�ȁH������҂�Chopin�����D�̃f���J�V�[��Y�킹�A�s�A�m�̈����͂��Ȃ藬��ɋZ�I�I�B�I�[�P�X�g���̔��t�A���@�C�I�����E�\���̗��ݍ������������B����Michael Ponti�i1937�2022���ė����j�̑N�₩�ȋZ�I�����\�ł��܂��B�i14:45�jRies��Beethoven�̒�q�A����������ĖY�ꋎ����悤�ȑʍ�ɔA�[���ɗ͋����������W�J����邯��ǁA���������H�x�����������y�c�i�����j�������Ԃ�Ƌ����������A�s�A�m���f���J�V�[�Ɍ����܂��B��1�y�́uAllegro maestoso�v�i14:50�j��2�y�́uLarghetto�v�i5:03�j��3�y�́uRondo,Allegretto�v�i10:36�j
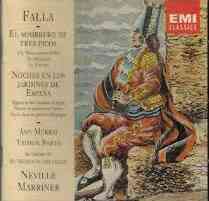 de Falla �o���G���y�u�O�p�X�q�v/�X�y�C���̒�̖�`�l���B���E�}���i�[/�A�J�f�~�[�E�I�u�E�Z���g�E�}�[�e�B���E�C���E�U�E�t�B�[���Y/�A���E�}���C(ms)/�c�B�����E�o���g(p)�i1992/93�N�j�E�E�E���t�̃J�X�^�l�b�g�Ə����\���������Ԃ�Ɖ������i�����̗x��(�t�@���[�J)�����l�j��s���s������������ǁA���Ƃ͗��Neville Marriner�i1924�2016�p���j�ɂ�閾���ȕ\���A�o�����X���o���Q�ȃ��Y�����������ė\�z�O�̍D���I���lj��Ƃ��D�L���Ƃ��Ƃ͂�����ƈႤ�悤�ȋC�����邯��ǁA���Q�ɏ�肢�I�[�P�X�g���̐������ꂽ�Z�ʂɂȂ�̕s���������܂���B��i�̊y�����A�����̔��������Y���������Ղ芬�\�B�i1:25-5:19-4:00-4:11-3:33-8:08-6:13-6:09�j�X�y�C���̒�̖��̓{�f�B�r���_�[�ł�����Tzimon Barto�i1963����ė����j�̒S���B����͓쉢�̔Z���ȕ�����Ղ�ɂ��Ȃ�A�c���A�m���m���̕\���ł����B�u�w�l�����[�t�F�ɂāv�i10:30)�u�͂邩�ȗx��v�i4:55�j�u�R���h�o�̎R�̒�ɂāv�i8:26�j�����͗ǍD�B
de Falla �o���G���y�u�O�p�X�q�v/�X�y�C���̒�̖�`�l���B���E�}���i�[/�A�J�f�~�[�E�I�u�E�Z���g�E�}�[�e�B���E�C���E�U�E�t�B�[���Y/�A���E�}���C(ms)/�c�B�����E�o���g(p)�i1992/93�N�j�E�E�E���t�̃J�X�^�l�b�g�Ə����\���������Ԃ�Ɖ������i�����̗x��(�t�@���[�J)�����l�j��s���s������������ǁA���Ƃ͗��Neville Marriner�i1924�2016�p���j�ɂ�閾���ȕ\���A�o�����X���o���Q�ȃ��Y�����������ė\�z�O�̍D���I���lj��Ƃ��D�L���Ƃ��Ƃ͂�����ƈႤ�悤�ȋC�����邯��ǁA���Q�ɏ�肢�I�[�P�X�g���̐������ꂽ�Z�ʂɂȂ�̕s���������܂���B��i�̊y�����A�����̔��������Y���������Ղ芬�\�B�i1:25-5:19-4:00-4:11-3:33-8:08-6:13-6:09�j�X�y�C���̒�̖��̓{�f�B�r���_�[�ł�����Tzimon Barto�i1963����ė����j�̒S���B����͓쉢�̔Z���ȕ�����Ղ�ɂ��Ȃ�A�c���A�m���m���̕\���ł����B�u�w�l�����[�t�F�ɂāv�i10:30)�u�͂邩�ȗx��v�i4:55�j�u�R���h�o�̎R�̒�ɂāv�i8:26�j�����͗ǍD�B
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
������Ɠۂ݉߂��āA���傤�Ǒ��c�ݎU����č���͈݂��������d�������B�H�~������܂���B���肪��⌑�ӊ��{�ߑO������̖ҏ��ɂ������肵�Ă���܂����B���̐���̎��A����ĒE�����Ԑݒ��1���ɁE�E�E����ł������Ɋ����̂ł��ˁB�X�g���b�`�Ƃ킸��4���قǂ�YouTube�G�A���r�N�X�͎��{�B6�����C�ɂȂ��Ă������㉜���͌y���������Ɛf�f����A�X�ɕ����������L�A�{���[���̗\������܂����B���Ƃ͖ҏ��ɂ�������B�����̑̏d��67.8kg��100g�A���Ȃ����Đg�������Ȃ����������ɂ�����҂茸��܂����B
�O���ۂ݂ɍs�����A���߂��̃R�~�j���e�B�o�X��҂��Ă�����70���݂̖ꂳ�������z���āA�����̏ꁁ�o�X��̑O�ɍ��荞��ʼn����������Ƃ����̂��ȂȂ��i���͌����Ȃ̂ł�����Ɨ���Ă���܂����j�z���k�͂��̂܂̂ĂĂ���܂����B�������ď�荞��r�[���i������/�������́j���i���āA���܂茒�N�Ȑ����𑗂��Ă��Ȃ��A�Ƃ������A�����o�X���œۂނȂ�ȁB�Ƃ�ł����������a��ɂ�����ʂāA���ꂩ��ǂ��ɏo�|����̂��B�����͓r���ō~��ĉw�������܂����B
���퉹�y�����Ɏg���Ă���Simplenote�A���炭�����������̂ɂ܂��܂��N�����邽�т�email���O�C����v������Ă�����ƟT�������B
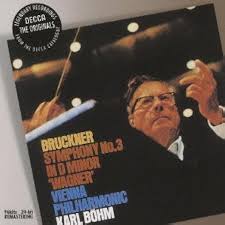 Bruckner �����ȑ�3�ԃj�Z���i�m���@�[�N�Łj�`�J�[���E�x�[��/�E�B�[���E�t�B���i1970�N�j�E�E�E���������ōō��̉��t�I�Ɛ��]��������ǁA���Đ̂̋L���ł͖��ɂ�������Ƃ������t�Ɋ����āA�C�}�C�`�Ȉ�ۂ͂����炭�͎����̎��̂����ł��傤�B��i�I�ɂ�����Ƌ��ӎ�������܂����BGerhart Hetzel�i1940�1992�j�R���}�X����̃E�B�[���E�t�B���A�pDECCA�͋��NJy��̐[�����F��N�X�Ƒ����āA���������܂��ܓ��肵�������͂�≹���������܂����B��1�y���uMassig bewegt�v�g�����y�b�g�ɂ���1���̒���A�₪�ăR���[�������ǂ̔���������Ă���`���̊y�͂��ǂ������܂�D���ɂȂ�Ȃ��āA���̍�i�ւ̋��ӎ��ƂȂ��Ă��܂��Ƃ���B�x�[��76�̋L�^�A�I�[�P�X�g���̓����ɂ͖����[���ȃe���V�����������āA���Ă̂�������Ƃ�����ۂ͏����܂����B�i22:05�j��2�y���uAdagio. Bewegt, quasi andante�v�����͏��łł̓N���C�}�b�N�X�Ɂu�^���z�C�U�[�v�̐��������p���ꂽ�Ƃ���B�I���W�i���̐����ɂ��[�����͂������āA���̕ӂ肩��E�B�[���E�t�B���̋��ǍՂ�S�J�Ɏ���܂��B�i14:49�j��3�y���uScherzo: Ziemlich schnell�vBruckner�̃L���͂��́u�X�P���c�H�v�B�ؔ����ĕs���Ȍ��ɏ���Č��������Y��������3/4���q�B���ɓo�ꂷ��y�₩�ɉ����ȃ����c�Ƃ͍D�ΏƁA����̓g���I�̃m���r���Ƃ������͋C�Ƃ悭���Ă���܂��B�i6:58�j��4�y���uFinale: Allegro�v���_�}�������邮�邮�錷�̉��^�ɏ���āA���ǂ��y�܂��B�����͂��Ȃ�J�b�R�ǂ��Ƃ���B�₪�đ�1�y�͂��3�y�͂���A���ē��X����e���V���������t�B�i�[��������Ă��邯��ǁA�ӊO�Ƒf���C�Ȃ��I���܂��B���̂�����Ɏ���Ƌ��ǂ̋P�������̗͂����̂��]���Ƃ���A�悤�₭�x�[���ƃE�B�[���E�t�B���̖��͂ɂ�����҂�ڊo�߂܂����B�i12:58�j
Bruckner �����ȑ�3�ԃj�Z���i�m���@�[�N�Łj�`�J�[���E�x�[��/�E�B�[���E�t�B���i1970�N�j�E�E�E���������ōō��̉��t�I�Ɛ��]��������ǁA���Đ̂̋L���ł͖��ɂ�������Ƃ������t�Ɋ����āA�C�}�C�`�Ȉ�ۂ͂����炭�͎����̎��̂����ł��傤�B��i�I�ɂ�����Ƌ��ӎ�������܂����BGerhart Hetzel�i1940�1992�j�R���}�X����̃E�B�[���E�t�B���A�pDECCA�͋��NJy��̐[�����F��N�X�Ƒ����āA���������܂��ܓ��肵�������͂�≹���������܂����B��1�y���uMassig bewegt�v�g�����y�b�g�ɂ���1���̒���A�₪�ăR���[�������ǂ̔���������Ă���`���̊y�͂��ǂ������܂�D���ɂȂ�Ȃ��āA���̍�i�ւ̋��ӎ��ƂȂ��Ă��܂��Ƃ���B�x�[��76�̋L�^�A�I�[�P�X�g���̓����ɂ͖����[���ȃe���V�����������āA���Ă̂�������Ƃ�����ۂ͏����܂����B�i22:05�j��2�y���uAdagio. Bewegt, quasi andante�v�����͏��łł̓N���C�}�b�N�X�Ɂu�^���z�C�U�[�v�̐��������p���ꂽ�Ƃ���B�I���W�i���̐����ɂ��[�����͂������āA���̕ӂ肩��E�B�[���E�t�B���̋��ǍՂ�S�J�Ɏ���܂��B�i14:49�j��3�y���uScherzo: Ziemlich schnell�vBruckner�̃L���͂��́u�X�P���c�H�v�B�ؔ����ĕs���Ȍ��ɏ���Č��������Y��������3/4���q�B���ɓo�ꂷ��y�₩�ɉ����ȃ����c�Ƃ͍D�ΏƁA����̓g���I�̃m���r���Ƃ������͋C�Ƃ悭���Ă���܂��B�i6:58�j��4�y���uFinale: Allegro�v���_�}�������邮�邮�錷�̉��^�ɏ���āA���ǂ��y�܂��B�����͂��Ȃ�J�b�R�ǂ��Ƃ���B�₪�đ�1�y�͂��3�y�͂���A���ē��X����e���V���������t�B�i�[��������Ă��邯��ǁA�ӊO�Ƒf���C�Ȃ��I���܂��B���̂�����Ɏ���Ƌ��ǂ̋P�������̗͂����̂��]���Ƃ���A�悤�₭�x�[���ƃE�B�[���E�t�B���̖��͂ɂ�����҂�ڊo�߂܂����B�i12:58�j
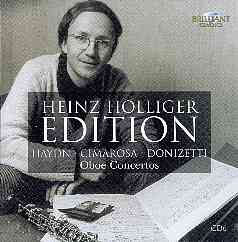 �i�`�jHaydn �I�[�{�G���t�ȃn����/Cimaroza-Benjamin�� �I�[�{�G���t�� �n�Z���i�C�E���W�`�j/Donizetti �R�[���E�A���O���̂��߂̏����t�ȃg����/�I�[�{�G�ƃn�[�v�̂��߂̃A���_���e�E�\�X�e�k�[�g �w�Z���`�n�C���c�E�z���K�[(ob)/�E���X���E�z���K�[(hp)/�f�C���B�b�h�E�W���}��/�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�i1986-1989�N�j�E�E�E�i�`�jHaydn�Ƃ͔ނ̐^��Ɗm�肵�Ă��Ȃ�����炵���B��1�y�́uAllegro spiritoso�v�i10:48�j��2�y�́uAndante�v�i6:07�j��3�y�́uRondo, Allegretto�v�i6:12�j����Ȃ�A�y���Ȗ��x�Ɉ��閼�ȁIMozart�ɕ����ʖ��ȂƊ�����͖̂���Heinz Holliger�i1939������j�̖��Z�̂Ȃ���Z�ł��傤���BCimaroza�̓`�F���o���E�\�i�^����I�[�{�G���t�Ȃɕ҂��̂炵���āA���D�̋���������͂��������L���ł��B�i2:18-2:37-3:00�j�R�[���E�A���O���i�C���O���b�V���z�����j�̓I�[�{�G��肿����҂艹�悪�Ⴂ�������B���l��������ăX�e�L�Ȑ����������܂����B�i10:55/3:09�j
�i�`�jHaydn �I�[�{�G���t�ȃn����/Cimaroza-Benjamin�� �I�[�{�G���t�� �n�Z���i�C�E���W�`�j/Donizetti �R�[���E�A���O���̂��߂̏����t�ȃg����/�I�[�{�G�ƃn�[�v�̂��߂̃A���_���e�E�\�X�e�k�[�g �w�Z���`�n�C���c�E�z���K�[(ob)/�E���X���E�z���K�[(hp)/�f�C���B�b�h�E�W���}��/�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�i1986-1989�N�j�E�E�E�i�`�jHaydn�Ƃ͔ނ̐^��Ɗm�肵�Ă��Ȃ�����炵���B��1�y�́uAllegro spiritoso�v�i10:48�j��2�y�́uAndante�v�i6:07�j��3�y�́uRondo, Allegretto�v�i6:12�j����Ȃ�A�y���Ȗ��x�Ɉ��閼�ȁIMozart�ɕ����ʖ��ȂƊ�����͖̂���Heinz Holliger�i1939������j�̖��Z�̂Ȃ���Z�ł��傤���BCimaroza�̓`�F���o���E�\�i�^����I�[�{�G���t�Ȃɕ҂��̂炵���āA���D�̋���������͂��������L���ł��B�i2:18-2:37-3:00�j�R�[���E�A���O���i�C���O���b�V���z�����j�̓I�[�{�G��肿����҂艹�悪�Ⴂ�������B���l��������ăX�e�L�Ȑ����������܂����B�i10:55/3:09�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
��m�̑䕗���F�X�e���^���āA���������ҏ��������炵�Ă���炵���B�T���ɂ͋C����������݂���������A����܂ł̐h�����B���̓������ɐ��͂悭�����܂��B�Q�ꂵ���A������낵���Ȃ������}���ăX�g���b�`���{�AYouTube�G�A���r�N�X�͋��R���s���K-POP�Ƃ��ɏ悹�Č�����10���قǁA�����ɂ͂܂������t���Ă������A���͏オ��܂����B�����ĘA�x�����̎s���̈�قցA�����W���W���ƏĂ��t����悤�ȓ������̒��A��������S�~�E��������ς݂܂����B�g���[�j���O���[���͏�A�����o�[�����āA�����̋g���{�G�A���o�C�N15����������b�B�ρB�����̊�Ԃ�����̗���ɏ��X�Ƀ����o�[�`�F���W���āA���������ĖK�⎞�Ԃ��ς�������������B�����C�ł��邱�Ƃ��F��܂��傤�B
�~��44%�̎��n�Ǝf��������ǁA�u�i������Ƃ̂��ƁB�܂�H�~�Ɍ����āA�ǂ肪���肸�F�͐H�������߂Đl���ɏo�Ă���\���������Ƃ������Ƃł��ˁB�Ƃ��낪����i�n���^�[�j�͂܂��������肸�A��V���܂�ɏ��Ȃ��A������u���ی�Ɓv�����SNS�o�b�V���O�������Έӗ~�܂��܂��ނ��鈫�z�B�ȑO�ɂ�����������ǁA�����e�������ĕߊl�]�X�Ƃ����̂͌���ł͂قƂ�NJG�Ȃ����B�K�x�Ȗ����ʂ̔��肪����A�܂����������Ȃ����A�����߂��ČF�̐�����D���\���������B���ꂩ��Z���ւ̔�Q�����������B���R���ɍl������ɂ͌���ł̃��A���ȓ��퐶����̌����Ă������������E�E�E���āA����������ȑ厩�R�ɂ͂��܂艏���Ȃ�����A�G���\�[�Ȃ��Ɖ]���Ȃ��B�ƂĂ��c�O�����ǁA�F���l�Ԃ̐�������ł��B
��F��l�{���������i��������j�ɂċv�X�̎��B������Ƒ̒����S�z���������ǁA�ߑO����������b���Ē��H�͍T���߂ɒ�����o�|���ēr�������w�\����QB�n�E�X�ɂĎU���A�����ė[�����X�ɓۂݎn�߂܂����B����o�ł�����F�͂܂��V���Ȑ�`�o��Ĉ��R�B�����ЂƂ�̖�F�͑��ς�炸���E��̈������]�������āA���̂��Ƃ����������߂܂����B���艺�̌�����������͋C�ɂȂ��Ă����Č��̏����f���܂����B�����������ēۂ�Ŏ���ɂ͖�7�����ɋA�ҁA�ґĂ��m�[�~�\�ւ̉����h���ł���B�v�X�ɂ�������ۂ̂Ŗ��肪�ǂ����A�݂̒��q�����܂����B�����̑̏d��67.9kg�{500g�͎��Ǝ����A�܂��_�C�G�b�g��蒼���ł��B
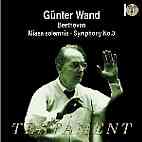 Beethoven �����ȑ�3�� �σz�����u�p�Y�v�`�M�����^�[�E���@���g/�P�����E�M�����c�F�j�q�nj��y�c�i1956�N�j�E�E�E���肬��X�e���I�ɊԂɍ����Ă��Ȃ����^����Le Club Francais Du Disque�^���i��6�ԑ�8�Ԕ����j�����͌��𐅏���◎��������ǁA�𑜓x�͂��Ȃ�ǍD�BGunter Wand�i1912�2002�ƈ�j54�A�������܂������`�Ƒ��߂̃e���|�͔ӔN�Ƃ��قǂɕς��Ȃ��B�I�[�P�X�g���̃A���T���u���͗D�G�A�T�E���h�͏a�߁B��1�y���uAllegro con brio�v�����D�u�Ƃ��ăN�[���A�h���ɍd�h�ȃ��_�ȏ���̂Ȃ����t�͐����ƔM�C�ƃe���V�������������́B���J��Ԃ��Ȃ��͎c�O�B�i14:49�j��2�y���uMarcia funebre: Adagio assai�v�͂�������Ƃ���������O�Ƀ��Y��������ŁA�������r�Q�ȔS�����\���ɔA�C���E�e���|����ɓ��O�ȕ\��t���ɗ͋�����͍��܂�܂��B�i14:13�j��3�y���uScherzo: Allegro vivace�v����������̂悢���Y��������ŁA�m���m���̉������i�͂������܂����B�g���I�̃z�����O�d�t�͂ǂ�����Ƃ��݂��ƁB�i5:49�j��4�y���uFinale: Allegro molto�v�ϑt�Ȃ͂��Ȃ葬���A�X�����ȋ����Ƀe���V���������i��ŔM�C�̓}�V�}�V�A�J�b�R�ǂ��ł���B���X�g�̓p���t���Ȏ����̂����ɏI�����܂����B�i11:22�j�܁A�V�������̘^��������������ċ��߂�K�v���Ȃ��悤�ȋC�����܂����B
Beethoven �����ȑ�3�� �σz�����u�p�Y�v�`�M�����^�[�E���@���g/�P�����E�M�����c�F�j�q�nj��y�c�i1956�N�j�E�E�E���肬��X�e���I�ɊԂɍ����Ă��Ȃ����^����Le Club Francais Du Disque�^���i��6�ԑ�8�Ԕ����j�����͌��𐅏���◎��������ǁA�𑜓x�͂��Ȃ�ǍD�BGunter Wand�i1912�2002�ƈ�j54�A�������܂������`�Ƒ��߂̃e���|�͔ӔN�Ƃ��قǂɕς��Ȃ��B�I�[�P�X�g���̃A���T���u���͗D�G�A�T�E���h�͏a�߁B��1�y���uAllegro con brio�v�����D�u�Ƃ��ăN�[���A�h���ɍd�h�ȃ��_�ȏ���̂Ȃ����t�͐����ƔM�C�ƃe���V�������������́B���J��Ԃ��Ȃ��͎c�O�B�i14:49�j��2�y���uMarcia funebre: Adagio assai�v�͂�������Ƃ���������O�Ƀ��Y��������ŁA�������r�Q�ȔS�����\���ɔA�C���E�e���|����ɓ��O�ȕ\��t���ɗ͋�����͍��܂�܂��B�i14:13�j��3�y���uScherzo: Allegro vivace�v����������̂悢���Y��������ŁA�m���m���̉������i�͂������܂����B�g���I�̃z�����O�d�t�͂ǂ�����Ƃ��݂��ƁB�i5:49�j��4�y���uFinale: Allegro molto�v�ϑt�Ȃ͂��Ȃ葬���A�X�����ȋ����Ƀe���V���������i��ŔM�C�̓}�V�}�V�A�J�b�R�ǂ��ł���B���X�g�̓p���t���Ȏ����̂����ɏI�����܂����B�i11:22�j�܁A�V�������̘^��������������ċ��߂�K�v���Ȃ��悤�ȋC�����܂����B
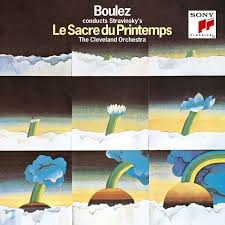 Stravinsky �o���G���y�u�y�g���[�V���J�v�i1911�N��/�j���[���[�N�E�t�B��/1971�N�j/�o���G���y�u�t�̍ՓT�v�i1947�N��/�N���[�������h�nj��y�c/1969�N�j�`�s�G�[���E�u�[���[�Y�E�E�ECBS�ɂ�鋌�^���B���ǂ��̍��������݁ALP������u�t�̍ՓT�v�͂��ꂪ���_�B�u�y�g���[�V���J�v��1971�N�^�������̂͂��̐��\�N��̂��ƁA����i1991�N�^���Ƃ́j�u�_�D�̋Z�ʂ̍��v�ƈ��ՂȂ��ẴR�����g���p����������ǁA�Ē����Ă݂Ă�����Ɣ��Ȃ��܂����B�I�[�P�X�g���̖��邢�����ȋ����A�Ę^���͂��܂�ɐ����āA�����Ƃ藎���������o�����X���t����������ǁA�������k���ȕ\����O��ɁA�u�[���[�Y40�Α�̗͉̑���A���B���B�b�h�ȗV���n�̌����������Ղ芬�\�����Ă�������A�c�����₩��������܂����B��i�I�ɂ͂�����̂ق��������Ɖf����\���A�������A�I���������t�����B���������قǂɌÂ������������܂���B�i5:40-1:59-2:36/4:04/2:49-0:47-3:12/3:26-1:25-1:08-2:00-1:33-0:39-0:45-2:07�j
Stravinsky �o���G���y�u�y�g���[�V���J�v�i1911�N��/�j���[���[�N�E�t�B��/1971�N�j/�o���G���y�u�t�̍ՓT�v�i1947�N��/�N���[�������h�nj��y�c/1969�N�j�`�s�G�[���E�u�[���[�Y�E�E�ECBS�ɂ�鋌�^���B���ǂ��̍��������݁ALP������u�t�̍ՓT�v�͂��ꂪ���_�B�u�y�g���[�V���J�v��1971�N�^�������̂͂��̐��\�N��̂��ƁA����i1991�N�^���Ƃ́j�u�_�D�̋Z�ʂ̍��v�ƈ��ՂȂ��ẴR�����g���p����������ǁA�Ē����Ă݂Ă�����Ɣ��Ȃ��܂����B�I�[�P�X�g���̖��邢�����ȋ����A�Ę^���͂��܂�ɐ����āA�����Ƃ藎���������o�����X���t����������ǁA�������k���ȕ\����O��ɁA�u�[���[�Y40�Α�̗͉̑���A���B���B�b�h�ȗV���n�̌����������Ղ芬�\�����Ă�������A�c�����₩��������܂����B��i�I�ɂ͂�����̂ق��������Ɖf����\���A�������A�I���������t�����B���������قǂɌÂ������������܂���B�i5:40-1:59-2:36/4:04/2:49-0:47-3:12/3:26-1:25-1:08-2:00-1:33-0:39-0:45-2:07�j
�u�t�̍ՓT�v�͐V�^���Ɠ����N���[�������h�nj��y�c�B�V���^���Ƃ�1947�N�ł����������ǁA�h�E�V���E�g�ɂ͂ǂ����ǂ��Ⴄ�̂������ς�킩��Ȃ��B���ꂪLP���ぁ���w�����ゾ�����A���ꂪ�u�t�̍ՓT�v�̍��荞�݁A�������ɏ�肢�I�[�P�X�g���ł���B�����Ԃ�Ƌv�X�̔q�������ǁA�����������Ȃ��B���Ă̋L�����ו��C�t���Ȃ������p�[�g�̐�������t�������Ă��܂��B�k���m�I�\������{�Ƃ���\�������͂��̂܂܂ɁA�A�c�������A�����n���͂����肵�������A������̂ق����s�N�̗̑��i44�j���������芴�������āA��i�̃o�[�o���Y�������������ă��A���ȉ��t�ł����B�V�^���̗��������������x���D�������ǁA���߂Ē��������̊������h��N�x�����Ղ�Ɏv���o���܂����B�i3:37-3:20-1:26-3:53-1:59-0:44-0:21-1:20/4:07-3:18-1:32-0:39-3:38-4:37�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
����A�x���X�g���ҏ������A�����]���Η��T���A�x�Ȃ�ł��ˁB�̒��͂܂��܂������ǁA�W���͂͑����܂���B����Ԃɐ���{�X�g���b�`�{YouTube�X�g���b�`���{�B��͂�䗬�͂����܂ւ�ˁA�����̎����̓����ɋ߂����̂�����������ǁA��͂���̃C���X�g���N�^�[�̎w���ɂ͐����͂�����܂����B�V�����[�𗁂тĂ���Ɩ��X�[�p�[�H�ގd���ꌓ�E�H�[�L���O�B�����ɂ͕Ă̍ɂ͂Ȃ��āA�܂��܂����ɂ͕s����̂悤�ł��B�v�X��F�ɘA��������āA�{��������ۂނ��ƂɂȂ�܂����B�ЂƂ�͗��T���Ղɂ͊��ى����̎�p���T���āA�p��͂��炭�g�����ł��Ȃ������B�����̑̏d��67.4kg�{500g�ň��B
2024�N�x�̍��Y�~�͗�N��44%��s��A���̂��Ƃ͂��������̕Œm���Ă���܂����B���낢��ƓV��������d�Ȃ荇���������ł��B�u���ɒʂ��s���̈�ٓr���A��̔������A�����a�������₵�������ɔ�������ʎ����A����Ă��Ĕ~��2�{�A��N��2�|30�E���Ĕ~�W��������������̂ł��B���N�́E�E�E�܂������}�̏�ɔ~�̎��̎p�����܂���B�܂��ɕǂ���B�т�����͌����Ȃ��Ȃ��A�Ă݂����J�����͑��v�݂����B����͏n�����炱�����肢����������A���ɗ��������̂͐ޓ��ɂȂ��ł��傤�B�J�����Ɏ����Ă͒N���g�킸�A�����ʂĂ����ł����B��N�̓W���������܂��������B
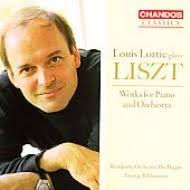 Schubert-Liszt�� Beethoven�́u�A�e�l�̔p�Ёv�̎��ɂ�錶�z��/Weber-Liszt�� �ؗ�Ȃ�|���l�[�Y �z����/Liszt �ߜƋ��t�� �z�Z��/�n���K���[���w�ɂ�錶�z�ȃw�Z��/Schubert-Liszt�� �����炢�l���z�� �n�����`���C�E�����e�B(p)/�W���[�W�E�y�[�����@�j�A��/�n�[�O�E���W�e���e�B�nj��y�c�i1999-2000�N�j�E�E�EThe Golden Age of the Romantic Piano Concerto�Ƃ���CD20���g�̃{�b�N�X���o���A����VOX�ӂ�ŏo�Ă�����������i�{�����W�߂āA�����̕����L����ׂ����ĎႢ���M�S�ɒ����Ă������̂��܂܂�܂��B�����Chandos�������ȁH�i�ʐ^�͂�����j�ŋ߃l�b�g��肢�����ē��肵�āA�Ⴆ�����������Weber��Tchaikovsky�̒�������i�����̂ЂƂBLouis Lortie�i1959����ޑɁj�͖��肾����ȉ�����Z�I�]�X�͗��AGeorge Pehlivanian�i1964��t�b�c�j�Ƃ͏����w���ҁB���̈ꖇ���i�����͋��ȁjLiszt����l�̐����𗬗p���ė�̒���Z�I�s�A�m���t�ȂɎd�グ�����́A�����͗ǍD�ł��B�u�A�e�l�̔p�Ёv���z���͒N�ł��m���Ă���Beethoven�́u�g���R�s�i�ȁv���Ȑ������o�ꂷ��Schubert�̍�i�B�X��Liszt���S�[�W���X�Ƀf�[�n�[�Ƀf�R���[�V�����������̂炵���B�قƂ�Ǔ��₩�ȃA�N���o�b�g�ł���B�i10:47�jWeber�̌��Ȃ͂悭�m��Ȃ�����ǁA��̔@���f�p�ȏ����̃��Y�����y���ɒe��ŁA����ɉؗ�Ȉߑ����ς��{�����悤�Ȗ��邢��i�ł����B�i9:31�j�u�ߜƋ��t�ȁv�̓I���W�i���H��҂̓\����i�����狦�t�ȕ��Ɏd�グ���Ƃ��B�C����Ȑ����ɂ��炫�玩�݂ȃs�A�m�̃e�N�j�b�N���l�A�����̃C���[�W�ʂ胏���E�p�^�[�����I�ɍ��g���Ă�����i�B�i16:19�j�u���z�ȁv�̓n���K���[�����ȑ�14�ԃw�Z������̊nj��y���t�ҋȁA���̗E�s�Ȗ��w�������͂��Ȃ�L���Ǝv���܂��B�e�B���p�j�����₩�ȁA������s�A�m���`��ɖZ�����A���܂������Ƃ��l�����ɂ����Ղ�₩�Ȓ���Z�I�����\���ׂ���i�B�i14:43�j�u�����炢�l�v�͒N�ł��m���Ă��������������B���N�̃s�A�j�X�g�����������^�����Ă��āA�ŋߎ������������Ă��邻���B���C�̂�낵���̗w�I�Ȑ����͎����ɂƂ��Ă͉��㉮���d�˂��ہA�]�v�ȋ�����������Ă����Ⴒ����A��͂�I���W�i�����X�e�L�Ɗ����܂����B�i6:07-6:43-4:31-3:41�j
Schubert-Liszt�� Beethoven�́u�A�e�l�̔p�Ёv�̎��ɂ�錶�z��/Weber-Liszt�� �ؗ�Ȃ�|���l�[�Y �z����/Liszt �ߜƋ��t�� �z�Z��/�n���K���[���w�ɂ�錶�z�ȃw�Z��/Schubert-Liszt�� �����炢�l���z�� �n�����`���C�E�����e�B(p)/�W���[�W�E�y�[�����@�j�A��/�n�[�O�E���W�e���e�B�nj��y�c�i1999-2000�N�j�E�E�EThe Golden Age of the Romantic Piano Concerto�Ƃ���CD20���g�̃{�b�N�X���o���A����VOX�ӂ�ŏo�Ă�����������i�{�����W�߂āA�����̕����L����ׂ����ĎႢ���M�S�ɒ����Ă������̂��܂܂�܂��B�����Chandos�������ȁH�i�ʐ^�͂�����j�ŋ߃l�b�g��肢�����ē��肵�āA�Ⴆ�����������Weber��Tchaikovsky�̒�������i�����̂ЂƂBLouis Lortie�i1959����ޑɁj�͖��肾����ȉ�����Z�I�]�X�͗��AGeorge Pehlivanian�i1964��t�b�c�j�Ƃ͏����w���ҁB���̈ꖇ���i�����͋��ȁjLiszt����l�̐����𗬗p���ė�̒���Z�I�s�A�m���t�ȂɎd�グ�����́A�����͗ǍD�ł��B�u�A�e�l�̔p�Ёv���z���͒N�ł��m���Ă���Beethoven�́u�g���R�s�i�ȁv���Ȑ������o�ꂷ��Schubert�̍�i�B�X��Liszt���S�[�W���X�Ƀf�[�n�[�Ƀf�R���[�V�����������̂炵���B�قƂ�Ǔ��₩�ȃA�N���o�b�g�ł���B�i10:47�jWeber�̌��Ȃ͂悭�m��Ȃ�����ǁA��̔@���f�p�ȏ����̃��Y�����y���ɒe��ŁA����ɉؗ�Ȉߑ����ς��{�����悤�Ȗ��邢��i�ł����B�i9:31�j�u�ߜƋ��t�ȁv�̓I���W�i���H��҂̓\����i�����狦�t�ȕ��Ɏd�グ���Ƃ��B�C����Ȑ����ɂ��炫�玩�݂ȃs�A�m�̃e�N�j�b�N���l�A�����̃C���[�W�ʂ胏���E�p�^�[�����I�ɍ��g���Ă�����i�B�i16:19�j�u���z�ȁv�̓n���K���[�����ȑ�14�ԃw�Z������̊nj��y���t�ҋȁA���̗E�s�Ȗ��w�������͂��Ȃ�L���Ǝv���܂��B�e�B���p�j�����₩�ȁA������s�A�m���`��ɖZ�����A���܂������Ƃ��l�����ɂ����Ղ�₩�Ȓ���Z�I�����\���ׂ���i�B�i14:43�j�u�����炢�l�v�͒N�ł��m���Ă��������������B���N�̃s�A�j�X�g�����������^�����Ă��āA�ŋߎ������������Ă��邻���B���C�̂�낵���̗w�I�Ȑ����͎����ɂƂ��Ă͉��㉮���d�˂��ہA�]�v�ȋ�����������Ă����Ⴒ����A��͂�I���W�i�����X�e�L�Ɗ����܂����B�i6:07-6:43-4:31-3:41�j
 Tchaikovsky �s�A�m���t�ȑ�1�� �σ������i���T�Łj�`���[�U���E�x���}��(p)/�����E�e�~���J�[�m�t/�x���������������y�c�i1986�N�j�E�E�E���t�͂����炭�͋������̕��������y�c�B�����͗Տꊴ�������Ĉ����Ȃ�����ǁA1986�N�ɂ��Ă͂��f���J�V�[�Ɍ����Ĕ������e�����ɋ������ɂ���܂��B�iLP���������炵���j���T�łƉ]���Ă�������h�E�V���E�g�u�s�A�m�̃p�[�g��10�����̕ύX���������A�`�����_�炩���A���y�W�I�ɂȂ����̂��킩��v�Ƃ̃l�b�g���܂����B�u��O�y�͂͒��ԕ��̂Ȃ��������ł��������Ȃ��Ă���v�����B��1�y���uAllegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito�v����`����ۓI�ȃz�����Ԃ����܂��ALazar Berman�i1930-2005�I�����j�̃s�A�m�͂�������Z���ɍ��������Ƃ�A�Â�����ɏ[���ĘN�X�Əd�ꂵ�����͋������́B�i21:45�j��2�y���uAndantino semplice - Prestissimo�v�`���̃t���[�g���炢���̐������͂���܂���B�������x���e���|�ɂ�������A���O�ɉ̂����́B���Ԃ̓��₩�ȂƂ���ɂ��₩�Ȍy���͂���܂���B�i7:33�j��3�y���uAllegro con fuoco�v�������}�����A���ݒ��߂�悤�Ȏn�܂�B�\���̐[�݂̂��鋿���A�����ȃe�N�j�b�N���Ă����A�I�[�P�X�g���̋����̑��肪���X�C�ɂȂ�܂����B�i7:36�j
Tchaikovsky �s�A�m���t�ȑ�1�� �σ������i���T�Łj�`���[�U���E�x���}��(p)/�����E�e�~���J�[�m�t/�x���������������y�c�i1986�N�j�E�E�E���t�͂����炭�͋������̕��������y�c�B�����͗Տꊴ�������Ĉ����Ȃ�����ǁA1986�N�ɂ��Ă͂��f���J�V�[�Ɍ����Ĕ������e�����ɋ������ɂ���܂��B�iLP���������炵���j���T�łƉ]���Ă�������h�E�V���E�g�u�s�A�m�̃p�[�g��10�����̕ύX���������A�`�����_�炩���A���y�W�I�ɂȂ����̂��킩��v�Ƃ̃l�b�g���܂����B�u��O�y�͂͒��ԕ��̂Ȃ��������ł��������Ȃ��Ă���v�����B��1�y���uAllegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito�v����`����ۓI�ȃz�����Ԃ����܂��ALazar Berman�i1930-2005�I�����j�̃s�A�m�͂�������Z���ɍ��������Ƃ�A�Â�����ɏ[���ĘN�X�Əd�ꂵ�����͋������́B�i21:45�j��2�y���uAndantino semplice - Prestissimo�v�`���̃t���[�g���炢���̐������͂���܂���B�������x���e���|�ɂ�������A���O�ɉ̂����́B���Ԃ̓��₩�ȂƂ���ɂ��₩�Ȍy���͂���܂���B�i7:33�j��3�y���uAllegro con fuoco�v�������}�����A���ݒ��߂�悤�Ȏn�܂�B�\���̐[�݂̂��鋿���A�����ȃe�N�j�b�N���Ă����A�I�[�P�X�g���̋����̑��肪���X�C�ɂȂ�܂����B�i7:36�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�{���h�V�̓��A65�Έȏ�̐l�����29.3%�Ƃ��A����̓_���g�c���E��B�����������l��7�l�Ɉ�l�͍���҂Ƃ��B�����͖����V��œ����Ă܂��B������O�߂��炵���Ƃ莼���Ă���E�E�E�锼�ɂ�����ƍ~�����̂ł��ˁB���͐���݂̂ŃX�g���b�`�AYouTube�G�A���r�N�X�̓T�{��A���̂܂s���̈�ق֏o�|���܂����B�܂��ɍō��C����30�xC���x�A�y���S�~��ʃy�b�g�{�g�����E��������蓞���A�����}�X�N���L���`���āA���[�Ɉ��ՂɎ̂Ă�łق����B���j���̃g���[�j���O���[���͘A�x���̂������Ă��āA���𐢑�͘A�x���ƒ�T�[�r�X�ɖZ�����̂��B������莩���̏��Ԓʂ�ɋg���}�V���͏����ł��܂����B�G�A���o�C�N15�����������ăV�����[���g������u���A�A��X�[�p�[�H�ގd����Ɋ������u�����h�āA�R�V�q�J���e�X�ɂ͑����āA�A���A���i�̓��E���c�ɍ����B�������ăl�b�g���Ă𒍕����蓞���ς����ǁA���ʓI�ɂ̓�������ł��Ԃɍ����܂����B�����o�����X�̕s��͂ق�̂�����Ƃ̊Ԃ������̂����B�����̑̏d��66.8kg�{100g�A�Ȃ��Ȃ�����܂���B
�����ŋߘA�����Ĕq�����������̉�쎖�Ƃ̌��B�^���{�ݓ��ɂāu�L���o�N���v�J���i�����j�ꂳ�܂����������ɏ��˂�����Ă��āA�����E�����������ĐڑҁB�I�T�����֎~�����ǁA�v�킸�������ɂ�����Ă��܂��č����i������E���j�����ӁB����Ɓu�r���������Ă���I�v�Ƃ̕Ԃ����G��ł����B����͖ꂳ�܂͌��C�o�܂���B�����Ƃ��Ƃ��Ə��X�����������̎{�݂Ȃ�ł��傤�B
����A�����͂ǂ����B�ʔԑg�ɂăl�C���P�A�����Ă���̂�q���A�Q������̍����������Ő��������Ƃ���̂ł��ˁB����ȃj���[�X�߂A�`��̂Ƃ���ɂ������؍݂��Ă���k�����i94�j�̂Ƃ���ɏ��[�a�͉��ɏo�|���Ă����܂����B
 Brahms �����ȑ�1�ԃn�Z���`���j�N�E�l�[���Z�K��/���[���b�p�����nj��y�c�i2022�N�j�E�E�EYannick Nezet-Seguin�i1975����ޑɁj�͌��݂����Ƃ��Z�����w���҂̈�l�B�t�B���f���t�B�A�ƃ��g���|���^���̌���̉��y�ē��C�A���E�̎�v�ȃI�[�P�X�g���Ƃ��ӗ~�I�ɋq�����Ă���悤�ł��B���[���b�p�����nj��y�c�Ƃ͎�X�����ȑS�W��^�����āA�����̏���Țn�D�����ǁA�l�[���Z�K�������̒c�̂����܂�D�݂��Ⴀ��܂���B�Ƃ��ɂ��̎����nj��y�c�ɂ͗B�ꖳ��̐F�Ƃ����킢�Ɍ�����E�E�E�悤�ȋC�����܂��B��肢���ǂˁB���{�ł̉��ڃg�b�v�𑈂��I�X�Ƃ��Č��I���h�Ȍ����Ȃ͈ӊO�ɂ���ǕҐ��A������\����Ȃ����Ǐ��X�H���C���A����Ⴋ���̏��V�����Œ�������i�B���ꂪ��1�y���uUn poco sostenuto-Allegro�v�`����������B��̈Ј��������Ղ�̗��h�ȏ��t���d��������������Ȃ��A��S�����ɂ��������Ƃ����\���B����̓p�[���H�E�x���O�����g��`���[���Y�E�}�b�P���X�̈�ۂɋ߂��Ɗ����܂����E�E�E�����Ԃ炭�����Ă��Ȃ����ǁB���J��Ԃ��B�i15:28�j��2�y�́uAndante sostenuto�v�ɏ��y�͂����Ґ��̌����^�X�Ƃ��ăf���P�[�g�B�����ς�Ƃ��Čy�������ł����B�i8:46�j��3�y���uUn poco allegretto e grazioso�v�̓X�P���c�H�ɔԑt�ȕ��D��ȂƂ���B�����͌��̗͂������ėD��ȕ���Y���܂��B�i4:37�j��4�y���uAdagio-Piu andante-Allegro non troppo, ma con brio�v�d�ꂵ���d�t����₪�āA�I�X����u��т̉́v�����͔����Ƃ��Čy���A�I�[�P�X�g���̋������f���ɗ���̂�낵�����́B���X�g�Ɍ����đ��߂̃e���|�E�A�b�v�͑u���B�i15:43�j
Brahms �����ȑ�1�ԃn�Z���`���j�N�E�l�[���Z�K��/���[���b�p�����nj��y�c�i2022�N�j�E�E�EYannick Nezet-Seguin�i1975����ޑɁj�͌��݂����Ƃ��Z�����w���҂̈�l�B�t�B���f���t�B�A�ƃ��g���|���^���̌���̉��y�ē��C�A���E�̎�v�ȃI�[�P�X�g���Ƃ��ӗ~�I�ɋq�����Ă���悤�ł��B���[���b�p�����nj��y�c�Ƃ͎�X�����ȑS�W��^�����āA�����̏���Țn�D�����ǁA�l�[���Z�K�������̒c�̂����܂�D�݂��Ⴀ��܂���B�Ƃ��ɂ��̎����nj��y�c�ɂ͗B�ꖳ��̐F�Ƃ����킢�Ɍ�����E�E�E�悤�ȋC�����܂��B��肢���ǂˁB���{�ł̉��ڃg�b�v�𑈂��I�X�Ƃ��Č��I���h�Ȍ����Ȃ͈ӊO�ɂ���ǕҐ��A������\����Ȃ����Ǐ��X�H���C���A����Ⴋ���̏��V�����Œ�������i�B���ꂪ��1�y���uUn poco sostenuto-Allegro�v�`����������B��̈Ј��������Ղ�̗��h�ȏ��t���d��������������Ȃ��A��S�����ɂ��������Ƃ����\���B����̓p�[���H�E�x���O�����g��`���[���Y�E�}�b�P���X�̈�ۂɋ߂��Ɗ����܂����E�E�E�����Ԃ炭�����Ă��Ȃ����ǁB���J��Ԃ��B�i15:28�j��2�y�́uAndante sostenuto�v�ɏ��y�͂����Ґ��̌����^�X�Ƃ��ăf���P�[�g�B�����ς�Ƃ��Čy�������ł����B�i8:46�j��3�y���uUn poco allegretto e grazioso�v�̓X�P���c�H�ɔԑt�ȕ��D��ȂƂ���B�����͌��̗͂������ėD��ȕ���Y���܂��B�i4:37�j��4�y���uAdagio-Piu andante-Allegro non troppo, ma con brio�v�d�ꂵ���d�t����₪�āA�I�X����u��т̉́v�����͔����Ƃ��Čy���A�I�[�P�X�g���̋������f���ɗ���̂�낵�����́B���X�g�Ɍ����đ��߂̃e���|�E�A�b�v�͑u���B�i15:43�j
 Stravinsky �o���G���y�u�t�̍ՓT�v�i1947�N�Łj/Scriabin �����ȑ�4�ԁu�@�x�̎��v�`�������[�E�Q���M�G�t/�L�[���t�̌���nj��y�c�i1999�N�j�E�E�E�ڂ��o�߂�قǃN���A�ȉ����A�Ƃ��ɑŊy��̒�ʂ⑶�݊��̓��A���ɕ��������đ��̘^���͈�����悷�����B�u�t�̍ՓT�v�͐��m�����ǂ��Ȃ�\�͓I�Ƀ��B���B�b�h�A�����n�������Ƀn���̂������狿���Ŋy��̓��A���ɕ��������ăI�[�P�X�g���̓��E���c�ɏ�肢�E�E�E�Ƃ������A�e�p�[�g�̉��F���Z���Č��I�A��ȍ����p���[�����Ղ�Ƀ��Y���͏d���A�Ⴆ�Βm�I�ȉ�͂�����������u�[���[�Y�Ƃ͂��Ȃ�قȂ���ǐ⋩���P�N�\�I�D�L�����t�ō��B���������D���ł��A���ꂪ���Ƃ��Ƃ̍�i�̎�|�i���n�̃p���[�j�Ɏ������Ă����Ȃ����A��Ɋ������ċ����̉Q�E�E�E����Ȑ����͂����������܂����B�i3:23-3:12-1:17-3:41-1:46-1:46-0:40-0:26-1:10/4:23-3:34-1:36-0:49-3:51-4:45�jScriabin�Ƃ̑g�ݍ��킹�͒���������Ǐ�����1908�N�A�u�t�̍ՓT�v��1913�N������قړ�����̉��y�B�����Ղ芯�\�I�Ɏv��������G�b�`�ȃh���͉��t�B�NJy��ɂ͌��݂������ċɐF�ʂɑs��B����ȂɗY�قȃg�����y�b�g�ɂ͖ő��ɏo��܂���B�i20:26�j�G�����N�U���Ȃ�������Ɗ��Ă����͂��̐l�ł����B
Stravinsky �o���G���y�u�t�̍ՓT�v�i1947�N�Łj/Scriabin �����ȑ�4�ԁu�@�x�̎��v�`�������[�E�Q���M�G�t/�L�[���t�̌���nj��y�c�i1999�N�j�E�E�E�ڂ��o�߂�قǃN���A�ȉ����A�Ƃ��ɑŊy��̒�ʂ⑶�݊��̓��A���ɕ��������đ��̘^���͈�����悷�����B�u�t�̍ՓT�v�͐��m�����ǂ��Ȃ�\�͓I�Ƀ��B���B�b�h�A�����n�������Ƀn���̂������狿���Ŋy��̓��A���ɕ��������ăI�[�P�X�g���̓��E���c�ɏ�肢�E�E�E�Ƃ������A�e�p�[�g�̉��F���Z���Č��I�A��ȍ����p���[�����Ղ�Ƀ��Y���͏d���A�Ⴆ�Βm�I�ȉ�͂�����������u�[���[�Y�Ƃ͂��Ȃ�قȂ���ǐ⋩���P�N�\�I�D�L�����t�ō��B���������D���ł��A���ꂪ���Ƃ��Ƃ̍�i�̎�|�i���n�̃p���[�j�Ɏ������Ă����Ȃ����A��Ɋ������ċ����̉Q�E�E�E����Ȑ����͂����������܂����B�i3:23-3:12-1:17-3:41-1:46-1:46-0:40-0:26-1:10/4:23-3:34-1:36-0:49-3:51-4:45�jScriabin�Ƃ̑g�ݍ��킹�͒���������Ǐ�����1908�N�A�u�t�̍ՓT�v��1913�N������قړ�����̉��y�B�����Ղ芯�\�I�Ɏv��������G�b�`�ȃh���͉��t�B�NJy��ɂ͌��݂������ċɐF�ʂɑs��B����ȂɗY�قȃg�����y�b�g�ɂ͖ő��ɏo��܂���B�i20:26�j�G�����N�U���Ȃ�������Ɗ��Ă����͂��̐l�ł����B
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
������ٗl�Ȗҏ��p���A�̒����ǂ���p�����B�[�����J�̗\��������ǁA�V�C�͕ۂ��܂����B���[�a�͋v�X�Ɏs���̈�كg���[�j���O���[���֏o�|���āA�n�C�v�[���[�����ԓƐ肨����Ɍ��{���Ă���܂����B�X�g���b�`��YouTube�G�A���o�C�N�͍ĊJ�ł��܂����B�����ŋߎ����̑̒��s�ǂɂ�����݂̔~�c�w�O�r���n���������͍s���Ă��Ȃ��̂ŁA���[�a�͋v�X�ɏo�|�������Ƃ̂��ƁB������R�~���j�e�B�o�X�̎��Ԃ��ɂ�ŏd�������グ�܂����B�r�[�������X�A�N�x�̗ǂ��h���g�Ƃ����i�Ƃ����������j���[���\�������܂����B�A�x�ɓ������������A���������ǂ��̓X������ł���܂����B�����̑̏d��66.7kg��700g�A���̒��q�Œb���čX�Ɍ��炵�����B
2024�N9��13��JR�ޗǐ��ɂă|�C���g����ւ��ʈُ픭���A���11�{�ɉe�����o���Ƃ̕B�����̓|�C���g�ɃJ�������܂����`���}���̗��p�҂ɂ͐\����Ȃ���������ǁA�傫�Ȏ��̂ɂ����炸�A�ǂ��ƂȂ����[�����X�ȃj���[�X�Ɗ����܂��B���i������j�̃J���͖����������̂��A���̃J���͂���������ɐB���Ă���~�V�V�b�s�[�A�J�~�~�K���Ȃ̂��A���̕ӂ�u�J���͑������������A�傫�����ނ͕s���v�Ƃ̂��Ƃ�����A�����ƒׂ�Ă��܂�����ł��傤�ˁB
�����ۂ��A�Ƒ��A��̎��Ɨp�Ԃ��Փˎ��̂ŗc�����ǂ����S���Ȃ鎖���͑����āA����͑��X���Ȃ̂ł��傤���A����Ƃ��S�̂Ƃ��Č����Ă���Ȃ��ł̎c�O�Ȏ��ۂȂ̂��A�����ς肻�̕ӂ�͓ǂݎ��܂���B��������������ăX�}�z���W���Ă���̂��A�Ȃ�Ƃ��킩��Ȃ��B
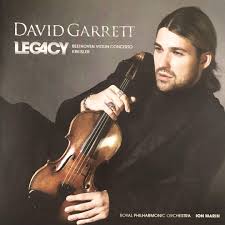 Beethoven ���@�C�I�������t�ȃj����/Kreisler �O�t�ȂƃA���O���iPugnani�̃X�^�C���ɂ��j/Rachmaninov �p�K�j�[�j�̎��ɂ�鋶���ȁv����18�ϑt/�E�B�[����z��/Coreelli�̎��ɂ��ϑt���iTartini�̃X�^�C���ɂ��j/���}���X�iWeber�̎��ɂ�郉���Q�b�g�j/�����̑���/���̔߂��݁`�f�C���B�b�h�E�M�����b�g(v)/�C�I���E�}����/���C�����E�t�B���i(c)(p)2011�N�j�E�E�E�C�P���� ���@�C�I���j�X�g�ł��胂�f���A�f��o�D�����Ă���炵��David Garrett�i1980-�ƈ큨���ė����j�͍d�h�ȃN���V�b�N����n�܂��āA���݂̓N���X�I�[�o�[�Ȋ��������Ă���Ƃ̂��ƁB����͒�Ԃ�Beethoven����n�܂��āA�㔼��Kreisler����݂̐����������Ղ荋�Ȋnj��y���t�t���ɒ������Ă��������āA�����ɂ�Pop�I�ނ炵���e���݂₷������̃A���o���ł����B
Beethoven ���@�C�I�������t�ȃj����/Kreisler �O�t�ȂƃA���O���iPugnani�̃X�^�C���ɂ��j/Rachmaninov �p�K�j�[�j�̎��ɂ�鋶���ȁv����18�ϑt/�E�B�[����z��/Coreelli�̎��ɂ��ϑt���iTartini�̃X�^�C���ɂ��j/���}���X�iWeber�̎��ɂ�郉���Q�b�g�j/�����̑���/���̔߂��݁`�f�C���B�b�h�E�M�����b�g(v)/�C�I���E�}����/���C�����E�t�B���i(c)(p)2011�N�j�E�E�E�C�P���� ���@�C�I���j�X�g�ł��胂�f���A�f��o�D�����Ă���炵��David Garrett�i1980-�ƈ큨���ė����j�͍d�h�ȃN���V�b�N����n�܂��āA���݂̓N���X�I�[�o�[�Ȋ��������Ă���Ƃ̂��ƁB����͒�Ԃ�Beethoven����n�܂��āA�㔼��Kreisler����݂̐����������Ղ荋�Ȋnj��y���t�t���ɒ������Ă��������āA�����ɂ�Pop�I�ނ炵���e���݂₷������̃A���o���ł����B
Bee���̍�i���A�����Ƃ������ɔ�������i�̂ЂƂł������@�C�I�������t���͒��f�̃e���|�A�ӊO�Ɛ��ׂ̍��f���P�[�g�ȃ\���ł����B��1�y���uAllegro ma non troppo�v���₩�ȉ��F�ɔA�����Ƃ藎�������ăN�[���BBee���炵����ʁA���X�Ɛ�������悤�Ȑ����͖��S�ȃe�N�j�b�N�ɗ��������đ���Ȃ��B�₩�ɂ����Ƃ��\���Ƃ������ɃI�[�\�h�b�N�X�B�i25:05�j��2�y���uLarghetto�v���������������Đ�捂ɍT���߁A�����Ȋɏ��y���i9:39�j��3�y���uRondo Allegro�v�I�y�͂Ɏ����Ă��n�f�ȃp�t�H�[�}���X�ɔA�l�X�Ƃ��Ē[���ȕ�������܂����B�i10:07�j�C�I���E�}�����̔��t�̓\�����������ĂčT���߁A�t�c�E���Ȃ��B
���Ƃ�Kreisler�̉����������������āA�nj��y���t�͂��ɂȂ��S�[�W���X�ł����B��ԍD���ȁu���̔߂��݁v�ɂ͂����Ղ舣�D�̏��t��������āA�\���͂����Ղ�X�^�b�J�[�g�B�i6:11/8.13/4:31/3:39/3:22/4:02/4:37�j
 Bach ���y�̕������� �iIgor Markevitch�ɂ��3�̊nj��y�Q�Ǝl�d�t�ɂ��ҋȔ�/1949-1950�j�`�N���X�g�t�@�[�E�����h�����W�[/�A�[�l���E�t�B��/*���~�E�{�[�f(v)/�_�[�N�E���C���X(cem)/�C�F���[���E�����[�����N(vc)/�n���X�E�t�@���E���[�l��(fl)�i1997�N�j�E�E�EWebern�ɂ��u6���̃��`�F���J�[���v����L�������ǁAIgor Markevitch�i1912�1983�G�����H�������j�ɂ��S�ȕҋȂ͒��ڂ��ׂ����́A����������̘^���i1956�N�j���������L���͂���������ǁA�������ĉ�����Ԃ̂�낵�����t�Œ����Ɗ����͂��������[�܂���́B Bach�͂ǂ�ȕҋȂ����Ă����y�̍��i�A�[���Ȃ閣�͕͂ς��Ȃ��BChristopher Lyndon-Gee�i1954-�p���j�̓W�~�ȑ��݂����ǁA��ȂƂ��Ă�����Ă���Ƃ̂��ƁB�����ȃg���I�E�\�i�^*�͂����炭�I���W�i���ɋ߂��A�_���ɃI�[�\�h�b�N�X�A��������������ł����B3���̃��`�F���J�[���i6:37�j/���ƕϑt�i0:29-1:06-1:09-0:38-0:35-0:33-0:31-2:19-2:03-3:20-4:27�j/�g���I�E�\�i�^���i5:05-6:27-3:02-1:06-3:42�j/6���̃t�[�K�i���`�F���J�[���j�i8:50�j
Bach ���y�̕������� �iIgor Markevitch�ɂ��3�̊nj��y�Q�Ǝl�d�t�ɂ��ҋȔ�/1949-1950�j�`�N���X�g�t�@�[�E�����h�����W�[/�A�[�l���E�t�B��/*���~�E�{�[�f(v)/�_�[�N�E���C���X(cem)/�C�F���[���E�����[�����N(vc)/�n���X�E�t�@���E���[�l��(fl)�i1997�N�j�E�E�EWebern�ɂ��u6���̃��`�F���J�[���v����L�������ǁAIgor Markevitch�i1912�1983�G�����H�������j�ɂ��S�ȕҋȂ͒��ڂ��ׂ����́A����������̘^���i1956�N�j���������L���͂���������ǁA�������ĉ�����Ԃ̂�낵�����t�Œ����Ɗ����͂��������[�܂���́B Bach�͂ǂ�ȕҋȂ����Ă����y�̍��i�A�[���Ȃ閣�͕͂ς��Ȃ��BChristopher Lyndon-Gee�i1954-�p���j�̓W�~�ȑ��݂����ǁA��ȂƂ��Ă�����Ă���Ƃ̂��ƁB�����ȃg���I�E�\�i�^*�͂����炭�I���W�i���ɋ߂��A�_���ɃI�[�\�h�b�N�X�A��������������ł����B3���̃��`�F���J�[���i6:37�j/���ƕϑt�i0:29-1:06-1:09-0:38-0:35-0:33-0:31-2:19-2:03-3:20-4:27�j/�g���I�E�\�i�^���i5:05-6:27-3:02-1:06-3:42�j/6���̃t�[�K�i���`�F���J�[���j�i8:50�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
���̏o���x���Ȃ��Ă�������ǁA�ҏ��p�����A���ފݖ��͌������C���͑��������ł��B�̒����܂��������o�e�̂܂T�����}���܂����B������A���Ă���z�c���x�����_�Ɋ�����������������萦�����A�X�g���b�`��YouTube�G�A���r�N�X�����߂āA�Ȃ�Ƃ��s���̈�ق������܂����B�����A�N���̎��ӎG������A�����͎R����̐������đ��������Ƃ���A�y�n���삦�Ă��邩�炻�̔ɖ͐���A�q��ɔB�������������̐A�������э��킹�Ĉ琬���y����ł�������ǁA��������ׂĊۖV��ɂȂ��Ă��܂��܂����B�V���o�[��1,500�~/���̃g���[�j���O���[���͏�A�����o�[�ɖ��t�A�g���}�V���͈������ł��܂���ł����B�̒��͓݂��d���̂ŃG�A���o�C�N�͍Œᕉ�ׂ�15���A���̑̒��Ȃ�Ƃ��Ȃ��̂��B���y�ɂ��܂������W���ł��܂���B�����̑̏d��67.4kg�{500g�A���̃A���p�����v�����B
���̃��C�h�V���E�ɉ^�]���u�X�}�z���́v�������b��ɂȂ��Ă���܂����B����͊������H�M���҂��ɂ����ڂɂ��܂���A�o�C�N�܂߂āB�l�Z������ʂ���ڂ������ʂقƂ�ǒ��ŏǏ�Ȃ�ł��傤�B�g���Œ��ł��X�}�z��������Ȃ��l�͂��������ڌ����܂��B���d���̘A�����Ȃ��A�Ǝv���Ă�������ǁA��x���R�ɉ�ʂ���������Q�[���ł����B��Ȃ��Ȃ��A����Ȃ��ƂŐl�g���̂��N��������ꐶ������܂���B
�������ŋ��k�����ǁA�V���o�[����ɂ͋�����܂����B
���V�����č��z�̒��̓L���b�V�����X
�ō�����ł���B
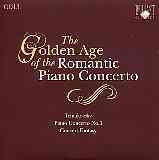 Tchaikovsky �s�A�m���t�ȑ�3�� �σz���� ��i75/79�i���C�E�h�E�t���}��/���N�Z���u���N�����nj��y�c�j/���t�I���z�� ��i56�i���`���[�h�E�J�b�v/�v���n�����y�c�j�`�}�C�P���E�|���e�B(p)�E�E�E����͔�Ȃ��W�߂�The Golden Age of the Romantic Piano Concerto���BMichael Ponti�i1937�2022���ė����j�̘^���̓��W���[�ɔ�VOX���S�A�����Ղ�Z�I�L���ɒ�������i�𑽂��^�����Ă��������܂����B�����炭��1970�N��̘^���A�����͂܂��܂��ł��傤�B��ɓ����f�ނ��g���������ȑ�7�� �σz�����iSemion Bogatyrev��M�����Łj���I�[�}���f�B�̘^���Œ���������ǁA�����f�ނ��g�����s�A�m���t���͑�2/3�y�͂�Sergei Taneyev�i1856-1915�I�����j���������������́B����͋M�d�Ș^���ł��傤�BLouis de Froment�i1921�1994�������j�͒��N�̗����Ո��D���i=���V�j�ɂ͉����������O�B�s�A�m���t�ȑ�1�� �σ������͖`���z�����̂Ԃ����܂��A�s�A�m�̋���Șa���ɂ��o�������܂�Ɉ�ۓI�A��������3������1�y���uAllegro Brillante�v���烊���J���ɉ��������������\���Ɗnj��y�����a���āA����������オ���Ă�����������Ɗ����܂��B�r���̃J�f���c�@�͂��܂�Ɉ�࣍��B�i14:16�j��2�y���uAndante�v�͗I�X�ƊÂ��������������̊ɏ��y�́B�`�F���⃔�@�C�I�����̃\������ۓI�����Ǐ��X�f���ɉ߂��ė슴�ɕs�����銴���B�s�A�m�݂̂��ƂȋZ�I�t���[�Y�͌��݂ł��B�i9:26�j��3�y���uFinale: Allegro Maestoso�v�͖��邭�A�ڂ܂��邵���������e�ނ悤�Ȏ����A�₩�ȃt�B�i�[�����}���܂����B�i7:52�j�I�[�P�X�g���͉����������̂Ȃ������B
Tchaikovsky �s�A�m���t�ȑ�3�� �σz���� ��i75/79�i���C�E�h�E�t���}��/���N�Z���u���N�����nj��y�c�j/���t�I���z�� ��i56�i���`���[�h�E�J�b�v/�v���n�����y�c�j�`�}�C�P���E�|���e�B(p)�E�E�E����͔�Ȃ��W�߂�The Golden Age of the Romantic Piano Concerto���BMichael Ponti�i1937�2022���ė����j�̘^���̓��W���[�ɔ�VOX���S�A�����Ղ�Z�I�L���ɒ�������i�𑽂��^�����Ă��������܂����B�����炭��1970�N��̘^���A�����͂܂��܂��ł��傤�B��ɓ����f�ނ��g���������ȑ�7�� �σz�����iSemion Bogatyrev��M�����Łj���I�[�}���f�B�̘^���Œ���������ǁA�����f�ނ��g�����s�A�m���t���͑�2/3�y�͂�Sergei Taneyev�i1856-1915�I�����j���������������́B����͋M�d�Ș^���ł��傤�BLouis de Froment�i1921�1994�������j�͒��N�̗����Ո��D���i=���V�j�ɂ͉����������O�B�s�A�m���t�ȑ�1�� �σ������͖`���z�����̂Ԃ����܂��A�s�A�m�̋���Șa���ɂ��o�������܂�Ɉ�ۓI�A��������3������1�y���uAllegro Brillante�v���烊���J���ɉ��������������\���Ɗnj��y�����a���āA����������オ���Ă�����������Ɗ����܂��B�r���̃J�f���c�@�͂��܂�Ɉ�࣍��B�i14:16�j��2�y���uAndante�v�͗I�X�ƊÂ��������������̊ɏ��y�́B�`�F���⃔�@�C�I�����̃\������ۓI�����Ǐ��X�f���ɉ߂��ė슴�ɕs�����銴���B�s�A�m�݂̂��ƂȋZ�I�t���[�Y�͌��݂ł��B�i9:26�j��3�y���uFinale: Allegro Maestoso�v�͖��邭�A�ڂ܂��邵���������e�ނ悤�Ȏ����A�₩�ȃt�B�i�[�����}���܂����B�i7:52�j�I�[�P�X�g���͉����������̂Ȃ������B
���t�I���z����Richard Kapp�i1936-2006���ė����j�̒S���B���̐l��VOX�^���ɂ͂悭�o�Ă���܂����B������1895�N�\����Sergei Taneyev�̃s�A�m�����������B�uQuasi Rondo: Andante Mosso�v�̓��[�����X�ɋC�܂���ȋȑz�������āA�\���͗Y�قɕ������悤�B����ȃJ�f���c�@�̓s�A�m���t�ȑ�1�Ԃɂ�������Ǝ��āA�v��������Z�I�I�B���̊y�͂����Ŋ������闧�h�ȋ��t�Ȃł���B�i14:44�j�uContrastes: Andante Cantabile�v�͊Â��Ȃ��A�u�A�����t�F�X�v���C���[�W������悤�ȐȂ������݁B�s�A�m�̃A���y�W�I�ɏ���Č����Ȃ��̂��āA�₪�Đ���₩�ȕ\��Ƀe���|�E�A�b�v�������܂����B�㔼��A�����ɂ��I�������z�������Q�����āA���̖q�̓I�ȉ��F�����܂�ʃ��[�J���F�ł����B�i13:15�j
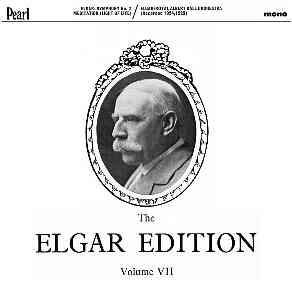 Elgar �����ȑ�2�� �σz����/�ґz���i�I���g���I�u�����̌��v���j�`�G�h���[�h�E�G���K�[/���C�����E�A���o�[�g�E�z�[���nj��y�c�i1924/25�N�j�E�E�E�ȑO�u���y�����v�Ɍ��y���Ă����悤�L��������������ǁA�ߋ����������Ă��o�Ă��Ȃ����^�N�b���BEdward Elgar�i1857�1934�p���j�͉p�����y���A��r�I�������Y���͂�����Ɨ͋����A䩗m�ƒ݂͂ǂ���̂Ȃ��`����ȉp�����y�Ƃ̓C���[�W�����X�قȂ�Ɗ����Ă���܂��B2023�NDVD��HDD�ɕۑ������f�[�^���ړ������鎞�ɁA��ȎҎ����̉����͂̓_�u�������Ȃ��A�Ȃ�ē��e�_�����Ă�����1910-20�N��^����1930�N�O��̘^���͕ʂ��̂Ə��߂ċC�t���܂����B ����͑O�ҁA�����h�������y�c�Ƃ̍Ę^���i1927�N�j�Ƃ͕ʕ��ł����B1911�N�����A�O�ǕҐ��ɂ��Y��Ȃ�����ȁB��������{�ł͂܂������l�C�̂Ȃ���i�B�A�R�[�X�e�B�b�N�^�����ȁH ���Ȃ茵������Ȃ����������ǁA����Ȃ�ɍ�i�≉�t�̗l�q�͗����\�ł����B�e���|�ݒ�ɂ͕����I�Ȑ������������Ƒz�����܂��B�����������̃|���^�����g������ł��傤�B�ނ��닻���[�������B
Elgar �����ȑ�2�� �σz����/�ґz���i�I���g���I�u�����̌��v���j�`�G�h���[�h�E�G���K�[/���C�����E�A���o�[�g�E�z�[���nj��y�c�i1924/25�N�j�E�E�E�ȑO�u���y�����v�Ɍ��y���Ă����悤�L��������������ǁA�ߋ����������Ă��o�Ă��Ȃ����^�N�b���BEdward Elgar�i1857�1934�p���j�͉p�����y���A��r�I�������Y���͂�����Ɨ͋����A䩗m�ƒ݂͂ǂ���̂Ȃ��`����ȉp�����y�Ƃ̓C���[�W�����X�قȂ�Ɗ����Ă���܂��B2023�NDVD��HDD�ɕۑ������f�[�^���ړ������鎞�ɁA��ȎҎ����̉����͂̓_�u�������Ȃ��A�Ȃ�ē��e�_�����Ă�����1910-20�N��^����1930�N�O��̘^���͕ʂ��̂Ə��߂ċC�t���܂����B ����͑O�ҁA�����h�������y�c�Ƃ̍Ę^���i1927�N�j�Ƃ͕ʕ��ł����B1911�N�����A�O�ǕҐ��ɂ��Y��Ȃ�����ȁB��������{�ł͂܂������l�C�̂Ȃ���i�B�A�R�[�X�e�B�b�N�^�����ȁH ���Ȃ茵������Ȃ����������ǁA����Ȃ�ɍ�i�≉�t�̗l�q�͗����\�ł����B�e���|�ݒ�ɂ͕����I�Ȑ������������Ƒz�����܂��B�����������̃|���^�����g������ł��傤�B�ނ��닻���[�������B
��1�y���uAllegro vivace e nobilemente�v�͗N���オ��p���[�����������āA�O�̂߂�ɃJ�b�R�悢�E�s�Ȏn�܂�B�e���|�ݒ�͒W�X�ƁA���ǂ��y��͂������ɏ��X�����ۂ������͎̂d�����Ȃ��B�i13:53�j
��2�y���uLarghetto�v�͈ßT�ɏd�X�����ɏ��y�́B�l�X�ƊÂ������݂��Ă͕Ԃ��āA��͐���オ��܂��B�i12:30�j
��3�y���uRondo: Presto�v�X�P���c�H�ɋ߂��y�₩�ɖ�������A�͋����y�́B�㔼�͂��Ȃ范���������𑝂��܂����B�i7:50�j
��4�y���uModerato e maestoso�v�͈��J�ɗ��������āA��������Ƃ������݂ɂ܂䂢�������i���L���鈳���̊����[���t�B�i�[���B�i12:40�j
�u�ґz�ȁv�͋����i�Ƃ��Ƀz�����j�������[�����Ɨ��ݍ����āA�Â��ɗD���������͂̂����������i�ł����B�i4:55�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
����ǂ͏�̑��i4�j���M���o���āA���[�a�͑�������o�|���Ă����܂����B���������傫���������ɍs���Ă���Ƃ̂��肢���A������c�O�ȑ̒��s�ǁA�Ǐ�͂܂��܂��������Ă���܂��B����A���͐�����ƃX�g���b�`��YouTube�G�A���r�N�X�����y�q�����s�A�N���Ă����Ȃ��قǁB���낢��l���Ă���͍R�A�����M�[�܂̕���p���v��������܂����B���͂���ւ��Ă�����Ƃ�����Ȃ��A���ɂ��Ђǂ��Ē��ɍܕ��p�����炿����҂胉�N�ɂȂ�܂����B���ς�炸����ȓ������p�����A����Ԃ̗\��ł͂₪�Ĉꎞ�J�Ƃ̂��ƁA�����͍~��Ȃ��Ɣ��f���ĕz�c�����͋��s�A�J�͗[���ȍ~�������̂ő��v�ł����B�ߑO�����֒f�̃G�A�R������āA�悤�₭�̒��͂�����҂藎�������܂����B�O��̍R�A�����M�[�܂��ꂽ�̂��B�����̑̏d��66.9kg�{300g���܂����Ă��Ȃ����ǁA�g�������Ă��Ȃ��ł�����B��b��ӌ������B
�I�B�̃h���t�@�������͐�D�̏T�����l�^�B���ړI�ȏ؋��͂Ȃ���ł���H���čٔ��̍s���͂ǂ��Ȃ邱�Ƃł��傤���B�����ɂ͂���Ȗ@�O�Ȃ鎑�Y�Ƃ͉����Ȃ��ėǂ������B
���d�����ނ��������`����Șb��́u���ޖ{�v�ɕK���o�Ă��܂��B�w�������4����y�i������ʎ��Ȃ��j�₪�ċ��R�ɂ��d����5�N�قǒS���ɂȂ��Ă�������e�����Ȃ������́A���ތ�G��ɖڊo�߂Ďs�̓W����Ȃǂɏo�W����Ă���܂��B64�ΌǍ��̖�F�͊C�O�T�㏬���̎���V���āA���̕]�_�{���o�ł��܂����i�A���A�Ȃ�₩���400���̏o��̓i�j�₯�ǁj������l�̖�F�͕���������ďZ�ݍ��ݎ���̎�Ń��m�x�[�V���������Ă���܂��B�F���h�I �����́E�E�E���w���ȗ��̉��y���Ȃ��A���w���Z�ƈꐶ�����M�^�[�Ȃ��e���Ă����̂́A���傤�ǂ���Ȑ��ゾ��������B�A�E������E��݂�ȂŃI���W�i����i������ėV��ł��܂��������B�₪�āA�N���V�b�N�i�q���j��ӓ|�Ɏ����ăl�b�g����ɂ́y�� KechiKechi Classics ��z�J��25�N�قږ����X�V�p�����E�E�E�������エ�d����ӓ|�̕��X�A���ތ�̕t���Ă��n�ł̎�͐g�ɂ��܂����B7-8�N�O�Ɏn�߂��X�|�[�c�N���u�b�B���K���p���蒅�ł��܂����B
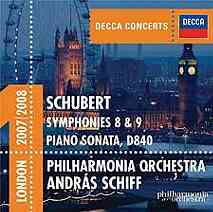 Schubert �����ȑ�9�ԃn�����`�A���h���[�V���E�V�t/�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�i2007-8�N���C���j�E�E�E���C�ɓ����i�Ȃ̂Ő������̉������肵�Ă���܂��B����͖��s�A�j�X�g�ł���Andras Schiff�i1953-�^�嗘���ґ������p���j�ɂ�鉉�t��C���B16:04-15:17-14:45-16:08 �e���|�͒��f�A���̉��t���Ԃ����Ă���������킩��悤�ɁA���Ȃ肵�����J��Ԃ����{���Ă���܂��B䩗m�I�g�Ƃ��Ĕ������������̂��X�P�[���傫�Ȗ��ȁA���N�̑勐���ɂ�鋐��Ȃ铩�����t���X�e�L�����A���Ґ��Êy��ɂ��f�p�ȃT�E���h�A�L���̂��鉉�t���D���B���̉��t�̓I�[�P�X�g���̑f���ȋ����ɉ߂��A�I�[�\�h�b�N�X�ȕ\���͈����Ȃ��E�E�E���ǁA�B�ꖳ��̌������߂�Ȃ�A������҂�I�������Ɍ�����̂����B����Ȋ��z���킪�܂܂��ґ�ł��傤�B
Schubert �����ȑ�9�ԃn�����`�A���h���[�V���E�V�t/�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�i2007-8�N���C���j�E�E�E���C�ɓ����i�Ȃ̂Ő������̉������肵�Ă���܂��B����͖��s�A�j�X�g�ł���Andras Schiff�i1953-�^�嗘���ґ������p���j�ɂ�鉉�t��C���B16:04-15:17-14:45-16:08 �e���|�͒��f�A���̉��t���Ԃ����Ă���������킩��悤�ɁA���Ȃ肵�����J��Ԃ����{���Ă���܂��B䩗m�I�g�Ƃ��Ĕ������������̂��X�P�[���傫�Ȗ��ȁA���N�̑勐���ɂ�鋐��Ȃ铩�����t���X�e�L�����A���Ґ��Êy��ɂ��f�p�ȃT�E���h�A�L���̂��鉉�t���D���B���̉��t�̓I�[�P�X�g���̑f���ȋ����ɉ߂��A�I�[�\�h�b�N�X�ȕ\���͈����Ȃ��E�E�E���ǁA�B�ꖳ��̌������߂�Ȃ�A������҂�I�������Ɍ�����̂����B����Ȋ��z���킪�܂܂��ґ�ł��傤�B
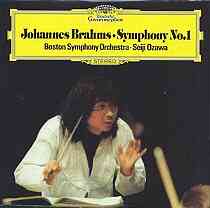 Brahms �����ȑ�1�ԃn�Z���`���V����/�{�X�g�������y�c�i1977�N�j�E�E�E42�̋L�^�B�I�[�f�B�I�ʂ̕��ɂ��Ɖ��t���Ă����A������CD���͂��܂��肭�s���Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB������Ȃn�����I�[�f�B�I���A�܂��܂��̉��������\�����V�A���Z�ҁB��N�̘^���͒����Ă��Ȃ�����ǁA���̎����Ȃ����c���2�ԃj���������Ȃ��͎̂c�O�B�{�X�g�������y�c�͔������C�i�����������āA�݂͂�d�����啗������������A�f���P�[�g�ɍו��Ă��˂��ɕ`������ł���͗�̔@���_�o���ȂقǁB��1�y���uUn poco sosutenuto-Allegro�v���瑬�߂̃e���|�ɗD��ȗh��ɐ����������ė]�T�A���J��Ԃ��͂Ȃ��B�i13:05�j��2�y���uAndante sosutenuto�v�͐����ɉ̂��ɏ��y�́B�i9:52�j��3�y�́uUn Poco Alegretto e Garzioso�v�̓X�P���c�H�ɔA�D��Ȋԑt�ȁB�����������Ɨ����ăG�G���B���B���B�b�h�����ǕK�v�ȏ�ɃA�c��������i5:08�j�����v�������ŏI�y���uAdagio-Allegro non troppo�v�̃N���C�}�b�N�X�Ɍ����������͂����ɂ���X���������Ƀe���|�E�A�b�v���ăt�B�i�[������߂�����܂����B�i16:48�j
Brahms �����ȑ�1�ԃn�Z���`���V����/�{�X�g�������y�c�i1977�N�j�E�E�E42�̋L�^�B�I�[�f�B�I�ʂ̕��ɂ��Ɖ��t���Ă����A������CD���͂��܂��肭�s���Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB������Ȃn�����I�[�f�B�I���A�܂��܂��̉��������\�����V�A���Z�ҁB��N�̘^���͒����Ă��Ȃ�����ǁA���̎����Ȃ����c���2�ԃj���������Ȃ��͎̂c�O�B�{�X�g�������y�c�͔������C�i�����������āA�݂͂�d�����啗������������A�f���P�[�g�ɍו��Ă��˂��ɕ`������ł���͗�̔@���_�o���ȂقǁB��1�y���uUn poco sosutenuto-Allegro�v���瑬�߂̃e���|�ɗD��ȗh��ɐ����������ė]�T�A���J��Ԃ��͂Ȃ��B�i13:05�j��2�y���uAndante sosutenuto�v�͐����ɉ̂��ɏ��y�́B�i9:52�j��3�y�́uUn Poco Alegretto e Garzioso�v�̓X�P���c�H�ɔA�D��Ȋԑt�ȁB�����������Ɨ����ăG�G���B���B���B�b�h�����ǕK�v�ȏ�ɃA�c��������i5:08�j�����v�������ŏI�y���uAdagio-Allegro non troppo�v�̃N���C�}�b�N�X�Ɍ����������͂����ɂ���X���������Ƀe���|�E�A�b�v���ăt�B�i�[������߂�����܂����B�i16:48�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�c���p�����B��m����䕗13���ڋߒ��B���������˓����ɍō��C��35�xC���オ���āA������c���o�e���p�����B���������̎��@�Ȃ̏������������ʔ����O��r���o���A������g�̂��d�������B������ς܂��ăX�g���b�`�AYouTube�G�A���r�N�X��15���قǂ̃{�N�T�T�C�Y�A����ɂ͊��ǂ�ǂ�A�V�����[���g���Ďs���̈�ق�ڎw���܂����B�O��͋g���}�V����픲�����̂ŁA�܂����̃n�C�v�[���[������{�E�E�E�����̕��ׂȂ̂ɂ��ꂪ���ɏd���E�E�E�����̉䗬���j���[���Ȃ�Ƃ����Ȃ�������ǁA�ǂ���ꂵ���̂͑̒��̂����ł��傤�B�G�A���o�C�N15�����h���������B�A��A�������Ɋ�炸�A�����d���������A������܂����B���Ƃ͏I����������A��ԁB����������A�̒��͂ǂ���d�ꂵ�������B�̏d��66.6kg��300g�B
���d���������㖘���������V�����n�ǂ��Ă�������ǁA���ޓ]�����@�ɍw�ǂ���߂܂����B����͎�ɐV�����̎n�����C�ɂȂ�������A�^�u���b�g����肵�ăf�B�W�^���łɕύX�\�肪�������傭���̂܂܂ɂȂ��Ă��܂��܂����B������ƃm�[�~�\�������S�z�ł��B�l�b�g�j���[�X�͂܂������Ӗ�����������āA�قƂ�ǂ��ϑ��C���A�l�q���������m�F����悤�Ȃ��́B�L���������B�u�n���X���g�����v���v�̋L�������A���Ȑ^���͂킩��Ȃ��B����͐V���ł����������B���ɁE�֓��m�����u�������猃�㑽���v������Ăق�܂ł����H
��錧��胋�C�E���B�g���P�ޕA�͂��A�����ł������x�B�����̐����ɂ͂��������̊W���Ȃ�����ǁA����������̓|�Y���������Ƃ��A���̕ĕs���ɒl�グ�ɕĔ_�Ƃ̔p�Ƃ��������Ă���Ƃ��A�K�\�����X�^���h�͔N��500�قǕX���Ă���Ƃ��A���̕ӂ�͐��������̘b��B�Ă�y�b�g�{�g���̐��s���͌�������A���x�ꂽ�Ɗ����܂��B�ĕs�������������ӂ�A���̑啝�l�グ��\����������ǁA���̂��Ƃ��͒x�������B����؎��{�̌|�\�l�̊����͂�낵������ǁA�s�ˎ��ւ̂������o�b�V���O�͒��X�ɂ��ė~�����B������܂����������͂Ȃ��Ƃ������A�N���N�����Ȃ��Ȃ���ʂ����Ȃ��B
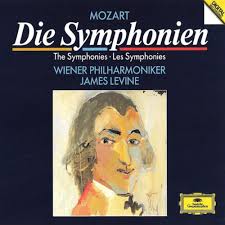 Mozart �����ȑ�36�ԃn���� K425�u�����c�v/�����ȑ�38�ԃj���� K504�u�v���n�v�`�W�F�[���Y�E�����@�C��/�E�B�[���E�t�B���i1984-1990�N�j�E�E�E2�N�Ԃ�̔q���BJames Levine�i1943�2021���ė����j�ɂ��E�B�[���E�t�B���Ƃ̑S�W�^�����B�Ό��z�u�A�J��Ԃ����{�͂��肪�����B��������I�Ɂh�E�B�[���E�t�B���ɂ��Mozart�����ȑS�W�^���I�h�͂��ꂪ���X�g�����B�Êy��ɂ�锬���y���ȃ��Y�����D�������ǁA�Ă��˂��Ȏd�グ�͗D��ɗ݂͂̂Ȃ��I�[�\�h�b�N�X�A����Ȓ��f�ȉ��t�������Ȃ����̂ł��B�ÓT�I�ɒ[�����u�����c�v�͂ǂ��ɂ��������Ȃ��A�����ďI�y�́uPresto�v�ɂ͖��x���������܂����B�i10:45-13:33-4:31-11:04�j�B�������Ƃ������t���琰��₩�Ȗ������n�܂��u�v���n�v�͌��삼�낢��Mozart�����Ȓ���Ԃ̂��C�ɓ���B�̂т̂тƂ��Đ��X�����m��������܂����B�i17:41-11:33-7:45�j�B
Mozart �����ȑ�36�ԃn���� K425�u�����c�v/�����ȑ�38�ԃj���� K504�u�v���n�v�`�W�F�[���Y�E�����@�C��/�E�B�[���E�t�B���i1984-1990�N�j�E�E�E2�N�Ԃ�̔q���BJames Levine�i1943�2021���ė����j�ɂ��E�B�[���E�t�B���Ƃ̑S�W�^�����B�Ό��z�u�A�J��Ԃ����{�͂��肪�����B��������I�Ɂh�E�B�[���E�t�B���ɂ��Mozart�����ȑS�W�^���I�h�͂��ꂪ���X�g�����B�Êy��ɂ�锬���y���ȃ��Y�����D�������ǁA�Ă��˂��Ȏd�グ�͗D��ɗ݂͂̂Ȃ��I�[�\�h�b�N�X�A����Ȓ��f�ȉ��t�������Ȃ����̂ł��B�ÓT�I�ɒ[�����u�����c�v�͂ǂ��ɂ��������Ȃ��A�����ďI�y�́uPresto�v�ɂ͖��x���������܂����B�i10:45-13:33-4:31-11:04�j�B�������Ƃ������t���琰��₩�Ȗ������n�܂��u�v���n�v�͌��삼�낢��Mozart�����Ȓ���Ԃ̂��C�ɓ���B�̂т̂тƂ��Đ��X�����m��������܂����B�i17:41-11:33-7:45�j�B
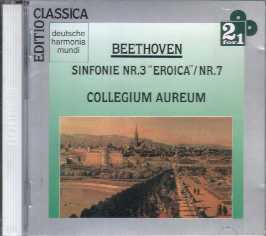 Beethoven �����ȑ�3�� �σz�����u�p�Y�v�`�R���M�E���E�A�E���E�����t�c/�t�����c���[�t�E�}�C���[�i�R���T�[�g�}�X�^�[�j�i1976�N�j�E�E�E2006�N���̍Ē��B���������Êy���Beethoven�͈�ʓI�ł͂Ȃ���������B�w�p�I�ɍׂ������Ƃ͒m��Ȃ�����ǁACollegium Aureum�i��������1962-�H�j�͌��y��Ƀ��B�����[�g���|���Ă�����A���@�C�I�����E���B�I���ɕI���Ă��t���Ă�����A�Êy��t�@��y��̈����͒��r���[�����������B���̒c�̂��i�^���ł́j�����̐l�X�Ɉ�����A���݂ł��l�C������悤�ł��B�S�̂ɉ��F�T�E���h�͑f�p�Ȋ����B�o�������͏d������Q���̖��J�����������Ȃɂ͏Ռ��\���I�������炵�����ǁA��̌Êy��n���t�̂悤�ɃG�b�W�𗧂Ă��������Y���ɔA�����ɂ������������������A�S�̂ɃI�[�\�h�b�N�X�ȕ\����21���I�̎��ɂ͂�����ƃt�c�E�Ȉ�ۂɎ����������m��܂���B��2�y�́uAdagio assai�v�����s�i�ȕӂ�A�Ȃ��Ȃ������ɖ��킢����Ǝv�����ǂ��ǂˁB�����̈����I�[�f�B�I�����Ă����A�����I�ɂ͂��Ă̋P���������܂���ł����B�i18:33-14:08-5:56-11:34�j
Beethoven �����ȑ�3�� �σz�����u�p�Y�v�`�R���M�E���E�A�E���E�����t�c/�t�����c���[�t�E�}�C���[�i�R���T�[�g�}�X�^�[�j�i1976�N�j�E�E�E2006�N���̍Ē��B���������Êy���Beethoven�͈�ʓI�ł͂Ȃ���������B�w�p�I�ɍׂ������Ƃ͒m��Ȃ�����ǁACollegium Aureum�i��������1962-�H�j�͌��y��Ƀ��B�����[�g���|���Ă�����A���@�C�I�����E���B�I���ɕI���Ă��t���Ă�����A�Êy��t�@��y��̈����͒��r���[�����������B���̒c�̂��i�^���ł́j�����̐l�X�Ɉ�����A���݂ł��l�C������悤�ł��B�S�̂ɉ��F�T�E���h�͑f�p�Ȋ����B�o�������͏d������Q���̖��J�����������Ȃɂ͏Ռ��\���I�������炵�����ǁA��̌Êy��n���t�̂悤�ɃG�b�W�𗧂Ă��������Y���ɔA�����ɂ������������������A�S�̂ɃI�[�\�h�b�N�X�ȕ\����21���I�̎��ɂ͂�����ƃt�c�E�Ȉ�ۂɎ����������m��܂���B��2�y�́uAdagio assai�v�����s�i�ȕӂ�A�Ȃ��Ȃ������ɖ��킢����Ǝv�����ǂ��ǂˁB�����̈����I�[�f�B�I�����Ă����A�����I�ɂ͂��Ă̋P���������܂���ł����B�i18:33-14:08-5:56-11:34�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
���ς�炸�̖ҏ������A��m��p�j���Ă���䕗�̌��͂��������Ɍ������J�ƔM�C�������炵�Ă���炵���B�O��r���o���A�����s�@�ӂɂ������肵�A����A�X�g���b�`�A10���قǂ�YouTube�G�A���r�N�X�͂����ǂ�����{�B�����ČߑO10���ɂ���5kg�͓͂��܂����B���ەĔ�3�I�}�P�t���B�l�i�͂������肷����̂̔{�ł��ˁB���������̂ł���A�����͂��̎��ۂɂ����Ԃ�Ɨ�W�Ɗ����܂��B�Ǐ��������P���Ȃ��̂Ŏ��@�Ȃ̗\������ė[���ʉ@�A���傤�Ǔy���~�肪����Ă��܂����B�����̑̏d��66.9kg��200g�܂��܂��B
�i����̑����j�ݓ��؍��l4���̏����������l�U�� �ɉœ��肵�����ǂ��O�l�A���{�Ɉ���ē��{�H������Ȃ������ė��A�蓮������܂����E�E�E���ǁA���ɃR�����g�Łu���{�l�ł��Ȃ��̂Ɂv�ƐS�Ȃ����e����������A�؍��̂��F�B���������ē��{�H�����\���铮��Ɂu�}�i�[�]�X�v���ׂȃP�`��t���āA����폜�ɒǂ����܂ꂽ�肵���悤�ł��B������āA�ق�̈ꕔ�̐S�Ȃ��l�ł��傤�B�C����������ق��Č��Ȃ�������ǂ��̂Ɉꌾ�]����������ȁB�����͊؍����Ƃ��ׂD���ł��Ȃ�ł��Ȃ�����ǁA�K�����ē��{�����\���Ă���������X�͊��}���������́B
���ʓI�������ł������e�ł��Ȃ��̂͌��߂����C�����͂���̂ł��傤�BSNS��̓����R�����g�ɂ͔�排����⋕�U�������Ƃ̂��ƁB�����œ��X�Ǝ����̎咣���J���������͂܂��}�V�i���Ƃ̗ǂ��������Ă����j�����Ŏv������A�J�����炵�ɂЂǂ����Ƃ������U�炵�āA�������ƍ폜�B�F�X�o�܂������Ĉꕔ���̔��M�������肳��A�g���𖾂炩�ɂ��Ȃ����Ƃ������ɏڍf���ƁA�y���C�����ŏ������A�������ƍ폜����o���Ȃ��A�b��������Ɛ����Ă��܂����A���C�͂Ȃ������Ƃ̋L����q�����܂����B�����ꂽ���̓^�C�w���Ȑ��_�I�����I�Ō��ł���B
������ĂȂ�ł���H��̕��Ɍ��m���Ƃ��ƒ���\�́A�E��̃p���n�����u�w���v�u���������ɓ����v�ƐM���Ă���l�ɋ߂��̂��A����Ƃ�����Ȃ�J�����炵�A���ɋ߂��S��Ȃ̂��B�����ɂ��ŋߖ������Ă������ȁA���܂��낵����ʓ��{�̕����Ɗ����ĈÞȂƂ��Ă���܂��B���x������������ǁA�R���i�����Ɂu������ƔM�ۂ���������ǁA�X�|�[�c�N���u�s�������s�����v�Ɓu���y�����v��������u���Ȃ��̃T�C�g�ɂ͓�x�ƖK�₵�Ȃ��v�Ƃ��i�����ғ����Ă����jBBS�ɂ��Ă��˂��ɏ������݂�����܂��������B����͎��l�x�@�̗��ꂾ�����̂��B�������Ă��邯��ǁu����͖�������K�v�͂Ȃ��v�v��ʂǂ��ł��ǂ��悤�ȗ]�v�Ȃ����b�������݂������������A���Ȃ����l�H�ォ��ڐ��ɂ͎Q��܂����B�܁A��排������ʓI�U���I������肸���Ɖ�������₯�ǁB
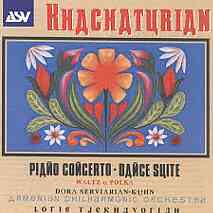 Khachaturian �s�A�m���t�� �σj����/���t�y�̂��߂̃����c/���t�y�̂��߂̃|���J/�����g�ȁ`�����X�E�`�F�N�i���H���A��/�A�����j�A�E�t�B��/�h�[���E�Z�����@���A�����N�[��(p)�i1995�N�j�E�E�EASV��Universal�ɐg���肵�Ă�����ł��ˁBLoris Tjeknavorian�i1937-�ɗ��j�͈����l�A�۔[�Ɋw�щp���Ŋ��A�₪�ăA�����j�A�E�t�B����C���ꂽ�̂�1989�N���炾�����B�N��I�ɂ͂������ނ���Ă��邱�Ƃł��傤�BDora Serviarian Kuhn���t�b�c�o�g�̂�͂舟���l�AKhachaturian�͓��ӂ̍�i�̂悤�ł��B�t�@���L�[�ȃ��Y���ƃI���G���^���ɓD�L�������ɏ[�������f�����t���͑�2�y�́uAndante con anima�v�ɗd�����t���N�T�g�[�������҂�������ǁA�����ł͗p�����Ă��Ȃ��悤�ł��B�N���ȉ����ƃL���̂���s�A�m���͂��Ƃ���قǐV�N�A���t���̂��̂͂������ēD�L���킯����Ȃ��B�i13:46-10:15-9:18�j���]�R�����g��q������Ɓu�������ɂ���肢�I�[�P�X�g������Ȃ��v�Ƃ��邯��ǁA�������Ȃ��B�ȉ��������u�����c�v�u�|���J�v�ӂ�Ƃ��Ă����������A�Ȃ�Ɗy�����ɓ��₩�Ȗ��킢�n�̉��t�B�i1:52-1:09�j�����g����������i�����ǁA�N�ł��m���Ă���Khachaturian�̐������Y���E�p�^�[�����Ȃ�Ƃ��c�ɏL�����������āA�̂̉f�批�y�݂����B�����E�p�^�[���ƌ������̒ʂ�A���B���B�b�h�ɑ�O�I�� Trans-Caucasian Dance�i4:10�jArmenian Dance�i4:34�jUzbek Dance Tune�i8:54�jUzbek March�i2:42�j Lezghinka�i2:47�j���t�Z�ʂ͂������ŖJ�߂Ă������������B
Khachaturian �s�A�m���t�� �σj����/���t�y�̂��߂̃����c/���t�y�̂��߂̃|���J/�����g�ȁ`�����X�E�`�F�N�i���H���A��/�A�����j�A�E�t�B��/�h�[���E�Z�����@���A�����N�[��(p)�i1995�N�j�E�E�EASV��Universal�ɐg���肵�Ă�����ł��ˁBLoris Tjeknavorian�i1937-�ɗ��j�͈����l�A�۔[�Ɋw�щp���Ŋ��A�₪�ăA�����j�A�E�t�B����C���ꂽ�̂�1989�N���炾�����B�N��I�ɂ͂������ނ���Ă��邱�Ƃł��傤�BDora Serviarian Kuhn���t�b�c�o�g�̂�͂舟���l�AKhachaturian�͓��ӂ̍�i�̂悤�ł��B�t�@���L�[�ȃ��Y���ƃI���G���^���ɓD�L�������ɏ[�������f�����t���͑�2�y�́uAndante con anima�v�ɗd�����t���N�T�g�[�������҂�������ǁA�����ł͗p�����Ă��Ȃ��悤�ł��B�N���ȉ����ƃL���̂���s�A�m���͂��Ƃ���قǐV�N�A���t���̂��̂͂������ēD�L���킯����Ȃ��B�i13:46-10:15-9:18�j���]�R�����g��q������Ɓu�������ɂ���肢�I�[�P�X�g������Ȃ��v�Ƃ��邯��ǁA�������Ȃ��B�ȉ��������u�����c�v�u�|���J�v�ӂ�Ƃ��Ă����������A�Ȃ�Ɗy�����ɓ��₩�Ȗ��킢�n�̉��t�B�i1:52-1:09�j�����g����������i�����ǁA�N�ł��m���Ă���Khachaturian�̐������Y���E�p�^�[�����Ȃ�Ƃ��c�ɏL�����������āA�̂̉f�批�y�݂����B�����E�p�^�[���ƌ������̒ʂ�A���B���B�b�h�ɑ�O�I�� Trans-Caucasian Dance�i4:10�jArmenian Dance�i4:34�jUzbek Dance Tune�i8:54�jUzbek March�i2:42�j Lezghinka�i2:47�j���t�Z�ʂ͂������ŖJ�߂Ă������������B
 Ravel �o���G���y�u�_�t�j�X�ƃN���G�v�i�S�ȁj/����Ŋ����I�ȃ����c�`���V����/�{�X�g�������y�c/�h�D���I�E�A���g�j�[�E�h���C���[(fl)/�^���O���E�b�h���y�Ս����c�i1973�N�j�E�E�E�{�X�g�������y�c�̉��y�ēɏA�C��������A����30�Α�̋L�^�B�����LP���ォ��̓���݂ł����B�������������ׂ�������������ł���̂��H�k������࣍����u�_�t�j�X�v���f���P�[�g�ɁA�ו����_�o���Ȃقǐ��m�ɕ`������ŁA���߂̃e���|�A�O�̂߂�̕������悤�ȎႢ���������������鉉�t�B�����̋L���ł͐��^�ʖڂɉ߂��āA�]�T�ƐF�C�ɕs������E�E�E���傤��50�N���o�A���݂Ɏ����ĉ�������낵�����A���̐����ȃt���[�W���O���ނ���D�܂������\�������܂����B�{�X�g�������y�c�͑@�ׂȐF�ʂ����������āA���͂��[���B�i��1��/2:37-2:12-2:30-0:53-0:59-0:45-2:25-2:29-1:41-1:15-1:42-1:23-3:01/��2��/2:55-2:03-1:48-3:27-0:22-1:53-5:06-2:01-3:58-0:58-3:21�j
�u�����c�v�����l�A�������萳�m�Ƀ��Y�������ނقǂɍ�i�̃I���������ۗ������B�i1:25-2:36-1:28-1:26-1:00-2:52-4:28�j
Ravel �o���G���y�u�_�t�j�X�ƃN���G�v�i�S�ȁj/����Ŋ����I�ȃ����c�`���V����/�{�X�g�������y�c/�h�D���I�E�A���g�j�[�E�h���C���[(fl)/�^���O���E�b�h���y�Ս����c�i1973�N�j�E�E�E�{�X�g�������y�c�̉��y�ēɏA�C��������A����30�Α�̋L�^�B�����LP���ォ��̓���݂ł����B�������������ׂ�������������ł���̂��H�k������࣍����u�_�t�j�X�v���f���P�[�g�ɁA�ו����_�o���Ȃقǐ��m�ɕ`������ŁA���߂̃e���|�A�O�̂߂�̕������悤�ȎႢ���������������鉉�t�B�����̋L���ł͐��^�ʖڂɉ߂��āA�]�T�ƐF�C�ɕs������E�E�E���傤��50�N���o�A���݂Ɏ����ĉ�������낵�����A���̐����ȃt���[�W���O���ނ���D�܂������\�������܂����B�{�X�g�������y�c�͑@�ׂȐF�ʂ����������āA���͂��[���B�i��1��/2:37-2:12-2:30-0:53-0:59-0:45-2:25-2:29-1:41-1:15-1:42-1:23-3:01/��2��/2:55-2:03-1:48-3:27-0:22-1:53-5:06-2:01-3:58-0:58-3:21�j
�u�����c�v�����l�A�������萳�m�Ƀ��Y�������ނقǂɍ�i�̃I���������ۗ������B�i1:25-2:36-1:28-1:26-1:00-2:52-4:28�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
������̑��͔M���o���Ē���Ԕk�����i=���[�a�j�ً͋}�o���B�ҏ��̒��^�C�w�������ǁA�����͂����ǂ���̃m���r�������ł����B�b�x���i����͂��Ă����j���Ɍ��c��c���͂��ׂẲ�h�����m�����C�����߂������B�c�O��Ȃ��A�ېV�͂����ƔS���ė~���������B�K���֓����F�m���͉��߂đ�����\�����Ă��̋��S���͂����ς�A�Ƃ��Ƃ�撣���Ď��Ԃ��|���Ă�����s����A�������萢�Ԃɔ����̂��Ƃɔ��i����j���Ăق������́B�J���^���ɓ����Ă�����Ă͍���B���Ď��͒N�ł��傤���B�B
���ς�炸�̎E�l�ҏ������ǁA�̒��͂����P�X���B����Ԃ̐�����u���A�X�g���b�`��������ς܂��āAYouTube�G�A���r�N�X�ĊJ�B�����Ďs���̈�قɂ������肢���ʂ�̋g���{�G�A���o�C�N15�������B�A���A�n�C�v�[���[�͋����Ȃ�������ɒ����ԓƐ肳��ė��p�ł��܂���ł����B�n�[�h�Ń}�b�`���Ȉ��D�҂͂ǂ������̎{�݂ɍs���Ă�����āA�킪�܂܉]���Ό����{�݂͉��h�E�V���E�g�ɏ����Ă�������ʂ��B�h�W���[�Y�̑�J����͉����݂����ł��ˁB�����̑̏d��67.1kg��700g�B
�؍��̏������������ē��{�������ł������铮���͊��������́B�^�C�w���ȋ�J������ĒE�k���Ċ؍��ցA�����炭�͗T���ȕ��ƌ������ꂽ�̂ł��傤�B�Ȃ�ƁI�k���N�ł��i�����j���{������ǁA���{���i�ɑ�����Ȃ�i���M�����Ă��Ƃ̂��ƁB�����𒆐S�Ɋ��x���K�₳��A�k���N�ł̋ꂵ�������A�ٗl�Ȕ�������ƌ����̈Ⴂ�ɋ����A���{�̗����ɐ�ۂ�łp�͐M���ł��܂��B���͂����̍��A���{�̂��Ă����������ƖJ�߂���A����͂ق�܂ł��傤�B�\����Ȃ�����ǁA���Ă̕��ɂ��Ă̖��A���̖��A�����̖��A���������Ď��i�����[�������A���̔����Ȗ��o�͂�����҂�^���Ă���܂��B����ɂ͓��{�ꎚ�����t���Ă��āA�����炭��Google�|����ł��傤�B�|��͖Œ��ꒃ�A���ƒ�͍������Ă��邵�A���i�Ǝh�g�A�V���[�}�C���L�q�̋�ʂ͕t���܂���B���q���|�͎��ɍs���s���`����ł����{�����\���Ă���p�͂������藝���ł���B���{�ꂨ���������I ����ȓ˂����ݓ������͂���������Ȃ��͂��B�i����Ɋ֘A���銴�S�����L�j
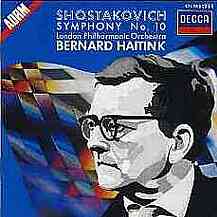 Shostakovich �����ȑ�10�ԃz�Z���`�x���i���g�E�n�C�e�B���N/�����h���E�t�B���i1977�N�j�E�E�E���̍�i�̓I�[�P�X�g���̋Z�ʃp���[�K�{�ȓ����i�B�O�ǕҐ��ł����H�Ґ��͎v�������傫���Ȃ�����ǁA�Ŋy���7��L�B�J�����������グ����i�Ƃ��Ă��L���ł��傤�B���̍�i�̓J�b�R�ǂ��Ɗ�����悤�ɂȂ��Ă�������D���ɂȂ�܂����BBernard Haitink�i1929�2021�����Ɂj�͐����ł͔�r�I���߂ɑS�Ȃ�^�����Ă����̂ł��ˁB�����h���E�t�B���͖��邭�f���ȃT�E���h�A��肢�I�[�P�X�g���ł����B
Shostakovich �����ȑ�10�ԃz�Z���`�x���i���g�E�n�C�e�B���N/�����h���E�t�B���i1977�N�j�E�E�E���̍�i�̓I�[�P�X�g���̋Z�ʃp���[�K�{�ȓ����i�B�O�ǕҐ��ł����H�Ґ��͎v�������傫���Ȃ�����ǁA�Ŋy���7��L�B�J�����������グ����i�Ƃ��Ă��L���ł��傤�B���̍�i�̓J�b�R�ǂ��Ɗ�����悤�ɂȂ��Ă�������D���ɂȂ�܂����BBernard Haitink�i1929�2021�����Ɂj�͐����ł͔�r�I���߂ɑS�Ȃ�^�����Ă����̂ł��ˁB�����h���E�t�B���͖��邭�f���ȃT�E���h�A��肢�I�[�P�X�g���ł����B
��1�y�́uModerato�v�͟T�X���X�Ƒ�����������捂Ɣ����A���̎㉹�𖾝��ɁA�e���V�����ێ����Ē�������͎̂���̋ƁB�����̓����h���E�t�B���̒n�͂��������ăN�����l�b�g���z�����������f���ȉ��F�A�D�L����d�ꂵ���̏��Ȃ��N�[���ɑ���̂Ȃ��A���邢�����Ɏd�グ�Ă킩��₷���B���ǁA������Ɛ��^�ʖډ߂��ɐ^�������A��������Đ��m�Ȑ���オ��̓n�C�e�B���N�̌��ł��傤�B���������D���B�i24:22�j
��2�y�́uAllegro�v�̃p���t���ȑ唚���ɂ̓I�[�P�X�g���̐ꖡ�K�{�B�����̐��i�́A���ǂ̃N���A�ȑ唚���Ə����ۂɂ�鐳�m�Ȉ�Ďˌ��͂̓��E���c�ɃJ�b�R�悢���́B�����̃T�E���h����������Ĉ����̃L���A�pDECCA�̉��������ʓI�ɃN���A�����́B�i4:03�j
��3�y�́uAllegretto�v�͂Ƃ��Ă��������A�E�͂��݂ɓr���ɕ�ꂽ�����d���ɏ��y�́BMahler�u��n�̉́v���z���������������x���ؗ삵�āA���ԕ��̃N���C�}�b�N�X�͖��邭�A�L���������ăe���V�����̍����M�C�̑Δ�������ǂ���ł��傤�B�i12:23�j
��4�y�́uAndante - Allegro�v�t�B�i�[���̏��t�͑O�y�͂̈ßT�Ȑ�捂��������p���ŁA�Ƃ��Ƀt�@�S�b�g�����鐣�Ȃ��B�₪�ăN�����l�b�g�ɓ�����Čy���ɖ��邢�f���P�[�g�Ȑ����o��A����̓m���m���̐�������������1���A���̂�����̃T�E���h�͂ƂĂ���������Ă���Ɗ����܂��B�₪�Ă����ɂ��I�������̐��������C���M�C�������āA�Â��ȑ�2���͒Z���A��1��肪�����A���̕ӂ�̓]���͑N�₩�ł���A�؊Nj��ǂ̃_�������͈����̃p���[�̂����ɏI���B�i13:41�j
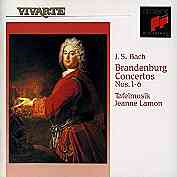 Bach �u�����f���u���N���t�ȏW�`�W�[���E������(v)/�^�[�t�F���E���W�[�N/�V�������b�g�E�j�[�f�B�K�[(cem)�i1993�N�j�E�E�E2019�N���̍Ē��B�^�[�t�F���E���W�[�N�̓g�����g�̌Êy��c���i1979�N�n�݁jJeanne Lamon�i1949�2021���ė����j��1981�N���R���}�X�A���y�ēA�C�i�`2012�N���j���̑O�Ƀt���b�c�E�u�b�V���̑��Ø^�����������ȂĂ�����҂�q����������ǁA��͂�s�J�s�J�̉����A�Êy��̌y���ȃ��Y���͑u���A�����ɂƂ��Ĉ�Ԃ̂��C�ɓ����i�𐴁X�����C�����ł����Ղ芬�\�������܂����B��a���̂Ȃ��e���|�ݒ�A�]�T������������Êy��̃��Y���A�e�p�[�g�̋Z�ʂ͂��̎��_���S�ɏn�����A�f�p����艐������������T�E���h�ɖ�������܂����B���R�Ȏc���L���ɍō��̉����B
Bach �u�����f���u���N���t�ȏW�`�W�[���E������(v)/�^�[�t�F���E���W�[�N/�V�������b�g�E�j�[�f�B�K�[(cem)�i1993�N�j�E�E�E2019�N���̍Ē��B�^�[�t�F���E���W�[�N�̓g�����g�̌Êy��c���i1979�N�n�݁jJeanne Lamon�i1949�2021���ė����j��1981�N���R���}�X�A���y�ēA�C�i�`2012�N���j���̑O�Ƀt���b�c�E�u�b�V���̑��Ø^�����������ȂĂ�����҂�q����������ǁA��͂�s�J�s�J�̉����A�Êy��̌y���ȃ��Y���͑u���A�����ɂƂ��Ĉ�Ԃ̂��C�ɓ����i�𐴁X�����C�����ł����Ղ芬�\�������܂����B��a���̂Ȃ��e���|�ݒ�A�]�T������������Êy��̃��Y���A�e�p�[�g�̋Z�ʂ͂��̎��_���S�ɏn�����A�f�p����艐������������T�E���h�ɖ�������܂����B���R�Ȏc���L���ɍō��̉����B
��1�ԃw���� BWV1046�@���ڂ̓z�����̋Z�ʂ̑N�₩�Ȃ��ƁB�e���|�ݒ�͓K�������������闎�����������́B�i4:12-3:40-4:09-7:29�j
��2�ԃw���� BWV1047�@�g�����y�b�g�̋Z�ʂ̓X���[�X�B�e���|�͍Q�Ă��K�������������܂����B�i5:20-3:25-3:05�j
��3�ԃg���� BWV1048�@�o�����X�̂�낵�������Ȍ��y�A���T���u���B��2�y�͂͒Z�����@�C�I�����E�\��������܂����B�i5:59-4:47�j
��4�ԃg���� BWV1049�@���R�[�_�[�̐����ȉ��F�A���@�C�I�����̒���Z�I�ɒ��ځB�i6:53-3:11-4:50�j
��5�ԃj���� BWV1050�@�m���E���B�����[�g�̃t���[�g�̉��F���ۂ��Ă�ۂ��i�\���X�g�͓���ł����j���@�C�I�����E�\���͐���₩�ȕ\��B�`�F���o���͍T���߁A���ꂪ�{���̃o�����X�Ȃ̂����B�i10:10-5:02-5:11�j
��6�ԕσ����� BWV1051�@���@�C�I�����͔����Ă����߂̃e���|�ɉ����A����̂�낵�����Y�����ł����B�i6:07-4:25-5:38�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
������j���c���o�e�p���ǂ��납�������B������ăX�g���b�`���āE�E�EYouTube�G�A���r�N�X���{���錳�C���o�܂���B�N���オ�ꂸ���y�����炭���ɂȂ��Ă���܂����B�O�������珊�v�ɏo�|���鏗�[�a�ɂ��肢���āA�����X�[�p�[�ɂ��Ă��������甃���Ă����Ă˂Ƃ��肢��������ǁA��͂�I�͂������炩��B���낲�낵�Ă��Ă��d�����Ȃ��ƈӂ������āA���������˓����̒��ʂ̃X�[�p�[�ɃE�H�[�L���O�֏o���B��͂�Ă̒I�ɂ͂Ȃɂ��Ȃ��āA�l�D���i�����I�j���u����l�l��܁v�̒��莆�̂ݎc���Ă���܂����B�䂪�Ƃ̕čɂ͎c���T�Ԃ��炢���Ȃ��A�Ԃɍ����̂��B���̒��̑����̉ƒ�͍����Ă邱�Ƃł��傤�B�H�א���̂��ǂ�������Ƃ̓^�C�w���B�l�b�g�ʔ̂Ɏ���o���܂����A���Ȃ肨�������ǁB���������\��B�ق�܂��B���̒��J�l����Ȃ̂��B�����̑̏d��67.8kg�{200g�����ǂ����傤������܂���B
�����������q�����Ă�����{�ʂ̊O���l�̓���ɂ͂��낢��h����������������̂ł��B�g�C�����L���C�A���i���������A�R���r�j���֗��Ƃ����肪���̘b��ɔA������{�̐��������Ă��ē�����O���Ǝv���Ă��邱�Ƃ����͋M�d�ł��邱�ƂɋC�t�����Ă��������܂��B���x�J��Ԃ�����ǁA�g�C����X�H�̔������A��捂⎡���̗ǂ������N�̓��X�w�͉��P�̐ςݏd�˂̌��ʂ�����A���f��G�B���̂Ȃ��ł̔����ЂƂB���{�l�͊O���l�̓��{��Ɋ��e�ł���A������ƃJ�^�R�g�Łu�A���K�g�S�U�C�}�X�v���u���{�ꂨ���I�v����͂��Ȃ������Ǐ]�i�����傤�j�ɔA��������ł�����{���b���Ă��������Ă��肪�Ƃ��������܂��A����ȋC�����Ǝv���܂��B���X�Ԉ�������t�ł��Ӗ���ސ����Ď��܂���B���������p�ꌗ�̐l�͌������݂����ł��ˁA���`���s�ɍs�����p�ꌗ�̕��ɁA���n�̕����ꐶ�����p��Ŋό��ē����Ă�����u�w�^�ȉp��v�Ɠf���̂Ă�悤�ɉ]��ꂽ�̂�ڌ������Ƃ̂��ƁB
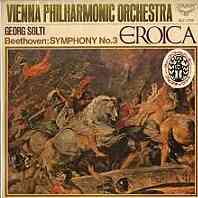 Beethoven �����ȑ�3�� �σz�����u�p�Y�v�`�W���[�W�E�V�����e�B/�E�B�[���E�t�B���i1959�N�j�E�E�EGeorg Solti �i1912�1997�^�嗘���ƈ큨�p���j�ɂ͂����ӎ��������āA���̖c��Ȃ鉹���ɑ��Ă��܂�q���@��͂���܂���B�V�J�S�����y�c�Ƃ̐V���^���A�����Ă��̃E�B�[���E�t�B���Ƃ�1960�N���O�̘^�����قƂ�ǒ��������o�͂���܂���ł����B���ꂪ�����ׂ������A�����ăE�B�[���E�t�B�����������B�I�[�P�X�g���ɂ͂��̌���������������ꂽ�Ƃ̉\��u��������ǁA47�̃V�����e�B�̕\���̓C���E�e���|����ɂ��x�߂̃e���|�͓��X�Ƃ��ĔZ���A�����Ղ�͋����A�Q���̖��J�����������ȁu�p�Y�v�����\�������܂����B
Beethoven �����ȑ�3�� �σz�����u�p�Y�v�`�W���[�W�E�V�����e�B/�E�B�[���E�t�B���i1959�N�j�E�E�EGeorg Solti �i1912�1997�^�嗘���ƈ큨�p���j�ɂ͂����ӎ��������āA���̖c��Ȃ鉹���ɑ��Ă��܂�q���@��͂���܂���B�V�J�S�����y�c�Ƃ̐V���^���A�����Ă��̃E�B�[���E�t�B���Ƃ�1960�N���O�̘^�����قƂ�ǒ��������o�͂���܂���ł����B���ꂪ�����ׂ������A�����ăE�B�[���E�t�B�����������B�I�[�P�X�g���ɂ͂��̌���������������ꂽ�Ƃ̉\��u��������ǁA47�̃V�����e�B�̕\���̓C���E�e���|����ɂ��x�߂̃e���|�͓��X�Ƃ��ĔZ���A�����Ղ�͋����A�Q���̖��J�����������ȁu�p�Y�v�����\�������܂����B
��1�y���uAllegro con brio�v����[������������畏��̂Ȃ��t���[�W���O�A�����◬��͂�낵���A�����Ȉ�ۂ͂���܂���B���J��Ԃ��L�A�E�B�[���E�t�B���̃}�C���h�ȃT�E���h�͂Ƃ��Ɍ��ƃz���������͓I�B�i19:18�j
��2�y���uAdagio assai�v�����s�i�Ȃ͔Z���ȕ\��͉A�e�[���A�͋������݁B���������́B�i16:28�j
��3�y���uAllegro vivace�v�X�P���c�H�͑O�̂߂�Ƀp���t���ȉ����B�}�������n�܂肩��͂߂Ė����������������n�܂�܂����B�g���I�̃z�����͊��Ғʂ�̔Z�����F�B�i5:35�j
��4�y���uAllegro molt�v�t�B�i�[���͑O�y�͂̐������̂܂܁A�����ł悤�Ɏn�܂��āA�ϑt�Ȏ��͓��O�ȕ\��t���B�e�ϑt�Ȃ͋ؓ����������ɃA�N�Z���g�������荏��ł��育��Ɛ��i���܂����B���̃e���V�����̍����͎Ⴓ���Ȃ��A���̌�V�J�S�����y�c�Ƃ̍Ę^���āX�^���͂������ł��傤���B�X�J�b�Ƃ���悤�ȕ@�����Ȃ�ʃe���V�����̍����ƗY�ق������āA���x���������킩��ʓ���́u�p�Y�v�͂��ɂȂ��V�N�Ɏ~�߂����́B�i12:34�j
 Bartok �nj��y�̂��߂̋��t�ȁ`�Y�[�r���E���[�^/�C�X���G���E�t�B���i1975�N�j�E�E�E1987�N�x�������E�t�B���Ƃ̍Ę^���͒m���Ă��邯��ǁA�����狌�^���͕s���̑��݁B�E�B�[���E�t�B���Ƃ́u�����v��^������������̘^����39�Ύ��w���҂̐��������������A�C�X���G���E�t�B���Ƃ̑��������Q�ȔM�C���鉉�t�ł����B����̓I�[�P�X�g���̋Z�ʂ�����閼�ȁB���ĊNJy��̋Z�ʉ]�X���ꂽ�I�[�P�X�g���́A���ɉ��y�ږ�Ƃ��ďA�C���Ă������[�^�i1968���/1977-2019���y�ēj�̎�r�Ȃ̂��A�݂��ƂɃp���t���ȃT�E���h�A�k���ȃA���T���u���Ɏd�グ�Ă���܂����B�e���V���������Ⴓ�ɏ[���������A���Y���̃L������X�B�����ĉpDECCA�̉������f���炵���B�i9:33-6:19-6:58-4:24-9:38�j
Bartok �nj��y�̂��߂̋��t�ȁ`�Y�[�r���E���[�^/�C�X���G���E�t�B���i1975�N�j�E�E�E1987�N�x�������E�t�B���Ƃ̍Ę^���͒m���Ă��邯��ǁA�����狌�^���͕s���̑��݁B�E�B�[���E�t�B���Ƃ́u�����v��^������������̘^����39�Ύ��w���҂̐��������������A�C�X���G���E�t�B���Ƃ̑��������Q�ȔM�C���鉉�t�ł����B����̓I�[�P�X�g���̋Z�ʂ�����閼�ȁB���ĊNJy��̋Z�ʉ]�X���ꂽ�I�[�P�X�g���́A���ɉ��y�ږ�Ƃ��ďA�C���Ă������[�^�i1968���/1977-2019���y�ēj�̎�r�Ȃ̂��A�݂��ƂɃp���t���ȃT�E���h�A�k���ȃA���T���u���Ɏd�グ�Ă���܂����B�e���V���������Ⴓ�ɏ[���������A���Y���̃L������X�B�����ĉpDECCA�̉������f���炵���B�i9:33-6:19-6:58-4:24-9:38�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�T���Ɏ����Ă������������������Ďc���o�e�A�������68kg�V���b�N�������đ̒����C����������B���H���ɒ��߂��e���r�́u���{�̃`�J���v�B�s���R�Ȑg�̂ŗ��h�ɓƂ��炵�A���ɂ��킦���f�U�C���i�C�t�𑀂��đf���炵���؊G���d�グ�Ă����p�Ɋ���������A�������p�����������A��Ȃ����B�b���p�������s�b�N�̑��������_���l���A�s�ˎ�����b���ܗ֏o�ꎫ�ނ����{�c♎q����͍����X�|�[�c���ɏo�ꂵ�đ劈��B�F���h�ł��E�E�E�����Đ���X�g���b�`���������̂�
 Beethoven �����ȑ�3�� �σz�����u�p�Y�v�i1977�N�j/��8�ԃw�����i1978�N�j�`�������E�}�[�[��/�N���[�������h�nj��y�c�E�E�E�f�B�W�^���^���ɕς�钼�O�̎�������낵���Ȃ������̂��H�m���x�ɔ�ׂė������Ă�������ȑS�W���B�Ȃ�ƂȂ��������˂ď����A�Ⴂ���̑�5�ԑ�6�Ԙ^���ȗ���Lorin Maazel�i1930-2014���ė����H�j��Beethoven�q���ł����B�����̃I�[�f�B�I�����Ă����āA����͉����ň��B�e�p�[�g�͕�����낵���ו������A�D�G�ȃA���T���u���Ȃ̂ɁA����͗n�����킸�����ăg�[�^���̋����A�T�E���h�Ƃ��Ĕ����炭�A�܂����������߂Ȃ��B���S�ɒ����Έ������܂��ċْ����̂���}�[�[���̓����͊ԈႢ�Ȃ��A���f�̃e���|�ɓ��قɂ����Ƃ��\���ł��Ȃ�����ǁA�ǂ���������ė��������Ȃ���ۂ��痣����Ȃ��u�p�Y�v�B�i17:28-14:52-5:35-11:29�j��8�ԃw�����̂ق��͍�i�I�ɂ̂т̂тƖ��邢����ɐ���₩�ȕ\����ǁA��{��ۂ͕ς��܂���B�i9:39-3:30-4:57-7:06�j����͉����F������ʗ��j�I�����ɔA�ȂƂĂ��K�b�J���B���̑S�W���̍�i���C�ɂ��Ȃ�܂���E�E�E
Beethoven �����ȑ�3�� �σz�����u�p�Y�v�i1977�N�j/��8�ԃw�����i1978�N�j�`�������E�}�[�[��/�N���[�������h�nj��y�c�E�E�E�f�B�W�^���^���ɕς�钼�O�̎�������낵���Ȃ������̂��H�m���x�ɔ�ׂė������Ă�������ȑS�W���B�Ȃ�ƂȂ��������˂ď����A�Ⴂ���̑�5�ԑ�6�Ԙ^���ȗ���Lorin Maazel�i1930-2014���ė����H�j��Beethoven�q���ł����B�����̃I�[�f�B�I�����Ă����āA����͉����ň��B�e�p�[�g�͕�����낵���ו������A�D�G�ȃA���T���u���Ȃ̂ɁA����͗n�����킸�����ăg�[�^���̋����A�T�E���h�Ƃ��Ĕ����炭�A�܂����������߂Ȃ��B���S�ɒ����Έ������܂��ċْ����̂���}�[�[���̓����͊ԈႢ�Ȃ��A���f�̃e���|�ɓ��قɂ����Ƃ��\���ł��Ȃ�����ǁA�ǂ���������ė��������Ȃ���ۂ��痣����Ȃ��u�p�Y�v�B�i17:28-14:52-5:35-11:29�j��8�ԃw�����̂ق��͍�i�I�ɂ̂т̂тƖ��邢����ɐ���₩�ȕ\����ǁA��{��ۂ͕ς��܂���B�i9:39-3:30-4:57-7:06�j����͉����F������ʗ��j�I�����ɔA�ȂƂĂ��K�b�J���B���̑S�W���̍�i���C�ɂ��Ȃ�܂���E�E�E
����Ȃ��Ƃ�������Ȃ��A���������C���͒������YouTube�G�A���r�N�X�ł����悤�Ǝv������u�V�v���W�F�N�gX�v���n�܂��āA�����ڂ������Ȃ��B�u�F��̓�1300�N�̎����Ȃ������t�������@�S��̏C���v
�����̍Č��i1981�N�j�����ۂɖڂɂ����̂��ǂ����L���͔����B���ꂾ������Ȃ�����1,300�N���j�I���z�����ێ�������{�̗́A�����������݂��o���������I���W�i���Ɏp�ɏC���ł���Z�p���ێ��ł��邱�Ƃ͑f���炵���Ǝv���܂��B���ꂾ����Â��i���������݂ł����ׂĂ̕a��������킯���Ȃ��A�܂��Ă��̂͐S����t�@���ɋF�������Ƃł��傤�B���̌h�i�ȋC�����͌���ł��ς��Ȃ��B�{��H�̐Έ�_�i����͎Ⴂ���A���i�g�Ƌ��n���D���ŁA���|���C���ɖ��l�E�������ɒ�q����A�ނ̃A�E���Ɉ��|����ē������Ȃ��Ȃ��������B�����̉�̏C�����A�n�������̐E�l�̎v���������U���������A���l���a�ɓ|��ē����̐l�X�̊肢�Ɏv����y���܂��B�S���i�������/�d���ǂł��ˁj���C���������{�S�F����͑O�l�����̋Z�p����g���ďC���A�����ꌚ���S�̓����̍ޗ���90%�ȏ�c�����Ƃ̂��ƁB�����܂����B�E�l�̌��������_�X�����瑊�Ɋ����A�l�����������Ȃ��d���͎蔲���݂̂Ȃ炸�A���܂Ŕ����Ă��������̃�������Ƃ͐l���̏d�݂͑�Ⴂ�A�p���������Ȃ�܂����B�d���̂͑̏d�����ł����B
������菬�ꎞ�Ԃقǒx��Ďs���̈�قցB���ǂ������̑싅���͑���킢�B�����̓g���[�j���O���[���ɂ����ʂ�̂��g����������A�G�A���o�C�N15���������ł��܂����B����4km�������E�H�[�L���O�ƂȂ�܂����B�����̑̏d��67.6kg��400g�v������茸���Ă���܂���B
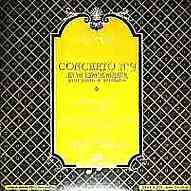 Mozart �s�A�m���t�ȑ�9�� �σz����K.271�u�W���m�[���v�i�}�C���E�w�X(p)�j/��22�� �σz���� K.482�i���h���t�E�[���L��(p)�j�`�p�u���E�J�U���X/ �y���s�j�������y�Պnj��y�c�i1951�N���C���j�E�E�E�����͑z���ȏ�ɗǍD�BMyra Hess�i1890-1965�p���j�̃s�A�m�͗D��ɒW�X�Ƃ��ăf���P�[�g�����́B���C�Ȗ��x�Ɉ�ꂽ�ؗ�Ȃ��σz�������t��K.271�̓R���R���Ɣ������^�b�`�ɗ���悭�i�݂܂����B�i10:54-14:00-10:36�j���邭���C��낵��舒B�� �σz���� ���t��K.482�͖���40�Α��Rudolf Serkin�i1903�1991�H�����ė����j�S���B�_�炩���[���ȃ^�b�`�ɁA��������W�X�Ƃ��āA�����Ƃ�Ƃ����������h������鉉�t�B��1�y�́uAllegro�v�̃J�f���c�@�͉ؗ�ɗY�فB��2�y�́uAndante�v�ɉ�����NJy��݂̂̊��z�͂������Ă���i�B�I�y�́uRondo.Allegro�v�̗��������ăm���r���Ƃ����Ðł͐�i�ł��B�i13:44-11:33-12:51�j�@�J�U���X�̔��t�͂��d���A�e���Ɖ]�����]�������邯��ǁA�\���Ɋ��Y���Ă�������͋������̂ł����B
Mozart �s�A�m���t�ȑ�9�� �σz����K.271�u�W���m�[���v�i�}�C���E�w�X(p)�j/��22�� �σz���� K.482�i���h���t�E�[���L��(p)�j�`�p�u���E�J�U���X/ �y���s�j�������y�Պnj��y�c�i1951�N���C���j�E�E�E�����͑z���ȏ�ɗǍD�BMyra Hess�i1890-1965�p���j�̃s�A�m�͗D��ɒW�X�Ƃ��ăf���P�[�g�����́B���C�Ȗ��x�Ɉ�ꂽ�ؗ�Ȃ��σz�������t��K.271�̓R���R���Ɣ������^�b�`�ɗ���悭�i�݂܂����B�i10:54-14:00-10:36�j���邭���C��낵��舒B�� �σz���� ���t��K.482�͖���40�Α��Rudolf Serkin�i1903�1991�H�����ė����j�S���B�_�炩���[���ȃ^�b�`�ɁA��������W�X�Ƃ��āA�����Ƃ�Ƃ����������h������鉉�t�B��1�y�́uAllegro�v�̃J�f���c�@�͉ؗ�ɗY�فB��2�y�́uAndante�v�ɉ�����NJy��݂̂̊��z�͂������Ă���i�B�I�y�́uRondo.Allegro�v�̗��������ăm���r���Ƃ����Ðł͐�i�ł��B�i13:44-11:33-12:51�j�@�J�U���X�̔��t�͂��d���A�e���Ɖ]�����]�������邯��ǁA�\���Ɋ��Y���Ă�������͋������̂ł����B
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
���������̂����̖ҏ��B����������ʂ�����������Ă����̃X�g���b�`�AYouTube�G�A���r�N�X10���ς܂��ăV�����[���тĂ��̒��͗D��܂���B���ɂ������ĕۗ�܂����f�R�Ɋ����܂����B���Ԃł͂���͎c���o�e�ƌĂԂ炵���B�܂��܂��I����������A�g�����ł����B������̏d�����������A�F�X�l���Ă݂�ƃ|�C���g�́h�o���ׂ����̂��o���h�`���̑O�����Ȃ�o�������o������܂����B����������I�ȃi�j�͂���������ǁA���̎��͂����Ǝ艞����������E�E�E����������͂܂��c�������Ђǂ������B�����̑̏d��68.0kg�{1.7kg����������ł���قǑ�������̂ł��傤���B
���炭��s��������SimpleNote�̌��A�ǂ����O�̒ʂ�ɖ߂�܂����B�摜�m�F�����[���F���o�Ȃ��Ȃ��āA�����Ȃ莩���̃y�[�W���o�����܂��B���ׂȂ��Ƃ����ǁA���������X�g���X��������ł���B�Ȃ�Ƃ����̂܂ܑ����Ăق����B
������i-Phone�͎g�������Ƃ͂Ȃ�����ǁA�l�b�g�̋L����ǂނƋ@��ɂ���Ă̓o�b�e���[�̕ۂ��͂��܂��낵���Ȃ������B�����̌����X�}�zTone e20��3�N��g����1�������炢�M���M�����v�A�܂蒩����ǂ����o�|���Ė�A��Ă�OK�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�}�V�ȕ��ȂȁH�����v���܂����B�܁A���܂范�����g��Ȃ����炩������ǁB�����Apple Watch�����l�ɖ����[�d���K�v�Ƃ��A�@������[�J�[���������ƒ��ׂĂ��Ȃ��A���ɋ�������������My�����X�}�[�g�E�H�b�`��3-4���قǕۂ��܂��B
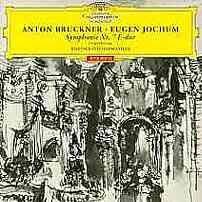 Bruckner �����ȑ�7�ԃz�����i�m���@�[�N�Łj�`�I�C�Q���E���b�t��/�x�������E�t�B���i1964�N�j�E�E�E���n��́H�悤�ȋ���f�b�T���̃W���P�b�g�͕��͋C����܂��ˁBEugen Jochum�i1902�1987�ƈ�j��Bruckner�͐��]�����Ă��A���̓��O�ɗh�ꓮ���e���|�A����߂��A����߂��̕\���͂��܂�D�݂ł͂���܂���B�S�Ȓ����w�̔������������ւ��i�͋ؓ����̗͋������t�ł����B���̎����ɂ��Ă��Ȃ�̗ǎ��ȉ����A��1�y���uAllegro Moderato�v����S�������߂̃e���|�Ƀx�������E�t�B���͐h���ɏd�S�̒Ⴂ�[���T�E���h�A���f�̃z�����̋����B��a���͂قƂ�ǂ���܂���B�i20:35�j��2�y���uAdagio.sehr Feierlich Und Sehr Langsam�v�͂��̍�i�̐S�h���Ԃ銴���I�Ȕ����B�x�������E�t�B���̉A�e�L���Ȍ��̖��͑S�J�A�t���[�g��Ⴢ��悤�Ȑ[�����F�A�͋������O�����LjӊO�ƒW�X�Ƃ������Y�����B�N���C�}�b�N�X�ɑŊy�����͂����ɂ����b�t���炵���B�i25:01�j��3�y���uScherzo.sehr Schnell�vBruckner��i�̃L���̓X�P���c�H�B�����̓x�������E�t�B���̃p���[�S�J�̔��͂Ɛ����������B�i9:47�j��4�y���uFinale.bewegt.doch Nicht Schnell�v�t�B�i�[���̓S�c�S�c�������_�̃��Y���ɔ����ȃe���|�̗h��A�M���M���Ɨ͊�����\���͌͂ꂽ�בR���Ⴉ��͉����A��������b�t���炵���B�i12:34�j�S�̂Ƃ��ă^�C�v����Ȃ�����ǁA62�̃��b�t���̐��͟��i�݂Ȃ��j�鉉�t�͂����Ղ薣�͓I�Ɗ����܂����B
Bruckner �����ȑ�7�ԃz�����i�m���@�[�N�Łj�`�I�C�Q���E���b�t��/�x�������E�t�B���i1964�N�j�E�E�E���n��́H�悤�ȋ���f�b�T���̃W���P�b�g�͕��͋C����܂��ˁBEugen Jochum�i1902�1987�ƈ�j��Bruckner�͐��]�����Ă��A���̓��O�ɗh�ꓮ���e���|�A����߂��A����߂��̕\���͂��܂�D�݂ł͂���܂���B�S�Ȓ����w�̔������������ւ��i�͋ؓ����̗͋������t�ł����B���̎����ɂ��Ă��Ȃ�̗ǎ��ȉ����A��1�y���uAllegro Moderato�v����S�������߂̃e���|�Ƀx�������E�t�B���͐h���ɏd�S�̒Ⴂ�[���T�E���h�A���f�̃z�����̋����B��a���͂قƂ�ǂ���܂���B�i20:35�j��2�y���uAdagio.sehr Feierlich Und Sehr Langsam�v�͂��̍�i�̐S�h���Ԃ銴���I�Ȕ����B�x�������E�t�B���̉A�e�L���Ȍ��̖��͑S�J�A�t���[�g��Ⴢ��悤�Ȑ[�����F�A�͋������O�����LjӊO�ƒW�X�Ƃ������Y�����B�N���C�}�b�N�X�ɑŊy�����͂����ɂ����b�t���炵���B�i25:01�j��3�y���uScherzo.sehr Schnell�vBruckner��i�̃L���̓X�P���c�H�B�����̓x�������E�t�B���̃p���[�S�J�̔��͂Ɛ����������B�i9:47�j��4�y���uFinale.bewegt.doch Nicht Schnell�v�t�B�i�[���̓S�c�S�c�������_�̃��Y���ɔ����ȃe���|�̗h��A�M���M���Ɨ͊�����\���͌͂ꂽ�בR���Ⴉ��͉����A��������b�t���炵���B�i12:34�j�S�̂Ƃ��ă^�C�v����Ȃ�����ǁA62�̃��b�t���̐��͟��i�݂Ȃ��j�鉉�t�͂����Ղ薣�͓I�Ɗ����܂����B
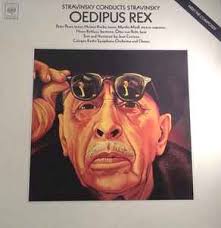 Stravinsky �I�y�����I���g���I�u�G�f�B�v�X���v�`�C�[�S���E�X�g�����B���X�L�[/�P�������������y�c/�����c�s�[�^�[�E�s�A�[�Y�i(t)/�G�f�B�v�X�j/�}���^�E���[�h���i(ms)/���J�X�^�j/�n�C���c�E���[�t�X�i(br)/�N���I���j/�I�b�g�[�E�t�H���E���[���i(b)/�e�B���V�A�X�j/�w�����[�g�E�N���v�X�i(t)/�r�����j/���F���i�[�E�w�b�Z�������g�i���j�i1951�N�j�E�E�E�u�������q�̋A�ҁv�ƕ����Stravinsky�̍�i�Ƃ��Ă͋��Ȃ��́B����̓\�t�H�N���X�̋Y�ȁu�I�C�f�B�v�X���v�Ȃ�ƂȂ��؏����͒m���Ă���܂����B��ȎҎ��g�̃��m�����^���͗\�z�O�ɑN���ȉ����B�O�ǕҐ��A�j����������ۓI�Ȋ���������āA�V�ÓT�h�̂킩��₷�������͒[���N���A�Ɋ�������ł����B���͂Ȃ������������i�������㉉�n�̌��ꂪ�w�肾�����͂��j�j���\���͂�������ј\�����Ղ�B�i51:13�j
Stravinsky �I�y�����I���g���I�u�G�f�B�v�X���v�`�C�[�S���E�X�g�����B���X�L�[/�P�������������y�c/�����c�s�[�^�[�E�s�A�[�Y�i(t)/�G�f�B�v�X�j/�}���^�E���[�h���i(ms)/���J�X�^�j/�n�C���c�E���[�t�X�i(br)/�N���I���j/�I�b�g�[�E�t�H���E���[���i(b)/�e�B���V�A�X�j/�w�����[�g�E�N���v�X�i(t)/�r�����j/���F���i�[�E�w�b�Z�������g�i���j�i1951�N�j�E�E�E�u�������q�̋A�ҁv�ƕ����Stravinsky�̍�i�Ƃ��Ă͋��Ȃ��́B����̓\�t�H�N���X�̋Y�ȁu�I�C�f�B�v�X���v�Ȃ�ƂȂ��؏����͒m���Ă���܂����B��ȎҎ��g�̃��m�����^���͗\�z�O�ɑN���ȉ����B�O�ǕҐ��A�j����������ۓI�Ȋ���������āA�V�ÓT�h�̂킩��₷�������͒[���N���A�Ɋ�������ł����B���͂Ȃ������������i�������㉉�n�̌��ꂪ�w�肾�����͂��j�j���\���͂�������ј\�����Ղ�B�i51:13�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
����������ɍō��C��34�xC�A���B����ł��s���̈�ٖ���2km�r���A���͂킸���ɏH�̋C�z�A���A�ł͂�����҂胉�N�A���c�䂪�͎キ�e���Ă���܂����B����X�g���b�`�{YouTube�G�A���r�N�X�̓X�N���b�g���x�[�X�ɂ���10���قǁA�g���[�j���O���[���͏�A�猩�m�胁���o�[����A�g�����G�A���o�C�N�������ʂ�A�䗬���j���[������������ł��܂����B���������ɂ͊���Ă���܂���B�����̑̏d��66.3kg��1.5kg�A�����������ɋ�������o�͂��邯��ǁA�v�X�̌��ʂł����B
9���̐����Ă��ҏ��͌p�����A�䕗����m�ɑҋ@���H������ǂ����̒��͂�낵���Ȃ��B�^��7-8���Ȃ�Ƃ����f���ɏ����āA���낻��ؗ�Ȃ����ɔ�I���~�ς��Ă������̂��Aႂ̗��݁A�����s�@�ӂƓ��ɂɔY�܂���Ă���܂��B���X�A�g���Ƃ��L�_�f�^���Ƃ��p�����Ēb���Ă������Ȃ��ǂȂ��B�̏d�͑��X���A�H�~�������Ă���킯����Ȃ��̂ł����������Ƃ͂Ȃ�����ǁA������Ƃ��������������Ɉ�a���͂����ăX�b�L�����Ă���܂���B�ڂ��ڂ������I�ɖ�F�Ǝ���U���Ă��ǂ�����ǁA�̏d���X���Ȃ̂Ƒ̒����������āA�ǂ����C���i�݂܂���B������낵���Ȃ��A�v�X45-6�N�O�H��w�𑲋Ƃ��ׂ����Ȃ̂ɁA���ƃT�{�肫���āA������s���^���Â̈����ɂ��Ȃ���܂����B�i���ۂ͂��肬��4�N�ő��Ƃ��Ă���j
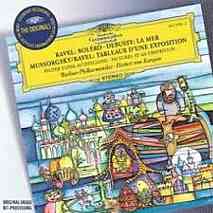 Debussy �����I�f�`�u�C�v�i1964�N�j/Mussorgsky/Ravel�� �g�ȁu�W����̊G�v�i1965�N�j/Ravel �{�����i1966�N�j�`�w���x���g�E�J������/�x�������E�t�B���E�E�ELP���������A�����̃I�[�P�X�g���̈З͔����I�s��ȉ��̍ՓT�I�����Ղ胀�[�f�B�ɃZ�N�V�[�ɕ��������F���苿���u�C�v�i8:35-6:13-8:00�j�u�W����̊G�v�͂������Ƃ����]�T�̃e���|�ɉؗ�ȃT�E���h���f�[�n�[�ɖ苿���āA����Ȃ��̃h���́I�㉹�͂܂�ŃI���K���̂悤�ɐ[�������x�������E�t�B���̖؊ǂ͖��f�A���̃X�P�[���̑傫���A���\�́u�C�v������ɐF�ʂɈ��|����܂����B�Ⴂ��������x�����Ă��邯��ǁA���X���ʂ��グ�Ē�������A������Ɩ�ῂ�����قǂɂ��̃S�[�W���X�E�T�E���h�ɐ����܂�����B�i1:50-2:45-1:14-4:36-0:42-1:04-2:49-1:02-1:12-2:18-1:26-2:14-2:22-3:31-6:52�j�u�{�����v��LP����̋L���ł́A�ȂS�����ɐ���オ��ʂ����ɏI������E�E�E����͋L���Ⴂ�H�]�T�̃I�[�P�X�g���̃p���[�A�����ǂ��ɏ�ɖ����グ��ꂽ���F�ɖ肫���āA���X�g�͗]�T�������ďI������ƌ���ׂ��ł��傤�B������ƈ����̊����̔����Ƃ͈Ⴄ�����B�i16:08�j
Debussy �����I�f�`�u�C�v�i1964�N�j/Mussorgsky/Ravel�� �g�ȁu�W����̊G�v�i1965�N�j/Ravel �{�����i1966�N�j�`�w���x���g�E�J������/�x�������E�t�B���E�E�ELP���������A�����̃I�[�P�X�g���̈З͔����I�s��ȉ��̍ՓT�I�����Ղ胀�[�f�B�ɃZ�N�V�[�ɕ��������F���苿���u�C�v�i8:35-6:13-8:00�j�u�W����̊G�v�͂������Ƃ����]�T�̃e���|�ɉؗ�ȃT�E���h���f�[�n�[�ɖ苿���āA����Ȃ��̃h���́I�㉹�͂܂�ŃI���K���̂悤�ɐ[�������x�������E�t�B���̖؊ǂ͖��f�A���̃X�P�[���̑傫���A���\�́u�C�v������ɐF�ʂɈ��|����܂����B�Ⴂ��������x�����Ă��邯��ǁA���X���ʂ��グ�Ē�������A������Ɩ�ῂ�����قǂɂ��̃S�[�W���X�E�T�E���h�ɐ����܂�����B�i1:50-2:45-1:14-4:36-0:42-1:04-2:49-1:02-1:12-2:18-1:26-2:14-2:22-3:31-6:52�j�u�{�����v��LP����̋L���ł́A�ȂS�����ɐ���オ��ʂ����ɏI������E�E�E����͋L���Ⴂ�H�]�T�̃I�[�P�X�g���̃p���[�A�����ǂ��ɏ�ɖ����グ��ꂽ���F�ɖ肫���āA���X�g�͗]�T�������ďI������ƌ���ׂ��ł��傤�B������ƈ����̊����̔����Ƃ͈Ⴄ�����B�i16:08�j
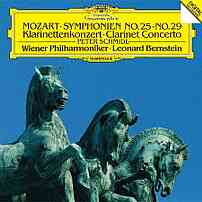 Mozart �����ȑ�25�ԃg�Z��K.183/��29�ԃC����K.201/��38�ԃj����K.504�u�v���n�v�`���i�[�h�E�o�[���X�^�C��/�E�B�[���E�t�B���i1987/1985�N�j�E�E�E�����Ă��ē�����O�̒����ȉ��t�����ǁA���͏����B�C���[�W�Ƃ��Ă̓j���[���[�N����̌��C�����ς��ɑe���ۂ��\���`���ꂩ��20�N�قnjo�߂��čŔӔN�A�����Ƃ�Ɨ��������ē��X����A�e�����Ղ�Ȋ����x�A�뜜�����悤�ȏd�߂��ĔS�����ȕ���ɔA�E�B�[���E�t�B���̐��X�����������������ė������������t�͈ӊO�ł����B�ߌ����ؔ��������g�Z��������K.138�i8:10-4:12-3:50-5:57�j���c�ɂ����U��Ԃ�悤�ɖ��킢�[���C����������K.201�i8:14-6:53-3:26-5:07�j�����Ė��x�Ɩ����Ɉ�ꂽ�ÓT�I���j����������K.504�u�v���n�v�i13:35-9:11-8:41�j�B�Êy��ɂ�鑬�߂̃e���|�ɐ�������Y���A�e��ɑf�p�ȋ�������D�������ǁA����ȃS�[�W���X�ɓ��X���镗������Ɉ����Ȃ�Mozart�ł����B
Mozart �����ȑ�25�ԃg�Z��K.183/��29�ԃC����K.201/��38�ԃj����K.504�u�v���n�v�`���i�[�h�E�o�[���X�^�C��/�E�B�[���E�t�B���i1987/1985�N�j�E�E�E�����Ă��ē�����O�̒����ȉ��t�����ǁA���͏����B�C���[�W�Ƃ��Ă̓j���[���[�N����̌��C�����ς��ɑe���ۂ��\���`���ꂩ��20�N�قnjo�߂��čŔӔN�A�����Ƃ�Ɨ��������ē��X����A�e�����Ղ�Ȋ����x�A�뜜�����悤�ȏd�߂��ĔS�����ȕ���ɔA�E�B�[���E�t�B���̐��X�����������������ė������������t�͈ӊO�ł����B�ߌ����ؔ��������g�Z��������K.138�i8:10-4:12-3:50-5:57�j���c�ɂ����U��Ԃ�悤�ɖ��킢�[���C����������K.201�i8:14-6:53-3:26-5:07�j�����Ė��x�Ɩ����Ɉ�ꂽ�ÓT�I���j����������K.504�u�v���n�v�i13:35-9:11-8:41�j�B�Êy��ɂ�鑬�߂̃e���|�ɐ�������Y���A�e��ɑf�p�ȋ�������D�������ǁA����ȃS�[�W���X�ɓ��X���镗������Ɉ����Ȃ�Mozart�ł����B
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�J���J���Ƃ�c�������A�ō��C���\����34�xC�B9���ł��̋C���͂��������g�̂Ɋ����܂��B�G�A�R���͂Ȃ��ŏA�Q�\�B�����瓪�ɗL�A�ۗ�܂����ł��Ɋ����܂����B�����̉䗬�X�g���b�`��YouTube�G�A���r�N�X�i�����10���قǂ̃X�g���b�`�j���{�B�O�������̔z�B�������āA�H�ނ͖L�x�Ȃ̂Ŕ������ɏo��K�v�͂���܂���B����ႂ�����ŊP������ŁA�̒��͂ǂ�����낵���Ȃ��A�Ȃ�̈ӗ~���N���܂���B�I���ڂ���߂����Ă��܂��܂����B�����̑̏d��67.8kg�{700g�ň��B
�����哇����}���O�[�X����Ƃ̕B����͐����B30�N�|���ċ쒀�����Ƃ̂��ƁB�n�u��ɓ�������Ă��قƂ�nj��ʂ͂Ȃ��āA�ݗ������ɔ�Q���������Ƃ̂��ƁB�S�����������W�����{�^�j�V��E�V�K�G���Ƃ��v�����ŊC�O���瓱�����āA���ꂪ�����o���ĂƂ�ł��Ȃ��������i��̓I�ɂ͂킩��ʂ���ǁj���Ԍn�ɉe����^���Ă���̂ł��傤�B���ߏ��ł�������������~�~�V�b�s�[�A�J�~�~�K���i�~�h���K���j�͂��Ղ�̉����Ŕ����āA�₪�Ď���ł͎����Ȃ��Ȃ��ĉ͐�ɕ������Ɨސ��B����͌����ڂ��Ă����i�ٗl�ȔɐB�j���ɂȂɂ��e���͂���̂ł��傤���B�ŋߌ��Ă��Ȃ����ǁu�r�̐��S�������v�݂����Ȕԑg�ł̓g���f��������t�o�Ă��܂�����ˁA�C�O�������Ă����̂��BTOKIO�̔ԑg�ł���Ȃ����i�O����j��ߊl���ĂȂ�Ƃ����������A�݂����Ȋ�悠��܂�����ˁB�邩�ǂ����ʂƂ����i�W�����{�^�j�V��E�V�K�G���͂��Ƃ��ƐH�p�j�Ȃ�Ƃ��A���Ƃ��Ɠ��{�×��̐��Ԍn������遁���������R�����߂����Ƃ��肢�܂��B������A�����O����͂������邱�Ƃł��傤�B
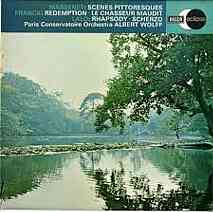 Charpentier �������u�C�^���A�̈�ہv/Massenet �nj��y�g�ȑ�4�ԁu�G�̂悤�ȕ��i�v/�nj��y�g�ȑ�7�ԁu�A���U�X�̕��i�v/Franck �������u���ꂽ��l�v/�������u�܍߁v/Lalo �u�m���E�F�[�����ȁv/�X�P���c�H �C�Z��/�̌��u�C�X�̉��l�v�����i�p�����y�@�nj��y�c/1955-56�N�j/Massenet �̌��u�t�F�[�h���v����/�̌��u�E�F���e���v�O�t�ȂƃN���X�}�X�̖��i�p���E�I�y���E�R�~�[�N���nj��y�c/1951�N�j�`�A���x�[���E���H���t�E�E�EAlbert Wolff�i1884�1970�������j�͂�����ƃW�~�ȑ��݂̉��N�̎w���ҁB�I�y���n�E�X����@���グ�ăR���Z�[���E�������[��R���Z�[���E�p�h���[�̎�Ȃ����߂��Ƃ̂��ƁBLP������Ȃ�ƂȂ�������LP�ɂĂ����b�ɂȂ��Ă����L���͂���܂����B�p�����y�@�nj��y�c�Ƃ̘^���̓X�e���I�����A�܂��܂��̉����̓Z�s�A�F�̉�����������߂Ă���݂����B���������y�ł͂�����Ɠ��{�ł͐l�C������i��葵���Đ��肾������A�ǂ�����������A�y���A�킩��₷����������B�쉢�B�̗z���̓�����̂����u�C�^���A�̈�ہv�i�Z���i�[�h Serenade/8:55-��̂قƂ�� A la Fontaine/3:55-���o�ɏ���� A mules/5:24-�R�̒����ɂ� Sur les cimes/6:47-�i�|�� Napoli13:56�j�y����@���ɓ��₩���u�G�̂悤�ȕ��i�v�i�s�i�ȁiMarche�j/3:17-�����ȁiAir de ballet�j/2:35-�������̏��iAngelus, Angelus�j/4:58-�W�v�V�[�̍ՁiFete Boheme�j/5:13 �����̓��Y�~�J���ɖ����j�u�₩�ɗD��ȋ�C���L�����u�A���U�X�̕��i�v�i���j���̒��iDimanche matin�j�z�������q�̓I/6:47-����ŁiAu cabaret�j�e�B���p�j��������₩�ȃ����c�A�z�������劈��/5:03-�����̉��ŁiSous les tilleuls�j�`�F���ƃI�[�{�G����捂ɗ��ݍ���/5:06-���j���̗[���iDimanche soir�j�����ȔM�C�����₩�Ɉ��܂���/5:50�j�������Ƃ��Ă���@���ȉ��y�p�����B
Charpentier �������u�C�^���A�̈�ہv/Massenet �nj��y�g�ȑ�4�ԁu�G�̂悤�ȕ��i�v/�nj��y�g�ȑ�7�ԁu�A���U�X�̕��i�v/Franck �������u���ꂽ��l�v/�������u�܍߁v/Lalo �u�m���E�F�[�����ȁv/�X�P���c�H �C�Z��/�̌��u�C�X�̉��l�v�����i�p�����y�@�nj��y�c/1955-56�N�j/Massenet �̌��u�t�F�[�h���v����/�̌��u�E�F���e���v�O�t�ȂƃN���X�}�X�̖��i�p���E�I�y���E�R�~�[�N���nj��y�c/1951�N�j�`�A���x�[���E���H���t�E�E�EAlbert Wolff�i1884�1970�������j�͂�����ƃW�~�ȑ��݂̉��N�̎w���ҁB�I�y���n�E�X����@���グ�ăR���Z�[���E�������[��R���Z�[���E�p�h���[�̎�Ȃ����߂��Ƃ̂��ƁBLP������Ȃ�ƂȂ�������LP�ɂĂ����b�ɂȂ��Ă����L���͂���܂����B�p�����y�@�nj��y�c�Ƃ̘^���̓X�e���I�����A�܂��܂��̉����̓Z�s�A�F�̉�����������߂Ă���݂����B���������y�ł͂�����Ɠ��{�ł͐l�C������i��葵���Đ��肾������A�ǂ�����������A�y���A�킩��₷����������B�쉢�B�̗z���̓�����̂����u�C�^���A�̈�ہv�i�Z���i�[�h Serenade/8:55-��̂قƂ�� A la Fontaine/3:55-���o�ɏ���� A mules/5:24-�R�̒����ɂ� Sur les cimes/6:47-�i�|�� Napoli13:56�j�y����@���ɓ��₩���u�G�̂悤�ȕ��i�v�i�s�i�ȁiMarche�j/3:17-�����ȁiAir de ballet�j/2:35-�������̏��iAngelus, Angelus�j/4:58-�W�v�V�[�̍ՁiFete Boheme�j/5:13 �����̓��Y�~�J���ɖ����j�u�₩�ɗD��ȋ�C���L�����u�A���U�X�̕��i�v�i���j���̒��iDimanche matin�j�z�������q�̓I/6:47-����ŁiAu cabaret�j�e�B���p�j��������₩�ȃ����c�A�z�������劈��/5:03-�����̉��ŁiSous les tilleuls�j�`�F���ƃI�[�{�G����捂ɗ��ݍ���/5:06-���j���̗[���iDimanche soir�j�����ȔM�C�����₩�Ɉ��܂���/5:50�j�������Ƃ��Ă���@���ȉ��y�p�����B
Franck��Lalo�͐����ȂƂ���ꕔ�̍�i�������ċ��n�A�����ł�5�Ȃ����������Ƃ͂���E�E�E���x�̂��t�������BFranck�̎����y�̊��\���͍D�������ǁA�nj��y�͂ǂ����T�������`����ς�����܂����B�������u���ꂽ��l�v�̓z�������E�s�ɑ����Ȏn�܂�A�₪�ė��Franck�炵���������Y�����e���|�E�A�b�v���Đ���オ��܂����B�i15:11�j�u�܍߁v�͏����H�_���捂Ȏn�܂肩��A�₪�Đ��y������E�E�E�͂����nj��y�̂݁A����Ȕł����݂���̂ł��傤�B�����Ȍ��̃A���y�W�I�ɏ���ĊNJy��̔������̂͏��X���C���Ȃ������B�i11:52�j
Lalo���قƂ�ǁu�X�y�C�������ȁv�{�����炢���������ł��Ȃ��āA��i�����ɋL���͂���܂���B�ʂɐ��lj������ł��Ȃ��炵�����u�m���E�F�[�����ȁv�͑�1�y�́uAndantino�v�ɂ͑��Ж��w�����p���Ă���H�炵�����ǁA���܂����݂͂ǂ��낪�Ȃ������B�i5:58�j��2�y�́uPresto�v����͉����ȃ��Y�����������ĂȂ��Ȃ��ْ̋������J�b�R�ǂ��B�i5:00�j�X�P���c�H �C�Z���̓s�A�m�O�d�t�ȑ�3�ԃC�Z������̕ҋȂł����H�i���M�͂Ȃ��j����͑O�ȁu�X�P���c�I�v�ɂ悭����������������ȃ��Y���ɒ��ԕ��ɂ͗D��ȉ̂�������܂����B�i5:09�j�̌��u�C�X�̉��l�v������Wagner�̉e��������������B�������ɂ�����Ƒ�O�I��Wagner����Ɍ��I�Ȑ����A�A���A�I�[�P�X�g���̋����͂�����҂蔖�������B�i11:54�j
���X�g�A�p���E�I�y���E�R�~�[�N���nj��y�c�ɂ��Massenet�̍�i�̓��m�����^���B�����Eloquence�ɂ��CD���̎��Ɏ��^���ꂽ���܂��A������ۂ͂��قǂɈ�������܂���B���I�ɐ_���A�Â��������Y�ق� �̌��u�t�F�[�h���v�����i9:03�j�̌��u�E�F���e���v�`�O�t�ȂƃN���X�}�X�̖��͔ߌ��I�Ȏn�܂�A�₪�Ă����Ղ�D��Ȑ������̂���Massenet�͂ق�܂Ƀ����f�B���[�J�[�Ǝv���܂��B�i9:05�j
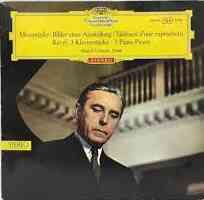 Mussorgsky �g�ȁu�W����̊G�v�`���h���t�E�t�B���N�X�j�[(p)�i1960�N�j�E�E�E���̍�i�͂��C�ɓ��肾���ǁAHDD�g���u���ɂ�肹�������̉����͂���Ԏ����܂����BRudolf Firkusny�i1912�1994�����j�ɂ��s�A�m���Ȃ͕ʂ�HDD�ɕۑ����Ă����̂ŃZ�[�t�ł����B���ȂƉ]�������q�e����1958�N�\�t�B�A�E���C���A�����������z�����̋S�_�̔@���s��ȏW���͉��t���o��ł���A���t�@�����X�B����͖����ē���Ē����Ă���܂���B�i�E�E�E���ƂŒ��ׂ���ʓr�܂Ƃ߂Ċm�ۂ��Ă���܂����j������[���ȋZ�I�ƕ\���ɁA�ǂ����I�[�\�h�b�N�X�ɉ߂��Ă��܂����I�����Ȃ��E�E�E����͒���̑̒����ł��傤���B�ǂ����ŋC����ς��čĒ��킢�����܂��B�v�����i�[�h�i1:22�j/�O�m�[���i2:39�j/�v�����i�[�h�i0:49�j/�Ï�i4:43�j/�v�����i�[�h�i0:27�j/�`���C�����[�̒�i1:04�j/�u�C�h���i3:02�j/�v�����i�[�h�i0:42�j/ �k�������ЂȂ̗x��i1:16�j/�T�~���G���E�S�[���f���x���N�ƃV���~���C���i1:58�j/�v�����i�[�h�i1:16�j/�����[�W���̎s��i1:19�j/�J�^�R���u�i1:54�j/�����錾�t�ɂ�鎀�҂ւ̌Ăт����i1:53�j/�o�[�o�E���[�K�̏����i3:06�j/�L�[�E�̑傫�Ȗ�i4:47�jRavel ���̋Y��/�����t�̒��̉�/���̒J�����^����A������͂Ȃ��Ȃ��f���P�[�g�ȃ^�b�`�����\�ł��܂����B�i5:11-6:02-6:02�j
Mussorgsky �g�ȁu�W����̊G�v�`���h���t�E�t�B���N�X�j�[(p)�i1960�N�j�E�E�E���̍�i�͂��C�ɓ��肾���ǁAHDD�g���u���ɂ�肹�������̉����͂���Ԏ����܂����BRudolf Firkusny�i1912�1994�����j�ɂ��s�A�m���Ȃ͕ʂ�HDD�ɕۑ����Ă����̂ŃZ�[�t�ł����B���ȂƉ]�������q�e����1958�N�\�t�B�A�E���C���A�����������z�����̋S�_�̔@���s��ȏW���͉��t���o��ł���A���t�@�����X�B����͖����ē���Ē����Ă���܂���B�i�E�E�E���ƂŒ��ׂ���ʓr�܂Ƃ߂Ċm�ۂ��Ă���܂����j������[���ȋZ�I�ƕ\���ɁA�ǂ����I�[�\�h�b�N�X�ɉ߂��Ă��܂����I�����Ȃ��E�E�E����͒���̑̒����ł��傤���B�ǂ����ŋC����ς��čĒ��킢�����܂��B�v�����i�[�h�i1:22�j/�O�m�[���i2:39�j/�v�����i�[�h�i0:49�j/�Ï�i4:43�j/�v�����i�[�h�i0:27�j/�`���C�����[�̒�i1:04�j/�u�C�h���i3:02�j/�v�����i�[�h�i0:42�j/ �k�������ЂȂ̗x��i1:16�j/�T�~���G���E�S�[���f���x���N�ƃV���~���C���i1:58�j/�v�����i�[�h�i1:16�j/�����[�W���̎s��i1:19�j/�J�^�R���u�i1:54�j/�����錾�t�ɂ�鎀�҂ւ̌Ăт����i1:53�j/�o�[�o�E���[�K�̏����i3:06�j/�L�[�E�̑傫�Ȗ�i4:47�jRavel ���̋Y��/�����t�̒��̉�/���̒J�����^����A������͂Ȃ��Ȃ��f���P�[�g�ȃ^�b�`�����\�ł��܂����B�i5:11-6:02-6:02�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
���C�֓��n���͑�J�炵�����ǁA������͓܂��ɍō��C��32�xC�Ƃ��A�������������������܂��B��G�A�R���͕K�v����܂���B���̂܂H�ɂȂ��Ăق������ǁA�����ł��Ȃ��炵���B�c���̉ăo�e���ۂ��āA�̒��͂��܈����ԁA�����̐���ɃX�g���b�`�{YouTube10���قǂ̃G�A���r�N�X���ς܂��Ă����͂��܂�o�Ȃ��āA���̂܂s���̈�ق֏o�|���܂����B�}���`�v���X�̐ȂɃ_���x���ƃX�}�z����������Œ����ԓƐ肷���Y���o�����āA���g����f�O�o�債������ǁA���̂���7��I�����Ƃ���œP�ނ��Ă��ꂽ�̂ł���������B�G�A���o�C�N�͑̒������i���j�݂ċx�~�Ƃ��܂����B���̂܂܃X�[�p�[�Ɋ���č�������R�ꂽ���lj��w���B�I�X�X���̋��������܂����B
�Ԃ������O�r�[�����_���I���h�B���̓w�͂́A�ƂĂ������ǃ}�l�ł���ȁB�����Ĉ�㏮�툳���B�����獡��67.1kg��500g�A66kg��ɂ��߂�Ȃ��Ȃ�܂����B�����Ȑ����s�@�ӁA�@�l�܂�A�̒��s�ǂ��e�����Ă���̂��B
1,100�~�{��/���̌���TonMobile�iTone20e/�_���[�������j�͂ڂ��ڂ�3�N�A������Ȃ��Ƃ����X��̂��Y�܂����āA�Ȃ�ƂȂ����̌������킩��܂����B�t�������N�ŏ����đ�ւ𑗂��Ă����X�}�[�g�E�H�b�`�ƘA�g���āA�Ȃ�Ƃ����炪���Ă���E�E�E����������Bluetooth�A�g���~�߂���߂�̂��A���ꂶ��X�}�[�g�E�H�b�`�̈Ӗ��Ȃ����ǁB�����X�}�[�g�E�H�b�`�Ȃ̂ɒʘb���ł���I�i�炵��/�g�������ƂȂ����ǁj����������ł����A�g�����Ȃ��ʃh�E�V���E�g�́E�E�E�ƁA������������Simplenote�܂��܂��s���A�����q���������Q�Ƃł��܂���B���炭���ĉ����݂��������ǁA�������Ȃ��A����B
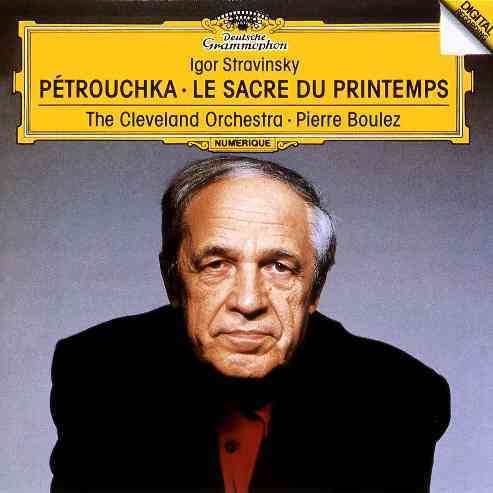 Stravinsky �o���G���y�u�y�g���[�V���J�v�i1911�N�Łj/�o���G���y�u�t�̍ՓT�v�i1947�N�Łj�`�s�G�[���E�u�[���[�Y/�N���[�������h�nj��y�c�i1991�N�j�E�E�EHDD���̂�Stravinsky������S���������̂ŁA���J�茴�_�ɖ߂��Ē���������i�߂Ă���Ƃ���B����͓S�̉��t�A�����ɂƂ���Stravinsky�̊��Pierre Boulez�i1925�2016�������j2016�N���̍Ē��B�����H��
Stravinsky �o���G���y�u�y�g���[�V���J�v�i1911�N�Łj/�o���G���y�u�t�̍ՓT�v�i1947�N�Łj�`�s�G�[���E�u�[���[�Y/�N���[�������h�nj��y�c�i1991�N�j�E�E�EHDD���̂�Stravinsky������S���������̂ŁA���J�茴�_�ɖ߂��Ē���������i�߂Ă���Ƃ���B����͓S�̉��t�A�����ɂƂ���Stravinsky�̊��Pierre Boulez�i1925�2016�������j2016�N���̍Ē��B�����H��
�u�y�g���[�V���J�v���X�^�[�g�A�\����Ȃ����j���[���[�N�E�t�B���i1971�N�j�Ƃ͉_�D�̋Z�ʂ̍��A�t���[�W���O�̏������}�C���h�ɂ�����������������̂��A�ނȂ�̏n���������̂ł��傤�B�㉹�����ł̗}������Ă��A�ו������ȋ����A�ŋ������ւ̎��R�Ȉڍs�̓X���[�X���̂��́A�e�p�[�g��Ⴢ��قǃj���A���X���ׂɔ��f����Ă��A������ꂽ�o�����X�͋����قǐ���i�Ƃ���������������Ȃ��j�N���A
������悤�ɑN���ȉ����{���ɑŊy��̒ቹ�����������܂����E�E�E���܂�ɂ����Ƃ�A�o�����X�悭�d�グ�����āu�y�g���[�V���J�v�̖��͂ł�����X�������x�A�Ղ�̌����̃E�L�E�L���ɂ͂��傢�ƌ�����̂����B�u�t�̍ՓT�v�����l�B�}�C���h�ȃt���[�W���O�̎d�グ���O�ꂳ��A����̗���X���[�X�Ɏ����āA1969�N�̏Ռ��͔���܂����B
������牜�s�A�Ŋy��̐[�݂������āA����͂���Ő����O�ꂳ��Ė��͓I
8�N���o�A��L�C���[�W�ƂقƂ�Ǖς��Ȃ��B���]�߂�ƈꕔ�u�N���[�������h�nj��y�c�̓h�z�i�[�j�ȗ����[�J���̃I�[�P�X�g���ɐ��艺�������B�����������v�Ƃ̍��]���A�ӌ���~�ߕ��̑��l���i�H�j�͂�낵�����Ƃł��B�V���n�̌����ƃE�L�E�L����悤���u�y�g���[�V���J�v�͂��܂�ɂ����Ƃ萮���ė��������āA���B���B�b�h�ȃ��Y�����╂�����悤�ȓ��₩���ɑ���ʈ�ۂ͂���܂����B�ł��A������肢�]�T�̃I�[�P�X�g���Ȃ̂͊ԈႢ�Ȃ��B
��1�� �ӓ��Ղ̓�-��i�t�̌|-���V�A�̗x���i9:57�j��2�� �y�g���[�V���J�̕����i4:30�j��3�� ���[�A�l�̕���-�o�����[�i�̗x��-�o�����[�i�ƃ��[�A�l�̃����c-�y�g���[�V���J�i7:01�j��4�� �ӓ��Ղ̓��̗[��-����̗x��-�F��A�ꂽ�_�v-�z�C�ȍs���l�ƃW�v�V�[���i13:33�j
�u�t�̍ՓT�v���ȑO�̒ʂ�̈�یp���B����������Ƃ萮���ė��������ė݂͈͂�Ȃ��\���A�k���ȃo�����X�͍ו����s���n���āA�ǂ̃p�[�g�̐������Y�����������ʂƂ���͂Ȃ��I��������20�N�Ԃ̔M�C�͔���Ă��A�ߕs���̂Ȃ��\������i�̃o�[�o���Y���̍�����N�₩�ɕ����яオ�点��E�E�E�Ŋy���y���������Ĉ����̃N���C�}�b�N�X�Ɏ����Ă��N�[���ɃX�}�[�g�A���ꂼ���F���E�x�X�g�B����������ɏ�B
��1��:��n��^ ���t�i3:34�j�t�̂������Ƃ��Ƃ߂����̗x���i3:13�j�U���i1:22�j�t�̗x���i3:45�j�G�̓s�̐l�X�̋Y���i1:49�j���l�̍s��-��n�ւ̂����Â�-���l�i0:58�j��n�̗x���i1:18�j��2��:�����ɂ� ���t�i4:06�j���Ƃ߂����̐_��Ȃǂ��i3:06�j �����ɂ��̎^���i1:25�j�c��̌Ăяo���i0:37�j�c��̋V���i3:26�j�����ɂ��̗x���i4:43�j
 Smetana �A��������W�u�킪�c���v�`�J�����E�A���`�F��/�`�F�R�E�t�B���i1963�N�j�E�E�E���������肵�������͉����͂��܂ЂƂB��������z���Č̍��ւ̎v�����Ċ����I�ȋL�^�ł��傤�B�_�X�����u������v�N���m���Ă����X�����̗��������������u�����_�E�v�������L���Ő��Ԃł͎c��u���̑��v�����B�ؔ����Y���ȁu�V�����J�v�A�厩�R��I�X�Ɖ̂��u�{�w�~�A�̐X�Ƒ�������v�A���I�Ȑ킢��\�������u�^�[�{���v�����Čp�������킢�ɋP�������ŏI�������肤�u�u���j�[�N�v�B�S���ʂ��Ē����ɂ͏��X�������K�v�����ǁA��������z���Ă�������S�Ȗ��킢�������́B�BVysehrad (The High Castle)�i14:21�jVltava (Moldau)�i12:33�jSarka�i9:55�jFrom Bohemia's Woods and Fields�i12:18�jTabor�i12:22�jBlanik�i13:45�j
Smetana �A��������W�u�킪�c���v�`�J�����E�A���`�F��/�`�F�R�E�t�B���i1963�N�j�E�E�E���������肵�������͉����͂��܂ЂƂB��������z���Č̍��ւ̎v�����Ċ����I�ȋL�^�ł��傤�B�_�X�����u������v�N���m���Ă����X�����̗��������������u�����_�E�v�������L���Ő��Ԃł͎c��u���̑��v�����B�ؔ����Y���ȁu�V�����J�v�A�厩�R��I�X�Ɖ̂��u�{�w�~�A�̐X�Ƒ�������v�A���I�Ȑ킢��\�������u�^�[�{���v�����Čp�������킢�ɋP�������ŏI�������肤�u�u���j�[�N�v�B�S���ʂ��Ē����ɂ͏��X�������K�v�����ǁA��������z���Ă�������S�Ȗ��킢�������́B�BVysehrad (The High Castle)�i14:21�jVltava (Moldau)�i12:33�jSarka�i9:55�jFrom Bohemia's Woods and Fields�i12:18�jTabor�i12:22�jBlanik�i13:45�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�V������T�Ԃ��n�܂��āA���[�a�͔k����Ɗ�Ȏ��@�ȂցB�䕗����M�ђ�C���͂��ԂƂ������{���k�ɑ�J�������炵�ă^�C�w���A���̑䕗���������蔭�����Ă��̐�S�z�ł��B������͂�������J�͏オ���Ėҏ��p�����A����ł���͂�����҂�������G�A�R���Ȃ��ŏA�Q�ł��܂����B����Ԃ�ɐ��͊O�����o���B�̒��͂��܂����A�����s�@�ӂɓr���o����x�Q�A��������肿����҂�Q�V���ăX�g���b�`�͓r�����AYouTube�G�A���r�N�X�͑O������{�����o���G�̏������Ƃ���12���قǁA���ꂪ�����ɂ����ɂ��̊��Ɍ����I�������Ƃ������������ǑS�g���I�V�����[�𗁂тĂ���A�Ɩ��X�[�p�[��ڎw���܂����B�����Ă����̂ŕ�[���āA�E�H�[�L���O5,000����Ƃ��܂����B���ɂ��C�ɂȂ��Ē��ɍܕ��p�B�����̑̏d��67.6kg+200g�Ȃ�Ƃ��Ȃ�B
�������p���Ă���SimpleNote�B���ꂪ�ǂ������������B�ӂ���͌������Ƃ��Ȃ�Log in with email��ʂ��o�Ă���̂͗ǂ��Ƃ��āA�o�^���[�����͂��Ȃ����̂Ƀm�[�g���J���Ȃ��B�����Ƒ匳�̃T�[�o�[�s�ǂȂ̂ł��傤�B����������Ɨl�q������������ǁA���y�q�������͂��ׂĂ����ɏW�������Ă���̂Łu���y�����v�X�V�Ɏx�Ⴊ�o�邩���m��܂���BSupport�ɂ��uLogin proces asks for code, but no email is sent�v�Ƃ������ۂ�����Ă���܂��E�E�E5-6��J��Ԃ��ƃ��[���͓͂��܂����B
���i��������炪��J�ĕ��B��^���\�������������̂ɁA����𐁂�����Ă�����������ł���B���n�ł���l�C�Ȃ̂͊ԈႢ�Ȃ�����ǁA���ė����ݏZ���{�l��YouTube�����q������ƁA�싅���̂��̂����Ăقǂ̐l�C�͂Ȃ����i�ꎞ����������肪�����炵���j��J�ĕ��̖��O���m��ʂ��ǂ����ӊO�Ƒ����Ƃ̂��ƁB������ƈӊO�B����Ɨ��V�[�Y���̓��͂ǂ��Ȃ�̂��A���ݎ�p��̃��n�r�����̂͂��A���G���蕜���͂����Ƃ��̗͕̑��S�ɁE�E�E�ł��A�������Ȃ��A�����ƁB�������{�̏ꖖ�ŏ���ɐS�z���Ă���܂��B
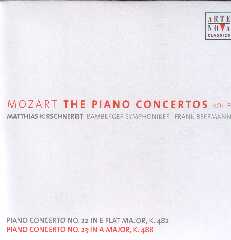 Mozart �s�A�m���t�ȑ�22�� �σz����K.482/��23�ԃC����K.488�`�}�e�B�A�X�E�L���V���l���C�g(p)/�t�����N�E�x�[���}��/�o���x���N�����y�c�i2005�N�j�E�E�E2009�N���̍Ē��B��̊o�߂�悤�ȑN���ȉ����i�I�[�f�B�I�ʂ̕��ɂ��ƃv�A�ȋ@��ł��ǂ������/�Ȃ�قǁjMatthias Kirschnereit�i1962��ƈ�j�ɂ��y���Ƀf���P�[�g�ɖ��c�ɂ����s�A�m�̃^�b�`�A������悤�ȃI�[�P�X�g���̔������B���Đ̂̓ƈ탍�[�J���ȃT�E���h�E�C���[�W�͊������܂���B�������悤�Ȗ��x�ɏ[�����σz�������t��K.482�A��2�y�́uAndante�v�͐[���d�v���ɒ��Ȓ��ɁA�r���NJy��݂̂ɂ��ԑt�͖�����悤�Ȕ������A�����đ�3�y�́uAllegro�v�͉f��u�A�}�f�E�X�v�̒��A��̏�ʂ������v���o���܂��B�i13:41-9:02-1:34�j�C�������t��K.488��Mozart��i�����w�̘Q���Ɉ�ꂽ�������������ւ��āA��2�y�́uAdagio�v�̐[���Â������݂ɐS�D���܂����B�i11:14-7:11-8:07)
Mozart �s�A�m���t�ȑ�22�� �σz����K.482/��23�ԃC����K.488�`�}�e�B�A�X�E�L���V���l���C�g(p)/�t�����N�E�x�[���}��/�o���x���N�����y�c�i2005�N�j�E�E�E2009�N���̍Ē��B��̊o�߂�悤�ȑN���ȉ����i�I�[�f�B�I�ʂ̕��ɂ��ƃv�A�ȋ@��ł��ǂ������/�Ȃ�قǁjMatthias Kirschnereit�i1962��ƈ�j�ɂ��y���Ƀf���P�[�g�ɖ��c�ɂ����s�A�m�̃^�b�`�A������悤�ȃI�[�P�X�g���̔������B���Đ̂̓ƈ탍�[�J���ȃT�E���h�E�C���[�W�͊������܂���B�������悤�Ȗ��x�ɏ[�����σz�������t��K.482�A��2�y�́uAndante�v�͐[���d�v���ɒ��Ȓ��ɁA�r���NJy��݂̂ɂ��ԑt�͖�����悤�Ȕ������A�����đ�3�y�́uAllegro�v�͉f��u�A�}�f�E�X�v�̒��A��̏�ʂ������v���o���܂��B�i13:41-9:02-1:34�j�C�������t��K.488��Mozart��i�����w�̘Q���Ɉ�ꂽ�������������ւ��āA��2�y�́uAdagio�v�̐[���Â������݂ɐS�D���܂����B�i11:14-7:11-8:07)
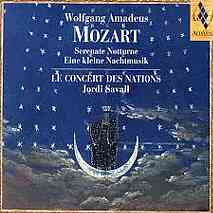 Mozart �Z���i�[�h��6�� �j�����u�Z���i�[�^�E�m�b�g�D���i�vK.239/�Z���i�[�h��13�� �g�����u�A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N�vK.525/�Z���i�[�h �j�����u4�̃I�[�P�X�g���̂��߂̃m�b�g�D���m�v K.286/���y�̏�k K.522�`�W�����f�B�E�T���@�[��/���E�R���Z�[���E�f�E�i�V�����i2005�N�j�E�E�EJordi Savall�i1941-���lj�j�J�^���[�j���o�g������z���f�B�ɔW�����f�B�̂ق��������ɋ߂������B��D���ȍ�i����W�߂āA�Êy��̑e���舒B�ȋ����������Ղ芬�\�����Ă��������܂����B������ƃl�b�g��T���Ă݂����ǁA�܂������b��ɂ͂Ȃ��Ă��݂����ł��ˁB�Ⴂ����͂����ς肻�̍�i������߂Ȃ������u�Z���i�[�^�E�m�b�g�D���i�v�͋[�o���b�N�I��2�Q�ɕ�����ꂽ�A���T���u���ɂ�鍇�t���t�ȁA�e�B���p�j���劈��I�����ł͉��X�Ƒ����H���t������̂�����ł����B�i4:01-4:21-6:18�j�N�ł��m���Ă�������ȁu�A�C�l�E�N�v�i7:59-4:40-2:02-5:03�j�u4�̃I�[�P�X�g���̂��߂̃m�b�g�D���m�v K.286��4�̌��y�A���T���u������1�A���T���u����ǂ�������u�G�R�[�v�������������i6:41-2:21-8:06�j�B�����Ċ��x�����Ă�������|���[�����X�ȁu���̉��y�Ƃ̘Z�d�t�ȁv�����̃i�`�������E�z�����̌��ʂ͐��B��D���ȍ�i�ł���A�^�ʖڂɉ���Ή���قǂ��̌��ʂ͔��Q�ł��B�i4:29-6:56-5:06-5:06-4:17�j
Mozart �Z���i�[�h��6�� �j�����u�Z���i�[�^�E�m�b�g�D���i�vK.239/�Z���i�[�h��13�� �g�����u�A�C�l�E�N���C�l�E�i�n�g���W�[�N�vK.525/�Z���i�[�h �j�����u4�̃I�[�P�X�g���̂��߂̃m�b�g�D���m�v K.286/���y�̏�k K.522�`�W�����f�B�E�T���@�[��/���E�R���Z�[���E�f�E�i�V�����i2005�N�j�E�E�EJordi Savall�i1941-���lj�j�J�^���[�j���o�g������z���f�B�ɔW�����f�B�̂ق��������ɋ߂������B��D���ȍ�i����W�߂āA�Êy��̑e���舒B�ȋ����������Ղ芬�\�����Ă��������܂����B������ƃl�b�g��T���Ă݂����ǁA�܂������b��ɂ͂Ȃ��Ă��݂����ł��ˁB�Ⴂ����͂����ς肻�̍�i������߂Ȃ������u�Z���i�[�^�E�m�b�g�D���i�v�͋[�o���b�N�I��2�Q�ɕ�����ꂽ�A���T���u���ɂ�鍇�t���t�ȁA�e�B���p�j���劈��I�����ł͉��X�Ƒ����H���t������̂�����ł����B�i4:01-4:21-6:18�j�N�ł��m���Ă�������ȁu�A�C�l�E�N�v�i7:59-4:40-2:02-5:03�j�u4�̃I�[�P�X�g���̂��߂̃m�b�g�D���m�v K.286��4�̌��y�A���T���u������1�A���T���u����ǂ�������u�G�R�[�v�������������i6:41-2:21-8:06�j�B�����Ċ��x�����Ă�������|���[�����X�ȁu���̉��y�Ƃ̘Z�d�t�ȁv�����̃i�`�������E�z�����̌��ʂ͐��B��D���ȍ�i�ł���A�^�ʖڂɉ���Ή���قǂ��̌��ʂ͔��Q�ł��B�i4:29-6:56-5:06-5:06-4:17�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�䕗�͔M�ђ�C���ցA�܂��܂���J�̉e���͂�������B�����I���̒��s���ɐQ������B������j�̒������ɂƔ��M�p����������ǁA�����̉䗬�X�g���b�`��YouTube�G�A���r�N�X�̓X�g���b�`�݂�����12���������s�A�������������o�ăV�����[���g���Ă���s���̈�ق�ڎw���܂����B�̒����i�j�Ȃ̂Ŏ蔲�����đ��X�ɋA�낤�Ǝv��������ǁA���J�肢���ǂ���̂��g�����n�߂���̒���C�ɉ��P�A���ǂ����ʂ�G�A���o�C�N15�����������ċC���͑u���ł����B�V�C�\��͒�����J�Ƃ̗\��ɐ��͎��������A���Ǘ[���ɂ�����҂�~�����̂݁B�[�т͏��[�a���C�����Ď��i�Ƃ����Ƃ��o�������̂��̂��Ă����̂ŁA��������߂��܂����B�����̑̏d��67.4kg��200g���߈���B
�������̢�����@�܂����������ɔ����w�i
�Ȃ��Ȃ��y�����L����q�����܂����B�u�����@�܂����v�u���S���n�сv�u�ōk��v�u�A���t�H�[�X�q�v�`���j�[�N�ȃl�[�~���O�Ɛ��\�̗ǂ����獂���V�F�A���ւ�u�}���L���j�R���v�B�_�@��Ƃ��A���܂艏�̂Ȃ������ł��v��ʐg�����o���I���W�M���O�͐e���݂₷���A�Ă��˂��Ȍڋq����̕������ɉ��P�𑱂��Ă���炵���B�u2023�N�̎������54�J���A����グ��100���~��˔j�����v�Ƃ̂��ƁB����Ȍ��C���郁�[�J�[�����{�ɂ��邱�Ƃ��ւ�Ɏv���܂��B
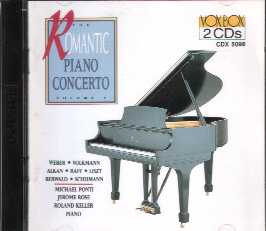 Weber �s�A�m���t�ȑ�1�ԃn���� ��i11/��2�� �σz���� ��i32/�s�A�m�����t�ȃw�Z�� ��i79�`���[�����h�E�P���[(p)/�W�[�N�t���[�g�E�P�[���[/�x�����������y�c�i1979�N�j�E�E�E2006�N�ɔq���L�^�L�B���̊ԁAHDD���̂ɂ��Weber�����͂��ׂď����A���J��ē��肷�ׂ��l�b�g�������ɔ��������̂�����AVOX��Brilliant�ɂčĔ�������Ă����̂ł��ˁBRoland Keller�i1949��ƈ�jSiegfried Ko"hler�i1923�2017�ƈ�j�͂���������{�ł͒m���x�͂��܂�Ȃ��悤�ł��B�ǂ���f�p�ȓƈ햯�O�̕���Ɉ��āA�����ו���������L���L�A�����̚n�D����������v���o���܂����B���t�@���^�������Ȃ��̂��M�����ʂقǂ̖��邢���ȁB����1979�N�Ƃ̘^�������m��o���A�����͂܂��܂��Ȃ�₯��Berliner Symphoniker�̉��F�͂�����҂���肪���B�����̎����̓X�^���E�G�C����Ȃ��ƃG���\�[�ɏ����Ă��邯��ǁA�������ɂ�����Ǝ����[�����F�����B�n����/�σz�������t�ȂƂ��悭���āA�V���v���ɉ����ȕ���A�h�E�V���E�g���C���[�W����Ƃ���̓ƈ햯�O�̉��������f�p�Ȑ��������삵�Ė����A���������ƌ���Ȃ��B�]�T�̌y���ȋZ�I������܂����B
Weber �s�A�m���t�ȑ�1�ԃn���� ��i11/��2�� �σz���� ��i32/�s�A�m�����t�ȃw�Z�� ��i79�`���[�����h�E�P���[(p)/�W�[�N�t���[�g�E�P�[���[/�x�����������y�c�i1979�N�j�E�E�E2006�N�ɔq���L�^�L�B���̊ԁAHDD���̂ɂ��Weber�����͂��ׂď����A���J��ē��肷�ׂ��l�b�g�������ɔ��������̂�����AVOX��Brilliant�ɂčĔ�������Ă����̂ł��ˁBRoland Keller�i1949��ƈ�jSiegfried Ko"hler�i1923�2017�ƈ�j�͂���������{�ł͒m���x�͂��܂�Ȃ��悤�ł��B�ǂ���f�p�ȓƈ햯�O�̕���Ɉ��āA�����ו���������L���L�A�����̚n�D����������v���o���܂����B���t�@���^�������Ȃ��̂��M�����ʂقǂ̖��邢���ȁB����1979�N�Ƃ̘^�������m��o���A�����͂܂��܂��Ȃ�₯��Berliner Symphoniker�̉��F�͂�����҂���肪���B�����̎����̓X�^���E�G�C����Ȃ��ƃG���\�[�ɏ����Ă��邯��ǁA�������ɂ�����Ǝ����[�����F�����B�n����/�σz�������t�ȂƂ��悭���āA�V���v���ɉ����ȕ���A�h�E�V���E�g���C���[�W����Ƃ���̓ƈ햯�O�̉��������f�p�Ȑ��������삵�Ė����A���������ƌ���Ȃ��B�]�T�̌y���ȋZ�I������܂����B
�s�A�m���t�ȑ�1�� �n�����i��1�y�́uAllego�v�i8:40�j��2�y�́uAdagio�v�i4:09�j��3�y�́uPresto�v�i6:43�j�j�s�A�m���t�ȑ�2�� �σz�����i��1�y�́uAllegro maestoso�v�i8:27�j��2�y�́uAdagio�v�i4:58�j��3�y�́uRondo,Presto�v�i6:47�j�j�s�A�m�����t�ȃw�Z���͂Ȃ��Ȃ���I�������āA�푈�ɍs�����v��҂w�l���A�ނ��C�����s���Ɏv���Y��ł���Ƃ���ɖ����߂��Ċ���ɂ܂�`����ȕ����\�����������B�Ȃ��Ȃ����I�ȕ���ɏ[���������������ł����B�iLarghetto, ma non troppo - Allegro appasionato/Adagio - Tempo di marcia - Presto assai/16:20�j
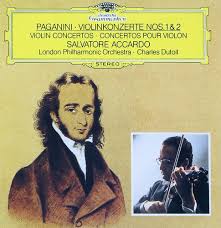 Paganini ���@�C�I�������t�ȑ�1�ԃj����/��2�ԃ��Z���u���E�J���p�l�����v�`�T�����@�h�[���E�A�b�J���h(v)/�V�������E�f���g��/�����h���E�t�B���i1975�N�j�E�E�EHDD������߉ނɂȂ���Paganini�������S�������܂����B��X�����ȃ��@�C�I�������t�Ȃ͂������A���@�C�I�����ƃM�^�[�ɂ�鎺���y�Ƃ����傢�ƒ�������i����������W�߂đS���A�E�g�B���ݏ������������芚�ݒ��߂ē��蒆�E�E�E�܂��A�S�]����Salvatore Accardo�i1941��ɑ������j�̉������ē���ł��܂����B�f���g��39�A�������܂蔄��Ă��Ȃ����̘^���B�i�����g���I�[�������y�c�A�C�O�j�����ꃔ�@�C�I�����̑s��ȋZ�I���X�����A�����Ԃ��Ȃ��̂������āA����͂܂�ŃC�^���A�E�I�y���̃A���A�̂悤�B���t�́u�h�E�V���[���v�u�Y���E�`���`���v�̘A���A���܂������Ƃ͍l�����Ƀ\���X�g�̖��Z�ɒ��������ׂ���i�ł��傤�B�\�����I�[�P�X�g������������ƂĂ��˂��ɁA�B�����̂Ȃ��Z�I�ƕ\���������Ղ芬�\�������܂����B�u���E�J���p�l�����v�͗L����Liszt�̐������ŏI�y�͂ɂ���Ă�����́B�i22:01-5:59-9:40/14:56-7:06-8:57�j
Paganini ���@�C�I�������t�ȑ�1�ԃj����/��2�ԃ��Z���u���E�J���p�l�����v�`�T�����@�h�[���E�A�b�J���h(v)/�V�������E�f���g��/�����h���E�t�B���i1975�N�j�E�E�EHDD������߉ނɂȂ���Paganini�������S�������܂����B��X�����ȃ��@�C�I�������t�Ȃ͂������A���@�C�I�����ƃM�^�[�ɂ�鎺���y�Ƃ����傢�ƒ�������i����������W�߂đS���A�E�g�B���ݏ������������芚�ݒ��߂ē��蒆�E�E�E�܂��A�S�]����Salvatore Accardo�i1941��ɑ������j�̉������ē���ł��܂����B�f���g��39�A�������܂蔄��Ă��Ȃ����̘^���B�i�����g���I�[�������y�c�A�C�O�j�����ꃔ�@�C�I�����̑s��ȋZ�I���X�����A�����Ԃ��Ȃ��̂������āA����͂܂�ŃC�^���A�E�I�y���̃A���A�̂悤�B���t�́u�h�E�V���[���v�u�Y���E�`���`���v�̘A���A���܂������Ƃ͍l�����Ƀ\���X�g�̖��Z�ɒ��������ׂ���i�ł��傤�B�\�����I�[�P�X�g������������ƂĂ��˂��ɁA�B�����̂Ȃ��Z�I�ƕ\���������Ղ芬�\�������܂����B�u���E�J���p�l�����v�͗L����Liszt�̐������ŏI�y�͂ɂ���Ă�����́B�i22:01-5:59-9:40/14:56-7:06-8:57�j
2024�N9���^��/���B�������������S�ғ�������X
�Ƃ��Ƃ�9���ɓ����đ䕗�͔����O�i�ɖ����^���Œ��B�����͓��C�n���ɔ������Ƃ��A���͎͂�߂Ă��J�ɂ͗v���ӂ������ł��B��B�l���͂������A�����{�ɂ��r��Ȃ��Q��^���āA��������ӂ�͕����Ȃ��A�����璋���炢�����Ƃ��ƍ~�����̂݁B���͎��������A�����������Ƃ͂���܂���B�[���ɂ͐���o�܂����B�O��G�A�R������ĐQ���̂���낵���Ȃ������݂����ŁA�����瓪�ɂ��Ђǂ��A�X�g���b�`��YouTube�G�A���r�N�X���T�{��܂����B�I���قƂ�Nj�����A������҂蒋�Q�̂��肪�����薰���Ă��܂��܂����B�ꃖ���o���Ă܂����ׁH���M������悤�Ȋ����B�{���͂��ꂩ��ߑO���A�V�C����낵�������Ɏs���̈�ق֏o�|���悤�Ǝv������ǁA�̒��ň��A���͂��B�����300�����x�A�������Q�̌�����67.6kg�{400g�ň��B
���Ɍ��֓����F�m���̘b��A���˂��肪�ǂ��̂Ƃ��w���ȕ����̂��Ƃ�����グ���Ă��邯��ǁA����������ׂ����Ƃ����̂��ő�̖��ł��傤�B�Ȃ��Ȃ��S�苭���J�������Ă����܂Ŋ撣���Ă��������̂́A���]������������ɏ[���Ȏ��ԁB�����Ă��Ȃɂ�����������u�s���̒v���Ƃ���v�Ƃ��Ȃ�Ƃ��A�������Ǝ��߂ăE�������ɂȂ�`����ȃp�^�[�����������A����͌��グ�������A�Ƃ��Ƃ�M���M�����撣���ė~�����B�����͓��ʂȑ��݂ƐM�����ċ�C�͓ǂ߂Ȃ���ł��傤�B���ɍ���̌��������Ă��u���v�͂���܂����B�ېV���Ή�������āA���ʎs���I�̌��EW�X�R�A�s�ނ����ď��߂ē����o���āA����͈���̓T�^�ł����B�ق��A�����͐�Ό��Ȃ��i��x���������Ƃ͂Ȃ��j24���ԃe���r�Ƃ��A�䕗�ڋߒ��₷�q�̃}���\�����s���Ȃ��Ȃ��A�����������Ǝ��Ă���B���Ƃ��̓I�g�i�̎���H�Ɏ��{��������ǁA���N�͂������ł��傤���B������ꖖ�̈��ޖ��i=���V�j���Ԃ₢�Ă����̓˂�����ɂ��Ȃ�܂���B
 Shstakovich �����ȑ�5�ԃj�Z���`�X�^�j�X���t�E�X�N�����@�`�F�t�X�L/�~�l�A�|���X�����y�c�i1961�N�j�E�E�EMercury�^���͒ቹ�������Č��𐅏��B�̂���L���Ș^�������ǁA�����ł����B�ǂȂ������u�����̂悤�ȉ��t�v�ƕ]���Ă��āA����͂��В����Ă݂Ȃ�������Ǝv�������́B���̕��͋������Ȃ̂��A����Ƃ������̔��������n�m����Ă�����Ȃ̂��͕s���B��1�y���uModerato - Allegro non troppo�v ���߂̃e���|�A��̗E�s�Ȏ��͂�������Ƃ��ăh���C�ȃt���[�W���O�i���̕ӂ肪�������Ȃ��H�j����Ȑh���\���͒��������Ƃ͂Ȃ��B�I�[�P�X�g���̃A���T���u���͗D�G�ɏW���͂̍������́B�i14:18�j��2�y���uAllegretto�v�m���m���̃X�P���c�H�̓V�j�J���Ƀ��[�����X�ȃ����g���[�B�����̓��B���B�b�h�O�̂߂�Ȑ����ɃN�[���Ȏ��_���������鐶�^�ʖڂȕ\���ł����B�i5:21�j��3�y���uLargo�v�͋��ǔ����A�t�N�U�c�Ȍ���̂ɂ���捈��ɂ̊ɏ��y�́B�������e���|�͑��߁A�j���A���X�����߂��t���[�W���O�̓T���T���Ɨ���܂��B�N���C�}�b�N�X�͐ؔ������āA�₪�Ē��قɎ������܂��B�i13:41�j��4�y���uAllegro non troppo�v�����͗\�z�O�ɒʏ�e���|�Ɏn�܂��āA�N���C�}�b�N�X�Ɍ����ăe���|�E�A�b�v�B�L���̂���t���[�W���O�͑�������ǁA���X�g���y�ʂɗ��������ʊ����B�A���T���u���ْ̋����͍Ō㖘�ێ�����A�I�[�P�X�g���̋Z�ʂ������Ɗ����܂����B�i9:23�j
Shstakovich �����ȑ�5�ԃj�Z���`�X�^�j�X���t�E�X�N�����@�`�F�t�X�L/�~�l�A�|���X�����y�c�i1961�N�j�E�E�EMercury�^���͒ቹ�������Č��𐅏��B�̂���L���Ș^�������ǁA�����ł����B�ǂȂ������u�����̂悤�ȉ��t�v�ƕ]���Ă��āA����͂��В����Ă݂Ȃ�������Ǝv�������́B���̕��͋������Ȃ̂��A����Ƃ������̔��������n�m����Ă�����Ȃ̂��͕s���B��1�y���uModerato - Allegro non troppo�v ���߂̃e���|�A��̗E�s�Ȏ��͂�������Ƃ��ăh���C�ȃt���[�W���O�i���̕ӂ肪�������Ȃ��H�j����Ȑh���\���͒��������Ƃ͂Ȃ��B�I�[�P�X�g���̃A���T���u���͗D�G�ɏW���͂̍������́B�i14:18�j��2�y���uAllegretto�v�m���m���̃X�P���c�H�̓V�j�J���Ƀ��[�����X�ȃ����g���[�B�����̓��B���B�b�h�O�̂߂�Ȑ����ɃN�[���Ȏ��_���������鐶�^�ʖڂȕ\���ł����B�i5:21�j��3�y���uLargo�v�͋��ǔ����A�t�N�U�c�Ȍ���̂ɂ���捈��ɂ̊ɏ��y�́B�������e���|�͑��߁A�j���A���X�����߂��t���[�W���O�̓T���T���Ɨ���܂��B�N���C�}�b�N�X�͐ؔ������āA�₪�Ē��قɎ������܂��B�i13:41�j��4�y���uAllegro non troppo�v�����͗\�z�O�ɒʏ�e���|�Ɏn�܂��āA�N���C�}�b�N�X�Ɍ����ăe���|�E�A�b�v�B�L���̂���t���[�W���O�͑�������ǁA���X�g���y�ʂɗ��������ʊ����B�A���T���u���ْ̋����͍Ō㖘�ێ�����A�I�[�P�X�g���̋Z�ʂ������Ɗ����܂����B�i9:23�j
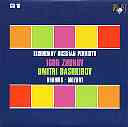 Brahms �s�A�m���t�ȑ�2�� �σ������`�C�[�S���E�W���[�R�t/�Q���i�W�E���W�F�X�g���F���X�L�[/�\���B�G�b�g���������y�c�i1963�N�j�E�E�EIgor Zhukov�i1936�2018�I�����j�ɂ�鉉�t�͂�����LP����ɒ������L��������܂����B���I�t�E�}�C�N�ɐF�C�̂Ȃ��U���ȉ��������ǂ܂��܂��̗Տꊴ�Ɖ𑜓x�A�������������ǂ����̓ƚҌnBrahms���d�S�̒Ⴂ�^�b�`�ɔA�s�A�m�E�I�u���K�[�g�t�������ȂƂ���鋐��ȋ��t�Ȃ́A�e��ȕ����䩗m�Ƃ��Ċ������^�b�`�ɂ͏W���ł��Ȃ������B������ۂ��Ȃ��B�Z�p�I�ȕs���͂���܂���B�i17:47-9:12-12:19-9:04�j
Brahms �s�A�m���t�ȑ�2�� �σ������`�C�[�S���E�W���[�R�t/�Q���i�W�E���W�F�X�g���F���X�L�[/�\���B�G�b�g���������y�c�i1963�N�j�E�E�EIgor Zhukov�i1936�2018�I�����j�ɂ�鉉�t�͂�����LP����ɒ������L��������܂����B���I�t�E�}�C�N�ɐF�C�̂Ȃ��U���ȉ��������ǂ܂��܂��̗Տꊴ�Ɖ𑜓x�A�������������ǂ����̓ƚҌnBrahms���d�S�̒Ⴂ�^�b�`�ɔA�s�A�m�E�I�u���K�[�g�t�������ȂƂ���鋐��ȋ��t�Ȃ́A�e��ȕ����䩗m�Ƃ��Ċ������^�b�`�ɂ͏W���ł��Ȃ������B������ۂ��Ȃ��B�Z�p�I�ȕs���͂���܂���B�i17:47-9:12-12:19-9:04�j
Mozart �s�A�m���t�ȑ�24�ԃn�Z��K.491�`�h�~�g���[�E���@�V�L�[���t(p)/�A���N�T���h���E�K�E�N/�\���B�G�b�g�������������y�c�i1958�N�j�E�E�EDmitri Bashkirov�i1931�2021�������j�̘^���͏��X�����������ē܂肪���B���Ȃ葬�߂̃e���|���k���ȃ^�b�`�A��������Ƃ����e�N�j�b�N�����Ǘ��������Ȃ���1�y�́uAllegro�v�A��2�y�́uLahghetto�v�͒W�X�Ƃ��ĂȂ��Ȃ��̔Z���ȃA�N�Z���g�A��3�y�́uAllgretto�v�����݂�X�����ϑt�ȁA���������߂̃e���|�Ɍ��I���x�ȏW���͕\���ł����B�i12:42-8:03-8:30��������L�j