2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
暑い暑い6月も本日終了。前夜は涼しくて久々しっかり眠った感じ。昨日日曜も朝から天気もよろしく、気温はどんどん上がりました。鹿児島では震度4、彼(か)の辺りの住民は日々不安でしょうね。
いつもどおりのストレッチ(膝関節の可動域も問題なし)例の如く東南亜細亜系女性が10分ほど動き続けるYouTubeエアロビクスを済ませて、ウォーキング兼、ご近所スーパーに野菜など買い足しに出掛けました。これで計測上は一日の運動量クリア(ほんまか?)帰宅したら汗みどろ、朝サボっていた洗濯を実施いたしました。じつはここ数日、中途半端に収集していた某音源全集がネットに出現してダウンロード中、ゆっくり点検整理作業も老後の趣味の醍醐味です。今朝の体重は昼夜しっかり喰って66.4kg▲500g。呑むと戻すのに三日ほど掛かるのですね。一ヶ月で1.5kgほど減った計算となります。
昨年2024年10月ころ破産宣告されたフナイ電気はご近所、その後正式にFUNAI GROUP(株)は破産したらしい。隔日市立体育館への通り道にあって、おそらくは管財人グループ事務処理数人、毎回同じクルマが数台、残務整理を続けていたんでしょう。最近は一台のみとか、まったくなかったりするから概ね終了したのかも。入口守衛のおじさんは寂しそうでした。フォークリフトはじっと動かず、工場前の樹木はそのまま。以前は定期的に美しく剪定されていたけれど、花は咲いても放置され荒れ果て、ゴミも溜まって殺伐と虚しさを痛感いたします。建物や工場はしっかりしているように見えても誰もいない、やがて資産は処分され建物ごと売られたり、取り壊されて更地になったりするのでしょう。馘首された従業員はその後どうなったのか。この物価高に日々の生活はタイヘンと類推されます。
毎度通りかかるたび「諸行無常」という言葉が思い出されました。
夜はしっかりリアルタイムに男子バレーは強豪斯洛文尼亜戦。3-0完全勝利は久々。今回は高いセッター永露がきっちり機能しました。相変わらず宮浦好調、大塚も富田も佐藤も良かった。小川の超絶ディグにも痺れました。斯洛文尼亜も高くパワーもあって第1セットはジュースから崩れるパターンか、心配したけれどなんとか勝ち切って、あとはサーブミスにも救われました。最近の男子バレーはけっこう強い攻撃を拾ってラリーが続くことも多くて、見応えがありますよ。いよいよ日本(千葉)ラウンドへ。石川髙橋藍、いつもの主力メンバーが合流します。
 Bach カンタータ第138番「何ゆえに悲しむや、わが心よ」/第99番「神のみわざは善きかな」/第51番「もろびとよ歓呼して神を迎えよ」/第100番「神のみわざは善きかな」~ジョン・エリオット・ガーディナー/イングリッシュ・バロック・ソロイスツ/モンテヴェルディ合唱団/マリン・ハルテリウス(s)/ウィリアム・タワーズ(a)/ジェイムズ・ギルクリスト(t)/ピーター・ハーヴェイ(b)(2000年)・・・膨大なるBachカンタータ音源を眼の前に嘆息するのはいつものこと。プロテスタントの宗教的儀礼、独逸の節季などいくらネットを駆使しても理解できず、こちらの浅学を情けなく嘆いて、もちろん言葉の壁もあります。仕方がないので時々、その美しい和声に集中して堪能するのみ。John Eliot Gardiner(1943-英国)は古楽器演奏に多大なる貢献をして、挙げ句トラブルから2024年にイングリッシュ・バロック・ソロイスツ/モンテヴェルディ合唱団より馘首されたとのこと。(新しい団体を設立して活動しているらしい)器楽アンサンブルの古楽器の技術的に洗練され、マイルドに安定した響きとリズム、それは声楽陣も同様。音質は極上でした。
Bach カンタータ第138番「何ゆえに悲しむや、わが心よ」/第99番「神のみわざは善きかな」/第51番「もろびとよ歓呼して神を迎えよ」/第100番「神のみわざは善きかな」~ジョン・エリオット・ガーディナー/イングリッシュ・バロック・ソロイスツ/モンテヴェルディ合唱団/マリン・ハルテリウス(s)/ウィリアム・タワーズ(a)/ジェイムズ・ギルクリスト(t)/ピーター・ハーヴェイ(b)(2000年)・・・膨大なるBachカンタータ音源を眼の前に嘆息するのはいつものこと。プロテスタントの宗教的儀礼、独逸の節季などいくらネットを駆使しても理解できず、こちらの浅学を情けなく嘆いて、もちろん言葉の壁もあります。仕方がないので時々、その美しい和声に集中して堪能するのみ。John Eliot Gardiner(1943-英国)は古楽器演奏に多大なる貢献をして、挙げ句トラブルから2024年にイングリッシュ・バロック・ソロイスツ/モンテヴェルディ合唱団より馘首されたとのこと。(新しい団体を設立して活動しているらしい)器楽アンサンブルの古楽器の技術的に洗練され、マイルドに安定した響きとリズム、それは声楽陣も同様。音質は極上でした。
第138番「何ゆえに悲しむや、わが心よ」
「Chorale and Recitative: Warum betrubst du dich (Alto, Tenor)」しっとり嘆きのヴァイオリンとオーボエから、気高いテナーとアルト、荘厳壮麗な合唱が静かに始まりました。この辺り、ほんまに美しい旋律と感じます。(5:02)「Recitative: Ich bin veracht (Bass)」(0:53)「Chorale and Recitative: Er kann und will dich lassen nicht (Soprano, Alto)」(3:15)「Recitative: Ach susser Trost (Tenor)」(0:58)「Aria: Auf Gott steht meine Zuversicht (Bass)」弾むような弦に乗ってバスが自信たっぷりに朗々と歌う。(4:28)「Recitative: Ei nun! (Alto)」(0:21)「Chorale: Weil du mein Gott und Vater bist」オーボエと弦による決然たる伴奏に乗って、劇的な合唱が歌いました。(2:09)
第99番「神のみわざは善きかな」
「Was Gott tut, das ist wohlgetan (Chorus)」晴れやかに細かい音型の木管に合唱が絡みます(4:23)「Recitative: Sein Wort der Wahrheit stehet fest (Bass)」(0:58)「Aria: Erschuttre dich nur nicht, verzagte Seele (Tenor)」清潔なテナーにもの哀しいフルートがオブリガート(5:25)「Recitative: Nun, der von Ewigkeit geschloss'ne Bund (Alto)」(0:58)「Duet Aria: Wenn des Kreuzes Bitterkeiten (Soprano, Alto)」女声二重奏の嘆きをフルートとオーボエが支えて(4:21)「Chorale: Was Gott tut, das ist wohlgetan」心安らぐ合唱によるコラールの締め括り(2:10)
第51番「もろびとよ歓呼して神を迎えよ」これはトランペットが大活躍して(珍しく)かなり馴染みの作品。
「Aria: Jauchzet Gott in allen Landen! (Soprano)」喜びに充ちたソプラノが自在にスムースなトランペットに躍動します。(4:18)「Recitative: Wir beten zu dem Temel an (Soprano)」切々として清楚なソプラノ(2:09)「Aria: Hochster, mach deine Gute (Soprano)」引き続き通奏低音のみ(オルガンとチェロ)の伴奏にソプラノの嘆きが続きました。旋律の美しさ格別。(4:31)「Chorale: Sei Lob und Preis mit Ehren (Soprano)」軽快な弦に乗ってソプラノが晴れやかに歌う(3:39)そのままテンポ・アップして「Aria: Alleluja! (Soprano)」へ。満を持してトランペット再登場して、華やかに幸いなる神への賛美のうちに終了。(2:10)
第100番「神のみわざは善きかな」(第99番と同じ題名ですか?)
「Chorale: Was Gott tut, das ist wohlgetan」ホルンとティンパニ、オーボエにリコーダーも賑やかに加わって、喜ばしい快活な合唱の始まり。(4:29)「Duet: Was Gott tut, das ist wohlgetan (Alto, Tenor)」動きのある通奏低音に乗った女声男声の掛け合い(3:03)「Aria: Was Gott tut, das ist wohlgetan (Soprano)」ちょっと切ないソプラノは動きの多いフルートによるオブリガートが支えます(4:43)「Aria: Was Gott tut, das ist wohlgetan (Bass)」バス?にしては声は軽め。弦のみの闊達な伴奏でした。(3:10)「Aria: Was Gott tut, das ist wohlgetan (Alto)」粗野なオーボエに導かれたアルト独唱。(3:52)「Chorale: Was Gott tut, das ist wohlgetan」冒頭の賑やかなアンサンブルが戻って、喜びに満ちた合唱が晴れやかな表情に歌いました。(1:56)
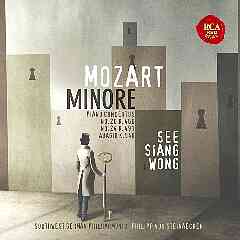 Mozart ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.266(カデンツァは Hummel)/第24番ハ短調K.491(カデンツァはKarl Philipp Hoffmann)/アダージョ ロ短調K.540~シー・シャン・ウォン(p)/フィリップ・フォン・シュタインネッカー/南西ドイツ・フィル(2016-17年)・・・See Saing Wong(1979-阿蘭陀)による意欲的な演奏。モダーン楽器使用、劇性を強調せずしっとりと端正なタッチ、あまり聴いたことのないカデンツァ+装飾音を多用して、もちろんテクニックはスムース。Mozartには珍しい屈指の劇性と美しい旋律を湛えた短調の作品揃えて、しっとり落ち着いた風情に仕上がっておりました。ここ最近、こんな抑制され内省的に暗いMozart表現も珍しいほど。
Mozart ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.266(カデンツァは Hummel)/第24番ハ短調K.491(カデンツァはKarl Philipp Hoffmann)/アダージョ ロ短調K.540~シー・シャン・ウォン(p)/フィリップ・フォン・シュタインネッカー/南西ドイツ・フィル(2016-17年)・・・See Saing Wong(1979-阿蘭陀)による意欲的な演奏。モダーン楽器使用、劇性を強調せずしっとりと端正なタッチ、あまり聴いたことのないカデンツァ+装飾音を多用して、もちろんテクニックはスムース。Mozartには珍しい屈指の劇性と美しい旋律を湛えた短調の作品揃えて、しっとり落ち着いた風情に仕上がっておりました。ここ最近、こんな抑制され内省的に暗いMozart表現も珍しいほど。
Allegro(14:49)Romance(9:02)Rondo: Allegro assai(8:27)/Allegro(15:39)Larghetto(7:47)Allegretto(9:08)
ロ短調のAdagioは底知れぬ、透明な苦悩を湛えた名曲中の名曲。(10:50)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
梅雨は明けたそう。水不足は大丈夫?それとも真夏の豪雨がやってくるのか。沖縄ではキャベツ壱萬玉廃棄、出荷すればするほど赤字なんだそう。なんかとっても悲劇的な話題ですね。
気休めなんやけど・・・呑みに出掛ける前にはドラッグ・ストアに「ウコンの力」みたいなものを服用することがありました。(日本の居酒屋を堪能する卓爾治亜の別嬪さん「ナノちゃんねる」のナノちゃんはヘパリーゼを愛用している)先日は出発前最寄りの駅の店にそれを求めたらPB半額ほど?116円くらいのが出現、もともと気休めなんやからそれで充分。いつもよりかなり酒は過ぎて、夕方駅より自宅迄徒歩2kmほど、途中業務スーパーにパンとたまご、ねぎなど購入して帰宅、風呂に入ったあとに洗濯して早々に眠くなりました。朝にはほぼ干せ上がりました。
深夜途中覚醒はここのところ(酒抜きでも)いつものこと、無事二度寝もできて朝の体調もさほどに悪くはない、ちょっと怠い程度。ストレッチ、短いYouTube済ませて(気持ち根性ましましに)市立体育館へ。しっかり汗を流してMyメニューをこなせば体調は整います。この時点体重参考記録66.7kgそう変わらず、血圧は予想通り瀑上がり(大反省)今朝の体重は66.9kgほぼ前日と変わらずちょろ増え、食事をかなり意識して抑制して、しっかり運動しても「呑んだ翌々日は体重が増える」そんな経験は幾度もしております。昨夜は気温もちょっと落ち着いたせいか、しっかり朝迄眠れました。
前日、厳しく諌めた爺友は引退4年以上経っても「朝起きて、お仕事にいかなくても良い喜びを噛み締めている」との言葉、それはまったく同感。自分は毎日音楽をじっくり聴いたり、YouTube動画やドラマ、料理レシピ検索など拝見してユルい、シアワセな時間を過ごしております。
 Brahms ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調~ヴァン・クライバーン(p)/キリル・コンドラシン/モスクワ・フィル(1962年ライヴ)・・・おそらくは旧ソヴィエット再訪問時の映像音源。冒頭ちょっぴりオーケストラの響きが割れるけれど、概ね状態のよろしい音質(ステレオ?)でした。鬱蒼として重厚なピアノ・オブリガート付きの交響曲風威容を誇る作品。3年ほど前に聴いたメモはあって、この作品は大好きだから、ほぼどんな演奏にも感銘深く受け止められるもの。この時点Van Cliburn(1934-2013亜米利加)はスムースな技巧に、瑞々しい感性を失っておりません。亜米利加のみならず当時のソヴィエットでも大人気だったみたいですね。
Brahms ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調~ヴァン・クライバーン(p)/キリル・コンドラシン/モスクワ・フィル(1962年ライヴ)・・・おそらくは旧ソヴィエット再訪問時の映像音源。冒頭ちょっぴりオーケストラの響きが割れるけれど、概ね状態のよろしい音質(ステレオ?)でした。鬱蒼として重厚なピアノ・オブリガート付きの交響曲風威容を誇る作品。3年ほど前に聴いたメモはあって、この作品は大好きだから、ほぼどんな演奏にも感銘深く受け止められるもの。この時点Van Cliburn(1934-2013亜米利加)はスムースな技巧に、瑞々しい感性を失っておりません。亜米利加のみならず当時のソヴィエットでも大人気だったみたいですね。
第1楽章「Allegro non troppo」いつものイメージ通り、余裕の明朗に瑞々しいタッチに楽天的な風情。独墺系鬱陶しいほどの重厚深遠さ、威圧感とは異なるピアノにはキレがあって、作品に爽やかな熱気と鮮度を感じさせました。コンドラシンとの息はぴったりでしょう。(17:57)
第2楽章「Allegro appassionato」巨壁が崩れ落ちるようなスケルツォ。切迫するピアノ、テンポの揺れにも微妙なデリカシーと勢いがあって、切なさが募ります。(8:34)
第3楽章「Andante」この楽章以降トランペットとティンパニが抜け、ここの主題は絶品のチェロが歌って弦や木管に引き継がれました。やがてピアノは静かに参入して無垢に安寧の風情漂って、やがて情感は切々と高まります。ピアノのタッチはあくまで明るく、神経質を感じさせぬもの。ここは管弦楽とソロの対話が絶品、魅惑の緩徐楽章。(12:01)
第4楽章「Allegretto grazioso」ここは時に精神の陰りはあるけれど、トランペットもティンパニもない抑制の効いた上機嫌なフィナーレ。剛直より可憐さを感じさせるピアノはデリケートに明るさを失わない。モスクワ・フィルとのバランスにも文句はありません。(9:14/拍手込み)
 Tchaikovsky ピアノ協奏曲第1番 変ロ長調~ヴァン・クライバーン(p)/キリル・コンドラシン/モスクワ・フィル(1962年モスクワ・ライヴ)・・・コンクール優勝4年後の再訪の演奏会より。映像が出ていて、当時の最高権力者フルシチョフ第1書紀も臨席していたそう。かなり状態のよろしいモノラル音源は露西亜の怪しいサイトより入手したもの、他GriegとRachmaninovの第2番同時入手。28歳、未だ瑞々しい感性を維持していた時期の記録。彼の録音には必須のコンドラシンは当時の手兵を従えて、ソロとの息はぴたり、第1楽章冒頭のホルンぶちかましからオーケストラは好調でした。楽天的に明るい音色、余裕のテクニックに爽やかな高揚感が継続する圧巻のピアノ、この時点に後年の陰りは感じさせぬ輝きたっぷりでした。
Tchaikovsky ピアノ協奏曲第1番 変ロ長調~ヴァン・クライバーン(p)/キリル・コンドラシン/モスクワ・フィル(1962年モスクワ・ライヴ)・・・コンクール優勝4年後の再訪の演奏会より。映像が出ていて、当時の最高権力者フルシチョフ第1書紀も臨席していたそう。かなり状態のよろしいモノラル音源は露西亜の怪しいサイトより入手したもの、他GriegとRachmaninovの第2番同時入手。28歳、未だ瑞々しい感性を維持していた時期の記録。彼の録音には必須のコンドラシンは当時の手兵を従えて、ソロとの息はぴたり、第1楽章冒頭のホルンぶちかましからオーケストラは好調でした。楽天的に明るい音色、余裕のテクニックに爽やかな高揚感が継続する圧巻のピアノ、この時点に後年の陰りは感じさせぬ輝きたっぷりでした。
第1楽章「Allegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito」/第2楽章「Andantino semplice - Prestissimo - Tempo I」/第3楽章「Allegro con fuoco」(36:18/拍手込)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日は快晴。前夜女房殿は婆さん宅に泊まりだったので独り(朝送り出さないとデイ・サービスをサボってしまう)。深夜途中覚醒がクセになって、二度寝も眠りが浅い。左膝の調子はかなり良好、朝ゴミ出しに出たけれど腰の違和感もありません。いつものストレッチ、短いYouTubeエアロビクス済ませて微妙に頭痛があるのは睡眠不如意のせいでしょう。気分転換にご近所コンビニ迄ネット銀行端末処理にちょっぴりウォーキングして、昼から早々に爺友との待ち合わせに出掛けました。今朝の体重は66.85kg+450g。
奴らは呑みだすと止まらない性格は知っているので「次の店」は辞去してさっさと帰るように心掛けております。もうムリできる年齢(とし)でもないっすよ。ムダ金も使いたくないし・・・と、事前に思っていたのに、結果的にもう一軒居酒屋に付き合ったのは、自分より一年先60歳で引退した爺友にどうしても云っておきたいことがあったから。
もう4年経ったのに、現役時代のマネージャーとしての立場、言い種が意識せずに出てしまうこと。もう、自分ら以外誰ともほぼお付き合いもないから、ま、問題はないけれど、時に不快な上から目線を(エラソーに)感じていたことをはっきり指摘いたしました。自分は当時のお仕事ぶりの評価について、他人のことに言及することは絶対にないし、自分のことも今更(冗談めかしても)云々されたくもない。もう引退したんじゃないの、全部忘れようよ、そうかなりキツく申し渡しました。おっさんサラリーマンの成れの果ては、いつまでも自分の消え去った過去の立ち位置基準を忘れぬものか、女性はもっと潔いでしょう。
男子バレー対(大会初出場)烏克蘭戦は2-3フルセット敗退とのこと。これからビデオでしっかり拝見いたしましょう。次は斯洛文尼亜です。
ヘンタイ小学校教諭集団には呆れるばかり、こどもを学校に通わせるご両親や爺婆は気が気じゃないでしょう。おそらくは大多数の先生は身を粉にして日々奮闘されていると思うけれど、ストレスの多いお仕事、しかもある種の閉鎖社会だからヘンなことも起こる可能性はあります。信じられぬようなモンスター・ペアレントの噂もあります。もう本人の良心のみに頼るような日本社会じゃなくなりつつあるのか、イジメ隠蔽とある意味同根かも知れません。教師不足、つまり教師希望者が減って質的な劣化もそれに伴って発生しているのでしょうか。大学の親しい後輩がかなり教員になったけれど、既に引退世代。甥夫婦が埼玉県で教員をしているけれど、どんな実態か伺う機会もありません。
またまた逆走事故。飲酒でベンツ運転?若い人みたいだからご老人の話題ではありません。どうしてこんなに逆走や異常運転が増えてしまったのか。ひょっこり自転車野郎は実刑判決とのこと。
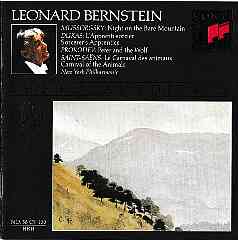 Mussorgsky 交響詩「禿山の一夜」/Ducas 交響詩「魔法使いの弟子」(1965年)/Prokofiev 交響的物語「ピーターと狼」(1960年)/組曲「動物の謝肉祭」(1962年)/交響詩「死の舞踏」(1967年)~レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィル・・・このRoyal Editionはデザインセンスはよろしくないけれど、収録はお得用盛りだくさん。音質はちょいと大味だけど、分厚い響きはかなり良好でした。大好きな作品ばかり、ま、演奏がどうのとかあまりムツカしいことを云うようなものでもないけれど、どれも熱気に充ちて骨太な勢い、最近この時期(1960年代)のLeonard Bernstein(1918-1990亜米利加)の少々荒っぽい元気な演奏を気に入っております。
Mussorgsky 交響詩「禿山の一夜」/Ducas 交響詩「魔法使いの弟子」(1965年)/Prokofiev 交響的物語「ピーターと狼」(1960年)/組曲「動物の謝肉祭」(1962年)/交響詩「死の舞踏」(1967年)~レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィル・・・このRoyal Editionはデザインセンスはよろしくないけれど、収録はお得用盛りだくさん。音質はちょいと大味だけど、分厚い響きはかなり良好でした。大好きな作品ばかり、ま、演奏がどうのとかあまりムツカしいことを云うようなものでもないけれど、どれも熱気に充ちて骨太な勢い、最近この時期(1960年代)のLeonard Bernstein(1918-1990亜米利加)の少々荒っぽい元気な演奏を気に入っております。
メタリックな響きにやや遅いテンポが重く、不気味な「Night On The Bare Mountain」(Rimsky-Korsakov編/10:57)
ディズニーの「Fantasia」に登場するミッキー・マウスにすっかり人気作品となった「L'apprenti Sorcier」は華やかな管弦楽技法、打楽器も7種ほど駆使して、前のめりの熱気を感じさせてユーモラス。パワフルな重量級サウンドに表情付けは入念にテンポは動きます。(10:36)
Prokofiev「Peter And The Wolf」にはナレーションが入っていないのも音楽の流れがよろしい感じ。爽やかにわかりやすい旋律作品、よく歌って表情は晴れやかに元気いっぱい、管楽器は名人揃えて、弦も優雅に美しい。
Andantino(0:54)Allegro - Andantino, Come Prima(1:13)L'istesso Tempo - Piu Mosso(2:00)Moderato - Allegro Ma Non Troppo - Moderato(1:43)Poco Piu Andante(0:51)Andante Molto(0:53)Nervoso - Allegro - Andante(0:55)Allegretto - Moderato(1:15)Andantino, Come Prima - Meno Mosso(1:18)Vivo - Andante Molto - Vivo - Andante(0:53)Allegro - Poco Meno Mosso - Moderato (Meno Mosso)(1:01)Allegro Moderato(1:23)Andante(1:21)Moderato - Poco Piu Mosso (Allegro Moderato) - Sostenuto - L'istesso Tempo - Poco Piu Mosso(0:36)Andante - Allegro(0:30)
Saint-Sae"ns「Le Carnaval Des Animaux」も音楽のみ、きらきらと楽しく、夢見るように大好きな作品でした。著名な「白鳥」はずいぶんとジミな音色やなぁ、と思ったらチェロならぬ名手Gary Carr(1941-亜米利加)によるコントラバス・ソロだったのですね。華やかなフルートは名人ポーラ・ロビンソン(Paula Robison,1941-亜米利加)でした。
No 1 Introduction Et Marche Royale Du Lion(1:51)No 2 Poules Et Coqs(0:44)No 3 Hemiones(0:37)No 4 Tortues(1:30)No 5 L'Elephant(1:11)No 6 Kangourous(0:58)No 7 Aquarium-David Hopper(Glockenspiel)(2:14)No 8 Personnages A Longues Oreilles(0:38)No 9 Le Coucou Au Fond Des Bois(2:02)No 10 Voliere-Paula Robinson(fl)(1:07)No 11 Pianistes(1:08)No 12 Fossiles-Paul Green(cl)Tony Cirone(Xylophone)(1:17)No 13 Le Cygne-Gary Carr(cb)(1:59)No 14 Finale(1:59)
「Danse Macabre」スコルダトゥーラ(変則調弦)ヴァイオリン・ソロはDavid Nadien(1926-2014亜米利加)。これは怪しい死神を表現しているそう。1875年の初演は大失敗「シロフォンによる骨のかち合う表現などは作曲者の悪趣味の極み」(Wikiより)そんな評判だったらしい。そのシロフォンがなかなかのアクセントに不気味、ステキな作品でした。パワフルに粗っぽいけど、なかなかのアツい演奏。(7:00)
 Stravinsy バレエ組曲「火の鳥」(1919年版)~レナード・ バーンスタイン/イスラエル・フィル(1984年)・・・バーンスタインは1957年ニューヨーク・フィルとの録音でも短い、編成の比較的小さな1919年版を録音しておりました。
Stravinsy バレエ組曲「火の鳥」(1919年版)~レナード・ バーンスタイン/イスラエル・フィル(1984年)・・・バーンスタインは1957年ニューヨーク・フィルとの録音でも短い、編成の比較的小さな1919年版を録音しておりました。
イスラエル・フィルをその能力いっぱいまでドライヴしきった、バーンスタインの快演ニューヨーク・フィル時代の演奏と比べると、その差歴然・・・はるかに生気に満ちてグロテスクしてる
とは某宣伝文句抜粋。音楽は嗜好品なので演奏評価の良し悪し、好き嫌いは当然の前提として・・・この演奏はオーケストラの技量も音楽に対する熱気や集中力も、がっかりするほど落ちると感じます。アンサンブルはもっさりとして重く、リアルな音質?にその冴えない響きが際立ちます。ま、こちらメルヘンに賑やかな作品、上記コメントは「春の祭典」込のことらしいから、そちらのことでしょう。あちこち称賛のコメントを探してみたけれど、ほとんど話題になっておりませんでした。残念。たまたま、偶然に「火の鳥」のみ不調だったのかも。「春の祭典」「ペトルーシュカ」はこれから拝聴いたしましょう。
Introduction(3:35)The Firebird and its Dance(0:15)Variation of the Firebird(1:19)Ring dance of the Princesses(5:34)Infernal Dance of King Kashchey(4:18)Lullaby(3:54)Finale(3:28)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
トカラ列島付近の連続する地震がちょっと不安です。
前日蒸々した暑さに連続途中覚醒して二度寝、良質な眠りは足りない。昨日朝「ほぼ降っておりません」というのはリアル、洗濯物をしっかりベランダに干して、YouTubeエアロビクス済ませて市立体育館に出掛けたら、途中ぽつぽつ降り出しました。鍛錬中はジャジャ降り、女房殿は洗濯物を室内に移動してくれました。トレーニングルームは珍しく妙齢の女性多数派、マシンは順番通り使えてシャワー後血圧計測は・・・ついに最高122!正常域へ。ま、たまたま偶然瞬間参考記録かも知れないし、一喜一憂せず明日以降の数値に注目しましょう。そんな矢先、とっても悪い爺友から酒の誘い、せっかくのダイエットはこれで中断となります。わかっちゃいるけど・・・情けない。自業自得だけど明日の体重、血圧が心配です。今朝の体重は66.4kg▲350g思ったより減りません。
男子バレー勃牙利ラウンドは格下相手のはずが、現地の応援を受けた相手チームの若さと高さに負けて0-3。セッターは永露、未だチームとしては息が合っていないのか。続く強豪前回覇者仏蘭西戦は3-2白熱の逆転勝利。宮浦の活躍が素晴らしい。本日夜は烏克蘭戦です。
Yahoo!によく出てくるカンタンな計算式、自分はずっと算数は苦手と自覚しているけれど、けっこうほぼ100%正解できて、小学生時代のお勉強が現在に役立っておりました。読み書き算盤は教育の基礎。
やはりよく出てくる漢字の正しい読みは、専門知識必須前提以外ならば、かなり正答率は高いはず。植物や魚、昆虫や動物のムツかしい名前にはお手上げになることもありました。(地名は意外と得意)
先日某ブログを拝見して「夏ツバキ=沙羅双樹の花」とは浅学にして初めて伺いました。平家物語冒頭ですよね。阿諛追従(あゆついしょう)に長(た)けた~この言葉は忖度上手ということでしょうか。(NHK「森友問題」番組を思い出しました)これはぎりぎり読めました。梅雨入(ついり) と読むでのですね、これは正直知らんかった。「閉門蟄居(へいもんちっきょ)の身」これは時代小説に出てくるから知っているけれど、現代では体調よろしくなくじっと自宅に身動きしない様子を意味しているようでした。
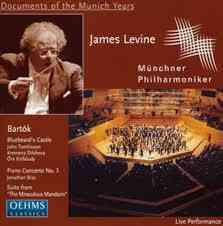 Bartok 歌劇「青髭公の城」~ジェームズ・レヴァイン/ミュンヘン・フィル/ジョン・トムリンソン(bb)/クレメーナ・ディチェーヴァ(s)/エルス・キスファルディ(語り)(2003年ライヴ)・・・晩節を汚して病のうちに亡くなったJames Levine(1943-2021亜米利加)あまり評判はよろしくなかったミュンヘン時代1999-2004年の記録。おそらくは演奏会形式の上演なのでしょう。四管編成、打楽器は8種、オルガン、チェレスタ、ハープ2台、トランペット4、トロンボーン4の舞台裏バンダも必要とする大掛かりな作品。ミュンヘン・フィル時代レヴァインのリハーサル時間は短かったそう。それでもメトロポリタンでの豊富な経験から、ちゃんと本番に完成度高く間に合わせたのでしょう。
Bartok 歌劇「青髭公の城」~ジェームズ・レヴァイン/ミュンヘン・フィル/ジョン・トムリンソン(bb)/クレメーナ・ディチェーヴァ(s)/エルス・キスファルディ(語り)(2003年ライヴ)・・・晩節を汚して病のうちに亡くなったJames Levine(1943-2021亜米利加)あまり評判はよろしくなかったミュンヘン時代1999-2004年の記録。おそらくは演奏会形式の上演なのでしょう。四管編成、打楽器は8種、オルガン、チェレスタ、ハープ2台、トランペット4、トロンボーン4の舞台裏バンダも必要とする大掛かりな作品。ミュンヘン・フィル時代レヴァインのリハーサル時間は短かったそう。それでもメトロポリタンでの豊富な経験から、ちゃんと本番に完成度高く間に合わせたのでしょう。
オリジナルの筋は青髭公が新しい妻を次々と城に迎え、殺してしまう~そんな筋だったと思うけど(そんな古い洋画をテレビで見た記憶がある)ここでは過去の妻たちは幻想的な象徴となって、いつもの暴力的かつローカルな旋律リズムとは異なった幻想的に魅惑のサウンドとなっておりました。但し、一連のミュンヘン・フィルとのライヴ音源はどうも乾き気味、陰影や怪しさに足りない?明るく響きました。オペラ・ド・シロウトである自分が云々するのはナニだけど、二人の歌い手は安定した歌唱と感じました。
拍手(0:24)
プロローグ「さて、ひそやかな言い伝え」(語り部)(6:27)ユディット「これが青髭の城なのね」(5:34)
ユディット「大きなとびらが閉まっているわ」(4:41)
第一の扉 ユディット「ああ!」-青髭「何が見えるかね?」(4:29)
第二の扉 青髭「何が見えるかね?」(4:39)
第三の扉 ユディット「おお、たくさんの宝もの!」(2:51)
第四の扉 ユディット「おお!花だわ!」(5:22)
第五の扉 青髭「ごらん、城の中が明るくなってきた」(6:50)
第六の扉 ユディット「静かな白い湖が見える」(5:09)
青髭「最後のとびらは開けないぞ」(4:31)
ユディット「わかっているの、わかっているの、青髭よ」(4:13)
第七の扉 青髭「むかしの女たちを見るがいい」(11:25/長い拍手込み)
 Bruckner 交響曲第9番ニ短調~デニス・ラッセル・デイヴィス/リンツ・ブルックナー管弦楽団(2005年ライヴ)・・・Dennis Russell Davies(1944ー亜米利加)はBrucknerやHaydnの交響曲全集を録音して、同時代の音楽にも造詣が深い人、いずれもあまり話題ににはなっていないような感じ。このBrucknerも音源を入手して数年を経て、3-4曲しか手を付けておりませんでした。三管編成+ティンパニ、ワーグナー・チューバ入り、未完の作品。音質は解像度高く良好。以下いろいろ文句つけたけれど、さっぱり風情も悪くない演奏と受け止めて、作品を充分堪能できる演奏でした。
Bruckner 交響曲第9番ニ短調~デニス・ラッセル・デイヴィス/リンツ・ブルックナー管弦楽団(2005年ライヴ)・・・Dennis Russell Davies(1944ー亜米利加)はBrucknerやHaydnの交響曲全集を録音して、同時代の音楽にも造詣が深い人、いずれもあまり話題ににはなっていないような感じ。このBrucknerも音源を入手して数年を経て、3-4曲しか手を付けておりませんでした。三管編成+ティンパニ、ワーグナー・チューバ入り、未完の作品。音質は解像度高く良好。以下いろいろ文句つけたけれど、さっぱり風情も悪くない演奏と受け止めて、作品を充分堪能できる演奏でした。
第1楽章「Feierlich, misterioso」静かな波が寄せては返す、広い浜辺の情景を彷彿とさせる神々しい始まり、D・R・デイディスは煽ったり走ったりとは無縁に常に一歩引いてクールな表情+オーケストラの響きはわずかに軽量。仕上げは細部迄丁寧に神妙、清潔だけれど、やや響きは素っ気なく淡々というかヤワく、パワーやカタルシスに物足りなさを覚えます。(25:11)
第2楽章「Scherzo: Bewegt, lebhaft」神妙かつ緊張感高まるピチカートから、熱狂的な法華の太鼓が激しいリズムを刻むところ。ここも金管のパワーは今一歩、突き抜けた爆発に足りない知的な抑制を感じさせました。トリオの肩の力が抜けた風情はなかなか対比よろしく、表現意欲やサウンドバランスはっけして悪くはない。オーケストラが弱いのかな。(11:00)
第3楽章「Adagio: Langsam feierlich」未完成だけど万感胸に迫る諦観に充ちて、人生の締めくくりを感じさせる緩徐楽章。天空に登るようなしみじみとした弦から、金管のクライマックスがやってきて、やはりここはもっと壮絶なパワーを!お願いしたい。続くワーグナー・チューバは神々しい。第2主題は優しく、深く、そしてちょっと緊張が弱い。足取りは軽めに、贅沢云えばホルンの音色はすっきり素直過ぎ、上手いけどね。ド・シロウトの戯言さておき、神々しい作品にたっぷり感動をいただきましたよ。(23:24)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
こちら前夜半には雨は上がって、朝もほぼ降っておりません。気温は30度Cくらい迄上がって、なんせ湿度が高く不快。深夜途中覚醒して二度寝したけど、眠りは浅いまま。体調は悪くなくて、左膝も悪化はしていないけれど、改善もしていない。なんとかストレッチはいつもどおりこなせる程度。YouTubeエアロビクスはいつもの東南亜細亜系女性がシンプルに動き続けるものを実施しました。あとはいつもどおりのヒマな生活が続きます。今朝の体重は66.75kg+450g、久々のピーナツ復活があかんかったのか。反省。
以色列と伊蘭の停戦合意とか。それがほんまに実効化することを祈っております。
自分はパチンコ競馬競輪競艇とは一切無縁の人生を送ってきたので、この間世間を騒がしているオンラインカジノとやらの詳細はまったく理解できません。(株主総会直前の)フジテレビでは逮捕者も出て、ギャンブル依存症と自覚していたそう。けっこう日本には無法に蔓延しているのですね。プロ・スポーツ選手とか放送関係者、芸能人ばかり話題になっているけれど、一般社会のサラリーマンとか主婦とか学生とか、じつはたくさん隠れているものか、想像もつきません。そして「オンライン」ならぬ(万博後)ほんまもんの「カジノ」建設とやら、これはまったく別モンの”佳きもの”なのか、かなり疑問。博打中毒者量産なんじゃないの。「万博の赤字を”カジノ”で埋める」なんていう理屈がまかり通るのでしょうか。
男子バレー勃牙利ラウンド第1戦は御当地勃牙利戦、0-3完敗との結果だったとのこと。残念。
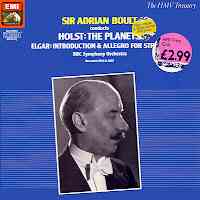 Holst 組曲「惑星」~エイドリアン・ボウルト/BBC交響楽団(1945年)・・・Adrian Boult(1889-1983英国)の十八番「惑星」音源在庫を確認すると一番最初の録音を発見、じつは2021年に拝聴済。この時期にして音質かなり良好、2007年には既に聴いていた記録もありました。
Holst 組曲「惑星」~エイドリアン・ボウルト/BBC交響楽団(1945年)・・・Adrian Boult(1889-1983英国)の十八番「惑星」音源在庫を確認すると一番最初の録音を発見、じつは2021年に拝聴済。この時期にして音質かなり良好、2007年には既に聴いていた記録もありました。
颯爽と華やか、スペクタクルにカッコ良い作品、この人は幾度録音を重ねてこの作品を普及させた立役者、四管編成にティンパニ6台(二人)打楽器9種(三人)チェレスタ、オルガン、ハープに女声ヴォカリーズが入る盛大なる規模を誇ります。新しい”映える”音質で聴いたほうが良いに決まっているけれど「木星」の壮麗なスケール、「火星」「海王星」に於ける強烈なリズムにさほどの不満も覚えぬもの。「土星」や「天王星」の静謐を聴き取るのに苦痛はありませんでした。56歳壮年の気力と自信に溢れて、戦後間もないBBC交響楽団も意外と充実しておりました。(47:18/楽章間含む一本ファイル)
 Schubert 交響曲第9番ハ長調~カール・ベーム/ベルリン・フィル(1963年)・・・駅売海賊盤を偏愛していた20世紀後半に聴いて、かっちりしすぎてオモロない、当時はそう感じたもの。Schubertの交響曲中、深遠な思索を感じさせる第8番ロ短調と並んで、平易に歌謡的旋律が延々と続くスケール大きな作品は大好き、拝聴機会は多いものです。これは鉄板の世評だったと記憶するけれど、時に流れとともにその存在をすっかり忘れておりました。交響曲全曲録音していた?ことも記憶の彼方。Karl Bo"hm(1894-1981墺太利)69歳、未だ矍鑠としてテンポやアンサンブルも弛緩せず、楷書に几帳面なアンサンブル、オーソドックスに引き締まった演奏は聴き応えたっぷり。美しい旋律は虚飾なく映えました。音質も良好。最近古楽器系の素朴な響きや軽妙なリズムをを好んで聴くけれど、こちら昔馴染みの立派な風情も悪くない感じ。
Schubert 交響曲第9番ハ長調~カール・ベーム/ベルリン・フィル(1963年)・・・駅売海賊盤を偏愛していた20世紀後半に聴いて、かっちりしすぎてオモロない、当時はそう感じたもの。Schubertの交響曲中、深遠な思索を感じさせる第8番ロ短調と並んで、平易に歌謡的旋律が延々と続くスケール大きな作品は大好き、拝聴機会は多いものです。これは鉄板の世評だったと記憶するけれど、時に流れとともにその存在をすっかり忘れておりました。交響曲全曲録音していた?ことも記憶の彼方。Karl Bo"hm(1894-1981墺太利)69歳、未だ矍鑠としてテンポやアンサンブルも弛緩せず、楷書に几帳面なアンサンブル、オーソドックスに引き締まった演奏は聴き応えたっぷり。美しい旋律は虚飾なく映えました。音質も良好。最近古楽器系の素朴な響きや軽妙なリズムをを好んで聴くけれど、こちら昔馴染みの立派な風情も悪くない感じ。
第1楽章「Andante - Allegro ma non troppo」冒頭のホルンから既にカラヤン時代のベルリン・フィルは辛口に響いて、かっちりと噛み締めるようなアクセントにテンションは充分に高く、疾走感もパワーも充分でした。繰り返しなしは残念。ラストの大仰なルバートも時代を感じさせて微笑ましい。(14:23)
第2楽章「Andante con moto」途方に暮れたオーボエと激烈な弦がリズムを刻む対比際立つ、異形の緩徐楽章。ここも生真面目に清潔なフレージングが印象的なアンサンブルでした。中間部のスムースなホルンは絶品。ラストに向けてのさっくりとした軽い流れの対比も上々でした。(13:53)
第3楽章「Scherzo: Allegro vivace」ここも几帳面なアンサンブルにあまり颯爽としない、不器用に重量感たっぷり。噛み締めるように急がぬスケルツォ。トリオのワルツ?もあまり対比を強調しない、やや一本調子。(11:18)
第4楽章「Allegro vivace」想像より(記憶より)テンポは速め。質実かつ重量級、颯爽とテンションの高いフィナーレ。ベルリン・フィルは圧巻の技量に力技に押し切った感じでした。(11:25)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
鹿児島、新見、関では大雨降ったようですね。台風2号接近中関東地方にもこれから大雨予報が出たようです。昨日朝はけっこうな雨、あとは終日ちょっと降ったりやんだり、夕方には一時ジャジャ降りへ(ここからワリと近い)南山城村にも警報が出ました。
やや左膝腰に鈍い痛みはあるけれどいつものストレッチに関節の可動域は確保できました。YouTubeエアロビクスはいつもどおり10分ほど実施してから市立体育館へは傘は必要でした。トレーニングルームは自転車組がお休みだから空いていて、順調にMyメニューをこなせました。盛大な汗にシャワー済ませて、血圧は一昨日より下がったけれど未だ高い。帰り自家製ヨーグルト用の牛乳と朝食用チーズ入手してから帰宅して、一日の鍛錬目標を達成いたしました。今朝の体重は66.3kg▲150g、65kg台への道は遠い。
観光や在日居住している外国人の方の動画はよく眺めて、こちら日常当たり前としている生活に新しい価値を見出してくださるからけっこう新鮮に感じます。オーバーツーリズムや非常識迷惑外国人は論外、コンビニが便利トイレがキレイ、そんなありきたりな話題はもう陳腐になりました。感心したのは時節柄、紫陽花の美しさに目覚めた方々が多いこと。その前にツツジもあったんやけどなぁ、古刹名所に美しい季節の花が映えます。
日本を愛して、ありきたりな観光地に非ず、地方の自然風景や環境を堪能される動画も増えて、メジャーな観光地、便利な都会のみならず、人里離れた田舎でも美味しいもの、それなり便利な生活を営めるところが日本の良いところでしょう。但し、少子化、高齢化、人口減、経済の衰退、インフラの劣化は覆うべくもないリアルな現実です。
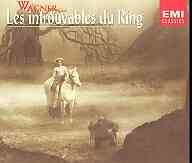 Wagner「知られざるリング/Les introuvables du Ring」(EMI)よりCD4
Wagner「知られざるリング/Les introuvables du Ring」(EMI)よりCD4
かなり以前より聴いていた記憶も鮮明な音源(4CD分)は「音楽日誌」にも記録は探せません。(「ラインの黄金」(抜粋)ルドルフ・ケンペ/ベルリン州立歌劇場/は別途言及有、それも含まれます)EMIの蔵出し音源はおそらく往年の名歌手のための録音寄せ集め。久々に音源入手できました。オーケストラは主にフィルハーモニア管弦楽団が担当しておりました(これは優秀なアンサンブル)。歌い手は著名な人ばかり、指揮陣はGeorges Sebastian(1903ー1989洪牙利→仏蘭西)Hermann Weigert (1890-1955波蘭→亜米利加)辺りはあまり聴いたことのない指揮者でした。「神々の黄昏」の旋律は馴染みだけど、オペラ・ド・シロウト(=ワシ)には全曲聴き通すのはなかなかの難行苦行、こうしてCD1枚分エエトコ取りしてくださると助かります。著名なWolfgang Sawallisch(1923-2013独逸)の管弦楽作品はステレオ、ほか音質はかなり良心的。モノラル録音は人工的に広がりを入れているものもあって(フルトヴェングラー)それなり聴きやすい。
自分はオペラ・ド・シロウト故、演奏歌云々もちろん言及不可。馴染みの旋律、鬼気迫る往年の名歌手の熱気を感じ取りましたよ、そんな記録のみいちおうメモしておきましょう。Kirsten Flagstad(1895-1962諾威)の気品ある貫禄、Set Svanholm(1904-1964瑞典)のカッコよさ、Gottlob Frick(1906-1994独逸)の重量感は理解できました。太古音源、寄せ集めでも聴手を高揚させる魅力たっぷり。管弦楽演奏にWagnerの旋律を学んだけれど、歌が入ってこその画竜点睛。フルトヴェングラーにはこんな録音もあったのですね。その異様な集中力とテンポの動きの説得力は期待通りでした。
楽劇「神々の黄昏」より(最初に「夜明け」の収録が欲しかったところ)
序幕「Zu Neuen Taten, Teurer Helde」(2:38)/「Mehr Gabst Du, Wunderfrau」(6:35)/「O Heilige Gotter!」(3:03)(ジョルジュ・セバスチャン/フィルハーモニア管弦楽団(1951年)/キルステン・フラグスタート(s)(ブリュンヒルデ)/セット・スヴァンホルム(t)(ジークフリート))
「Siegfrieds Rheinfahrt」ホルンの技量は圧巻!(7:00)(ヴォルフガング・サヴァリッシュ/フィルハーモニア管弦楽団/1958年)
第1幕「Hier Sitz' Ich Zur Wacht」(4:21)/第2幕「Hoiho! Hoihohoho!」(10:03)(フランツ・コンヴィチュニー/ベルリン州立歌劇場/合唱団(1959年)/ゴットロープ・フリック(b)(ハーゲン))オーケストラの艶がフィルハーモニアとは異なる個性。これもステレオ。
第2幕「Helle Wehr! Heilige Waffe」(2:41)(ヘルマン・ヴァイゲルト/フィルハーモニア管弦楽団(1951年)/キルステン・フラグスタート(s)(ブリュンヒルデ)/セット・スヴァンホルム(t)(ジークフリート))
第3幕「Traumermarsch」(8:48)(ヴォルフガング・サヴァリッシュ/フィルハーモニア管弦楽団/1958年)けっこう劇的な説得力。
「Starke Scheite Schichtet Mir Dort」(2:32)/「Wie Sonne Lauter Strahlt Mir Sein Licht」(2:22)/「O Ihr, Der Eide Ewige Huter!」(3:45)/「Mein Erbe Nun Nehm' Ich Zu Eigen」(2:33)/「Fliegt Heim, Ihr Raben!」(1:16)/「Grane, Mein Ros, Sei Mir gegrusst!」(6:28)(ウィルヘルム・フルトヴェングラー/フィルハーモニア管弦楽団(1948年)/キルステン・フラグスタート(s)(ブリュンヒルデ))
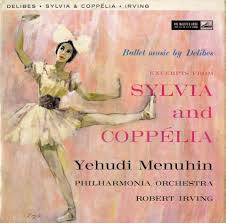 Delibes バレエ音楽「コッペリア」(前奏曲/マズルカ/ワルツ-「麦の穂」バラード/スラヴの主題と変奏曲/祈り/チャルダッシュ)/バレエ音楽「シルヴィア」(前奏曲/間奏曲/ゆるやかなワルツ/ピチカート-アンダンテ/行進曲とバッカスの行列)~ロバート・アーヴィング/フィルハーモニア管弦楽団/ユーディ・メニューイン(v)(1959年)・・・もうCDはほぼすべて処分済だけれど、懐かしい駅売海賊盤はわずかに生き残っておりました。Robert Irving(1913-1991英国)はニューヨーク・シティ・バレエ団の音楽監督を長く務めた人(1958-1989年)前回拝聴は5年前2020年。音質は良好、オーケストラの響きは明るく、リズムは軽妙にあまり入念を極めぬ卒のない表現、、ラフなリズム感も作品風情に似合っておりました。これはお気に入りの作品、演奏です。
Delibes バレエ音楽「コッペリア」(前奏曲/マズルカ/ワルツ-「麦の穂」バラード/スラヴの主題と変奏曲/祈り/チャルダッシュ)/バレエ音楽「シルヴィア」(前奏曲/間奏曲/ゆるやかなワルツ/ピチカート-アンダンテ/行進曲とバッカスの行列)~ロバート・アーヴィング/フィルハーモニア管弦楽団/ユーディ・メニューイン(v)(1959年)・・・もうCDはほぼすべて処分済だけれど、懐かしい駅売海賊盤はわずかに生き残っておりました。Robert Irving(1913-1991英国)はニューヨーク・シティ・バレエ団の音楽監督を長く務めた人(1958-1989年)前回拝聴は5年前2020年。音質は良好、オーケストラの響きは明るく、リズムは軽妙にあまり入念を極めぬ卒のない表現、、ラフなリズム感も作品風情に似合っておりました。これはお気に入りの作品、演奏です。
「コッペリア」は二管編成。前奏曲はホルンがしっとり歌って~「マズルカ」はさっくりとしてシンプル、ヴィヴィッドなリズムを刻みました。(5:14)
「ワルツ」は淡々として素っ気なくさっぱり、これがバレエには実用的な演奏なのでしょう。(1:52)
「麦の穂のバラード」にYehudi Menuhin(1916-1999亜米利加)のヴァイオリン・ソロがヴィヴラートたっぷりに登場します。彼はエイドリアン・ボウルトのBrahms交響曲など、時々思わぬところで参加してますよね。(2:34)
「スラヴの主題と変奏曲」は愉快にリズミカルな主題から、華やかな管楽器とか細かい弦の刻みなど加わって色彩を加えました。ノンビリとしたクラリネットは名人芸でしょう。(6:29)
「祈り」は弱音器を付けた弦、木管も夢見るように美しい。(2:37)
ラスト「チャルダッシュ(ハンガリー舞曲)」は金管のファンファーレ風大仰な始まり、徐々に熱気とテンポ・アップして、期待通りの愉快な興奮が疾走しました。(3:17)
「シルヴィア」の楽器編成は調べが付かなかったけれど、おそらく二管編成。
前奏曲「狩りの女神」はWagner風にホルンが勇壮に活躍してカッコよい始まり。フィルハーモニア管弦楽団の管楽器は名人揃ってますよ。優雅な「マズルカ」間奏曲のクラリネットも上手いもの。表情豊かな「ゆるやかなワルツ」は心ときめくように華やかな旋律でした。(8:56)
「ピチカート」は題名通り、そっと静かに弦がつぶやいております。そっと管楽器がオブリガートして、おとなしい「ピチカート・ポルカ」風。(1:45)
「祈り(鐘の祭りのディヴェルティスマン)」は爽やかなクラリネット、フルートに導かれて「アンダンテ」にメニューイン再び登場してソロを披露します。「タイスの瞑想曲」に似て、もっと安寧に明るく晴れやかな感じ。(4:35)
ラスト「行進曲とバッカスの行進」はトランペットも勇壮に堂々としてカッコよい、Elgarの威風堂々を彷彿とさせました。(6:17)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
今朝はけっこうな雨。終日雨の予報です。昨日は朝一番より蒸し暑く、どんより曇って昼前ジャジャ降りの雨、洗濯物は急ぎ室内に取り込みました。女房殿は婆さんの耳鼻科の付き添いに出掛けて、自分は前夜眠り浅く、ぼちぼち昼寝しつつ、いつも通りのんびり過ごしました。
ビデオに録った女子バレー対捷克戦ゆっくり拝見。香港ラウンドは初戦の泰国戦から苦戦気味だったし、世界一の伊太利亜や中国に善戦しても敗れて、チームとしての課題は多かったと思います。捷克はチャレンジ・リーグから競り上がってきて勢いのあるチーム、もちろん高さも力もあります。今回もちょっと先行されたりしてヒヤヒヤしたけれど、無事立て直して3-0勝利!石川、和田の攻撃も決まり、リベロ福留も相変わらず凄い守り。さて、日本(千葉)ラウンドに向けて強豪との試合が続きます。どう若いチームを育成していくのでしょうか。それにしてもネットやマスコミの扱いが小さいのは残念。
左膝はほんのちょっとずつ軽快中、一時はこのまま悪化して否応なく整形外科受診も考えたけれど、マッサージ、ストレッチ+膏薬が効いたようです。いつものストレッチも問題なく、例の元気のよろしい東南亜細亜系女性によるYouTubeエアロビクス(短いの)実施いたしました。但し、昨夜辺りまたまた左腰に違和感はやや復活して、油断はできません。夕方あまりに不快、風呂上がりに(試しに)今季初エアコン動作確認して涼みました。本日これより女房殿は上の孫の保育所の参観日へ。
前月、健康診断三連覇ならず!残念な結果は体重増、内臓脂肪過多→肝臓の数値基準値オーバー、血圧も高い結果になったと反省しております。若い頃からの積年の内臓脂肪を退治するにはどうするのか!YouTubeに対策を検索していくつか眺めて、すっかり忘れていた当たり前のことを思い出しました。
ハラが出ている→腹筋を鍛えても凹みません。
結論。内臓脂肪だけは減らせない。全身脂肪を落として痩せて、初めて内臓脂肪もそれに従って減るということですよ。そういえば最近ずっと体重は増傾向に悩んでおりました。現在、ピーナツ/柿の種など間食を抑制ならぬ、ニ週間ほど完全に禁食して、ま、もちろん食事も抑制して現在鋭意減量努力途上だけど、行ったり来たり状態。カンタンには減ってくれません。今朝の体重は66.45kg▲550g。
「続・続・最後から二番目の恋」最終回も劇的な展開はほぼない、ゆるっとした終わりかたでした。もうテレビ・ドラマはもちろん、バラエティ番組ともすっかり無縁となって、必要に応じてニュースと二時間ドラマの再放送を眺めるくらい。ハデなアクションやら道ならぬ恋とか暴力・殺人とは無縁、なにも起こらないフツウの日常風景ドラマ、鎌倉の自然を堪能いたしました。ま、同世代ですし。あいかわらずCMはほとんどなし、番組ドラマ映画の宣伝ばかり。例のトラブル隠蔽はTV業界衰退に拍車が掛かったかも。
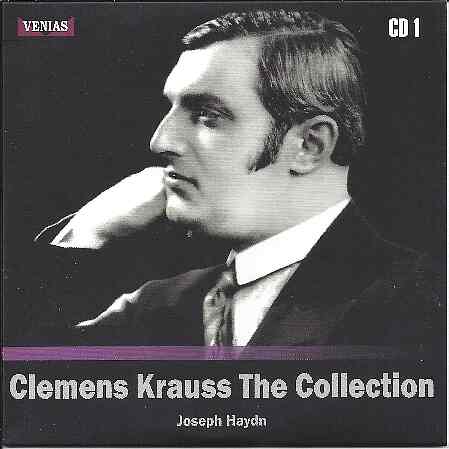 Enescu ルーマニア狂詩曲第1番(1944年)/Stravinsky バレエ組曲「プルチネルラ」(1947年版/1952年)/de Falla バレエ音楽「三角帽子」第2組曲(1953年)/Ducas 交響詩「魔法使いの弟子」(以上ウィーン・フィル1953年)/Ravel スペイン狂詩曲(バイエルン放送交響楽団1953年)~クレメンス・クラウス・・・2018年に一度ちょろ聴き。Clemens Krauss(1893ー1954墺太利)にはちょっと珍しい演目の記録はどれもモノラル時代に寿命が尽きたことを残念に思わせる記録でした。
Enescu ルーマニア狂詩曲第1番(1944年)/Stravinsky バレエ組曲「プルチネルラ」(1947年版/1952年)/de Falla バレエ音楽「三角帽子」第2組曲(1953年)/Ducas 交響詩「魔法使いの弟子」(以上ウィーン・フィル1953年)/Ravel スペイン狂詩曲(バイエルン放送交響楽団1953年)~クレメンス・クラウス・・・2018年に一度ちょろ聴き。Clemens Krauss(1893ー1954墺太利)にはちょっと珍しい演目の記録はどれもモノラル時代に寿命が尽きたことを残念に思わせる記録でした。
「ルーマニア狂詩曲」はユーモラスな風情に大仰な表情付けが楽しい作品。オーケストラには厚みもパワーも色気もあって、優雅にヴィヴィッドに最後は突っ走ります。音質もまずまず。(12:47)
Stravinskyは声楽の入らぬ組曲版、擬バロック風端正優雅な作品。ちょっと収録音量が低くて響き薄く、様子がわかりにくい音質が残念だけど、速めのテンポにヴィヴィッドにカッコ良い勢いの演奏。ここでもオーケストラに艶を感じさせます。
Overture: Sinfonia(15;12)Serenata(2:44)Scherzino(4:28)Tarantella(1:07)Toccata(0:52)Gavotta(2:53)Vivo(1:34)Menuetto(1:57)Finale(2:13/拍手込)
「三角帽子」は残念、第2組曲3曲のみ。たっぷり厚みと低音が効いた雰囲気のある音質。これが一番良好でしょう。西班牙風情に賑やかに愉しいリズムは、熱気に満ちて堂々たる優雅な演奏・・・だけど、できれば声楽入り全曲で聴きたいもの。
「The Neighbour's Dance: Sequidillas」 (3:21)The Miller's Dance: Farruca(2:57)Final Dance: Jota(11:31)
ユーモラスな「魔法使いの弟子」もウィーン・フィルには珍しいかも。これもちょっと音量低く、薄い音質だけど、演奏そのものはメリハリしっかりして、表情は大仰に豊かに、足取りはけっこう重量級でした。(11:31/拍手込)
「スペイン狂詩曲」はバイエルン放送交響楽団への客演。音質は曇りがちだけど、低音もしっかりして雰囲気はありました。
気怠いけど気品を感じさせる「前奏曲(Prelude a la nuit)」(4:34)リズム感はしっかり妖しい深みのある「マラゲーニャ(Malaguena)」(2:13)儚くもデリケートに華やかな「ハバネラ」(Habanera)ホルンの音色に厚みが感じられます(2:25)魅惑のフルートから始まる「祭り(Feria)」には浮き立つような細かい音型に祭りの浮き立つ気分、西班牙のリズムが快く響きました。(6:16)
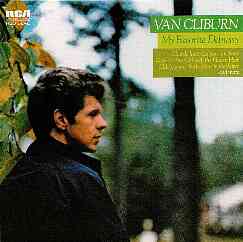 Debussy 練習曲集第1巻/第5番「オクターヴのために」/月の光がふりそそぐテラス/月の光/レントより遅く/雨の庭/夢/水の反映/花火/亜麻色の髪の乙女/グラナダの夕暮れ/喜びの島~ヴァン・クライバーン(p)(1972年)・・・Van Cliburn(1934-2013亜米利加)は1960年代売れに売れて、やがてRCA専属録音は協奏曲からオムニバス・ソロばかりとなりました。Beethovenのピアノ協奏曲も第1番第2番の録音が抜けて全曲録音は揃いません。この録音は39歳、まだまだこれからの年齢だったはず。明晰に楽天的な瑞々しいタッチは健在、もちろん技術的な問題はいっさいない、音質も良好。とくにちょっぴり切ない「レントより遅く」のゆったりとした風情は大好き、妖しい魅力あふれるDebussyの名旋律揃えて、ていねいに心のこもった仕上げ・・・けれど、心が波立つような陰影や、鬼気迫る緊張、唯一無二の個性にやや 不足、ワリとフツウと受け止めました。世評さておき、最晩年迄亜米利加ではたいへんな人気だったそう。名曲を堪能するには充分な存在でしょう。(2:42-4:18-5:14-4:44-3:32-4:49-5:32-4:10-2:47-5:51-6:38)
Debussy 練習曲集第1巻/第5番「オクターヴのために」/月の光がふりそそぐテラス/月の光/レントより遅く/雨の庭/夢/水の反映/花火/亜麻色の髪の乙女/グラナダの夕暮れ/喜びの島~ヴァン・クライバーン(p)(1972年)・・・Van Cliburn(1934-2013亜米利加)は1960年代売れに売れて、やがてRCA専属録音は協奏曲からオムニバス・ソロばかりとなりました。Beethovenのピアノ協奏曲も第1番第2番の録音が抜けて全曲録音は揃いません。この録音は39歳、まだまだこれからの年齢だったはず。明晰に楽天的な瑞々しいタッチは健在、もちろん技術的な問題はいっさいない、音質も良好。とくにちょっぴり切ない「レントより遅く」のゆったりとした風情は大好き、妖しい魅力あふれるDebussyの名旋律揃えて、ていねいに心のこもった仕上げ・・・けれど、心が波立つような陰影や、鬼気迫る緊張、唯一無二の個性にやや 不足、ワリとフツウと受け止めました。世評さておき、最晩年迄亜米利加ではたいへんな人気だったそう。名曲を堪能するには充分な存在でしょう。(2:42-4:18-5:14-4:44-3:32-4:49-5:32-4:10-2:47-5:51-6:38)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日日曜も猛暑続き。いつもどおりの朝を迎えて左膝はちょっぴり軽快、腰にもまったく違和感もなくいつものストレッチ、東南亜細亜系どこの国かわからんお姉さんによるYouTubeエアロビクスは背景にある国旗から越南を類推できました。夜は相変わらずの痰の絡み+気温湿度の関係で夢見よろしくなく、眠りが浅い。
こちら社会的接点を失った引退爺だけど、ちょっと不安だったネット銀行の扱い、来月に迫った萩旅行の夜の居酒屋ネット予約に苦戦、地元の居酒屋はネット予約会社との契約を嫌うらしくて(おそらく経費問題)情報は拾えるけれど電話予約が必須とか、膝腰の不調含めてしばらく精神的にテンションが上がらぬ日々が続きました。先輩の入院は如何ともしがたく快復を祈るしかないけれど、概ねその辺りの小さな悩みは解消して、市立体育館のトレーニングに気持ちの良い汗を流しました。血圧は残念高いまま、今朝の体重は67.0kg+300g逆戻りコース。昼に冷蔵庫残り物の惣菜を思いっきり消化して喰い過ぎた自覚有。
前日女子バレー対中国戦は1-3敗北、ビデオでしっかり応援いたしました。相手も若手を入れて育成中、高さもパワーもあって、日本は明らかにコンビネーションはよろしくない。ミスも多い。日本も巴里五輪よりメンバーをかなり変えて若手も多く、まだ実力差があると感じました。石井さんの解説がマイルドな語り口にわかりやすくステキ。ネットの声に「ちょっと強い相手にはすぐ負ける」~そんな心ない書き込みがあったけれど、この先ワールドカップもあるし、若手の経験とチームの成長熟成に注目しましょう。和田や山田はけっこう活躍しておりました。
次の捷克戦は3-0勝利。これからビデオで内容確認しましょう。
とうとう亜米利加は伊蘭攻撃、トランプさん前政権では「戦争をしない人」と云ったイメージだったけれど、こんどはなにもかもむき出しみたい。石油は上がることでしょう。世界は不穏です。
東京都議選は都民ファースト第1党31議席へ。自民党過去最低21議席(進次郎米旋風吹かず)裏金問題で党の公認を得られなかった無所属候補もかなり落ちました。公明党も共倒れした選挙区もあり(大田区)▲4議席。国民民主党9議席、参政党3議席各々初獲得、立憲は19議席に伸ばして、共産党は14議席に減らしました。れいわも維新も議席ならず、再生は風吹かず事前予想通り議席なし。小池都政は安泰?これが参院選への流れになるのでしょうか。問題は投票率が半分に届かぬことと、祭り(選挙)のあとでしょう。国民民主党はこの間の逆風の影響をあまり受けなかったように見えて、但し、急激に伸びた関係か全国あちこち議員の不祥事は出ているようです。平愛理の弟は落ちたみたい。
 Barber 弦楽のためのアダージョ/Brahms 大学祝典序曲/Mahler 交響曲第1番イ長調/Dvora'k スラヴ舞曲ホ短調 作品72/2~クルト・マズア/オーケストラ・アカデミカ(カンポス・ド・ジョルドンの冬国際音楽祭2005年ライヴ)・・・Kurt Masur(1927-2015独逸)はこの時期既にニューヨーク・フィルを降りて、ロンドン・フィルやフランス国立管弦楽団のシェフ在任最終盤、80歳近いけれど矍鑠としてヴィヴィッドな演奏ぶりでした。オーケストラは若い人中心でしょうか。音質はまずまず。Festival de Inverno de Campos do Jordao とは何ぞや?ようわからん音源を入手したけれど、いろいろその評価をネットを探ると「CDは聴いてすぐ処分した」という凄い?ブログ情報が出現しました。若者の育成を目的にしているらしいから、オーケストラにも参加しているのでしょう。実態はわかりません。ちょっと線は細く軽いラフな響きだけれど、かなりしっかりとした、明るいアンサンブル、音質も上々のライヴ、各々盛大な拍手も入ります。
Barber 弦楽のためのアダージョ/Brahms 大学祝典序曲/Mahler 交響曲第1番イ長調/Dvora'k スラヴ舞曲ホ短調 作品72/2~クルト・マズア/オーケストラ・アカデミカ(カンポス・ド・ジョルドンの冬国際音楽祭2005年ライヴ)・・・Kurt Masur(1927-2015独逸)はこの時期既にニューヨーク・フィルを降りて、ロンドン・フィルやフランス国立管弦楽団のシェフ在任最終盤、80歳近いけれど矍鑠としてヴィヴィッドな演奏ぶりでした。オーケストラは若い人中心でしょうか。音質はまずまず。Festival de Inverno de Campos do Jordao とは何ぞや?ようわからん音源を入手したけれど、いろいろその評価をネットを探ると「CDは聴いてすぐ処分した」という凄い?ブログ情報が出現しました。若者の育成を目的にしているらしいから、オーケストラにも参加しているのでしょう。実態はわかりません。ちょっと線は細く軽いラフな響きだけれど、かなりしっかりとした、明るいアンサンブル、音質も上々のライヴ、各々盛大な拍手も入ります。
「弦楽のためのアダージョ」はしっとりとしたアンサンブルに、追悼の念しみじみ漂う哀しい作品。(7:21)
「大学祝典序曲」は速めのテンポにアツいノリ、たいへんな盛り上がりでした。あまりに馴染みの親しい旋律作品はいつになく新鮮、拍手も熱狂的。(9:58/拍手有)
青春の憧憬に充ちて爽やかなMahlerの交響曲も好演。
第1楽章「Langsam, schleppend」やや速めのテンポに、テンポの揺れもほとんどなく、ストレートにオーケストラの響きも素直に爽やかな演奏。提示部繰り返し有。(14:49)
第2楽章「Kraftig bewegt, doch nicht zu schnell」元気のよろしいスケルツォはけっこうノリノリ。若者が多いのかな?(7:35)
第3楽章「Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen」神妙な葬送行進曲もちょっと浮き立つような風情。途中の哀愁の風情も濃厚に重くならず、やや素っ気ないほど。「彼女の青い眼が」の夢見るような旋律はデリケートに、やがて冒頭の静謐に収束しました。(9:56)
第4楽章「Sturmisch bewegt」シンバルの一撃から始まる熱気に充ちた爆発も、オーケストラは充分な厚みを感じさせ、あくまで爽やかに威圧感はないもの。若々しいフィナーレを迎えました。(18:33/拍手は約30秒)
スラヴ舞曲「Allegretto grazioso」はアンコールでしょう。直截な表現に静かに弦が歌い、木管が高らかに歌う哀愁の旋律最高。(5:39/40秒ほどの拍手)
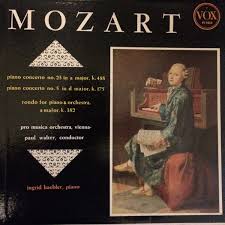 Mozart ピアノ協奏曲第5番ニ長調K.175/ロンド ニ長調K.382~イングリット・ヘブラー(p)/パウル・ワルター/ウィーン・プロムジカ管弦楽団(1956年Release)・・・「Mozart Piano Concertos Vintage Recordings」とやらの全曲音源より。Ingrid Haebler(1929-2023墺太利)は当時未だ30歳に届かぬ若手時代、彼女のMozartは旧録音含め概ね集めて聴いたと思っていたけれど、この存在は初めて知りました。Paul Walter(1906-2000墺太利)はオペラ畑に活躍した人だそう。VOXのモノラル録音は予想外に明晰な音質、怪しげな伴奏も息が合って立派でした。
Mozart ピアノ協奏曲第5番ニ長調K.175/ロンド ニ長調K.382~イングリット・ヘブラー(p)/パウル・ワルター/ウィーン・プロムジカ管弦楽団(1956年Release)・・・「Mozart Piano Concertos Vintage Recordings」とやらの全曲音源より。Ingrid Haebler(1929-2023墺太利)は当時未だ30歳に届かぬ若手時代、彼女のMozartは旧録音含め概ね集めて聴いたと思っていたけれど、この存在は初めて知りました。Paul Walter(1906-2000墺太利)はオペラ畑に活躍した人だそう。VOXのモノラル録音は予想外に明晰な音質、怪しげな伴奏も息が合って立派でした。
ニ長調協奏曲K.175は二管編成に+ティンパニという堂々たる立派な古典的な伴奏。1773年17歳にして既に完成されたスタイルの名曲でした。
第1楽章「Allegro」快活に駆け出すとピアノは一点の曇もない。管弦楽とデリケートに有機的な対話を続けてノリノリ、笑顔に充ちて輝かしい。(7:52)
第2楽章「Andante Ma Un Poco Adagio」安らぎの緩徐楽章。静かな序奏は1:22も続いて、ようやくピアノがそっと参入いたしました。可憐なソロはしっかり芯を感じさせる落ち着いたタッチ、静かに高まる深い幸福感。後半のそっと呟くような抑制も極上に名残惜しいところ。(8:13)
第3楽章「Allegro」晴れやかなフィナーレの始まり。力みを感じさせぬ流れは徐々に熱を加えて、気分は高揚を続けます。ラスト、カデンツァを経てちょっぴり素っ気なく終わりました。(4:44)
Rondo D K.382は上記作品終楽章の別稿なんだそう。シンプルに屈託のないリズムと旋律、喜びに溢れた変奏曲は時にしっとりと優雅に変幻自在な表情付け。かつてこの作品はFM番組のテーマにもなっておりましたっけ。(10:06)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日土曜も猛暑継続中。朝一番の「音楽日誌」に女子バレー対伊太利亜の詳細が載ったのは、じつはさっさと寝てしまって深夜途中覚醒、録画を再生してじっくり眺めたため。したがって睡眠不足気味、幸い体調も左膝は引き続きまずまず、我流メニューは手抜きなく、短いYouTubeエアロビクスも実施できました。洗濯物はしっかり外干し、気温も高いので早々に乾きます。食材は揃っているので、あるもので食事を準備して、ちょっぴりウォーキング歩数稼ぎにご近所コンビニにネット銀行処理に出掛けました。本日東京都議選投票日、さてどうなることでしょう。事前のマスコミ予想の趨勢は当たるでしょうか。今朝の体重は66.7kg+100g、節制したつもりでもなかなか減りません。
昨夜は女子バレー対中国戦1-3で連敗残念。内容はこれからビデオ録画でしっかり拝見させていただきましょう。世界の強豪にはカンタンに勝たせてもらえません。
「ピアノ教室・・・エステのようにレッスンだけ受ければ上達すると思ってる人多すぎ」~なるほど、筋トレとかエアロビクスもたしかに、通った時だけの鍛錬ですもんね。その記事に嘆いている方多数。 自分もそこからの引用に元記事を拝見いたしました。ピアノが好きでほんまに上達したいと思っている方は自宅でも練習するでしょう。ダンスとか、歌とか、なんの習い事でもそう、学校の勉強でもそうだけど、予習復習は必須と思います。誤った「カネ払ってるんだから」みたいな安易な考えが蔓延しているのかな。効率よく上手く教えてもらって、短時間で魔法のように上達~なんてできるはずないじゃん、ほんの一部の天才除いて。効率的なお仕事、練習、作業は大切だけど、行き過ぎた「タイパ」「コスパ」発想(言葉も大嫌い)の行き着く先の風潮かと思います。嘆かわしい。
例の如くほぼ興味はないけれど、有名芸能人がなにか?わからんけど問題を起こして無期限活動停止とか。売れている人も一瞬で消える虚業の世界、そして「水に落ちた犬を叩け」状態のマスコミ報道やネット、やがて忘れられるのは、これまでの例をみてもおそらく間違いありません。本人はアウトだけど、家族が可愛そうだな。先の問題があったので日本テレビは迅速に慎重に動いたみたいですね。
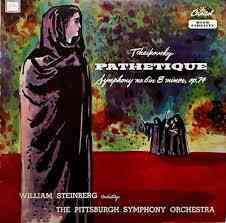 Tchaikovsky 交響曲第6番ロ短調「悲愴」(1953年)/イタリア奇想曲(1959年)/スラヴ行進曲(1958年)~ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグ交響楽団・・・William Steinberg(1899-1978独逸→亜米利加)ピッツバーグ交響楽団の音楽監督在任は1952-1976年、米Capital、米Command、RCA、DGに膨大なる録音があるけれど、日本での人気はいまひとつ状態でした。誰も知っている名曲「悲愴」はCD時代投げ売り輸入盤を聴いたような?記憶も曖昧、1953年のモノラルだったことを初めて知ったけれど、米Capitalの録音はかなり鮮明、まずまず不足を感じさせぬ水準でした。期待通りの重量級、そして明るいサウンド、オーケストラの技量は優秀でした。
Tchaikovsky 交響曲第6番ロ短調「悲愴」(1953年)/イタリア奇想曲(1959年)/スラヴ行進曲(1958年)~ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグ交響楽団・・・William Steinberg(1899-1978独逸→亜米利加)ピッツバーグ交響楽団の音楽監督在任は1952-1976年、米Capital、米Command、RCA、DGに膨大なる録音があるけれど、日本での人気はいまひとつ状態でした。誰も知っている名曲「悲愴」はCD時代投げ売り輸入盤を聴いたような?記憶も曖昧、1953年のモノラルだったことを初めて知ったけれど、米Capitalの録音はかなり鮮明、まずまず不足を感じさせぬ水準でした。期待通りの重量級、そして明るいサウンド、オーケストラの技量は優秀でした。
第1楽章「Adagio - Allegro non troppo」重苦しい暗鬱な始まりから、暗く楚々とした第1主題、安らぎと憧憬によく歌う第2主題が対比されて、語り口やサウンドは意外とさっぱりとして前向きな浪漫を感じさせました。一転展開部は激烈!な疾走はパワフル、オーケストラはクリアに粘着質を感じさせぬパワーと勢い有。やがてすべてを悟ったような諦めに似た落ち着きに終了。テンポは中庸、動きに不自然さもありません。(18:24)
第2楽章「Allegro con gracia」5/4拍子に不安を孕んだ甘いワルツは優雅そのもの。ピッツバーグ交響楽団の弦には甘さもあって一流ですよ。中間部の暗転対比表現もあまり”泣き”を強調しない、さっぱり味の表現でした。(814)
第3楽章「Allegro molto vivace」溌溂としたスケルツォ。あまり力みなく熱を高めていく熟達の表現。アンサンブルの縦線はお見事でしょう。(9:44)
第4楽章「Finale: Adagio lamentoso」やや速めのテンポ、前のめりの流れは絶望感に過ぎない流麗なフィナーレ。モノラルでも銅鑼は絶望的に響きました。(9:22)
以下はステレオ録音だけど、前曲との音質的な違和感はありません。
「イタリア奇想曲」は途中テンポを落として、たっぷり雄弁優雅に歌う演奏。(17:33)「スラヴ行進曲」は明るく金管を朗々と歌わせて、パワーと勢いたっぷり。(11:02)
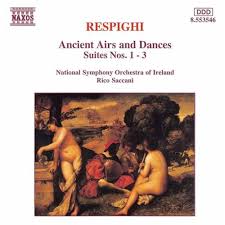 Respighi リュートのための古風な舞曲とアリア~リコ・サッカーニ/アイルランド・ナショナル交響楽団(1995年)・・・Ricco Saccani(1952-亜米利加)はカラヤン・コンクール優勝、洪牙利に活躍した指揮者とのこと。ブダペスト・フィルとのライヴがまとめてCD化されておりました。これは知名度乗り越え、意外としっとりとしたアンサンブルに作品を堪能できました。この作品は16-17世紀のリュート音楽を採譜し、管弦楽に編曲したものだそう。静かに落ち着いたアルカイックな風情がステキな作品ばかり。チェンバロ(通奏低音)が入った古(いにしえ)のバロック風はお気に入りでした。楽器編成は各々異なるそう。
Respighi リュートのための古風な舞曲とアリア~リコ・サッカーニ/アイルランド・ナショナル交響楽団(1995年)・・・Ricco Saccani(1952-亜米利加)はカラヤン・コンクール優勝、洪牙利に活躍した指揮者とのこと。ブダペスト・フィルとのライヴがまとめてCD化されておりました。これは知名度乗り越え、意外としっとりとしたアンサンブルに作品を堪能できました。この作品は16-17世紀のリュート音楽を採譜し、管弦楽に編曲したものだそう。静かに落ち着いたアルカイックな風情がステキな作品ばかり。チェンバロ(通奏低音)が入った古(いにしえ)のバロック風はお気に入りでした。楽器編成は各々異なるそう。
第1組曲は室内楽~小編成管弦楽/小舞踏曲(Balletto)(3:00)/ガリアルダ(Gagliarda)(3:35)/ヴィラネッラ(Villanella)(5:55)/酔った歩みと仮面舞踏会(Passo mezzo e Mascherada)(4:05)
第2組曲は管弦楽編成/優雅なラウラ(Laura soave)(4:06)/田園舞曲(Danza rustica)(3:57)/パリの鐘(Campanae parisienses)(5:47)/ベルガマスカ(Bergamasca)(5:38)
第3組曲は弦楽合奏。ここがいちばん有名でしょう/イタリアーナ(Italiana)(2:47)/宮廷のアリア(Arie di corte)(7:31)/シチリアーナ(Siciliana)(3:59)パッサカリア(Passacaglia)(3:32)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
未だエアコンも使用していないし、本格的な夏はこれからだけど、寝苦しく早朝覚醒しております。1ヶ月後に迫った萩旅行の件、地元山口には親しい先輩二人、一人は元気だけど、もうひとりはニ年先輩、昨年11月の京都OB会に出席され、心臓の病に入院していたと伺っておりました。旅行の詳細調整に彼より適切な助言有。しかし、当初新山口到着時に昼食御一緒する予定が、体調を崩して入院中との報告「ジェームス三木」みたいになるかも、とは冗談にもなりません。快復を心より願っても珍しい心臓の奇病とのこと、安易な励ましもできず、心は落ち込んでります。
自分は体重増から肝臓の数値やや異常値に至り、血圧が高いなんてただの不摂生じゃないの。努力でどうにでもなりますよ。当たり前だけど心身共の健康はすべての前提条件、体調を整えて元気に遊ぶ! おカネも大切だけど、その前に自分の身体の養生最優先。
左膝はかなり軽快、通常のストレッチは可能になって、YouTubeエアロビクスは例の東南亜細亜系のお姉さんご指導による、シンプルに動き続けるもの実施して炎天下市立体育館を目指しました。いつもどおりのMyメニューこなして、なんせ暑いからすごい汗と心拍数上がって、鍛錬後の血圧測定はとっても高い!けど、これは計測時間のせいと信じたい。今朝の体重は66.6kgほぼ変わらず。昼を喰い過ぎた自覚有。
LINEはもちろんスマホで使うけれど、旅行の詳細スケジュールとか注意事項をフリック入力するにはあまりに苦手、QRコードを読み込ませてコンピューターよりキーボード入力必須なこともあります。現在、コンピューターはよほどの不具合がない限り電源入れっぱ。結果、LINEはコンピューターで常に使用できることに気づきました。他の作業をしているときに連絡があるのは、ちょっぴり鬱陶しい感じ。来月の萩旅行の夜の店は電話して(ネット予約不可)ようやく予約が取れて,ひとつ肩の荷が降りました。あとは自分の切符をどうするか決めるだけ。
夜は女子バレー対強豪伊太利亜戦生中継。2-3惜敗。第1セット、最終第5セット競り合ってぎりぎり負けたのは未だ自力が足りない結果だけど、伊太利亜の高さ上手さに力負けしていないのには驚きました。かつてはエース・エゴヌにやられっぱなしだったのに、けっこう抑えておりました。石川、関、福留の伊太利亜リーグ三人衆が相手に慣れているのか、174cmの和田のスパイクも通用します。負けたけど立派、興奮しました。次は中国です。
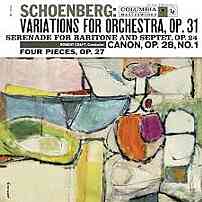 Scho"nberg 管弦楽のための変奏曲 作品31(ロバート・クラフト/管弦楽団/1957年)/4つの混声合唱曲 作品27(マルニ・ニクソン(s)/キャスリーン・ゲイヤー(a)/リチャード・ロビンソン(t)/サム・ヴァン・デューセン(b)/マックス・グラールニック(マンドリン/ヒューゴ・ライモンディ(c)/ドロシー・ウェイド(v)/エメット・サージェント(vc)/ロバート・クラフト)/3つの風刺 作品28より 第1曲「分かれ道で」(マルニ・ニクソン(s)/キャスリーン・ゲイヤー(a)/リチャード・ロビンソン(t)/サム・ヴァン・デューセン(b)/ロバート・クラフト/1957年)/バリトンと七重奏のためのセレナード 作品24(サム・ヴァン・デューセン(b)/ウィリアム・ウリアーテ(bcl)/マックス・グラールニック(マンドリン)/シオドア・ノーマン(g)/ドロシー・ウェイド(v)/セシル・フィジェレスキ(va)/エメット・サージェント(vc)ロバート・クラフト/1957年)・・・Robert Craft(1923-2015亜米利加)はストラヴィンスキーの助手であり、同時代音楽の養護普及に尽力された立派な人。1950年代にこのScho"nbergやWebern辺りまとめて、絶対に売れそうもない録音発売したCBSも立派、後年ディジタル時代には再録音をしておりました。これはモノラルけれど、かなり明快に解像度の高い音質でした。
Scho"nberg 管弦楽のための変奏曲 作品31(ロバート・クラフト/管弦楽団/1957年)/4つの混声合唱曲 作品27(マルニ・ニクソン(s)/キャスリーン・ゲイヤー(a)/リチャード・ロビンソン(t)/サム・ヴァン・デューセン(b)/マックス・グラールニック(マンドリン/ヒューゴ・ライモンディ(c)/ドロシー・ウェイド(v)/エメット・サージェント(vc)/ロバート・クラフト)/3つの風刺 作品28より 第1曲「分かれ道で」(マルニ・ニクソン(s)/キャスリーン・ゲイヤー(a)/リチャード・ロビンソン(t)/サム・ヴァン・デューセン(b)/ロバート・クラフト/1957年)/バリトンと七重奏のためのセレナード 作品24(サム・ヴァン・デューセン(b)/ウィリアム・ウリアーテ(bcl)/マックス・グラールニック(マンドリン)/シオドア・ノーマン(g)/ドロシー・ウェイド(v)/セシル・フィジェレスキ(va)/エメット・サージェント(vc)ロバート・クラフト/1957年)・・・Robert Craft(1923-2015亜米利加)はストラヴィンスキーの助手であり、同時代音楽の養護普及に尽力された立派な人。1950年代にこのScho"nbergやWebern辺りまとめて、絶対に売れそうもない録音発売したCBSも立派、後年ディジタル時代には再録音をしておりました。これはモノラルけれど、かなり明快に解像度の高い音質でした。
「管弦楽のための変奏曲」は1928年フルトヴェングラー/ベルリン・フィルにより初演、Wikiには一大スキャンダルを巻き起こした、なんて書いてあるけれど、当時の演奏者には新し過ぎて作品への理解や解釈は追いつかず、まともな演奏は不可能だったらしい。四管編成に9種の打楽器、フレクサトーン、ハープ、チェレスタ、マンドリンという大編成。オーケストラ名は表示されないけれど、ハリウッドでの録音、当時盛んだった映画音楽を生業(なりわい)とする音楽家たちを集めたのでしょう。もちろん市井のド・シロウトには楽曲の詳細分析やら理解は不可能なドデカフォニー作品。これが大編成なのに大音響がほとんどない、各パートが順繰り浮かび上がって意外と静謐、そして知的な作品。音楽はなんでもそうだけど、繰り返し聴いて馴染むしかない。Shostakovichをちゃんと聴けるようになるのに2-30年は掛かりましたよ。この作品は怪しい無機的な響きが美しく、聴き通すのに意外と苦痛はありません。
導入部(1:16)主題(0:52)第1変奏(1:00)第2変奏(1:32)第3変奏(0:46)第4変奏(1:09)第5変奏(1:48)第6変奏(1:16)第7変奏(2:07)第8変奏(0:35)第9変奏(1:00)終曲(三部に分かれているそう/5:48)
「4つの混声合唱曲」はドデカフォニーによる最初の合唱作品とのこと(1925年)。「避けられないこと」(1:08)「 「べき」でなく「ねばならぬ」」(0:50)「月と人間」(2:36)「恋する者の願い」(3:41)。「分かれ道で」(0:56)も含め一連のScho"nbergの声楽作品はどれも心情の波みたいなものが感じられて、言語の壁を乗り越えて、その緊張感が快いもの。管弦楽作品より平易と感じます。
「セレナード」はかなり以前よりマールボロ音楽祭などの録音で聴いていた作品~だけど、どこがセレナードやねん!的面倒臭い晦渋な作品。ギターとマンドリン、そして歌が入るからか。なかなか馴染んで拝聴するには難物な作品でした。初演は1924年。
「行進曲(Marsch)」(3:50)「メヌエット(Menuett)」(6:18)「変奏曲(Variationen)」(3:34)「ペトラルカのソネット(Sonett von Petrarca)」ここにバリトンが入る(2:40)「舞踏の情景(Tanzscene)」(6:42)「無言歌(Lied (ohne Worte)」(1:46)「フィナーレ(Finale)」(4:28)
100年経っても新しい!こどもの頃からのユルい音楽愛好家(=ワシ)に安易な緩みを許さぬ緊張感を堪能いたしました。
 Mozart 3つのピアノ協奏曲 K.107(ニ長調/ト長調/変ホ長調/J.C.Bachからの編曲)~ジャン=ベルナール・ポミエ(p)/ルイ・オーリアコンブ/トゥールーズ室内管弦楽団(1965-66年)~懐かしいJean-Bernard Pommier(1944-仏蘭西)もLouis Auriacombe(1917ー1982仏蘭西)の演奏は3年ほど前に拝聴した記録があって、その音源は今何処?.mp3音源は整理してしまったのか。この度ネットより「Mozart Piano Concertos Vintage Recordings」とやら全曲音源入手したら、その冒頭にこの音源がありました。伴奏の編成はヴァイオリン2/バス1というシンプルなもの、ここではけっこう立派な厚みに低音も効いております。J.C.Bachは若きMozartに影響を与えた人、編曲ものなので全集にも含まれず、チェンバロで演奏されることも多い。
Mozart 3つのピアノ協奏曲 K.107(ニ長調/ト長調/変ホ長調/J.C.Bachからの編曲)~ジャン=ベルナール・ポミエ(p)/ルイ・オーリアコンブ/トゥールーズ室内管弦楽団(1965-66年)~懐かしいJean-Bernard Pommier(1944-仏蘭西)もLouis Auriacombe(1917ー1982仏蘭西)の演奏は3年ほど前に拝聴した記録があって、その音源は今何処?.mp3音源は整理してしまったのか。この度ネットより「Mozart Piano Concertos Vintage Recordings」とやら全曲音源入手したら、その冒頭にこの音源がありました。伴奏の編成はヴァイオリン2/バス1というシンプルなもの、ここではけっこう立派な厚みに低音も効いております。J.C.Bachは若きMozartに影響を与えた人、編曲ものなので全集にも含まれず、チェンバロで演奏されることも多い。
15-17歳頃の作品、オリジナルの第5番ニ長調K.175以前の協奏曲は、モダーン楽器を駆使してしっとり優雅に落ち着いたタッチ、初期作品には似つかわしくない浪漫風表現かも知れないけれど、いつもの才気煥発なMozartをたっぷり、静かに堪能できました。おそらくLP復刻音源?冒頭オーケストラの濁りがちょっぴり気になったけれど(わずかな音飛びも有)まずまずの音質を維持しておりました。
第1番ニ長調(Allegro-AndanteーTempo di menuetto/15:20)屈託のない淡々とした始まりから、ポミエのピアノは瑞々しく慌てぬ始まり。緩徐楽章もシンプルに優しい懐かしさ絶品!ラストも初期作品とは思えぬデリケートに優雅な風情に落ち着いた歌がありました。哀しい暗転はいつものMozartを連想されました。
第2番ト長調(Allegro-Theme and Variations: Allegretto/8:14)ゆったり笑顔に弾むようなシンプルな始まり。ポミエのソロには適度な力感があって、カデンツァは華やかでした。そしてしっとり、たっぷり歌う主題と懐かしい変奏が続く名曲。
第3番 変ホ長調(Allegro-Allegretto/10:34)快活優雅な始まりから、やがてちょっぴり暗転して落ち着いた風情に収束いたしました。
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
この気温と湿度はもう真夏並みだけど、未だ夏バテには早過ぎ。せっかくの好天に洗濯物は良く乾いて、布団も気持ちよろしく干せました。体調は良好です。ここしばらく不調だった左膝腰だけど、昨日朝はかなり軽快、腰は大丈夫、膝は未だ完全に不自由なく曲げられないけれど、ストレッチや歩行には問題ありません。例のシンプルな動きを続ける東南亜細亜系女性によるエアロビクス実施。右側のお姉さんが動きに付いけないのにも親密を感じつつ、一昨日タイム・サービス690円カット長蛇の列に断念した激安美容室(980円)に出掛けて5番札。ヘアカラーのお姉さんもいらっしゃるので(待ち時間があって、その合間)すぐ順番は回ってきて、涼しげに短くカットしていただきました。更にスーパーに寄って野菜中心に仕入れて、じっくりコメの棚を眺めて「ななつぼし5kg」4,280円(税抜)も買ってきました。ここしばらく残念な味だったカルローズを喰っていたので贅沢しました。今朝の体重は66.65kg+400g ガッカリ。
女房殿は婆さん宅に泊まりへ。この暑さにエアコンの使い方がわからないとのこと。今夜は女子バレー伊太利亜戦、なんとか喰い下がって善戦して欲しい。
先日聴いた珍しい浪漫派ピアノ協奏曲は昨年2024年9月に聴いていたことを発見。このBOXに含まれる作品はけっこうちゃんと聴いている記録がありました。昔馴染みの鬱蒼とした名曲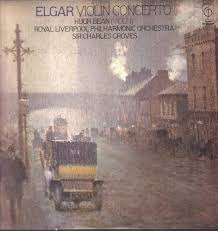 Elgar ヴァイオリン協奏曲ロ短調(ヒュー・ビーン(v)/1972年)を聴いて、EMI Elgar Collecter's BOXとCharles Groves音源まとめたものにダブって収録されていたことに驚いていたら、やはり以前に幾度も聴いていたことを発見、短いコメントも画像も「音楽日誌」に掲載されておりました。手当たり次第に音源ファイルを集めて、なんとか聴かなくっちゃ~そんな焦りもあって、じつは聴いていたけれど記憶が落ちているだけ~そんな発見を幾度繰り返しております。それが毎日更新しているホームページの取り柄なのでしょう。
Elgar ヴァイオリン協奏曲ロ短調(ヒュー・ビーン(v)/1972年)を聴いて、EMI Elgar Collecter's BOXとCharles Groves音源まとめたものにダブって収録されていたことに驚いていたら、やはり以前に幾度も聴いていたことを発見、短いコメントも画像も「音楽日誌」に掲載されておりました。手当たり次第に音源ファイルを集めて、なんとか聴かなくっちゃ~そんな焦りもあって、じつは聴いていたけれど記憶が落ちているだけ~そんな発見を幾度繰り返しております。それが毎日更新しているホームページの取り柄なのでしょう。
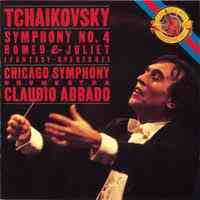 Tchaikovsky 交響曲第4番ヘ短調/幻想序曲「ロメオとジュリエット」~クラウディオ・アバド/シカゴ交響楽団(1988年)・・・Claudio Abbado(1933-2014伊太利亜)アバドが亡くなってもう10年経ったのか・・・ベルリン・フィル就任以降はあまりにメジャーな存在に至ったので拝聴機会は減っておりました。このシカゴ交響楽団との全集録音もなんとなく避けていたもの~これが強靭なオーケストラのパワーとキレは重量感、スパッとして粘着質にならぬ爽快な表現、シカゴ・オーケストラ・ホールのデッドな響きが似合って、とくに金管が印象的。馴染みのデーハーな露西亜名曲は都会的に響き渡りました。
Tchaikovsky 交響曲第4番ヘ短調/幻想序曲「ロメオとジュリエット」~クラウディオ・アバド/シカゴ交響楽団(1988年)・・・Claudio Abbado(1933-2014伊太利亜)アバドが亡くなってもう10年経ったのか・・・ベルリン・フィル就任以降はあまりにメジャーな存在に至ったので拝聴機会は減っておりました。このシカゴ交響楽団との全集録音もなんとなく避けていたもの~これが強靭なオーケストラのパワーとキレは重量感、スパッとして粘着質にならぬ爽快な表現、シカゴ・オーケストラ・ホールのデッドな響きが似合って、とくに金管が印象的。馴染みのデーハーな露西亜名曲は都会的に響き渡りました。
第1楽章「Andante sostenuto - Moderato con anima」冒頭ホルンとファゴットによる「運命のファンファーレ」は衝撃の充実した響き、この旋律が全編に登場して作品の悲劇性を高めます。テンポは中庸、うねうねとした暗い響きに非ず、都会的センスに飾りのないストレートな勢いが、カッコよく耳に快い説得力充分。クライマックスは符点にリズムにテンション上がりまくり。朗々たるホルンのソロには痺れ、やがて再登場する「運命のファンファーレ」金管のド迫力な存在感に打ちのめされ~シカゴの金管最高。(19:41)
第2楽章「Andantino in modo di canzona」切なく哀しいオーボエ・ソロに始まる緩徐楽章。それが弦に引き継がれてパワーと悲劇性を高めて雄弁、その分厚い輝かしい響きに圧倒されました。(9:57)
第3楽章「Scherzo: Pizzicato ostinato - Allegro」緊迫感いっぱいのピチカート連続技から高まる熱気、中間部はピッコロと軽快な金管の行進曲風。シカゴ交響楽団のアンサンブルに脱帽です。(5:34)
第4楽章「Finale: Allegro con fuoco」いきなりの大爆発から始まるフィナーレ、それはスピーカーより風圧を感じるほどの重量級の金管、弦、そして打楽器、それはほとんどスポーツのようなキレ味と快感。こんなの露西亜じゃないと云ったご批判覚悟、洗練された流麗な旋律に心奪われました。そして満を持して「運命のファンファーレ」登場!ラストに向けて、これでもかっ!金管の圧を高めて力で乗り切る!そんな表現にも納得できました。(9:27)
「ロメオとジュリエット」も神妙に抑制した始まりから、やがて重量級パワフルな推進力がたっぷり高揚する演奏でした。弦の力感、クールなフルート、チューバの低音、そしてホルン、トランペットがとても美しい。(20:32)
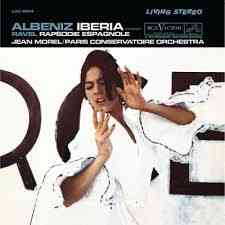 Albeniz イベリア/Ravel スペイン狂詩曲~ジャン・モレル/パリ音楽院管弦楽団(1959年)・・・Albenizの最高傑作とされる4巻からなるピアノ作品からの管弦楽編曲(Arbos*/Surinach編)。
Jean Morel(1903-1975亜米利加?)は仏蘭西生まれ、亜米利加で教鞭を執りつつオペラハウスや仏蘭西のオーケストラに客演していたそう。ジャケットのデザインはとっても雰囲気がありますね。音質もかなり良好なステレオ。
Albeniz イベリア/Ravel スペイン狂詩曲~ジャン・モレル/パリ音楽院管弦楽団(1959年)・・・Albenizの最高傑作とされる4巻からなるピアノ作品からの管弦楽編曲(Arbos*/Surinach編)。
Jean Morel(1903-1975亜米利加?)は仏蘭西生まれ、亜米利加で教鞭を執りつつオペラハウスや仏蘭西のオーケストラに客演していたそう。ジャケットのデザインはとっても雰囲気がありますね。音質もかなり良好なステレオ。
「イベリア」は西班牙の哀愁+情熱が漲るような魅惑の旋律とリズム連続・・・なんだけど、これはちょっと悩ましい演奏やなぁ。泥臭いローカルな風情たっぷりな旋律リズム連続に、アンサンブルの縦線かっちり揃ったクールを表現は求めないけれど、パリ音楽院のオーケストラはかなりラフと云うか、いまいちノリもよろしくなくて説得力が足りない散漫な感じ。妙にローカルな風情はありそうな・・・しばらく作品そのものを聴いていないので、ちょっと演奏云々の判断がつきません。
Evocacion*(5:06)El Puerto*(4:30)El Corpus En Sevilla*(6:06)Rondena(8:48)Triana*(4:56)Almeria(7:46)Lavapies(6:55)El Polo(6:06)El Albaicin*(7:28)Malaga(5:15)Eritana(5:04)Jerez(11:03)
スペイン狂詩曲は緻密な作品。ひっそりと気怠い「夜への前奏曲」(Prelude a la nuit)ファンダンゴのリズムもゆったりと妖しい「マラゲーニャ(Malaguena)」デリケートに息を潜めるような「ハバネラ(Habanera)」フルートの躍動から始まる「祭り(Feria)」華やかに賑やかな高揚が待っておりました。こちらは雰囲気たっぷりな演奏に仕上がっておりました。(11:09)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日【♪ KechiKechi Classics ♪】の表示確認のため「音楽日誌」にアクセスしたら、一度だけ「このサイトは安全が確保されておりません」と表示されてしまいました。なにか頭の良いワルいやつらに踏み台にでもされているのでしょうか。なんの悪意もないし、商売にも一切関係ないのですが。
暑いですね、天気予報は変更となって30度超えがずっと続いて梅雨の中休み?それともさっさと終わったのか。6月にして既に「殺人猛暑」というのも大げさに非ず、熱中症に運ばれたり生命を失う方も出ているようです。前夜も寝苦しくて眠り浅く、しかも早朝覚醒、体調は悪くありません。もともと夏は嫌いじゃないのは、北海道出身の自分は冬の厳しさを知っているから、それでもここ10年ほどの猛暑と華麗なる加齢に夏バテ気味・・・左膝は完全に曲げることが難しい痛みはあるけれど、腫れとか熱はありません。そこだけ避けてストレッチ実施、カンタンなYouTube体操を済ませて体育館へ。エアコンやシャワー完備は快適ですよ。前居住地である長久手市の体育館だったら夏はホット・ヨガ状態、冬は耐寒訓練風、難行苦行だったことを思い出します。Myメニュー消化後血圧は最高135、まずまず安定してきました。帰宅直後計量瞬間参考記録はついに65.7kg、これはかなり久々の65kg台でした。今朝は66.25kg前日と変わらず、昼を喰いすぎました。残念。
サプリメントのCMは盛りだくさん。けっこう高いのに利用者は多いと類推できます。偶然見かけたブログにもその様子が出ておりました(この方の判断はクール)。亡き母もにんにく黒酢だっけ? 服用してましたっけ。我が家も朝のグラノーラ(オートミール増量)に粉末青汁入れて(一番安いもの。いちど止めたけれど女房殿希望で復活)あれは安心感なのかなぁ。きな粉と純ココアも少々加えて、スキムミルクでいただいております。庶民が続けられる安いもの、それなりの裏付けがあるもの狙い。できるだけ日常の食品が望ましい。
身体に害にならなければ外野から云々すべきものでもないのでしょう。気持ちも大切ですから。男性向けの南米の秘薬ベースの精力剤?疲れに効く、膝腰用のサプリメント、肌が美しくなる粉末、骨が丈夫になりそうなもの、眼の衰えに効果、ようわからんけど元気が出そうなすっぽんなんとか、そういえば頭髪方面の前線後退に抗うのもありました 。オーソドックス?そうな総合ビタミン剤、そしてよく眠れる、睡眠補助的なもの・・・財力に任せて試しに全部服用したらそれだけでハラ一杯、それでほんまに健康になれるのでしょうか。気休めじゃないのかなぁ、鍛錬の代わりにはならんと思うけど。CMはご高齢に至っても元気な方、美しい方を探して出演していただいているのでしょう。
亡き親父のネタに、老人倶楽部に「極楽の塩」~なんにでも効く!料理にもどんどん使って、風呂にも入れて欲しい(これはなんとなく良さげ)ちょっとお高い、怪しい塩の売り込み有。あまりの流暢なセールスの弁舌に負けそうになりつつ、撃退したと自慢しておりましたっけ。
やがて効能あらたかな「極楽の塩」を買ってしまった知り合いの爺さんが亡くなって、葬式会場は「極楽寺」であった・・・というオチ。お粗末。
夜は女子バレー香港ラウンド、対泰国戦を堪能。カンタンに勝つんじゃないかとの安易な期待を打ち砕くように、よく拾う粘り強いコンビーネーションプレイは、どっちが日本?2セット先取されるまさかの展開に苦戦しました。いままでの高さとパワーのチームとは違う個性に困惑したのでしょうか。辛くも3-2逆転勝ちしたけれど、冷や汗ものでした。和田佐藤は引き続き大活躍。伊太利亜とはもっと苦戦することでしょう。そのあとには中国も控えております。
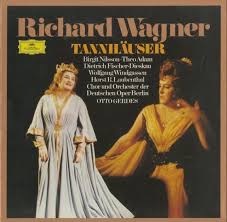 Wagner 歌劇「タンホイザー」(ドレスデン版)~オットー・ゲルデス/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/合唱団/ヴォルフガング・ヴィントガッセン(t)/ビルギット・ニルソン(s)/ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(br)/テオ・アダム (b)他(1969年)・・・Otto Gerdes(1920-1989独逸)はオペラハウスの経験もあるけれど、プロデューサーとして有名だった人。錚々たるスター歌手揃えて、きっと指揮者がドタキャンして、もったいなからプロデューサー自ら指揮して録音したと類推されております。例のカッコよい序曲(12:19)と第1幕のみ拝聴。筋書きはこちら参照お願い
Wagner 歌劇「タンホイザー」(ドレスデン版)~オットー・ゲルデス/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/合唱団/ヴォルフガング・ヴィントガッセン(t)/ビルギット・ニルソン(s)/ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(br)/テオ・アダム (b)他(1969年)・・・Otto Gerdes(1920-1989独逸)はオペラハウスの経験もあるけれど、プロデューサーとして有名だった人。錚々たるスター歌手揃えて、きっと指揮者がドタキャンして、もったいなからプロデューサー自ら指揮して録音したと類推されております。例のカッコよい序曲(12:19)と第1幕のみ拝聴。筋書きはこちら参照お願い
騎士であり吟遊詩人であるタンホイザー役はヴィントガッセン、彼とただれた関係を過ごしていたセクシーな女神ヴェーヌスはニルソン、帰りを待つ恋人エリーザベトもニルソン兼任なんだそう。
じつはこの演奏はかなり以前より幾度も聴いて、意外と昔馴染み、これが・・・オペラ・ド・シロウトである自分でも理解できるほどに、なんか元気もテンションも足りない。名歌手の歌はさておき、Wagnerでは肝心な管弦楽担当は演目に慣れているはずのベルリン・ドイツ・オペラ、これはやはりオットー・ゲルデスが表現意欲に溢れた専門の指揮者ではない、やっつけ仕事な伴奏だからでしょう。ま、それでも作品はそれなりに楽しめる・・・というか現状「タンホイザー」全曲はこれしか持っていないんです。ま、久々にけっこう愉しんで聴きました、そんなアリバイでした。
第1場 岸辺に近づきましょう(Naht euch dem Strande)」(4:45)「第2場 愛する人よ、今何を考えているの(Geliebter, sag, wo weilt dein Sinn)」(4:26)「あなたのための賛歌よ響け!(Dir tone Lob, Die Wunder sei'n gepriesen)」(5:33)「愛しい人よ、そこの洞窟を見に来てください(Geliebter, komm, Sieh dort die Grotte)」(3:02)「私の悲しみは常にあなただけに響き渡る(Stets soll nur dir mein Leid ertonen)」(1:34)「わが狂える者よ、行くがいい(Zieh hin, Wahnsinniger, zieh hin)」(3:19)「第3場 わがホルダの女神が山から降りて来て(Frau Holda kan aus dem Berg hervor)」(2:07)「わがイエス・キリストよ、なんじにわれはあこがれる(Zu dir wall ich, mein Jesus Christ)」(6:42)「熱心に祈るあの男はだれか?(Wer ist der dort in brunstigem Gebete)」(5:56)「君は大胆な歌い方でわれわれに挑戦し(Als du in kuhnem Sange uns bestrittest)」(6:39)
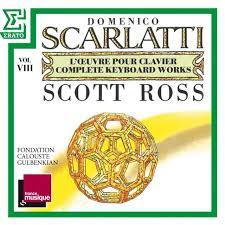 D.Scarlatti Sonata F K.94 Minuet/Sonata C K.95/Sonata D K.96 Allegrissimo/Sonata G Minor K.97 Allegro/Sonata E Minor K.98 Allegrissimo/Sonata C Minor K.99 Allegro/Sonata C K.100 Allegrissimo/Sonata A K.101 Allegro/Sonata G Minor K.102 Allegro/Sonata G K.103 Allegrissimo/Sonata G K.104 Allegro/Sonata G K.105 Allegro/Sonata F K.106 Allegro/Sonata F K.107 Allegro/Sonata G Minor K.108 Allegro/Sonata A Minor K.109 Adagio/Sonata A Minor K.110 Allegro/Sonata G Minor K.111 Allegro/Sonata B Flat K.112 Allegro~スコット・ロス(cem)(1984-85年)・・・Scott Ross(1951ー1989亜米利加)によるDomenico Scarlatti(1685-1757伊太利亜)の膨大なるソナタ集はCDなら34枚分。ピーター=ヤン・ベルダーだったら36枚分、たまに思い出して、どれを聴いてもウキウキ珠玉の旋律リズムが延々と続いて、チェンバロの済んだ音色がしみじみ心洗われるような瞬間が連続。ピアノのニュアンスたっぷりな表現と甲乙付けがたい魅力に陶然といたします。これは全集6枚目、恥ずかしくも情けないけれど仮に20枚目を聴いても、特別なコメントは増えません。時々、馴染の旋律が出てきて(ここでもハッとして)いやぁこんなところで顔見知りに出会いました~そんな感慨に至ります。
D.Scarlatti Sonata F K.94 Minuet/Sonata C K.95/Sonata D K.96 Allegrissimo/Sonata G Minor K.97 Allegro/Sonata E Minor K.98 Allegrissimo/Sonata C Minor K.99 Allegro/Sonata C K.100 Allegrissimo/Sonata A K.101 Allegro/Sonata G Minor K.102 Allegro/Sonata G K.103 Allegrissimo/Sonata G K.104 Allegro/Sonata G K.105 Allegro/Sonata F K.106 Allegro/Sonata F K.107 Allegro/Sonata G Minor K.108 Allegro/Sonata A Minor K.109 Adagio/Sonata A Minor K.110 Allegro/Sonata G Minor K.111 Allegro/Sonata B Flat K.112 Allegro~スコット・ロス(cem)(1984-85年)・・・Scott Ross(1951ー1989亜米利加)によるDomenico Scarlatti(1685-1757伊太利亜)の膨大なるソナタ集はCDなら34枚分。ピーター=ヤン・ベルダーだったら36枚分、たまに思い出して、どれを聴いてもウキウキ珠玉の旋律リズムが延々と続いて、チェンバロの済んだ音色がしみじみ心洗われるような瞬間が連続。ピアノのニュアンスたっぷりな表現と甲乙付けがたい魅力に陶然といたします。これは全集6枚目、恥ずかしくも情けないけれど仮に20枚目を聴いても、特別なコメントは増えません。時々、馴染の旋律が出てきて(ここでもハッとして)いやぁこんなところで顔見知りに出会いました~そんな感慨に至ります。
じつは少々大音量の歴史的録音(の音質)に聴き疲れて、落ち着いてクリアな響きを聴きたいなぁ、そんな気持ちににぴったりな静謐に闊達なチェンバロを堪能いたしました。お粗末。
(1:27-1:19-5:12-4:31-3:03-4:59-3:03-4:26-3:06-3:36-6:44-5:23-2:38-4:54-3:33-4:43-4:08-2:34-4:30)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
前夜も寝苦しくて、昨日朝一番ちょっと降ったけれど、予報通りの蒸し暑さがやってきました。1ヶ月後に迫った大学時代の先輩との萩旅行の細かいスケジュールを連絡、微妙に詳細のツメが難しい。夜の酒席の予約もネットでは難しそうで、後で電話を入れる必要がありました。左膝の鈍い痛み継続中、なんとかストレッチと短いYouTubeエアロビクスを済ませました。昼から激安美容室にてタイムサービス(690円也)カットに出掛けてウォーキングの代わりにしようと思ったら・・・自分と似たような風体の爺連かなりの列満杯繁盛に断念。ちょっぴり食材を買い足して帰りました。いつも通り朝一番のスケジュールに出直しましょう。昨夜も寝苦しかったなぁ。今朝の体重は66.2kg▲350g 思うように減りません。
ポイ活なる言葉があることは伺って、楽天ポイントは有効に活用していると自覚しております。ところが・・・その他Pontaとか種々いろいろ、とんと理解していない。ホットペッパーのポイントが先月2,000円分失効していることは先程知りました。Yohoo!ポイントが660円ほど残っているのは自覚しているけれど、もう使いようもない囲い込み、これは諦めております。その辺り、自分はマメな性格じゃないみたい。
Windows11の6月アップデートに不具合続出とのこと。我がVaio-tapは「最新の状態です」となっていて、大丈夫だったのか。ある日、起動しなかったらショックやろなぁ。
今夜は女子バレー対泰国戦を愉しみにしましょう。
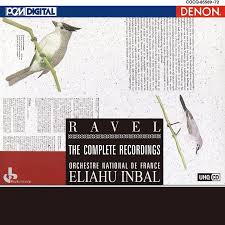 Ravel バレエ音楽「マ・メール・ロワ」/クープランの墓/逝ける女王のためのパヴァーヌ/海原の小舟/「ジャンヌの扇」~ファンファーレ~エリアフ・インバル/フランス国立管弦楽団(1987-88年)・・・Eliahu Inbal(1936-以色列)はさすがにもう引退年齢でしょう。我らがDenon録音CD4枚分、Brilliantの廉価盤CDにずいぶんお世話になったけれど、幾度聴いてその素っ気ない風情と乾いた音質にあまり好感を抱けなかった記憶もありました。一般にRavelは大好きだけど、とくにお気に入り作品を集めくれた一枚、前回いつ聴いたか記憶も記録もありません。
Ravel バレエ音楽「マ・メール・ロワ」/クープランの墓/逝ける女王のためのパヴァーヌ/海原の小舟/「ジャンヌの扇」~ファンファーレ~エリアフ・インバル/フランス国立管弦楽団(1987-88年)・・・Eliahu Inbal(1936-以色列)はさすがにもう引退年齢でしょう。我らがDenon録音CD4枚分、Brilliantの廉価盤CDにずいぶんお世話になったけれど、幾度聴いてその素っ気ない風情と乾いた音質にあまり好感を抱けなかった記憶もありました。一般にRavelは大好きだけど、とくにお気に入り作品を集めくれた一枚、前回いつ聴いたか記憶も記録もありません。
これが・・・久々の拝聴に印象一変! 音質は細部迄明晰にリアル、アンサンブルは緻密にクール、仏蘭西の代表的なオーケストラを駆使して、仏蘭西らしい色気はほとんど感じさせぬ軽い響きは神経質なほど。それが瑞西の精密時計と評されたRavelに似合って細身に淡彩、曖昧さのない仕上げに感心いたしました。
とってもメルヘンな旋律が夢見るような「マ・メール・ロワ」は二管編成に3種の打楽器、ハープにチェレスタ入ってきらきらサウンドが優雅そのもの、ラスト「妖精の園」の大団円迄ひんやり怜悧に続いて、聴手を夢の世界に誘(いざな)います。
前奏曲(Prelude)(3:27)
第1場 紡車の踊りと情景(Danse du rouet et scene)(3:41)
第2場 眠れる森の美女のパヴァーヌ(Pavane de la belle au bois dormant)(2:40)
第3場 美女と野獣の対話(Les entretiens de la belle et de la bete)(5:22)
第4場 親指小僧(Petit Poucet)(4:54)
第5場 パゴダの女王レドロネット(Laideronette, imperatrice des pagodes)(4:52)
終曲 (Le jardin feerique)(3:21)
「クープランの墓」は打楽器なしの二管編成+ハープ。これも息を潜めてデリカシー極まる可憐な作品。アンサンブルは精緻な集中力、オーボエの腕が試されます。正確なリズムにほとんど特別な色付けしない表現が作品風情を際立たせて、そこはかとなくユーモラス。
第1曲 「前奏曲(Prelude)」(3:35)第2曲 「フォルラーヌ(Forlane)」(6:17)第3曲 「メヌエット(Menuet)」(5:04)第4曲 「リゴードン(Rigaudon)」(3:07)
「逝ける女王のためのパヴァーヌ」は神々しい畏敬の念と堪能漂う透明な名曲。ヴィヴラートの掛かったホルンはなぜかあまりセクシーさが際立たない。(6:44)
「海原の小舟」(「鏡」第3曲)たしか葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」にインスパイアされた作品。大波に翻弄される小舟の風景を描写した、とのこと。(7:29)
「ファンファーレ」は大仰な小太鼓から木管、トランペットへと続く、ちょっぴりユーモラスな作品。「ジャンヌの扇」全曲を続けて聴くべき作品でしょう。(1:53)
 Stravinsky バレエ音楽「ミューズを率いるアポロ」~イーゴリ・マルケヴィッチ/ロンドン交響楽団(1963年)・・・少々前にネットよりLP復刻音源を発見、ダウンロードしたけれど細かいトラック分けが大混乱して行ったりきたり、その復元を断念してがっかりした記憶もありました。するとある日、ハイティンクのStravainsy三大バレエ旧録音(ロンドン・フィル)2枚組にこれが含まれていることを発見(組曲など小品集は含まれない)しかも、ちゃんと以前聴いているメモも出現して、相変わらず自分の記憶力減退を嘆いたものです。初演は1928年、打楽器の爆発、泥臭く激しいリズムとは無縁にアルカイックに静謐な弦楽合奏のみ34人、最高11声部に分かれるところがあるそう。音質はまずまず。Igor Mrkevitch(1912-1983烏克蘭→瑞西)による一連の録音は、どんなオーケストラの組み合わせにも不満を感じたことはなくて、その緻密な統率は作品に似合った緊張感でした。
Stravinsky バレエ音楽「ミューズを率いるアポロ」~イーゴリ・マルケヴィッチ/ロンドン交響楽団(1963年)・・・少々前にネットよりLP復刻音源を発見、ダウンロードしたけれど細かいトラック分けが大混乱して行ったりきたり、その復元を断念してがっかりした記憶もありました。するとある日、ハイティンクのStravainsy三大バレエ旧録音(ロンドン・フィル)2枚組にこれが含まれていることを発見(組曲など小品集は含まれない)しかも、ちゃんと以前聴いているメモも出現して、相変わらず自分の記憶力減退を嘆いたものです。初演は1928年、打楽器の爆発、泥臭く激しいリズムとは無縁にアルカイックに静謐な弦楽合奏のみ34人、最高11声部に分かれるところがあるそう。音質はまずまず。Igor Mrkevitch(1912-1983烏克蘭→瑞西)による一連の録音は、どんなオーケストラの組み合わせにも不満を感じたことはなくて、その緻密な統率は作品に似合った緊張感でした。
第1場/アポロの誕生 Naissance d'Apollon(5:32)
第2場/アポロのヴァリアシオン Variation d'Apollon ー Apollon et les Muses(2:52)パ・ダクシオン(アポロと3人のミューズ) Pas d'action ー Apollon et les trois Muses : Calliope, Polymnie et Terpsichore(5:23)カリオペの踊り Variation de Calliope (l'Alexandrin)(1:31)ポリヒムニアの踊り Variation de Polymnie(1:16)テルプシコールの踊り Variation de Terpsichore(1:33)アポロのヴァリアシオン Variation d'Apollon(2:43)パ・ド・ドゥ Pas de deux - Apollon et Terpsichore(4:23)コーダ(アポロとミューズの踊り)Coda - Apollon et les Muses(3:20)アポテオーズ Apotheose(3:50)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
新しい一週間が始まった昨日最高気温は34度C、本日も似たような気温らしいけど、なんせ湿度が高いから不快。夜も寝苦しい。洗濯物はちゃんと外に干せてよく乾きました。左膝の痛みに耐えつつストレッチ、例の東南亜細亜系女性のシンプルに動き続けるYouTubeエアロビクス8分ほど実施して市立体育館へ。トレーニング・ルームは流石に新顔現役世代は不在、常連マイナスαのメンバーに空いておりました。いつもどおりのゆる筋トレをこなしたけれど、もう2-3年メニューは変わっていないマンネリ状態。YouTubeを参考にすると同じ運動ばかりすると身体が慣れてしまって、効果は薄くなってしまう、筋トレに変化をつけよとのことでした。そんな工夫するほどの知識は残念、ありませんが。エアロバイク15分済ませてシャワー後、血圧は138やや高状態、正常値迄いま一歩。今朝の体重は66.55kgほぼ変わらない。昨日トレーニングから帰宅時の瞬間参考記録66.3kgだったので期待したけど、戻ってしまいました。
そういえばここ数日屁が少なくなっている・・・もしかして最近自粛しているピーナツがキモだったのか。Google検索AI回答によると「ピーナツ喰い過ぎは屁の要因になり得る」とのこと。日々かなりの量を愛食摂取してましたから。
昨日のネット銀行のすったもんだ(アプリ導入)の流れ。Windows11の新機能にスマホ連携というのがあるらしいのは知っておりました。以前メールにて「わからん曲を調べるアプリがある」旨ご教授があって、それをスマホならぬコンピューターよりネットに検索して出現、インストールすると・・・なんと(別部屋にあった)スマホ連携してそのまま導入されました。おそらく以前 別なアプリ(おそらくLINEか?)連携したした時にMyスマホを認識したんでしょう。驚きました。
昨日女房殿の誕生日。それなりに健康で・・・なんて云った矢先。眼科に出掛けて右目軽い網膜剥離レーザー手術したと連絡有。10年ぶり二度目。日常生活には支障はないそう。華麗なる加齢に、あちこちガタがくるのは仕方がないでしょう。だましだまし生きていくしかない。
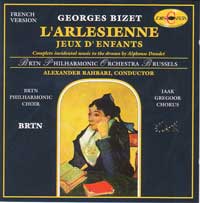 Bizet 劇付随音楽「アルルの女」(全曲)/小組曲「こどもの遊び」~アレクサンダー・ラハバリ/BRTNフィル(ブリュッセル)/合唱団/ヤーク・グレゴール合唱団/マルセル・ドソーニュ(ナレーター)(1992年)・・・2013年来の再聴。Ali Rahbari(1948-伊蘭)とは懐かしい名前、現ブリュッセル・フィルへの首席在任は1988-1996年、Discoverレーベルは自身が起こした会社でした。これは組曲ならぬ、ナレーター入りの戯曲向け音楽をすべて? 収録した貴重なもの。ナレーター(Marcel Dossogne/仏蘭西語/意味は理解できないけれどステキな低音男声)のみ、それは劇を再現したものなのか、それとも筋を追ったものかは不明。いずれほとんど録音は演奏会用組曲版なので貴重な存在でしょう。他にはミシェル・プラッソンの録音があったはず。二管編成だけど弦が人数は少なく(これがオリジナルの姿らしい)ハープ、ピアノ、ハルモニウム、ティンパニ+プロヴァンス太鼓。
Bizet 劇付随音楽「アルルの女」(全曲)/小組曲「こどもの遊び」~アレクサンダー・ラハバリ/BRTNフィル(ブリュッセル)/合唱団/ヤーク・グレゴール合唱団/マルセル・ドソーニュ(ナレーター)(1992年)・・・2013年来の再聴。Ali Rahbari(1948-伊蘭)とは懐かしい名前、現ブリュッセル・フィルへの首席在任は1988-1996年、Discoverレーベルは自身が起こした会社でした。これは組曲ならぬ、ナレーター入りの戯曲向け音楽をすべて? 収録した貴重なもの。ナレーター(Marcel Dossogne/仏蘭西語/意味は理解できないけれどステキな低音男声)のみ、それは劇を再現したものなのか、それとも筋を追ったものかは不明。いずれほとんど録音は演奏会用組曲版なので貴重な存在でしょう。他にはミシェル・プラッソンの録音があったはず。二管編成だけど弦が人数は少なく(これがオリジナルの姿らしい)ハープ、ピアノ、ハルモニウム、ティンパニ+プロヴァンス太鼓。
先月聴いたGrieg 劇音楽「ペール・ギュント」(ビャルテ・エンゲセト)台詞付き全曲はなかなか楽しめたけれど、Mendelssohnの「真夏の夜の夢」を全曲聴くと、ほほ途中で集中力が続かぬ言葉の壁と精神力に難がありました。
こちら馴染の旋律ばかり続いて最後迄楽しく拝聴可能。第2組曲フルートが晴れやかな「Menuetto」は歌劇「美しきパースの娘」からの引用なのでここには出現しません。Belgian National Radio Philは意外と雰囲気もあって、しっとりと爽やかな演奏、概ね馴染みの音楽に+組曲に収録されなかった魅惑の旋律も堪能できました。音質はまずまず。
Overture - 1 Act/Melodrama/Chorus: "Grand Soleil De La Provence" And Melodrama(13:55)/
2 Act/Pasto/Chorus/Melodrama/Melologue/Finale(10:21)/
3 Act/Entr'acte/Finale(4:03)/
4 Act/Intermezzo. Valse Menuet/Entr'Acte. Carillon/Melologue/Melodrama/Farandole*合唱入り(13:41)/
5 Act/Entr'acte/Chorus: "De Bon Matin, J'Ai Rencontre Le Train"/Melologue/Chorus: "Sur Un Char, Dore De Toutes Parts"/Melodrama/Finale*序曲の旋律を無伴奏の合唱で歌う場面も入ります(12:56)
「Jeux D'Enfants」はもともとピアノ連弾用作品だったそう。1872年管弦楽版初演。とっても愉快に溌溂とした作品でした。
「Marche - Trompette Et Tambour(ラッパと太鼓)」は軽妙に可愛らしい、弾むような始まり(2:11)/「Berceuse - La Poupee(お人形)」はそっと呟くように安らかな子守唄(2:57)/「Impromptu - La Toupie」緊張感漂う「こま」の回転(1:04)/「Duo - Petit Mari, Petite Femme(小さな旦那様、小さな奥様)」おままごとでしょうか。夢見るように美しい弦のアンサンブル。(3:15)/「Galop - Le Bal(舞踏会)」は軽快かつ快速な踊りの情景でした。(1:44)
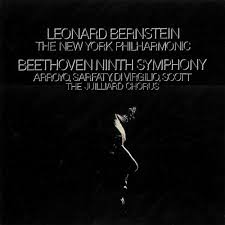 Beethoven 交響曲第9番ニ短調「合唱付き」~レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィル/ジュリアード合唱団/マーティナ・アーロヨ(s)/レジーナ・サーファティ(ms)/ニコラス・ディ・ヴァージリオ(t)/ノーマン・スコット(b)(1964年)・・・Leonard Bernstein(1918-1990亜米利加)ニューヨーク時代の旧録音。LP復刻音源の音質はまずまずでしょう。二管編成だけど、終楽章にはピッコロも入るし、ティンパニ以外4種の打楽器(土耳古風)そして声楽ソロ4人+混声合唱が加わる、当時としては壮大な編成でした。誰も知っている日本人大好きな祝祭的名曲を久々に堪能いたしました。独墺系伝統の響きじゃないけれど、この熱気は貴重ですよ。
Beethoven 交響曲第9番ニ短調「合唱付き」~レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィル/ジュリアード合唱団/マーティナ・アーロヨ(s)/レジーナ・サーファティ(ms)/ニコラス・ディ・ヴァージリオ(t)/ノーマン・スコット(b)(1964年)・・・Leonard Bernstein(1918-1990亜米利加)ニューヨーク時代の旧録音。LP復刻音源の音質はまずまずでしょう。二管編成だけど、終楽章にはピッコロも入るし、ティンパニ以外4種の打楽器(土耳古風)そして声楽ソロ4人+混声合唱が加わる、当時としては壮大な編成でした。誰も知っている日本人大好きな祝祭的名曲を久々に堪能いたしました。独墺系伝統の響きじゃないけれど、この熱気は貴重ですよ。
第1楽章「Allegro ma non troppo, un poco maestoso」宇宙の果から得体の知れない神秘ななにかが降っている・・・熱のこもった力強い始まりは意外とオーソドックスに、壮麗な重量感と推進力たっぷり。弦の響きがやや薄く、金管の響きはメタリックに感じました。(15:25)
第2楽章「Molto vivace」ヤケクソのように力強いリズムに、アクセントがアツくパワフルなスケルツォ。速めのテンポに前のめりの熱狂、推進力、叩きつけるようなティンパニが大活躍します。(10:40)
第3楽章「Adagio molto e cantabile - Andante moderato」ここはバーンスタインらしい、じっくり腰を据えて瞑想的に美しい変奏曲。ここの弦も木管もていねいなアンサンブルに仕上げて、ホルンの存在感は今一歩。クライマックスでの浅い響きはちょっぴりもの足りない。(17:36)
第4楽章「Finale: Presto - Allegro assai」たっぷり力こぶと詠嘆の入った出足。そして「喜びの歌」主題提示のパワフルな高揚は若々しく感動的。声楽ソロ(とくに男声)は勝手に自分のイメージじゃない軽さ明るさ、合唱は少人数?っぽい余裕のなさ、力みがありました。後半戦はちょっと音質劣化を感じさせたのはLP復刻問題でしょう。それはさておき、熱気とパワーに感動的なフィナーレを迎えました。(26:23)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日日曜は終日湿っぽい曇り空。前日昼の洗濯物は午前中にまだ乾いておりませんでした。ローソン銀行に仮預けしてあった雀の涙をSBI新生銀行に移動すべく(激安金利)定期満期を待って、例えば途中解約の方法など調べて読み込んでも、自分のノーミソではまったく理解できない。定期預金のタブに「途中解約」など出てこない。なんとか四苦八苦して新しい銀行に振り込もうと思ったら、ワンタイムパスワード?設定が必要とのこと。それはなに?ようはするにスマホにアプリ入れよ、とのこと。先日セブン銀行アプリを入れたし、スマホはますます大切なツールに至ったことを実感いたしました。一日の振込金額制限があって、これじゃ手数料がけっこう掛かりそう。そもそも本日、ほんまに手続きできているのか自信もありません。(今朝無事に振込は成功確認)
昨日朝起きだしたら左膝の痛み、こわばりは悪化しておりました。なんとかいつものストレッチ、短いYouTube有酸素運動済ませてから「膝痛 ストレッチ」の動画検索、いくつか対策実行しつつ、いままでの古傷(左膝前十字靭帯一本切れている)の痛みとは違う~自分は勝手に坐骨神経痛と診断して、実態はわかりません。動かしているうちにちょっぴり症状は改善いたしました。今朝の体重は66.6kg▲400g、ようやく久々の66kg台。本日女房殿誕生日、そこそこ健康に年齢を重ねられることを喜びましょう。
調子の悪かったビデオ・デッキを取り出したらホコリが大量に溜まっていて、これは構造的な問題。時々掃除していたけれど久々、今回もそうとうホコリまみれ、我が強力Dysonで入念に吸い取った結果・・・無事復活いたしました。どうやらリモコンの責任ではなかったみたい。一個ムダになったけど、本体が無事だったからマシ。
その後、万博はレジオネラ菌繁殖とか?トラブルさておき、けっこう人気は上がって来場者は増えているようです。赤字は減るでしょうか。業者への支払いトラブルが問題になっていた泥婆羅館はようやく開館とのこと。
以色列/伊蘭は泥沼戦争へ。世界はあちこちきな臭くて、無辜の民はどの国を問わず苦しんでいることでしょう。日本へはどんな影響があるのか。
そして夜は男子バレー対阿蘭陀戦。このチームは世界で一番高い。それをものともせず宮浦絶好調、一番身長のある佐藤駿一郎登場して活躍、結果的に3-0勝利したけれど西本圭吾や山崎彰都を初投入して、危うい場面を乗り切ります。ラストはやはり高身長の高橋慶帆も一発決めて勝利しました。波蘭戦は残念だったけれど、新しいメンバーの活躍を確認できました。
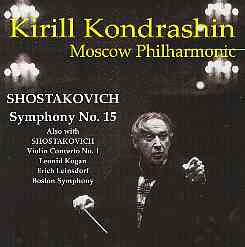 Shostakovich 交響曲第15番イ長調~キリル・コンドラシン/モスクワ・フィル(1972年/ミュンヘン・ライヴ)・・・これはミュンヘン・オリンピックを記念した演奏会の記録とのこと。アナウンスが入る放送エア・チェック?音質はイマイチなモノラル、低音はしっかり捉えられておりました。(.mp3音源)フルート二本+ピッコロは拡張された二管編成?ハープもなくて比較的編成は小さいけれど、14種の打楽器が入ります。ま、こんな希少音源聴く前に正規セッション録音ちゃんと聴けよ、ということですよね。
Shostakovich 交響曲第15番イ長調~キリル・コンドラシン/モスクワ・フィル(1972年/ミュンヘン・ライヴ)・・・これはミュンヘン・オリンピックを記念した演奏会の記録とのこと。アナウンスが入る放送エア・チェック?音質はイマイチなモノラル、低音はしっかり捉えられておりました。(.mp3音源)フルート二本+ピッコロは拡張された二管編成?ハープもなくて比較的編成は小さいけれど、14種の打楽器が入ります。ま、こんな希少音源聴く前に正規セッション録音ちゃんと聴けよ、ということですよね。
第1楽章「Allegretto」は「ウィリアム・テル」も引用されてなんとなくシニカルにリズムカル、ユーモラスな始まり。心持ち速めのテンポに表情厳しく、前のめりに緊張感を湛えて疾走する始まりでした。(7:46)
第2楽章は「Adagio- Largo」暗鬱な金管から暗く彷徨うようなチェロのソロが続いて、これは十二音列風なんだそう。やがてLargoに至ってリズムが変わるけれど、重苦しい低減のピチカートに乗って金管が重苦しい葬送行進曲風へ。トロンボーンの音色がエグいヴィヴラート、中盤には激しい爆発もありました。チェレスタとコントラバス?ですか、静謐な沈黙が続きました。(13:41)
第3楽章は「Allegretto」不気味に怪しく、静謐に躍動するスケルツォ。ここも十二音階とか、各パート勝手バラバラに順繰りに出番を競っているような素っ頓狂に不安なところでした。(4:58)
第4楽章「Adagio」は冒頭Wagner 楽劇「神々の黄昏」~「運命の動機」まるまる引用。不気味な低弦のピチカートに乗って浮遊する弦や木管、これはpassacaglia?(変奏)いろいろ引用されているようで、金管による苦渋の大爆発はHaydn交響曲第104番「ロンドン」ニ長調冒頭とか。難解であり、掴みどころのない消えゆくようなフィナーレでした。(15:40/30秒ほど拍手有)
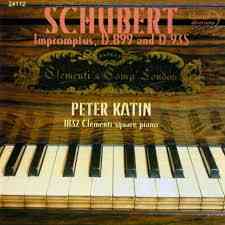 Schubert 即興曲集 作品90/D899/作品142/D935~ピーター・ケイティン(fp)(1993年)・・・ピッチはa'=423のブロードウッド使用。Peter Katin(1930-2015英国)自らのスタジオでの録音とのこと。素朴に温かい音色のピアノ、音質はちょっと鮮明さを欠くように感じるのは楽器の違い?勘違いでしょうか。浮き立つようにステキな旋律連続する絶品作品、浪漫派の真骨頂はピアノに有、いつもそう感じます。モダーン楽器によるデリケートなニュアンスに慣れているせいか、マイルド?なタッチにちょっと洗練とキレが足らない?作曲当時はこんな響きだったのでしょう。
Schubert 即興曲集 作品90/D899/作品142/D935~ピーター・ケイティン(fp)(1993年)・・・ピッチはa'=423のブロードウッド使用。Peter Katin(1930-2015英国)自らのスタジオでの録音とのこと。素朴に温かい音色のピアノ、音質はちょっと鮮明さを欠くように感じるのは楽器の違い?勘違いでしょうか。浮き立つようにステキな旋律連続する絶品作品、浪漫派の真骨頂はピアノに有、いつもそう感じます。モダーン楽器によるデリケートなニュアンスに慣れているせいか、マイルド?なタッチにちょっと洗練とキレが足らない?作曲当時はこんな響きだったのでしょう。
作品90/D899/No. 1 in C Minor「Allegro molto moderato」決然として力強い、淡々とした歩みから、やがて表情は明るく、優しく変化する絶品の始まり。(9:20)
No. 2 in E-Flat Major「Allegro」目まぐるしく細かい音型による華麗なる疾走と陰影。流麗なテクニックにここはソフトなタッチと音色が似合っておりました。(4:24)
No. 3 in G-Flat Major「Andante」流れるように懐かしい風情が延々と続くところ。(5:31)
No. 4 in A-Flat Major「Allegretto」 はらはらと落ちた枯れ葉が、静かな水面に流れるように、ちょっと儚い寂しい名曲。(7:28)
作品142/D935/No. 1 in F Minor「Allegro moderato」暗い劇性から安寧の風情に移行してやがて切ない、感情の揺れ動きを感じさせる浪漫。(11:11)
No. 2 in A-Flat Major「Allegretto」万感の思いを胸に、人生に静かに別れを告げる~そんなイメージはバックハウスの最後の演奏会からの刷り込みでしたっけ?(7:18)
No. 3 in B-Flat Major「Theme and Variations」時に優しく切ない、優雅な懐かしさ溢れる「ロザムンデ」の主題と変奏曲。(12:10)
No. 4 in F Minor: Allegro scherzando」符点のリズムが哀しげな躍動しました。(6:58)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日土曜午前は降ったり止んだり、市立体育館往復には傘が必要でした。左膝は症状やや悪化して膝の辺りのストレッチは難しく、歩く速度は変わらないけれどちょっと痛いなぁ、それでもいつものトレーニングは消化できました。シャワー前に血圧を測ると最高134、かなり下がってきて130を切ればほぼ正常。このまま節制と減量を続けて一喜一憂せずに様子を眺めましょう。体調は悪くない感じ。昼前に女房殿が体育館より戻って洗濯開始して昼からジャジャ降り、室内干し必須。明後日は女房殿の誕生日、寿司が喰いたいと曰うけれど、くら寿司にはどうも食指が伸びないし、JR北新地迄出掛ける元気もなし。ご近所(やや高級)スーパーにまぐろとアジの寿司、惣菜と野菜を入手して、サラダと汁物を+ささやかな夕食としました。今朝の体重は67.0kg▲200g。
なんか国民民主党は山尾志桜里さんを巡って泥沼な感じ、都議選の動きはどうなるのでしょう。風頼みは脆いものです。
現金を使う機会は減って、耳鼻科の支払いの時に気付いたのは、旧札が消えたこと。新旧札が交じるのはサイズが違うのでどうにも違和感があって、新札に離れていないのでなんとなくウソっぽく、安物に感じるのは勝手な先入観でしょう。それでもわずか数ヶ月で旧札は消えていくものなんやなぁ、妙な感慨がありました。ズボンを洗濯したらポケットから500円玉が出てきました。小銭も使う機会は減りました。
通販にて故障したビデオのリモコン到着・・・ところが・・・故障していたのはじつはリモコンではない?本体だったみたい。1,200圓ほどムダにしたかも。これから本体取り外してお掃除してみようと思います。
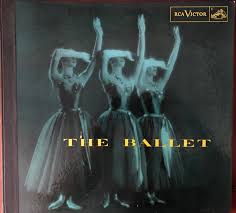 これはLP時代3枚組で発売された「The Ballet」(RCA LM-6113)復刻音源はすべて1950年前後のモノラル、どれもかなり良心的な音質でした。選曲はややマニアック、画像も、内部詳細調べて幾度も聴いた記憶もあるのにサイト内検索に言及やら別途拝聴メモが探せません。
これはLP時代3枚組で発売された「The Ballet」(RCA LM-6113)復刻音源はすべて1950年前後のモノラル、どれもかなり良心的な音質でした。選曲はややマニアック、画像も、内部詳細調べて幾度も聴いた記憶もあるのにサイト内検索に言及やら別途拝聴メモが探せません。
Meyerbeer バレエ音楽「預言者」(Lambert編)(アーサー・フィードラー/ボストン・ポップス管弦楽団/1951年?)オリジナルのオペラのことはようわかりません。パリのオペラにはバレエが付き物なので、その関係の編曲でしょうか。
賑やかにウキウキするような「Ensemble」(1:28)ノンビリとして快活な変拍子ワルツである「Redowa」中間部には軽妙な哀愁を挟んで、最後は疾走(5:43)大股で歩くようなリズムとアクセントがおもろい「Pas de Patineuses」後半は優雅に流れの良いもの(4:21)「Finale」弦のピチカートから始まって、常動曲的な疾走が華やかに軽快に続きました。(4:08)
Piston バレエ音楽「不思議な笛吹」(1953年?)これも筋書きはわからない初耳作品だけど、とってもわかりやすい、楽しい賑やかな旋律ばかり。
オリエンタルに気怠い「Siesta in the Market Place」(1:01)「Entrance of the Vendors」ここは素っ頓狂にリズミカル。(2:31)「Entrance of the Customers」ホルンとトランペットによる来客者(0:33)「Tango of the Merchants' Daughters」優雅なタンゴ?中間部はモロにそのリズムでした。(3:25)「Arrival of the Circus」小太鼓のリズムに乗ってサーカスがやってきた!楽しげな歓声が響いて、犬も鳴きます。途中の神妙なフルート・ソロはなにを表しているのでしょう。オシャレな踊りも始まって、ピアノ・ソロに終了。(3:09)「Spanish Waltz」は賑々しい元気いっぱいのワルツ。ラスト柱時計が鳴ります。(1:20)「Siciliano」は寂しげなオーボエ、そして弦の歌。(1:57)「Polka FInale」不気味なピチカートの囁きから、華麗なポルカがそろりそろり手探りに始まって、賑やかなフィナーレを迎えました。(2:30)
Stravinsky バレエ組曲「火の鳥」(1919年版)(レオポルド・ストコフスキー/彼の管弦楽団/1950年)
ステレオも含め彼は幾度も録音しているけれど、すべて1919年組曲版二管編成(打楽器少なめ)音質は上々、ニューヨークの録音用オーケストラも色彩豊かに、たっぷり華やかに歌って金管爆発!(フィナーレの金管せり上げ部分の楽譜はどうなっているのでしょうか)期待通りのデーハーな演奏でした。
「Introduction, Dance of the Firebird」(4:25)「Round Dance of the Princesses, Infernal Dance of King Kashchei」(9:23)「Berceuse, FInale」(7:45)
Ravel バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲(アルトゥール・トスカニーニ/NBC交響楽団/1949年)デリケートに華やかな作品はオーケストラがモウレツに上手くて、強烈な集中力にテンション高く、ノリノリ。 (4:53-7:17-4:12)
Weber 「舞踏への勧誘」(1951年)かなり速いテンポにかっちりとしたリズムは強烈、これでは踊れそうもありません。中間部はちょっと優しい表現でした。(7:53)
 Delibes バレエ音楽「シルヴィア」/「コッペリア」(抜粋)(ピエール・モントゥー/ボストン交響楽団のメンバー/1953年)これは意外と有名な録音。「Members of」となっているのは各パート首席が抜けてるからなんだそう。だったらボストン・ポップスのことだけれど、契約問題があったのでしょう。モノラルだけれどかな良好な音質。仏蘭西らしい華やかなリズム、明る軽い金管が華麗な作品、そして実力充分のオーケストラ。
Delibes バレエ音楽「シルヴィア」/「コッペリア」(抜粋)(ピエール・モントゥー/ボストン交響楽団のメンバー/1953年)これは意外と有名な録音。「Members of」となっているのは各パート首席が抜けてるからなんだそう。だったらボストン・ポップスのことだけれど、契約問題があったのでしょう。モノラルだけれどかな良好な音質。仏蘭西らしい華やかなリズム、明る軽い金管が華麗な作品、そして実力充分のオーケストラ。
「Sylvia」Prelude - Les chassaresses(4:43)Intermezzo and Valse lente(5:29)Pas de Ethiopiens(1:52)Chant bacchique(1:52)Chant Bachique(2:45)Pizzicati, Violon solo(6:04)Pizzicati(4:09)Cortege de Bacchus(5:52)
「Coppelia」Prelude, Marzurka(5:32)Scene et Valse de Swanhilde(3:34)Czardas(3:41)Scene et Valse de la poupee(3:43)Ballade(2:48)Theme slav varie - Variations 1-4(6:34)
Ravel 「ラ・ヴァルス」(シャルル・ミュンシュ/ボストン交響楽団/1950年)は珍しい旧録音。後年のステレオ録音があるから隠れてしまったけれど、これは血湧き肉躍るような熱狂的な金管の技量強烈!(10:30)
Roussel バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」第2組曲(1953年)これは1930年初演にしてはヴィヴィッドなリズムに平易な旋律がカッコよく、勇壮華やかな名曲。音質はかなり良好。後年の仏蘭西名曲集にも収録されておりました。相変わらずミュンシュはパワフルな熱血演奏でした。
Prelude - Le sommeil d'Ariane(2:57)Reveil d'Ariane(2:09)Bacchus danse seul(1:48)Le baiser(1:01)L'enchantement dionysiaque(1:05)Le thiase defile(0:37)Danse d'Ariane(3:48)Bacchanale(2:54)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
本日は終日雨らしい。週末に入って昨日は終日曇ったり晴れたり。洗濯は外干しできて気持ち良よく乾きました。前夜、痰がひどくて寝苦しく途中覚醒、起き出して蒸気吸入してから二度寝。左膝の痛みの原因は坐骨神経痛?ちゃんと診てもらっていないから、ほんまの要因はわからんけど、それをこらえてしっかりストレッチ、そして何語か?わからん東南亜細亜の女性による13分動き続けるYouTubeエアロビクスに汗を流しました。左膝以外の体調は悪くはない。
朝一番に婆さんのところに女房殿は出掛けて、夕食は必要とのことなのでしっかり準備しました。食材は揃っております。ぼちぼち一週間ほど間食を自主規制していて、じつはピーナツと柿の種が大好き(お仕事引退記念に職場の皆様よりドンキのデカボトルをいただいたくらい)前者は身体には良さげなビタミンE豊富だけどカロリーが高い、後者は塩分が気になります。さて、その成果はいかがでしょうか。今朝の体重は67.2kg▲100gあまり変わらない。
男子バレーは対塞爾維戦3-0完勝。相変わらず相手チームは高くパワフルだけど、こちら若手甲斐が先発、サーブにアタックにブロックに大活躍して時期への育成をしております。宮浦は相変わらず絶好調。村山もラリーも好調を維持しておりました。最終セットジュースから競り勝った26-24は実力でしょう。次は阿蘭陀戦です。石川、髙橋藍、高橋健太郎や小野寺、山本が抜けても勝てるのですね。(西田は代表ご遠慮/関田は怪我の治療中)相変わらず小川の堅守が光っております。
他人のふんどし~なんだけど、gooブログが消える前にリンクしておきましょう。
 Tchaikovsky 歌劇「エフゲニー・オネーギン」の件、自分はずっとボリス・ハイキン1955年盤を気に入っておりました。ロストロポーヴィチの1970年盤は日本では当時話題となって、なんとか賞も取ったらしい。そこはオペラ・ド・シロウトの哀しさ、どこがどうの具体的理由はわからぬまま、せっかく入手できたロストロポーヴィチLP復刻音源にはガッカリ・・・じつは、歌い手の実力や役割と表現個性、そして筋書きにそぐわないテンポ設定などいろいろ問題があったのですね。それに・・・音質的にも不満を覚えたもの。
Tchaikovsky 歌劇「エフゲニー・オネーギン」の件、自分はずっとボリス・ハイキン1955年盤を気に入っておりました。ロストロポーヴィチの1970年盤は日本では当時話題となって、なんとか賞も取ったらしい。そこはオペラ・ド・シロウトの哀しさ、どこがどうの具体的理由はわからぬまま、せっかく入手できたロストロポーヴィチLP復刻音源にはガッカリ・・・じつは、歌い手の実力や役割と表現個性、そして筋書きにそぐわないテンポ設定などいろいろ問題があったのですね。それに・・・音質的にも不満を覚えたもの。
漫然とした不満には、ちゃんとそれなりの理由があったのですね。いろいろお勉強になりました。
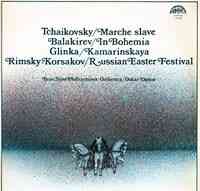 Tchaikovsky スラヴ行進曲/Balakirev 交響詩「ボヘミアにて」(チェコの主題による序曲)/Glinka 幻想曲「カマリンスカヤ」/Rimsky-Korsakov 「ロシアの復活祭」序曲~オスカー・ダノン/ブルーノ・フィル(1978年リリース)・・・CD化はされていないらしいOskar Danon(1913ー2009塞爾維)の露西亜もの、オーケストラも選曲も渋いし、音質もまずまず良好でした。
Tchaikovsky スラヴ行進曲/Balakirev 交響詩「ボヘミアにて」(チェコの主題による序曲)/Glinka 幻想曲「カマリンスカヤ」/Rimsky-Korsakov 「ロシアの復活祭」序曲~オスカー・ダノン/ブルーノ・フィル(1978年リリース)・・・CD化はされていないらしいOskar Danon(1913ー2009塞爾維)の露西亜もの、オーケストラも選曲も渋いし、音質もまずまず良好でした。
「スラヴ行進曲」は颯爽と勇壮なカッコよい名曲。遅めのテンポに物々しい貫禄と重みを感じさせて、切々と歌う立派な演奏でした。オーケストラの響きはあまりに泥臭く、ローカルに素朴な勢い。(9:50)
「ボヘミアにて」は秘曲、もちろん初耳。懐かしい旋律が静かに始まり、やがて上機嫌にテンポを上げて明るく、高らかに踊るステキな作品でした。オーケストラの技量はあまり流麗ではない味わい系~というか、かなりリズムがたどたどしい。(12:50)
「カマリンスカヤ」は堂々たる重厚な始まりから露西亜風の短い素材(わずか3小節)はつぎつぎ姿を変えつつ、70回繰り返す熱狂的ノリノリ作品(ネット情報受け売り)なんだけど・・・ちょっとノリ不足。(6:30)
ラストは有名な「ロシアの復活祭」。三管編成に6種の打楽器+ハープという堂々たる規模。吉幾三「酒よ」による荘厳なるテーマが静々と歌いだして、それが緊張感を高めて風雲急を告げるカッコよい作品。ここでは颯爽として流れよろしく、前2曲のダルさを覆す勢い~やはりクライマックスでは、とくに金管のパワー不足を感じさせました。(素朴さ丸出し!)(15:10)
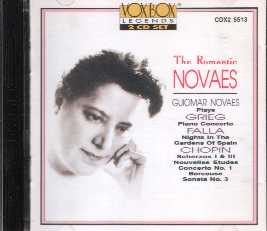 Grieg ピアノ協奏曲イ短調/de Falla スペイン庭の夜/Chopin スケルツォ第1番ロ短調 作品20/第3番 嬰ハ短調 作品39/新しい練習曲第1番第1番ヘ短調/第2番 変イ長調/第3番 変ニ長調~ギオマール・ノヴァエス(p)/ハンス・スワロフスキー/ウィーン交響楽団・・・Guiomar Novaes(1894-1979伯剌西爾)の2枚組「Romantic Novaes」は1993年発売され即入手した記憶有。この度ネットに.mp3音源出現、キリがないので基本.mp3は収集対象外なんやけど、懐かしさもあってずいぶんと久々に確認してみました(CD1のみ)。1950年代のモノラル録音は意外と奥行きと雰囲気もあって悪くない。
Grieg ピアノ協奏曲イ短調/de Falla スペイン庭の夜/Chopin スケルツォ第1番ロ短調 作品20/第3番 嬰ハ短調 作品39/新しい練習曲第1番第1番ヘ短調/第2番 変イ長調/第3番 変ニ長調~ギオマール・ノヴァエス(p)/ハンス・スワロフスキー/ウィーン交響楽団・・・Guiomar Novaes(1894-1979伯剌西爾)の2枚組「Romantic Novaes」は1993年発売され即入手した記憶有。この度ネットに.mp3音源出現、キリがないので基本.mp3は収集対象外なんやけど、懐かしさもあってずいぶんと久々に確認してみました(CD1のみ)。1950年代のモノラル録音は意外と奥行きと雰囲気もあって悪くない。
Griegは劇的な力強さと詩情が両立して慌てず、やや遅いテンポに優しく暖かいタッチに歌う演奏でした。スワロフスキーのバックも立派。伴奏は古典的二管編成+ティンパニ。
第1楽章「Allegro molto moderato」ティンパニからフィヨルドの氷壁が崩れ落ちる衝撃の始まりは、じっくり腰を据えて落ち着いたピアノの音色は瑞々しい。曖昧さのないテクニックのキレは強面にならず、懐かしくも華やかなスケールに歌います。(13:10)
第2楽章「Adagio」清涼な緩徐楽章はさらりとして、流れのよろしい表現。朗々たるホルンとピアノの掛け合いも爽快、そしてデリケート。(6:00)
第3楽章「Allegro molto moderato e marcato」劇的なフィナーレの始まりは力感は充分でも叩きつけるような激しさに至らない。中間部、懐かしいフルートに導かれて極限の懐かしさにそっとピアノが囁くところは絶品、ラストは悠々と美しいタッチを駆使してスケール大きく終了いたしました。(10:41)
「スペイン庭の夜」は三管編成にティンパニ、シンバル、トライアングル、チェレスタ、ハープが入ります。名曲です。モノラル音質が薄靄の掛かったような特殊な効果を上げておりました。
第1楽章「En el Generalife(ヘネラリーフェにて)」はなんとも湿度の高い濃密な南国の夜を連想させるセクシーな始まり。呟くように濃密なピアノにオーケストラも雰囲気たっぷりに雄弁。(11:10)
第2楽章「Danza lejana(はるかな踊り)」オリエンタルに快活に妖しい舞曲が遠くから響いていくる・・・第3楽章「En los jardines de la Sierra de Cordoba(コルドバの山の庭にて)」哀愁の旋律リズムがなんとも切なく、やがて祭りの後の気怠い気分感情が漂うピアノも最高。(13:27)
Chopinは音質やや落ち。スケルツォはキレのあるテクニックを駆使して流麗、即興的な緊張感が続きました。(9:18-7:15)練習曲はそっとデリケートな哀愁、郷愁、雰囲気たっぷり。(2:28-1:46-1:40)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日は午前中雨との予報も、結局降りませんでした。左膝は久々に調子がよろしくないけれど、朝のストレッチ+YouTubeエアロビクス(短い6分ほどのもの)済ませて市立体育館を目指しました。道中、どうも左膝辺りが鈍く痛むけれど、筋トレ、エアロバイクはいつもどおりのメニューをこなせました。帰りスーパーに寄ってちょっぴり食材入手して一日の目標運動量はクリアできました。コメの棚はちょっと在庫少なめだったけど、買えぬことない程度、あまり安くはありません。今朝の体重は67.3kg▲300g思うように減りません。
先日いつもの爺友と呑んで珍しく含蓄深い話題。それは英語露西亜語堪能、孤高の独身を守って種々執筆(自費出版など)に引退後の生活を送っている生真面目一方の65歳。女性関係の話題でした。「女性関係」と云っても華やかだったり、劇的なトラブル物語でもなくて、学生時代より同じサークルに在籍して、いまでも仲間達とは交流があるそう。思い出の彼女は卒業して長崎に帰郷して教職一筋、いかにも昭和の先生といった品行方正、化粧っ気もない生真面目なタイプ、幾度か京都大阪に出てきてアプローチらしきものもあったそう。
しかし残念、彼は(柄にもなく)もっとデーハーな化粧の濃いタイプが好みだったそうで関係は進展せぬまま、お互い独身のまま引退世代を過ぎました。最近はLINEへの反応も薄く、ある日アルツハイマー症状が始まっていることを告白されたとのこと。ちょっとほろ苦い、切ない話しでした。
日大重量挙げ部で起きた前監督による学費不正徴収事件発覚、またまた~根深いですね。悪しき体質というのは一朝一夕には一掃できぬものか。
夜は男子バレー強敵対波蘭戦1-3敗北。第1セットぎりぎりで逆転されてから勢いは相手チームに、競り合っているようで勝ち切れないのは実力の差でしょう。第4セットはジュース連続!37-39。若手高橋慶帆、甲斐優斗、リベロの藤中颯志も登場して新しい戦力としたけれど、残念。
 Mendelssohn 交響曲第2番 変ロ長調「賛歌」作品52~ジョン・エリオット・ガーディナー/ロンドン交響楽団/モンテヴェルディ合唱団/ルーシー・クロウ(s)/ユルギタ・アダモニテ(ms)/マイケル・スパイアーズ(t)(2016年ライヴ)・・・バービカン・ホールのデッドなサウンドを懸念したけれど、音質は良好でした。二管編成+ティンパニ、そして第2部にはオルガン、女声ソロ二人、テナー、混声合唱団。Beethovenの「第九」風であり、Bachにインスパイアされた、それなりの長さに拝聴機会の少ない作品。聴いたのは一体何年ぶりでしょう。演奏個性云々のコメントはもちろんできそうにありません。端正に素直な演奏と感じました。
Mendelssohn 交響曲第2番 変ロ長調「賛歌」作品52~ジョン・エリオット・ガーディナー/ロンドン交響楽団/モンテヴェルディ合唱団/ルーシー・クロウ(s)/ユルギタ・アダモニテ(ms)/マイケル・スパイアーズ(t)(2016年ライヴ)・・・バービカン・ホールのデッドなサウンドを懸念したけれど、音質は良好でした。二管編成+ティンパニ、そして第2部にはオルガン、女声ソロ二人、テナー、混声合唱団。Beethovenの「第九」風であり、Bachにインスパイアされた、それなりの長さに拝聴機会の少ない作品。聴いたのは一体何年ぶりでしょう。演奏個性云々のコメントはもちろんできそうにありません。端正に素直な演奏と感じました。
第1部は器楽演奏のみ/第1楽章「Sinfonia: Maestoso con moto - Allegro」最初の3本のトロンボーンによるシンプルに荘厳な主題は全編に登場して統一感を高めます(ラストにも登場)。主部は快活なAllegroが疾走、ここにも冒頭の主題が出現します。ここの屈託のない軽みと熱気、華やかな勢いは、いかにもMendelssohnらしいとのところ。(11:45)
第2楽章「Allegretto un poco agitato」はほの暗く、つぶやくような魅惑のスケルツォ。この旋律も素直にわかりやすく、軽い流れ。ここもリズムを変えて第1楽章冒頭の旋律が登場します。(6:06)
第3楽章「Adagio religioso」は安らぎの静かな緩徐楽章。中間部はちょっぴりテンポを上げて息抜き風でした。(6:25)
第2部より声楽とオルガン参加して、冒頭旋律があつこち顔を出して全曲の統一感を形作ってわかりやすい、威圧感のないもの。ガーディナー手兵の合唱団は端正に充実して、清潔清楚なソロに文句ありません。歌詞は聖書より。
「Alles was Odem hat (Chorus)」(4:10)「Lobe den Herrn meine Seele ((s)/Chorus)」(2:24)「Recitative: Saget es, die ihr erlost seid(t)」(0:52)「Er zahlet unsre Tranen (t)」(2:17)「Sagt es, die ihr erlost seid (Chorus)」(1:42)「Ich harrete des Herrn (s)I, II, Chorus)」(5:33)「Aria: Stricke des Todes hatten uns umfangen(t)」(4:04)「Die Nacht ist vergangen (Chorus)」(4:17)「Choral: Nun danket alle Gott」(1:32-2:56)「Drum sing' ich mit meinem Liede(s)(t)」(4:16)「Ihr Volker, bringet her dem Herrn (Chorus)」言葉の意味はわからんけど、冒頭の荘厳な旋律回帰して気分高揚、感動的な締め括りでした。(5:22)
 Shostakovich 交響曲第1番ヘ長調/交響曲第9番 変ホ長調~ミラン・ホルヴァート/ザグレブ・フィル(1963年)・・・3年前に一度拝聴済。LP復刻音源は時に響きは濁るけれど、バランスも解像度もそう悪くないリアルな音質でした。Milan Horvat(1919-2014克羅地亜)はかつて怪しげな廉価盤CDに多く登場して、自分にとってはお馴染みの指揮者でした。
Shostakovich 交響曲第1番ヘ長調/交響曲第9番 変ホ長調~ミラン・ホルヴァート/ザグレブ・フィル(1963年)・・・3年前に一度拝聴済。LP復刻音源は時に響きは濁るけれど、バランスも解像度もそう悪くないリアルな音質でした。Milan Horvat(1919-2014克羅地亜)はかつて怪しげな廉価盤CDに多く登場して、自分にとってはお馴染みの指揮者でした。
交響曲第1番は栴檀は双葉より芳しい若者の作品。才気煥発なユーモア作品には生真面目な鋭さが際立つ演奏。オーケストラの弱さは感じさせぬ立派なアンサンブルでした。
第1楽章「Allegretto - Allegro Non Troppo」かなり速めの落ち着かぬテンポに始まって、金管はかなり激烈に爆発してヴィヴィッドな始まり。
第2楽章「Allegro」ここも鋭い緊迫感に充ちた快速。ピアノと金管が活躍して、怪しいテンポの緩急も決まっております。
第3楽章「Lento」重苦しい緩徐楽章を経て
第4楽章「Allegro Molto」緊張感ただよう疾走から、やがてAdagioに沈静化。ラストは金管が粗野に大爆発してティンパニが印象的なソロに中断、ウネウネとエネルギーが湧き上がってパワフルに終了いたしました。(合計30:12)
交響曲第9番は妙に軽快、シニカルに明るい作品。ちょっぴり曇って音質の劣化を感じたけれど、気になるほどではない。こちらもなかなかテンションの高い演奏でした。
第1楽章「Allegro」ノーテンキなステップを刻むピッコロと、無遠慮な金管の対比がオモロいはじまり。ここもかっちりと楷書の表現にパワフルに緊張感たっぷりな推進力。図太いトローンボーンとそれに呼応するヴァイオリン・ソロや木管の対比がわかりやすい表現でした。
第2楽章「Moderato」快活な前楽章とは対象的に、クラリネットやフルート、やがて弦が虚無的な足取りにゆったり歩むところ。途中ヴィヴラートたっぷりのホルンもなかなかの技量に、切迫感を高めていく緩徐楽章。
第3楽章「Presto」快速に剽軽に自在軽妙な木管の躍動は弦へ引き継がれ、金管の爆発は強烈であり、トランペットの勇壮なソロも妙に俗っぽくシニカルなスケルツォ。
第4楽章「Largo」は神妙に仰々しい金管のファンファーレ。これは終楽章への導入。
第5楽章「Allegretto」怪しいファゴットはユーモラスなのか?不安なのか微妙に始まるフィナーレ。堂々たる歩みからラスト、モウレツな追い込みにテンポ・アップして忙しなく終了しました。(合計25:31)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
こちら雨は昼から上がったようだけど、どこにも出掛ける気分になれません。九州地方には土砂災害厳重警戒が出ているとのこと。前夜女房殿は婆さんのところに泊まりなので独り。飯を喰って、風呂に入ってさっさと洗濯を済ませて室内干し。もちろん一晩では乾かず、当たり前だけどスポーツ用上下はさっさと乾くようにできていることに感心いたしました。コンピューター・オーディオ部屋は洗濯物の湿度で不快。なんとかいつものストレッチ、YouTube鍛錬はお気に入りのシンプルな動き15分継続したらすごい汗!でした。今朝の体重は67.6kg+150g現在食事はしっかり摂って、間食を止めるトライアルお試し中。
珍しく着信有。自分の激安スマホは050/090、ニ種の番号所有。090のほうを種々登録に使っていない(知り合いにも知らせていない)のはSMSが鬱陶しいから。だからそんな着信は100%迷惑電話と決まっております。自分の生活に占めるスマホの位置は小さいので、リビングに置きっぱなし、別の部屋で音楽など聴いていると着信にも気付かず、不義理することもありました。
たまたまスマホの近くに座っている時に着信があって、番号を見るといかにも迷惑電話っぽい。試しに出てみると自動音声、内容は確認せず、すぐ切って迷惑電話登録音完了しました。未だいまのところ大丈夫だけど、新たな「オレオレ詐欺」風テクニックが出現して自分も引っ掛かる日がやってくるのでしょうか。ちょっと不安です。
あまり使用頻度の多くないビデオ・レコーダーだけれど、リモコンが故障したみたい。さてどうしましょう。中古で探すか、悩みどころです。(数年ぶりにヤフオク入手しようとしたら、なんか失敗。現在キャンセルお願い中。情けない→無事キャンセルできました)
山尾志桜里さん国民民主党公認取り消しとか。だめですよ中途半端は、一度決めたらとことんやらんと。幹部は日本の空気の恐ろしさを甘く見たのか。岐阜中央道で99歳逆走、大きな事故にはならなかったようだけど、ちょっと多くないですかこの類の話題。
そして夜、楽しみしていた男子バレー対中国戦は3-0勝利。女子バレーも大好きだけど、男子バレーの高さ、速さ、強さには痺れるもの。イケ面揃って女性は大騒ぎでしょう。日本チームは海外でも(中国でも)大人気らしい。石川も髙橋藍もお休み(関田は怪我で治療中)宮浦が大活躍、セッターは大宅、富田がキャプテン代理。リベロは小川。ラリー、村山、この辺りが代表新顔。中国は高いけど荒削りな印象、サーブ・ミスも目立ちました。日本も富田、大塚はいまいちセッターと息が合っていないように見えたけれど、まずは初戦完全アウェイのなかでの勝ち抜けました。今夜は強豪波蘭戦、カンタンには勝たせてくれんでしょう。
「エフゲニー・オネーギン」~ボリス・ハイキンを久々に聴いて、耳がすっかり露西亜歌劇になってしまいました。印象イマイチだったロストロポーヴィチ盤、音質優秀に作品風情堪能できたエミール・チャカロフも続けて(摘み)聴きして、さらにMussorgsky 歌劇「ホヴァーンシチナ」(アナトス・マリガリトフ盤)のサワリを確認、これは音源再入手できていて、思わぬ臨場感たっぷりの音質に感心したものです。「ボリス・ゴドゥノフ」との出会いであったアセン・ナイデノフ盤はその後、ネットに音源が出現しておりません。そんなこんな、その辺りの音源をネットに探って次々とダウンロード、オペラは長いからどーせちゃんと聴けないんだけれど、もうどうにも止まらない。さらにその流れ・・・
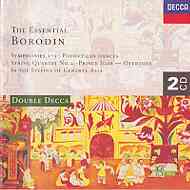 Borodin 歌劇「イーゴリ公」序曲/だったん人の踊りと合唱(ジョージ・ショルティ/ロンドン交響楽団/合唱団/1966年)/「わしに栄誉が与えられ」/「ごきげんいかが? 公爵さま」(ニコライ・ギャウロフ(b)/エドワード・ダウンズ/ロンドン交響楽団/1966年)/遠い祖国の岸辺のために(ニコライ・ギャウロフ(b)/ズラティカ・ギャウロフ(p)/1971年)/交響曲第1番 変ホ長調(ウラディミール・アシュケナージ/ロイヤル・フィル/1992年)/交響曲第2番ニ長調(ジャン・マルティノン/ロンドン交響楽団/1958年)/弦楽四重奏曲第2番ニ長調(ボロディン弦楽四重奏団/1961年)/交響詩「中央アジアの高原にて」(1961年)/交響曲第3番イ短調(未完成/Glazunov編/エルネスト・アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団/1954年)・・・今更英DECCA録音在庫寄せ集め音源かよ・・・なんて油断して聴き始めたら音質も意外と良好、Borodin魅惑のオリエンタルな旋律次々と押し寄せて、演奏もなかなかよろしくCD2枚分の音源を一気に聴いてしまいました。
Borodin 歌劇「イーゴリ公」序曲/だったん人の踊りと合唱(ジョージ・ショルティ/ロンドン交響楽団/合唱団/1966年)/「わしに栄誉が与えられ」/「ごきげんいかが? 公爵さま」(ニコライ・ギャウロフ(b)/エドワード・ダウンズ/ロンドン交響楽団/1966年)/遠い祖国の岸辺のために(ニコライ・ギャウロフ(b)/ズラティカ・ギャウロフ(p)/1971年)/交響曲第1番 変ホ長調(ウラディミール・アシュケナージ/ロイヤル・フィル/1992年)/交響曲第2番ニ長調(ジャン・マルティノン/ロンドン交響楽団/1958年)/弦楽四重奏曲第2番ニ長調(ボロディン弦楽四重奏団/1961年)/交響詩「中央アジアの高原にて」(1961年)/交響曲第3番イ短調(未完成/Glazunov編/エルネスト・アンセルメ/スイス・ロマンド管弦楽団/1954年)・・・今更英DECCA録音在庫寄せ集め音源かよ・・・なんて油断して聴き始めたら音質も意外と良好、Borodin魅惑のオリエンタルな旋律次々と押し寄せて、演奏もなかなかよろしくCD2枚分の音源を一気に聴いてしまいました。
硬派ショルティはさすがオペラの人、物語が始まる期待にワクワクする 歌劇「イーゴリ公」序曲(10:55)「だったん人」の野蛮に強靭な勢いと躍動と爆発(13:49)ロンドン交響楽団も颯爽と速いテンポにノリノリ、キレのある優秀なアンサンブルは輝かしい演奏でした。合唱団もおみごと。
Nicolai Ghiaurov(1929-2004年勃牙利)による重厚に艶のある圧巻のアリアは序曲のあと/「だったん人の踊り」の前に収録され、短いけれどオペラの流れが味わえます。(3:57-7:12)ピアノ伴奏の歌曲は初耳だけど貫禄ある風情に懐かしい旋律、著名な作品なんだそう。(4:32)
アシュケナージはたしか交響曲第2番も録音していたはず。交響曲第1番 変ホ長調は1868年初演、古典的二管編成+ティンパニ、演奏機会は少ないと思います。
第1楽章「Adagio-Allegro-Andante」重苦しく暗い大地のような始まりから、軽快な躍動はあまりBorodinらしいオリエンタルな泥臭い風情は感じさせぬもの。(13:05)
第2楽章「Scherzo」これはデリケートに早足、明るく軽妙に走り出すところ。トリオは優しく懐かしく小声に歌って、全体にちょっと素っ気ない楽章。(7:00)
第3楽章「Andante」Borodin得意のゆったり夢見るように懐かしい旋律。後年に比べるとちょっぴり薄味に感じます。(8:03)
第4楽章「Finale: Allegro molto vivo」符点のリズム、粗野に躍動するフィナーレ。アシュケナージはきりりとした統率に盛り上げておりました。(7:12)(ここまでCD一枚目)
著名な交響曲第2番ニ長調は1879年改訂版初演が成功し、20世紀初頭パリに大ブームが起こったそう。三管編成+打楽器5種+ハープと拡大しております。やや曇っているけれど1958年とは思えぬリアルな音質、Jean Martinon(1910-1976仏蘭西)は未だ40歳代、ごりごりと低音を効かせてパワフル、ヴィヴィッドに緩急自在、表情たっぷり豊かな演奏でした。ロンドン交響楽団は好調、作品そのものを見直しましたよ。あまり量を聴いていないからナニやけれど、この作品ヴェリ・ベスト。
第1楽章「Allegro moderato」ダルな演奏で効くと、ダサい冒頭のリズムも颯爽とカッコよく疾走します。(6:44)
第2楽章「Scherzo. Molto vivo」トロンボーンの細かいリズムに乗せて快速テンポ。ノリノリのスケルツォ楽章。(4:38)
第3楽章「Andante」しみじみホルンが雄弁に美しい。悠々と広がりと情感の高まりを堪能できる緩徐楽章。大音量でちょっと金管が濁りました。ラスト安寧のオーボエ、遠いホルンがハープに包まれて収束。(7:44)
第4楽章「Finale. Allegro」ワクワクするような符点のリズムに打楽器も活躍、オリエンタルな旋律はいかにもBorodinの個性横溢。アツい勢いのまま全曲を上機嫌に締め括りました。(5:58)
弦楽四重奏曲第2番ニ長調は深く瞑想する第3楽章「夜想曲」が忘れられぬ名曲。たしかボロディン弦楽四重奏団は幾度かこの作品を録音していたはず。お気に入り作品だから正直云うと、誰の演奏でも感動しなかったことはない。音質は極上。
第1楽章「Allegro moderato」は夢見るように懐かしい節回したっぷり、ここもオリエンタルな異国情緒漂う静謐デリケートな魅惑の始まりでした。(7:51)
第2楽章「Scherzo」は優雅なワルツのリズムに躍動するスケルツォ。前楽章の浮き立つように懐かしい気分は、引き続き高揚して陰影もたっぷり。(4:45)
第3楽章「Notturuno,Andante」そして甘美に絶品の夜想曲。これは変奏曲でしょうか。(8:09)
第4楽章「Andante-Vivace」はちょっぴり怪しい序奏からテンポを上げて、明るく疾走する主部へ。この晴れやかな表情はいかにもラストに相応しい希望に充ちておりました。(6:51)
ラストは御大アンセルメによる雰囲気たっぷり余裕の演奏。音質も悪くない。
「中央アジアの高原にて」は砂漠のシルクロードにラクダの一行がゆっくり接近し、やがて静かに去っていく・・・これはなんの変哲も展開もない、心を無にして耳を傾けるべき哲学的な作品。けっこう好き。(6:44)
交響曲第3番イ短調は未完成(Glazunov補筆)二管編成+ティンパニ。1954年驚異のステレオ録音!さほど音質的に違和感はありません。第1楽章「Moderato assai」いつものBorodinらしい優雅な風情はあるけれど、特異なリズム感とかクサい節回しはあまり出現しない。(7:15)第2楽章(本来は第3楽章だった予定とのこと)「Scherzo」は5/8拍子。まるで賑やかな村祭りの喧騒のような愉快な変拍子リズムが面白いところ。中間部のオーボエ・ソロはいかにも泥臭い、懐かしい旋律でした。(8:45)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
雨が続いてますね。こちらもしっかり降っているけれど、九州では厳重注意が出ているそう、被害はいかがでしょうか。名古屋のホテルで男性が絞め殺されたり(容疑者は確保されたらしい)茨城県境では逆走事故、36歳だからご高齢者のうっかり事故ではないみたい。こんな物騒な事故や事件ばかり、増えてませんか、日本。前夜女子バレーの活躍をしっかりテレビに堪能して満足、それなりに眠った翌朝、いつものストレッチ、そして軽いYouTube体操済ませて、市立体育館へ目指しました。雨だから運動公園は誰もいない。トレーニングルームは自転車組が休みだから空いておりました。いつもどおりのゆる筋トレ+エアロバイク15分こなしました。血圧はやや高いまま、先日呑んだ前の水準に戻った・・・と思ったら、今朝の体重は今朝の体重は67.45kgほぼ変わらない。夕食に自ら作っった麻婆豆腐がとても美味くて、しっかり喰ってしまったからか。
芬蘭土大統領夫人はかつて能登の高校に教えていたとのこと。震災の被害を心配して、再訪されたとの心温まる記事を拝見しました。こういうほっこりのは全国ニュースにならんのか。
北大生協にて「物体X」販売開始! 無視できないニュース発見。
遠く大阪の地より声高に異議を唱えたい。北海道なら「おやき」でしょうが!今川焼きという一般名称に負けるとはなんたること。新大阪駅に出る度に「御座候」は必ずおみやげに買うし、こちらでは回転焼きとか太鼓饅頭とかいろいろ呼ぶらしい。ローカル文化は意識して守らないと、消えていきますよ。
今夜は男子バレー対中国戦。さて、初戦メンバーは誰が出るのでしょうか。
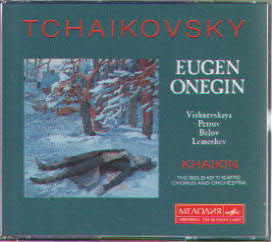 Tchaikovsky 歌劇「エフゲニー・オネーギン」~ボリス・ハイキン/ボリショイ歌劇場管弦楽団/合唱団/エフゲニー・ベロフ(br)/ガリーナ・ヴィシネフスカヤ(s)他(1955年)・・・じつは最近このオペラ、念願のロストロポーヴィチ/ボリショイ歌劇場の1970年録音(LP復刻)を入手、自分にとってはLP時代これが作品との出会い、刷り込みのはずが世間ではもうほとんど話題になっていないようで、音源も入手難っぽい。ちょっと聴いてみたけれど残念、音質印象も散漫に集中できませんでした。
Tchaikovsky 歌劇「エフゲニー・オネーギン」~ボリス・ハイキン/ボリショイ歌劇場管弦楽団/合唱団/エフゲニー・ベロフ(br)/ガリーナ・ヴィシネフスカヤ(s)他(1955年)・・・じつは最近このオペラ、念願のロストロポーヴィチ/ボリショイ歌劇場の1970年録音(LP復刻)を入手、自分にとってはLP時代これが作品との出会い、刷り込みのはずが世間ではもうほとんど話題になっていないようで、音源も入手難っぽい。ちょっと聴いてみたけれど残念、音質印象も散漫に集中できませんでした。
ネットに「オネーギン ロストロポーヴィチ ボリショイ」で検索したら・・・2000年には聴いていたらしい自らのシンプルな(とっても恥ずかしい)ボリス・ハイキン盤言及出現。懐かしく思い出して疑似ステレオ音源を久々に取り出しました。
これが音場の不自然さはあるけれど、意外と音質鮮明に驚きのわかりやすさ、歌い手も際立って甘い魅惑の旋律連続堪能できました。 Boris Khaykin(1904-1978露西亜)はオペラの大家。Galina Vishnevskaya (1926-2012露西亜)も未だ29歳でした。筋書きはこちら参照お願い。原作は文豪プーシキンらしい。
主人公のエフゲニー・オネーギン(Evgeny Belov,1912-?露西亜)はクズ男だったんですね。昔、あっさり袖にした田舎地主の娘タチアナ、その妹オリガ(Larisa Avdeyeva,1912-2013露西亜)を弄び、激怒したその婚約者レンスキー(Sergey Lemeshev ,1902-1977露西亜)と決闘して勝利、その後放浪の旅へ。旅から戻ったオネーギンはタチアナと再会、彼女は公爵夫人となって、しっとりとした人妻の色香満載に変身、今更ながらクズ男は言い寄るが結局は振られる~そんな昭和の連続昼メロドラマ風筋書きらしい。それが例の濃密にわかりやすい甘美な旋律サウンドに乗せて歌われます。露西亜歌劇は重厚な男声中心のイメージがあるけれど、これは哀愁の女声ソロが活躍してなかなか楽しい~時間も比較的短いし。第3幕の「ポロネーズ」は独立して演奏会用演目になっているほど有名でした。以下Google翻訳を使ったので、意味不明なところ有。申し訳ない
CD1(68:00)
第1幕/第1場
序奏。デュエットとカルテット(7:04)農民の合唱と踊り(4:40)オルガのアリア(3:21)ラリーナ(?)のシーン(2:55)カルテット(3:23)レンスキーのアリオーソ(5:38)最後のシーン(2:39)
第2場
導入と乳母とのシーン(7:56)タチアナの手紙の場面(12:52)デュエット(6:04)
第3場
少女合唱団(3:04)オネーギンのアリア(8:17)
CD2(72:02)
第2幕/第1場
ラリンス劇場での舞踏会。休憩、ワルツ、舞台、合唱(7:37)トライクの連句((?)6:19)マズルカ(4:35)最後のシーン(5:02)
第2場
序奏。レンスキーのアリア(9:38)決闘(5:35)
第三幕/第1場
ポロネーズ(4:25)アリア・グレミナ(11:53)オネーギンのアリオーソ(3:49)最後のシーン(13:06)
じつはこのあと、エミーロ・チャカロフ/ソフィア・フェスティヴァル/アンナ・トモワ・シントウ(s)(1988年)を聴いたら音質良好。オペラ・ド・シロウト(=ワシ)にもいっそう愉しめると痛感したものです。この録音も現役ではなさそう。
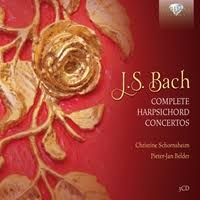 Bach チェンバロ協奏曲ニ短調 BWV1052/チェンバロ協奏曲ホ長調 BWV1053/チェンバロ協奏曲ニ長調 BWV1054/チェンバロ協奏曲イ長調 BWV1055~クリスティーネ・ショルンスハイム(cem)/ブルクハルト・グレッツナー/新バッハ・コレギウム・ムジクム(1990年)・・・ Christine Schornsheim(1959-独逸)はチェンバリストであり、フォルテピアノの録音も数多く出ております。Burkhard Glaetzner(1943-独逸)はオーボエの名手として有名でした(ライプツィヒ放送交響楽団の首席在任)。Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzigは1979年創立のモダーン楽器アンサンブル。残響豊かに自然な音質は極上、控えめに躍動するチェンバロ、スッキリと整った弦楽アンサンブル、古楽器云々など先入観なしにBachの名曲を堪能できる素晴らしい記録でした。Pieter-Jan Belderによる2006年録音を加えてCD3枚分、Bachの鍵盤協奏曲をほぼ全曲拝聴できます。馴染みの旋律にゆっくり耳を傾けると、精神が整うような思いに至りました。
Bach チェンバロ協奏曲ニ短調 BWV1052/チェンバロ協奏曲ホ長調 BWV1053/チェンバロ協奏曲ニ長調 BWV1054/チェンバロ協奏曲イ長調 BWV1055~クリスティーネ・ショルンスハイム(cem)/ブルクハルト・グレッツナー/新バッハ・コレギウム・ムジクム(1990年)・・・ Christine Schornsheim(1959-独逸)はチェンバリストであり、フォルテピアノの録音も数多く出ております。Burkhard Glaetzner(1943-独逸)はオーボエの名手として有名でした(ライプツィヒ放送交響楽団の首席在任)。Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzigは1979年創立のモダーン楽器アンサンブル。残響豊かに自然な音質は極上、控えめに躍動するチェンバロ、スッキリと整った弦楽アンサンブル、古楽器云々など先入観なしにBachの名曲を堪能できる素晴らしい記録でした。Pieter-Jan Belderによる2006年録音を加えてCD3枚分、Bachの鍵盤協奏曲をほぼ全曲拝聴できます。馴染みの旋律にゆっくり耳を傾けると、精神が整うような思いに至りました。
ニ短調協奏曲 BWV1052はピアノでの演奏が多く聴かれるもの。Bachの鍵盤作品は一般にピアノのほうが強弱ニュアンス表現の幅を愉しめるけれど、この作品は例外。ちょっと暗い風情はピアノでは重すぎると感じます。しっとりと憂愁はチェンバロのほうが軽快かつ清潔清楚に響きました。I. Allegro(7:47)/II. Adagio(5:39)III. Allegro(8:00)
ホ長調協奏曲 BWV1053は屈託のない明るく軽妙な風情。オーボエ協奏曲として有名でしょうか。I. (Without tempo indication)(7:46)II. Sicilianoは絶品の楚々とした哀しみ(4:27)III. Allegro(6:28)
ニ長調協奏曲 BWV1054はヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調として有名。ノンビリと優雅な風情は鍵盤のほうが映えると感じます。I. (Without tempo indication)(7:46)II. Adagio e piano sempre(5:10)III. Allegro(2:48)
イ長調協奏曲 BWV1055は浮き立つように牧歌的に躍動する風情。これもオーボエ・ダ・モーレ協奏曲として有名。I. Allegro(4:24)II. Largetto(5:28)III. Allegro ma non tanto(4:11)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
どうも鼻が詰まって痰が絡んで睡眠がよろしくない。昨日月曜は昼から雨の予報に、ストレッチはうんと手抜き、10分ほどのピラティス風YouTube鍛錬済ませてから早々に耳鼻科に向かいました。予約時間通り診療は済んで、特別に新たな治療法もないらしく、いままで通りの抗アレルギー薬+対処療法のみ。自宅での蒸気吸入を再開いたしましょう。帰りちょぴり食材買い足して帰宅したら一日の運動量に達しました。業務スーパーにもそれなり手頃な価格のコメは潤沢に並んでおりました。洗濯物は概ね乾いたとところで室内へ移動。ぼちぼち梅雨入りですかね、今朝は本格的な雨が降っております。九州では線状降水帯発生したとのこと。例年、水害は続いております。今朝の体重は67.5kgほぼ変わらない。思うように減ってはくれません。
幾度か言及しているけれど、ステレオ・タイプな「日本礼賛」の動画は危うい存在と思います。
某ブログを読んでいっそう感じました。
「電車で実家に行ったが、席に座っている乗客が黙々と携帯電話を見つめているのはちょっと異色。じゃまにならないように戸口の脇に大きなスーツケースを移動させたのだが、一番脇に座っている人が肘を手すりから出しているのでスーツケースの上にリュックサックを置けない。ほんの僅か動かしてくれれば改善されるのだけれど、ご本人はスマホに夢中。
日本の電車は正確に運行されるし、乗車のマナーも外国に比べるとずっと良い。でも乗車してからの乗客同士の配慮はドイツの方が良い。ドイツではよく席を譲り合うし、大きな荷物を持っている人は周りが助けてくれる。日本では重いスーツケースが引っかかって乗車時にもたもたすると、申し訳ない気分になる」
日本の悪いところ、良いところもたくさんある。謙虚に改善しないと悪化の道を進むでしょう。例えば公共トイレの美しさ、路上にゴミ捨てないこと(残念、我が街には路上ゴミや川に捨てるのはけっこう日常風景)それはすべて努力して、年月を掛けて積み重ねてきた結果でしょう。つまり、現状を過去現在未来~動的に見ないと将来への道を誤ると思います。大切な魂を失うと、せっかくの成果を失います。既に治安の良さにも陰りを感じております。
女子バレー加奈陀ラウンドのラスト、土弥尼加共和国に3-0これで4連続勝利落としたセットなし。ミッドブロッカーには島村宮部が戻って、リベロには岩澤初登場、これが凄い粘りに大活躍。キャプテン石川20得点、佐藤も好調でした。日本のお家芸フェイク・セットも登場。お相手の高さ(ブライリン・マルティネスは201cm!)と圧巻のパワーをサーブとディフェンスに対応、課題であったブロックも要所で成功させ(若い秋元も)力負けしませんでした。前戦の加奈陀は相手チームのミスに助けられた感じもあったけれど、今回はほんまもんの勝利。明日から男子バレーが始まります。
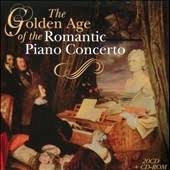 The Golden Age of the Romantic Piano Concerto(Brilliant Classics/CD20枚分)はもともとVOX録音?現在では+20CD=40枚分出ているようです。ちょっとマニアックな作品、演奏家揃えてVOX時代にいくつか興味深く聴いて、こうしてまとめた状態で入手しやすくなったことは幸いでした・・・てなこと書いたけれど、すっかり忘れていて、偶然在庫音源を再発見したもの。情けないっすね。録音情報は不明、ステレオ初期?あちこちの録音はばらつきがあります。最初の3曲を聴いてみたけれど、忘れ去られるにはもったいほどの名曲揃いでした。
The Golden Age of the Romantic Piano Concerto(Brilliant Classics/CD20枚分)はもともとVOX録音?現在では+20CD=40枚分出ているようです。ちょっとマニアックな作品、演奏家揃えてVOX時代にいくつか興味深く聴いて、こうしてまとめた状態で入手しやすくなったことは幸いでした・・・てなこと書いたけれど、すっかり忘れていて、偶然在庫音源を再発見したもの。情けないっすね。録音情報は不明、ステレオ初期?あちこちの録音はばらつきがあります。最初の3曲を聴いてみたけれど、忘れ去られるにはもったいほどの名曲揃いでした。
Johann Baptist Cramer(1771-1858独逸→英国)
ピアノ協奏曲第5番ハ短調 作品48~相良明子(p)/ピエール・カオ/ルクセンブルク放送管弦楽団(1973-74年)・・・相良明子さんはザルツブルク・モーツァルテウム音楽大学の先生だったそう。詳細情報は探せませんでした。Cramerとは初耳、Beethovenとほぼ同世代のピアノの名手だったらしい。これは1813年の作品。ピアノはしっとりとしたタッチに美しく、オーケストラはちょっと響きが薄く、アンサンブルも粗い。おそらくは二管編成にティンパニ、フルートの存在感は効果的でした。
第1楽章「Allegro maestoso」劇的な風情から始まって、やがて名残惜しくも晴れやかな表情に展開して、哀愁の甘い旋律はしみじみ、ちょっぴりChopinも連想いたしました。(14:26)
第2楽章「Larghetto」ここはホルンが牧歌的に始まって、それを爽やかにフルートが受け継ぐ始まり。懐かしくも淡々とシンプルな旋律がしみじみ歌うピアノ。変奏曲かな?ここはなかなかの名曲ですよ。(6:46)
第3楽章「Rondo a l'hongroise」暗く寂しげだけど、ピアノは可愛らしい軽妙な符点のリズムを刻んでフィナーレが始まります。やがて明るく表情を変えて穏健、ソロの音色は落ち着いて瑞々しいもの。(8:48)
Carl Czerny (1791-1857墺太利)はSchubert辺りとほぼ同世代、教則本はあまりに有名。
演奏会用ディヴェルティメント 作品204~マイケル・ポンティ(p)/パウル・アンゲラー/南西ドイツ・プフォルツハイム室内管弦楽団(録音年不明)は懐かしさ溢れて、しっとりと落ち着いた始まりから、やがて可憐なリズムに走り出す明るい名曲。秘曲専門っぽいMichael Ponti(1937-2022独逸→亜米利加)の技巧は明晰。ラスト辺りヴィオリン・オブリガートとピアノの掛け合いはうっとりと美しい。(14:45)
Ferdinand Ries(1784-1838独逸)たしかこの人はBeethovenの弟子。
ピアノ協奏曲第3番 嬰ハ短調 作品55~マリア・リッタウアー(p)/アロイス・シュプリンガー/ハンブルク交響楽団(録音年不明)・・・ちょっぴり音質は曇りがち、オーケストラはかなり安っぽく響きます。Maria Littauerは(1920-?墺太利)Vox_Turnaboutに録音をよく見掛けて、揺れ動く浪漫の表情豊かに軽快な技巧は充分、美しい音色でした。ちょっと型通りっぽいけれど、これは陰影豊かなけっこうな名曲。
第1楽章「Allegro maestoso」はいかにも初期浪漫風の劇的な始まり。やがて優しくピアノが歌って、緩急豊かに華やかな旋律が躍動して名残惜しい。Mendelssohnを連想させました。(14:50)
第2楽章「Larghetto」しっとり纏綿と歌うピアノは静謐、時に力強いもの。(5:03)
第3楽章「Rondo: Allegretto」フィナーレは弾むような希望に溢れた快速パッセージが走り出します。ピアノは華やかな軽さにスムースな技巧にノリノリ、中間部の「泣き」も楚々として聴きもの、ほとんどChiponですよ。力強くパワフルな打鍵に全曲を閉じました。(10:37)
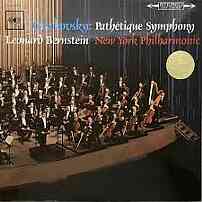 Tchaikovsky 交響曲第6番ロ短調「悲愴」(1964年)/幻想序曲「ハムレット」(1970年)~レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィル・・・古い方のステレオ録音。小学生時代から聴いて、いささか食傷気味の名曲「悲愴」。2024年HDDお釈迦事件のどさくさ、彼のTchaikovsky交響曲全集音源失っていることに気付いて、なんとかネットより再入手。1893年のラスト作品は三管編成+4種の打楽器には銅鑼も含まれます。おそらくは数十年ぶりの拝聴。ちょっと肌理は粗いけれどかなり良好な音質、そして記憶通りの前向きの熱気とパワー溢れる46歳の記録。晩年の再録音より速めのテンポ、ニューヨーク・フィルにはちょっと濁りはあるけれど、それを凌駕する入れ込みと集中力がありました。散々聴いてきた馴染みの作品、小綺麗に整った大人しい演奏など求めて聴きたいとは思いません。
Tchaikovsky 交響曲第6番ロ短調「悲愴」(1964年)/幻想序曲「ハムレット」(1970年)~レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィル・・・古い方のステレオ録音。小学生時代から聴いて、いささか食傷気味の名曲「悲愴」。2024年HDDお釈迦事件のどさくさ、彼のTchaikovsky交響曲全集音源失っていることに気付いて、なんとかネットより再入手。1893年のラスト作品は三管編成+4種の打楽器には銅鑼も含まれます。おそらくは数十年ぶりの拝聴。ちょっと肌理は粗いけれどかなり良好な音質、そして記憶通りの前向きの熱気とパワー溢れる46歳の記録。晩年の再録音より速めのテンポ、ニューヨーク・フィルにはちょっと濁りはあるけれど、それを凌駕する入れ込みと集中力がありました。散々聴いてきた馴染みの作品、小綺麗に整った大人しい演奏など求めて聴きたいとは思いません。
第1楽章「Adagio - Allegro non troppo」は抑制された熱気が滾るように落ち着かぬ、前のめりな始まり。たっぷり陶酔する弦も続く木管も大仰に歌ってクサいほど、展開部の大爆発も決然!と決まって若々しく疾走しました。荒々しい、暑苦しいほどのパワー炸裂、Leonard Bernstein(1918-1990亜米利加)46歳気力体力充実しております。(18:45)
第2楽章「Allegro con gracia」4/5拍子という特異なワルツは甘く、これも浮き立つように前のめりに落ち着かない。勢いと熱気を感じさせて、やや速めのテンポに進行しました。(7:11)
第3楽章「Allegro molto vivace」ここも同様。ちょっぴりアンサンブルが合わないところなど枝葉末節なこと、この勢い、いや増す熱気と、ほとんどヤケクソ的明るいパワーこそスケルツォに必須な表現、ラストのテンポ・アップも決まっております。(8:55)
第4楽章「Adagio lamentoso; Andante」再録音では17分掛けて演奏したところ。こちら通常テンポ、哀しみと浄化を感じさせるフィナレーも、うねうねと筋肉質のアツい響きにたっぷり前のめり。たっぷり泣いて粘着質表現も若々しい。渾身の集中力からやがて力尽きて全曲を閉じる風情も見事に決まりました。(11:39)
「Hamlet」は一連のシェクスピアにインスパイアされた劇的作品は三管編成+7種の打楽器、けっこう大きなもの。これは既に欧州進出後の録音、アンサンブルはいっそう粗く、ちょっと仕上げに乱暴さを感じさせる演奏でした。(19:18)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
月曜の朝は未だ雨は降っていないようです。本日以降今週は梅雨っぽい気候が続くとのこと。昨日日曜は終日曇天、洗濯物はまとめて外に干しました。洟水痰の絡みがずっと軽快しないので、今回は速めに本日これから耳鼻科の予約を入れております。昨日眠り浅く目覚めてストレッチ、YouTubeエアロビクスはオーソドックスなもの済ませて市立体育館へ。可愛らしいこども達の剣道柔道の集まりで満杯、トレーニングルームには早めに入れたので、あとからやってきた若い人たちより前に筋トレマシンを済ませました。エアロバイク15分=70kcalも消化して、スーパーに野菜とかキウイを仕入れに寄りました。こうして継続して体調を整えられることに感謝。今朝の体重は67.45kg▲450gまだまだ。
屁がよく出る要因
恥ずかしいけれどここしばらく屁がやたらと多くて難儀しております。迂闊にマッサージにもいけません。ネットに要因を尋ねると・・・
早喰いをしている(これが一番思い当たるフシがある)
食物繊維を過剰に摂取している(過剰かどうかわかないけれど、意識して摂っているのはたしか。いっぱんに焼き芋に屁、というのはこのことなのですね)
高脂質なものや動物性たんぱく質を多く摂取することが多い(これは当てはまらない。My屁はまったく臭わない)
慢性的に運動不足である(これも大丈夫)
精神的なストレスがある(これは微妙やなぁ、ここ最近夢見よろしくないし)
早喰いには体重増とも関係が深くて、そのクセを意識して治さないといけませんね。食物繊維の摂り過ぎの弊害というのはあるものでしょうか。もちろん腸内環境は大切なのでしょう。
夜は女子バレー対加奈陀戦はお相手ホームゲームだからアウェイ。これも朝一番に3-0完勝の結果は知っておりました。内容はよろしくなくて、和田は絶好調だけど、佐藤淑乃が抑えられていたし、お相手のサーブミスに助けられた感じ。ヴァン・ライクのパワーにはまったく歯が立っておりません。ミッドブロッカーは山田と荒木、リベロは西村に変わっておりました。加奈陀ラウンドのラスト、土弥尼加共和国にも既に3-0勝利の結果はわかっているけれど、問題は内容です。今夜のテレビを愉しみにしておきましょう。
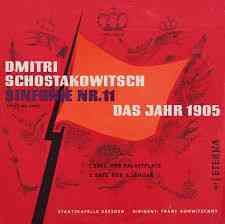 Shostakovich 交響曲第11番ト短調「1905年」~フランツ・コンヴィチュニー/シュターツカペレ・ドレスデン(1959年)・・・この時期にして残念なモノラルだけど、音質はそう悪くなくて解像度も高い。最近拝聴機会の多い作品だけど、これは屈指の完成度に演奏堪能できました。ヴェリ・ベストかも。
Shostakovich 交響曲第11番ト短調「1905年」~フランツ・コンヴィチュニー/シュターツカペレ・ドレスデン(1959年)・・・この時期にして残念なモノラルだけど、音質はそう悪くなくて解像度も高い。最近拝聴機会の多い作品だけど、これは屈指の完成度に演奏堪能できました。ヴェリ・ベストかも。
第1楽章「The Palace Square(Adagio)」冒頭不気味な弦の静寂も、ティンパニは重心低くリアルな存在感、トランペットやホルン、木管も音質環境乗り越えて細部曖昧にならぬ雰囲気たっぷりに浮き立ちます。ドレスデンのサウンドはクールに神妙なもの。ヤワな演奏だと音楽の流れが行方不明になる可能性もある抑制された始まりは、表情豊かに緊張感は高まって、これは嵐の前の静けさ。(16:16)
第2楽章「The 9th of January (Allegro)」低弦の怪しい動きは民衆の行動を表現しているんだそう。そしてわかりやすく決然とした主題が幾度繰り返され、力を加えて暴力的なかつ壮絶悲痛な金管の爆発へ~やがてそれはいったん鎮まって・・・ゴリゴリとした低弦、小太鼓から始まるヒステリックな金管、打楽器による皇帝軍の一斉射撃へ。音質条件乗り越え、その緊張感とカッコ良さは劇的壮絶、やがて悲惨な犠牲者累々の情景に静かに収束しました。(18:30)
第3楽章「In Memoriam(Adagio)」ここはゆったりとした低弦ピチカートから始まる犠牲者へのレクイエムなんだそう。有名な「同志は倒れぬ」の弦が神妙に呟いて、中間部は革命歌「こんにちは、自由よ」(これは知らん歌)の旋律が切々と、やがてヤケクソ気味に叩きつけるティンパニとともに激昂します。(14:10)
第4楽章「The Tocsin(Allegro non troppo)」はティンパニとトランペットがちょっと俗っぽいほどに、颯爽と煽る始まり。ごりごりと低音も響いて有名な「ワルシャワ労働歌」へ。高らかなトランペットもホルンも痺れるように深い音色に絶叫、ピッコロもそれに追随します。この辺りドレスデンは絶好調。そして第1楽章冒頭の静謐が戻って、イングリッシュホルンの懐かしい旋律が歌って、不気味な大太鼓連打から不穏に決然たるクライマックスへ。金管絶叫して鳴り響く打楽器、チューブラーベルの中、感動的に終了。(15:09)
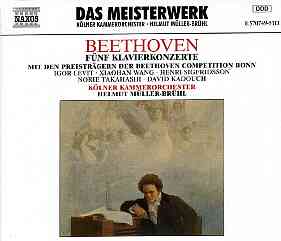 Beethoven ピアノ協奏曲第1番ハ長調(イゴール・レヴィット(p))/ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調(王笑寒/ワン・シャオハン(p))~ヘルムート・ミュラー=ブリュール/ケルン室内管弦楽団(2007年ライヴ)・・・ Helmut Mu"ller-Bru"hl (1939-2012独逸)が(録音当時)期待の若手5人を集めた全集録音より。ケルン室内管弦楽団は1923年創設の室内オーケストラの老舗、モダーン楽器使用。小編成、管楽器が際立ってややオン・マイクに直接音中心、奥行きが足りないな音質はリアルでした。
Beethoven ピアノ協奏曲第1番ハ長調(イゴール・レヴィット(p))/ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調(王笑寒/ワン・シャオハン(p))~ヘルムート・ミュラー=ブリュール/ケルン室内管弦楽団(2007年ライヴ)・・・ Helmut Mu"ller-Bru"hl (1939-2012独逸)が(録音当時)期待の若手5人を集めた全集録音より。ケルン室内管弦楽団は1923年創設の室内オーケストラの老舗、モダーン楽器使用。小編成、管楽器が際立ってややオン・マイクに直接音中心、奥行きが足りないな音質はリアルでした。
Igor Levit(1987-露西亜→独逸)による青春躍動する晴れやかなハ長調協奏曲。陰影や微細なニュアンスより、愉悦に充ちた明晰なタッチは力強いアクセント刻んで、逡巡のない若く元気な躍動と大胆な勢いたっぷり。当時20歳、若手にありがちの細身な神経質を感じさせない。
第1楽章「Allegro con brio」(14:30)第2楽章「Largo」(11:13)第3楽章「Rondo: Allegro」このフィナーレはとくに快速にノリノリ、華やかな勢いと熱気を感じさせました。(8:45)
Xiaohan Wang(1980-中国)は現在天津ジュリアード音楽院の先生を務めているとのこと。録音当時は27歳。変ロ長調協奏曲はたしか、こちらのほうが成立が早かった作品のはず。
第1楽章「Allegro con brio」は屈託のないシンプルに明るいエネルギーを感じさせる始まり。こちらも若い勢いたっぷり、元気闊達なピアノ。ちょっぴり硬質なタッチに、カデンツァは思いっきり華やかでした。(14:13)第2楽章「Adagio」緩徐楽章も硬質にかっちりとした明晰なタッチは変わらない。ちょっと力みが目立つかも。(8:41)第3楽章「Rondo: Allegro molto」最終楽章に至って表現の単調さ、陰影の不足にちょっと力みが気になりました。(5:54)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日土曜はは終日曇り。前々日睡眠不如意だったので、昼しっかり運動して前夜は早々に就寝したのに、またまた途中覚醒。どうも睡眠不如意が続きます。これは昼寝で埋めましょう。ストレッチとYouTubeエアロビクスはいつもどおり。膝腰の不調は比較的マシ。前日、孫の参観に出掛け、そのまま婆さんのところに寄った女房殿は結果的に泊まって、朝一番に帰ってきました。珈琲フレッシュやパンが切れて買い物に出掛けるか逡巡してグズグズして、結局引き隠りました。Brahmsの交響曲辺り、著名だけれどどうしても自分が納得できない音源ファイルを点検かなり廃棄しました。今朝の体重は67.9kg+250gこりゃあかんな。
べこもち、知ってますか?もしかして北海道特有のお菓子?母親がよく作ってくれて、黒糖の部分が嬉しかった。もう数十年喰っていないけれど、某ブログにお店で買ったものが写真に出現、特別に求めて喰いたいとも思わないけれど、優しい甘さを懐かしく思い出しました。そのブログには
「その昔、何のために存在するのだろうと思ったお菓子も、今になると存在意義が分かってくる 」
Wikiに調べてみたら、東北北海道(道南地域 /両親は道南の出身)端午の節句に食される木の葉状の和菓子とのこと。記憶では一年中喰っていたような?行事食とは知りませんでした。この先、東北旅行は行ってみたいので、その時に探してみましょう。
夜は女子バレー対塞爾維戦を楽しみしていたけれど、朝一番に3-0完勝ぶりはネット情報より知っておりました。塞爾維もベストメンバーじゃないと思うけれど、やはり高い。サーブが凄い、ディフェンスが鉄壁、そして和田絶好調。小さなリベロ小島満菜美(LOVBソルトレイク)に痺れました。
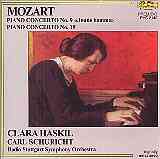 Mozart ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調K.271「ジュノーム」(1952年ライヴ)/ピアノ協奏曲第19番ヘ長調K.459(1956年ライヴ)~クララ・ハスキル(p)/カール・シューリヒト/シュトゥットガルト放送交響楽団・・・懐かしくも2008年来の再聴。CD時代の印象と変わらず、モノラルだけど音質はそう悪くない。Mozartに駄作なしを大前提に、その中でもピアノ協奏曲は大のお気に入り、Clara Haskil(1895-1960羅馬尼亜)のMozartは絶品ですよ。しっかり芯を感じさせる力感、気品のあるピアノに幾度感銘を受けて、少々の音質不備を忘れさせる最高の演奏。この度Carl Schuricht(1880-1967独逸)のSWR音源より録音情報を確認できました。
Mozart ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調K.271「ジュノーム」(1952年ライヴ)/ピアノ協奏曲第19番ヘ長調K.459(1956年ライヴ)~クララ・ハスキル(p)/カール・シューリヒト/シュトゥットガルト放送交響楽団・・・懐かしくも2008年来の再聴。CD時代の印象と変わらず、モノラルだけど音質はそう悪くない。Mozartに駄作なしを大前提に、その中でもピアノ協奏曲は大のお気に入り、Clara Haskil(1895-1960羅馬尼亜)のMozartは絶品ですよ。しっかり芯を感じさせる力感、気品のあるピアノに幾度感銘を受けて、少々の音質不備を忘れさせる最高の演奏。この度Carl Schuricht(1880-1967独逸)のSWR音源より録音情報を確認できました。
「ジュノーム」は第1楽章「Allegro」いきなりのオーケストラの呼びかけに、ピアノが呼応する革新的な始まり。本編に入ると粒立ちのしっかりとしたピアノが華やかに歌って、清涼な熱気に疾走します。(10:09)
第2楽章「Allegretto」は深い哀しみに沈んで名残惜しいハ短調の緩徐楽章(10:44)
第3楽章「Allegro assai」快速にころころ流れるようなフィナーレの始まり。シューリヒトのバックもピアノに呼応して爽やかな熱気を加え、途中リズムを変えてCantabileが落ち着いて歌う対比もしみじみ名曲。(9:34)
軽快なリズム躍動するヘ長調協奏曲K.459は、伴奏にティンパニとトランペットはないけど、作品目録には存在して、それを加えた録音も存在するとのこと。ぜひ聴いてみたい。
第1楽章「Allegro」は軽妙かつしっかりとしたタッチのピアノが符点のリズムに、ウキウキするような快速な始まり。このノリと熱気がライヴならでの感興でした。(12:05)
第2楽章「Andantino」6/8拍子。陰影豊かなピアノと伴奏の呼び交わしがしみじみ美しく、淡々と懐かしい緩徐楽章。(8:03)
第3楽章「Rondo: Presto」快速にデリケートな躍動と疾走が続くフィナーレ。浮き立つような軽みと勢いに溢れたピアノとオーケストラ。(7:10/拍手なし)
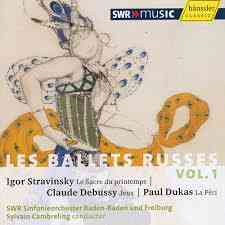 Stravinsky バレエ音楽「春の祭典」/Debussy 舞踊詩「遊戯」(2006年)/Ducas 舞踏詩「ラ・ペリ」(2004年)~シルヴァン・カンブルラン/バーデンバーデン南西ドイツ放送交響楽団・・・まず音質極上。20世紀の古典「春の祭典」は打楽器の低音を強調させたデフォルメに非ず、どのパートもクリアに浮き立ってわかりやすい。クールなギーレン時代を継いでSylvain Cambreling(1948-仏蘭西)のアンサンブルは精緻に、硬派な南西ドイツ放送交響楽団は色彩豊かに各舞曲を描き分けて精緻なニュアンスたっぷり、メリハリもリズム迫力もしっかりして、土俗的な粗さや響きの濁り皆無の演奏でした。大好きな作品を堪能いたしました。
Stravinsky バレエ音楽「春の祭典」/Debussy 舞踊詩「遊戯」(2006年)/Ducas 舞踏詩「ラ・ペリ」(2004年)~シルヴァン・カンブルラン/バーデンバーデン南西ドイツ放送交響楽団・・・まず音質極上。20世紀の古典「春の祭典」は打楽器の低音を強調させたデフォルメに非ず、どのパートもクリアに浮き立ってわかりやすい。クールなギーレン時代を継いでSylvain Cambreling(1948-仏蘭西)のアンサンブルは精緻に、硬派な南西ドイツ放送交響楽団は色彩豊かに各舞曲を描き分けて精緻なニュアンスたっぷり、メリハリもリズム迫力もしっかりして、土俗的な粗さや響きの濁り皆無の演奏でした。大好きな作品を堪能いたしました。
Part One Introduction(3:32)The Augurs of Spring(3:34)Game of Abduction(1:24) Spring Round Dances(3:54)Games of the Rival Tribes(2:03)Procession of the Sage(0:47)The Sage(0:27)Dance of the Earth(1:14)
Part Two Introduction(4:59)Mystical Circles of the Young Girls(3:35)Glorification of the Chosen One(1:33)Evocation of the Ancestors(0:45)Ritual of the Ancestors(4:04)Sacrifical Dance (The Chosen One)(4:41)
「Jeux」は四管編成、1919年ピエール・モントゥーにより初演。掴みどころのない、自在なバレエ音楽は、わかりやすい緻密デリケートに洗練された演奏でした。(18:57)
「La Peri」は知名度は低いけれど、これも名曲。古代ペルシアを題材に取った作品とのこと。「fanfare to the ballet」の祝祭的なファンファーレは希望に充ちた響き(2:46)「Poeme dance」オリエンタルに妖しい旋律は静謐に、やがて華やかに高揚する熟達した管弦楽技法、それは精密に表現されております。(19:01)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
週末は好天、来週より雨が続くようです。前日昼酒を呑んで夕方5時には帰宅、フロに入って夜10時迄しっかり女子バレーボール対阿蘭陀戦を堪能して就寝したのに、不快な気分に12時過ぎに目覚めて小一時間ネットなど眺めてから二度寝、朝いつもの時間に目覚めたら体調は改善しておりました。ネットからの音源入手(失っていた某歴史的音源を発見!)や大量の洗濯など時間配分をちょっと誤ったのでストレッチお休み、短いYouTube体操を済ませてから市立体育館へ出掛けました。トレーニングルームは常連メンバー+若いカップルも参加しておりました。順に全身ゆる筋トレ+エアロバイク15分済ませて、シャワーを使って気分爽快。血圧は前夜の酒の影響か+10も仕方がない。今朝の体重は67.65kg。運動して食事抑制してもほとんど変わらない。今朝も眠りが浅い自覚有。
女房殿は朝一番に下の孫の保育園参観日に出掛けました。
お仕事引退以来ここ3年以上クルマを運転していないし、これからも運転予定はなし。そんな生活に馴染んだので、来年2026年運転免許切り替えとともに返上予定をしております。少々前だけれど、東北地方の高速道路にてご高齢運転者の突然路上停止。エンストらしいけど、ハザードランプもなし、路肩に寄せるでもなし、ドアを開けて後部確認をしたあとに路肩に寄せた動画がニュースに出ておりました。後続車はなんとか衝突回避できたけれど、それが危うい行為であることを認識できないドライバーは免許は返上すべきでしょう。ブレーキとアクセルを間違えた、バックを入れ間違えた、そんな事故はほとんど日常茶飯事、自分はもう正常な運転反応が出来ない~そんなことも既に自覚できないのでしょう。
自分は未だ大丈夫と思うけれど、自己認識がOKなうちに潔く退く、というのが肝要かと。
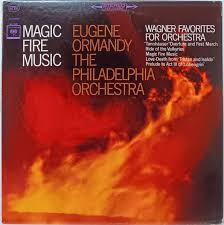 Wagner 歌劇「タンホイザー」より「入場行進曲」/歌劇「ローエングリン」より歳3幕への前奏曲/楽劇「ワルキューレ」より「魔法の火の音楽」/歌劇「タンホイザー」序曲/楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死/楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲~ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団(1963-4年)・・・歌劇場経験のないEugene Ormandy(1899-1985洪牙利→亜米利加)によるWagner管弦楽名曲集録音は1959年に続くもの。数曲似たような演目がダブって、微妙に趣向は違います。優秀録音。ゴージャスな厚みを誇る瑞々しいサウンド、ケレン味のないストレートかつオーソドックス、余裕の技巧に明晰な表現はほとんど耳へのご馳走。硬派Wagner愛好家には亜米利加のWagnerなんて!明る過ぎ華やか過ぎ、陰影に乏しい、軽いんじゃないか(精神性に欠ける?)そんなご批判もありそうだけど、誰でも知っている旋律揃えてわかりやすく、楽しいこと限りなし。Wagnerの勇壮かつ官能的雰囲気たっぷりな旋律に目覚めた、こども時代の感銘が蘇りました。締め括りの「マイスタージンガー」全曲の壮麗なこと!(6:56-3:30-7:06-5:04-14:53-16:34-10:05)
Wagner 歌劇「タンホイザー」より「入場行進曲」/歌劇「ローエングリン」より歳3幕への前奏曲/楽劇「ワルキューレ」より「魔法の火の音楽」/歌劇「タンホイザー」序曲/楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死/楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲~ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団(1963-4年)・・・歌劇場経験のないEugene Ormandy(1899-1985洪牙利→亜米利加)によるWagner管弦楽名曲集録音は1959年に続くもの。数曲似たような演目がダブって、微妙に趣向は違います。優秀録音。ゴージャスな厚みを誇る瑞々しいサウンド、ケレン味のないストレートかつオーソドックス、余裕の技巧に明晰な表現はほとんど耳へのご馳走。硬派Wagner愛好家には亜米利加のWagnerなんて!明る過ぎ華やか過ぎ、陰影に乏しい、軽いんじゃないか(精神性に欠ける?)そんなご批判もありそうだけど、誰でも知っている旋律揃えてわかりやすく、楽しいこと限りなし。Wagnerの勇壮かつ官能的雰囲気たっぷりな旋律に目覚めた、こども時代の感銘が蘇りました。締め括りの「マイスタージンガー」全曲の壮麗なこと!(6:56-3:30-7:06-5:04-14:53-16:34-10:05)
 Sibelius 「カレリア」組曲/組曲「レンミンカイネン」(カレワラによる四つの伝説)~オッコ・カム/ヘルシンキ放送交響楽団(1975年)・・・Okko Kamu(1946-芬蘭土)は1969年カラヤン・コンクールに優勝して、世界的に活躍しているけれど、意外とレパートリーも活動の幅も広げていないように見えます。ヘルシンキ放送交響楽団とはフィランド放送交響楽団のこと?1971-1977年首席在任、その辺り未だ20歳代の録音でしょう。金管の響きは細身、アンサンブルは整って涼やかな響きはSibeliusに似合っていると感じます。音質はまずまず。
Sibelius 「カレリア」組曲/組曲「レンミンカイネン」(カレワラによる四つの伝説)~オッコ・カム/ヘルシンキ放送交響楽団(1975年)・・・Okko Kamu(1946-芬蘭土)は1969年カラヤン・コンクールに優勝して、世界的に活躍しているけれど、意外とレパートリーも活動の幅も広げていないように見えます。ヘルシンキ放送交響楽団とはフィランド放送交響楽団のこと?1971-1977年首席在任、その辺り未だ20歳代の録音でしょう。金管の響きは細身、アンサンブルは整って涼やかな響きはSibeliusに似合っていると感じます。音質はまずまず。
Karelia Suite, Op. 11は牧歌的に親しみやすい、懐かしい旋律連続。古典的二管編成+5種の打楽器は効果的。もともとは劇音楽だったらしい。
「Intermezzo (Moderato)」は遠いホルンからノンビリとしたリズムを刻んで、静かに落ち着いたホルンに収束。(4:00)
「Ballade (Tempo di menuetto) 」は寂しい木管から、泣けるようにしみじみとした弦がたっぷり歌う美しいところ。(7:14)
「Alla marcia (Moderato)」は弾むようにスキップして明るく、うきうき希望に充ちた歩みは幸福感いっぱいでした。(4:12)
Four Legends from the Kalevala, Op. 22はかつて経験したこともない熱血演奏でした。基本は二管編成だけど、微妙に各曲違うそう。名曲と思うけれど「トゥオネラの白鳥」以外はまとめての演奏機会は少ないように感じます。
「Lemminkainen and the Maidens of the Island(レンミンカイネンと島の乙女たち)」色(クズ)男レンミンカイネンは島の乙女たちにモテモテ。島中の娘達と関係を持ったけれど狙いのキュッリッキにだけは見向きもされず、ムリヤリさらって必死に口説いて条件付きで結婚を受け入れる~そんな筋なんだそう。爽やかな木管の躍動、朗々とした弦が歌って劇的雄弁、魅惑の旋律が続きました。ラストの金管とそれに応える木管がカッコ良い!(15:24)
「Lemminkainen in Tuonela(トゥオネラのレンミンカイネン)」Wikiでは第3曲に配置されていて、筋書き的にはそちらが正しい。トゥオネラの白鳥を狙うレンミンカイネンは、宿敵の羊飼い「濡れ帽子」に襲われて生命を落とす場面。不安げな弦と木管の細かい音型から始まって、悲劇的な金管が叫びます。この辺り不穏な木管と金管の絡み合いの雰囲気最高、ちょっと細身の金管が旋律風情によく似合います。(15:05)
著名な「The Swan of Tuonela(トゥオネラの白鳥)」ここはフルートなし。色(クズ)男レンミンカイネンは妻キュッリッキが約束を破ったとして激怒、新しい妻を求めるべくポヒョラに向かって老婆から娘を娶る条件のひとつに、三途の川に浮かぶ白鳥を一矢で射ることを提示される・・・その静謐な白鳥の情景をイングリッシュ・ホルンがしみじみ歌う絶品の名曲。(8:23)
「Lemminkainen’s Return(レンミンカイネンの帰郷)」レンミンカイネンの母がばらばらになった息子を蘇生させる場面。色(クズ)男レンミンカイネンは生き返ってもポヒョラの娘に執着するド・スケベ野郎、母親に諭されて泣く泣く諦める~ここはフルートならぬピッコロ二本の編成。颯爽とした推進力に緊張感を以て疾走する始まり。木管の細かい音型を刻む見事なアンサンブルに締め括りました。(6:08)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日梅雨前線は南に下がって、全国的好天だったとのこと。本日も連続にて佳き天気、週末に向けて崩れていくそう。朝一番に洗濯は気分爽快に外干し、女房殿も布団を干して掃除も済ませました。ストレッチ、YouTubeエアロビクスは高齢者向けユルいのを実施、なにごともムリせず継続が大切でしょう。昨日思うように体重は減らずがっかり、昼食を抑制して爺友との昼酒に出掛けました。コミュニティバスを一本遅らせてぎりぎりかちょうどの時間にJR北新地駅に到着狙い、性格的に遅刻はイヤなのでいつも30分ほど余裕をみていたけれど、ものは試し、ぴったり約束の時間に到着できました。珍しく含蓄深い話を訊けました。今朝の体重は67.8kg+150gこれは自業自得。
夜は既に結果がわかっているネーションズリーグ第1戦はキャプテン石川(イゴール・ゴルゴンゾーラ・ノヴァーラ)率いる女子は対阿蘭陀戦3ー0ストレート勝ち、お相手はエース不在とは云え高いですよ。それをものともせずセッターは関菜々巳(UYBAブスト・アルシーツィオ)和田由紀子/佐藤淑乃(レッドロケッツ)を応援しているので彼女らの大活躍に興奮しました。サーブが凄い!得意のディグも当たり前に拾って、宮部のブロックにも惚れ惚れ。ラストは若手・秋本美空(18歳)を起用して活躍させる余裕もありました。たしか阿蘭陀にはサービス・エースはなかったんじゃないか。
SVリーグは男子が圧倒的人気、女子も盛り上がってほしい。次の塞爾維戦は強敵です。
自分にとって万博は税金の無駄遣い、カジノのへの道と考えるけれど、それなりの人出に賑わって、来場者は愉しんでいらっしゃることも承知しております。そのことに横からちゃちゃ入れるつもりもありません。バルト館入口のミャクミャクぬいぐるみが盗まれて、その様子は防犯カメラに写っておりました。犯人は誰か知らんけどそれは情けない行為、その知らせを訊いた来場者が続々と「返還祈願」とミャクミャクグッズを寄付したそう。それは素晴らしい情景、日本人の心意気に感銘を受けました。(来場できなかった全国の方にプレゼントするとのこと)
持っていってしまった御本人も胸を痛めてくださるでしょうか。日本人の方なのか、そうじゃないのか。
 Mozart セレナード第9番ニ長調「ポストホルン」 K.320~フェルディナント・ライトナー/バイエルン放送交響楽団(1956年)・・・ザルツブルグ時代の作品は古典的二管編成+ティンパニ。第6楽章「Menuetto」にはポストホルンが登場します。Ferdinand Leitner(1912-1996独逸)による録音は、ぎりぎりステレオに間に合っていないけれど、これはバイエルン放送交響楽団の暖かくてノンビリ、ちょっぴりローカルなサウンドがステキな味わい深い演奏でした。音質には芯は感じられるけれどやや曇りがち、この時期ぎりぎりステレオに間に合っておりません。聴き進めるとそれはあまり気にならない。
Mozart セレナード第9番ニ長調「ポストホルン」 K.320~フェルディナント・ライトナー/バイエルン放送交響楽団(1956年)・・・ザルツブルグ時代の作品は古典的二管編成+ティンパニ。第6楽章「Menuetto」にはポストホルンが登場します。Ferdinand Leitner(1912-1996独逸)による録音は、ぎりぎりステレオに間に合っていないけれど、これはバイエルン放送交響楽団の暖かくてノンビリ、ちょっぴりローカルなサウンドがステキな味わい深い演奏でした。音質には芯は感じられるけれどやや曇りがち、この時期ぎりぎりステレオに間に合っておりません。聴き進めるとそれはあまり気にならない。
第1楽章「Adagio maestoso: Allegro con spirito」晴れやかな表情に颯爽と力強い、決然と前向きな始まり。途中暗転もいかにもいつものMozart。(7:56)
第2楽章「Menuetto: Allegretto」3/4拍子によるリズムをしっかり刻む大柄なメヌエット。トリオのフルートとファゴットのシンプルな旋律はいかにも牧歌的でした。(4:16)
第3楽章「Concertante: Andante grazioso」淡々とフルート、オーボエ、ファゴットによる「Concertante」。魅惑の木管がしみじみ懐かしく、名残惜しく、のびのびと歌い交わしております。(8:06)
第4楽章「Rondeau: Allegro ma non troppo」前楽章の木管の対話(フルートとオーボエ)がそのままテンポ・アップしてウキウキ増し増し、優雅に爽やかな表情が続きます。(5:30)
第5楽章「Andantino」優雅な緩徐楽章。晴れやかな木管のオブリガートもステキだけれど、ここでの主役は陰影豊かな弦でした。この楽章は鎮静度が深い。(6:34)
第6楽章「Menuetto」屈託のない元気よろしい3/4拍子。ここに待ってました!(ド・ミ・ソの自然倍音だけの/Wikiによる)朗々たるポストホルン登場。(Karl Benzinger)(5:04)
第7楽章「Finale: Presto」一気呵成快速のフィナーレは全曲の締め括りに相応しい推進力でした。(3:55)
 Tchaikovsky 交響曲第5番ホ短調~ヘルベルト・カラヤン/ベルリン・フィル(1975年)・・・例の如く憂いを含んだ甘い旋律溢れる名曲中の名曲は三管編成+ティンパニ。2016年来の再聴。当時曰く
Tchaikovsky 交響曲第5番ホ短調~ヘルベルト・カラヤン/ベルリン・フィル(1975年)・・・例の如く憂いを含んだ甘い旋律溢れる名曲中の名曲は三管編成+ティンパニ。2016年来の再聴。当時曰く
語り口が圧倒的に上手い!流麗であり、微妙なニュアンス、絶妙な間、甘い歌・・・オーケストラの技量も絶品!常に余力を残して、各パートの自発的な歌に溢れ、自分の出番にはしっかり自己主張しておみごと・・・耳あたりの良い美しいサウンド
なるほどなぁ、茫洋として作為のない音質。そして常に静謐を感じさせるスケール。露西亜系の演奏を聴き慣れていたためか、金管があまり際立たないように思えます。
第1楽章「Andante - Allegro con anima」から常に八分の力の入れ方に余裕、ぎらぎらとした爆発的表現皆無。全編を支配する「運命の主題」は悠々と決然、重量感たっぷりに慌てぬ、落ち着いた歩み。(15:40)
第2楽章「Andante cantabile con alcuna licenza」茫洋としたホルン・ソロも独墺系の素直な響きに陰影が深い。弦は痺れるようにセクシー、それに応える木管の音色もスムースそのもの。ここは官能と陶酔に充ちたデリケートな語り口最高、テンポの僅かな揺れも効果的でした。(14:31)
第3楽章「Valse: Allegro moderato」そっと囁くようなワルツが粛々と踊ります。ちょっと憧憬とか前向きな勢いに不足を感じるほど、抜いたようにマイルドなところ。(6:32)
第4楽章「Finale: Andante maestoso - Allegro vivace」「運命の主題」もい神妙な、というか達観して肩の力抜けた始まり。やがてテンポ・アップしてそれは重量級の重心の低さに進撃にも常に余裕を感じさせて「運命の主題」のファンファーレも声高には叫んでおりません。じわじわと押し寄せる圧巻のオーケストラの威力だけど若々しい精一杯の若々しさはもっと欲しくなるところ。(12:24)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日夜には雨は上がって、天気はからりと晴れました。左膝の調子はまずまず、ほとんどストレッチの可動域に問題なし、YouTubeは手抜きして3分少々の短いもの実施して市立体育館に向かう途上・・・悪~い爺友から悪魔のLINE有、本日昼から酒の誘い、肝臓を労って抑制自粛しつつお付き合いしましょう。トレーニングルームは常連メンバーと若者(おそらく学生)数人、いつもどおりのマシントレーニング+エアロバイク15分消化して、帰り道スーパーに寄って野菜と魚を入手しました。3,000円台のコメは潤沢に棚にありました。体育館での血圧計測はちょっぴり落ち着いたけれど、今朝の体重は67.65kgほぼ変わらず。高め安定中。
この間のコメ対応は政府のマッチポンプという説もあって、以前の備蓄米放出はほとんど市場に出回らなかったとのこと。ほんまでしょうか。報道を伺うと、ウチのご近所だけではなく全国各地、ちょっと高いのは潤沢に出回りだしたとのこと。在庫はどこかにあったんでしょう。理屈で云うとこれから値下がっていくはず。粗悪米を買い占めた人が飛び込み営業というのはほんまですか?コロナ時期のマスクを連想させます。人々が困った状況に付け込む商売なんて、そんなもの長続きするはずがない。
2024年の出生数はとうとう70万人割れ、若い人たちが赤ちゃんを生み、育てにくい社会なのでしょうか。
総額247億円を上回る巨額の不正融資?いわき信用組合の報道を見て、今どきこんな悪質な企業が存在していることに驚き、それが20年以上続いていたんでしょ?信じられない。全社一丸となって代々不正を隠蔽していたらしいけど、ふつうどこからから漏れますよ、そんな噂は。そんな会社は日本全国あちこちあるのか、ないのか。地方経済に与える影響も甚大でしょう。真面目に働いていていた人もいたのか、見て見ぬふりをしていたのか、とても不快な事件でした。
 Grieg ピアノ協奏曲イ短調/Rachmaninov パガニーニの主題による狂詩曲~辻伸之(p)/ヴァシリー・ペトレンコ/ロイヤル・リヴァプール・フィル(2018年ライヴ)・・・大好きな作品連続。素晴らしい技巧、緻密な集中力、音質も良好。Amazonのレビューは絶賛一色!フィヨルドの氷壁が崩れ落ちる冒頭のティンパニに、決然としたピアノから始まる劇的浪漫は、爽やかにキレもあってわかりやすい、そして軽量なGrieg。
Grieg ピアノ協奏曲イ短調/Rachmaninov パガニーニの主題による狂詩曲~辻伸之(p)/ヴァシリー・ペトレンコ/ロイヤル・リヴァプール・フィル(2018年ライヴ)・・・大好きな作品連続。素晴らしい技巧、緻密な集中力、音質も良好。Amazonのレビューは絶賛一色!フィヨルドの氷壁が崩れ落ちる冒頭のティンパニに、決然としたピアノから始まる劇的浪漫は、爽やかにキレもあってわかりやすい、そして軽量なGrieg。
第1楽章「Allegro molto moderato」(12:58)第2楽章「Adagio」(6:15)第3楽章「Allegro moderato molto e marcato」(10:05)
濃厚甘美な露西亜風旋律がたっぷり歌うRachmaninov。いずれも細部微塵も忽(ゆるが)せにせぬ仕上げは入念、タッチは精密にかっちりとして曖昧さは感じられない・・・世評絶賛も納得・・・なんだけど、ヴァシリー・ペトレンコの伴奏含めどうも雑味が足りない。作品になにを求めるか、聴手の勝手な思い込みだけど、凄絶に叩きつけるような入れ込みや凄み、どんより漆黒の粘着性、そんなものはどこにも見当たらない軽快。ファンの方には叱られそうだけれど、若者の未来への成熟を期待しましょう。あまりビットレートの高い音源ではなかったので、自分の激安オーディオの責任かも知れません。
序奏「Allegro vivace」(0:08)第1変奏「Allegro vivace」(0:19)主題「L'istesso tempo」(0:19)第2変奏「L'istesso tempo」(0:19)第3変奏「L'istesso tempo」(0:26)第4変奏「Piu vivo」(0:31)第5変奏「Tempo precedente」(0:30)第6変奏「L'istesso tempo」(1:06)第7変奏「Meno mosso, a tempo moderato」(1:09)第8変奏 Tempo I(0:36)第9変奏「L'istesso tempo」(0:34)第10変奏「Poco marcato」(0:54)第11変奏「Moderato」(1:22)第12変奏「Tempo di minuetto」(1:21)第13変奏「Allegro」(0:36)第14変奏「L'istesso tempo」(0:34)第15変奏「Piu vivo scherzando」(0:54)第16変奏「Allegretto」(1:42)第17変奏「Allegretto」(2:19)第18変奏「Andante cantabile」(2:52)第19変奏「A tempo vivace」(0:34)第20変奏「Un poco piu vivo」(0:38)第21変奏「Un poco piu vivo」(0:27)第22変奏「Un poco piu vivo (Alla breve)」(1:45)第23変奏「L'istesso tempo」(0:54)第24変奏「A tempo un poco meno mosso」(1:24)
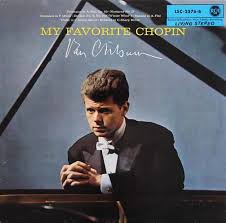 Chopin ポロネーズ 変イ長調 作品53「英雄」/夜想曲ロ長調 作品62-1/幻想曲ヘ短調 作品49/練習曲イ短調 作品25-11「木枯らし」/練習曲ホ長調 作品10-3/バラード第3番 変イ長調 作品47/ワルツ 嬰ハ短調 作品64-2/スケルツォ第3番 嬰ハ短調 作品39~ヴァン・クライバーン(p)(1961年)・・・Van Cliburn(1934-2013亜米利加)売れ過ぎて忙し過ぎて、燃え尽きてしまう前の瑞々しい記録。やがて録音は途絶えて逝去迄、過去の名声と余韻に生きたピアニストの貴重な記録。Chopinの名旋律集めて、強靭なテクニックに明るい音色、前のめりの勢いに流れず、スマートなキレ味に非ず、崩れ落ちるような怒涛の迫力でもない、ちょっと楽天的な味わい深さを堪能できる温かいタッチでした。
Chopin ポロネーズ 変イ長調 作品53「英雄」/夜想曲ロ長調 作品62-1/幻想曲ヘ短調 作品49/練習曲イ短調 作品25-11「木枯らし」/練習曲ホ長調 作品10-3/バラード第3番 変イ長調 作品47/ワルツ 嬰ハ短調 作品64-2/スケルツォ第3番 嬰ハ短調 作品39~ヴァン・クライバーン(p)(1961年)・・・Van Cliburn(1934-2013亜米利加)売れ過ぎて忙し過ぎて、燃え尽きてしまう前の瑞々しい記録。やがて録音は途絶えて逝去迄、過去の名声と余韻に生きたピアニストの貴重な記録。Chopinの名旋律集めて、強靭なテクニックに明るい音色、前のめりの勢いに流れず、スマートなキレ味に非ず、崩れ落ちるような怒涛の迫力でもない、ちょっと楽天的な味わい深さを堪能できる温かいタッチでした。
(7:01-7:08-12:13-3:31-4:48-7:28-3:21-7:17)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
昨日は終日雨。洗濯はもちろん室内干し。どこにも出掛けられません。ストレッチとほんの短い6分ほどのYouTube運動のみの結果は67.7kg+150g。
長嶋茂雄さん逝去(89歳)号外も出て話題騒然だけど、長く患っていらっしゃったし、申し訳ないけれど自分にとっては過去の方、充分な寿命、栄光の人生だったと感じます。昭和の名選手が引退後の生活に苦労する話題に心痛めて、例えば米田哲也さんとか、既にお亡くなりになったけれど村田兆治さんとか、哀しい状態でした。スポーツ選手一般にセカンド・キャリアは難しそう。フツウのサラリーマンでもタイヘンですから。
韓国大統領選は李在明さん当選確実。また日韓関係は微妙となる可能性もあります。
先日大学時代の先輩が東海地方から出てきて酔狂にも新大阪で呑んだときの話題。一年先輩同士結婚した親しい御夫婦は来年3月70歳迄働くとのこと、経理のスペシャリストらしくて、組織には欠くべからざる存在らしい。来春には名古屋に引退記念酒に出掛けましょう。奥様は岡山の人(息子の高校の先輩)残念お母様は数年前に亡くなって、お父様は認知症を患って介護施設へ、地元に妹がいるけれど時々名古屋から出掛けているらしい。
旦那のほうはは西尾の資産家みたいだけれど、先にお父さんが亡くなり、お母さんは認知症に至って介護施設へ、訪問しても息子の顔もわからないと嘆いておりましたっけ。身体も心臓も屈強!だったらしいけど、最近2025年4月にお亡くなりになったとのこと。92歳かな?十数年介護施設にお世話になって、かつて経営していた工場を畳んで更地に、アパートに建て替えて収入をその経費に充てていたらしい。ある朝、職員の方が部屋を覗いたら亡くなっていた~突然の安らかな逝去だったようで、先輩も笑顔で報告しておりました。
我が婆さんは95歳、足腰弱って身動きはなかなか難しいけれどボケもせず、通院に付き添った女房殿によると最新の血液検査や心電図は改善され、問題ないそう。娘婿(=ワシ)も負けてられん。
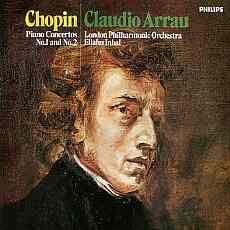 Chopin ピアノ協奏曲第1番ホ短調(1970年)/アンダンテ・スピアナートと華麗なるポロネーズ/「お手をどうぞ」による変奏曲(1972年)~クラウディオ・アラウ(p)/エリアフ・インバル/ロンドン・フィル・・・お気に入りの演奏なんやけど、ずいぶんと久々の拝聴。若きインバルの伴奏が始まったら記憶より音質はちょっと落ちる?半世紀以上前の録音。Claudio Arrau(1903-1991智利)の重心の低い、厚みのあるピアノはChopinとの相性とはちょっと違うような気もするけれど、じつはどれも絶品。
ピアノ協奏曲第1番ホ短調はまったり落ち着いて暖かく、タメが絶妙の味わいとなった微妙な揺れに、テクニックが前のめりに空回りしない。若者の登竜門作品だから拝聴機会は多くて、ちょっと食傷気味なくらいの名曲中の名曲は盤石の横綱相撲的愉悦に充ちて、これはヴェリ・ベスト。
Chopin ピアノ協奏曲第1番ホ短調(1970年)/アンダンテ・スピアナートと華麗なるポロネーズ/「お手をどうぞ」による変奏曲(1972年)~クラウディオ・アラウ(p)/エリアフ・インバル/ロンドン・フィル・・・お気に入りの演奏なんやけど、ずいぶんと久々の拝聴。若きインバルの伴奏が始まったら記憶より音質はちょっと落ちる?半世紀以上前の録音。Claudio Arrau(1903-1991智利)の重心の低い、厚みのあるピアノはChopinとの相性とはちょっと違うような気もするけれど、じつはどれも絶品。
ピアノ協奏曲第1番ホ短調はまったり落ち着いて暖かく、タメが絶妙の味わいとなった微妙な揺れに、テクニックが前のめりに空回りしない。若者の登竜門作品だから拝聴機会は多くて、ちょっと食傷気味なくらいの名曲中の名曲は盤石の横綱相撲的愉悦に充ちて、これはヴェリ・ベスト。
Allegro maestoso(20:53)Romanza: Larghetto(11:20)Rondo: Vivace(10:27)
Chopinでは一番好きな「アンダンテ・スピアナート」、後半に入る前の落ち着いた名残惜しさ絶品。「ポロネーズ」のリズムもたっぷり堂々と揺れて、味の濃い浪漫の味わい満載。これは管弦楽伴奏版でした。(15:24)
Mozart「ドン・ジョヴァンニ」の主題による変奏曲は序奏のデリケートな始まりから、堂々たるスケールの大きなソロが劇的な展開、やがて著名な「お手をどうぞ」の主題がリズミカルに登場、それが自在に賑やかに変奏されました。(19:26)インバルの伴奏はまずまず、音質云々は聴き進めるうちに気にならなくなりました。
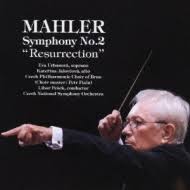 Mahler 交響曲第2番イ短調「復活」~リボル・ペシェク/チェコ・ナショナル交響楽団/ブルノ・チェコ・フィルハーモニック合唱団/エヴァ・ウルバノヴァ(s)/カテジーナ・ヤロフツォヴァ(a)(2010年)・・・少なくとも日本ではほとんど話題にならなかったLibor Pesek(1933-2022捷克)による交響曲全集録音より。21世紀は作曲者の予言通りMahlerの時代がやってきて、実演、録音とも百花繚乱、かつて贅沢品の極みだった全集録音も、幾種も日常拝聴可能となりました。四管編成+打楽器付きバンダ、もちろんハープ、そしてオルガン。二人の女声と混声合唱という壮大な規模、壮麗長大なる作品も演奏機会は多い人気作品となりました。1993年に創立されたオーケストラは2007-2019年ペシェクが常任を務めたそう、その時期に全集録音したのでしょう。
Mahler 交響曲第2番イ短調「復活」~リボル・ペシェク/チェコ・ナショナル交響楽団/ブルノ・チェコ・フィルハーモニック合唱団/エヴァ・ウルバノヴァ(s)/カテジーナ・ヤロフツォヴァ(a)(2010年)・・・少なくとも日本ではほとんど話題にならなかったLibor Pesek(1933-2022捷克)による交響曲全集録音より。21世紀は作曲者の予言通りMahlerの時代がやってきて、実演、録音とも百花繚乱、かつて贅沢品の極みだった全集録音も、幾種も日常拝聴可能となりました。四管編成+打楽器付きバンダ、もちろんハープ、そしてオルガン。二人の女声と混声合唱という壮大な規模、壮麗長大なる作品も演奏機会は多い人気作品となりました。1993年に創立されたオーケストラは2007-2019年ペシェクが常任を務めたそう、その時期に全集録音したのでしょう。
なんともオーケストラの響きが素朴と云うか、パワーと色気、華やかさと厚みに足らない。ずばりあまり上手いオーケストラではない感じ。それでも手堅いオーソドックスなバランスに、作品を堪能するには充分な誠実演奏、最終楽章「復活」に向けて精一杯の力演でした。
Allegro maestoso: Mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck(21:30)Andante moderato: Sehr gemachlich(9:27)In ruhig fliessender Bewegung (Scherzo)(10:41)Urlicht(4:52)Im Tempo des Scherzo(34:25)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
今朝はしとしと雨、夕方まで降り続くそう。
昨日月曜は予報通り晴れから曇り、雨は大丈夫でした。毎日同じ生活のリズム、ストレッチとYouTubeエアロビクス10分ほど消化して、いつもどおり市立体育館を目指しました。途中帰りの抜け道、美しからぬ疎水沿いには種々樹木が植えられて、自分も青梅を少々拾ったものです。ちゃんと摘花をしてないから粒は小さいけれど枇杷がけっこう色付いて、先日母子が収穫しておりましたっけ。トレーニングルームは常連メンバー数人お休みの代わり、若い人が数人、筋トレマシンは混んでいたけれど、なんとかいつもどおりのメニューを消化できました。今朝の体重は67.55kg▲500g、どうも眠りが浅い。夢見もあまりよろしくない。
備蓄米放出の威力はたいしたもの、 内閣支持率も上がったとのこと。朝のニュースによると備蓄米を買いたい、買いたくない世論調査は拮抗しているとのこと。これは「備蓄米放出があかん」とかいう意味でもないでしょう。なんせ「買いたくない人」が「買いたい人」を阻止行動するわけじゃないので。そういう「安ければ買いたい」階層が存在して、4割もいればそれはけっこうな需要ですよ。
小泉進次郎は人気があって、前の農水大臣が無為無策な~んもせんかったようだし、野村哲郎元農相 (81歳)は一連の動きを批判して老害の典型と話題となっているようですね。これが政府与党大多数の本音なんですかね。基本はムリムリな減反政策、硬直した農協組織の問題と思うけれど、地方の農家は多く現与党に投票しておりました。
別に声高に云々するつもりもないけれど、国民民主党は相次ぐ不倫議員とか不適切運営、比例区の候補選定を巡って不穏な空気、さらには「家畜の餌でしょ」発言が拍車を掛けたみたい。どうしても議員政党は当事者の人気や発言に頼りがち、先の総選挙時に「空気は一気に流れは変わるもの」と感じておりました。一喜一憂することもない。
東名高速道路の路側帯へと転落、こどもふたりを残して逃走した男は無免許、逮捕されたけれど、血縁者ではなかった?こどもの生命に別状がなかったのは良かったけど、ワケのわからん事件ですね。(逃げた男を匿った女のこどもだったらしい)なんかおかしな事件ばかり続きます。
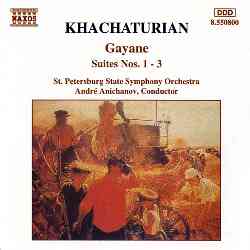 Khachaturian バレエ音楽「ガイーヌ」(組曲第1/2/3番)~アンドレイ・アニハーノフ/サンクトペテルブルグ交響楽団(1993年)・・・Andrey Anikhanov (1965-露西亜)によるお気に入りの作品録音。とっても不思議な組曲版連続には一番好きな「レズギンカ」や「バラの乙女たちの踊り」が入らない独自の配列でした。某レビューに「泣いてしまうくらい、素晴らしい演奏」とあって、その聴手はとってもシアワセ。残念、サンクトペテルブルグのニ番手オーケストラの粗野なパワーも嫌いじゃないけれど、オフ・マイクに妙な残響な音質加減か?いまいち乾いたサウンドに感じて、印象はやや散漫でした。泥臭くも魅惑の俗っぽい旋律はサウンドに芯が足りない、ちょっと腰が定まらぬ感じ。
Khachaturian バレエ音楽「ガイーヌ」(組曲第1/2/3番)~アンドレイ・アニハーノフ/サンクトペテルブルグ交響楽団(1993年)・・・Andrey Anikhanov (1965-露西亜)によるお気に入りの作品録音。とっても不思議な組曲版連続には一番好きな「レズギンカ」や「バラの乙女たちの踊り」が入らない独自の配列でした。某レビューに「泣いてしまうくらい、素晴らしい演奏」とあって、その聴手はとってもシアワセ。残念、サンクトペテルブルグのニ番手オーケストラの粗野なパワーも嫌いじゃないけれど、オフ・マイクに妙な残響な音質加減か?いまいち乾いたサウンドに感じて、印象はやや散漫でした。泥臭くも魅惑の俗っぽい旋律はサウンドに芯が足りない、ちょっと腰が定まらぬ感じ。
introduction(1:31)Gayane and Giko(2:51)Armen's Solo(3:44)Matsak and Armen(3:38)Gayane's Solo(3:35)/
Harvest Holiday(2:33)Dance of the Girls(2:31)Dance of the Boys(2:18)Choosing the Bride(3:04)Lullaby(5:16)Sabre Dance(2:27)/
The Hunt - Andante(5:01)Dance of the Comrades(1:50)Matsak's Solo(1:42)Gayane's Adagio(4:56)Solo - Love Duet(4:49)Finale(4:17)
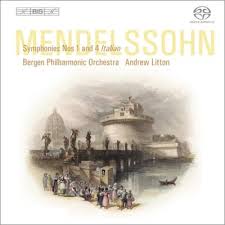 Mndelssohn 序曲「ルイ・ブラス」/交響曲第1番ハ短調/交響曲第4番イ長調「イタリア」~アンドルー・リットン/ベルゲン・フィル(2007年)・・・Andrew Litton(1959ー亜米利加)はベルゲン・フィル(諾威)首席在任2003-2015年。BISに意欲的な録音を続けました。どれも古典的二管編成+ティンパニ。金管はあまり目立たぬサウド。なんせ拝聴機会の少ない作曲家なので、演奏の善し悪し、好き嫌いなど基準を持っておりません。どれもジミめのサウンド、誠実に整ったアンサンブルはヴィヴィッドに軽妙、作品個性を堪能できました。音質もよろしい感じ。
Mndelssohn 序曲「ルイ・ブラス」/交響曲第1番ハ短調/交響曲第4番イ長調「イタリア」~アンドルー・リットン/ベルゲン・フィル(2007年)・・・Andrew Litton(1959ー亜米利加)はベルゲン・フィル(諾威)首席在任2003-2015年。BISに意欲的な録音を続けました。どれも古典的二管編成+ティンパニ。金管はあまり目立たぬサウド。なんせ拝聴機会の少ない作曲家なので、演奏の善し悪し、好き嫌いなど基準を持っておりません。どれもジミめのサウンド、誠実に整ったアンサンブルはヴィヴィッドに軽妙、作品個性を堪能できました。音質もよろしい感じ。
序曲「ルイ・ブラス」は劇音楽のための作品とのこと。荘厳な金管ファンファーレから始まって、これが途中幾度も効果的に繰り返されます。やがて弦が曰く有りげに登場して、明るく力強い歩みは劇性を加えます。(8:03)
交響曲第1番ハ短調は作曲者わずか15歳、その完成度はまさに天才の技。WeberやBeethoven、MozartやHaydnの影響顕著との作品説明、”疾風怒濤”風、なかなかの劇的作品でした。この作品はLPからCDに変更し始めた30年以上前、最初期に偶然入手していたため細部旋律は馴染みでした。(誰の演奏だったのかは失念)
第1楽章「Allegro di molto」悲劇的な力強い始まり。躍動するリズムに前向きな推進力もありました。(10:17)
第2楽章「Andante」は落ち着いた緩徐楽章。15歳の作品とは思えぬ優しく、憧憬に充ちたステキな旋律が続きます。(5:58)
第3楽章「Menuetto: Allegro molto」しっかりとしたリズムを刻むメヌエット。ここはMozartの交響曲第40番ト短調第3楽章「Menuetto」を連想させる緊張感。中間部は優雅に落ち着いた風情でした。(605)
第4楽章「Allegro con fuoco」快速に走りだす悲劇の始まり。やがて決然、力強くリズムを刻んで転調、疾走する弦と寂しげな木管の対比も効果的。ラストはガラリと雰囲気を変えて、明るいフィナーレでした。(8:06)
有名な「イタリア」は24歳の作品。
第1楽章「Allegro vivace」明るくリズミカルな勢いを感じさて陰影もある天衣無縫な始まり。快速テンポに軽みのあるサウンド。(10:02)
第2楽章「Andante con moto」哀愁漂うなかにも軽妙なリズムを感じさせる個性的な緩徐楽章。中間部の木管の音色が素朴でした。(5:51)
第3楽章「Con moto moderato」は弦による優雅に穏健なメヌエット風。中間部はホルンから木管が呼応して、ここも軽妙な明るさを失わぬところ。(6:42)
第4楽章「Saltarello: Presto」サルタレルロのリズミカルなリズムが支配する、緊張感漂うフィナーレも軽快ノリノリなリズムが続きました。(6:04)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
新しい一週間が始まって、天気は一日保ちそう。
昨日日曜は終日曇り、本日も似たような感じとのこと。女房殿は某集まり(ウクレレを始めたらしい)経由婆さん宅へ、自分はストレッチ+YouTubeのエアロビクスはお気に入りのシンプルな所作に動き続ける東南亜細亜系の女性によるもの。撮影が始まっているのに途中参入する人など、それはいつもパターン、そんなユルさも大好き。そのままマヨネーズやらニンニク(最近気に入っている)天然酵母食パンが切れていたので業務スーパーへウォーキング、ちょっと左膝が痛みます。1日分の運動量は確保したつもりだけど、今朝の体重は68.05kg+550g。また仕切り直しです。
どうでも良いご近所の動静。我が家のすぐ近くというか真ん前にある地域の憩い(?)スナック「マリー」は週に3-4日夜8時開店、一度も行ったことも(行きたいと思ったことも)ないけれど、一度夜その前を通り掛かったら、嬉しそうに爺さんが階段を上って行く姿を目撃したものです。昨日、前を通ったら貼り紙有「体調不良のためしばらく休業させていただきます」とのこと。想像の世界だけどママは70歳辺り?通っていた爺は残念やろなぁ、自分は関係ないけど。
すぐ前の駐車場にカーシェアが1台分あって、おそらく稼働率が高いのでしょう。この度二台に増えておりました。自家用車はイニシャル・コストのみならず維持費経費はけっこう掛かって、この物価高にちょっと贅沢品に感じます。小さいこどもの送り迎えとかお仕事とか必需品だったら仕方がないけど、ある資料では自動車の稼働率は20%くらいとのこと。週末しか使わないとか、時々必要になるのだったらカーシェアが有意義にムダのない仕組みと感じます。我が家にはもう自家用車はありません。
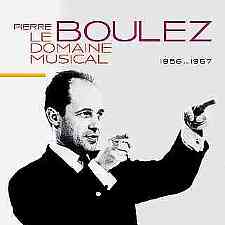 Stravinsky 12の器楽のためのコンチェルティーノ(弦楽四重奏のためのコンチェルティーノからの編曲/1920/1952/ピエール・ブーレーズ/ジャック・パレナン(v)/ピエール・ペナスウ(vc)/ジャック・カスタニエ(fl)/クロード・メゾンヌーヴ(ob)/ポール・タイユフェール(eh)/ギー・ドプリュ(cl)/アンドレ・ラボット、ジャン=ピエール・ラロック(fg)/ピエール・ポリン、ジャック・ルコワントル(tp)/ルネ・ピエール・アラン、モーリス・スザン(tb)) /クラリネット・ソロのための三つの小品(1919/ギー・ドプリュ(cl))/弦楽四重奏のための三つの小品(1914/パレナン弦楽四重奏団/ジャック・パレナン(v)/ジャック・ゲステム(v)/ミシェル・ワレス(va)/ピエール・ペナソウ(vc))/管楽器のためのサンフォニー(1920/version 1947/ピエール・ブーレーズ/ドメーヌ・ミュージカル管弦楽団)/バレエ音楽「ルナール」(狐、歌われ演じられる滑稽な物語/1915-16/ピエール・ブーレーズ/ドメーヌ・ミュージカル管弦楽団/ジャン・ジロドー、ルイス・デヴォス(t)/ルイ=ジャック・ロンデルー(br/グザヴィエ・ドゥプラ(b)/エメール・キシュ(ツィンバロン))/アゴン(12人のためのバレエ/1953-57/ハンス・ロスバウト/バーデンバーデン南西ドイツ放送交響楽団)・・・60-70年を経て現在でも前衛音楽。これはPierre Boulez(1925-2016仏蘭西)が率いたDomaine Musical(パリ)1956-1965年の記録より。自分が比較的馴染んでいるStravinskyの作品を聴きました。詳細録音年情報はわからないけれど、1960年前後の記録はどれも音質良好。
Stravinsky 12の器楽のためのコンチェルティーノ(弦楽四重奏のためのコンチェルティーノからの編曲/1920/1952/ピエール・ブーレーズ/ジャック・パレナン(v)/ピエール・ペナスウ(vc)/ジャック・カスタニエ(fl)/クロード・メゾンヌーヴ(ob)/ポール・タイユフェール(eh)/ギー・ドプリュ(cl)/アンドレ・ラボット、ジャン=ピエール・ラロック(fg)/ピエール・ポリン、ジャック・ルコワントル(tp)/ルネ・ピエール・アラン、モーリス・スザン(tb)) /クラリネット・ソロのための三つの小品(1919/ギー・ドプリュ(cl))/弦楽四重奏のための三つの小品(1914/パレナン弦楽四重奏団/ジャック・パレナン(v)/ジャック・ゲステム(v)/ミシェル・ワレス(va)/ピエール・ペナソウ(vc))/管楽器のためのサンフォニー(1920/version 1947/ピエール・ブーレーズ/ドメーヌ・ミュージカル管弦楽団)/バレエ音楽「ルナール」(狐、歌われ演じられる滑稽な物語/1915-16/ピエール・ブーレーズ/ドメーヌ・ミュージカル管弦楽団/ジャン・ジロドー、ルイス・デヴォス(t)/ルイ=ジャック・ロンデルー(br/グザヴィエ・ドゥプラ(b)/エメール・キシュ(ツィンバロン))/アゴン(12人のためのバレエ/1953-57/ハンス・ロスバウト/バーデンバーデン南西ドイツ放送交響楽団)・・・60-70年を経て現在でも前衛音楽。これはPierre Boulez(1925-2016仏蘭西)が率いたDomaine Musical(パリ)1956-1965年の記録より。自分が比較的馴染んでいるStravinskyの作品を聴きました。詳細録音年情報はわからないけれど、1960年前後の記録はどれも音質良好。
「12の器楽のためのコンチェルティーノ」は心が浮き立つような快活な緊張感を湛えて、仏蘭西管の名手たちによる色彩の饗宴(5:45)「クラリネット・ソロ」は低音がよく響く寡黙から始まって、躍動する高音、ラストはノリノリのジャズ風でした。(1:47-1:04-1:14)「三つの小品」はギクシャクした土俗的なリズムと和声、不協和音と途切れ途切れ自在なやり取りが続いて、やがて絶望的に暗い囁くようなアンサンブルに終了(0:56-1:54-3:31)「管楽器のためのサンフォニー」は最近は演奏会にも取り上げられる。素っ頓狂かつ色彩的、荘厳な管楽アンサンブル。初演は大失敗したそうだけど、これは大好きな作品でした。(8:33)
「ルナール(Renard )」は仏蘭西語が理解できないけれど、すこぶるヴィヴィッドにパワフルかつユーモラスな緊張感を湛えた名曲。声楽男声4人+管弦楽は弦も含めて各一人(ホルンは2本)打楽器と妖しいツィンバロンが入ります。1922年初演は失敗だったとのこと、言葉の響き含めて、すこぶるオモロい作品でした。(15:01)
バレエ音楽「アゴン」は(1957年これと同じもの?驚くほど良好なステレオ録音)ドデカフォニーの難解晦渋な作品だけど1957年初演(ロバート・クラフト/ニューヨーク・シティ・バレエ)は大成功だったとのこと。三管編成+4種の打楽器+マンドリン、ピアノ、ハープ。これもアルカイックな風情が大好きでした。同時代音楽の擁護者Hans Rosbaud(1895-1962墺太利)はクールかつ緻密、緊張感を湛えた統率はおみごと。
Pas-de-Quatre(1:35)Double Pas-de-Quatre(1:27)Triple Pas-de-Quatre(0:59)Prelude(0:50)First Pas-de-Trois : Saraband-Step(1:14)Gaillarde(1:12)Coda(1:16)Interlude(0:49)Second Pas-de-Trois(0:56)Bransle Gay(0:51)Bransle Double(1:20)Interlude(0:50)Pas-de-Deux- Coda(5:37)Four Duos(0:35)Four Trios - Coda(2:21)
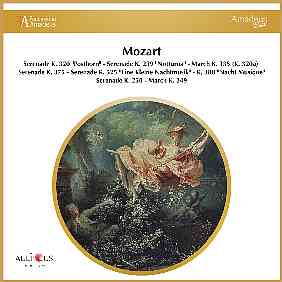 Mozart 行進曲ニ長調K.335(320a)/セレナーデ第9番ニ長調K.320「ポストホルン」/セレナード第6番ニ長調K.239「セレナータ・ノットゥルナ」~カルロ・デ・マルティーニ/アカデミア・リッタ(Accademia Litta)(2005年)・・・伊太利亜AmadeusレーベルからMozartのセレナーデCD6枚分の録音をネットより入手したけれど、諸情報をあちこち探るのに苦労いたしました。Carlo De Martiniが自ら創設した古楽器アンサンブル、彼の情報もなかなか出現しません。著名なIl Giardino Armonicoのメンバーだったらしい。
Mozart 行進曲ニ長調K.335(320a)/セレナーデ第9番ニ長調K.320「ポストホルン」/セレナード第6番ニ長調K.239「セレナータ・ノットゥルナ」~カルロ・デ・マルティーニ/アカデミア・リッタ(Accademia Litta)(2005年)・・・伊太利亜AmadeusレーベルからMozartのセレナーデCD6枚分の録音をネットより入手したけれど、諸情報をあちこち探るのに苦労いたしました。Carlo De Martiniが自ら創設した古楽器アンサンブル、彼の情報もなかなか出現しません。著名なIl Giardino Armonicoのメンバーだったらしい。
ノンビリと晴れやかな入場行進から始まって(3:05)著名なセレナーデは古典的二管編成+ティンパニ、持ち替えで味わい深いポストホルン(第6楽章「Menuetto」)が登場する名曲。これが比較的最近の古楽器アンサンブルとは思えぬ、なんとも鄙びた素朴なテイスト、はっきり云うとあまり技術的に洗練されていないし、リズムも妙にキリッとしない。乾いた音質イメージもあるのでしょう。それでもそんな演奏風情は作品に似合って、ほっとするような寛いだ気分に全曲飽きずに聴けるのも事実。残りCD5枚分あるのでちゃんと聴きましょう。
第1楽章「Adagio maestoso: Allegro con spirito」(8:20)第2楽章「Menuetto: Allegretto」(3:53)第3楽章「Concertante: Andante grazioso」(7:44)第4楽章「Rondeau: Allegro ma non troppo」(5:28)第5楽章「Andantino」(10:20)第6楽章「Menuetto」(4:25)第7楽章「Finale: Presto」(4:35)
「セレナータ・ノットゥルナ」は異色の二群の弦楽合奏が掛け合う合奏協奏曲風。ティンパニの闊達な動きがオモロい優雅な作品。こちらのほうがソロ・ヴァイリンがずっといきいき、よろしい感じ。終楽章のティンパニとコントラバスの自在なカデンツァ(?)には驚かされました。
第1楽章「Marcia. Maestoso」(4:15)第2楽章「Menuetto」(3:40)第3楽章「Rondeau. Allegretto」(5:04)
2025年6月某日/●
隠居生活もやや馴染みつつある日々
6月に入りました。季節は動いてもノンビリとヒマ、安閑とした生活は変わりません。
昨日土曜もどんより曇って気温もあまり上がりませんでした。前日洗濯強行したのは正解、朝一番のストレッチ、YouTubeは軽いスワイショウ済ませていつもの市立体育館に向かいました。常連メンバー+土曜は若い人も新顔も参入したけれど、幸い筋トレマシンは順繰り消化できて、前回断念した「チェスト」もクリア+エアロバイク15分も膝のリハビリとしました。体調は良好です。シャワーの前に血圧を測るようにしているけれど、前回ちょっと落ち着いて喜んでいたら、また高い。今朝の体重は67.5kg高め安定中。
読者よりメールをいただき前日更新分「弦楽」→「原爆」というトンデモ誤りをご指摘いただき、あわてて修正。赤面の至りでございます。日本の何処かに【♪ KechiKechi Classics ♪】の読者は存在するということですね。
古古古(古)?米は不味いとかなんとか、専門筋の人に伺うとそれは保存状態次第、玄米の外皮は削ってしまうし、それなりのちゃんとした味らしいとのこと。あるブログには「日本人も贅沢になったもんだ」価格と味の問題なら、必要とする方に安く放出するのは当たり前との声でした。自分もそれは納得、なんせカルローズ米5kgニ度に渡って買ってますから。正直なところ、あまり美味しくはないけど、贅沢言うつもりもありません。買い占めて投機の対象にした人間が苦しむのと、盗んだ輩が捕まることを祈っております。
お昼のテレビ報道を眺めたら、店頭に並んだ備蓄米はあっという間に売り切れたそう。
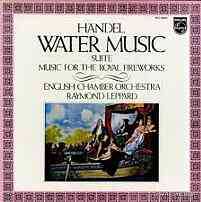 Handel 王宮の花火の音楽 HWV 351(Ouverture(8:24)Bourree(1:28)La Paix(3:46)La Rejouissance(3:41)Menuet I - II(4:27))/「水上の音楽」第1組曲 ヘ長調 HWV348(Ouverture (Grave-Allegro-Adagio E Staccato)(6:01)Allegro-Andante-Allegro(7:25)Passepied(3:34)Air(2:59)Bourree(1:08)Allegro(3:28)Hornpipe(1:18)Menuet(2:59))/「水上の音楽」第3組曲 ト長調 HWV350(Sarabande(3:07)Rigaudon(2:46)Menuet I - II(3:09)Gigue I - II(1:31))/「水上の音楽」第2組曲 ニ長調 HWV349(Allegro(2:03)Hornpipe(3:03)Lentement(1:18)Bourree(0:42)Menuet(1:55))~レイモンド・レパード/イギリス室内管弦楽団(1971-75年)・・・Raymond Leppard(1927-2019英国)はLP時代にバロック音楽の演奏に知られ、やがて古楽器隆盛の流れの中、フル・オーケストラの指揮者に移行していった印象がありました。これはモダーン楽器による端正かつオースドックスなバランス演奏によるHandelの名曲、音質もハデさのない(音質やや劣化した印象も手伝って)しっとりとした風情。アーノンクールの登場以来?古楽器によるインパクトのあるオモロい演奏が主流となったけれど、こんなに抑制してスッキリと品とバランスのあるモダーン楽器アンサンブルも悪くないもの。金管前面に壮麗な祝祭的風情溢れる「王宮の花火」はけっこう質実、浮き立つような快活に豪華な「水上の音楽」もジミだけど、バロック音楽の多彩な旋律をしみじみ堪能できました。
Handel 王宮の花火の音楽 HWV 351(Ouverture(8:24)Bourree(1:28)La Paix(3:46)La Rejouissance(3:41)Menuet I - II(4:27))/「水上の音楽」第1組曲 ヘ長調 HWV348(Ouverture (Grave-Allegro-Adagio E Staccato)(6:01)Allegro-Andante-Allegro(7:25)Passepied(3:34)Air(2:59)Bourree(1:08)Allegro(3:28)Hornpipe(1:18)Menuet(2:59))/「水上の音楽」第3組曲 ト長調 HWV350(Sarabande(3:07)Rigaudon(2:46)Menuet I - II(3:09)Gigue I - II(1:31))/「水上の音楽」第2組曲 ニ長調 HWV349(Allegro(2:03)Hornpipe(3:03)Lentement(1:18)Bourree(0:42)Menuet(1:55))~レイモンド・レパード/イギリス室内管弦楽団(1971-75年)・・・Raymond Leppard(1927-2019英国)はLP時代にバロック音楽の演奏に知られ、やがて古楽器隆盛の流れの中、フル・オーケストラの指揮者に移行していった印象がありました。これはモダーン楽器による端正かつオースドックスなバランス演奏によるHandelの名曲、音質もハデさのない(音質やや劣化した印象も手伝って)しっとりとした風情。アーノンクールの登場以来?古楽器によるインパクトのあるオモロい演奏が主流となったけれど、こんなに抑制してスッキリと品とバランスのあるモダーン楽器アンサンブルも悪くないもの。金管前面に壮麗な祝祭的風情溢れる「王宮の花火」はけっこう質実、浮き立つような快活に豪華な「水上の音楽」もジミだけど、バロック音楽の多彩な旋律をしみじみ堪能できました。
 Shostakovich 交響曲第12番ニ短調「1917年」~オハン・ドゥリアン/ゲヴァントハウス管弦楽団(1967年)・・・2020年来の再聴。Ogan Durjan(1922ー2011以色列→亜美尼亜?)は1963-1968年ライプツィヒ歌劇場の音楽監督を務め、ゲヴァントハウス管弦楽団とも関係が深かったそう。これは幻の音源と呼ばれたもの。音質かなり良好だけど、低音はもうちょっと欲しいところ。LPのA/B面復刻音源。作品に慣れていなかったと類推されるゲヴァントハウス管弦楽団は優秀なアンサンブルでした。
Shostakovich 交響曲第12番ニ短調「1917年」~オハン・ドゥリアン/ゲヴァントハウス管弦楽団(1967年)・・・2020年来の再聴。Ogan Durjan(1922ー2011以色列→亜美尼亜?)は1963-1968年ライプツィヒ歌劇場の音楽監督を務め、ゲヴァントハウス管弦楽団とも関係が深かったそう。これは幻の音源と呼ばれたもの。音質かなり良好だけど、低音はもうちょっと欲しいところ。LPのA/B面復刻音源。作品に慣れていなかったと類推されるゲヴァントハウス管弦楽団は優秀なアンサンブルでした。
第1楽章「革命のペトログラード」は全編を支配する主題が、なかなか経験できぬ叩きつけるような激烈な迫力と勢い、そして緊張感。
第2楽章「ラズリーフ 」レニングラードの北部の湖「ラズリーフ」でレーニンは革命の計画を練る~そんな思索を感じさせる静謐なところ。掴みどころのないような緩徐楽章はわかりやすく表現され、ラスト辺りのホルンは重苦しく雄弁。(A面27:32)
第3楽章「アヴローラ 」(巡洋艦の名前)からの空砲に革命を合図を告げる、静かなピチカートとティンパニから始まり、決起の機運は高まります。やがて第1楽章のわかりやすい主題が顔を出して、激しい打楽器は銃撃戦を意味しているのでしょうか。
第4楽章「人類の夜明け」ホルンの明るい雄弁なファンファーレは革命の勝利を表して、ちょっとありがちな盛り上がりに、最初の主題も壮麗に回帰して金管と打楽器爆発・・・この作品はもしかして交響曲第5番ニ短調より俗っぽく大衆的にわかりやすい作品なのかも~そんな感慨を得たものです。(B面25:02)