Elgar 交響曲第1番 変イ長調 作品55
/序奏とアレグロ 作品47(ジョン・バルビローリ)
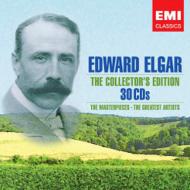 Elgar
Elgar
交響曲第1番 変イ長調 作品55
フィルハーモニア管弦楽団
序奏とアレグロ 作品47(弦楽四重奏と弦楽のための)
アレグリ弦楽四重奏団/シンフォニア・オブ・ロンドン
ジョン・バルビローリ
EMI 5036032/1 1962年録音 30枚組 6,608円
「CD在庫総量抑制計画」遂行に大苦戦中。棚中に溢れかえる在庫と残された人生の時間を鑑みて、オークションに毎週、継続的に出品しているけれど、結果的にそれ以上購入・・・棚に余裕が生まれること、いくら安く処分しても小銭が貯まって軍資金となること・・・Elgarはお気に入り、交響曲第2番はエドワード・ダウンズ盤しか手許にない、と嘆いていたら、レナード・スラットキン盤を(安く)入手できたのが今年2008年1月のこと。更にBBSでちょっとだけ話題になって、嗚呼、バルビローリが聴きたいな、という思いムクムクと〜
その昔、CDは一枚3,000円以上した時代もあったし、現在だってレギュラー盤は2,000円じゃないですか。わずか3枚分コストでごっそり30枚(数枚ダブり買いでも)入手可。ある日泡銭(あぶくぜに=バブル・マネー)入って即、通販にて発注しておりました。待つこと一ヶ月以上、ある日、感動到着。一枚目がこの交響曲第1番でして、なんど繰り返して聴いたことかっ!(次に進めないよ)
最初に「序奏とアレグロ 作品47」の件。おそらくはVaunghan Williams「タリス」「グリーンスリーヴス」幻想曲と同時録音で、その組み合わせがオリジナルと類推できました。シンフォニア・オブ・ロンドンとのセッションでLP一枚になりますもんね。弦楽合奏と弦楽四重奏が詠嘆合戦をする素敵な作品であって、いかにもバルビローリ向け!事実(既に聴いていた)ハレ管弦楽団との1956年旧録音は、期待通りのまったりとした歌に充ちた味わい深いものでした(1947年録音も有)。「タリス」「グリーンスリーヴス」の路線で行ってくれ!(祈)。
ま、当たり前の話しだけれど、「噎せ返るような浪漫に充ちて」「纏綿甘美な”泣き”の表現」「たっぷり横流れの粘着質+ゆるゆるな歌は、まさに”バルビローリ節”」前出Vaunghan Williamsと寸分違わない。想像より颯爽と雄弁、これより遅いテンポの演奏はあります。「弦楽合奏と弦楽四重奏が詠嘆合戦」は、たっぷりのヴィヴラートで痛み分け。後半の「アレグロ」の推進力にも満足。音質はそれなりの水準ながら、こちら英国盤のほうが(やや)改善されております。
●
交響曲第1番との出会いはジェームス・ロッホラン(←再コメント鋭意検討中)であって、当時若者であったワタシには少々味付けが薄過ぎました。でもね、このバルビローリ盤で出会っていたら、他のは聴けなくなっちまうんじゃないか、そんなことを考えさせる”超・個性的”演奏也。やや遅めのテンポ、悠々たる旋律の歌の幅広さ呼吸の深さ、きめ細かい味付け、泣き(ヴィヴラート)、粘着質でありながら、時に抜いてそっと囁くような優しさ。変幻自在なる”揺れ”。
決然とした大爆発時にも安易に走らない、たっぷりとしたタメが待っております。第1楽章「Andante. Nobilmente e semplice-Allegro(高貴に、気高く)」の意味合いが初めて理解できました。こんな”大きな”作品だったのか。第2楽章は「Allegro molto」ですか?広野を駆ける駿馬を連想させ、フィルハーモニア管弦楽団は絶好調の鳴りっぷりがカッコ良い。木管の繊細さも特筆すべきでしょう。
第3楽章「Adagio-Molto espressivo e sostenuto」は、Bruckner交響曲第8番ハ短調を連想しませんか。但し、御大バルビローリはもっと、もっと清冽かつ思いっきり甘美な”涙”を加えて、陶酔の世界を作り出しているから、独墺の世界とはずいぶんと異なります。エグいくらいのオーヴァーな表情付けと、優しい静謐との対比絶妙。ここ全曲中の白眉。弦を賛美したい。
終楽章「Lento-Allegro-Grandioso」は前楽章の残り香を引きずって開始、やがて金管が叫んで(フィルハーモニア管は優秀だ!)じわじわ懐かしい大団円への歩みを進めます。淡彩なる主旋律が微妙に変容して、いかにも英国らしい魅力なところだけれど、若い頃はこの魅力が理解できまなかったもの。タメを作ってしっかり金管の見栄を決めたら、第1楽章の主題が懐かしく、輝かしく回帰しました。
録音は例の如しの中低音が甘いEMI系だけれど、自然な空気感のある(それなり)聴きやすいもの。さて、これから残り「未踏峰ミチョランマ」を克服せねば。 (2008年5月23日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●
▲To Top Page.▲
|