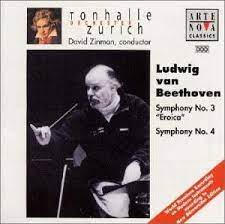”Beeやん苦手”〜言い続けて拾余年(単品除く)Beeやん関連への言及ラストが愚行・Beethoven 2011年〜それはCD入手の話題でした。入手すること、所有することより、まず聴くこと、それは当たり前。それからわずか2年経過、ネットにてデータ入手、いや入手しなくて音楽は拝聴できるようになりつつあって、所有CDは時々復活するオークションにて少しずつ削減しております。例えばBach 、Beethoven 、Mozart 、Brahms 、Stravinsky辺り、おそらく全曲を意識して入手、Sibelius 、Bartok、Mahler 、Elgar、Debussy、Ravel もほぼ棚中に揃ったと思います。Haydnの交響曲全集、弦楽四重奏曲、Schumann、Schubert 、Handel の主要作品も同様〜だからどーなんだ?半分聴いているでしょうか。聴いていても心の琴線に触れるような感動を得た記憶はわずかでしょう。 贅沢三昧Beethoven 編(2000年)を読めば、一生懸命安い全集を集め、そして聴いていた、意欲は伺えますよ(なけなしの小遣いはたいて)。当時の在庫CD過半は処分し、例えばシューリヒト、クリュイタンス、カラヤン/フィルハーモニア管弦楽団はパブリック・ドメインに至って自由に聴けるように。ブルーノ・ワルターやオットー・クレンペラー、フランツ・コンヴィチュニー(これはCDが棚中に残っている)、エルネスト・アンセルメのほとんど、その他、著名な歴史的録音は、御大フルトヴェングラー、トスカニーニ全集などすべて無料入手可能な時代となりました。(復刻云々言わなければ) 自由に、無料で聴けるようになる=ほんまに音楽に集中する、ということは別もんだったですね。上記例に上げた音源中、ほんまに感銘をうけたのは(昔馴染みの)クリュイタンスくらいじゃないか。あと、LP時代廉価盤としてなかなか登場しなかったブルーノ・ワルター/コロムビア交響楽団(それも第3番「英雄」第6番「田園」くらい)か。いちおう耳にした、というのが大部分、著名歴史的録音に至ってはCD処分してからほとんど聴いておりません。いつでも聴ける、となると優先順位は下がるんです。もとよりBeeやんの拝聴機会は低いし。
いくら不遜な”Beeやん苦手”野郎でも、こどもの頃からの馴染み、旋律細部迄聴き知っておりますよ。つい先日、中学生時代愛聴した
時代は古楽器乃至古楽器系演奏が主流となっており、おそらくはワタシもその時流に乗っております(音質良好なものがほとんど、ということもあるのか)。 ここ数年、Beethoven 拝聴機会が減って忘れていたけれど、リファレンス(参照の基準)はなにか〜世間ではカラヤン?現代だったらサイモン・ラトルでしょうか。話題の新しい音源を拝聴したり、著名かつ評価の高い”名盤”に接する機会ないでもないけれど、ほとんど?状態。ある日、気付きました。賛否いろいろ世評も喧(かまびす)しいデイヴィッド・ジンマン/チューリヒ・トーン・ハレ管弦楽団全集(1997/98年)が自分にとっての基準になっていると。
その後、若手による快速激上手演奏どんどこ出たでしょ?ハイリヒ・シフ/ドイツ・カンマーフィルとか、最近だったらアントニーニ/バーゼル室内管弦楽団とか。それを全部無条件称賛はできないんです。けっこう激賞コメント見ますけどね。いずれ、機会があれば拝聴ちゃんとさせていただきます。 相変わらず罰当たり”Beeやん苦手”野郎も10年スパンで変化しておりました。 |
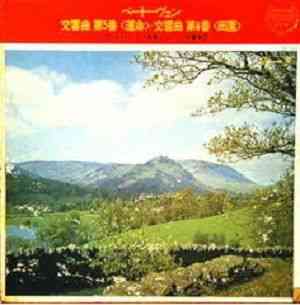 Beethoven 交響曲第5番ハ短調/第6番ヘ長調「田園」〜ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグ交響楽団数十年ぶりに拝聴して、涙が出ました。クリュイタンスも含め、結局”想い出昔話”(母の味みたいな)刷り込まれたノーミソが反応しているだけじゃないの?もうちょっと冷静に考察すれば、音質厳しいものは避けて、やや旧い音源でも比較的良好なものを選んでいるのかも。
Beethoven 交響曲第5番ハ短調/第6番ヘ長調「田園」〜ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグ交響楽団数十年ぶりに拝聴して、涙が出ました。クリュイタンスも含め、結局”想い出昔話”(母の味みたいな)刷り込まれたノーミソが反応しているだけじゃないの?もうちょっと冷静に考察すれば、音質厳しいものは避けて、やや旧い音源でも比較的良好なものを選んでいるのかも。