Sibelius 交響曲第2番ニ長調
(ウラディミール・アシュケナージ/フィルハーモニア管弦楽団)
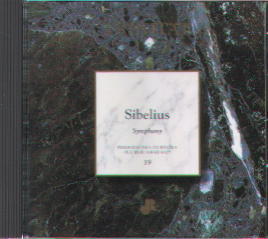 Sibelius
Sibelius
交響曲第2番ニ長調(1979年録音)
交響詩「フィンランディア」
組曲「カレリア」
ウラディミール・アシュケナージ/フィルハーモニア管弦楽団
LONDON HT-119 中古250円
よく歌っているし、力演でしょう。でも(ファンの方には申し訳ないが)演奏に品がない。彼が指揮を始めた初期の頃だし、まだ慣れていなかったのかな?たくさん聴いていないが、底流にロシアがあるようで、この曲にはやや違和感を感じました とは2001年11月10日自らの(傲岸不遜なる)コメントです。アシュケナージもいつのまにか70歳を超えたんだな。もうヴェテランですよ。指揮者としてのキャリアはこの録音辺りからのはずで、たしかボリス・ベルキンの協奏曲伴奏が録音デビューであったと記憶します。「おおよそピアニスト上がりの指揮者はロクなもんじゃない」との通説があって、エッシェンバッハ、バレンボイム、そしてアシュケナージが代表例か?ワタシは是々非々でちゃんと聴いているつもり。十余年ぶりの再聴はずいぶんと印象を変えました。音質は極上。
ネットを検索すると曰く、指揮法技術がアマチュアレベルとか、素人っぽいなんて、そんなコメントが目に付きました。ワタシは中学校時代のクラス合唱指揮くらいしか経験がないので”指揮法技術云々”など理解の外(=ド・シロウト)。”演奏に品がない”、”底流にロシア”というのは(傲慢なる表現さておき、やや)当たっていないこともなくて、この度は個性として愉しく拝聴いたしました。先日更新のアルヴォ・ヴォルメルとは、またずいぶん方向性が異なって、こうだから音楽表現への興味は尽きまへんな。
フィルハーモニア管弦楽団は明るく清涼サウンド、整ったアンサンブルが特徴か。ここではオーケストラを開放的に鳴らして荒々しい情熱の発露、細部アンサンブルの彫琢にこだわらぬ、朗々雄弁なる歌が聴かれます。彼はいくつかSibelius を再録音していて、おそらく現在ならもっとオーケストラ・コントロールに優れると想像可能(未聴)だけれど、こんな粗削りなテンションもけっして悪くない。アデレード響も素敵だったが、フィルハーモニア管弦楽団の厚い響き(どんより重苦しくはない)には敵わないかも。
第1楽章「アレグレット」。好き嫌い乗り越え、この作品表現に相応しいか別にして、ジョージ・セルのアンサンブル水準が刷り込みになっていて、それに比べて(というのはとても失礼な行為だと自覚しつつ)弦の快速パッセージの扱いなど、完全に足並みは揃っていないと感じます。しかし、アシュケナージには誠実な歌と情熱、器用に洗練されていないが、精一杯のエモーションを感じることは可能でしょう。
第2楽章「アンダンテ」。ティンパニと不気味なピツィカートで開始され、その暗い怪しさはファゴットに引き継がれます。暗鬱な重さは、なかなかエエ味出しているじゃないですか。やがて弦が急いた足取りで追い越して、金管の警句へと至る!ところが、やや表現として(タメが)甘い・・・かも。こんな劇的濃厚な旋律はアシュケナージ好みのはずだけれど、思い余って”間”に不足する印象ないでもない。
第3楽章「ヴィヴァーチシモ」スケルツォですな。快速弦を中心とするアンサンブル、そして迫力+低音充分なる金管の絡みも上々です。この辺りはやはり上手いオーケストラなんだな。レント・エ・スアーヴェ(ゆっくり、しなやかに)指定のトリオのシミジミとした情感表現もお見事。そして、やがて、そのまま盛り上がって終楽章へ休みなく突入する・・・(経過部がいかにも取って付けた感じの表現)
終楽章は精一杯の金管の高らかな歌〜清涼なる木管が決まっております(第1主題)。しかし第2主題の展開に何故か躓くアシュケナージ。ここはよくできた(第1主題/第2主題の)絡みですからね。緩急の「緩」部分の扱いがやや甘いのだな。朗々と開放的に歌う部分は上手いし、雰囲気ちゃんとあるんだけれど。ラスト・クライマックス前、延々と吹雪の中を突き進むような金管嵐もいまいちスムースな足取りではない。
それでも精一杯、誠実な叫びのラストに、充分聴き手は心を震わせることでしょう。
●
名曲続きます。「フィンランディア」は豪快に、一筆書きのように仕上げた迫力演奏。組曲「カレリア」第1曲「間奏曲」はやや表情が硬く、重いが、ホルンに深みを感じます。美しい「バラード」は神妙な抑制があり、息も絶え絶えの繊細な呼吸がありました。ここもちょっと重いかな?「行進曲」の軽妙な足取りに文句はありません。 (2011年12月18日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●
▲To Top Page.▲
|