Shostakovich 交響曲第13番 変ロ短調「バビ・ヤール」
(ラディスラフ・スロヴァーク/スロヴァキア放送交響楽団)
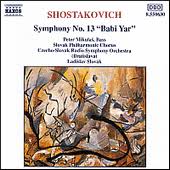 Shostakovich
Shostakovich
交響曲第13番 変ロ短調「バビ・ヤール」
ラディスラフ・スロヴァーク/スロヴァキア放送交響楽団/スロヴァキア・フィル合唱団/ペテル・ミクラーシュ(b)
NAXOS 8.550630 1990年
若い頃苦手系の極北!だったShostakovichを好んで聴くようになったのは、ここ10年ほどでしょうか。彼(か)のシニカルなユーモアを孕んだ苦い風情に、時代が追いついてきたのかも知れません。20世紀後半から21世紀に入ったディジタル時代、録音は一気に増えて演奏会レパートリーとしても定着。入手可能な音源たくさん揃えて、CD時代最初に手に入れたLadislav Slovak(1909ー1999斯洛伐克)全集は必ずしもベストな存在ではなくなりました。それでも音質良好、初めて真面目に集中できたShostakovichという思い入れもあって、大切にこの名曲を聴いております。テンションはちょっと低い、芯も甘い、でもユルいオーケストラはなかなかの敢闘賞。音質もよろしいし、作品を堪能するのに不足はないと思う・・・けど、じつは続けてキリル・コンドラシンによる1962年ライヴ(初演の2日後)を聴いたら、申し訳ないけど作品に賭ける情熱やら切迫感危機感が桁違い!なことに驚いたものです。あれは時代の緊張感が反映していたのですね。閑話休題(それはさておき)
フルート2本+ピッコロは拡張された二管編成?三管編成と呼ぶのか。いずれ12種の打楽器、チェレスタ、ハープ、ピアノ、男声バス・ソロ+バス合唱という大掛かりなもの。政治的メッセージに当局の圧力はあったけれど、初演は大成功であった由。交響曲第14番にも登場するPeter Mikulas(1954-斯洛伐克)はなかなか立派に押し出しもよろしい渋い低音(イケボ)男声合唱団も力強く、絶望的にズズ暗いものでした。物々しい雰囲気に悲痛な重厚感も感じさせるアンサンブルはかなりの力演、音質解像度とも優秀。難解晦渋重暗鬱、華のないオトコ祭り的な苦い風情の作品は絶望的に・・・とてもわかりやすい。但し心身ともに調子を整えておかないと、この重い音楽はなかなか受容できないかも。
第1楽章「Babi Yar/バビ・ヤール(Adagio)」堂々たる男声ソロの貫禄に、管弦楽も低音中心に苦渋漂うところ。ま、全編そうなんやけど。バビ・ヤール(烏克蘭)に於けるユダヤ人虐殺を題材にとって、反ユダヤ主義を激しく糾弾した内容とのこと。バスは圧巻の説得力、合唱も同様に充実した押し出し。金管に少々キレは足らぬけれど、重苦しい風情はちゃんと後半に向けて苦渋の大爆発!して下さいました。(追加。後出しジャンケンだけど、この翌日アンドリス・ネルソンス/2023年を聴いたら、あまりのオーケストラの上手さ、キレに仰け反りました。それでもスロヴァークは敢闘賞!)(14:55)
第2楽章「Yumor (Humor)/ユーモア(Allegretto)」はスケルツォでしょうか。反権力(どんな権力者、支配者もユーモアを手なずけることはできなかった)シニカルなバスは表情豊かにノリノリ、合唱がヴィヴィッド、ユーモラスに呼応します。言語が理解できなくてもちゃんと理解可能。変拍子リズムの重み、打楽器群の楔、管弦楽のキレや重み、厚みや切迫感は努力賞もんの賑やかな勢い。Bartokを意識した楽章とのこと(Wikiより)(7:38)
第3楽章「Magazine (At the Store)/商店で(Adagio)」 ペリメニ(露西亜風水餃子)を買いに来た詩人は、寒風の中行列に並ぶ女性を「女神たち」と讃え、ぼったくり商人に怒りを覚える静かな緩徐楽章。地の底からのような低弦から始まり、重苦しく絶望的に荘厳な男声ソロが延々と暗鬱、管弦楽も合唱も蠢くように静謐、そしてデリケート。そしてラストにモノクロの怒りの爆発(絶叫)がやってきました。ここは内向きに感動的なところ。(12:23)
第4楽章「Strachi (Fears)/恐怖(Largo)」スターリンは去ったけれど、あらたな「恐怖」が生まれている。静かなチューバから始まり低弦へ、声楽も管弦楽も地底を這うような絶望的な静謐とつぶやき。雄弁さ際立つ男声ソロに呼応して、切ないヴィヴラートたっぷりのトロンボーンが泣いて、細かい金管の動きも、弦の不気味な動きもなかなかの切迫感でした。ま、お経みたいな音楽だけど、後半の露西亜民謡風葬送行進曲風リズムも興味深く、絶望の爆発も壮絶な迫力。時々鳴る鐘もなかなか不気味。(12:12)
第5楽章「Kariera (Career)/出世(Allegretto)」地動説を否定されても自説を曲げなかったガリレオ・ガリレイを称える終楽章。まるで妖精の踊りのようにデリケートに印象的な木管に始まって弦がそれを受け継ぎます。ファゴットのユーモラスな音型に導かれ(けっこうあちこち際立った活躍ぶり)男声ソロと合唱があいも変わらず苦渋に充ちて、時に晴れやかに、抑制を以て朗々ヴィヴィッドに歌い続けました。そして冒頭の旋律が弦とチェレスタに再現されて静かに終了。(11:35) (2025年3月29日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●
▲To Top Page.▲
|