Mahler 交響曲第2番ハ短調「復活」
(ズービン・メータ/ウィーン・フィルハーモニー/1975年録音)
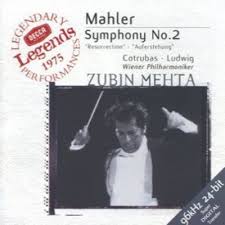 Mahler
Mahler
交響曲第2番ハ短調「復活」
ズービン・メータ/ウィーン・フィルハーモニー/ウィーン国立歌劇場管弦楽団/イレアナ・コトルバス(s)/クリスタ・ルートヴィヒ(ms)
Decca 4669922 1975年録音
2024年夏の猛暑中、夏風邪に体調を崩したのでカンタンに更新しておきます。お恥ずかしい2009年のコメント(しかも駅売海賊盤!)が残ってこれは懐かしい昔馴染み。Zubin Mehta(1936ー印度)30歳台、若き日の有名な記録でしょう。やがて彼はこの巨大なる「復活」を幾度録音を繰り返して、結局Mahler交響曲全曲は揃わないと記憶します。ちゃんと全部集中して聴いていないけど、一番最初のこの録音が音質、演奏とも一番かと思います。若者らしくきりりと引き締まって、やや速めのテンポにちょっぴり前のめり、以前はその辺りが気に喰わなかった記憶もありました。現在の耳なら、老獪な一流オーケストラを統率して全力疾走するのも若さの勢い、ウィーン・フィルの豊満かつ美しいサウンドをしっかり引き出して余すところがない。そんな魅力に響きます。
第1楽章「Allegro maestoso」に於ける緊張感テンションの維持、疾走、オーケストラの陶酔の響き、厚みと迫力、若々しい前のめりの勢いのまま圧巻の締めくくり。(21:03)第2楽章「Andante moderato」はウィーン・フィルの弦が優雅に伸びやかな楽想。若い頃はオモロないと感じて、緩徐楽章の魅力を発見したのは華麗なる加齢を迎えた最近のことでした。ここも情感の高まりに若々しさを感じさせます。(10:21)第3楽章「Scherzo」は「魚に説教するパドヴァの聖アントニウス」旋律、3/8拍子のヴィヴィッドなリズム感は一番好き。この演奏を初めて聴いた時、冒頭のティンパニのリアルな存在感に仰け反った記憶も鮮明でした。英DECCAのデフォルメした録音も最高。(10:28)第4楽章「原光(Urlicht)」クリスタ・ルートヴィヒ(ms)の声は神々しいですね。管弦楽もデリケートそのもの。(5:30)第5楽章「Im Tempo des Scherzos」静かな始まりから圧巻のオーケストラの大爆発迄の自然な流れと、堂々たるクライマックスへの足取りはストレートな表現。やがてフルートとピッコロが夜鶯の啼き声、やがて声楽「復活賛歌」静かに参入して、それは大団円に静かに成長して感極まりました。金管は余裕の厚みに爽快なるクライマックスへ。(9:54-7:33-2:21-6:39-7:39)
最近の記憶ではレナード・バーンスタイン(1987年)にひときわ大きな感銘を受けていて、それに匹敵する完成度と感じます。より大きく、重く、遅く、たっぷり粘着質なヴェテランの記録より、こちら長時間弛緩させぬ勢い溢れ、若者の爽やかに滾(たぎ)る熱気を感じさせました。 (2024年8月3日)
●
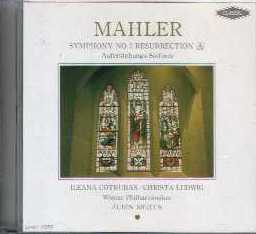 Mahler
Mahler
交響曲第2番ハ短調「復活」
ズービン・メータ/ウィーン・フィルハーモニー/ウィーン国立歌劇場管弦楽団/イレアナ・コトルバス(s)/クリスタ・ルートヴィヒ(ms)
ECHO INDUSTRY CC-1017/18 英DECCA1975年録音 2枚組 2,000円で購入
1990年代前半に購入したCDであって、ずいぶんと処分した駅売海賊盤だけれど棚中に(しぶとく)生き残ったもの。長いお付き合いとなります。21世紀は廉価盤の時代、などと力まんでも、現在なら一枚物で、これよりずっと安い。 若きメータ39歳の録音。得意の曲らしく、後2回の録音有。これワタシにとっての実質上「復活」との出会いで、DECCA録音は極上だし、オーケストラは上手くて美しいし、で、10年前は喜んでいたけれど、いま聴くと呼吸が浅く、尻が軽い。完成度は高いが、まだ成熟が足りない。懊悩・苦悩が感じられない。これはこれで「若さの勢い」的魅力かな?スケルツォ楽章はすっぱり気持ちヨロシい。声楽ソロは抜群の雰囲気。終楽章はやや上滑りか?何故かシミジミと盛り上がってくれない。(2002年7月14日)
とは7年前の自らの辛口コメント(とくに終楽章)であります。
先の引用先ユーザーレビューでも評価極めて高い。こういったマルチ・マイク系鮮明なる(英DECCA)録音は、Mahler に極めて効果的なんです。(この駅売海賊盤でも充分なる威力)”呼吸が浅く、尻が軽い。完成度は高いが、まだ成熟が足りない”というのは若さの勢いで充分補いをつけて余りある魅力、と現在の自分ならそう感じます。”懊悩・苦悩が感じられない”〜これも嗜好の世界でして、明るく前向きな情熱はこれでひとつの完成であったと思います。その後の再(々)録音には失われてしまった世界(ずばりユルい!感じ)。
やや早めのテンポ、前のめり急いて落ち着かない、シミジミとした練り上げられた響きではなく、細部仕上げがやや粗い・・・それでも、これは賞賛の対象としてよろしい青春の記録でしょう。第1楽章は尋常ならざる緊張感で開始し、第2楽章「アンダンテ・モデラート」は少々素っ気ない感じ。第3楽章「魚に説教するパドヴァの聖アントニウス」の冒頭ティンパニの迫力は衝撃的だし、リズムのノリが溌剌としてこれが若さの魅力なのでしょう。
「原光」(おお、紅の小さき薔薇よ)に於けるルートヴィヒの深淵さ(終楽章も同様)、終楽章前半(「荒野に叫ぶ者」)のウィーン・フィルは若きメータに煽られ、走り、高らかに歌い、これほどアツく華やかに爆発することは希でしょう。第3楽章と並んでスケルツォ風リズムがはっきりしているところでの成果に文句なし。オーケストラ・コントロール完璧、テンポの変化も的確。
さて、万感迫る最終版声楽合流場面〜数年前は”やや上滑りか?何故かシミジミと盛り上がってくれない”とのコメントは、どの演奏との比較が念頭にあったのでしょうか(記憶なし)。久々の聴取では”何故かシミジミと”とは思わぬが、”やや上滑り”というか表層に流れ、さっぱりとした表現に過ぎる感触はありましたね。しかし、”煽られ、走り、高らかに歌い、これほどアツく華やかに爆発”という若さの表現に魅力が足りないわけでもない。声楽含め、宇宙的広がり迄は行かないけれど。
80分に及ぶ長丁場を、最後まで弛緩させず、一気に聴かせる集中力を賞賛いたしましょう。思えば良い時代だった、新しい録音テクノロジーが開発され、若手が意欲的な録音を次々と出すことができた(=売れた)幸せな時代。アラン・ギルバートがニューヨーク・フィルの音楽監督になったそうだけれど、彼のCDってそんなに出ていないでしょ?前任者の巨匠マゼールだって、このオーケストラとの録音はほとんど出なかったはず。やはりナマを聴いてあげなくっちゃいけないな。 (2009年4月10日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●
▲To Top Page.▲
|