Schubert 交響曲第9番ハ長調
(カール・シューリヒト/シュトゥットガルト南ドイツ放送交響楽団)
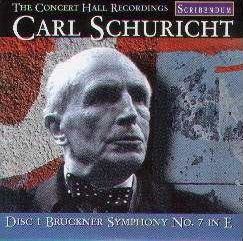 Schubert
Schubert
交響曲第9番ハ長調 D.944 「ザ・グレイト」
シューリヒト/南ドイツ放送交響楽団(シュトゥットガルト)
SCRIBENDUM SC 011-4 1960年録音 10枚組 6,552円で買ったウチの一枚
懐かしいConcertHall音源、LP時代よりの愛聴盤は20年ぶりの拝聴。劣悪音質を覚悟していたせいか、イアン・ジョーンズのマスタリングの成果か、響きに濁りはあるけれど意外と臨場感があって聴きやすい音質でした。Carl Schuricht(1880-1967独逸)は往年の重厚長大世代だけれど、その個性は特異にその真反対。壮麗にシンプル、ステキな歌謡的旋律は連続してどの楽章も軽やかにデリケート、爽やかな熱気に溢れます。オーケストラと相性はよろしい感じ。各楽章ラストのルバートもほとんどなくて素っ気ないほど。テンポは中庸からやや速め。
第1楽章「Andante - Allegro ma non troppo」冒頭のシンプルなホルン・ソロから伸びやかな音色、夢見るような味わい深さ。微妙なテンポの揺れに、愉悦が湧き上がるようにノリノリのスウィング、軽快軽妙な牧歌的風情が疾走しました。提示部は繰り返しなし。(13:10)
第2楽章「Andante con moto」途方に暮れた緩徐楽章もシミジミとさっぱり、軽やかにスタッカートするように、浮き立つような足取りにはやはりノリを感じさせます。トリオの弦は爽やかに美しく、テンポとニュアンスの揺れは表情豊かでした。ここもホルンが印象的。(15:10)
第3楽章「Scherzo. Allegro vivace」冒頭ゴリゴリとした弦から始まるスケルツォもリズミカルに上機嫌、軽快さを失わない。トリオも優雅な3/4拍子がスウィングしております。(10:19)
第4楽章「Finale. Allegro vivace」肩の力も抜けて、あまり急がぬ晴れ晴れとした表情に、快い熱気のフィナーレ〜だけど、ちょっぴり響きの濁り、音質が気になるなぁ、ここは。弾むようなスウィング感は最後まで持続いたしました。(12:43)
(2025年7月19日)
●
カール・シューリヒトのコンサート・ホール・レーベル録音が、2002年に正規CD復刻されました。(全部ではない)この録音が含まれていたので、以前コメントした以下の駅売海賊盤(FIC)は用済みとなって、どなたかにプレゼント。(ミュンヒンガーのSchubert は誠に残念。ちゃんと正規盤がそこそこの価格で出れば、海賊盤ばかり買わないぜ・・・当たり前か)
「イアン・ジョーンズによるリマスター盤!」とか宣伝していたけど、ま、もともとの録音がたいしたことはないハズだし、このCDもあんまりヨロしくない音質でした。(むしろ悪化?いっそう奥行きがなくなっている)わずか4〜5年前は絶賛!だったのに。まず、音楽に没入するのに苦労するようになったのは、加齢による集中力の低下です。というより、この作品そのものをあまり聴かなくなっているのかな。音質云々言うようになっちゃ、もう堕落しちょる!(自戒)それでも二度三度、聴いているウチに彼(か)の感激が蘇ってきましたね。
軽いのではなく、重苦しさが存在しない。フレージングに粘着質皆無。スッキリ爽やかで、ハズむようなリズムと推進力があります。第1楽章も素っ気なく始めているようで、知らず知らず熱が入ってノリノリ、手に汗握る興奮の渦に巻き込まれ・・・って、助走からのテンポ・アップ(このダッシュは気持ちいいよ!)以降は、ほとんどイン・テンポなんですけどね。(第1楽章ラストだって意固地にルバートせず。さっさと終わる潔さ)
オーケストラの響きが明るくて(亜米利加西海岸的明るさに非ず)暖かい。第2楽章「アンダンテ・コン・モト」〜ちょっと道を踏み外すと、どーしょーもなくダルな世界に突入するんです。ココ、ポイントはリズム。緩叙楽章だけれど、大きくてゆったりとしたリズムがしっかり刻まれていないと、または、聴き手がそこを感じ取らないと、15分は退屈なものと成り果ててしまう・・・
美しいオーケストラだと思うが、ぞくっとするほどセクシーな木管とか、目眩く豪華な厚みの弦〜という訳じゃないでしょ。シューリヒトは大げさなテンポの揺り動かしをしないし(音質と相まって)な〜んもしない演奏、みたいに聞こえるかも。冒頭旋律(何度も繰り返される)のきっちりとしたスタッカートがあるから、次の優しい表情も生きるんです。峻厳、と呼びたい表現。ティンパニの楔もピタリと決まっています。
スケルツォ楽章の適性は想像付きますよね。軽快なるリズム感、ノリノリの楽しげな表情〜それがお下品なる大騒ぎにならない節度。中間部のワルツの典雅なこと。終楽章は予想よりテンポが控えめだと思います。ここでもしっかりとしたリズム感生命(いのち)で、安易に横流れさせない。しっかり、拍子にアクセントが強調されていて、しかもそれが動的であって、アツい。
録音問題有り。シューリヒトは神経質にアンサンブルを整えるタイプとは少々異なります。しかし、これは細部に指揮者の配慮が行き渡った”爽やか熱血系”演奏でしょう。繰り返し聴取に耐える、というか、繰り返して聴かないと真価は分かりにくい演奏かも。ワタシ個人的には真空管アンプで聴いたほうが、この演奏の特徴がよく見えました。
(2004年4月9日)
以下、数年前の拙文もそのまま掲載。
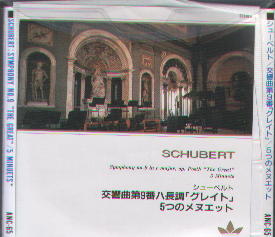 Schubert
Schubert
交響曲第9番ハ長調 D.944 「ザ・グレイト」
シューリヒト/シュトゥットガルト放送交響楽団(1960年録音)
(「5つのメヌエット」付き
ミュンヒンガー/シュトゥットガルト室内管弦楽団1955年録音)
海賊盤(コンサートホール)FIC ANC65 3枚2,000円(で買ったと思う。)
これ、コンサートホールで昔出ていたはず。記憶違いでしたら、どなたかご教授下さい。LP時代もこの演奏を楽しんでいましたが、訳のわからんへんなレーベルの輸入盤でした。FICシリーズのなかでも、屈指のマニアック音源のひとつ。購入を迷っている人は、即買うこと。
演奏は最高。というか、これほど燃えるようなスピード感は滅多に経験できない。
峻厳で、スリムに引き締まった演奏。壮大で美しい旋律を持つこの曲を、無駄な響きもなく、すっきりと聴かせています。熱演で力強さもある。飾り気や鼻につくような節回し皆無。即興的でノリノリの演奏。
例えば、第1楽章の、序奏からアレグロに入るところの素晴らしいスピードと高揚感。軽くなく、重すぎない。これしかない、と思わせる説得力。ラストもリタルダンドしない。第2楽章の弾むような入魂のリズム。よ〜く聴くと旋律の歌わせ方に、細かいニュアンスいっぱい。
第3楽章の爆発する喜び。勢いが止まらない第4楽章の疾走。かなり長い曲のはずが、いっきに聴き終わります。
この人はあまりオーケストラを選ばない人でしょうが、シュトゥットガルト放響は良い音で鳴っています。とくに管楽器の暖かさは出色。音は良好とは言いかねるが、それを超越して、いつ聴いても新鮮。ステレオであるだけでも感謝しなくちゃ、罰が当たります。
おまけで、懐かしいミュンヒンガーの演奏が8分ほど入っています。 じつは、この演奏もLPで持っていたので懐かしい。旧い録音だけど、ちゃんとしたステレオです。ノンビリとした牧歌的な曲で、フィル・アップとして違和感はありません。
比較対象盤
ま、バルビローリとかクーベリックとか好きだけど、シューリヒトの前にはかすみがち。許して下さい。(2000年8月6日更新)