Vaughan Williams 交響曲第8番ニ短調/
交響曲第9番ホ短調
(ゲンナジ・ロジェストヴェンスキー/
ソヴィエット国立文科省交響楽団)
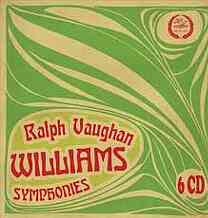 Vaughan Williams
Vaughan Williams
交響曲第8番ニ短調
交響曲第9番ホ短調
ゲンナジ・ロジェストヴェンスキー/ソヴィエット国立文科省交響楽団
MELCD1002170 1988-89年ライヴ
Gennady Rozhdestvensky(1931-2018露西亜)によるいかにも露西亜風脂っこい、色彩どぎついRVWが聴けるのかと思ったらそんなことはない、意外と端正にまとも、ちゃんとした英国風情の演奏でした。音質はかなり良好と思うけれどソヴィエット露西亜のライヴだから、どうしても評価は甘くなりがち。数奇な運命を辿った国策オーケストラのアンサンブルは優秀でした。
交響曲第8番ニ短調は1956年バルビローリが初演、二管編成だけど5人の奏者による8種の打楽器+チェレスタ+ハープが入ります。
第1楽章「Fantasia (Variazioni senza tema)」主題のない変奏曲とか。ちょっぴり寂しげに木管が歌い交わして時に激昂する(シンバルも入ってなかなかの迫力)牧歌的穏健な幻想曲?なんだそう。自分はこんな鬱蒼として苦い風情も大好きだけど、ジミだし日本じゃ人気ないやろなぁ。(9:39)
第2楽章「Scherzo alla marcia (per stromenti a fiato)」管楽器のみのスケルツォは妙に辛口な軽妙。なかなか珍しいテイスト、これもユーモアですよ。(3:31)
第3楽章「Cavatina (per stromenti ad arco)」弦のみのこれは絶望的に寂しく、美しい静謐な緩徐楽章。哀愁のヴァイオリン・ソロも切なく、チェロは暗鬱。(8:49)
第4楽章「Toccata」は冒頭種々打楽器が怪しい効果を上げて、堂々と落ち着いて勇壮なフィナーレが始まります。金管と打楽器群が絡み合って高揚しつつ終了、この作品はけっこう大好きですよ。(5:56/拍手有)
ラストの交響曲である交響曲第9番ホ短調の初演は1958年(マルコム・サージェント)三管編成+12種の打楽器+2台のハープ+チェレスタ、かなりの大規模に至っております。この作品はサキソフォーンが聴きもの。ファンである自分でもちょっと難曲と感じます。
第1楽章「Moderato maestoso」劇的に切なく金管が重い足取り、サキソフォーンの音色がとっても怪しい、うねうねとした眉間にシワな始まりは快く盛り上がらない。(10:40)
第2楽章「Andante sostenuto」虚ろに寂しげなフリューゲルホルンのモノローグに始まって、合いの手を入れるオーケストラのリズムも個性的、打楽器も重苦しい。ここも辛口な緩徐楽章でした。(7:40)
第3楽章「Schrzo:Allegro pesante」はグロテスクにスウィングして、巧まざるユーモラスも感じさせる重いスケルツォ。途中3本のサキソフォーンの絡みが幾度もエッチに怪しい。打楽器も盛大に活躍。ロジェストヴェンスキーの表現はなかなか大仰大柄に盛り上がりました。13年前には「魔法使いの弟子」を連想させるとのコメント有。この楽章は傑作!(5:53)
第4楽章「Andante tranquillo」呟くような弦からそっと始まるフィナーレ。それが幻想的に浮遊しつつ、フルート・ハープも加わってゆっくり広がって美しいけれど掴み所がない。やがて荘厳な金管が参入してクライマックス?に迫るけれど、それは力を失いました。ラストに向けて壮絶な締め括りに至るけれど、どうも辛気臭い作品・・・ロジェストヴェンスキーはかなりパワフルでした。(13:29/拍手有) (2025年6月14日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●
▲To Top Page.▲
|