Mendelssohn ヴァイオリン協奏曲ホ短調/
Paganini ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調
(リカルド・オドノポゾフ(v))
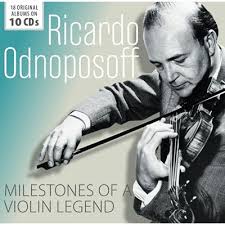 Mendelssohn
Mendelssohn
ヴァイオリン協奏曲ホ短調
Paganini
ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調
ジャンフランコ・リヴォリ/ジュネーヴ放送交響楽団(以上1954年)
Paganini
ヴァイオリン協奏曲第2番ロ短調より第3楽章「ラ・カンパネルラ」(コチャンスキ編)
Prokofiev
「ピーターと狼」より(グリュネス編)(以上ヴァレンタイン・パヴロフスキ(p)1945年)
リカルド・オドノポゾフ(v)
Membran 600476
Ricardo Odnoposoff(1914ー2004亜爾然丁)は若くして戦前ウィーン・フィルのコンマスを務めた人。晩年はおもに教育者として過ごしたらしい。コンサートホール・レーベルの録音?この時期にして予想外に音質は良好でした。
Mendelssohnは誰でも知っている、哀愁の甘い旋律が3楽章途切れずに続きます。第1楽章「Allegro molto appassionato」はいきなりのソロによる第1主題提示、テンポはあわてず急がず、艷やかに美音を強調したり、神経質なヴィヴラートに非ず、音色が美しく上品にしっとり、質実に歌って着実な表現に始まりました。華やかなカデンツァも技巧を前面に強調せず、纏綿に官能的でもない、バランスのあるもの。(12:48)ファゴットの持続音が続いてそのまま荘厳な第2楽章「Andante」緩徐楽章へ。この第1主題は安寧に充ちて切々と歌います。この美しい旋律はMendessonのメロディ・メーカーとしての面目躍如。伴奏は控えめに徹してヴァイオリン・ソロ中心の音録りはやや昔風か。中間部は暗転して重音はいかにもテクニックが要求されそうなことろ。あまりに親密なメロディが続いて、BeethovenやBrahmsに比べてスケールに足らんと感じる方がいらっしゃるかも知れないけれど、この軽み、親しみやすい甘さが持ち味なのでしょう。(8:42)
第3楽章「Allegretto non troppo - Allegro molto vivace」は前楽章の哀しみを引き継いだまま、やがて破顔一笑、第1主題が弾むように軽やかに始まって、それは技巧的なヴァイオリン・ソロに木管がそのままの旋律に絡んで晴れやか。ここもコロコロと旋律が歌って、オドノポゾフの超絶テクニックは余裕でしょう。やがて第2主題がオーケストラからソロに引き継がれ、満面の笑みのままノリノリにテンポ・アップして全曲を閉じました。(5:57)
超絶技巧は当たり前のPaganiniニ長調協奏曲は第1楽章「Allegro maestosoーTempo giusto」から、ベルカントないかにも!風クサい旋律がヴァイオリン・テクニックを駆使して、伴奏はほんの添え物。オドノポゾフは技巧にまったく不足はないけれど、それが上滑りすることもなく、たっぷりの節回しに歌うもの。左手ピチカートとか云々ド・シロウトは詳しくは良う知らんけど、フラジオレットはものすごく繊細でした。それにしてもお下品な旋律連続。(16:30)第2楽章「Adagio espressivo」もニ長調がロ短調に変わっただけで、大仰なクサい旋律なのは変わらない。伴奏も相変わらずずんちゃっちゃな感じ。(5:00)第3楽章「Rondo Allegro spiritosoー Un poco piu presto」は軽快なリズムを刻んで、デーハーなテクニックが次々披瀝されて、ダメ押しのようにオナカいっぱいなラッシュが続きました。(7:00)コンサート・ホール・レーベルにお馴染みなバックにも不足を感じませんでした。 Gianfranco Rivoli(1921ー2005伊太利亜)はオペラ畑の人みたいです。
「ラ・カンパネルラ」はピアノ伴奏版。これも予想外に音質良好。誰でも知っているLisztの旋律がPaganini風モウレツな難曲に変容され、ニ長調協奏曲よりいっそうヴァイオリンの繊細な技巧がわかりやすく浮き上がりました。(4:45)Prokofievはもちろんヴヴァイオリンの技巧に聴き惚れるけれど、Paganiniに比べてそのユーモラスに印影深い旋律の魅力を強く感じさせるもの。(3:16) (2023年8月26日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●
▲To Top Page.▲
|