Mahler 交響曲第7番ホ短調
(エリアフ・インバル/フランクフルト放送交響楽団)
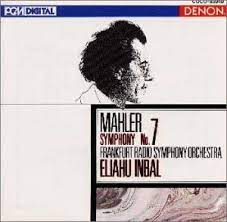 Mahler
Mahler
交響曲第7番ホ短調
エリアフ・インバル/フランクフルト放送交響楽団
DENON COCO7040 1986録音
Eliahu Inbal(1936ー以色列)50歳の記録は音質極上、我らがDENONの録音チームによる無指向性マイクでのワンポイント録音。サウンドや表現は濃厚粘着質ではない。Mahler中屈指の怪しい作品はけっこうお気に入り、第2楽章/第4楽章「Nachtmusik」が「夜の歌」俗称由来。四管編成+11種の打楽器+ハープ2台、テノールホルンなど珍しい管楽器も入るし、ギター、マンドリンはセレナーデ(夜の歌)だから必須、この辺り新ウィーン楽派にまっすぐつながります。初演は1908年チェコ・フィル/作曲者自身による指揮だそう。初演時の評価はいかがだったのでしょうか。現hr交響楽団なかなか優秀なのは当たり前。
気怠く気紛れに扱い難物な第1楽章「Langsam (Adagio) Allegro risoluto, ma non troppo(ゆるやかに)」はテノールホルンの生暖かい、気の抜けたような主題はなんとも妖しい。インバルはくっきり各パート明快に表情や起伏豊かに、美しく表現して、こんな細部明晰な演奏にはなかなか出会えません。この作品イメージつきまとうドロドロさや緩さがない。(22:39)
第2楽章「Nachtmusik I. Allegro moderato(夜曲)」冒頭のホルンの伸びやかに牧歌的な旋律と音色、それが呼び交わして続く管楽器やサワサワとした打楽器の鮮烈な存在感、符点のリズムにしっかりとした足取りは気怠い行進曲風。無遠慮なティンパニも途中乱入してそれはかなり衝撃的でした。各パートのニュアンスの変化をしっかり聴き取れる分離定位明瞭な音質が愉しめます。(14:43)
第3楽章「Scherzo. Schattenhaft(影のように)」揺れ動く3/4拍子。囁くようにさらさらと儚く。淡く駆け抜ける、文字通り”影のよう”なスケルツォもたっぷり怪しく、陰影強弱たっぷりに雄弁。いろいろ特殊奏法が指示されているそうで、バルトーク・ピチカート(fffff指定)やラスト、ティンパニの一撃も意表を突いた締めくくりでした。(10:15)
第4楽章「Nachtmusik II. Andante amoroso(夜曲)」切ないヴァイオリン・ソロから始まって、ギターやマンドリンも登場する「セレナーデ」は静かに、ゆったりと揺れるよう。ホルンもたっぷり朗々と美しく甘く愛の歌を奏でました。後半ラストの爽快なホルンの広がりも印象的に、消えいくように終わります。やがてここから調性をはみ出して新ウィーン楽派に至るのは容易に想像できます。(13:20)
第5楽章「Rondo-Finale. Allegro ordinario」はティンパニとホルンが俗っぽくも賑々しい始まり、心情風景定まらぬ難しい(ようワカラん)フィナーレ。せっかくの前三楽章の風情台なしな、金管鳴り響いて明るくもノーテンキな元気良さ。後半戦金管と種々打楽器との掛け合いも空疎な音楽に感じます。かっちりとアンサンブルはクリアかつデリケート、そして緻密に渾身パワフル入魂にまとめておりました。(16:53)これはこの作品、いままで聴いたうちのヴェリ・ベスト演奏でしょう。 (2024年12月21日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●
▲To Top Page.▲
|