Mahler 交響曲第5番 嬰ハ短調
(キリル・コンドラシン/ソヴィエット国立交響楽団)
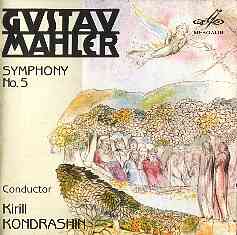 Mahler
Mahler
交響曲第5番 嬰ハ短調
キリル・コンドラシン/ソヴィエット国立交響楽団
MELCD1000810 1974年録音
2017年来の再聴。21世紀の眼の覚めるような音質を種々録音経験済、そしてKirill Kondrashin(1914ー1981露西亜→阿蘭陀)による昔馴染みを再確認したくなりました。雰囲気はあるけれど、全体にややオン・マイク、旧ソヴィエットらしいちょっぴり肌理の粗い録音は時代相応。これはモスクワ・フィルに非ず、スヴェトラーノフの国立交響楽団は粗野に骨太、洗練されぬサウンドは期待通りでした。
第1楽章「葬送行進曲 In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt.(正確な速さで。厳粛に。葬列のように)」冒頭トランペットからエッチ過ぎるヴィヴラートたっぷり、それは他の金管も同様の重量級インパクトたっぷりに際立ちます。(11:04)
第2楽章「Sturmisch bewegt. Mit grosster Vehemenz. (嵐のような荒々しい動きをもって。最大の激烈さをもって)」風雲急を告げる低弦の激しさ、オーケストラを煽ってこれはまさに「最大の激烈」な始まり。憂愁なチェロによる第2主題は曇って抑制的、甘さの欠片もない表現。ま、金管ばかり目立つオーケストラ、うねうねと粗々しい重量級の大爆発は続きます(12:44)
第3楽章「スケルツォ Kraftig, nicht zu schnell.(力強く、速すぎずに)」ここは絶品ホルン・ソロに注目。それに絡む木管の存在感もリアル、レントラーの優雅なリズムをしっかり刻んで、明朗に分厚い金管の刺激的なヴィヴラートに痺れました。トリオの静かに抜いた感じも、その後のヴィヴィッドな勢いの対比もダメ押しのド迫力に締め括りました(16:57)
第4楽章「Adagietto. Sehr langsam(アダージェット 非常に遅く)」ここが一番人気。前楽章の金管炸裂!から一転、金管打楽器はお休み。弦楽器は極上のニュアンス、たっぷりセクシーでした。ここ最高の出来でっせ。楽譜に詳しい人のご教授願いたいけれど、前半にチェロのソロ指定はありますか?(8:10)
第5楽章「Rondo-Finale. Allegro giocoso(ロンド - フィナーレ。アレグロ・楽しげに)」冒頭牧歌的なホルン、ファゴット、クラリネットも浮き立ってリアルな始まり。それを受ける弦も爽やかに、メリハリたっぷりなフィナーレを迎えました。ホルンを先頭に金管はいや増す鋭い雄叫びとリズム、遠慮会釈なき大噴火とテンポの揺れに痺れましたよ(13:50)途中から音質云々不満は吹き飛びました。結果的に昔の印象とそう変わらない。ここ最近、聴いた新しい演奏と比べても最高の出来かも。(2024年10月5日)
●
15年ぶりに再聴いたしましょう。キリル・コンドラシン(1914ー1981露西亜)は西側に亡命したので(1978年)旧ソヴィエット時代に全集を全曲録音できませんでした。(第2番第8番を欠く。第10番、「大地の歌」も)もうちょっと長生きして、バイエルン放送交響楽団のシェフに就任していれば新規全集が叶ったかも。1980年ディジタル以降、バブル時代、そして21世紀にはMahler演奏(録音)は日常となったので、この時期の録音は少々割りを食った感じ、とくに旧ソヴィエット録音には(よろしくないほうに)定評ありますし。ここではオン・マイク、やや繊細さ奥行き、残響に欠けるけれど、金管前面むき出しにリアルな音質、但し、自然な会場空気感には遠いもの。
ソヴィエット国立交響楽団といえばスヴェトラーノフ(1995年録音)しばらく聴いていないけれど、遠慮会釈ない金管爆発のエグさはこちらで本領発揮でしょう。コンドラシンが録音にあたって自由にオーケストラを選べる立場だったのかは不明、仮にそうだとしたらデーハーなド迫力を作品に求めたものか。第1楽章「葬送行進曲(正確な速さで。厳粛に。葬列のように)」からトランペットの肉厚な響きが生々しいド迫力。全63分だからテンポは標準的か。大昔のコメントでは「なんかへん。トランペットの音色がフツウじゃないんですよ。アクがあって、強烈で全体の響きに溶け合わない」と。
現在の耳では「なんかへん」とは感じぬけれど「強烈で全体の響きに溶け合わない」のは事実、金管は少々デリカシーに欠け、個性的エッチ過ぎ露西亜風ヴィヴラートに打ちのめされます。以下、どの楽章でも金管爆発のエグさ、泥臭い賑々しい饗宴連続。第2楽章「嵐のように荒々しく動きをもって。最大の激烈さを持って」〜これこそ作曲者の指示通り”激烈”。ここは低弦の激しい嘆きを分厚い金管がダメ押しするといった風情か。ある時は優しく、ある時は激昂して、うねるような対比は強烈でしょう。コンドラシンの表現はさほどに粘着質とは思わないけど、サウンドが粘っこいなぁ。こんな大仰大柄な演奏って最近まず出会えませんよ。
第3楽章「スケルツォ(力強く、速すぎずに)」は明るく、優雅なレントラー。出足は(そして楽章あちこち)ホルンが愉しげに、朗々と開始しました。その存在感の太いこと!技術的にどーのということじゃなくて、妙にリズム感がぎくしゃくして優雅から少々遠い感じ(でもユーモラス)。この楽章も金管が印象的な活躍ぶり、シカゴ交響楽団辺り都会的な鋭さとはテイストが異なって、もっと重量級でっせ。コーダの前は大人しく、しばらく抑制してラスト、文句なく”金管のための協奏曲”風、テンポアップして締めくくります。
第4楽章「アダージェット(非常に遅く)」。ここが全曲の白眉、しかし自慢の金管(+木管打楽器)はお休み。古くは快速メンゲルベルク(1926年)ブルーノ・ワルター(1938年)の時代より、官能的脂粉が漂うような表現が欲しいところ。6:22はやや速めか、さらりと抑制の効いた、デリケートな弦+ハープであります。この楽章はコンドラシンのモダーンなセンスが理解できるところ、前後の金管に耳が慣れているせいか、静謐さが際立ちました。
第5楽章「ロンド - フィナーレ(快速に、楽しげに)」は明るい楽章ですね。遠いホルンはヴィヴラートが効いて美しい開始、木管の絡みは牧歌的な雰囲気満載の第1主題の開始です。やがて忙しない弦による第2主題があちこちのパートに引き継がれ、華やかに音楽は盛り上がります。余裕のオーケストラの威力を活かして優雅に歌う表現、慌てたり走ったり、妙に力んだりしておりません。やがて金管全面参入へ、これが粘っこい重い音!でも賑々しくも華やか!強烈な泥臭さ。怒涛のフィナーレに満足。 (2017年7月16日)
●
本にしても、CDにしても、ま、酒にしても自腹で〜というのが基本です。自分で金を出さないと、真剣に身に付かない。もう6〜7年FM放送を聴いていないので、廉価盤で手に入らない音源とか、話題の若手の演奏は図書館で借りるようにしております。いちおうの一般教養のつもりだけれど、コンドラシンのMahler はとてもおもしろかったので、掟破りで「外伝」掲載します。
Mahler は好きですね。旋律が美しいし、演奏家によって驚くべきほど違いが出るのも興味深い。録音状態を気にする方面の曲ではあるけれど、旧い録音でも意外と楽しめることも有。「コンドラシンのMahler 」ということ自身「おっ!?」と思えるし、この第5番は普段指揮しないソヴィエット国立響でしょ。看過できません。
これ、相当な違和感溢れる演奏です。とくに第1楽章から、なんかへん。トランペットの音色がフツウじゃないんですよ。アクがあって、強烈で全体の響きに溶け合わない。いや、正直、最初のウチ、すべてのパートが独自の色合いでバラバラのような印象がありました。この曲特有の官能性とか、深い影のある甘さとか、そんな世界とはまったく異なる硬派の音楽。
第2楽章からはもう少しアンサンブルにまとまりが出てくるし、テンションの高さが良い方面に向かいつつあるのを感じました。それにしても、金管の洗練されない無骨なチカラ強さ(というか、なんというか強烈というか)は異形で超個性的。ホルンのヴィヴラートを先頭にして、怪しい響きがゴロゴロ続きます。
「アダージエット」は独自の解釈らしくて、ソロの弦楽器(ヴァイオリン?チェロ?)が出てくるんです。この楽章には、むせ返るようなエッチな雰囲気を求めたいが、アンサンブルの肌理が粗くて、濃密な雰囲気ではない。でも、呼吸が深くて揺れ動くこと、アクセントが個性的であることで、かなり楽しめる演奏です。
終楽章。これもなんかへんな演奏です。オーケストラがちっとものっていないというか「もう帰ろうよ」(むかし、そんな漫才があったな)みたいな感じもあって、コンドラシンが叱咤激励すると突如金管が爆発する、といった風情。アンサンブルはあちこちでギクシャクとして、オーケストラがこの曲に慣れていないのかも知れません。こういった硬質な音色を好む人はいるだろうと想像されますが。
全体に早めのテンポで、あか抜けない演奏振りでしょうか。ソヴィエット国立響のサウンドが良く理解できる演奏でもあります。コンドラシンは正規録音としては第1・3・4・5・6・7・9番が残っていて、どれもなかなか骨があって楽しめます。指揮者は緻密な解釈を求めていると思うが、オーケストラの色合いが(シロウト目にもわかりやすい)ロシア臭プンプンでなんともいえません。「Mahler は聴きすぎて飽きたぜ」といった人々にお勧め。(2002年5月31日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●
▲To Top Page.▲
|