The Dresden Album - ドレスデン宮廷の室内楽作品集(アンサンブル・ディドロ)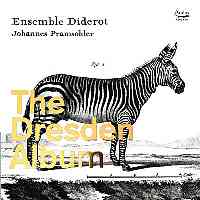 Handel
Handel トリオ・ソナタ ト短調 作品2-8 HMV393 Fux トリオ・ソナタ イ長調 K.340 Fasch トリオ・ソナタ ニ長調 FWV N:D4 Tuma トリオ・ソナタ ハ短調 Telemann ターフェルムジーク(食卓の音楽)第1部/トリオ ・ソナタ 変ホ長調 TWV 42:Es1 Handel トリオ・ソナタ ホ長調 HWV394 アンサンブル・ディドロ/ハネス・プラムゾーラー(v)/ヴァルジャン・ドネイヤン(v)/グルリム・チェ(vc)/フィリップ・グリスヴァール(cem) Audax Records ADX13701 2013年録音(NMLにて拝聴可能) 題して「The Dresden Album」18世紀前半のバロック時代、Bach は別格に魅力的と思うけれど、やや知名度の落ちる作曲家の作品だって、なんとも優雅典雅な響き。3声のソナタ、古楽器の技巧のキレは当たり前に至って、端正に整ったアンサンブルは生真面目過ぎるほど。30年ほど前の記憶にあった、あまり美しからぬノン・ヴィヴラート、素朴どころか素っ気ない響きが夢のような、古楽器演奏の進歩、成果。演奏スタイルはちょいとキレありすぎ、もうちょっとユルく、自由に遊んでも良いんじゃないの? Fux(1660-1741)の躍動する愉悦、Fasch (1688-1758)の優雅な陰影ある風情、Tuma(1704-1774)の作品は初耳だったかも、ほんの短い2楽章は嘆きに充ちてほの暗い魅惑の旋律(フーガ)でした。HaydnMozart 以降のピアノ・トリオより、Barock時代のトリオ・ソナタに多彩な広がりを感じます。馴染みの「食卓の音楽」は上手さ生真面目さが際立って、もうちょっと弾(ハジ)けて欲しいところ・・・2015年初拝聴時にはそんな感想を抱いておりました。 Bachを再発見したのはMendelssohn、Vivaldiは20世紀、Bach研究の中で編曲元作品として再発見されたとか、著名な無伴奏チェロ組曲は巨人・パブロ・カザルスが芸術作品として光を当てたのが名曲として地位確立の嚆矢であった・・・とかなんとか(そんな要らぬ薀蓄さておき)こどもの頃の出会いからBarock音楽は大好き、LP時代には稀少な音源だったものも、CD時代、そしてネットよりデータ拝聴時代に至った現在、まだまだ未知の音楽が溢れている!そんな魅力発見の日々がやってきました。ちょうどアナログ→ディジタルというのは偶然、古楽器隆盛と軌を一にしているのですね。 Handel トリオ・ソナタ ト短調は緩急緩急4楽章、哀愁の旋律はオン・マイクな音質にヴァイオリン2本、表情豊かに朗々歌われます(とくに第3楽章「Largo」わずか2:29)。「急」楽章に於ける集中力も息苦しいほど。Fux トリオ・ソナタ イ長調も緩急緩急4楽章、これは時代のスタイルなんでしょう。典雅な出足はすぐに哀愁の色を深めて、この陰影もBarock音楽の魅力のひとつ。第2楽章「Allegro」の晴れやかな躍動の愉しげなこと!第3楽章「Adagio」のしっとりもの哀しい風情から一転、終楽章「Allegro」の軽快なリズムに破顔一笑であります。通奏低音のリズムもみごと。わずか10分に充たない名曲でっせ。 Fasch トリオ・ソナタ ニ長調。第1楽章「Andante」ゆったり安らぎに歌い交わすヴァイオリン2本、この2:58は収録中の白眉でしょう。続く第2楽章「Allegro」はあまり急がず、ノリノリのリズミカルな音形繰り返しはBachを思い出させてやはり、これは時代のスタイルなのでしょう。第3楽章「Affettuoso(感情を込めた)」はしっとりとした情愛を感じさせるわずか2:20。終楽章「Allegro」もあわてず、ゆうゆうと余裕の歌でございます。Tuma トリオ・ソナタ ハ短調はわずか2楽章5分半ほどの短い、この収録中際立つ哀愁の作品。第1楽章「Adagio」の重苦しい出足、第2楽章「Alla breve-Adagio-Alla breve」は躍動的なフーガがカッコよく、アタッカでAdagio(ごく短い)再びフーガに戻る・・・なるほど、やはり緩急緩急のパターンだったのですね。 Telemann トリオ ・ソナタ 変ホ長調には他の作品とは一線を画す多彩さ、作品としての大きさ、面白さがあると思います。ヴァイオリン・ソロの妙技性、通奏低音の自在な動き(第2楽章「Vivace」に顕著)、第3楽章「Grave」の複雑な表情(重々しくゆるやかに〜語源は墓?)、終楽章「Allegro」がリズムが通り一遍ではないアクセントがありました。ラスト、Handel トリオ・ソナタ ホ長調は彼らしいノンビリとしたゆったりとした表情にほっとする第1楽章「Adagio」。陰りのない第2楽章「Allegro」の明るさ、シンプルな軽快さ、第3楽章「Adagio」の繊細な哀しみ、第4楽章「Allegro」には一点の陰りもありません。ヴァイオリン・ソロの躍動も聴きもの。 全体として前回拝聴ほどの硬さ、息苦しさは感じませんでしたよ。古楽器としての表情の豊かさ、たっぷりとした響きを堪能いたしました。 (2016年5月7日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】●愉しく、とことん味わって音楽を●▲To Top Page.▲ |