Debussy 交響的組曲「春」/サキソフォーンと管弦楽のための狂詩曲/
クラリネットと管弦楽のための狂詩曲/レントより遅く/バッカスの勝利/
劇音楽「リア王」(ルイ・ド・フロマン/ルクセンブルク放送管弦楽団)
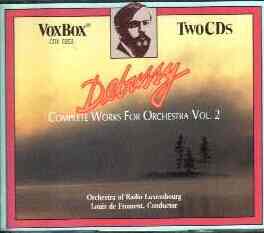 Debussy
Debussy
交響的組曲「春」(Busser編)
マリレーヌ・ドース(p)
ピアノと管弦楽のための幻想曲
マリレーヌ・ドース(p)
サキソフォーンと管弦楽のための狂詩曲(Roger-Ducasse編)
ジャン・マリー・ロンデクス(sax)
クラリネットと管弦楽のための狂詩曲
セルジュ・ダンガン(cl)
レントより遅く
カテリーナ・ツラトニコヴァ(ツィンバロン)
バッカスの勝利
劇音楽「リア王」(Roger-Ducasse編)
ルイ・ド・フロマン/ルクセンブルク放送管弦楽団
VOXBOX CDX5053(録音年不明/1973年初出)
これは懐かしいVOX4枚分/3枚目、協奏的な作品を揃えたもの。いったい幾度聴いたのか?前回拝聴は2010年。特別に新しい発見もない、安心して聴ける昔馴染み的存在でした。
若く貧しかった頃は「とにかく安いものを!」求めて、知名度世評など二の次、音楽はまず聴いてなんぼ、それ以来のお気に入り演奏と作品。やがて幾星霜。Louis de Froment(1921-1994仏蘭西)は廉価盤専門の指揮者?そんな勝手なイメージは極東日本の片隅の音楽愛好家(≒ワシ)の失礼な言い種。録音情報はとうとう探せず、一部1954年との表記を見掛けたけれど、それなり良好な雰囲気ある音質水準を考えると誤りと思います。ルクセンブルク放送管弦楽団(現ルクセンブルク・フィル)はホルンのヴィヴラートなど金管はかなり仏蘭西風情たっぷり、ちょいとローカルな味わい深いサウンドを堪能させてくださいました。こんな作品はあまりかっちりし過ぎないほうがよろしい。Debussy中知名度いまいちなの作品ばかり揃えて、どれも名曲に間違いなし。
「春」は若い頃の作品、オリジナルは消失して後年Henri Bu"sser(1872ー1973仏蘭西)が編曲したものだそう。薄靄がかかったように気怠く静謐、セクシーな管弦楽(とくに管楽器の音色)に吐息のように控えめなピアノが絡みます。(16:34)
「幻想曲」はなんとも夢見るように甘く、しっとりとした「Andante ma non troppo」(15:16)呟くようにデリケートな「Lento e molto espressivo - III. Allegro molto」ラストは軽快に晴れやか、小粋に締め括りました。(8:43)美しく可愛らしい協奏曲は絶品ですよ。Marylene Dosse(1939-仏蘭西)はVOXに多く録音を残しておりました。
名手Jean-Marie Londeix(1932ー2025仏蘭西)によるサキソフォーン狂詩曲は背筋がゾクゾクするような極上の遣る瀬なさ、エッチの極みに切ない美音は時に雄弁、気紛れな管弦楽が絡みます。(9:43)
Serge Dangain(1947-仏蘭西)はオーケストラのメンバーでしょうか?クラリネット狂詩曲は素直に、ちょっぴり線の細いクラリネットが控えめに歌います。(7:54)
「レントより遅く」はツィンバロンの響きがなんとも妖しく揺れる切ない、儚いレントラー?昔から大好きな作品、オリジナルはピアノ曲でした。(4:33)「バッカスの勝利」は勇壮なファンファーレと行進曲風、やがて静かに収束します。(4:40)劇音楽「リア王」は不安げかつ剽軽な風情から、いかにもこれから事件が起こりそうな劇的な旋律は華やか。(3:31) (2025年3月15日)
●
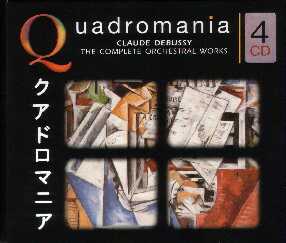 Debussy
Debussy
交響的組曲「春」(マリレーヌ・ドース(p))
ピアノと管弦楽のための幻想曲(マリレーヌ・ドース(p))
サキソフォーンと管弦楽のための狂詩曲(ジャン・マリー・ロンデクス(sax))
クラリネットと管弦楽のための狂詩曲」(セルジュ・ダンガン(cl))
レントより遅く(カテリーナ・ツラトニコヴァ(ツィンバロン))
バッカスの勝利
劇音楽「リア王」
ルイ・ド・フロマン/ルクセンブルク放送管弦楽団
クアドロマニア 222125-444 1972年(?)VOX録音 4枚組1,380円(総経費込)ほどで入手
ただでさえノーミソ前頭連合野の衰退+猛暑、愛用のメイン・パソコンが故障(修理中/昨日復活)でサイト原稿苦戦しております。受け付ける音楽の幅がどんどん狭くなってしまって、Beethoven 交響曲第5番ハ短調(ジョージ・セル/コンセルトヘボウ管弦楽団1964年)は立派な、すばらしい演奏との手応えはたっぷりだったが、聴き手の緊張感集中力が続きません。シャルル・ミュンシュ/ボストン交響楽団によるDebussy(夜想曲/春1962年)を聴いていて、嗚呼こちらのほうが精神(ココロ)にフィットするな、交響組曲「春」ってこんな美しい旋律だっったっけ・・・?
・・・ルイ・ド・フロマンの4枚組を思い出しました。以下の2枚組は処分済で4枚組を再入手したもの。既に1枚目には言及済。
貧しきものは幸いなれ。
1990年頃、VOXBOXはもっとも安いCDだったし、演奏者は(少なくとも日本では)無名、そして音質の劣悪さはLP時代からお気に入りでした。まず作品をしっかり聴きましょう、といった謙虚な姿勢が大切だったんです。慣れもあるんでしょう、結果的にこうして20年を経、数度転居し、オーディオ環境は変化し、徒に馬齢を重ねた結果、これは稀有な価値を持った演奏であることに気付きました。シャルル・ミュンシュとかジャン・マルティノン、ヤン・パスカル・トルトゥリエなどあちこち聴いた上での結論。
一糸乱れぬアンサンブル、どっしりとして重厚なる迫力サウンドを称揚する風潮は多いようだけれど、仏蘭西音楽だったら、それだけではあかんでしょう。この一枚は独奏楽器を含む協奏的作品が多く収録され、なかなか(薄)味わい深い出来上がりとなっております。音質だってそう悪くはない〜雰囲気(だけは)たっぷり。上手すぎないのがよろしい。
交響的組曲「春」は、囁くように繊細な幻想的旋律であって、ピアノはアルペジオにて控えめに参加。もともと女声合唱が加わっていたらしいけど、楽譜を火事で消失、Bu"sserが管弦楽に復元したとのこと。”官能的、そして爽やかな春の暖かさ、懐かしさがちゃんと存在する”とは5年前のコメントだけれど、その通り。但し、”洗練されていないし、安っぽくうるさい響きに”というのは賛同できない。雰囲気たっぷりの”薄さ”であります。ふわふわ、いつまでも雲上の世界に遊びたい気分。
これが、「ピアノと管弦楽のための幻想曲」なるとマリレーヌ・ドース(VOXに多く録音を残すが詳細経歴不明)が大活躍〜それは淡々として、神経質ではないが、けっして線の細いものではない、しっかりとした明晰タッチ。作品は明快でわかりやすい(まちがいなく協奏曲/全25分)。第1楽章「アンダンテ」はソロとオーケストラは掛け合って朗々と快活だけれど、その粋で華やかなる味わいは独墺系とは異なる対話でしょう。第2楽章「レント」は浪漫的かつ静謐であって、ピアノは従に回ります。この辺りオーケストラとの静謐幻想的な絡み合い、好きだなぁ、最高。
終楽章「アレグロ」は快活上機嫌に作品は進みます。颯爽とカッコ良く、快速細かい旋律にはあくまで力みが見られない。金管木管、そして弦も響きは薄いが雰囲気たっぷり。滅茶苦茶上手い!といったことではないが。
サキソフォーン、クラリネットをソロとした幻想曲は、二人ともほとんど超絶技巧。ロンデクス(1932年〜)はジャン・マルティノンの全集でもソロを担当していて、仏蘭西風エキゾチックな脂粉漂う官能的妖しい音色の第一人者。ダンゲイン(読み方が違うのか?DANGAIN)は見知らぬ名前だけれど、軽妙華やかな高音が特徴でしょう。あきらかに独墺のオーケストラに聴く音色とは別世界。颯爽と軽々と、そよ風のようなクラリネット。
「レントより遅く」も粋な風情が漂って、ツィンバロンの幻想的なソロが華を添えます。ワルツはRavel が名曲を二つ残して、わずか4分半の静かな、そっと消え行くように妖しい、はかない旋律。
VOX盤と収録順を変え、「バッカスの勝利」「リア王」というソロを含まない作品をラストに集めたのは配慮だと思います。前者は勇壮なファンファーレであり、後者はユーモラス、かつ不安げ細かい旋律から、勇壮な旋律が堂々と登場します。どちらも映画音楽みたいでわかりやすい。アンサンブルに対する不満は感じませんでした。 (2010年8月26日)
●
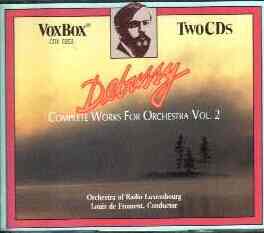 Debussy
Debussy
バッカスの勝利
交響的組曲「春」
ピアノと管弦楽のための幻想曲(ドース(p))
サキソフォーンと管弦楽のための狂詩曲(ロンデクス(sax))
クラリネットと管弦楽のための狂詩曲」(ダンゲイン(cl))
レントより遅く(ツラトニコヴァ〜ツィンバロン)
劇音楽「リア王」
スコットランド行進曲
おもちゃ箱
カンタータ「放蕩息子」より(仏語読めず)
交響的断章「 聖セバスチャンの殉教」(ナレーターと女声合唱入り)「ユリの園」「魔法の部屋」「異教神たちの宗教会議」「傷つけられた月桂樹」
英雄の子守歌
ルイ・ド・フロマン/ルクセンブルク放送管弦楽団/アンサンブル・ヴォーカル”Pesallet de Lorraine”/ジャック・ナヴァディック(ナレーター)
VOXBOX CDX5053 1972年録音 2枚組1,800円ほどで購入か/このCDは処分済
VOXはまだ息長く続いているようで、最近は価格相場もこなれてきたようです。Mozart のピアノ協奏曲集は、久々に購入したこのレーベルのCDとなりました。このDebussyは(p)(c)1991となっているから1990年代前半、個人的には未だLPに未練を残している頃の購入かと思います。もう2枚、比較的知名度の高い作品を収録したセットがあったはずで、そちらは購入しておりません。この度、QUADROMANIAで復活していて山尾さんのブログで取り上げられたのをキッカケに再聴しました。Debussyに造詣の深い人々には、以前から話題になっていたらしい音源。
同曲異演ばりばり購入しちゃうワタシとしては偶然出会いがなかったのか、この少々知名度の低い作品は十数年間、こればかり聴いてきました。昨年(2004年)だったか、ようやくマルティノン盤を購入したら(協奏的作品+おもちゃ箱が含まれる2枚)サキソフォーンがロンデクス(LONDEIXではなくLONEIXとなっているが?)、クラリネットもダンゲインだけれど、これは名前が異なりました。(こちらSERGEと、あちらGUI)ま、珍しい作品収録、ということかな?「バッカスの勝利」は初期珍曲らしいし。(3:31)勇壮でわかりやすい悲劇っぽいが、演奏は上質とは言い難い。
「春」は、あまり演奏される機会は少ないですか。「牧神」風のテイストが妖しくて、官能的、そして爽やかな春の暖かさ、懐かしさがちゃんと存在する。ピアノがとても効果的。洗練されていないし、安っぽくうるさい響きになっちゃう(録音の加減か?)こともあるが、ホルンのヴィヴラートもホンワカ雰囲気があって、カルめのサウンド。(15:14)
Debussyの協奏的作品もあまり演奏機会がないでしょうか。「幻想曲」に於けるドースのピアノは、まったり暖かく華やかだけれど神経質ではない。充分な技巧は親しみやすい旋律(「春」のイメージが持続する)を充分引き立てて、浮き立つような味わいが続きました。うんとさっぱり、静か、音符の少ないRachmaninov 風イメージか。ハックにはなんの問題もないと思います。(16:31)ロンデクスのサキソフォーンは、妖しさ満点でセクシー。(完璧にコントロールされた音の技巧)こんな楽器、いかにも近代仏蘭西風でして、他の木管群が東洋風のエキゾチックな旋律で絡みます。(9:38)
ダンゲインのクラリネットは、明るくカルく、いかにも仏蘭西系の響きが快い。剽軽な細かい音型がバックと呼応して楽しい作品です。(7:52)「レントより遅く」は、華麗でゆったりとしたワルツ(管弦楽版)だけれど、ツインバロンの響きには夢見心地の儚さがある。(4:30)「リア王」の音楽はファンファーレで始まり、いかにも王様が入城するような気高い旋律でした。(4:38)以上一枚目は、オーケストラがヘロいと感じることも少なく、ちゃんと楽しめましたよ。
●
スコットランド行進曲は快活な表情(6:12)、「おもちゃ箱」は29:20に及ぶ大曲だけれど、細かいエピソード盛りだくさん風で、少々全体像がわかりにくい作品ですか。それこそ、おもちゃ箱をひっくり返したような多種多様な(短くも楽しげな)旋律が次々登場します。やはりピアノが効果的に使用されております。(マリレーヌ・ドースなのだろうか)ちょっと「こどもの領分」を連想しましたね。「放蕩息子」はカンタータのはずだけれど、ここでは4:16オーケストラのみの演奏。これも東洋的エキゾチックな旋律が美しい。
さて、山尾さんも酷評していた「聖セバスチャン」の女声合唱は如何。全4曲21:17。「ユリの園」に繊細な旋律に女声がやがて絡むが、「女声コーラスが、なんか悪いものでも食ったか?というくらい下手」と迄は聞こえない(少々情けない感じは有)のは、ワタシの不勉強故でしょう。録音もそうデッドとは思えない。比較対照がないからなぁ、これだけ10年以上時々聴いて馴染んでますから。ナレーターが(意味当然わからんが)それらしい雰囲気を盛り立てます。
「魔法の部屋」は繊細かつ幻想的であり、「異教神たちの宗教会議」の「ファンファーレ」は金管とティンパニ(なんとなく間が抜けてパッとしないが)が荘厳です。「傷つけられた月桂樹」はヴィヴラートの掛かったホルンが静かに、不安げな弦に乗って囁くと、ダメ押しのようにワケありげな(意味理解できず)ナレーターが乱入。いやぁ、この作品(原曲)の筋はもちろんのこと、そちら辺りの宗教関係にも疎い人間なので、純粋に旋律と雰囲気を楽しませていただきました。
「英雄の子守歌」は3:57の短い作品です。慰安に充ちた静かな旋律だけれど、おそらくは演奏者の問題で様子がわかりにくい。全体として、線が細いというか、響きが痩せた情けないオーケストラであり、リズム感にも少々難有。でも、なんとなく、それらしいホンワカとした雰囲気はあって、他の録音も一度は聴いてみたいなと思わせます。ちなみに「夜想曲」は以前に聴いておりました。無理して「聴け!」というような録音でもないでしょうが。音質は並程度。 (2005年6月3日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●
▲To Top Page.▲
|