Mahler 交響曲「大地の歌」
(クラウス・テンシュテット/
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団)
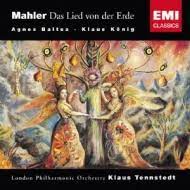 Mahler
Mahler
交響曲「大地の歌」
クラウス・テンシュテット/ロンドン・フィル/アグネス・バルツァ(ms)/クラウス・ケーニヒ(t)
EMI CDC7 54603 2 1982/84年録音
20年ぶりの再聴。音質状態も含め、受け止め方がどう変わったか自身で興味深いところ。ブルーノ・ワルターの1936年ライヴを感銘深く聴いて、もっと音質的に条件整った演奏を聴きたくなりました。このCDを入手した時には音質的に空間の広がり、伸びが足らぬと感じたもの。今回拝聴はさほどに不満は覚えず、やや薄いけれどそれなり艶のある鮮明な解像度と受け止めました。漢詩にそれなり馴染んでいる日本人として、この東洋的な諦観を感じさせる旋律(音階)直接言葉の意味は理解できないけれど、題名や訳から連想される雰囲気風情意味合いをたっぷり感じ取って大好きな作品。Klaus Tennstedt(1926ー1998独逸)は20世紀中に亡くなったけれど、Klaus Ko"nig(1934-独逸)Agnes Baltsa(1944-希臘)はご健在みたい。録音当時は脂の乗り切った頃でしょう。四管編成に多種多様な打楽器+ハープにマンドリン、チェレスタ迄入る大編成となります。
第1楽章「大地の哀愁に寄せる酒の歌」(李白「悲歌行」)はホルンの叫びから始まるテナーのシニカルに切迫した歌。金管の迫力には定評のあるロンドン・フィルは音質の関係か少々薄め?細めに感じます。いつもながらテンシュテットの悲劇的な鋭い表現、クラウス・ケーニヒはまっすぐな歌声、曲調や指揮者の表現に似合った鋭さがありました。酒に酔い、生も暗く、死も暗いと嘆きます。(9:48)第2楽章「秋に寂しき者」(銭起「效古秋夜長」?)太陽の光が衰え、冷たい風が吹き、花からは甘い香りが消えた秋の寂しさをしっとり歌う女声ソロ。寂しげな弦、木管を中心とした伴奏に凛としたバルツァの声も端正でしょう。(9:56)
第3楽章「青春について」(李白「宴陶家亭子」)いかにも東洋的な旋律(五音音階なんだそう)にユーモラスに明るくテナーが歌います。小さな池に建つ東屋(あずまや)に友人が着飾り、呑み、語る。池に東屋が逆さに映る。(3:10)第4楽章「美について」(李白「採蓮曲」)バルツァによる優しい、穏健な歌が流れます。若い乙女たちが花を摘んでいる。途中、馬に乗った若者が登場するところは賑やかに晴れやかに、この部分はかつてバーンスタインを聴いた時にその圧巻の爆発対比に驚いたところ。テンシュテットの疾走もなかなかのもの。この辺りの管楽器にはいまひとつの厚みが欲しいところ。(7:30)第5楽章「春に酔える者」(李白「春日酔起言志」)ここは第3楽章「青春について」に似てユーモラス、また第1楽章冒頭のホルンにもインスパイヤされた始まり。ここの木管金管の絡み合いのみごとさ、のびのびとしたテナーの晴れ晴れとした酒への讃歌。Der Vogel zwitschert: Ja!(鳥が囀ってる、そう)に呼応するオーボエがしっかり聴こえるか注目。太古ユリウス・パツァークの無頼に比べるとずいぶんと生真面目な男声歌唱でしょう。(4:44)
第6楽章「告別」(孟浩然「宿業師山房期丁大不至」/王維「送別」)ここが長大なるクライマックス。低音楽器と銅鑼に始まる不気味なフィナーレ、オーボエは交響曲第9番ニ長調にそのまま名残を継続します。女声は自然への賛美、そして別れをしっとり、延々とていねいな抑制に歌って、ここのフルート先頭に木管の詠嘆はモロに東洋風に絡みます。キャスリーン・フェリアーによる濃厚な太いヴィヴラートが刷り込みだけど、アグネス・バルツァの歌はずいぶんとモダーンなバランスを感じさせて、これがひとつの完成形でしょう。テンシュテットのデリケートな切れ味、悲痛な集中力も素晴らしい。Mahlerフィナーレのいくつかは万感胸に迫ります。(31:27) (2024年3月2日)
●
このCDを聴いたのは3年以上前かと思うけれど、再聴するとかなり下記と印象は変わっております。オーディオ装置は当時と基本変わっていないけれど、部屋の配置のせいか、「響きが乾き気味で、痩せて聞こえます。低音も弱い」という印象ではない。「なにかが足りない。例えば色気?怨み?退廃!心の底に澱んだもの」「ようはするに『カル』い」〜なに勝手なこと言ってるんだか。自分のサイトにも数回「音質問題」言及した(例えば第2番「復活」)が、修正が必要かも。
結論的に音質は鮮明です。但し、中低音に芯があって、奥行きあるホールトーンの残響が・・・という方向ではない。これだけ艶と鮮度があれば文句ないでしょ。テンシュテットの表現は明晰で神経質、そして切迫した悲劇みたいなものを感じさせます。ひとつひとつの旋律に魂を込め、一ヶ所たりとも流した表現など存在しない。ワタシは「大地の歌=ウィーン・フィル」といった先入観があるから、ホルンやら木管やらにややカルさを感じるが、これは純粋に個性の問題、好みの世界でしょう。ジミで重〜い音ではないが、それが致命的な弱点は思われないし、ましてや技術的な不備など存在するはずもない。
声楽方面のことは(まったく)勉強不足だけれど、「大地の歌」ならフェリア以来(正直、馴染むのに時間が掛かった)歌い手になんらかのコメントを付けたくなります。バルツァは知的で凛として(昔と同じ評価だ!)、表現は抑制され大仰にならない。楽章ごとの表情の変化は着実で、感情過多に陥らない。常に抑制を感じます。オーケストラとのバランスも完璧。これは交響曲です、といった知性でしょうか。
ケーニヒは声量的に少々苦しいですか?でも、ユリウス・パツァーク(ワルター1952年盤)でこの作品に出会っているから、「大地の歌」のテナーはこんなもんか?とも思います。もっと抜いたり、囁いたり、そんな余裕の表現が欲しいところ。
最終楽章「告別」へ。「色気?怨み?退廃!心の底に澱んだもの」を求める、ってこの楽章のことだったのか。バルツァの歌はあくまで明晰で冷静(表現としては完璧)、テンシュテットの表現も底光りのするような怜悧な情熱があって、むせ返るような浪漫の茫洋とした陶酔と香気・・・とは方向が異なります。当時は、この演奏の真価を理解できなかったんです。
オーボエは妙に冷静であり、ホルンはよそよそしい。弦は神経を逆なでるように語ります。各々美しいけれど、溶け合わない。響きは豊満ではない。(数年前のワタシはここが不満だったのか?おそらく)粛々淡々と歌い続けるバルツァ、透明さと冷静を失わないオーケストラは、そのまま青い炎となって聴き手のココロを燃やします。精緻なアンサンブルは、美しい。 繊細で神経質、非情な「大地の歌」でしょうか。これも充分魅力的でした。(2004年10月29日)
クラウス・テンシュテットをガンで失ったことは誠に残念。あと10年長生きして、ドイツ系のオーケストラで活躍して欲しかったもの。ドレスデンとか、バイエルンでもよろしい。LPOは立派なオーケストラだし、テンシュテット当時の蜜月時代を評価しない訳じゃないが、EMIの録音水準もあって響きの薄さが気になります。彼のMahler の全集は貴重な遺産だけれど、手放しで評価できないのも事実なんです。
ワタシの安物のオーディオでは、極細部の鮮明さより、音の芯というか、中低音が豊かに広がりを持ってくれると聴きやすい。EMIは全般にそうだけれど、この全集は響きが乾き気味で、痩せて聞こえます。低音も弱い。この「大地の歌」は、そのなかでも相対的に聴きやすい音質。でも、そのことは演奏とは関係ないのは当たり前。
テンシュテットのMahler はどれも音が泣いていて、胸に悲劇的な物語がズシンと来ます。この作品の白眉は30分を越える「告別」でしょう。バルツァの声質は凛として、知的な抑制が利いていて、ひとつの理想をみるような思い。オーケストラはため息と詠嘆の連続のような旋律を切々と歌って、切々と胸を打ちます。アンサンブルも緊密。どこに文句があるのか?
細部まで、どのパートも指揮者の意向が行き渡っているのは事実でしょう。しかし、ワタシの先入観には「ウィーン・フィル」がある。LPOの木管に文句などありません。清潔な音色で良く歌われ、旋律に感じ、充分に美しい。でもなにかが足りない。例えば色気?怨み?退廃!心の底に澱んだもの。そんな余計なことを勝手に求めるのは、ワタシの個人的趣味の問題だけれど、テンシュテットの指揮ならオーケストラにもその響きを求めたいもの。
ようはするに「カル」いんです。オーケストラの技量云々のことを言っているわけじゃない。クレンペラー盤におけるウィーン交響楽団(VOX)なんて、雰囲気タップリで悪くないし、(同じEMI録音の)パウル・クレツキ/フィルハーモニア管に「カル」さは感じない・・・なんて、ケチ付けるばかりだけれど、立派な演奏に間違いないのも事実。LPOファンの方々申し訳ありません。
ここでネタ切れ。で、追加。「大地の歌」はお気に入りだけれど、そう珍しい音源を所有していません。
ジュリーニ/ウィーン・フィルハーモニー/ファスベンダー(ms)/アライサ(t)
1987年1月18日 楽友協会大ホール・ライヴ(FM放送よりエア・チェック)・・・・・ジュリーニのスタジオ録音は、たしかベルリン・フィルでしたので、珍しいかも知れません。ベルリン・フィルとの録音は一度しか聴いたことがないので比較不能ですが、上記LPOとの違いは歴然。
細部まで明快、鮮明、極限迄ていねいに歌い込んでいく表現はいつも通り。特別エキセントリックなところは見あたらないが、全編にただよう(巧まざる)悲壮感の深さはいったい何?ウィーン・フィルの団員が、ひとりひとり自発的・個性的に旋律に精気を与えていくオーケストラの底力。極上の美しさ。
安物のカセット、しかも10年以上前のFMエア・チェックという悪条件でも鑑賞に差し支えないどころか、EMI録音よりずっと聴きやすいのはどうしてでしょうか。 (2001年8月10日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●
▲To Top Page.▲
|