Bruckner 交響曲第7番ホ長調
(ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグ交響楽団)
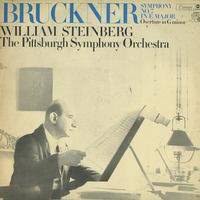 Bruckner Bruckner
交響曲第7番ホ長調
ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグ交響楽団
Command Classics 1968年録音
William Steinberg(1899-1978独逸→亜米利加)はピッツバーグ交響楽団の音楽監督を長く務めて(1952-76年)日本ではあまり人気知名度はありませんでした。自分が入手した音源はLP復刻2枚組より、音質は曇って音の状態はさほどによろしくないけれど、低温はしっかり。オリジナルは優秀録音だったはず。2005年に拝聴、更に2012年に再聴して
独墺系サウンド表現に聴き馴染んでいると、亜米利加のパワフル金属的な明るい響き、ストレートな表現はイン・テンポ?に非ず、9曲中美しさ際立つ作品は妙に空疎に響きます。オリジナル適正再生だと印象変わるのかも知れないけれど、この時期にして音質もいまひとつ。(「音楽日誌」より)
当時は未だネット上で意見のやり取りが盛んだった頃、今やClassic Musicヲタクも華麗なる加齢に大人しくなったのでしょうか。この演奏は当時より評判がよろしくないようでした。この作品はBruckner中、屈指の美しい旋律を誇る名曲。以前のイメージでは金管が明るすぎる印象だったけれど、そうでもない感じ。
第1楽章「Allegro moderato」から諄々と説得力たっぷりな美しい旋律を歌って、テンポはちょっぴり前のめりに中庸、間はしっかり取って素っ気なくも飾りの少ないストレート表現。イン・テンポが基調、ピッツバーグ交響楽団の金管パワーもリズムも重量級でしょう。(18:01)
この作品の白眉である第2楽章「Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam」。デリケートな弦は寄せては返す波のような静かな詠嘆、ちょっと淡々表現過ぎるけれど説得力は充分。ここもイン・テンポが基調、みごとなクライマックスに至って金管炸裂(以前に指摘したように)ティンパニの序奏が最高潮の爆発直前に長くクレッシェンドしました。ラスト金管の収束は以前だったらその明るい音色が我慢できなかったところ。今回の印象に違和感はありません。(21:22)ラスト、ちょっぴりオフ・センターっぽい揺れが気になるのはLP復刻ならでは。
ところがBruckner作品のキモである第3楽章「Scherzo: Sehr schnell」にはキレのある低音のアクセントがちょっぴり足りない?ちょっと前のめりっぽい熱気が疾走して、ここでの金管はいかにも亜米利加の明るい、軽い音色が気になります。パワーは充分だけど、やっぱり素っ気なく、落ち着かない。(8:41)
第4楽章「Finale: Bewegt, doch nicht schnell」はちょっと一本調子?やや落ち着かず流した軽い感じが残念でした。このフィナーレはもともと、なかなかの難物。もっとじっくり表現のニュアンスや幅がもう少し欲しいところ。(12:23)
LP2枚の余白に収録された序曲ト短調は1863年最初期の習作とのこと。緊迫感と優しい歌の対比もあってノリノリ、もっと演奏されてもおかしくない作品でした。1863年改訂版出そうだけど、どこがどう変わったのかわからない。他にも幾種か版があるそう。Wikiには14分ほど?となっていて、このテンポは快速なのでしょうか。馴染みの薄い作品なのでわかりません。(9:56) (2024年10月19日)
●
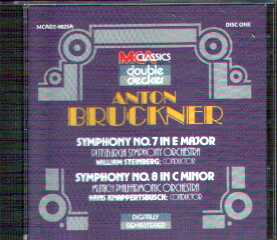 Bruckner
Bruckner
交響曲第7番ホ長調
ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグ交響楽団
MCA MCAD9825A(Command原盤) 1968年録音 2枚組$3.98にて購入
今となっては珍しい存在であり、2004年頃当BBSでちょっと話題になった音源でして
聴きました。7番は、取り柄の無い演奏と言えば言い過ぎでしょうか?(K氏)
とのこと。ワタシは「正直、ワタシ、スタインバーグ盤を数年ぶりに聴いたけれど、非常に感動しました」と反応〜「音楽日誌」では、
この演奏家組み合わせは、「運命」「田園」のLPで馴染んだ中学生時代以来の感想だけれど、オーケストラの響きがカタく、金属的と思います。スタインバーグはストレート系の表現一本槍で、第1楽章など落ち着かないテンポであまりに素っ気ない(Brahms でもそう感じる)。
オーケストラの音色も「Brucknerに期待したい地味渋系」(なんせアメリカの工業都市だし)じゃないし、どうしよう、なんて思っていると第2楽章以降の虚飾ない自然体が胸を打ちます。誠実でまっすぐ。(ところで第2楽章アダージョのサビではシンバル目立たず、ティンパニ大爆発の前に助走ロールが付いている)これはこれで「無為の為」の境地に達していて、誠実な演奏でした。
と、少々コメント。
Brucknerに関しても鋭い拘りを持たれていらっしゃる、B氏からは詳細書き込み有。
以前聴いた感想そのままの演奏でした。
緩急自在で面白く聞かせるという点では彼らの時代のお作法なのですが、ブルックナーの音楽が受容されていない時代はともかくとして、十分聞き込まれている現代においては苦笑する部分なしとはしません。今でもたまに使われるマーラー・ブルックナーという言葉、これは単純に二人の長大な交響曲をつくった作曲家をさして言う言葉で、受容度が低かった時代、教養主義的観点から一部のドイツ系やユダヤ系指揮者が熱心に紹介していた頃にゴッチャに使われていたわけですが、スタインバーグの7番はマーラー的な演奏のように思います。
速度変化の指示を的確に捉えるばかりでなく、独自にもブレーキ・アクセルをきかせています。そのような関係で第一楽章やフィナーレのラスト部分のアチェレランドする部分では8番交響曲のフィナーレ冒頭を思わせる音色はユニークですが、好みではありません。アダージョはなかなか出来が良く、メロディーがしっかりしている音楽ゆえ、やりやすいこともあったのでしょう、よく歌っている演奏です。
オーケストラの音色が溶け合わない録音は残念ですが、マルチマイクのおかげで低音(特にチェロ・コントラバス)の動きが明確に捉えられていて、勉強になりました。
ま、これ以上付け加えることもないんだけど、いちおう自分のサイトなので蛇足を少々。
ドレスデンとかコンセルトヘボウなどを念頭に置くと、やはりピッツバーグ響の音はBruckner向けではないでしょう。少々、金属的でカタいし、明る過ぎる感じ。(とくに金管がイメージと異なる)第1楽章は、細かい表情を付けてはいるが、いかにも「イン・テンポ」(ほんまの意味は違うんだろうなぁ)というか、やや早めで機械的な進行と感じました。そっけないが、けっこう努力賞か。とてもわかりやすいBruckner。
この作品中の白眉である「アダージョ」〜ここがよく歌って、瞑想的な味わいも深い。弦もホルンもヴァーグナー・チューバも(う〜んと)魅力的な音色とは思えないが、誠実にしっかり演ると見事なる成果を生む典型、といった感じでしょうか。曲が進むにつれ「このオーケストラの音色は・・・」云々は忘れ去ります。先にも書いたけれど、サビでのシンバル目立たず、ティンパニ大爆発の前に助走ロールが付いておりました。(ノヴァーク版ですか?いえ、その辺りのことには疎いのですが・・・)
スケルツォのリズムは元気よいが、少々テンポは揺れ、弦も泣き、生き生きとした、かなり濃厚な表情を作り出しました。但し、なんやら表情晴れやかで違和感有。でも、たいした迫力であり、盛り上がりもあります。この曲、最終楽章がちょっと尻切れトンボ的印象があるんだけど、スタインバーグは明快に、楽しく、最後まで疲れずしっかりとメリハリ付けて堂々たる貫禄が続きました。これはこれで、ひとつの個性だと思います。
たしかに全体として、陰影深いとか、Bruckner的荘厳なる雰囲気じゃない(先入観ですか?)か。
Command録音の肌理は粗いのか?それともCDへのマスタリング問題か。ひとつひとつのパートはよく聞こえるが、定位とか奥行きやら残響が不自然で損をしていると思います。海外のサイトも含めて録音年を探したが、不明。情報をお持ちの方はご一報下さい。1960年前後でしょうか。 |