Beethoven 交響曲第9番ニ短調「合唱付き」
(ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリン・フィル/
1942年3月22日/ベルリン旧フィルハーモニー・ライヴ)
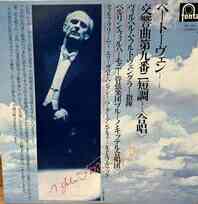 Beethoven
Beethoven
交響曲第9番ニ短調「合唱付き」
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリン・フィル/ブルーノ・キッテル合唱団
ティルラ・ブリーム(s)/エリーザベト・ヘンゲン(a)/ペーター・アンダース(t)/ルドルフ・ヴァツケ(bbr)
写真は懐かしい廉価盤LP fontana PL-1011 1942年3月22日/ベルリン旧フィルハーモニー・ライヴ
LP時代1,000円盤を購入して、曖昧模糊とした音質の中から異様な緊張感を聴き取っていた音源。4月の「ヒトラーの第九」とは別物なんだそう。おそらくは40年数年ぶりの拝聴。オーディオのことは門外漢なのでなんと云えぬけれど(記憶より)解像度はぐっと上がっていると感じます。これは一期一会、日常聴きする記録ではないなぁ、すごい迫力だけど。神格化されている「バイロイトの第九」(1951年)は幾度聴いても自分の耳にはさほどに絶賛するほど?そんな粗忽耳な自分だけど、こちらは大昔初めて聴いた時よりその壮絶さに仰け反った記憶がありました。
第1楽章「Allegro ma non troppo, un poco maestoso」宇宙より神秘ななにものかが音もなく降ってくる〜そんなイメージそのままに神妙に始まり、エネルギッシュなタメが際立ちます。ティンパニの無遠慮な突出が目立って、それは録音の加減?壮絶なアクセントに感じさえてつつ、まだちょっと様子見〜そう思ったらやがて情感のこもったテンポの揺れと緊張感にあっという間に壮絶な熱気が押し寄せます。(17:15)
第2楽章「Molto vivace」は激しく叩きつけるようなアクセント、自在に揺れ動くテンポが決まって、時に疾走する切迫感、時に抜いてサラリと流す対比の効果は比類がない。(11:24)
第3楽章「Adagio molto e cantabile - Andante moderato」深淵なる緩徐楽章には喧しいティンパニ連打も少なく、そっと息の長い弦の詠嘆が陶酔する荘厳な神秘。ゆったりとしたテンポにポルタメント奏法も異様にエッチな感じ。絡み合う静かな木管、遠いホルンも深淵なる魅惑の音色、ここはこの演奏全曲中の白眉。しわじわと興が乗って熱気を帯びて、聴手を興奮に導きます。(20:14)
第4楽章「Finale: Presto〜」冒頭は急ぎ足、おそらくは音質の関係から無遠慮に叩きつけるようなティンパニ際立って、前のめりに切迫した始まり。そして「喜びの歌」旋律の陶酔した詠嘆とテンポ・アップに興奮を高めていく凄み。バスバリトンのソロには雄弁と気品が感じられます。そしてブルーノ・キッテル合唱団の集中力はかつての記憶どおり、声楽陣の競演にテンポは速めに熱気を加えます。「Alla Marcia」前のタメとティンパニはみごとに決まっておりました。テナーは無頼な勢いがあり、それに応える合唱と打楽器(土耳古風)の迫力も尋常に非ず、そしてテンポをいっそう速めて息切れするほどに疾走する熱狂。「Andante maestoso(抱擁)」「Adagio ma non troppo, ma divoto(創造主の予感)」「Allegro energico, sempre ben marcato(「歓喜」と「抱擁」の二重フーガ)」この部分の合唱の充実ぶりは涙が出るほど。やがて独唱4人による立派な「Allegro ma non tanto」を経、例のごとしノー・リミッターに熱狂的なアッチェレランドに全曲を閉じる・・・(24:48拍手省略)
全曲聴き通すと音質云々は忘れてしまいました。
(2024年12月28日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】 ●愉しく、とことん味わって音楽を●
▲To Top Page.▲
|