Bach イギリス組曲第6番ニ短調/前奏曲とフーガ 変ホ長調(ニコライ・ペトロフ(p))
イギリス組曲第6番ニ短調 BWV811(1989年ライヴ) ニコライ・ペトロフ(p) YEDAGCLASSICS YCC-0131 10枚組3,490円セット購入したうちの一枚 収録わずか47分ほどだけれど、このシリーズ(一連のYEDAGCLASSICS)にしては収録作品演奏音質のばらつきもなく、まともな一枚収録でしょう。ニコライ・ペトロフはロシアの現役ピアニストであり、PRKOFIEVのソナタ全集など硬派で超絶技巧!といった印象はあるけれど、実際には(録音で)聴く機会の少なかったもの。彼にとってBach はどんな位置付けなのでしょうか。 イギリス組曲は明快で、乾いたタッチで始まります。愁いを帯びた前奏曲はやがてテンポを上げて、情感を排した熱気へと至ります。もちろんバロック・スタイルではなく、アルマンドの繊細な抑制は浪漫の方向。テンポの揺れは自然であって、エキセントリックではなく、技巧は余裕で正確そのもの。クーラントはリズムが硬質であって、サラバンド/ドゥーブルには、ていねいで囁くような歌がありました。ガヴォットⅠ/Ⅱも同様の奥床しさがあり、ラスト「ジーグ」で力強いタッチが輝かしく爆発します。 強靱なBach 。しかし、リヒテルほど変幻自在ではないか、といったところ。 前奏曲とフーガ 変ホ長調 BWV552とは「聖アン」と通称される作品でして、前奏曲の勇壮な部分は豪快にピアノを鳴らしてオルガンのスケールを出そうとしております。それはたしかに効果を上げているが、ワタシの嗜好としては弱音でのリリカルな味わいを維持して欲しかったところ。どうしても少々”リキみ”を感じてしまいます。 前曲に比べ音質の散漫さも、その印象を助長しているでしょう。いずれ豪放大柄な演奏に間違いなくて、これはBusoni編なのかな?(表記なし/他の演奏を聴いたこともない)フーガに至っては、静謐かつ硬質な音色が正確であって、しかも諄々とした説得力+アツき盛り上がりに事欠きません。硬派な浪漫か。 「主よ、人の望みの歓びよ」はマイラ・ヘス編だと思うが、敬虔、淡々とした歓びが溢れる・・・が、やがて主旋律の硬質な歌は、輝かしく力感を増していきました。 (2007年9月28日)
【♪ KechiKechi Classics ♪】●愉しく、とことん味わって音楽を●▲To Top Page.▲ |
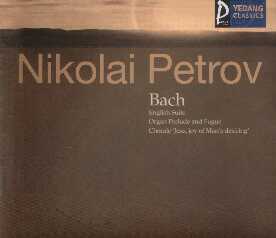 Bach
Bach