CLASSIC ちょろ聴き(26)
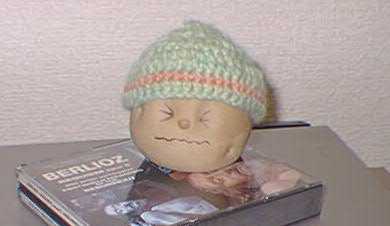 ● Schubert 交響曲第9番ハ長調〜セル/クリーヴランド管(1957年録音) ● Schubert 交響曲第9番ハ長調〜セル/クリーヴランド管(1957年録音)1970年最晩年の録音が有名だけれど、こちらのほうが録音は良いんじゃないの?(たまたま聴いた状態が悪かっただけか)「ワン・パターンだけれど、これほどリズム感やらフレージングが明快でわかりやすい、正しい音楽が提示された音楽は希有でしょう」(音楽日誌より)ワタシのいい加減な耳の責任大だけれど、ふだん聴き慣れない、思わぬフレーズが強調され、まったく新鮮です。基本、イン・テンポ系だけれど、思わぬタメもストップも豊かさも有。オーケストラが飛び抜けてセクシーとかはないんだけど、どうしてここまで音楽に説得力を持つのか不思議です。聴けば聴くほど、最近セルには完敗状態。(2004年2月15日) |
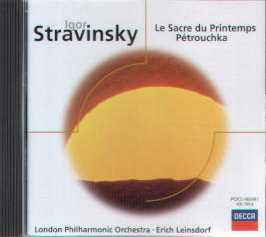 ● Stravinsky バレエ音楽「春の祭典」(1973年)/バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1911年版/1970年録音)〜ラインスドルフ/ロンドン・フィル ● Stravinsky バレエ音楽「春の祭典」(1973年)/バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1911年版/1970年録音)〜ラインスドルフ/ロンドン・フィルとにかく、いままで聴いたことのないパートが細部まで聞こえて、ある意味「聞こえるハズのない音」迄分離して鮮明に出現。打楽器なんかの鮮度(例えばタンバリン)は衝撃的。木管の内声部やら、金管の大絶叫の渦から「おおっ!」というくらい初体験の旋律が浮き出たり。不自然かつ人工的な世界だけれど、なんやらドキドキするのは、もちろん演奏が素晴らしいからか。しっかり、きっちり、全部鳴らすべき音は鳴らしますよ、といった、腕利き職人指揮者のワザでしょう。もちろん、それに輪を掛けているのが優秀録音だけれど。(音楽日誌より再掲) (2004年2月7日) |
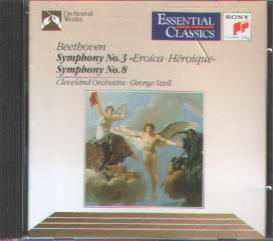 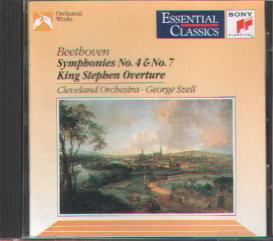 ● Beethoven 交響曲第3番(1957年)/8番(1961年)、第4番(1963年)/7番(1959年)+「シュテファン王」序曲〜セル/クリーヴランド管 ● Beethoven 交響曲第3番(1957年)/8番(1961年)、第4番(1963年)/7番(1959年)+「シュテファン王」序曲〜セル/クリーヴランド管(前回未聴で済ませちゃったので、少々コメントを)結論的にワタシはセルが好きなんです。「美しく聴かせよう」とか「しみじみ歌いましょう」ということではなく、正確に、明快に、誠実に演奏すれば、自ずから名曲としての真価は表出する、ということでしょうか。第7番終楽章は燃えるよう!以前聴いたBrahms 、Mahler とまったく同じ思いに、この度も襟を糺される思い有。 これほど峻厳で高潔でストレートで正しい演奏は滅多に経験できない。名曲が名曲として、文句なく、余すところなくその真価を聴衆に伝えるワザがすべてここに揃っています。すごい。(音楽日誌より再掲) ・・・但し、体調不良時にはお奨めできない。(2004年2月7日) |
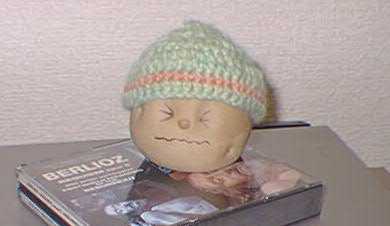 ● Delius 「フェニモアとゲルダ」「春、初めてのカッコウを聞いて」「川の上の夏の夜」「夜明け前の歌」「イルメリン」「ラ・カリンダ」〜ハンドリー/ロンドン・フィルハーモニー(1977年録音) ● Delius 「フェニモアとゲルダ」「春、初めてのカッコウを聞いて」「川の上の夏の夜」「夜明け前の歌」「イルメリン」「ラ・カリンダ」〜ハンドリー/ロンドン・フィルハーモニー(1977年録音)こんなに優しく、透明な音楽を聴いていると、現代社会に生きられないかもね。ビーチャムもバルビローリも素敵だけど、知名度的に地味なハンドリーだって凄腕名人です。ロンドン・フィルがここまで透明無垢に響くとは。静かで控えめな愉悦感に充たされ、しっかりとしたリズム感もあります。EMIとは思えぬ極上の録音水準も文句なし。上記、Bach とは別な意味で涙・涙の一枚でした。売ってませんか?安く。(2004年2月7日) |
【♪ KechiKechi Classics ♪】
●愉しく、とことん味わって音楽を●▲To Top Page.▲
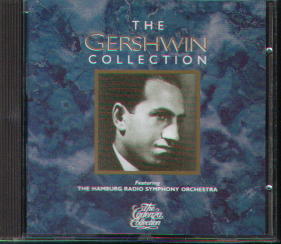
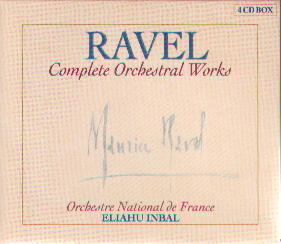 ● Ravel 管弦楽曲全集〜インバル/フランス国立放送管弦楽団(1987/88年録音)
● Ravel 管弦楽曲全集〜インバル/フランス国立放送管弦楽団(1987/88年録音)